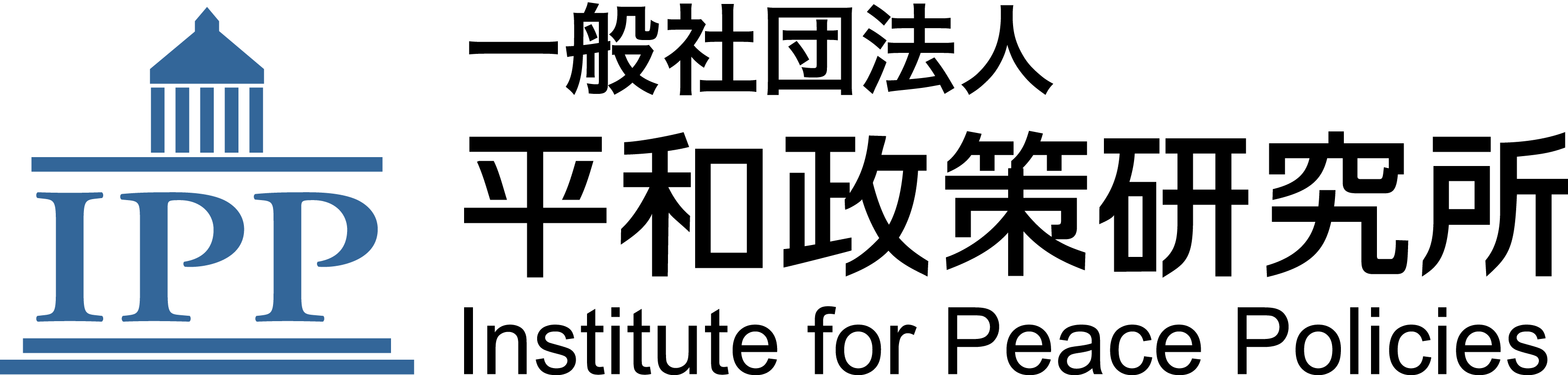はじめに
前回、前々回と2回にわたり、最近におけるロシアとその周辺諸国の関係を分析した。強いロシアの復活を目指すプーチン大統領は、旧ソ連邦を構成していた諸国を取り込み、ロシアの強い影響下に置くことで、ソ連あるいは帝政ロシア当時の勢力圏回復を狙っている。
しかし、ロシアと多くの周辺諸国の関係は良好とはいえないこと、ロシアがウクライナ戦争で優勢な戦いを進めてはいるが、ユーラシア全域でロシアの存在感や凝集力が高まっているとは言い難く、その影響力行使の拡大には制約が伴っている実情を眺めてきた。
一方、ロシアと戦っているウクライナを米国と共に支援してきた欧州諸国の現状はどうか。戦争は既に4年目に入ったが、停戦に向けた動きは依然として不透明である。しかもその間、欧州諸国ではロシアによる核戦争生起の恐怖やウクライナ以外の国や地域に戦争が拡大する危険性も取り沙汰され、緊張が高まる状態が続いている。
これに対し、第二期トランプ政権は米一国主義の下、欧州の安全保障に対する米国の関与を極力減らす方針を示し、欧州諸国に国防費の増額を迫るとともに、停戦実現後のウクライナの平和維持は欧州諸国の責任で進めることなど欧州の自律を強く求めている。ロシアの侵略脅威に直面する一方で、同盟国である米国からは対米依存からの脱却を迫られるなど厳しい安全保障環境のなかで、欧州各国はいまどのような国防体制や安全保障政策を講じようとしているのか、また対ウクライナ支援や停戦実現への取り組み、そして今後の対米関係はどうなるかなど今月は欧州の安全保障の現況と諸問題に目を向けてみたい。
1.ロシアウクライナ戦争と対露脅威の増大:核兵器使用や戦争拡大の恐怖
2022年2月24日、ロシアがウクライナへの侵攻を開始した。短期間でウクライナを制圧するというプーチン大統領の思惑は外れ、ロシアは苦戦を強いられた。ウクライナは東部諸州をロシアに奪われはしたが、欧米諸国の支援も得て善戦を続け、露軍の進撃を阻止し、戦線は硬直状態が続いた。
しかしウクライナ軍の反撃も期待した程の成果を挙げず、23年には反転攻勢に失敗、24年8月には戦局挽回を目指しロシア領クルスク州に攻め込んだが、当初制圧した地域は徐々に露軍に奪還された。ウクライナ東部での戦闘でもロシアの優勢が目立つ。またロシアによる無人機攻撃で首都キーウをはじめとする都市部や発電所などの社会インフラが攻撃を受け、市民の犠牲は増大し、ライフラインの欠乏など国民生活にも深刻な影響が広がっている。
戦争勃発以来、欧州各国はウクライナへの支援を継続しているが、ロシアのプーチン大統領はウクライナ支援を阻止、後退させるため、戦争拡大の脅威を煽り続けてきた。プーチン大統領はウクライナでの戦いが苦戦の様相を見せ始めた頃から、しきりにこの戦争が核戦争に発展する危険を強調するようになった。
ロシアは2014年の軍事ドクトリンで、通常戦力の劣勢を補うため「地域紛争での非戦略核兵器(=戦術核兵器)の使用」を認めるようになり、旧ソ連時代の「核先制使用」の禁止を放棄した。そして露軍がウクライナに侵攻した直後の22年2月27日、プーチン大統領は核戦力部隊を「特別な戦闘態勢」に引き上げるよう命じ西側諸国を威嚇。3月にはペスコフ大統領報道官が「我が国の存亡に関わる脅威があれば、核兵器の使用もあり得る」と述べるなど「使えないはず」だった核兵器の使用も厭わない姿勢を前面に押し出している。24年5月にはウクライナへの軍事侵攻の中心となっている南部軍管区で戦術核兵器の使用を想定した軍事演習を実施したほか、核搭載可能兵器の前線配備を進めるなど度々核兵器使用の脅しをかけている。
さらに24年9月、プーチン大統領はロシアが核兵器保有国の支援を受ける核を持たない国から攻撃された場合、それは「共同の攻撃」と受け止めると表明し、核を持たない欧州諸国からの攻撃にも核使用の可能性があるとする新たなルールを明らかにした。西側諸国が提供する武器でウクライナがロシア領内を攻撃することを容認したことへの対抗措置である。そして米国が許可を与え、ウクライナに供与した射程約300キロの地対地ミサイルATACMSを用いたロシア領内への攻撃が行われたことを受け、同年11月には大統領令によって核ドクトリンの改定に踏み切っている。
核戦争に至る恐怖に加え、欧州ではウクライナ以外の国や地域にも露軍が攻撃を掛けて来るのではないかとの懸念も強まっている。ドイツのピストリウス国防相は24年1月19日付け独紙「ターゲスシュピーゲル」でのインタビュー記事で、プーチン大統領が10年以内に北大西洋条約機構(NATO)加盟国を攻撃する可能性があるとの考えを示した。ピストリウス氏は、ロシアの攻撃は「差し迫ってはいない」としながらも、「我々の専門家の見立てでは、5年から8年後に攻撃が可能になると見ている」と語った。
また同年2月9日にはデンマークのポールセン国防相が地元紙で「ロシアの軍備生産能力は驚異的に向上している」と述べ、ロシアが予想以上に早く軍備を増強しているとの認識を示したうえで、「ロシアが3年から5年以内にNATO加盟国を攻撃する可能性は否定できない」との見方を示した。さらに25年2月には、デンマークの国防情報省が、今後5年以内にヨーロッパで大規模戦争の脅威が発生すると警告する報告書を発表した。同省の評価によれば、ロシアはNATOが軍事的にも政治的にも弱体化したと判断した場合、同盟国の1カ国以上に対して武力を行使する可能性があると見ている。
一方ロシアの側からもNATO加盟国との戦争の可能性が語られるようになった。24年3月7日にロシア通信(RIA)が報じたところでは、露軍参謀本部軍事アカデミーのウラジミール・ザルドニツキー学長が国防省の発行物「軍事思想」の中で、ウクライナ戦争が欧州の全面戦争にエスカレートし、露軍が新たな紛争に巻き込まれる可能性が「著しく高まっている」との認識を示した。この記事からは、戦争の拡大がロシアとの全面戦争に発展する危険性を強調することで、欧州諸国がウクライナ支援に加わる動きを阻止したいとの思惑が読んで取れるが、欧州諸国の緊張感をさらに高めたことは確かだ。
2.緊張高まる北欧:ロシアが第二戦線を開く危険性
では、仮にロシアがウクライナ以外に戦端を開くとした場合、どの国や地域が攻撃対象となるのか。勢力圏の拡大を狙い旧ソ連邦の構成国を取り込もうとしているロシアの行動原理から推察して、モルドバやバルト三国が狙われる可能性が高い。
モルドバを制圧すればロシアはウクライナを東西から挟撃することが出来る。またモルドバはNATOに加盟しておらず、攻撃を仕掛けても欧州諸国と全面的に対立する度合いは低い。最も手っ取り早い攻撃対象と言えよう。ただウクライナ戦の現状では、ロシアが黒海に沿ってクリミアからオデッサを経てモルドバに兵力を送り込むことは難しい。
これに対し、同じくソ連邦を構成していたバルト三国はロシア領から直接、あるいはベラルーシを経由して攻撃することが可能だ。バルト三国は北大西洋条約機構(NATO)に加盟しているが、ベラルーシからロシアの飛び地であるカリーニングラードに大規模な地上軍を送り込めばバルト三国を他のNATO諸国から孤立させることが出来る。またカリーニングラードに司令部を置くバルト艦隊との連携を強め、ノルウェーやスウェーデン、デンマークなど北欧諸国を制圧、ウクライナに対する第二戦線を開くことでNATOや欧州諸国のウクライナ支援を減じることも可能になる。英国のBBC放送によれば、スウェーデンのカール・オスカル・ボーリン民間防衛相は24年1月7日の防衛会議で「スウェーデンで戦争が起こるかもしれない」と語っている。
このように、ロシアによる攻撃の脅威を最も強く感じ取っているのが北欧の国々や歴史的にもロシアへの警戒感が強いバルト三国だ。その一つリトアニアの情報機関が24年3月に公表した自国への安全保障の脅威に関する報告書の中では、ロシアはウクライナ侵攻を続ける一方、バルト海周辺でNATOとの対立が長期化することを睨み軍の再編などの準備を進めているとの見方が示された。またチェコのシンクタンクEuropean Valuesのヤコブ・ヤンダ所長は、モルドバと並びバルト三国もロシアによる攻撃の選択肢の一つに挙げ、その中でも欧州で最大のロシア系住民を抱えているラトビアを狙う危険性を指摘。軍事攻撃に至らなくても、緊張を煽り難民を作り出し、混乱させる可能性もあると述べている。
フィンランドとスウェーデンがNATO加盟を申請
高まる対露脅威に対処すべく、北欧のフィンランドとスウェーデンの両国はロシアがウクライナに侵攻した直後の22年5月、同時に北大西洋条約機構(NATO)への加盟を申請した。約1300キロにわたりロシアと国境を接するフィンランドは、帝政ロシアによる統治を経て1917年に独立。第二次大戦中にソ連の侵攻を受け、国土の約1割を割譲した歴史がある。
戦後は1948年にソ連と友好協力相互援助条約を結ぶなど対ソ友好外交をとりつつも東西両陣営の間で中立を貫くことで独立を維持してきたまた。フィンランドは「総合的な安全保障」戦略を持ち、社会全体で自らを守る強力なシステムを構築しているが、近年ロシアに対する警戒心が高まり、特にウクライナの戦争は自国の苦難の歴史と重なり合うものがある。
一方のスウェーデンはナポレオン戦争終結後の1834年、時の国王カール14世ヨーハンが「中立」をはじめて導入して以来、200年近く武装中立・非同盟の自主国防路線を堅持し、北欧きっての軍事力を誇っている。スウェーデンの「中立」はオーストリアのように周辺国の同意を得る永世中立ではなく、政体法(憲法に相当)や条約に基づくものでもない。一方的な政治宣言であり、国際情勢の変化如何によって見直しもあり得る「中立」政策である。
だが冷戦の終焉でソ連という脅威が薄くなり、中立政策の意義は小さくなった。1995年にフィンランドと共にEUに加盟し、2009年にはリスボン条約に呼応して、EU非加盟国のノルウェー、アイスランドを含めた「中立から連帯へ」が安全保障政策の柱となる。百年以上続いた徴兵制も2010年に廃止した。
ところが2014年のロシアによるクリミア併合でロシアの脅威が俄かに高まり、国防への意識が再び高まる。2018年には徴兵制が復活、露海軍のバルト海での行動が活発化するようになった事態を受け、ロシアの飛び地カリーニングラードと対峙するバルト海のゴットランド島に、04年に一度は引き揚げた常駐軍を再配置した。またスウェーデン議会は22年、同国がNATOに加盟すれば「北欧で軍事紛争が起きる可能性を軽減し、抑止効果をもたらす」との分析を示した安保政策見直しの報告書を公表し、世論もNATO加盟を支持する声が強まった。
両国ともにNATOと「平和のためのパートナーシップ(PfP)」協定を締結しており、合同演習や平和維持活動には参加してきたが、正式な加盟国ではなかった。だが22年のロシアのウクライナ侵略が国防政策見直しの大きな転機となった。高まるロシアの脅威に備えウクライナの次に自国が攻撃される事態も想起し、集団防衛体制に加わる必要があると判断、ともにNATO加盟へと舵を切ったのである。
北欧・バルト海の防衛力強化 高い地政的価値と優れた兵器で国を守る
審議の結果、23年4月にフィンランドが、次いで24年3月にスウェーデンがともにNATOへの加盟を承認された。NATOが発足して昨年で75年目を迎えた。その間正式参加を見送ってきた両国が一転NATOに加わったことで、フィンランドやスウェーデンの対露体制が向上しただけではなく、NATOそのものの防衛体制も強靭化されることになった。
NATOを構成するノルウェーやデンマークに、新たにフィンランドとスウェーデンが加わることで北欧全体が一つのユニットとなり、NATO軍はバルト海から北極圏に至る地域で統合的な作戦を展開することが可能になる。両国の加盟でバルト海地域と北極圏を含む大西洋がNATOの領域として連結されたということである。
対露戦を想定した場合、両国の地政的価値は極めて高いものがある。ロシアと1300キロ以上の長大な国境線を有するフィンランドがNATOに加われば、ロシアの対NATO正面は一挙に2倍に延伸し、戦力分散を露軍に強いることができる。また国境線の北限はロシア北方艦隊の司令部があるムルマンスクやセヴェロモルスク軍港に、またその南限はサンクトペテルブルクやバルト艦隊のクロンシュタット軍港にそれぞれ近接している。そのためフィンランドの加盟でNATOはロシアの二大艦隊に睨みを利かせ、その行動を牽制することが可能になる。
スウェーデン加盟の戦略的意義も大きい。バルト艦隊の船が大西洋に出るにはデンマークとスウェーデンの間の狭いカテガット海を抜けるしかない。海峡両岸がともにNATO加盟国となれば、海峡の監視や封鎖作戦が行い易くなる。またスウェーデンの潜水艦はバルト海で遊弋するロシア潜水艦の捕捉力が高い。バルト海に面するロシアの飛び地カリーニングラードには、バルト艦隊の司令部や地上部隊が配備されており、カリーニングラードとベラルーシを結ぶスバウキ回廊でバルト三国は他のNATO加盟国と分断されている。
これに対しスウェーデンは、バルト海を挟みカリーニングラードの対面に位置するカールスクルーナやゴットランド島に陸海軍の基地を持つ。ここにNATO軍が展開すればバルト海軍の動きを抑止するとともにバルト三国防衛の能力も高まる。
このように両国の高い知性的価値を活かすことで、NATOは露軍をバルト海に封じ込め、ノルディックバランスの優位を獲得することが出来た。加えて、スウェーデンの持つ武器も大きな価値を持つ。潜水艦もそうだが、ロシアの脅威に対抗するために設計された戦闘機グリペンがそれだ。グリペンは短い離着陸距離でどこでも展開できる運用性能の高い戦闘機だ。23年8月、ウクライナのゼレンスキー大統領がスウェーデンのクリステション首相との会談で、グリペンのウクライナへの供与について協議を始めたことを明らかにした。F-16に加え、グリペンの供与でウクライナの防空能力向上や制空権奪還への寄与が期待された。またグリペンは今年4月からNATOの防空任務を担いポーランドに配備される予定である。
スウェーデンは、人口1千万人程でありながら戦闘機や潜水艦を国産化する稀有な国で、戦略的地勢的価値の高さに加えて高性能の武器を保有している。だからこそNATO入りが可能になったともいえる。高い知性的価値と高性能の武器を持つこと、それが自らの国を守る力となるだけでなく、強力な同盟関係構築にも寄与するのである。さらに有事の際の対処の仕方に関する国民への教育や啓蒙にも熱心だ。スウェーデンの民間緊急事態庁は24年11月、「機や戦争に備えて」と題した戦争対応マニュアルを発行し、国民への配布を始めた。ウクライナ戦争でのロシアの激しい攻撃の実態を念頭に、戦争の脅威に対抗するための団結の重要性を国民に訴え、スウェーデンが攻撃された時は「独立と民主主義を守るため各人の役割を果たすべき」と強調するほか、攻撃から身を守る手段や自活の方法などを詳しく説明している(図表1参照)。同様のマニュアルはフィンランドも国民に配布しており、さらにフランス政府も武力衝突事態を含めたサバイバルマニュアルを今夏までに全世帯に配布する予定である。
バルト三国の防衛体制
バルト三国はかつてソ連の支配下にあったが、1991年に独立。現在は欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)の加盟国で、ロシアの侵攻を受けるウクライナを強く支持している。ロシアがウクライナを制圧する事態になれば、「次はラトビア、エストニア、リトアニアだ」との見方も強い。
そのためロシアの攻撃を最も強く警戒するバルトの各国はロシアウクライナ戦争の勃発を受け、ロシアとの国境沿いにフェンスや有刺鉄線を設置したほか、地雷や「竜の歯」などを敷設している(図表2参照)。竜の歯とは第二次大戦以降、戦車などの進軍を阻止するために使われてきたコンクリート製の「防御用障害物」で、その名の通り地面からピラミッド型の巨大な歯がずらりと突き出したように見える。またバルト三国は今年2月、ソ連時代から続いてきたロシアとの電力網の遮断を完了させ、欧州連合(EU)側との接続に完全に切り替えエネルギー面でのロシア依存を解消させている。
活発化するロシアのハイブリッド戦
ロシアはウクライナとの戦争開始後、対露防衛体制の強化を急ぐバルト三国や北欧各国へ様々なハイブリッド戦を仕掛けている。政権や国民に動揺と不安を与え、防衛体制強化の動きを妨げウクライナ支援を後退させようとする狙いだ。バルト三国に対しては、その政府機関などを標的にしたロシアのサイバー攻撃が増えている。ロシアはウクライナに対し、サイバー攻撃など非軍事的な手段を組み合わせた「ハイブリッド攻撃」の手法を駆使した上で、侵略に踏み切った経緯がある。
サイバー攻撃だけでなく、24年5月、リトアニアの首都ビリニュスにある家具大手IKEA(イケア)の倉庫で火災が発生、当局は露軍情報部門の犯行と断定した。同年7月にはドイツ東部ライプチヒで貨物機に積み込まれる直前の荷物が発火したほか、英国やポーランドでも貨物の不審火災が相次ぎ、ロシアがウクライナを支援する国を狙った破壊工作との疑いが強い。ポーランドは24年10月下旬、国内で発生した放火計画事件の捜査で露軍参謀本部情報総局(GRU)の関与が裏付けられたとして、西部ポズナンのロシア総領事館を閉鎖した。同年11月にはリトアニアの首都ビリニュスの空港付近でドイツ物流大手DHLの貨物機が墜落し乗員1人が死亡した。この事故もドイツ当局はロシアが関与した可能性を示唆している。いずれも決定的な証拠はないが、プーチン政権が仕掛ける軍事的威圧と非軍事的な工作を組み合わせた「ハイブリッド戦争」の一環との見方がもっぱらだ。
バルト海では一昨年10月に海底パイプラインなどの損傷が確認されたほか、昨年11月以降、海底の電力ケーブルや通信ケーブルの切断事件も相次いでいる。周辺国からはロシアが関与する破壊工作の可能性が指摘され、NATOが船や航空機によるパトロールを強化している。
3.NATOの防衛体制強化
次にウクライナ戦争が生起して以降の北大西洋条約機構(NATO)における国防体制強化の取り組みを概観しておこう。ウクライナ戦争勃発を受け、22年6月に開催されたNATO首脳会合では、2010年以来12年ぶりに新たな戦略概念が採択された。それまでの戦略概念ではロシアと「真の戦略的パートナーシップ」を目指すとされていたが、新概念ではロシアを加盟国の安全保障と欧州・大西洋地域の平和と安定に対する「最も重大かつ直接的な脅威」と位置付けた。
ロシアの脅威を前面に押し出したNATOは、東部正面における部隊の規模を拡大するとともに、現行のNATO即応部隊に代わり30万人以上を高い即応態勢に置くことで合意するなど防衛協力の強化を進めた。
23年7月の首脳会合では、冷戦後、最も包括的で詳細な地域防衛計画が承認され、防衛体制の向上が図られた。これを受け、全ての加盟国が参加して冷戦後最大規模となる演習「ステッドファーストディフェンダー2024」が24年1月から5月にかけて実施された。その間、長年の軍事的非同盟政策を転換させたフィンランドが23年4月、スウェーデンが24年3月に相次いでNATO加盟を果たし、これでNATOの加盟国は32か国となった。
NATOにおける防衛力強化の動きは各国の国防費増額の取り組みからも窺うことが出来る。NATOは2014年の合意で国防費の対GDP比2%を目標に据えているが、ウクライナ戦争を受けてストルテンベルク事務総長は22年11月、「対GDP比2%は上限ではなく下限と考えるべきである」と表明、また23年7月の首脳会合では加盟国はGDPの最低2%を防衛支出に投資することで合意している。
しかしながらその実態を見ると、加盟各国の中で国防費の対GDP比2%をクリアできている国が少ないのが現実だ。冷戦の終焉後、直接的な脅威が消失して以降、NATO各国は国防費の削減に動いた。その後、ロシアの脅威が高まる中でも、国防費の増額に消極的な姿勢から抜け出せず、これが米国のトランプ政権に批判されることになった。
4.欧州諸国の対ウクライナ支援状況
欧州各国は自国及び集団防衛機構であるNATOの防衛体制強化に動くと同時に、米国と共にロシアと戦闘を続けているウクライナへの軍事、経済的な支援を続けている。そのうち武器支援について見ると、欧州諸国は戦況に応じてウクライナに武器の供与や訓練支援などを実施してきた。露軍の侵攻当初はジャベリンなどの対戦車ミサイルやスティンガー、スターストリークといった地対空ミサイルを、その後全面侵攻を食い止めた後は、反転攻勢を支援するため、23年1月、旧ソ連製以外の戦車や歩兵戦闘車の供与を開始、また旧ソ連製戦闘機に加えて、オランダ、デンマーク、ベルギー、ノルウェー等は100機以上のF16戦闘機を供与している。
25年2月にマクロン仏大統領とトランプ大統領が会談した際、対ウクライナ支援に関しトランプ氏は「米国は3000億ドル(約45兆円)以上を費やしているが、欧州は1000億ドル程度だ。この差は大きく、いつかは同額にすべきだ」と訴えた。これに対しマクロン氏はトランプ発言が正しくないと直ちに抗議した。では欧州各国のウクライナに対する実際の支援の規模はどれ程であるのか。
ウクライナへの戦時援助を調査しているドイツのシンクタンク、キール世界経済研究所によれば、2024年12月までに西側諸国が表明したウクライナ支援の総額は2670億ユーロ(2830億ドル、約42兆円)に上り、支援の内訳は軍事支援が49%、財政支援が44%、人道支援が7%だった。国別では、米国が1142億ユーロ(約1190億ドル)で最大だが、EUを含む欧州諸国は計1320億ユーロ(約1380億ドル)で米国を上回っている(図表3参照)。
軍事支援に限ってみれば、支援総額は計1297億ユーロで、うち米国が最大の641億ユーロで、欧州全体の620億ユーロを僅かに上回ってはいるが、それでもトランプ氏が述べたような大差にはほど遠い。欧州諸国は相当程度の支援をウクライナに行ってきたといえる。ただ、米一国で欧州全体に匹敵する程の負担を強いられているとの不満をトランプ氏が抱くことにも一理はあろう。
こうした欧米の巨額の支援にも拘わらず、ロシアウクライナ戦争の戦局はロシア優位の情勢となりつつある。ウクライナはロシア領を攻撃することのできるより長射程のミサイルなどの提供を求めているが、戦争がエスカレートし第三次世界大戦へと拡大することを恐れ米国はじめ各国は提供に慎重な姿勢を崩していない。また自国の国防力を強化する必要に迫られている中、同時にウクライナへの支援を続けることは財政上の負担が大きく、欧州諸国の中にはいわゆる支援疲れが出始め、戦争の長期化に伴い、ウクライナへの支援縮小や見直しを求める世論や政党の声も高まっている。早期の停戦実現への期待も強まりつつある。
5.トランプ2.0の衝撃
そうしたなか、24年11月の米大統領選挙では、「米国第一」を掲げ欧州との防衛協力やウクライナ支援に消極的なトランプ前米大統領が返り咲いた。移民排斥などでトランプ氏と政策が一致する欧州の右派勢力が勢いづく可能性もあり、欧州では不安が広がった。
トランプ氏は第一期政権の当時から欧州諸国の防衛努力が足りないことを批判し、国防費が国内総生産(GDP)の2%を下回る国は「守らない」と発言し、米国のNATO脱退もちらつかせてきた。また昨年の大統領選でも、防衛費を増やさなければロシアの攻撃から加盟国を「守らない」などと発言し物議を醸した。
さらに再選を果たしたトランプ氏は、米国の対ウクライナ政策の根本的な方針転換に出た。ロシアのウクライナへの侵略を軍事支援の継続で阻止するというバイデン政権の方針を見直し、戦争の早期終結へと舵を切ったのだ。「恒久的な紛争解決」を目指し、直接的な軍事関与よりも外交チャネルを活用し、ロシアとの「交渉による解決の道を探る」ことでウクライナ戦争を早期終結に導く。さらにロシアのG20復帰や軍縮交渉の進展などロシアとの全面的な関係改善を目指そうとするものである。またウクライナの戦争は基本的に欧州の問題であり、欧州諸国は対米依存を続けず、自らが解決に乗り出すべきであるとの考え方を前面に押し出し、これまで以上に欧州各国の国防努力を強く求めている。
大統領当選後の24年12月、トランプ氏はロシアの侵攻を受けるウクライナへの米国の支援を削減する意向を示した。また大統領就任前に戦争を終わらせたいと強調、第一期政権で脱退を検討したとされるNATOに関し、残留するかを問われると「彼ら(欧州の同盟国)は自分たちの(軍事支出の)請求書を支払わなければならない。彼らが払うのなら、もちろん(残る)」と述べ、脱退の可能性を否定せず、欧州に軍事支出の増加を改めて求めた。
そして大統領就任直後の25年1月23日、トランプ米大統領はスイス・ダボスで開催されている世界経済フォーラム年次総会にオンライン出席し、NATO加盟国は国防費を国内総生産(GDP)比5%に引き上げるべきとの考えを示した。
NATO加盟国のうち国防費がGDPの2%を超える国は、14年当時は僅か3カ国に過ぎなかったが、その後米国の圧力もあり24年には23カ国に増えた。だが約3分の1の国は未だ2%に達しておらず、5%の達成目標は極めて高いハードルだ。一方、米国はNATO最大の資金提供国で、2024年のNATO防衛支出の6割以上を米一国で負担している。政権一期目には同盟を重んじる側近がいたが、二期目はトランプ氏のイエスマンで固められており、大統領を抑え翻意させることは困難な情勢だ。欧州が自らの安全保障を米国に大きく依存し続けるなら、トランプ米政権は言葉通りNATOから離脱する可能性が高い。
トランプ新政権の衝撃はさらに続く。2月12日、トランプ大統領は戦争当事国のウクライナや欧州諸国の頭越しに、ロシアのプーチン大統領と直接電話で協議し、ウクライナ戦争終結に向け米ロ交渉を開始することで合意したのだ。
さらに2月14日に始まったミュンヘン安全保障会議では、バンス副大統領が欧州各国に防衛費の増額を求めるとともに、欧州諸国の多文化主義や偽情報、ヘイトスピーチの規制、移民政策などを厳しく批判、移民排斥を掲げる独極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」への実質的な支持を打ち出した。またケロッグ米特使(ウクライナ・ロシア担当)は、2014年と15年、独仏が主導してウクライナ東部紛争の解決をめざした「ミンスク合意」は失敗だったとし、「我々は同じ道は辿らない」と述べ、停戦交渉に欧州を参加させない考えを示した。さらにヘグセス米国防長官が米軍の欧州駐留は「永遠ではない」と述べ、欧州への関与を大幅に減らす意向を示した。
欧州のNATO加盟国に国防費の増額を強く迫る一方、対欧コミットメントは削減、さらに欧州の頭越しにロシアとの直接協議でウクライナ戦争の早期終結に動くトランプ新政権の動きに欧州諸国は強い衝撃を受け、対米不信も一挙に強まった。ウクライナのゼレンスキー大統領もミュンヘン安全保障会議で演説し、「真の安全の保証がなければ、停戦に同意することはできない」と強調。ロシアとの停戦協議を急ぐトランプ政権に対しては「ウクライナ抜きの決定は受け入れられない」と反発、さらに欧州安全保障への米国の関与低下に備えるため、自力での防衛努力を欧州諸国に求め「欧州統一軍を形成すべきだ」と訴えた。
安全保障だけでなく、経済でもトランプ新政権の対欧姿勢は厳しいものがある。2月26日、トランプ大統領は、欧州連合(EU)は米国を「騙すために設立された」との敵対認識を露にし、2356億ドルに上る米国の対EU貿易赤字(2024年)を念頭に、EUからの輸入品に25%の高関税を課す方針を明らかにした。
6.トランプ・ゼレンスキー会談の決裂
2月28日、トランプ大統領はホワイトハウスでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。第2次トランプ政権発足後、両首脳の対面での会談は今回が初めてだったが、話し合いは決裂に終わった(図表4参照)。
戦争の早期終結を目指すトランプ氏は、ロシアのプーチン大統領と停戦に向けた協議を開始することで合意し、両国の実務レベルの話し合いを進めている。一方ウクライナに対しては、これまでの多額の支援の見返りにその領内の鉱物資源の権益を要求し、合意文書への署名を迫った。これに対しゼレンスキー大統領はトランプ氏と直接この問題を話し合い、米国による安全の保障提供の確約を取り付けたうえで署名に応じるとともに、トランプ氏のロシアへの急接近を引き留めたい考えであった。
当初会談は和やかな雰囲気で進んだ。だが紛争解決に向けた外交の必要性を説くバンス米副大統領に対し、ゼレンスキー氏がプーチン氏の合意違反を米国は防げなかったと反論に出た。ゼレンスキー氏には、ウクライナが求める「安全の保証」を巡って根深い欧米への不信がある。ウクライナは94年、旧ソ連時代に配備された大量の核兵器の放棄に同意した。これを受けて米露英の核保有3カ国はウクライナの「安全の保証」を約束。だがその20年後の2014年、3カ国のうちロシアのプーチン大統領がクリミア半島を一方的に併合した。ゼレンスキー氏はトランプ氏の前で「さらに2014年から2022年の間、誰もプーチン氏を止められなかったと」と指摘、約束を破り信用の置けないロシアと交渉することに意味があるのかとの反駁であった。
これに対しバンス氏は「大統領執務室で、米メディアの前でこの問題を扱うのは失礼だ」と強く非難、2人の口論に加わったトランプ氏もゼレンスキー氏を批判し、取引に応じなければ米国は支援を打ち切ると通告するなど非難の応酬で会談は決裂。合意文書の署名は中止され、記者会見も開かれない異例の展開となった。
7.自立の途を模索する欧州諸国
ウクライナへの欧州平和維持部隊派遣
ロシアによるウクライナ侵略に関して米国とロシアが合意した停戦交渉を巡り、2月17日、フランスのマクロン大統領が英独など欧州8か国の首脳らを招集してパリで緊急の会議を開いた。ウクライナ情勢を巡って欧州の負担増を求める米国に対して欧州が独自の貢献策を示さなければ、交渉が今後も欧州の頭越しに進み、不利な条件で合意がなされかねないとの警戒感が欧州にあるからだ。各国は停戦実現後にロシアの再侵略を防ぐため、欧州がウクライナへの「安全の保証」提供で主体的な役割を果たす方針で一致した。
ただ戦闘終結後のウクライナへの派兵に関しては意見が分かれた。トランプ大統領は停戦後のウクライナの平和維持は欧州が中心になるべきだと主張し米軍の派遣に消極的である。そのため、米国がウクライナの戦後安全保障に関与しない形で「停戦」になった場合の欧州の対応が問われる。この問題に関してマクロン仏大統領はかねてより欧州各国による平和維持部隊の派遣に積極的な立場を示しており、スターマー英首相も「米国の後ろ盾」を条件に部隊派遣に前向きな姿勢を示している。
一方、ポーランドのトゥスク首相は自国軍隊派遣の考えはないと語り、ショルツ独首相やメローニ伊首相も否定的な姿勢を示した。露軍の再侵攻を阻止するには、99年にNATOがコソボに派遣した平和維持部隊4万8000人を上回る最大15万人規模の派遣が必要になるとのドイツのシンクタンクの試算があるが、ロシアとの戦闘に巻き込まれる事態を避けたいとの思惑に加え、米国からの国防費増加圧力が強まる中、部隊の派遣がさらなる経費負担の重圧となることから態度が慎重になっているのだ。
首脳会議での論議を踏まえ、マクロン仏大統領とスターマー英首相が相次いでホワイトハウスを訪れトランプ大統領と会談した。トランプ大統領は欧州の平和維持部隊派遣を支持したが、早期の停戦合意を目指すトランプ氏と、ウクライナへの「安全の保証」が必要であり「安全の保証なしに停戦はできない」と慎重なアプローチをとるマクロン氏の立場は相違した。スターマー英首相も「侵略者」のロシアを利する合意になってはならないと訴え、欧州諸国がウクライナに平和維持部隊を派遣する場合、米国の関与を求めたが、トランプ大統領は和平合意を優先すべきだと強調。米国の具体的な関与については明言しなかった。
その後、トランプ・ゼレンスキー会談決裂の衝撃を受け、欧州各国はゼレンスキー支持を相次ぎ表明、ゼレンスキー氏と会談したスターマー英首相はウクライナと米国の関係修復の橋渡しに乗り出し、3月2日、欧州など約15か国とウクライナの緊急首脳会議をロンドンで主催した。会議では、欧州首脳らがウクライナとの連帯を強調し、ウクライナの主権と安全保障を尊重した停戦交渉を支持することを確認した(図表5参照)。
そして①ウクライナへの軍事支援と対露制裁の継続②停戦交渉へのウクライナの参加③ロシアの再侵略を防ぐためのウクライナの防衛能力強化④ウクライナに「安全の保証」を提供するため、有志連合による部隊派遣構想を発展させるという4項目を停戦に向けた対露政策に据えることで一致した。各国はこのウクライナ支援策を踏まえ、欧州独自の停戦案を作成し米国側に提示する方針を固めた。
マクロン仏大統領は、和平の第1段階として「空域と海域、エネルギー施設」を対象とする1カ月の休戦案の作成を英仏で進めていると明らかにした。「前線での停戦が順守されているか確認するのは非常に困難」として、地上での戦闘は対象とせず、平和維持部隊の派遣は休戦が実現した後の段階になるとした。この動きに対してロシアのラブロフ外相は、中国など中立国による部隊派遣には反対しないが、欧州有志国連合のウクライナ駐留は「NATOが直接関与することになる」と述べ、認めないと述べた。
スターマー英首相は3月15日、2回目となる欧州諸国などの首脳会議をオンラインで開催、ロシアのプーチン大統領に「対等な条件で停戦に同意」するよう求め、即時かつ無条件の停戦を拒否した場合は、対ウクライナ軍事支援の拡大や対露制裁の強化に出ると警告した議長声明を取り纏めた。3月20日には英国で有志国の軍事担当者会合が開かれた。平和維持部隊の編成などの計画案が協議された。報道では派遣される地上部隊の規模は英仏を主体に3万人規模で、英政府は30カ国超の参加を見込んでいるという。
欧州の再軍備
ウクライナ支援策の検討と並行して、欧州の防衛力強化の検討も急ピッチで進められている。フォンデアライエン欧州委員長は3月4日、EU加盟国の防衛力強化のために、今後4年間で約8000億ユーロ(約125兆円)の資金確保を目指す「欧州再軍備計画」を発表した。計画では、EU独自の防衛力を強化するため1500億ユーロ規模の資金を市場から共同で調達し加盟国に融資する制度を創設するとともに、財政規律の緩和を通じ各加盟国が国内総生産(GDP)の1.5%分の軍事費を増強することで6500億ユーロを確保し、欧州の防衛産業育成と軍事的自立性の向上を目指す。
この計画は3月6日に開催されたEU特別首脳会議で加盟27カ国によって承認された。共同防衛のための大規模な資金調達計画が認められたことは、自らの安全保障を主体性を以て強化しようとする欧州各国の決意を示すものといえる。ただ計画は加盟国が防衛費を大幅に増やすことを前提としており、8000億ユーロを確保できるかどうかは微妙だ。この会議ではトランプ米大統領が軍事支援の停止を表明したウクライナに対する追加支援も協議されたが、ロシア寄りの立場で知られるハンガリーのオルバン首相が反対したため全加盟国一致の合意には至らず、足並みの乱れも出た。
またマクロン仏大統領は3月5日、フランスの核抑止力を欧州各国に提供し、核の傘の対象を広げるための議論に入る考えを示した。トランプ米大統領が、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援や欧州の防衛に消極的な姿勢をみせる中、ロシアの脅威に対し、欧州全体の軍事力、抑止力を強化し、対米依存からの脱却を加速させる狙いがある。
さらに欧州各国でも国防強化の動きが強まっている。ロシアが侵攻するウクライナに隣接し、最も厳しい安全保障環境にあるポーランドのトゥスク首相は、すべての成人男性の国民に対し軍事訓練を実施するための計画を今年末までに作成する考えをしめすとともに、国防費に国内総生産(GDP)の少なくとも4%を充てることを憲法に明記する案を提示した。チェコのフィアラ首相は2030年までに国防費を対GDP比3%まで段階的に増やす予定であると述べた。さらにドイツでは、新政権樹立に向けた連立協議における合意を受けて、財政規律を重視する基本法(憲法)が改正され、防衛力の強化やウクライナへの軍事支援追加に乗り出そうとしている。長年にわたり自らの安全保障を米国の軍事力に依存してきた欧州諸国は、自立的な防衛能力の向上へと舵を切り始めた。米国覇権下の安全保障体制から、より多元的な国際秩序への移行が始まっているといえよう。
8.総括
ロシアウクライナ戦争の勃発後、欧州はロシアの脅威に直面している。しかも長期化する戦争の終結が未だ見通せないなか、第二期トランプ新政権の発足で、欧州は安全保障の自立化を迫られている。第二次世界大戦後、北大西洋条約機構(NATO)という集団防衛の枠組みを軸に、米国の圧倒的な軍事力や核の傘によって欧州の安全保障は確保されてきた。しかしその構図に大きな変化が生まれた。欧州に対する米国の関与が大きく後退すれば、欧州の安全保障をNATOに期待することは難しくなる。
そうした新たな事態に対処するには、強大なロシアの軍事力に対抗するだけの軍事力を欧州各国が自らの手で整備する必要がある。EUや英仏独が中心となりNATOを補う、あるいはNATOに代わる新たな防衛体制を構築する場合、誰が主導して如何なる防衛の枠組みを作り上げるのか、指揮系統はどうするのか、また防衛力強化に必要な経費は確保出来るのか、各国の足並みは揃うのか、さらに欧州独自の核抑止力整備する案も出ているが、規模の小さい仏英の核戦力は米国の核の傘に代わり得るのか等々問題や克服すべき課題は多い(図表6参照)。いまはまだ構想検討の段階だが、実現に向けた道筋は平坦ではない。
平和維持部隊の派遣も先行きは不透明だ。ゼレンスキー大統領は停戦後の「安全の保証」を米国に繰り返し要望してきた。世界最強の軍事力を誇る米国の後ろ盾を得ることで約束を反故にし続けてきたロシアに備え、より盤石な安全を得たいからだ。いま欧州の有志国が平和維持部隊を停戦後のウクライナに派遣する計画が進んでいるが、米軍が参加しない欧州諸国だけの部隊でロシアの侵攻を抑え、かつ効果ある停戦監視の役割を担えるかどうか疑問なしとしない。
一方、米露主導の停戦協議の行方も楽観できるものではない。ウクライナは即時かつ暫定的な30日間の停戦を受け入れる用意があると表明したが、米露協議でプーチン大統領は、停戦は「危機の根本原因を取り除くものでなければならない」と述べ、米側が示した即時提案を事実上拒否し、エネルギー施設への30日間の攻撃停止にしか同意していない。米露は「黒海の海上での停戦の実施」や「完全な停戦と恒久的な和平」に向けた技術的な交渉を始めることで一致したが、プーチン氏はウクライナへの軍事支援や情報提供の停止、さらにウクライナ軍の動員停止などを要求しており、ウクライナ東部の戦線で優勢を続けるロシアが占領地の放棄など停戦条件で譲歩するとは考え難く、法と秩序に則り、侵略国を利することのない停戦条件を纏め上げることは容易ではない。トランプ大統領の思惑に反し、戦争の早期停止は難しくなった。焦るトランプ氏がプーチン氏に対し大幅な譲歩に出る恐れもある。
かように、ウクライナの停戦も欧州の安全保障自立の動きもともに先が見通せない状況にある。米国との同盟関係にある日本も決して他人事ではない。引き続き欧州の動向を注意深く見守っていく必要がある。
(2025年3月24日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)