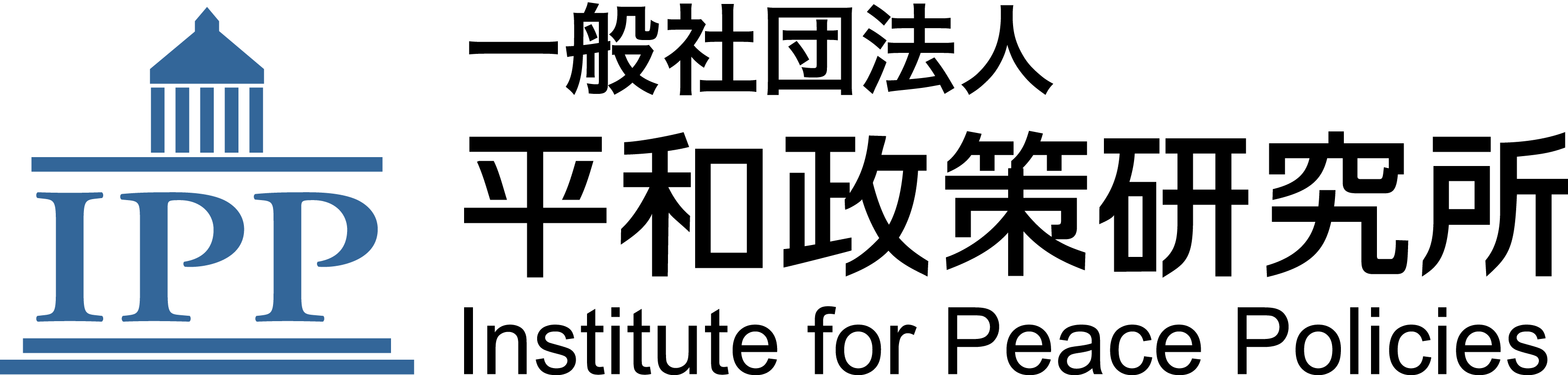はじめに:問題の提起
今年2025年は昭和百年という記念すべき年に当たるが、昭和の最大のできごとであった対米戦争について振り返ることは意義あることである。本稿の目的は、なぜ日本海軍が対米戦争に踏み切ったのかの遠因を、海軍大将山梨勝之進の生涯を通して考察することにある。最初に日本海軍の組織変更について考察するとともに、「海軍条約派」の中核的存在であった海軍大将山梨勝之進次官の更迭が、その後の日本海軍にどのような意味をもっていたかについて論述する。
幕末維新にかけて、日本海軍が模範としていた国は、当時世界の海上覇権を握っていた英国であった。嘉永6年(1853)6月、ペリー率いる米国東インド艦隊4隻が浦賀に来航したことによって、260年続いてきた「パックス・トクガワ—ナ」は終焉した。
万延3年(1860)1月、軍艦奉行木村喜毅と軍艦操練所教授勝安芳ら一行は、咸臨丸で米国に渡り、近代社会というものを肌で感じた。ところがそれから80年後の昭和16年12月8日、日本は真珠湾奇襲を仕掛けた。その遠因はどこにあったのだろうか。
昭和16年太平洋戦争開戦時における日本海軍の首脳は、海軍大臣及川古志郎、10月より嶋田繁太郎、そして軍令部総長は伏見宮博恭王、4月からは永野修身であった。この四人の将官はいずれも軍令部系の出身者であった。
すなわち及川古志郎は、大正13年〜15年に海軍軍令部第一班第一班長、さらに昭和5年〜7年に軍令部第一部長を務めた。
また嶋田繁太郎は、大正9年〜11年に軍令部第一班第一課員、さらに昭和7年〜12年には軍令部第一班長兼第三班長、続いて8年10月〜軍令部第一部長、10年12月軍令部次長に就任している。
伏見宮博恭王は、昭和7年〜16年4月の間、長すぎるほど長きにわたって軍令部総長の椅子にあった。また永野修身は、大正13年軍令部第三班長、さらに昭和5年〜6年に軍令部次長を歴任している。
このように上記の四人が全て軍令部系出身者であることは、対米開戦において、海軍軍令部が海軍をリードしていたことを物語っている。
昭和5年のロンドン海軍会議まで、日本海軍政策の中心は海軍省にあった。ところが太平洋開戦時の省部の首脳部に海軍省系出身者がいなかったという事実は、いつの間にか海軍省の優位体制が崩れ、軍令部優位の逆転現象が起こっていたことを裏書きしている。
昭和16年の対米開戦時、昭和5年のロンドン海軍軍縮条約締結のため奔走した山梨勝之進海軍大将や堀悌吉らの姿は海軍にはなかった。両人とも順調にいけば、日本海軍を代表すべき立場にいるべき海軍軍人であったにもかかわらずである。
昭和9年12月、第二次ロンドン海軍軍縮会議予備交渉のため英国に滞在していた山本五十六中将は、海軍随一の頭脳として評判の高かった親友の堀悌吉が予備役に編入されたことを聞くに及び、「海軍の前途は真に寒心の至りなり。かくの如き人事が行わるる今日の海軍に対し、これが救済のため努力するも、到底難しと思はる。やはり山梨さんが言はれる如く、海軍自体の慢心に斃るるの悲境に一旦陥りたる後、立て直すの外なきにあらずやをおもはしむ」と嘆いた。
このように山本五十六をして、全くの悲観に陥れた当時の日本の海軍大臣は、大角岑生海軍大将であった。しからば我々は、大角海相時代の日本海軍の実態に注目して、「海軍自体の慢心」とは何かについて解明しなければならないのである。
大角岑生は、昭和6年12月から途中岡田啓介海相時代(昭和7年〜8年1月)を挟み昭和11年3月まで、2年9カ月もの長きにわたって海相の椅子にあった。 その期間中、海軍内では次の三つの重要な出来事があった。
その第一は、昭和8年4月に行われた「戦時大本営編成・同勤務令」、および同年10月の「新軍令部条例・新省部互渉規定」の改定である。第二は、「大角人事」によってロンドン海軍軍縮条約の成立のために尽力した「条約派」の有能な海軍将官の大半を予備役に編入したことである。そして第三は、昭和11(1936)年1月、日本が第二次ロンドン海軍軍縮会議から脱退したことである。
1.海軍省優位体制から軍令部優位体制へ
日露戦争直前の明治37年、戦時大本営改正および同勤務令の制定が行われた。
この戦時大本営の編制は、大本営陸軍幕僚(参謀部、副官部)、大本営陸軍諸機関(兵站総監部、大本営陸軍管理部)、その他陸軍から大本営にあるもの(陸軍大臣)、大本営海軍幕僚(参謀部、副官部)、その他海軍から大本営にあるもの(海軍大臣)、海軍軍事総監部から成っていた。
この場合陸軍幕僚は、参謀本部から抽出された必要最小限の人員であり、陸軍諸機関の大部分は参謀次長の兼務する兵站総監の下にある軍令機関であったのに対して、海軍幕僚は軍令部から抽出され、海軍諸機関は海軍大臣の軍政に関する事務処理のために置かれていた。
また海軍軍事総監部には、「海軍軍事部、人事部、医務部、経理部が隷属し、軍事総監は海軍大臣の命を受けて服務し、また軍令部長の区処を受け、軍事計画の諮問に応ずるものとす」、と定められており、これらの諸機関は海軍省の職員によって構成されていた。
このように海軍では、伝統的に海軍省が軍令部よりもはるかにその地位や権限が大きく、絶対的優位体制にあったのである。
さて昭和7年2月、伏見宮博恭海軍大将(昭和7年5月、元帥)が海軍軍令部長に就任した。この時在任わずか4カ月の百武源吾に代わって次長に就任した加藤寛治海軍大将直系の高橋三吉中将は、軍令部第二課長時代に果たし得なかった軍令部の権限拡大を再度目論んだ。その高橋は、昭和7年から8年11月までの次長時代、(1)大本営関係規定、(2)軍令部編制、(3)軍令部条例、(4)省部互渉規定の改正、を行った。
昭和7年10月、軍令部長の権限で軍令部編制の改定が強行された。しかし定員の増加については海軍大臣の認めるところとならず、後日、軍令部条例、省部互渉規定が改定されるまで、既存の定員を広く新設組織に振り分ける形で据え置かれることになった。
昭和8年3月、軍令部側より、軍令部が最終目標にしていたところの軍令部条例と省部互渉規定の改正案が提示された。この改正案の主な点は次の三点である。
その第一は、陸軍の名称に倣って、海軍軍令部を「軍令部」にし、海軍軍令部長を「軍令部総長」にすることである。
第二は、軍令部条例で、海軍軍令部長は「国防用兵に関することを参画し、親裁の後これを海軍大臣に移す。但し戦時にありて大本営を置かざる場合においては、海軍軍令部長これを伝宣す」とあるのを、総長は「国防用兵を掌り、用兵のことを伝宣す」と改め、用兵、作戦行動の大命伝達は、常に軍令部総長の任としたことだった。
第三は、当時軍令部条例第六条の海軍軍令部参謀の分掌事項をすべて削除して、海軍軍令部担当事項は、さらに下位規定である「省部互渉規定」とか、「事務分課規定」とか、「服務規程」に具体的に出すことにしたことである。
これに対して海軍省側は、伝統に輝く名称を変更する必要はない。軍令部総長の「用兵の事を伝達」については、用兵の定義が不明瞭で拡大解釈できる可能性がある。また参謀の分掌事項は海軍軍令部の所掌を定めたものであり、これを削除するとなると、軍令部が何にでも干渉する恐れが出てくる、として反対した。
当時の海軍省には、海軍大臣は憲法上明確な責任を持つ国務大臣であるのに対して、海軍軍令部長は大臣の部下でもなく、また憲法上の責任を取る事もなく、こうしたことは憲法政治の原則に反するとの考え方があった。
海軍軍令部による「省部互渉改定案」は、それまで海軍省の権限と責任に属していた事項の相当部分を、軍令部の権限内に移そうというものであった。その第一は兵力量で、第二は人事行政、第三は警備船の派遣、その他教育、特命検閲などについてであった。
この軍令部改定案をめぐる省部の商議は、特に海軍省側の担当者であった井上成美軍務局第一課長の頑強な抵抗にあって難航したが、7月17日に至って、大角海相は、海軍省不同意のままこの改定案に基本的に合意した。その後法文化作業が行われ、天皇の裁可を得て、昭和8年10月1日「新省部互渉規定」として発布された。
2.「大角人事」の錯誤
昭和5年のロンドン海軍軍縮条約の締結をめぐる「条約派」と「艦隊派」との抗争は、正邪の判定を行わずして喧嘩両成敗的に処置された。
ところが昭和8年1月、大角岑生海相は伏見宮軍令部総長や東郷平八郎元帥に迎合して、谷口尚真、山梨勝之進、左近司政三、寺島健、堀悌吉、坂野常吉ら日本海軍の頭脳とまで言われた条約派の将官を次々に予備役に放逐した。
山本五十六は当時海軍評論家として高名だった伊藤正徳に向かって、「堀を失ったのと、大巡の1割とどちらかな。ともかくあれは海軍の大馬鹿人事だ」と批判した。
「海軍条約派」の名称は当時の新聞記者が名付けたものであったが、おおよそ次の様に定義することが出来る。
(1)海軍軍縮条約の成立を日本の国益のみで捉えるのではなく、国際的利益も考えて捉えこと。
(2)国際思潮なども総合的に考えて海軍政策策を決めること。
(3)山本権兵衛・斎藤実・加藤友三郎の衣鉢を継いだ将官たちのこと。
(4)米英協調をよしとすること。
(5)「常備艦隊」すなわち実力は発動しないが、戦略上無視できない「牽制艦隊」でよしとすること。
(6)主力艦や補助艦の軍縮条約をよしとすること。
(7)財部彪、谷口尚真、山梨勝之進、左近司政三、堀悌吉、下村正助ら、世間から「条約派」と呼ばれた将官たちのこと。
3.「条約派」の要・山梨勝之進海軍次官の更迭
大蔵官僚出身で『饒舌と寡黙』を著した橋口収(広島銀行頭取)によれば、山梨勝之進という人間は、海軍の将官の中でも随一の教養人であったと高く評価している。山梨勝之進自身は、夢窓国師(1276〜1351)とアナトール・フランス(1844〜1924)を尊敬していた。
昭和5年ロンドン海軍軍縮条約締結の際山梨勝之進は、海軍次官として粉骨砕身部内の取りまとめにあたった。
昭和20年5月25日、首都東京はB-25の大空襲を受け、海軍省も焼失した。その最中、山梨は終戦工作のため奔走していた高木惣吉少将に対して、「野火焼けども尽きず、春風吹いてまた生ず」(白楽天)の一節を口ずさんで急速な終戦工作をたしなめた。
この時期、井上成美次官は軍事参議官となったため中央にはおらず、小沢治三郎軍令部次長も海軍総隊長官に転出したため、高木にとって胸襟を開いて相談する人は誰もいなかった。高木惣吉が「どうもこうも、自分の健康の事なんか構って居れなくなりました」とこぼすと、山梨勝之進は「手っ取り早くなんて考えてはいかんぞ」と忠告した。
田島道治が宮内庁長官(昭和23年〜28年)をしている時、昭和天皇は武者小路実篤、志賀直哉、安倍能成、小宮豊隆、谷川哲三ら『心』の同人のメンバーと座談会を行った際、その中の一人が、「いろんな重臣や軍人との思い出をたくさん持っていらっしゃるでしょうが、その中で一番御信任されている方は誰ですか?」と問うと、即座に「山梨勝之進!」と答えられた。
昭和5年の補助艦に関するロンドン海軍軍縮条約の際、山梨勝之進は海軍次官としてその締結に尽力したにも関わらず海軍を追われることになって以降、学習院院長に就任するまでの7年間、世田谷千歳船橋の自宅でひたすらバラづくりに当たった。
昭和14年10月、山梨勝之進は皇太子明仁の学習院初等科入学に際して、野村吉三郎の後任として学習院院長に招聘された。
戦後山梨から学習院大学の英文学の教授に迎えられたブライスは、「私が日本で一番尊敬する人が二人いる。その一人が山梨さんで、もう一人が鈴木大拙さんである」と述べている。
北鎌倉の東慶寺には、鈴木大拙の墓と並んで「不来子」(ブライス)と刻まれた墓が建っている。ちなみにこの東慶寺には、高木惣吉海軍少将の他に岩波茂雄の墓もある。
「海軍良識派」(米内光政、山本五十六、井上成美)ら良識派トリオが、海軍省から去ったことによって、日本海軍は昭和14、15年の日独伊三国軍事同盟締結に際して、「英米可分」という致命的な判断ミスをすることになった。
終戦直後第二復員省を退官した後、物産会社の役員をして暮らしていた中山定義(後の海上幕僚長)は、海上警備隊という名の小さな日本海軍が復活する時、野村吉三郎や緒方竹虎、長沢浩ら先輩に勧められてこれに加わり、2年後の昭和29年秋には海将補となり、初代幹部学校長になった。
中山は、幹部学校の学生に対して、新海軍建軍の精神的支柱になるような講義をしてくれる人は誰かと、士官名簿を開いて思案した。
「自薦他薦の講師でよければ幾らでもいた。・・・・しかしながら井上成美海軍大将(昭和19年〜20年、海軍次官)のいう『ぐうたら兵術』ばかりではないにしても、敗戦の現実を基礎に戦後勉強をし直した形跡は全く窺えなかった。あの人たちの頭脳は、昭和20年8月15日正午を以て冷凍状態になったのだという気がした。しかし山梨勝之進大将と高木惣吉少将だけは違っていた。・・・・世間の風潮とは無関係に、戦争や第二次世界大戦後の世界の軍事情勢をよく勉強していた」と中山は述懐している。
山梨勝之進が歴史の表に登場したのは、補助艦に関する昭和5年のロンドン海軍軍縮会議の時だったが、第一次世界大戦後の大正10〜11年にかけて、ワシントンで海軍軍縮会議が開催された。この結果日米英の主力艦の比率が、6・10・10と決定された。この時勝之進は全権委員随員であった。
昭和2年3月、第一次若槻内閣は経済恐慌のため3週間のモラトリアムを実施した。同年4月20日田中義一内閣が成立し、昭和3年6月張作霖が奉天で関東軍の河本大作大佐らの手によって爆殺(張作霖爆殺事件)された。
昭和4年7月、田中義一内閣総辞職し、浜口雄幸民主党内閣が成立すると、直ちに「十大政綱」を発表し、経済の抜本的建て直しが図った。同年10月世界大恐慌が発生し、昭和5年1月金輸出解禁を実施した。
浜口首相は蔵相井上準之助らと共に、協調外交を掲げて不況からの脱却を図り、西園寺公望ら重臣の協力を得て、補助艦に関する海軍軍縮の実現を図った。すなわち軍事参議官の岡田啓介大将の協力の下に、「海軍首脳に不満はあったとしても軍縮会議の成立を図る」ことを確認し、「三大原則」をまとめた。すなわち(1)補助艦総保有量の対米7割、(2)大型巡洋艦の対米7割、(3)潜水艦は現有保有量の維持を目指した。
昭和5年1月、若槻礼次郎・財部彪らを全権として、ロンドン海軍会議が開催され、日米英の補助艦の比率は、補助艦の総量69.75%となった。ところがロンドン海軍条約の批准をめぐって、日本国内は紛糾したのである。
昭和5年4月3日開会の特別議会における条約批准に必要な枢密院での審査過程において、いわゆる「統帥権問題」が発生した。
野党の立憲政友会(犬養毅総裁、鳩山一郎内閣書記官長・文部大臣など)によれば、軍令部の反対を押し切って政府が回訓決定したことは、「統帥権上重大な問題であり、憲法上の疑義を免れない」として浜口内閣を強く批判した。
問題となったのは、帝国憲法第12条「天皇の陸海軍の編成及常備兵額を定む」と規定された天皇の編成大権であった。同11条には「天皇は陸海軍を統帥す」と規定されており、統帥部と共に国務大臣の輔弼によるものと一般には解釈されていた。
前述した通り、海軍の場合は陸軍と異なり、海軍大臣の権限は軍令部長より大きく、ロンドン海軍軍縮条約のような兵力量の決定は、海軍大臣の専権とされていた。しかし兵力量の基礎となる海軍の「国防計画」は軍令部で立案されることになっており、両者の権限には曖昧な点も存在した。
政友会はそこに付け込んで政府を攻撃するとともに、「艦隊派」と連携して政府攻撃をして倒閣を謀った。
これに対して政府側は、「条約は純然たる国務事項」として政府の権限である兵力量も政府の一員である海軍大臣、すなわち海軍省の権限であるとの見解を示した。
岡田らは回訓決定に際して、今後の紛糾を避けるために軍令部長加藤寛治の同意を取り付けようとした。
このように統帥権干犯問題は、その後の日本社会に大きな反響を巻き起こし、右翼の介入を招く結果となり、テロ事件の引き金となった。
政府は元老西園寺公望や重臣の協力によって議会を乗り切り、5月以降枢密院の批准を巡っても強い姿勢で臨み、ようやく10月2日ロンドン条約を批准した。しかしその後浜口雄幸首相に対する暗殺事件や、鈴木侍従長に対する暗殺事件(「二・二六事件」)が起こった。
軍令部をリードした末次信正軍令部次長の策動や、伏見宮博恭王や東郷元帥の頑迷よって財部海相は辞職に追い込まれた。
昭和6年9月18日満洲事変が勃発した。同年12月第二次若槻内閣が倒れ、代わって犬養毅政友会内閣が成立した。昭和7年2月9日には井上準之助が血盟団によって射殺され、続いて青年将校による白昼首相官邸における犬養首相の暗殺である「五・一五事件」が突発した。
昭和8年1月9日岡田啓介に代わって大角岑生海軍大将が新海相に就任し、同年11月、海軍の大異動が発表された。
同日付『朝日新聞』に、海軍大異動を批判する次の様な記事が掲載された。
「先の寺島(健、軍務局長)中将問題に続いて、佐世保鎮守府司令長官左近司政三中将、第一戦隊司令官堀悌吉中将をいずれも軍令部出仕としたことは、いわゆるロンドン条約派を排撃する一部勢力に押されて、有用な人材を無批判に閑地に投じた。・・・・これは決して歓迎すべきことではない」。
実松譲海軍大佐(在米国日本大使館付海軍武官補佐官)もその著『ああ日本海軍』の中で、「昭和9年、2年間の米国駐在を終えて帰国した中沢佑中佐は山梨勝之進に会い、『私が米国に行っている間に、軍政方面の権威者が相次いで海軍を去ったのは、どうしても腑に落ちん。一体どういうことですか?』と質問すると、勝之進は、『一旦大臣が肚を決めたら、どうにもならん。大角海相の後ろからいろいろな圧力がかかっている。具体的には伏見宮殿下と東郷さんだ』」と述べたことを紹介している
米内光政元首相兼海相は、「我々の三国同盟反対派は、あたかもナイヤガラの瀑布の一二丁上手で、流れに逆らって舟を漕いでいるようなものだった」と緒方竹虎に嘆いた。
4.山梨勝之進の学習院院長就任
昭和14年秋、山梨勝之進は松平恒雄宮内大臣(昭和11年3月〜20年6月)の訪問を受け、10月4日学習院院長に就任することになった。前任者の野村吉三郎海軍大将は阿部内閣の外務大臣に就任したため学習院院長を辞任した。このため当時浪人中の山梨勝之進海軍大将に白羽の矢が当ることになったのである。
学習院院長時代、山梨は鈴木大拙(貞太郎)を『輔仁会雑誌』(明治22年発行)の記事で知り、大いに共鳴した。山梨は「徳育は知性を通してなさるべきものであって、徳育を重視して知育を軽んずるのは間違いである」との考え方を持っていた。
昭和52年7月号『水交』において、戦前学習院高等科の生徒であった岡明は次の様に述べている。
「入学式でうちのムッター(母)が初めて目白に来た。門の所で小使さんに式場を聞いたら、わざ正堂まで案内してくれた。物腰が丁寧で応対が至れり尽くせりだったので、さすがに学習院の小使さんは違う、と感心していたが、入学式が始まるとその小使さんが、『本日は誠に天気もよろしく・・・』と挨拶されたので、ここに至って初めてその小使さんが院長なのだと分かった」。
昭和42年12月16日付『朝日新聞』の「声」には、次の様な投書が掲載された。投書の主は小倉鉄樹(小倉遊亀女史の夫で30歳年長の禅研究家)である。
「学習院初等科の校舎は維新の元勲山岡鉄舟の邸に建っている。やがてこの校舎の落成式典に、私の亡夫小倉鉄樹がご招待に預かった。その夕方、鉄樹は帰宅するなり、妻遊亀に言った。坐骨神経痛で足元もおぼつかなく立車を降りると、門衛とおぼしき一人が『さあ、どうぞ』と片手の腕を取った。礼儀深い門衛思っていたところ、『山梨でございます。失礼いたしました』と挨拶された」。
また皇太子明仁の英語教師であったヴァイニング夫人は、帰国後、『ラスト・サムライ』という一文を起したが、その中で山梨勝之進から「バラも人間と同じで、根を痛めないと駄目ですよ」と言われたと述べている。
5.明仁皇太子の疎開
敗戦直前の昭和20年7月14日、奥日光における南間ホテルで学習院初等科の再々疎開授業が始まった。
当時学習院院長の山梨勝之進は、この戦争に敗北した場合、明仁皇太子をいかにして落とすかについて頭を痛めていた。その結果、(1)日光から足尾街道を下らせるルート、(2)湯元から金精峠を抜けて群馬県片品村に抜けるルート、(3)日光から福島県田島に抜けるルート、の三つが頭に浮かんだ。
昭和30年代半ば、山梨勝之進は谷口尚真(海兵19期、昭和5年6月軍令部長、昭和8年9月予備役)の長男真を自宅に招いて次のように述べている。
「私が元気な間にお父さんの谷口大将が如何にお偉かったかを長男であるあなたに伝えておきたい。御父君は軍令部長時代に、ロンドン軍縮条約締結をめぐっての海軍上層部の紛糾処理にあたって、言葉では言い尽くせない程苦心惨憺された。御父君のような見識を当時の指導者が抱いておれば、今回の戦争のような悲惨な事態には至らなかったと思う」。
この勝之進の述懐は、谷口尚真大将に対すると同時に自分自身を重ねて語ったものでもある。
山梨勝之進の長男の山梨進一(埼玉大名誉教授)は、『父の思い出』と題したエッセイの中で次のように述べている。
「京都の妙心寺に旧知の管長を訪問した。管長同郷の宮城県出身であった。父は以前から禅に関する造詣が深かった。十牛の図の話など題は忘れたが、小童が春を探して野山を跋扈し、探しあぐねて自宅に帰ると、庭の一隅に梅が咲いているのを発見したという寓話である。要は幸福というものは、捜し歩いて求めるものではなく、自分の身近の再認識にあるということである」。
昭和8年勝之進は海軍を辞めた後、千歳船橋の自宅に落ち着いた。自宅では英文学の書物を好んで読んだが、その中でシェークスピアの戯曲の次の一節が心に刺さった。
“There is tide in the affair of men”(「人生には潮時というものがある」)
山梨勝之進は常々、「人間は自分のしたことなどは、自慢げに話すべきではない。自分の事は他人が言ってくれるものだ」ということを処世訓にしていた。
6.昭和天皇の「人間宣言」に関与
昭和21年元日、新聞に昭和天皇の「人間宣言」が発表された。
「朕は爾等国民と共にあり。常に利害を同じうし休戚を分たんと欲す。朕と爾等国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越せる民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基づくものに非ず」。
それから14年経った昭和35年正月の『サンデー毎日』では、天皇の「人間宣言」が世に出るに至った経緯について、宮内庁詰めの記者である藤樫準二が詳細に解説した。このため山梨勝之進も「人間宣言」が出るに至った経緯について、重い口を開けざるを得なくなった。
「自分は無関係とは言わないけれども、このことは私の口から決して言うべきではないという原則を守って14年経った。これが世間にわかったものだから、宮内庁はもちろんのこと、どこまで本当かということについて八方から私に聞こえてきた。
ところで、三、四年前に宮内大臣の石渡さんの年忌に今の総理大臣の池田さんや日銀総裁の山際さん、愛知撥一さんなども来られて、石渡さんのお手柄である。人間宣言の経緯を一言貴方の口から話してくれないかと言う要望があったので、断りきれないで、約30分間ほど簡単にその経緯を言ったことがある。政府と共に天皇陛下も、今お読みしたような意味のことを国民全般におっしゃりたかったのだと拝察するのである。
国民もあの日本の国が混乱の中でどうなるのか。天皇陛下がどうなるか。皇太子がどうなるか。そういうことが一切不明な場合に、なにがしかこういうような意味のことを知りたいと欲したのではなかろうか。またマッカーサーとしても、連合軍の立場やアメリカの立場として、こういうものが何かないといけないと思っていた。だがマッカーサーが注文してそんなことを言ったら大事になるわけで、誰も言えない。こっち側だけで出しても、マッカーサー連合軍やアメリカが横を向くのでは値打ちがない。向こうの言うことを聞いて、こっちが書くのでも意味がない。どうしたらこういう危ない、重大な問題が解決できるかということを考えたのである」(インタビュー記事のため文章が多少おかしいため、筆者が若干直した)。
勝之進は自分のやったことには非常に謙虚であった。手柄は他人に譲ることを旨とし、決して自分自身を誇示すような人間ではなかった。そのため慎重な言い回しをしているが、要は天皇の「人間宣言」は結局山梨自らが「考えた」と告白しているのである。
山梨の話はさらに続く。
「客観的にいろいろ見ると、よく古臭い言葉だが、『動かずして変えず、なすことなくしてなる』という。これは論語に出てくる。客観的に静かに拝見して、今の陛下の御徳というものは、こういうふうに動くかと言うことをひしひしと感じた。実際言えば、何の某がどういうふうに動いて、何の某がどういう手紙を書いた。何の某が何時やったと言うことではない。ただそういうものが動くようになった機運が、どこから動いてきたかと言うことを、もっと高い次元から考えてみると、見えない非常な力のものが動いている。
手を叩いて音が出る。どっちの手が先か。音が出るのはどっちの手が先かというのと同じである。火打石を打ったようなもので、火は出るがどっちが先か、一緒に出る。そういうものがあるのだなということを、無学なわれわれでもつくづく感銘した。それで、ああいうことになって動いていった。陛下のああいう勅語になって、それですっかり内外の情勢が落ち着いたのである」。
打てば響く。物事は呼応することによって美しい音色を発する。強制ではない。人間と人間が紡ぎだす美しき調和こそ、山梨勝之進が心から望む世界だった。
勝之進の意向を受け、総司令部(GHQ)との間の橋渡しを担当したのが、学習院雇入外国人教師のブライスである。そのブライスは山梨勝之進の人柄に深い敬意を抱いていた。
それでは勝之進はどのような経緯からブライスを学習院の教師として採用したのだろうか。その辺の事情について、勝之進の下で学習院事務長を勤めた浅野長光は、次のように回想する。
「山梨さんという方はとても立派な方です。よく調査して先の先まで読んで手を打っていました。私が一番尊敬している人です。清貧で英国好きでした。イギリス王室のあり方を日本の皇室は学ぶべきだという考えでした。海軍大将ですが、和漢・洋書を読みこなして、幅広い学識がありました。禅にも造詣が深くて、新渡戸稲造を尊敬していました。思想的にも近かったんじゃないかな。またリンカーンを非常に尊敬していました。ブライスを学習院に採用したのも、山梨さんが先の先まで読んでやったことです。日本のことをよくわかっているイギリス人で、単なる通訳や英語教師ではなく、その人物を見込んだんですね。英文学者の斉藤勇さんと山梨さんとは仲良しでした。その斎藤さんの推薦でブライスを雇ったわけです。ブライスはイギリス人で、皇太子にキングス・イングリッシュを教える教師としてもいいだろうし、GHQとの交渉にも第三者だから好都合と言う読みがあったのです」。
それではブライスという人間はどのような生い立ちだったのだろうか。
ブライスを一言で言えば、古武士風、あるいは高僧風な趣を持った徹底したリベラリストということができる。レジナルド・ホレス・ブライス(R. H. ブライス)は、1898年12月3日、父ホレス・ブライス、母ヘンリッタの一人息子として、イギリスのエセックス州の西南、ロンドンに近いイルフォードで生まれた。
父のホレス・ブライスは、グレイト・イースタン鉄道に勤務する駅員だった。そんなことから少年時代のブライスは、駅頭でチョコレートを売って家計を助けた。ブライスの父のホレス・ブライスは、ブライスがイギリスを出て6年目の1930年、ブライスが32歳の時に他界した。
労働者階級の家庭に生まれたブライスは、公立のクリーブランド・ロード校へ入った。その後カウンティ・ハイスクールに入学した。ブライスは12年間の小・中学校を終了すると、16歳から18歳までの2年間、「未資格生徒教師」として働いた。
1914年夏、ブライスが16歳の時、第一次世界大戦が始まった。満18歳に達した時ブライスは軍隊に召集されたが、兵役を忌避したため、1916年から1919年初頭までの3年間、ロンドン市のワームウッド・スクラブズ監獄に収監された。
当時イギリスには、祖国のために戦うことを拒否した C・O(Conscientious Objector)と呼ばれる良心的徴兵忌避者がいて、その数は1万6千人にも上った。
第一次世界大戦における良心的徴兵忌避者の大部分は、資本主義のために戦うのを拒否する社会主義者的兵役忌避者であったが、暴力そのものに反対する徹底した平和主義者や非戦主義者、人道主義者も少数ながら存在した。ブライスはそうした徴兵忌避者に属していた。ブライス自身は母方の独立教会会員としての非国教徒の宗教的信念と、彼自身の平和と非戦の信念によって、良心的徴兵忌避者になった。
吉村侑久代女史は、その著『R. H.ブライスの生涯—禅と俳句を愛して』の中で、当時英国における良心的兵役拒否者であるクエーカー教徒たちに対する凄まじい弾圧の様子を、デイヴィッド・ボウルトン著『異議却下—イギリスの良心的兵役拒否運動』(福田晴文他訳、未来社)から引用して紹介している。
「クエーカー教徒の青年、アーネスト・イングランドは以前身体検査ではねられたのに 、1917年に召集された。重労働二年の刑に服するためワームウッド・スクラブスに送られ、そこで最初の夜から具合が悪くなったが、当直看守から室内便器はやらんと言われ、さんざん苦しんだあげくイングランドは床を利用した、すると看守は彼の顔をその排便に突っ込むような事までした。数週間にわたり重症が続き、とどのつまりはダートムアに移されたが、そこで衰弱しているのに雪かき作業に就かされ、毎日作業後にマーガリンつきパン一片と茶を一杯という食事しか与えられなかった。休戦後三カ月、彼はダートムアで作業を続け、手の施しようもないほど衰弱しきったあげく、1919年3月6日死亡した」。
ブライスもこれとほぼ同様の扱いを受けたと思っていい。
京城帝国大学予科で、ブライスに英語とラテン語を習い、その後同校の有機化学の教授になった小西英一によれば、ブライス自身は自分の徴兵忌避の理由について、「私は生命が惜しくて戦争に行かないのではない。もしも、コレラやペストのような恐ろしい病気が兵隊の間に流行して、その看護のため軍隊に入れと言うのならいつでもどこへでも行きます。私は戦場へ行って敵兵を、つまり人間を殺すことが出来ないのです」と語っていたそうだ。
ブライスは、幼児から心に沁み込んだ信仰である「汝、殺すことなかれ」と言う戒律を固く守った。彼はまた菜食主義者でもあり、徹底した人道主義者だった。
口の悪い同僚の教師からは、「ブライスさんはセンチすぎる。動物性の食品は卵と牛乳以外は全く食べない。彼は自分が肉食しなければ、一頭でも一匹でも牛豚や魚が助かると言うが、彼が食べなくても、他人がその分を食べるから何にもならない」などと皮肉を言われても全く意に介さなかった。
朝鮮ホテルで、教官たちの忘年会や新年会が開催された際にも、日本人の教官がフルコースを食べたのに対して、ブライスのテーブルには、明治町の「寿司久」の稲荷鮨と海苔巻きが皿に乗せられて出された。
これは戦後のことだが、ある日ブライスは皇后陛下に、「ブライス先生は、肉も魚もお上がりにならないのによくお肥りになって、元気ですね」と言われた。これに対してブライスは、「象は木の葉だけ食べます」とジョークをもって答えると、皇后は声をたてて笑った。
第一次世界大戦終了後のブライスの経歴を見てみる。
大正12年(1923年)ロンドン大学英文学科を優秀な成績で卒業したブライスは、京城帝国大学予科の藤井秋夫教授より同校の雇入外国人教師として京城に赴任することを勧められ、即座に快諾した。ブライスが京城赴任を決めた理由には、大戦中またその後も、良心的徴兵忌避者に浴びせられた心無いイギリス社会の非難中傷があった。
大正13年(1924年)、ブライスは25歳の時、ロンドン大学で学友だったアンナ・ヴェルコヴィッチと結婚し、9月京城帝国大学予科の外国人講師に就任した。その際ブライスは、極めて貧しく優秀な学生数名に、月20円の奨学金を出すことにした。
大正15年、この年から京城帝国大学に学部が出来た。ここでブライスは、「自由作文」「英文学史」「英詩概論」などを担当した。
昭和2年(1927年)、ブライスは鈴木大拙のEssays in Zen Buddhism: First Seriesを読み、感銘を受け、以後大拙の説く禅思想の熱心な信奉者となった。
昭和10年、ブライスは、イギリスに一時帰国して、アンナと正式に離婚した。結婚破綻の原因について平川祐弘は、「ブライスが東洋の天地が気に入り、日本語を学び、朝鮮語の会話を楽しむようになればなるほど、そのアジアへの愛情自体が遮りとなって、アンナ夫人との間の障壁はいよいよ大きくなったのではあるまいか」と推測している。
翌昭和11年、ブライスはシベリア鉄道で京城に帰る途中、アーサー・ウェイリー英訳の『老子』に深く感銘を受けた。
京城帝国大学に復職したブライスは、旧市内梨花町に二階建ての日本家屋を建て、4年後に京城を去るまでここに住んだ。
昭和12年3月、ブライスが38歳の時、昭和2年から京城で土木建設請負業を営んでいた来島宮松の二女で、当時京城のデパートに勤め、いつも温かくブライスを迎えてくれた17歳下の萩市出身の来島富子と再婚した。裏表のない冨子の実直な人柄を、ブライスはこよなく愛した。
昭和14年9月3日、イギリス、フランスがドイツに宣戦し、第二次世界大戦が始まった。京城ではイギリス人が徐々に住みにくくなってきたため、ブライスは16年間に及ぶ朝鮮での生活にピリオドを打ち、日本に移住して帰化することすることを決意した。そして一旦夫人の郷里である萩に滞在した後、金沢第四高等学校の雇い入れ外国教師となり、金沢に住むことになった。
ところが昭和16年12月8日、太平洋戦争が勃発したため、ブライスは石川県警に保護され、金沢警察署内に抑留された。翌年2月長女春海が誕生するものの、3月金沢第四高等学校の職は解かれ、同月、神戸市内のイースタンロッジ・ホテルの交戦国民間人抑留所に収容されることになった。
「日本人はどうして古来のよいもの、よい習慣を、無反省、無雑作に振り捨てて、外来のよくないもの、よくない習慣を生活の中に取り入れるのだろうか」。
こう語るたびに、ブライスの顔は曇った。
またブライスは、「例えば礼法であるが、日本の礼法の美しさ、奥ゆかしさは世界一だ。キスだの握手だのは、犬や猫でもする動物的な愛情表現で、夫婦・親子・肉親の間ならともかく、第一に不潔・不衛生である。その点、目と目を見合わせ、控えめに静かに上半身を傾ける姿は実に美しい。・・・・美的なものは、皆すべて不便なものである」とも言った。「下駄、草履、畳、障子、襖など、日本の生活は美しい。そして不便である」。
ブライスの日本文化への傾倒は、日に日に深まっていった。
ブライスは京城長沙洞にあった臨済宗・花園妙心寺の京城別院で、華山大義老師につき、参禅した。日曜日などは、早朝五時から座禅、接心、朝粥を頂いて帰るという修行を、根気強く続けた。
当時妙心寺では、毎月3と8の日に、夕食後「三八会」と言うのが催され、華山老師の「無門関」の講話があった。その他、毎週土曜日の夕方には白隠禅師による『独語心経』の講義などもあったが、ブライスはそのいずれにも出席した。
さらにこの頃のブライスは、仏典を味読するため、漢字の学習を始め、習字までするようになった。ここでの漢字の学習が、ブライスの川柳研究の基礎になった。
華山大義老師は当時54、55歳で、東大哲学科出身。6年間にもわたって雲水修行をやり、兵隊にとられた時には、最下級の輸卒を勤めたこともある人物だった。篤学な学問僧で、講義にも講話にも優れたものがあった。
ブライスは、『英文学における禅と日本古典』(Zen in Literature and Oriental Classics)の序文において、「禅は現在最強の力である。人類が生くる限りそれは禅により生くるものである。詩的活動のある限り、宗教的活動のある限り、英雄的思想のある限り、自然が人の内に、また外にある限り、そこに禅がある」と書いた。
またブライスは、世界で最も短い詩の形式である「俳句」と「川柳」にも強く惹かれた。中でも芭蕉と一茶に傾倒し、HAIKU 四巻、History of HAIKU 二巻、SENRYU 一巻、Japanese Life and Character is SENRYU 一巻などを著した。
20代の京城時代のブライスの句に、「葉隠れや 青い夢見る かたつむり」があった。
「皇太子殿下は、自分が最も長く教えた学生です」、そして「皇太子殿下には考え方を教えました」とブライスは親しい人に話した。ある時には「人生を教えました」とも語ったことがある。
終戦の昭和20年からブライスが亡くなる昭和39年までの19年間、ブライスは学習院外国人教師、その後私立大学になってからは学習院大学文学部英文学科の教授として勤めたが、その間、小泉信三やヴァイニング夫人らと共に、皇太子明仁の教育にあたった。
明仁皇太子に対するブライスの教育方針は、英語力の向上を図ることはもちろんだが、それよりも増して、豊かな情操の涵養と「ノーブレス・オブリージ」の自覚を待つものだった。
こんなエピソードがある。皇太子と勉強中に、ブライスがペンか鉛筆を机の下に落としてしまった。ブライスはすぐには拾い上げず、しばらく皇太子の反応をみた後に質問をした。
「さて、どちらが拾うべきでしょうかね?」
すると皇太子は答えた。「近い人が拾うべきです!」
これに対してブライスは、「それではメジャーを持ってきてもらいましょうか?」と言った。ブライスらしくユーモアをもって応えた上で、「身分の高い人が拾うべきです!」と明確に言った。
「何故でしょうか?」
「殿下、身分が上の人は、常に下の人に仕える用意が出来ていななければなりません。それが、『ノーブレス・オブリージ』(高い身分に伴う義務)だからです!」
ブライスは、「自発性」と言うことを特に尊重した。単に定められたことをやるのではなく、自らの意思で行動することが大切だと教えた。一方的な強制や命令は、ブライスが最も嫌悪するものだった。
「物事と言うものは、またそれに対する対応の仕方は予め決まっているものではない。その時の当事者や状況によって変わらなければならない。自分で考え、判断しなければならない。物差しで測って判断すると言う合理主義、科学主義ではいけない。その人の意思や感情を尊重する人間主義が、人と人との本当の人間関係を作り上げるのだ」と固く信じていた。
ブライスは、「科学は人間性の敵である」とさえ言った。科学の進歩が人間性を蹂躙するとも考えていた。したがって「鉛筆を落とした時に近くの人が拾うべきだ」としたのでは、自主性が欠如していると考えたからだった。
授業中ブライスが学生に対する口癖は、「オサエナクテモイイデスヨ!」であった。
7.山梨勝之進とブライス
比較文学者の平川裕弘は、『平和の海と戦いの海』の中で、ブライスの勝之進に対する敬愛ぶりを、当時文部大臣であった前田多聞の言葉を引いて、次のように述べている。
「それにつけても想い出すのは、ブライス氏の山梨氏に対する傾倒ぶりである。詔書問題のずっと後、・・・・・田島道治氏の下に夕食によばれ、席上初めてブライス氏にお目にかかったその時のブライスさんの話に、『自分は日本で一番尊敬する人が二人いる。その一人は山梨さんで、今一人は鈴木大拙さんである。もし日本が、山梨さんを総理大臣にして、鈴木大拙さんが大僧正になれるような国になったら、日本はけだし理想的な国家になるであろう』と、真面目な顔をして言われたことがある」。
これはブライスの心底から出た言葉だった。ブライスは勝之進に自分の理想の人間像を見出していた。
ブライスと勝之進には、さまざまな面で共通するものがあった。それは古今東西の古典に通じている深い教養であり、キリスト教と禅に関する宗教の理解であり、武士道精神やジェントルマンシップへの理解であり、英国風のリベラル・アーツと常識への信頼であった。
勝之進の好きな言葉に、“There is a tide in the affairs of men.”と言うシェークスピアの戯曲『ジュリアス・シーザー』の中のアントニオの演説の一節があった。これは「人生には潮時というものがある」との意味であるが、勝之進とブライスの二人には、国家や人間というものに対するある種の諦観があった。
勝之進の諦観とは、昭和5年のロンドン海軍軍縮条約の際に海軍次官としてその取りまとめに当たり、それが故に海軍大臣を確実視されながらも予備役に追いやられた苦い思い出から来るものだった。
一方ブライスの場合は、第一次世界大戦時に、良心的徴兵忌避者として3年近くにわたってロンドンの監獄で労苦を体験させられたことであり、さらに太平洋戦争の目前、日本への帰化申請を出していたにもかかわらず認められず、今度は愛する家族と別れて将来の見通しがないままに3年数カ月にわたって神戸の敵性外国人抑留所へ収容されたことへの感慨であった。
しかし二人は、東西の古典を通じて、人間性そのものへ大いなる希望を抱いていた。
「外柔内剛」の二人の心に横たわっていたのは、「dignity(尊厳)」だった。ブライスは勝之進に尊厳の実態を見た。
ブライスは、天皇制に日本文化の真髄をみた。その天皇制を護ろうとしている勝之進は、日本文化そのものであった。したがってブライスとしては、敗戦後、日本の軍国主義に代わって占領軍が権力によって日本文化を壊そうとするのが、許せなかった。 高橋紘著の『天皇家の密使たち—秘録・占領と皇室』の解説を担当した袖井林二郎によれば、敗戦直後の時代に、天皇と皇室を守るために密かに動いた勝之進やブライスは、歌舞伎の黒衣と言ってよいとしている。
「『天皇家の密使たち』とは、あの危機の中で、天皇と皇室を守るために密かに動いた人々のことだが、それは何も宮中関係者に止まらない。占領する側の総司令部(GHQ)の中にさえ密使はいたと言える。
マッカーサーの軍事秘書官で知日派のフェラーズがそうだし、「人間宣言」の元になった文章を起草したヘンダーソン教育部長も、その役割を知らずに果している。東京裁判の首席検察官として天皇を証人に呼ぶことを食い止めたキーナンもそうである。
もちろん日本占領を成功させるためには天皇は不可欠で、その力は百万の軍隊に値するとマッカーサーは判断し、アメリカも戦争が終わる前から天皇制の効用を認めていたという大前提があったからこそ、天皇も皇室もその存続を許されたことは確かだ。
だが歴史は大前提だけで作られるものではない。一時は天皇自身が退位を考えるほど危機意識を持っていたのである。占領する者とされる者との間の意思の通い合いは難しい。
その間に介在した密使たちの一つ一つの動きが結びついて、始めて天皇は退位することもなく、皇室は今日ある姿で生き延びる事ができたことがよくわかる。・・・・・私の好みから言うと、「人間宣言」発表までの全過程にわたって、密使と言うよりはまるで歌舞伎の黒衣のような役割を果した学習院院長の山梨勝之進の働きが特に興味深い。
この元大将は、戦前にイギリスの王室制度を実際に見聞しており、そのモデルとして皇室の生き残りを策し、いわばGHQを巧みに操りながら、「人間宣言」によって象徴天皇制への地ならしに成功したのであった」
ブライスの「座右の銘」の一つに、「雁無遺足従之意 水無沈影之心」と言う『禅林句集』の一節があった。
この言葉の意味は、「自分の意思は雁が足跡を残さないように、自分の心は水が影を沈めることがないように、自分の意も心も人に申し上げるものではない。無い事を心に据えていることを理解して欲しい」というものである。当時のブライスの心境を表わす言葉であった。
話を昭和19年に戻す。
昭和19年5月、神戸にあった収容所はすべて一つに統合され、ブライスたちは神戸を見下ろす六甲山の布引滝に近い再度(ふたたび)公園の中の「林間学園」という以前感化院だった建物に収容された。「林間学園」は、寄宿舎と教職員の部屋と教室と三つの建物が接続して建てられていた。ここにブライスを含めて、175人の交戦国外国人が抑留されていた。
ブライスは6人の同室者と共に、教員宿泊室であったと思われる部屋で生活した。ブライスは床の間にベッドを置き、その上に自分で作った棚に本を何冊も重ねて積んでいた。一日中ベッドの上に座り、時に足を組み、また時に足を投げ出した。
ベッドカバーの上には辞書とノートを置き、ベッド脇のテーブルに聖書台を置いて、そこで書き物をした。ブライスが、「俳句」や「川柳」の執筆に取り組んだのはこの時期だった。
同じくここに抑留されていた米国人のロバート・エトケンに対してブライスは、「ここにいる監視人のような人間によるアメリカ領土の占領を、君は想像できるかね」と言った。
ブライスは、東南アジアにおける日本の占領の実態がかなりひどいものであると感じており、文化の成熟のためには、敗北を経験することが有益であると考えていた。
昭和20年3月17日、米空軍の神戸大空襲によって、神戸元町の冨子夫人が住む寓居はブライスの蔵書と共に灰燼に帰した。ただ夫人が抑留所へ運んでいた書物や原稿と、ブライスが学生時代から持っていた銀のフルートだけは戦禍を免れた。終戦後ブライスは、日本政府から財産の補償を受けた。
昭和20年8月15日、日本の敗戦によって神戸に抑留されていた交戦国の民間人は直ちに解放された。ブライスは神戸に居所を定めていたルイス・ブッシュ方に家族共々身を寄せ、ここから鎌倉の鈴木大拙に手紙を書き、無事を知らせると共に就職の世話を頼んだ。
10月2日、大拙はブライスからの手紙を読んで、「京都の大谷大学であれば、就職の世話が出来ると思う」と返信した。
早速10月中旬、ブライスは鎌倉に大拙を訪ねた。続いて英文学の重鎮の斉藤勇教授を訪問し、さらにGHQのCIE(民間情報教育局)にヘンダーソン中佐を訪ねた。ヘンダーソンとブライスは、お互いに俳句の研究を通してよく知った仲であったが、会うのは初めてだった。
抑留生活から解放された英米人の多くはGHQ関係の職に就いた。日本語を理解する者は特に優遇された。そんなわけでブライスも一時はGHQに勤務しようと考えていた。しかし斉藤勇の推薦と勝之進の決断によって、その直後の昭和20年11月初旬、ブライスの学習院への就職が決まった。年6千円の契約で、12月1日、発令と同時にブライスは家族と共に千歳橋に近い学習院の宿舎に入った。
この前後ブライスは、ヘンダーソン中佐の紹介でマッカーサー司令官の高級副官のフェラーズ准将と副官のバンカー大佐と親しくなった。
フェラーズ准将はその日本研究の一つとして、小泉八雲を研究していた。彼は、日本占領については、天皇を尊重することによってその実を挙げる事ができると主張する知日派の一人でもあった。
フェラーズは、昭和20年9月2日、天皇が米国大使館に始めてマッカーサー元帥を訪問した際、大使館の玄関に天皇を出迎えた。ブライスは天皇を深く尊敬しており、また八雲の著書を多数読んでいたので、フェラーズ准将とは初めから話が合った。
バンカー大佐は、ハーバード大学卒業後オックスフォード大学に学んだという英国贔屓の人間で、マッカーサーが最も信頼する副官だった。
マッカーサー元帥は、フェラーズ准将とバンカー大佐から、ブライスの人となりを何度も聞かされていた。さらに直接会ってみた結果、ブライスの実直で誠実な性格を認めた。
ブライスの学習院への就職後間もない頃、勝之進がブライスを直接外務大臣の吉田茂に紹介する機会があった。
吉田としては、フェラーズ准将やバンカー大佐と親しくなっていたブライスが、日本政府側の連絡役を勤めてくれる事は何よりもありがたかった。
非公式に宮内省とGHQの連絡役の役割を勤めていたブライスのGHQの窓口となったのは、ヘンダーソン中佐であった。
ある日のこと、二人の話題に、「教育勅語」のことが俎上に上った。その結果、勅語そのものの内容はともかくも、利用の仕方が日本の民主化を邪魔していると言うことになった。
ブライスは、週二回ほどヘンダーソン中佐を、宮内省の車で訪問することになっていた。
12月初め、ブライスは多少興奮気味にヘンダーソンのところにやって来て、「天皇は自分の神格化を否認したい意向であり、二度とあのように悪用されないようにしたがっていることを宮内大臣から聞いた」と伝えた。そして「そのような意向を公式に表明するには、どのようにすればよいのか教えて欲しい」と言った。
これを聞いて驚いたヘンダーソン中佐が、「上司のダイク代将が出張なため、自分では何とも言えない。したがって二、三日待って欲しい」とブライスに言ったところ、ブライスは、「時間がない。個人的な非公式な考えでいいから是非聞かせて欲しい」と迫ってきた。
ランチ・タイムになったので、ヘンダーソンは第一ホテルに戻って、次の文章を書いた。
「私と私の国民との間にある絆は、常に相互の信頼と愛情によって結ばれてきた。それは単なる神話や伝説に依存するものではない。天皇を神とし、また日本人は他の民族よりも優れた民族であって、世界を支配するよう運命づけられていると言った誤った考え方に、それは基づくものではない」。
この文章をヘンダーソンは、この頃彼がよく使っていた黄色い紙に書いた。ヘンダーソンがブライスにこのペーパーを手渡したのは、午後1時半頃だった。
早速ブライスはそれを勝之進のところへ持っていった。翌日ブライスは、その文章を含むさらに長い英文の草案を作って、ヘンダーソンに示した。ヘンダーソンはそれをダイク准将に見せ、ダイクはすぐにマッカーサーに見せに行った。ブライスの草稿を食い入るように見つめていたマッカーサーは、しばらくすると顔をほころばせた。
この時一つ不思議なことが起こった。それはブライスが、前日ヘンダーソンから貰った黄色い原稿を、自分の目の前で焼くように頼んだことである。
ともあれ、ヘンダーソンとしては、彼が作文した三つのセンテンスが、「オンリー」という一語だけを除いてそのままブライスの文章の中に生きているのを見て喜んだ。
このように事態が進んでいた頃、総理大臣であった幣原喜重郎は、天皇に呼ばれて皇居に赴いた。幣原は、既にヘンダーソンとブライスの草案を読んでいたため、天皇からどのような依頼があるのかおおよそ見当がついた。
英文の達人である幣原は12月中旬頃まで、ブライスとヘンダーソンの文章に、さらに推敲を加えたところの、後に「天皇の人間宣言」と呼ばれるに至った詔書の下書きを作成した。幣原はそれを日本語に訳すように、秘書の福島慎太郎に依頼した。
内容の重要性に鑑みて、福島は一週間かけて慎重に邦訳した。12月下旬、幣原は外務大臣の吉田茂に相談した上、12月23日、文部大臣の前田多聞に草稿を手渡して、「天皇のご意思としてこういうものを公表したいので、秘密裏に草稿を完成するように」指示した。前田は、内閣官房長官の次田大三郎と二人で、12月23日と24日の二日間かけて最終案を完成した。
12月24日夕方、幣原は皇居に赴いた。天皇はこの草稿に目を通した上で「民主化の考え方が現れている明治天皇の『五箇条のご誓文』を文中に含めるように」と要望した。
12月25日、幣原はこれまでの草稿に基づいて最終案の作成に取りかかったが、あいにく風邪をこじらせて翌日入院することになったため、止むを得ず前田文相に頼まざるを得なくなった。
12月27日、前田は天皇に拝謁した。天皇は、医師がお体に触らなかったため亡くなったという後水尾天皇の話をされた後、「草案には是非『五箇条のご誓文』を含めるように」との意向を洩らされた。さらに天皇自身が草稿に目を通して、所どころ声を出して読み上げられた。
「人間宣言」は英文の草稿から出発しただけに、日本語としてこなれているとは到底言い難かった。
前田と次田の二人は、何とか「五箇条のご誓文」を文中に入れるように努めたが、上手く行かなかった。二人は、詔書に関しては最終的に専門家が推敲してくれるものと思っていたが、これは期日からして無理だった。
12月28日夕方、前田文相は幣原首相を見舞いに行って、最終案を示した。幣原は、すでにマッカーサーが目を通しているヘンダーソンとブライスの草稿部分を変更しないように注意した。
翌29日、前田が天皇に再びお目にかかり、幣原首相からの「注意事項」に触れたところ、天皇もこれに同意した。つまり幣原としては、天皇の神格に関するヘンダーソンの数行を特に意識していたのであった。
12月30日の閣議を経て、GHQは「人間宣言」の英文の最終稿を正式に承認した。
こうして最終稿は12月31日正午、報道機関に渡され、元日の新聞に発表された。同時にマッカーサー元帥の次の声明も掲載された。
「天皇の新年の声明は、私の欣快とするところである。天皇はその詔書を声明したことにより、日本国民の民主化に指導的役割を果たさんとしている。天皇は、断固として今後の天皇の立場を自由主義的な線に置いている。このような天皇の行動は、如何にしても抗しえない健全な理念の影響を反映したものに他ならない。健全な理念と言うものは、到底止め得べきものではない」。
8.山梨勝之進、仙台「五城寮」の舎監に就任
昭和26年5月29日の『河北新報』は次の記事を掲載した。
「財団法人・仙台育英会では、東都に遊学する宮城県出身学生のための学生寮の建設を計画。宮城県、仙台市、その他の寄付により、東京都品川区大井林町の旧伊達藩邸跡を借り受け新築中であったが、このほど完成、26日、佐々木知事ら参列、盛んな落成式を挙行した。この学生寮は、仙台育英会五城寮と称し、木造二階建て、120坪、学生30名を収容、元学習院院長山梨勝之進氏が郷土学生のために訓育に当たる」。
ここで「仙台育英会」の歴史をみることにしよう。
戊辰政争によって仙台藩は一時自信を失ったが、郷土の再興を図るべく、仙台藩士の気概をいまだ持ち続けている富田鉄之助、木村信卿、佐和正、大槻如電、大槻文彦ら在京の有志数十名によって、明治10年頃「同求社」が結成された。この「同求社」の事業の一つとして、「仙台造士義会」が結成された。
この仙台造士義会の目的は、旧仙台藩の学生で家計が苦しい者に学費を貸与することにあった。
さらに明治30年7月、『仙台養賢義会』も設立された。創立委員は、在仙の岩崎総十郎、小倉長太郎、大町信、藤崎三郎助、峰八郎らであった。
その設立趣意書には、「鹿児島、佐賀、熊本、宇和島、米沢、庄内などの旧藩では、それぞれの藩の学生に対する援助制度があるが、本県にも早い時期に『仙台造士義会』が造られ実績を上げているが、金額や範囲などが他と比べて劣っている」として、「仙台養賢義会」の果す役割の大切さを謳っていた。
「仙台造士義会」や「仙台養賢義会」は、人材育成に大きな功績を残したものの、旧仙台藩出身者の東京への進学者の増加には到底追いつかず、このため学生を収容する寄宿舎建設に対する要望が高まった。
こうした中で大正2年、在京の旧藩出身者が協議して、「五城寮」が設立された。「五城寮設立報告書」には、創立の経過、現状、将来の抱負について、次のように記されていた。
「仙台旧藩出身者の学生で東京に遊学しているものが少なからずあるのに、一つの寄宿舎もないのは、大変残念なことである。在京の有志の間でも話題になり企画もなされたが、種々の障害に阻まれ実現されていない。そうした中で岡勇次郎が在京学生の父兄の意思を代表して有志に諮ったところ、菅原通敬、中川望、石川喜三郎、岡勇次郎、生江孝之の諸氏が明治45年2月をもって寄宿舎の設立が決定した。よって同年3月この趣意書を発表し、有志に賛同を求めたところ、幸い熱心な援助を得る事ができた。
同年5月建設場所を府下巣鴨町電車終点付近に決定し寄宿舎建設の工事を起こし、大正元年11月竣工した。
翌大正2年1月26日創立委員会を開き、旧仙台藩出身の在京学生の利便を図ることを目的に、寄宿舎を『五城寮』と名付けることにして寄付行為を決議した。
設立当時の寄宿舎は、東京府北豊島郡巣鴨町1106番地で、約300坪の土地に、木造瓦葺二階建て総坪数79坪の建物だった。
ところがこの『巣鴨五城寮』は、昭和20年4月14日米軍による東京空襲によって全焼した。しかし東京には宿舎に困っている学生が大勢おり、その対策が急務となった。
そこで当時の中川望会長、吉井桃磨呂理事長、保科善四郎理事などが中心となって協議した結果、品川区大井林町に焼け残っていた伊達家邸内の家屋を借り受け、昭和24年4月から10名の学生を収容して細々ながら運営をしていくことにした。
その後も都内にいる学生の窮状を目前にして、その対策が話し合われた結果、結局宮城県ゆかりの地として、伊達家の邸内で当時国が接収し東京都に移管していた公園用地(南品川公園の一部)を選び、その一部を借用することを理事会で決議して、東京都に出願した。
当初東京都は公園用地ということで許可しなかったが、保科理事の20数回にわたる粘り強い交渉の結果、昭和25年12月16日ようやく許可された。
建設資金は、巣鴨の土地を売却した資金60万円、宮城県の補助110万円、仙台市の補助25万円、有志からの支援金150万円を充当した。
その結果、昭和26年5月、木造瓦葺二階建て114坪、部屋数17室の寮舎が完成した。そして舎監に勝之進を迎え、5月1日寮生33名を収容して、戦後の『五城寮』が出発した」。
山梨勝之進は「五城寮」の舎監として新寮生に対して、その本分を次のように訓辞した。
「五城寮は旅館に非ず。市井下宿屋とは異なる貴き使命をもって新日本の黎明期に復興せる歴史的施設である。而してその母体たる仙台育英会は、寮生の生活を補助維持する為長時日にわたり相当の経済的負担を担い、これを累計する時は、各自に対しては決して少額ではない。・・・・・寮生の立場は前述の通りで、従って自由に選択せる民間に在泊するとは根本的に相違がある。この点を第一明白に認識正視するにあらざれば、精神的には既に在寮の資格を失うものである。
周知の如く入寮希望者は沢山あって、これを断るに苦しむほどである。品性、学力において、他の志願者より優位にありと認められたためである。果たして然らば、入寮後その日常において、その実証を示さんことを各人に期待するは当然である。
『夫生民を育し私ない。日々物を照す自ら公平』といわれた如く、『十年の視るところ十手の指す所、それ厳格なる乎』であって、もしその期待に反せば、かかる人は在寮を辞して、幾多熱心なるその他の優秀希望者に恩典を譲るべきは公平の処置である。・・・・・さりとて寮生活の一挙手一動窮屈なる規則制限を定めて、溌溂たる青年の元気を沈滞せしむる意義はなく、またその必要も存しないのである。故に上述の根本義を誤らざる範囲においては、十分自由と自治を享有し、雲愛口たる和気団欒の裡に相互敬愛し、共に手を携えて青春の心事を語り合う人生最大の至楽であって、品川湾頭景勝の地を占むる五城寮は、漸次進歩せしめらるべき造苑植樹の計画と相俟って、青春秋月終生寮生の忘れられない楽園となるであろう」。
漢和を織り込んだ格調の高い勝之進の話を、18、9歳の学生が正確に理解したとはいい難いが、寮生活を通して人格の陶冶を図らんとする勝之進の意気込みは十分に伝わった。
ところが昭和27年10月24日夕刻、「五城寮」の風呂場付近から出火して、寮舎の五分の一程度を残して焼失してしまった。火事の原因は漏電だった。
とりあえず山梨は、寮生を焼け残った寮舎と近くの寺や民家に一時分宿させた。急遽理事会が開かれ、寮の再建が話し合われた結果、幸い火災保険に加入していたことから、その保険金と民間有志からの援助などによって、直ちに再建に取り掛かり、突貫工事で木造モルタル瓦葺、二階建て寮室20室、浴室、水洗トイレなどを備えた40名収容の寮舎131.97坪、舎監居宅、倉庫を含めて、登記上147.05坪が、翌昭和28年2月28日出来上がり仮落成式が行われ、次いで4月、宮城音五郎宮城県知事も出席して、本落成式が挙行された。
学習院の教え子の一人である岡明氏は、「五城寮」の舎監をしていた当時の勝之進の日常生活を垣間見ている。
「先生のお宅に伺うと、『これ、やりかけているから、そこでしばらく待ってください』と一間に通された。やっと出来たばかりの舎監の家は二間。襖を明けた向こうの部屋で、奥様と寮の家計簿をつけておられる。
『大根が10円』『ハイ』
『大根が1本、10円』『ハイ』
『1本が10円ですね』『ハイ
『あとは何でした』『小松菜、25円です』
『何束?』『2束でございます』
『小松菜、2束で25円ですね』『ハイ』
先生がくどい程に確かめる大きな声に、奥様が小さく言葉少なに答えられる。しばらくそれが続いた。
先生の決めつけるようなくどさが、何かしら気になった。はじめはその頃よく話題になった、値上がりに驚いておられるのかと思った。しかし一言もそんな無駄なことを言われない。ちゃんと確かめて記入すべきところを記入しておられる風だ。
一時が万事で、先生はいつもこんな風に事を運んでこられたのだろう。少尉の時も、大将の時も、院長の時も。
やがて記入が片付いて、『セ・ラ・ヴィ。セ・ラ・ヴィ』とつぶやきながら出てこられて、『こういうのを、フランスでは“セ・ラ・ヴィ(これが人生さ)”と言うんだよ』と言われた」。
この『セ・ラ・ヴィ』は、“There is a tide in the affair of men”(人生には潮時と言うものがある)という言葉と共に、勝之進の人生観を示すものであった。
昭和26年6月16日の『河北新報』は、5月15日夕刻に、時の首相の吉田茂が「五城寮」を訪問して、仙台出身の寮生たちを、次のように激励したと報じた。
「再建に青年は百倍の努力を 吉田首相の話
山梨元大将と私は約30年前、山梨さんが海軍次官、私が外務次官時代同僚としてお付き合いした。当時海軍軍縮問題のやかましい時であったが、山梨さんは大変ご苦労されながらも衝に当たって善処されているのを見て、非常に敬意を払っていた。また近くは学習院長として皇太子殿下のご教育に当たられ、今日皇太子がかくもご立派になられたのは、ひとえに山梨元大将のご影響があずかって力があると思う。
先日はからずも山梨さんがこの寮の舎監になられたということを聞き、一度見に来ないかというので喜んで今日見せていただいたわけである。
敗戦後の日本の再建は一にかかって青年の双肩にある。青年が興国の精神に満ち満ちていなければ、再建はおぼつかない。日本を昔の日本にするには、戦前の青年の百倍、二百倍の努力が必要で、そのためには非常な決心が必要である。その第一は教育である。その点山梨さんの現在のお仕事は実に尊いと思う。・・・どうか諸君も常にこの気持ちで日常座臥に処して行くようにしていただきたい」。
山梨勝之進は「五城寮」の舎監を、昭和26年5月から昭和33年7月まで務めた。山梨勝之進、満74歳から81歳までの6年間であった。その間、昭和29年秋と昭和33年1月の2回にわたって元慶應義塾大学塾長の小泉信三が講演に訪れ、さらに昭和32年秋には、皇太子殿下の英語の家庭教師のヴァイニング夫人も来寮した。
法政大学教授で「五城寮」OBの一人である袖井林二郎は、昭和58年8月27日付『読売新聞』「百年の日本人」に次の論文を掲載している。
「公職追放により院長を退任したとき、学習院はその功績に名誉院長の称号を持って報いている。片瀬に引退して再び薔薇作りを始めたが、もともと植木を作るよりは人を作るのが好きな山梨さんである。旧仙台藩出身学生の寮として仙台育英会五城寮が再建された時、舎監就任を同郷の後輩である保科善四郎氏(元海軍中将)が頼み込むと、即座に快諾。品川沖を臨む旧仙台屋敷に建つ粗末な建物の一画に、夫人と共に住み込んで、40人ほどの学生との共同生活が始まったのが、昭和でいえば26年の春である。その前年に大学へ入った私は、最初の寮生の一人となった。
山梨さんが舎監として五城寮に注いだ情熱と努力は、並大抵のものではない。食糧難の時代に若者40人を養う苦労だけでも大変なのに(私はその恩義を一生忘れまいと思う)、あの混乱の時代に、理想の教育を貫こうとしたのである。だが教育というものが大抵そうであるように、生徒が教師の抱負を理解できるのは、はるか時間がたっての後である。
私は『遺芳録』で、初めて山梨舎監が預かっていた五城寮のあり方を知った。それは戦前にあった旧五城寮の三則にいう『求道の道場』であり、『仙台魂を練磨』し『尽忠報国の士』となることに始まる。戦前と戦後は、山梨舎監の中では見事に連続していた。さらに『相互親和と自治自由』をキリスト教施設から、『規律と清潔、真剣味』は陸海軍学校を模範とし、『団体精神、礼儀と気品』はオックスフォード、ケンブリッジの学寮に学び、『静寂と捨身の忍苦』は雲水禅堂の生活に従う。これが五城寮のあるべき姿だというのである。だから大酒を食らっては朝まで議論に耽り、万年床に寝て昼と夜を取り違えるような生活をしていた私(そして大半の寮生)は、それだけでも山梨学校の落第生だった。
禅問答と東西の古典の引用に満ちた講話もほとんど覚えていない。相手を誤ると教育とはかくも失敗するものかという見本であろう。愛国と愛郷の精神で英才教育に努める山梨舎監は、若い私には格好の反面教師だったのである。だが自分自身が今教育者になってみると、故郷を越え日本を越える学生を育てる難しさを痛感させられる。自由な社会でいかに規律を身につけさせるかということも、山梨さんは宿題として私に残したのであった」。
このように伝統ある「五城寮」であったが、40年経ち、敷地の所有者である東京都から、都市計画の障害になるとの理由で立ち退きを要求され、これに経営の悪化や舎監の後継者難などの諸事情が加わって、ついに昭和58年12月、正式に廃止することになった。昭和59年3月7日、多くの来賓や寮OBが出席する中で、「五城寮」の閉寮式が開催され、品川「五城寮」30年余の歴史を閉じた。
現在寮の跡地は大井公園の一部として整備され、周辺住民の憩いの場になっている。
9.最晩年の山梨勝之進
昭和26年9月、サンフランシスコ講和条約が調印された。その翌年の昭和27年旧海軍士官の親睦団体の「水交社」を受け継ぐ形で新たに「水交会」が設立され、9月14日山梨勝之進はここの初代会長に就任した。
昭和39年7月、学習院大学は山梨勝之進に「学習院名誉院長」の称号を贈った。
後に海幕長を勤められた中村悌次氏は、昭和32年1月幹部学校に入校した。その時の勝之進の講義の模様について、その著『生涯海軍士官—戦後日本と海上自衛隊』の中で、感動を込めて回想している。
「山梨先生の私どもへの話は、市来君が中心となってまとめた『歴史と名称』には載っていません。なぜ載っていないかというと、速記にとって残したものが四期以降の分だからです。先日、クラスの中だけで配った、学生の速記を取り出してみて、感銘を新たにしました。話の内容そのものもそうですが、何に一番感銘を受けたかと言うと、話から溢れる山梨さんの人柄、人格です。話を聞きながら、人間も磨けばここまでなれるものかといった、仰ぎ見るような感じを受けました。
ちょうど『明治天皇と日露大戦争』と言う映画が公開になったばかりで、山梨さんは『自分は観る気はしなかったけれど、人から勧められて観ていたら、出てくるのは嘘が多いんだけれども、涙が出て止まらなかった』と言う話から始められましてね。で、明治天皇、昭憲皇太后、東郷(平八郎)さん、伊藤博文、小村寿太郎、山本権兵衛、こういう方々についての—ご自分も皆知っておられますからね。『こういう人柄だった』と言う話から、乃木大将の話になって、日露戦争の話、旅順の二〇三高地の—この時山梨先生は、二〇三高地を突撃しているのを裏側から見ておられるわけです。そのお話1月2日に旅順に行って、日本兵の死体はさすがに片付けてあったけれども、まだロシア兵の死体がゴロゴロしているところを見ておられるんです。
日露戦争の話から、ナポレオンの話になる。ナポレオンがマルセーヌを攻略した時に、二〇三高地と同じように、マルセーユの港を管制する高地に目を付けて、そこに大砲を据え付けて、港に入っていたイギリスの軍艦を退去させたのが、名を揚げる一番最初だったと言う話から、次にウェリントンとナポレオンの半島戦争の話をされて、それから、ウェリントンの人柄の話。
そういった話の流れです。幹部学校の午後の教務は通常午後1時から始まって4時までの3時間です。ところが、山梨先生のお話は5時になっても終わらない。6時になっても終わらなくて、終わったのは6時半でした。
その間、校長が『どうぞ先生、お座りになって下さい』とおっしゃって、途中二回ぐらい休憩されましたが、立ったまま机の上に原書を置かれて、時々それを開きながら話をされました。ご自分が体験して、ご自分が知っている話が多いだけに、話に迫力があります。
それに加えて、先生がずっと勉強をし、あれだけ人生を経てきた、磨かれたと言うのは、学生にもそのまま通じるのです。今と同じで当時の学生もよく寝たわけですが、山梨先生の話の間は一人も寝るものがいませんでした。(中略)
山梨先生でもう一つ覚えているのは、卒業式で祝辞を述べられた時のことです。『君たちは、創設で非常に苦労しているけれども、苦労しているのは君たちだけではないんだ。君らは、隆々とした日本海軍しか知らんだろうけれども、明治海軍を作り上げる時には、君らの今の苦労以上のことがあったのだ。先人は皆苦労してあれだけのものを作ってきたんだ。君らは負けずにしっかりしたいいものを作れ。頼みにするものは人だけだ。君たちだけなんだ』と言った要旨でしたが、その迫力がね。先生は、身体は小さいのですが、その身体が本当に講堂一杯に広がったような感じがしました。あの温厚な先生のどこからあんな迫力が出るのか。先生は83、4歳ではなかったでしょうか。ちょうど私と同じぐらいの年だったと思います。89歳ぐらいまで幹部学校でお話をされていました」。
この中村元海幕長の回想にあるように、勝之進は、最晩年の82歳から89歳に至る最晩年、海上自衛隊幹部学校での講義に情熱を傾けた。
その講義禄は、昭和43年『山梨大将講和集』として纏められ、昭和56年10月、毎日新聞社から『歴史と名将—戦史に見るリーダーシップの条件』と題されて出版された。この講話集は、大版610枚、四百字詰め原稿用紙1200枚の大著である。
一回ごとの講話の準備に三カ月を費やし、その間資料の整理や原稿の作成に没頭した。資料不足や疑問点については関係外国公館に照会し、原書を読破した。その原稿は大学ノート40冊に上った。
山梨勝之進の精神的支柱はいわゆる「和魂洋才」、いや「禅魂洋才」といったものだった。勝之進の蔵書は、海上自衛隊幹部学校の図書館に「山梨文庫」として納められているが、洋書以外では漢籍の本が大部分であったことからもわかる。
勝之進が精神的中核に置いていたのは、「四書五経」にあったが、兵学や用兵に関しても、道徳をその根底に置いていた。
山梨勝之進はその『遺芳録』の中で、次のように述べていた。
「諸橋轍次先生が書いた『経史論考』というものによく出ている曾国藩((1811〜1872)、太平天国の乱にあって、農民義勇軍を募り、かつ水師『海軍』を編成して、太平軍鎮定にあたる。1868年直隷総督。西洋文化を移入して、同治中興の中心となって活躍)は、用兵、戦略、戦術というものがあって、一方に道徳というものがあるなら、修身、道徳、修養というものと一体であり、その延長にあるものが兵学だというのが、曾国藩の見識である。・・・そこでこれは自分の説であって、皆さんの批評を待つのであるが、例えばここで山登りの旅行をする。その時に教える人があって、あの山登りには、こういう危険なことがある。こういう楽なところもあり、こういう道があり、こういうやり方がある。天候が変わってくる時はこうせよというように、いろいろ詳細の用兵を教えたのが兵学なら、それが孫子、呉氏、太公望の兵書なのである。
ところが曾国藩は、ちょっとそれより一段上を行っている。山を登って、川を渡って行く。そういう知識はもちろん必要だが、本体、ご本人の精神状態の方が、それよりさらに必要である。それを修練、鍛錬、修養して鍛えておく方がさらに重要で、その方が上手だ。そこへ来ている。そこで克己ということが、用兵の根本だということを曾国藩が説いている。
こうやればよい。こういうことは気をつけろ。それはよい。しかしそれをやる本体は人間である。その人間そのものを固める心がけを練らなければ、やり方ばかり、こういう方法がある。こういうことを気につける、と言ったって駄目だと思う。この克己という犠牲的精神がなければ、本当は戦は駄目だというようなところを、曾国藩は押さえている。
また得意になって、俺は勝ったんだと、図に乗って怠りが出るのは一番悪い。これは幾重にもこの曾国藩の用兵の秘訣として戒めているわけです。・・・『用兵は道徳を基礎とする』という兵学。兵学というものと道徳というものとを一体化していることは、これは世界の兵学家で、いまだかつてない言葉と私は思う。・・・これは、われわれは今度の第二次世界大戦についても考え、顧みなければならないところではないかと思う」。
「手術は成功した。しかし患者は死んだ」との例えのように、「戦闘には勝った。しかし戦争には負けた」のでは、話にならない。われわれは、今次大戦における日本軍のあり方を見る時、戦略の基本の根本的過ちがいかに多かったかを知っている。
昭和41年(1866年)11月3日、山梨勝之進は宮中杖の御下賜に預かった。そして昭和42年12月17日、山梨勝之進は享年90歳をもってこの世を去った。
山梨勝之進海軍大将は、枯葉散る東京の青山墓地(第二二号一種イ八側六番)に静かに眠っている。