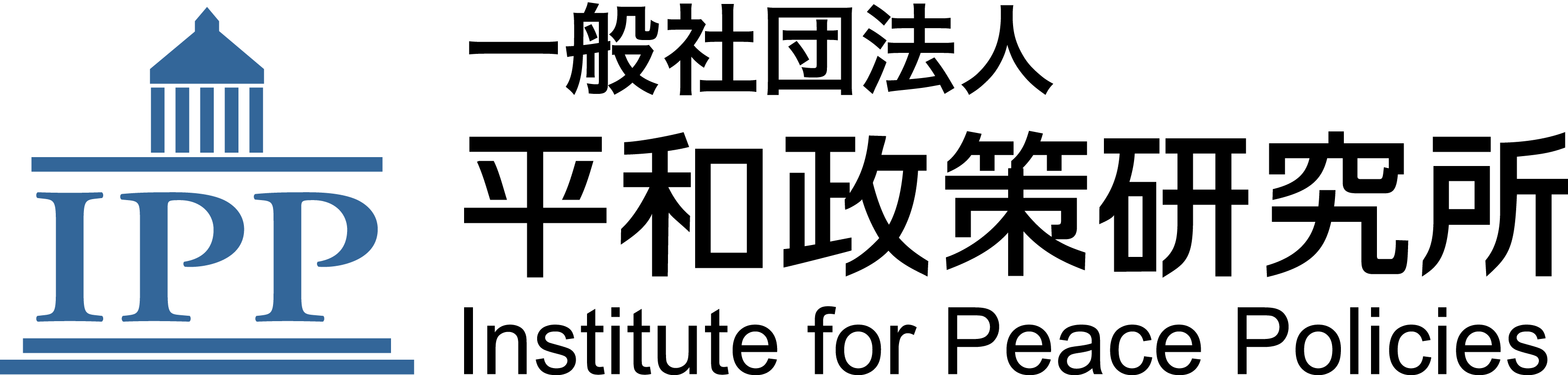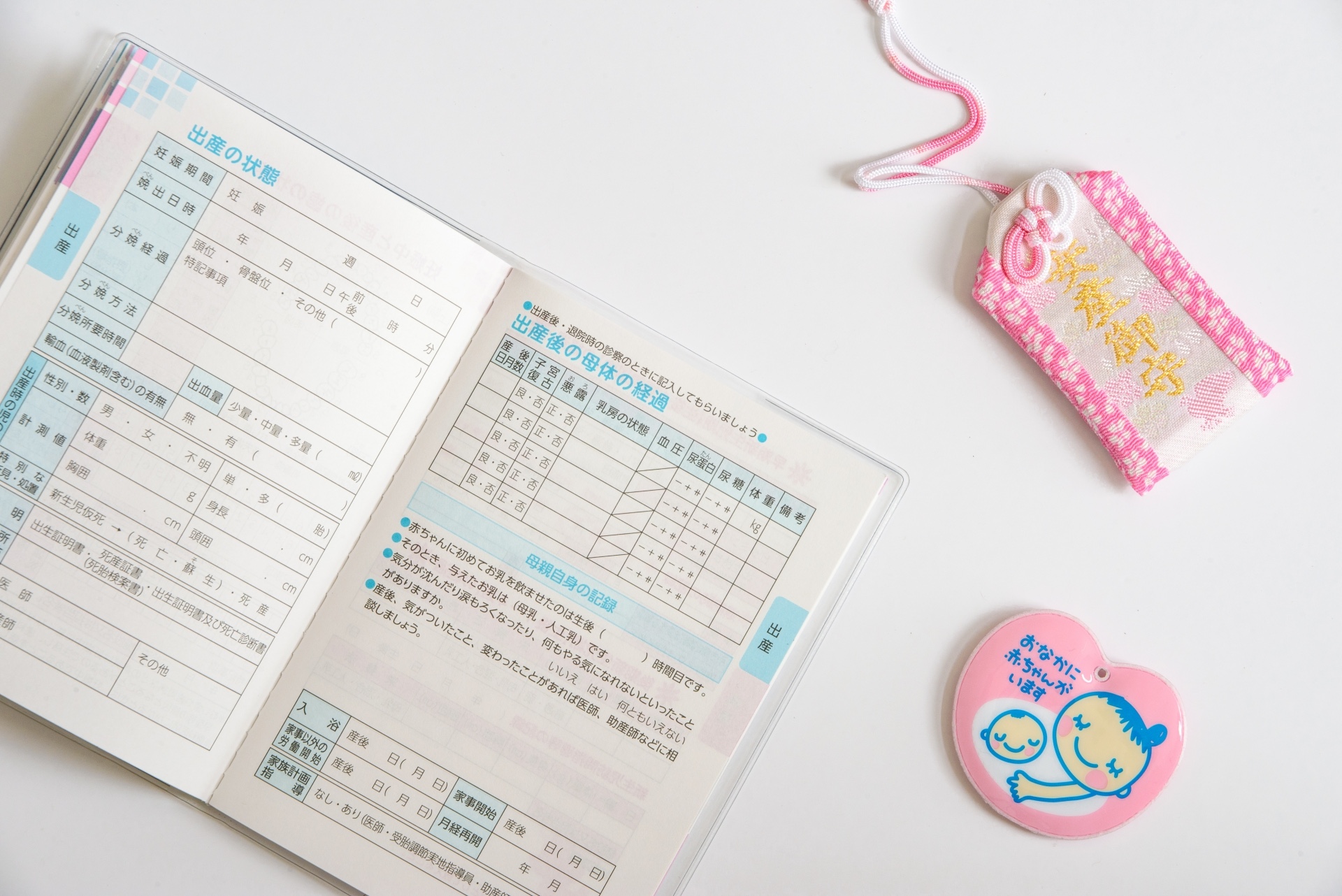1歳半までの「甘え」の重要性
私は、2年前にアラン・ショアという神経精神分析家が書いた『右脳精神療法』という本を翻訳した。なぜこの本を訳そうと思ったかというと、ショアは人間の脳と心の発達にとって誕生から1歳半までの時期が決定的に重要だと述べているからだ。赤ちゃんはお母さんとの関係において、情動的・感情的つながりから影響を受けて育つということを、脳科学の最新の知見をもとにはっきりと言っている。ここでいう情動は、実際の場面においては、その多くが私たち日本人であれば「甘え」にまつわる感情を指す。それで、私の言いたいことと非常に重なっており、ぜひとも訳したいと思った。
また、ショアは‘dependency’、つまり「依存」ということが極めて重要だと書いている。「依存」は生きていくための一番の土台であり、人間は「依存」が満たされなければ真っ当に生きていけないということである。ショアはアメリカ人であるが、アメリカでは‘independency’、つまり独立・自立が重視されており、‘dependency’はとてもネガティブなものとして扱われてきた。だから赤ちゃんを親と離して一人で寝かせることを良しとする。そのような中で、ようやく「依存」の大切さに注目する人が現れた。「依存」を「甘え」に置き換えれば、彼の言うことはとてもよくわかる。
一方で、私からみると、ショアの言っていることの半分はわかりづらい。なぜなら、ショアは「甘え」を知らないからである。「甘え」を知らないがゆえに、1歳半までの赤ちゃんとお母さんの関係を情緒的なものとしては実感を持って掴みかねている。「甘え」がわかって初めて、お母さんと赤ちゃんの関係が見えてくるが、行動ばかり見ているのである。
行動ばかりに注目し、「甘え」や情動に注目しないのは、日本におけるアタッチメント研究者も同じである。アタッチメント※は、親子の情動の流れを理解するためというよりは、行動観察のための概念である。アタッチメント研究では、新奇場面法(ストレンジ・シチュエーション法、P.3の写真も参照)という手法を用いて、赤ちゃんがお母さんにどのようにくっつくかという観点から、子どものアタッチメント行動を観察し評価する。
しかし、お母さんが赤ちゃんを育てる時に、行動だけに注目することなどありえない。「ああ、わたしにくっついたわ」などとは思わず、「甘えたいのね、よしよし」となるのが自然である。同様に、赤ちゃんの笑顔を見たお母さんは「表情筋が緩んだわ」などとは思わない。「うれしいのね、よしよし」となるはずである。その感覚が、親として子どもを育てる一番の動機づけになるのではないか。だが、アタッチメント研究では、科学的には「甘え」ではなく「アタッチメント」でなければならないと強調される。
甘えたいけど甘えられない気持ち
今から30年前から14年間、私は東海大学に勤めていた時、母子ユニット(P.3の写真を参照)をつくり、関係性に難しさを抱える0歳から5歳くらいまでのたくさんの子どもとお母さんを克明に観察してきた。全てのケースにおいて初回の面接時に新奇場面法を実施し、赤ちゃんとお母さんのアタッチメント関係の特徴を見出そうとした。
このときの親子の映像は全例丁寧に記録し、関係の視点から徹底的に観察した。新奇場面法を行う部屋には三台のビデオカメラをセットし、隣の観察室から親子の様子を捉えるのに最適なアングルのカメラに切り替えながらズーム機能を駆使して録画記録した。それにより、母子双方の細やかな動きや表情を捉えることができた。この時記録した映像が、その後の研究にとって大変な財産となっている。
難しい関係にある親子では、赤ちゃんはお母さんに甘えたいはずなのに、色々な事情があって甘えられない。人間というものは、甘えられないと欲求不満がたまって癇癪を起こしたくなる。当然そういう赤ちゃんもいるが、いつも癇癪を起こしてお母さんに嫌われたら生きていけない。だから、何とかお母さんにかわいがってもらって、捨てられずに生きていくために、どのようにふるまったらよいか、1歳過ぎると赤ちゃんは学ぶようになる。つまり、「甘え」を抑え我慢して生きていくことになる。
甘えたいけど甘えられない状況にある赤ちゃんは、生きるために知恵を働かせ、自分を守るための対処行動をとる。その方法は十人十色である。たとえば、甘えたいけど甘えられない、つらい思いを何とか無いものにしようとして、子どもによっては解離を起こす。あるいは、他のものに関心をそらして気を紛らわそうとする。お母さんに認めてもらうために徹底して良い子になる場合もある。
そのように、赤ちゃんは生後三年間で、どうやってお母さんとやり過ごすか、何らかの対処法を身につけることになる。こうして赤ちゃんの時に身につけた人との関係の取り方は、多くの場合、一生続くことになる。
私が記録してきた親子の映像を見ると、日本人は皆、明らかに甘えたいけど甘えられない子どもの気持ちを感じる。そして、不憫だな、可哀想だなと感じるのである。
それにもかかわらず、「甘え」を「アタッチメント」と言い換えてしまう。アタッチメントは学術用語、「甘え」は日常語だとして、科学に馴染まないと考えられているのだろう。アメリカ人は「依存」に対してネガティブなイメージを持っていると述べたが、日本人も「甘え」に対してネガティブになってきているように思われる。
「関係をみる」ことと「感性」
人間が一人で育つということはあり得ない。お母さんとの関係の中で育つ。そういう視点をアラン・ショアも力説するが、ある意味当たり前のことである。関係の中で育つからには、お母さんと子どもの間に何が起こっているのか、そこを見なければならない。
子ども個人を見て発達を語ろうとするのは個体能力発達観という見方である。「1歳になって言葉が出てきたね」とか、1歳半になったら「一語文しかなかったのが、二語文が出てきたね」というように、どういう能力が何歳頃に育つかという視点である。
一方、関係を見るとはどういうことか。お母さんが何をしているか、子どもが何をしているかというように、行動を見ることではない。関係を見るとは、お母さんと子どもの間に立ち上がる情動ないし感情の流れをみることである。感情の流れは目で見えないため、感じ取らなければならない。感じるためには、ある断面を切り取るのではなく、一瞬たりとも同じではない二人の関係を、ずっと一緒になって追いかける必要がある。冷めた態度で見ているのではなく、当事者になって自分もその関係の中に身を投じてこそ、初めて何が起こっているのかをつかめる。
1歳半までの子どもとお母さんの世界は、言葉が生まれる前の世界である。だから、全てが曖昧で漠然としている。未分化で、言葉で切り分けることができない。そういうお母さんと赤ちゃんの世界のことを論じようと思えば、オープンな気持ちで、感じたことに対して正直である必要がある。そうしないと、そこでどのような感情が起こっているか掴めない。
だから、子どもの能力ばかりを見て発達を論じてきた人は、関係を見て発達を論じることができない。子どもの能力だけを見ていれば、検査で能力を調べて同年齢の標準と比べることができる。だが、関係をみるためには、「感性」の働きが問われる。それゆえに、関係を見ることはものすごく難しい。
「感性教育」の取り組み
以上のような理由から、今、私は「感性教育」というものに取り組んでいる。感性教育では、新奇場面法で観察した親子のやりとりを録画した映像を、当事者の許可を得たうえで臨床家や学生に見せ、感じたことを言葉にしてもらう。
そこで目指していることは、親子間でどのような感情が流れているか、感じ取ることである。それが可能になるためには、今まで学んできた色々な専門知識をいったん脇に置くことである。映像で見たこのお母さんと子どもの間に一体何が起こっているのか、感じたまま自由に語り合うことを大切にしている。
だから、私は参加者がなんでも自由に語り合える場を作ることに心を砕いている。それがものすごく難しい。自分の内面には他人に触れられたくないものを誰しも持っている。そんな時、多くの人が抽象的な言葉や専門用語を使ってごまかしたりすることは少なくない。そういう気持ちに対して、専門用語なんかを使うのをやめて、感じたことを正直に言ってみてくださいと促す。赤ちゃんを相手にしていて専門用語を使うことなどない。そうではなくて、「あぷぷ〜」というような言葉にならない声を出して赤ちゃんをあやしたりする、そんな状態に近い気持になることが必要である。
臨床家をはじめ、人間が自分の心に正直になることは難しい。なぜなら、多かれ少なかれ、自分自身が赤ちゃん時代につらい思いを経験しているからである。甘えたくても甘えられない赤ちゃんの様子を見ていると、臨床家の心の中にある、幼い時のつらい感情が刺激される。そうすると、大変な混乱が起こり、赤ちゃんと同じように、甘えられなかったつらい気持ちをどう処理してよいかわからなくなる。特に、トラウマの臨床をやりたいという人の中には、とてつもなくつらい経験をしている人も少なくないのではないか。そういう領域に関心を持つ、それなりの動機があるものである。そのような気持ちに向き合うことはとてもではないが怖くて、蓋をしてしまう。それは、目の前にいる子どもが、トラウマの体験がつらくてたまらず、なかったことにして解離を起こしているのと同じようなものである。
そのように、子どもの臨床に一生を捧げている人の中には、フラッシュバックが起こることがある。感性教育の場でも、映像を見ているうちに涙が出てきて、苦しくなって何も語れなくなる人が少なくない。どうやって、そういう人たちを、相談に来た親子のつらい気持ちを受けとめられるようにしていくか。それが目標である。感性教育を通して臨床家は治療されているともいえるのではないか。
大人の「育ち直し」
感性教育は、育ち直しの場にもなっていく。私は、子どもが不登校や引きこもりになって、ずっと悩んできたお母さんたちにもたくさん会ってきた。そういう人たちにも新奇場面法の映像を見てもらうことがある。そうすると、そこに自分を発見して、大変な衝撃を受ける。子どもに悪いことをしたという思いに襲われ、自分をものすごく責める気持ちが強まる。
しかし、自分を責めている状態から、だんだん自分自身もそういう育ちを受けたという記憶もよみがえってくる。自分も同じようなつらい思いをして育ってきたということが、そこには共通していることに気づく。そうすると、自分が悪かったということではなく、自分が経験したつらい思いが子育ての中に表れたということで、なんとも言えない気持ちになる。
不思議なことに、自分の親が悪かったということにもならない。今までずっと悪者探しをしてきたけれども、それはどうしようもなかった、お母さん(祖母)が悪いからこうなったわけではないということに気づくのである。
学生向けに感性教育を行ったとき、ある学生が「悪者探しをしてもどうにもならないことだと気づきました」、「色々な事情があって、こうならざるを得なかったんだということにいきつきました」と、とても感動的なことを述べた。その学生は、小学校以来、ずっと不登校だった。どうにもならないものとして自分の過去を受けとめていくと、それでもよく頑張って生きてきた、と自分を褒められるようになる。でもそこまで到達するまでは死ぬほど辛かったとも述べている。
このように親の過去の受け止め方が変わると、子どもとの関係も変わってくる。子どもが遠慮がちにお母さんに甘えてきたりするようになる。それは親にとっても感動的な出来事である。
人間が生きていくということは、そのように世代を超えた親子間の辛い思いが連綿と繋がっているものである。関係を通して成長したり、苦しんだりする。それが人生というものだろう。
若者の感性教育
先に述べたように、学生に対して感性教育を行うと、とても素直に自分の体験したことを言葉にしてくれる。赤ちゃんとお母さんの感情のやり取りを自分のことに置き換えて、自分を理解していく過程を身近な言葉で語ってくれる。そうした学生の体験談を紹介すると、聞いた人は、皆心を揺さぶられたと異口同音に語る。私も揺さぶられた一人だ。私は、学生が体験したことを素直に言葉にしてくれたことにものすごく感謝しているし、学生がそういう風になってくれたことに誇りを感じている。
全ての人が、学生時代など若いうちに感性教育を受けられれば良いが、そこまでいかずとも、赤ちゃんを育てるとはどういうことかを経験しておくことが大切である。特に男性は、女性が担ってきた子育てが、いかに大変な営みかということを知らなければならない。
一番良い方法は、赤ちゃんとお母さんが自由に集まる場に、1週間くらいどっぷりつかり、赤ちゃんと触れ合うことではないかと思う。今は行政が実施している、こどもプラザといったような名称の子育て支援の場が全国にあるので、活用できたらうれしい。でも触れあうだけではダメである。赤ちゃんと触れ合った若者の体験を丁寧に聞いてあげながら、感性教育の観点から意味づけすることが欠かせない。どのような感情体験をしたか、丁寧に聞いてあげる人が必要である。そうすれば若者たちの人間への見方ががらっと変わっていくのではないか。
生きるための大人顔負けの振る舞い
赤ちゃんはいろんなことを教えてくれる。人間理解の原点である。感性教育の場で新奇場面法の映像を見せると、100人中100人が驚く。「赤ちゃんって、こんなに色々なことが分かったうえで、こんなに色々な行動をするんですね」という。
私が観察した母子の中に、衝撃的な振る舞いを見せた子どもがいた。新奇場面法の場でお母さんが退室した後(図の③から④に移るとき)、ストレンジャー(スタッフ)が優しく相手をしていた。すると、子どもがだんだんその気になり自分の気持ち、つまり「甘え」を出すようになってきた。そしてスタッフにしがみつこうとしたとき、お母さんがドアを開けて戻ってきた。その時、子どもはお母さんを見て、これはまずいと思ったのだろう。その手をすぐに引っ込めて、お母さんの方を向いてニコニコしながら、近づいていきお母さんの手を握った。子どもはお母さんの機嫌を取りに行ったのである。お母さんからすれば、自分が部屋に戻ってきたのでうれしくて、自分を求めて近づいたと思ったのだろう。全体の流れを見ていた私からすれば、他の人に甘えているところを見られたから大変だと感じて、すぐ引っ込めて取り繕った。2歳の子どもが「媚を売った」ということである。我々大人がやるならよくわかる。しかし、2歳の子どもがお母さんと生きていくためにこのように振る舞っている。衝撃的であるとともに子どもの生きるための知恵に感動させられる。
このような映像を見た臨床家の中には、子どもがお母さんと何とかやっていくために、大人と同じように様々な知恵を働かせて対処しようとしていることを感じ取ることが難しい人は少なくない。「お母さんが戻ってきたからうれしかったんだね」と単純に判断してしまう。新奇場面法の前半では、お母さんが相手をしようとしても子どもは逃げ回っていた。その様子と全然違うのに、お母さんが戻ってきた時の反応をみて「お母さんがいないとつらいんだな」「やっぱりお母さんに会えてうれしいんだな」と思ってしまう。2歳の子どもが媚びを売るなど、もしかすると、世界中の人が知らないのではないか。
1歳半までの間にお母さんと子どもの間で起こることは、子どもの一生を決める。甘えられない子どもは、人間の精神発達上、とんでもないことを赤ちゃんの時に経験することになる。いろんな心の病気があるが、この時期のつらい経験はすべての病気に通じている。
心の土台——赤ちゃんから学ぶ
ただ、甘えられなかったことによる心の傷は回復できないものではない。アラン・ショアは、1歳半までは右脳が活発に働き成熟するため、その期間に治療することが大切だと言っている。しかし、脳というものは、一生のうちに右脳が成熟する時期と左脳が成熟する時期があり、両者の臨界期は異なり、螺旋を描くように何度かの周期を繰り返す。つまり、右脳は、一旦成熟した後、その後の成長過程で変化を余儀なくされるため、もう一度作り直されていく。それが一生繰り返される。だから何歳になっても治療はできる。そういう意味では非常に前向きで、楽観的な考え方である。
左脳は言語を司るため、理屈ばかり考える。右脳は感情である。だから、まず右脳が十分に機能することが大切である。それから左脳が働くようになると、しっかりした土台をもとに理性が働き、非常にバランスのとれた人間になる。
今までの学問や、小中高・大学の教育では、正解を導き出すような勉強ばかりをしてきた。何が正解か、正解がどこかにあって、それを学ぶことが学問だと思われてきた。これは根本的に間違っている。正解とか誤りではなく、自分の中で感じたことは自分にとってまぎれもなく確かなことである。それを大切にしながら積み上げていくと、しっかりした自分ができあがっていく。自分の中にあるものを大切にしないで、どこか自分の外に正解があるのではないかと探し回っている限りは自分は育たない。
これまで理性を重視する教育ばかりが行われ、理性的であることが大人になることであるという価値観が根付いてきた。論理的であることを重視するアメリカの学問が優れているという思いからか、「甘え」や情動は重視されず、もっぱらアタッチメント行動ばかりが注目される。臨床家も専門家としてのプライドから、なかなか心を裸にすることが難しい。
日本人は「甘え」という、人間の心の一番大事なところを文化的に、経験的に理解しているはずである。人間にとって、「甘え」の充足がいかに心の土台になっているか、赤ちゃんに学ぶ必要がある。今そんな時代が到来したと私は考えている。
(初出は『EN-ICHI FORUM』2025年2月号)
※【解説】アタッチメントattachment
ボウルビィBowlbyが用いた原義は、危機的な状況に際して、あるいは潜在的な危機に備えて、特定の対象との近接を求め、またこれを維持しようとする個体(人間やその他の動物)の傾性で、負の情動状態を、他の個体とくっつく、あるいは絶えずくっついていることによって低減、調節しようとする行動制御システムである。しかし、わが国で「愛着」という訳語が定着するにつれ、人と人との情緒的絆が強調されるようになり、緊密な愛情関係の特質一般を指し示すという誤解が生まれやすいことから、最近ではボウルビィの原義に立ち返る意味から、アタッチメントと訳されることが多い。「アタッチメント」における勘所は、不安や恐怖という負の(不快な)情動が重要な他者に接近することによって中和化されるか、正の(快の)情動へと変化していくことにある。