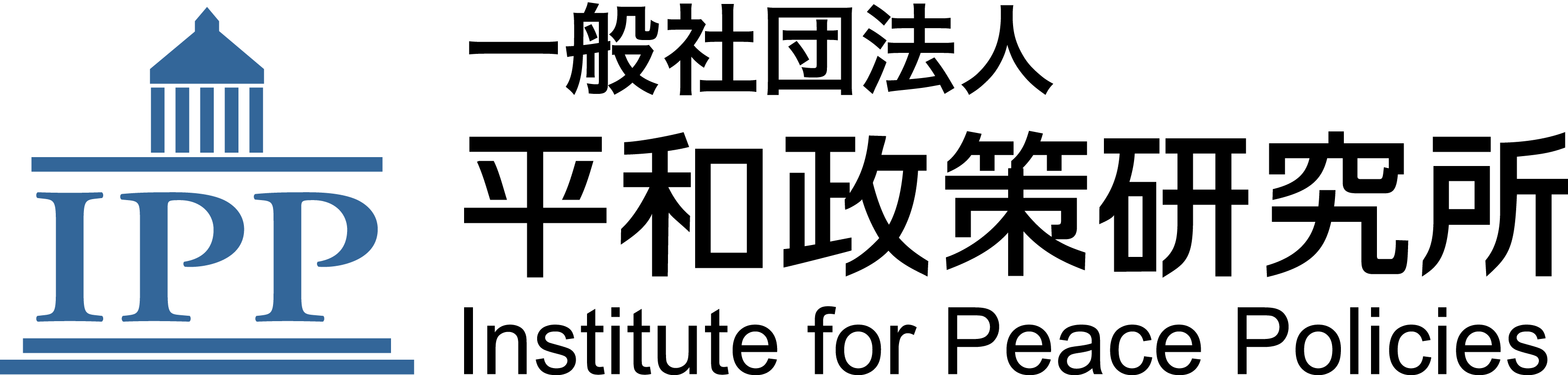はじめに
本稿では、昭和100年の期間にわたる「移民国家」日本の軌跡を振り返り、現在の問題状況を確認し、将来に向けての課題を提示する。ここでの中心論題は、社会としての意思決定および遂行の公式の制度である「国家」が、立法、行政、司法の公権力行使においてどのように「移民」を扱ってきたかである。なお、本稿では、「移民」を厳密に定義することはせず、国境を越えてある期間以上の移住を行う/行った外国起源の人、というような曖昧な言葉遣いをする。
昭和元年からの100年は、政治体制と経済状況のそれぞれの面で、大きく2分される。政治面では、1945年までは天皇の主権の下での制限された議会政治であったのに対し、戦後は、米国による占領を経て主権在民の原則に基づく議院内閣制である。ただし、官庁主導という国家の基本性格は変わらず、帝国官僚はそのまま居残り、統制と取締りにより秩序を維持することを旨とする官庁の思考および行動様式は変わらなかった。
本稿の主題との関連で重要なのは、政策の策定および実施において外国人の人権が尊重されることはなく、それについての関連国際機関からの勧告を意に介さないことである。それは、外国人管理を所管する入管行政においてとりわけ顕著である。さらに、司法判断においても、行政府の権限と裁量を重視することが多く、外国人の人権への配慮は乏しい。しかし、以下で示すように、司法が判示あるいは示唆を行ったことで、立法ないし行政において外国人の尊厳や人権を回復するための措置が取られたこともある。
長期の経済の視点では、1950年代半ばからの高成長を経た1970年代初めを境として、労働需給の基調が過剰から不足へと転換する。ただし、これとは別に、戦争への動員と戦後の復員・引揚という政治要因もまた労働需給に大きな影響を及ぼした。
1 移民送り出し国家としての日本
労働過剰基調であった時期の日本の移民政策は、海外への移民の送り出しにかかわるものであった。これにつき、戦前・戦中期には後述の満州開拓移民を別として国家は主たる役割を担うことはなく、募集、移送、到着後支援は民間の移民会社に委ねられた。その結果は、移民会社の誇大宣伝による移民者募集と現地での「棄民」であった。また、第2次大戦中は、受入国にとって日本は敵国となり、日系人は収容などの抑圧を受けることとなった。そのような苦難を乗り越えて、米州の多くの国で日系人コミュニティが形成され、世代を経て現地社会との融合が進んだ。
日本陸軍関東軍による満州事変を経て、1932年に日本の傀儡国家「満州国」が建国された。当時、日本経済は世界恐慌のあおりを受け深刻な不況に陥り、とりわけ農村経済を支えていた養蚕業は大打撃を受け、農村の生活困難と労働/人口過剰が政策上の大きな問題であった。このような情勢の下で、満州への移民送り出しへの関心が高まる。1932-35年の試験移民を経て、1936年に「満州農業移民二十ヶ年百万戸送出計画」が閣議決定され国策として推進され、1945年までの10年間に約27万人が移民として満州に渡った。この移民は「満州国」の防衛という関東軍の目的への貢献も期待された。試験移民の多くは武装した在郷軍人であり、1938年以降は、14−18歳の青少年からなる 満蒙開拓青少年義勇軍も移民として満州に入った。昭和100年の歴史の中で、これが日本の「移民政策」が最も強く打ち出された事例である。この大規模な移民送出計画は、ソ連軍の侵攻に際し関東軍が逸早く逃走したこともあり、死者8万人と多数の残留者という大規模な「棄民」の悲劇を結果した。
戦後1950年代には、中南米への移民送出での国家の役割が高まり、外務省に、51年に移住班、53年に移民課、55年に移住局、が設けられた。55年には、移民の送り出し機関として財団法人日本海外協会連合会(海協連)が、移住地の造成と耕地分譲の担い手として日本海外移住進行株式会社が、設立された。この両機関は1963年に統合され海外移住事業団が設立される。同事業団は1974年に海外技術協力事業団と統合され国際協力事業団が発足した。1950年代後半には、南米のいくつかの受入国と政府間での移住協定が締結され、自営開拓農民の送り出しが1970年代初頭まで続いた(最後の移民船となった「にっぽん丸」は1973年2月に南米に向かった)。このように国家としての移民送出であったにも関わらず、誇大広告による移民者募集と現地での「棄民」という実態は払拭されなかった。
それが最もはっきりとみられたのは、1956-59年のドミニカ共和国への移民においてであった。この件は日本政府として無視することができず、1961年に同国での政治混乱に際して閣議決定を踏まえて集団帰国の措置が取られた。2000年には、移住者有志が財産の損害と精神面の苦痛につき日本政府に対して国家賠償請求訴訟を起こした。2006年の東京地裁判決は、除斥期間経過を理由に移住者の請求は棄却したものの、日本政府担当者や担当大臣が法律上の義務を果たさなかったため「物心両面にわたって幾多の辛苦を重ねることを余儀なくされた」として国家賠償法上の損害賠償請求権の発生を明確に認定した。時の小泉首相は、2004年に国会で「外務省として多々反省すべきことがあった」とし、「今後、このような不手際を認め、移住者に対してどのような対応ができるか…考えたい」と答弁した。判決後に外務省は大臣の談話において「反省せず対応する」という趣旨の姿勢を表明し、小泉首相の謝罪と1人当たり200万円の一時金の支給を交換条件として上告を放棄するよう原告に対して働きかけ、裁判を終結させた。
2 移民受け入れ国家としての日本
戦前・戦中における植民地等からの受け入れとその後の対応
帝国日本は、日清戦争後1895年に台湾を領有し植民地とし、日露戦争後1910年に大韓帝国を併合し植民地とした。1930年代から朝鮮人の内地への移動が大規模に起こり、45年8月の終戦時には200万人以上の朝鮮人が内地に在住した。国家の関与としては、1938年に制定された国家総動員法の下で労務動員計画が立てられ、39年からは「募集」、42年からは「官斡旋」、44年からは「徴用」という形で、朝鮮半島から日本内地へと約80万人の朝鮮人が労務動員された。その他に、必ずしも内地への移動ではないが、38年から志願兵、44年からは徴兵、によって軍人として、そして、工員、傭人、軍夫、など軍属として、約37万人の朝鮮人が軍務動員された。さらに、朝鮮内部でも、満州、樺太、南洋に向けても、労務動員がなされた。なお、朝鮮人のみならず、中国人約4万人や連合軍捕虜約3万7千人も労務動員された。
終戦後、多くの朝鮮人が帰国し、在日残留者は終戦直後の約70万人から漸減し、現在では28万人ほどである。終戦直後から、在日の旧植民地(朝鮮、台湾)出身者は、国家によるさまざまな差別を受ける。「帝国臣民」として享受していた参政権(衆議院選挙・被選挙権)は、45年12月に改正選挙法の「付則」(「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権及び被選挙権は、当分の内之を停止す」)により剝奪される。47年5月2日、日本国憲法施行の前日に勅令として出された外国人登録令により「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされ、在日の旧植民地出身者には外国人登録の義務が課せられ、その移動には規制が課された。
その後、52年 4月19日に出された法務府民事局長通達(「講和条約の発効にともなう朝鮮人・台湾人に関する国籍及び戸籍事務の処理について」)では、「朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する」と述べられ、4月28日の講和条約発効後の「国籍及び戸籍事務の処理」に当たっての方針が定められた。これは、政策運営上の基本方針としても適用され、在日の旧植民地出身者は外国人として扱われることとなった。
原爆被爆者については、1974年に、「原爆医療法に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者が国外に居住地を移した場合には、原爆特別措置法は適用されず、同法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる」旨を定めた厚生省公衆衛生局長通達(402号通達)を発出し、その後、上記二法を統合する形で被爆者援護法が制定された後も、2003年まで上記通達に従った取扱いを継続した。
これらに関しては、戦後補償訴訟が相次いだ。1970年代から韓国在住被爆者による権利保障請求と樺太(サハリン)在留朝鮮人による帰還/補償請求、90年代からは労務動員および軍務動員された朝鮮人による日本企業への損害賠償請求あるいは日本国への国家補償請求、の訴訟が日本の裁判所においてなされた。
サハリン在留朝鮮人による訴訟は、原告死亡、永住帰国によって取下げられ1989年に終結した。しかし、裁判とは別に帰還を求める政治運動が展開され、日本政府はこの年以降サハリン残留韓国人に対する支援を実施した。元軍人・軍属(遺族)については、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」は国籍条項があるため適用されず、請求は棄却された。ただし、在日の韓国人戦傷病者と遺族については、2000年に「平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律」が制定・施行され、戦没者遺族に260万円、戦傷病者に400万円、が一時金として支給された。また、「国籍存在確認請求」に関しては、1961年最高裁判所大法廷判決と2012年の最高裁決定において、政府の方針を支持する見解が示された。
労務動員については、全ての裁判で強制動員の事実と企業の不法行為責任は認定されたが、被告企業および国に対する賠償請求は、時効、除斥期間、国家無答責、外交上の取決め、といった形式論のほうが重視され、棄却された。例えば、西松建設訴訟での最高裁判決(2007年)は付文で次のように述べる。「本訴請求は、日中戦争の遂行中に生じた中国人労働者の強制連行及び強制労働に係る安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求であり、前記事実関係にかんがみて本件被害者らの被った精神的・肉体的な苦痛は極めて大きなものであったと認められるが、日中共同声明5項に基づく請求権放棄の対象となるといわざるを得ず、…裁判上訴求することは認められない…。なお、…、個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ、本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人[西松建設]は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の[国からの]補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである。」
これを受け、2009年に東京簡易裁判所で「西松建設中国人強制連行・強制労働損害賠償請求訴訟 和解調書」が原告団と西松建設との間で締結された。他方、関係者である政府はなんらの対応も行わなかった。これに先立ち、鹿島建設訴訟については、2000年に東京高等裁判所で「鹿島花岡鉱山中国人強制連行訴訟控訴審和解条項」が原告団と鹿島建設との間で締結された。韓国人徴用工による訴訟では、日鉄釜石(1997年)、日本鋼管(1999年)、 不二越(2000年)で、被害者原告と被告企業との間で和解解決が成立した。
労務動員に関しては、1997年に、民間団体が多数の労組の協力を得て、戦時中の朝鮮人・中国人の強制連行・強制労働は労働条約(ILO29号条約)違反である、とILOの条約勧告適用専門家委員会に通報した。1999年、同専門家委員会は年次報告で日本の戦時強制労働について取り上げ、 次のような見解を公表した。「本委員会は、このような悲惨な条件での日本の民間企業のための大規模な労働者徴用は、強制労働条約違反であったと考える。本委員会は、請求が現在裁判所に係属しているにもかかわらず、被告者の個人賠償のためにはなんら措置が講じられていないことに留意する。本委員会は、政府から政府への支払いが被害者への適切な救済として十分であるとは考えない。… 本委員会は、 …日本政府が自らの行為について責任を受け入れ被害者の期待に見合った措置を講ずるであろうことを確信する。」この年以降、専門家委員会は日本政府に対し度々この見解を示しているが、日本政府は、専門家委員会報告には法的拘束力はないとして、被害者救済の勧告を無視し続けている。
韓国人被爆者については、最初の裁判では、一審、二審、三審とも不法入国者である原告の請求を認容し、原爆手帳交付、渡日治療を認めた。ちなみに、上述の「402号通達」はこの二審高裁判決後に発出された。三審最高裁判決(1978年)では、「原爆医療法は被爆者の置かれている特別の健康状態に着目してこれを救済するという人道的目的の立法であり、戦争被害について戦争遂行主体であつた国が自らの責任によりその救済をはかるという国家補償の趣旨を併せもち、国外被爆者をも適用対象者として予定した規定がある」旨を示した。2001年、在韓被爆者健康管理手当受給権者地位確認訴訟では、一審、二審とも原告の請求を認容し、国は上告を断念し「402号通達」は廃止された。さらに、2007年、三菱広島元徴用工被爆者訴訟で最高裁は402号通達を違法と認め、「402号通達を作成、発出し、また、これに従った失権取扱いを継続した上告人[国]の担当者の行為は、公務員の職務上の注意義務に違反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり、当該担当者に過失があることも明らかであって、上告人[国]には、上記行為によって原告らが被った損害を賠償すべき責任がある」として、国に損害賠償を命じた。この判決を受け、在韓被爆者は渡日せずとも健康管理手当等が受給できるようになった。
戦後から現在に至るまでの「移民政策」
戦後日本における実際上の移民政策は、昭和元年からの100年のうち4分の3の期間にわたる。 1950年、外務省に入国管理庁が設置され、翌年、出入国管理令の公布、 1952年には外国人登録法が公布・施行された。当時の移民政策は、在日韓国人・朝鮮人、在日中国人への対応を中心とした。 早くも1960年代半ば、産業界から人手不足対策として「単純労働者」の受け入れが要請された。これに対して、「第一次雇用対策基本計画」(1967年)の閣議決定の場において外国人労働者を受け入れないことが口頭了解された。この建前が「第二次雇用対策基本計画」(1973年)、「第三次雇用対策基本計画」(1976年)においても踏襲された。
1980年代後半には、労働力不足は深刻化し、外国人を労働者として動員することが政策上の課題となった。その際に、日本の人種・文化における純粋さを保つという国粋主義イデオロギーと日常生活の秩序維持という国民感情を踏まえて、単純労働者を受け入れないとの建前がとられた。「第六次雇用対策基本計画」(1988年)では外国人労働者を「専門的・技術的労働者」と「単純労働者」とに分け、前者は可能な限り受け入れるが、後者については慎重に対応するとの方針が示された。この方針に沿って 1989年に「出入国管理及び難民認定法」が改正され、1990年に施行された。同じ年には「研修」の在留資格制度が認められ、1993年には「外国人技能実習制度」が設けられた。これらの措置を通して、実際には、単純労働者を受け入れる政策が進められた。
最初に動員が図られたのは日系人であった。改正入管法では血統に基づく「身分」として就労可能な在留資格が設けられた。また、国際交流促進の一環として進められた留学生の増加も、外国人労働者の動員という側面を持った。これと並んで、企業での研修という名目での動員も始められた。その発展型が技能実習制度であり、この制度において、上記の建前と実際の政策との間の齟齬が最も露骨に現れた。技能実習制度は、建前としては技術移転を通じての国際協力を目的とすると唱えられたが、実際の目的は単純労働者の動員であり、国家としての偽装と偽善の制度化であった。この制度の下で、外国人労働者の尊厳と人権が損なわれる事例が頻発した。
2017年には、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、「技能実習の適正な実施」と「技能実習生の保護」を政策目標として明示し、「外国人技能実習機構」が新設され、送り出し国16か国(2024年10月時点)との間で技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)が取り交わされた。同法の採択に際しては衆参両院の法務委員会で付帯決議がなされ、実施状況を国会に報告することが求められた。この新体制は、「技能実習生の保護」の面では改善と評価しうる。とりわけ、転職を認める途を開いたことは重要である。他方、「技能実習の適正な実施」という面では、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(第3条2)と規定され、偽装は精緻となり手続きは煩瑣となった。それは、一面では、建前としての技能実習を実現するように働いたかもしれないが、他方では、偽装に要する負担を重くすることで受入れ企業のブローカーへの依存を強め労働調達費用を高め、そのしわ寄せが実習生に及んでいるかもしれない。
これと並行して、2019年に新たな在留資格として「特定技能」が設けられた。これは、「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる」と、本音を偽装せず目的として表明した点で、移民受入れ国家日本の歴史上で重要な画期をなす。これに伴い、「技能実習」終了後に「特定技能」へと在留資格を変更する途が開かれた。さらに、2024年には「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告書を受け、「技能実習」に代わり、「人手不足分野における人材の確保と育成」を目的として、「特定技能」資格への準備段階として「育成就労」制度を新設するための関連法の改正が国会で可決・成立した。改正法は、成立後3年以内に施行されることとされ、2027年の施行が予定されており、「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」で検討が進められている。施行後に3年間の移行期間が設けられることが予定されており、2030年までは技能実習制度と育成就労制度が併存するが、その後は外国人労働者受入れにおいて技能実習制度という偽装・偽善は払拭される。
「移民政策」の現状と課題
従来から、外国人労働者の受け入れについて、「専門的・技術的分野の外国人」は「我が国の経済社会の活性化に資する」として「積極的に受け入れていく必要があり、引き続き、…円滑な受入れを図っていく」との方針が取られる一方で、「いわゆる単純労働者」の受入れについては、「我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、さまざまな検討を要し、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応する」との姿勢が取られてきた。この二分法との関係では、「特定技能」資格は「専門的・技術的分野の外国人」に、「技能実習」と「育成就労」は「単純労働者」に、それぞれ該当する。
上述のように、「育成就労」制度は、「専門的・技術的分野の外国人」たる「特定技能」資格保持者を育成するとの位置付けで、単純労働者を受け入れる。それは、「育成」の実がみられない場合には、「単純労働者」の単純な受入れに終わる。これに関して重要なことは、需要側企業と供給側外国人のどちらにも、金銭面の節約ないし収入のみに関心があり「育成」には関心がない当事者が多数存在することである。そうである限り、「単純労働者」の偽装した受入れへの誘因は常に強く働く。当面はそれを規制しようとする方針と見受けられるが、需給両面での本音を本音として認める政策への転換が近い将来に不可避であるかもしれない。
上述のように、2019年の「特定技能」資格の設定、2024年の「育成就労」制度の新設と、外国人労働者の受け入れに重要な転機が画された。その一方で、時の岸田首相は2024年の国会審議の中で、「政府として、国民の人口に比して一定程度規模の外国人やその家族を、期限を設けることなく受け入れることで国家を維持する、いわゆる移民政策を取る考えはない」と、これまでの政府の方針を繰り返した。同時に、同首相は、「人口減少に対し、社会が適合する動きを並行して進めていかないと不都合が生じる。外国人と共生する社会を考えていかなければならない」とも述べている。
以下、これに関連する機構および施策について、時間を追って推移を見よう。1988年に5月に、「我が国の国際化の進展等の観点から外国人労働者の受入れの範囲拡大や円滑化が要請される一方、外国人の不法就労等が社会問題化している現状に鑑み、外国人労働者の受入れ範囲拡大の是非、拡大する場合その範囲及び受入れ体制の整備等外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するため」、「外国人労働者問題関係省庁連絡会議」が設置された。2006年には、「生活者としての外国人に関する総合的対応策」が打ち出され、「暮らしやすい地域社会づくり」、「子どもの教育の充実」、「労働環境の改善、社会保険の加入促進等」、「在留管理制度の見直し等」、の4事項につき政策指針が示された。
2018年7月には、「一定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れ及び我が国で生活する外国人との共生社会の実現に向けた環境整備について、… 政府一体となって総合的な検討を行うため」、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が設けられ、同年12月には「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が打ち出され、その後、毎年改訂がなされている。2021年1月には、関係閣僚会議の下に「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」が設けられ、同年7月に「共生社会の在り方及び中長期的な課題についての意見書」が提出された。
2022年以降、法務省により2026年度を目標年次とする『外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ』が策定されている。これは、「日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現を目指し、外国人がキャリアアップしつつ国内で就労して活躍できるようにすることなどにより、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるような環境を整備」することを目的とし、「安全・安心な社会」「多様性に富んだ活力ある社会」「個人の尊厳と人権を尊重した社会」の3つのビジョンが掲げられ、「取り組むべき中長期的な課題」として「円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組」「外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化」「ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援」「共生社会の基盤整備に向けた取組」の4つの事項が挙げられ、各事項につき対応策が示されている。
このような動きの中で、総務省は2005年6月に「多文化共生の推進に関する研究会」を立ち上げ、2006年3月に報告書を発表し、「地域における多文化共生」を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義し、地方自治体での多文化共生施策の推進に関する指針・計画の策定に資するため、コミュニケーション支援、生活支援、多文化共生の地域づくり、を3本の柱とする「地域における多文化共生推進プログラム」を打ち出した。2020年9月には、社会経済情勢の変化を踏まえ改訂がなされ、「多様性と包摂性のある社会の実現による『新たな日常』の構築」、「外国人住民による地域の活性化やグローバル化への貢献」、「地域社会への外国人住民の積極的な参画と多様な担い手の確保」、「受入れ環境の整備による都市部に集中しないかたちでの外国人材受入れの実現」、の4つの課題が新たに提示された。
上に引用した岸田前首相の発言で、「いわゆる移民政策」の内実は、定住する外国出身者の「規模」と「期間」という2つにより規定される、と解釈しうる。それらを明確にしない実際上の移民受入れ政策は、経済上の必要を主な動機としてこれまでも取られてきたし、今後も取られ続ける。そして、2018年の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」以降、人材としての労働者の受入れという経済の関心と人間としての外国人との共生という社会の課題、の両者を一体として取り組む移民政策が進められようとしている。
上に見たように、現在、政府の移民受入れ政策として、法務省を中心とする「外国人との共生社会の実現」と総務省による「地域における多文化共生推進」が併存している。これらはそれぞれ中央政府の方針と地方自治体の関心事を反映しており、その間に齟齬はない。ただし、前者のビジョンでは「安全・安心な社会」と「個人の尊厳と人権を尊重した社会」が掲げられている一方、後者では、「文化の違い」が明示され、また「外国人住民の地域社会への貢献」が強調されている。
「共生社会」の実現に向けて
「多文化共生」がいわれるときの「文化」とは、要は「生活習慣」にほかならない。「異文化」との接触は、日々の生活の中での違和感を生じさせ、秩序感を乱し、「共生」への反感の種となる。そして、そのような心理状態は、国粋主義・排外主義への共感の温床となる。そして、ネット空間には、特定の外国人集団への反感や憎悪の言葉があふれている。これまでのところ、「共生」を受容し支持する人々が援護することで、外国人への迫害は抑えられている。これから外国人がさらに増加する中で、異文化との接触はますます頻繁かつ広範となるであろう。それは「共生」への慣れを生むとともに反発も生じさせる。西欧での反移民勢力への支持の広がりを鑑みても、「共生」がどのような社会心理を生み出すかは予断を許さないとの感を強くする。
「外国人との共生社会」のビジョンとしての「安全・安心な社会」は「外国人が包摂され、全ての人が安全に安心して暮らすことができる社会」と敷衍され、「個人の尊厳と人権を尊重した社会」については、「外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏見なく暮らすことができる社会」と敷衍されている。これについては、次の重要な課題に正面から取り組む必要がある。一般に、社会の中で多数派と少数派の間には非対称があり、強者と弱者の関係にある。多数派の少数派に対する偏見や差別が、少数派の安全・安心を脅かし、またその尊厳と人権を毀損する。したがって、すべての人の安全・安心そして尊厳と人権が守られるような「共生」を実現するには、国家が、少数派たる外国人に対する偏見や差別を抑止し、外国人に安全・安心を保証し、またその尊厳と人権を擁護する、責任を果たすことが肝要である。この関連で、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)の施行(2016年)と自治体での同趣旨の条例の制定の意義は大きい。2022年には、大阪市の条例につき最高裁が合憲との判断を示している。また、法務省人権擁護局は「ヘイトスピーチ、許さない」と銘打って啓発の取り組みを行っている。
現在そして近い将来の日本で起こりうる外国人の受難に対しては、国内法の適用による対応がなされることがなによりも重要である。それとともに、加害者が事実と責任を認識することを表明し、被害者がそれを受け入れる、という形での当事者間の和解が司法の内外で実現されることも、外国人の「安全と安心」そして「尊厳と人権」を保証する「共生社会」を実現する上で、同様に重要であろう。これに関連して、上述の西松建設の件での和解の事例は、時代背景も受難の深刻さも大きく異なるものではあるが、外国人への迫害が起こった後の解決の途を見出す上での歴史上の参照例として役立ちうる。中国人受難者および遺族と西松建設株式会社との連名によって建立された「安野 中国人受難之碑」の裏面には、中文、 日文の両方で碑文が刻まれている。その一部を引用する。
第二次世界大戦末期、日本は労働力不足を補うため、1942年の閣議決定により約4万人の中国人を日本の各地に強制連行し苦役を強いた。広島県北部では、 西松組(現・西松建設)が行った安野発電所建設工事で360人の中国人が苛酷な労役に従事させられ、原爆による被爆死も含め、29人が異郷で生命を失った。1993年以降、中国人受難者は被害の回復と人間の尊厳の復権を求め、日本の市民運動の協力を得て、西松建設に対して、事実認定と謝罪、後世の教育に資する記念碑の建立、しかるべき補償の三項目を要求した。… 西松建設は、最高裁判決(2007年)の付言をふまえ て、中国人受難者の要求と向き合い、企業としての歴史的責任を認識し、新生西松として生まれ変わる姿勢を明確にしたのである。… こうした歴史を心に刻み、日中両国の子々孫々の友好を願ってこの碑を建立する。
2010年10月23日
安野・中国人受難者及び遺族
西松建設株式会社
国家の責任としては、次のことも重要である。国家自体が、外国人に対する偏見に基づく差別を行い、外国人の安全・安心を脅かし、またその尊厳と人権を毀損する、ことがあってはならない。これは、政策の基本方針といった大きなことから、窓口対応といった小さなことまで、公権力の行使のあらゆる局面および形態について妥当することである。本稿で示したように、「移民国家日本」昭和の100年は、国家による移民に対する偏見や差別、そして尊厳と人権の毀損、の歴史でもある。
本稿で触れなかった一例として、「指紋押捺」制度がある。同制度は、1952年の外国人登録法で導入され、55年に公布された政令により実施に移された。その後、80年以降の在日韓国人・朝鮮人による拒否の運動の広がりの中で順次緩和され、2000年に廃止された。その間に、拒否者は当該自治体により告訴され有罪判決を受けた。1995年には、最高裁が同制度を合憲とする判断を示している。これは、国家が立法・行政・司法の三権にわたり外国人の尊厳(人格権としての名誉感情)を毀損した事例である。
尊厳と人権の観点から、外国人にかかわる政策・制度・対応の総点検を行うことが求められる。その一環として、公務員に「無自覚な偏見(unconscious bias)」や「無自覚な侵害(micro-aggression)」についての研修を義務づけることが考えられてよい。また、外国人にかかわる政策・制度の策定と実施に当たり、当事者たる外国人ないし支援者からの意見聴取を行うことも有用であろう。さらに、「国際自由権規約議定書」を批准し、尊厳や人権を損なわれた個人が国連人権委員会に通報し救済を求める途を開くことも有意義であろう。