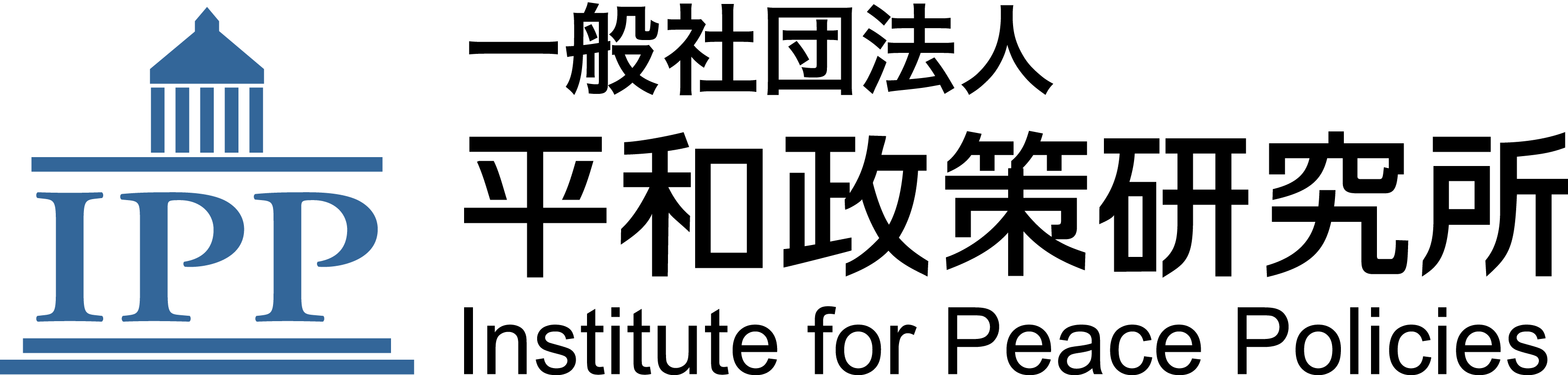はじめに
前回、なぜ我が国は大正から昭和の前半期にかけて国家の政策決定能力、言い換えれば国家戦略を策定する力が劣化していったのかを問うた。政策を決定するために長い時間を要するようになっただけでなく、国として統一された整合性ある政策を打ち出すことが出来ず、玉虫色の解釈が幅を利かせ、真に国論を纏め上げることが無いままに太平洋戦争に突入していった。その結果が未曽有の敗戦と大日本帝国の崩壊であった。
政策決定能力の劣化について考えられる原因としては、組織の肥大化や官僚化などが頭に浮かぶが、本稿では主として政治と軍事の調整メカニズムに焦点あわせ、その時代的変遷の過程を眺めることで問題の本質に迫っていきたい。
1 明治建軍と政軍一元主義の採用
1867年12月9日、王政復古が宣せられて兵権が天皇に帰属した。明けて68年1月17日、維新政府は「三職七課」の制を敷き、総裁(熾仁親王)は「万機ヲ総裁シー切ノ事務ヲ決ス」、つまり国政と軍事にわたる全権限を与えられた。七課とは、神祇、内国、外国、海陸軍、会計、刑法、制度であり、各課長に、議定による事務総督、参与による事務掛を置き、海陸軍総督は「海陸軍練兵守衛緩急軍務ノ事を督ス」と定められ、岩倉具視、嘉彰親王、島津忠義が任じられた。
三職七課は「三職八局」に部分改正された後、68年閏4月21日、新たに「太政官制」が定められた。これは、太政官内に議政(立法)、行政・神祇・会計・軍務・外国の五官(行政)、刑法(司法)の七官を創設、三権分立を取り入れたもので、軍務官が海陸軍の事務を管掌するものとされた。次いで69年7月8日、官制大改革に伴い軍務官が廃止されて兵部省が置かれた。さらに1871年2月2日、それまでの藩兵制にかわり士薩長土各藩の献兵により約1万人の御親兵が設置されることによって国軍としての姿がようやく整いはじめ、その武威の下に政府は廃藩置県を断行(7月14日)。同月29日には「太政官職制」により太政官制が改正され、太政官に一人の太政大臣を置くこととした。太政大臣(三条実美が就任)は「天皇ヲ輔弼シ庶政ヲ総判シ祭祀外交宣戦講和立約ノ権海陸軍ノ事を統知ス」る権限をもち、政治、軍事を総括する天皇の最高輔翼者であり、太政官の下に大蔵、工部、兵部、司法、宮内、外務、文部の七省が整備された。さらに翌年2月28日の太政官達第62号によって兵部省に代わり陸軍省及び海軍省が設置され、兵部省所掌の事務は夫々両省に移された。
この時期における統帥の特色は、維新政府が政軍一元主義を採っていたことである。もともと太政官制度は、天皇の下にある太政官を中心とする集権主義的色彩の強い制度であるが、軍事についても同様で、陸海軍務は軍政と軍令を分離させず、太政官に従属する海陸軍卿が軍政軍令を一元的に掌握し、それが太政大臣の輔弼によって天皇の軍事大権として発動されるシステムであった。こうした政軍一元主義の採用は、フランス軍制の影響によるものであった。1870年10月2日、政府は「兵制ノ儀ハ皇国一般之法式可被為立候共、今般常備兵員被定候二付テハ、海軍ハ英吉利式陸軍ハ仏蘭西式ヲ斟酌御編制相成候条……」旨の布告を出したが、明治初期の陸軍軍制は、大村益次郎を主導者とするフランス主義者の下に、フランス国防組織の伝統である軍政、軍令の国務大臣責任制が採用されたのであった。フランス式が取り入れられたのは、当時、フランスが世界最強の陸軍国であるとの認識に加え、ナポレオン3世の幕府への軍事援助の大きさ等それまでの同国の我が国軍制に及ぼしていた影響力の大きさを斟酌してのことであった。後の明治憲法下の政軍機構と比べると、太政官制の方が、国政の一元性、軍事に対する政治優先、政治統制が確保されていたといえる。
2 統帥権独立制度の導入
フランスの文民優位的な軍事制度の影響の下に、海陸軍に独立する何らの軍令機関 も認めず、軍務の全ては太政官に従属し、太政大臣が戦争指導の最高発言権を保持するという維新政府初期の統帥機構は、参謀本部設置に伴う統帥権独立制度の導入によって大きく変化する。
即ち、1874年2月に佐賀の乱が勃発し、文官たる大久保参議兼内務卿が軍隊指揮権を持つや、山県陸軍卿は陸軍省の外局として参謀局を設置し、陸軍卿の下に置かれはしたものの、陸軍の統帥は武官である参謀局長の専任に属することとなった。そして山県自ら参謀局長に任じ、天皇の分身である皇族を総督にかつぎ、自身は参軍として文官である大久保の手から統帥権を回収することに成功した。さらに1878年12月6日の参謀本部条例公布によって、陸軍省の外局であった参謀局が改組され、陸軍省とは独立した機関である参謀本部が設置された。参謀本部長の職務は「帷幕ノ機務二参画」(参謀本部条例第2条)することにあり、その権限は「其軍令二関スル者は、専ラ本部長ノ管知スル所ニシテ、参画シ親裁ノ後、直二之ヲ陸軍卿二下シテ施行セシム」(第5条)と定められた。
この参謀本部条例の制定と、それに伴う陸軍職制制定、陸軍省職制章程の改正により、陸軍における軍政と軍令は切り離され、太政官政府(1885年には内閣と改称)から統帥権が分離独立したばかりでなく、後者を天皇直隷とし、政治を担当する政府と参謀本部は対等の地位に置かれたのである。参謀本部長が軍の統率に関しては政府を経由することなく、大元帥である天皇に直属し、直接に天皇に上奏してその親裁を得る権限は「帷幄上奏権」と呼ばれたが、軍令事項が政府(陸軍卿)の権限外とされ、軍人の専管事項となったことによって、それまでのフランス流の文民統制原則は崩れた。
なぜこの時期に、それまでの政軍一元義を捨て去り、 統帥権を独立させる動きに出たのかといえば、(1)普仏戦争におけるフランス の敗北がその影響下にあったわが軍制におけ る一元主義を動揺せしめ、プロシャ式軍制主義を報じる山県、 桂らの帰朝と共にプロシャ軍制への傾斜が強まったこと(2)西南戦争において指揮系統の確立や参謀組織の必要性が痛感されたこと、さらには(3)国土防衛から外征軍へという建軍方針転換が影響していた。だが、参謀本部独立は、こうした軍事用兵上の必要性のみに起因していたわけではなく、当時の我が国政治状況が政権と兵権の分離を必要としていたこととも深く関わっていた。
先述したように、参謀本部独立以前は、太政官政府の下に政治権力(政権)と軍事権力(兵権)が一元的に掌握される建て前になっていた。しかし、維新政府設立当初、兵権の中核は薩長土三藩の連合兵力たる御親兵であり、しかもそれは実質的に西郷隆盛等一部指導者の人格的指導下にあった。権力基盤の未だ脆弱な維新政府は、御親兵の設置と西郷等の参議就任によって兵政両権を掌握しようと試みたが、こうした措置は逆に実質的に兵権を握る西郷等の政治的影響力を高めることになった。それゆえ、事実上の政治軍事支配者が仮に政府の政策に抵抗ないし反対する事態となれば、彼の人格的指導下にある軍の主力が政府の方針を支持せず、さらには政治集団化していく危険性がそこには内在していた。しかもこうした危惧は単なる危惧にとどまらず、西南戦争を含む一連の士族反乱や、1878年8月23日に起きた近衛砲兵の反乱、いわゆる竹橋事件の発生によって現実のものとなりつつあった。そのうえ、軍の動揺に乗じて自由民権運動の波が軍の内部に浸透することへの懸念も高まるばかりだった。
かかる危機意識は、フランス流の自由な気風の軍制に対する懐疑を維新政府に生み出すとともに、一部指導者の政治目的に軍が利用されることの危険性を痛感せしめ、それを防止するには「後害を防ぐ為文武の権を判つ事」(木戸孝允)、つまり、兵権と政権を分離し、一部指導者が政権に関与すると同時に兵権をも掌握し、軍が政治化する事態を防止する必要性に迫られたのである。「兵政の分離」、「政治と軍事の分離」は、軍の国家=政府への忠誠を確保してその政治化を防ぎ、維新政府の権力基盤を強化する為の措置であった。そしてその具体的施策が、兵士個々人の内面指導のための「軍人訓誠」(78年10月12日)や「軍人勅諭」(82年1月4日)であり、軍機構面における統帥権独立制の導入だったのだ。
軍政、軍令二元主義を採用した結果、軍令に関することは参謀本部長の権限に移り、軍政に関することは陸軍卿の所管となったが、運用の実際において軍令と軍政とは相互に密接不可分の関係を有し、機械的に分離しあうことは困難である。本家であるプロシャにあっても、両者の調整を円滑ならしめるための事務合議規定が制定されたように、参謀本部が独立した当時、明治政府の指導者においても政軍調整の必要性に関する認識が全く欠落していたわけではなかった。例えばプロシャに倣い、79年には省部事務合議書なるものが定められた。これは後の省部互渉規定の基をなすものであるが、これによっても陸軍省及び参謀本部に各々固有な事項に加え、両者協議の事項が依然として多数存在した。また参謀本部の長が参議(政府閣僚)を兼任していたのは、政治と軍事の調整を図ろうとする一つの試みであった。しかし、この慣行も内閣制度の発足以後は中断の憂き目に遭う。
1885年12月23日、それまでの太政官制は廃止され、同日付けの「内閣職権」によって内閣総理大臣及び各省大臣をもって内閣を組織する内閣制度に改められた。これによって、陸海軍大臣が誕生したが、重要な点は、統帥権の独立を内閣自体が明文をもって承認したことにある。「内閣職権ヲ定ムルノ件」の第6条は、参謀本部長と太政大臣の権限関係を明らかにし、各省大臣の内閣総理大臣への報告義務を課したが、「事ノ軍機二係リ、参謀総長ヨリ直二上奏スルモノト雖モ、陸軍大臣ハ其事件ヲ内閣総理大臣二報告スヘシ」と規定し、「軍機」に関するものについては参謀本部長より直ちに上奏し、総理は単に大臣からその報告を受ける権能のみを有することを定め、参謀本部長の管掌する軍令事項は内閣総理大臣の管掌外にあることを明らかにした。
かように、統帥権の独立は軍の国政における影響力拡大を直接の狙いとしたものではなく、文武両官混交の時期において、軍事機能の効果的発揮の確保や、政治の道具たる軍が一部指導者の私兵と化したり、政争の具に堕すことを防ぐための手段として導入された。しかし、軍の非政治化をめざしたこの統帥権独立制度には、その後の我が国の政軍関係の展開からみて重大な問題が潜んでいた。まず第一に、明治政府は従来の兵政両権の未分離状態が軍の政治化をもたらした事態を反省し、両権の分離によって対処しようとしたが、統帥権独立によって政府と軍令機関を対等・並列の位置に置いたため、政府(政治)と軍(軍事)が制度・機構上、対立・分裂する契機を内包させることとなった。また、軍が外部勢力によって利用される危険性を排除すること、つまり政治(それは、専ら「党派的対立」としての政治がイメージされていた)の軍に対する介入の防止に力点が置かれ、軍自体が軍事的合理性追及という美名の下に、その組織的な利益の追及拡大に腐心して、政治(=国家としての政策決定過程)を圧倒する危険性について十分な認識に欠けていた。
指導層における同質性
しかし、そうした構造的な問題をその初期から内在させながらも、明治中期(ほぼ日露戦争終了期)まではその弊害が際立たず、比較的有効に政治と軍事の調整統合が機能したことも事実であった。その理由の第一は、当時の権力主体が薩長藩閥勢力であり、政党勢力は例外的一次期(隈板内閣)を除いて政権から排除されていたため、軍を政治(党派的対立)の介入から守るために統帥権独立が発動されねばならない機会が稀であったことによる。
また、明治初期の軍は藩閥勢力の権力的基盤の一つであり、その点からすれば軍と政治の関係は密接ではあったが、そこでの関係は、“軍と政治との関係”とは意識されなかった。未だ文武が渾然一体で未分離の状態の下では文官が軍務につき、反対に武官が本来政治的な問題に関与しても、さほどの違和感は政権内部に生まれず、越権的意識はなかった。そこでは、現代的な意味における文民統制が機能してはいなかったが、同時に、未だ軍事の政治に対する優位という問題も表面化しなかった。では、なぜ個人的な折衝で解決できたかといえば、それは、政軍両指導者間に同質性が存在していたことにその要因を求めることができよう。たとえ軍と政府との間に対立が生じたとしても、それぞれの指導者の間には藩閥という強固な絆と同質性が存在したから、対立は彼等の個人的折衝と調停に委ねられ、分裂の事態へと拡大する前に解消が図られたのである。
もともと維新政府の構成員は、一部の公家出身者を除けば各藩の下級武士階級が大部分を占めていた。よって新政府成立後、文官の職に就く者も、あるいは軍務に従事するにせよ、軍事的な素養は等しくこれを共有しており、職制上の文官も軍隊指揮も不可能なことではなかった。未だ政治と軍事の機能分化がそれほど進行していなかったこの時期においては、統帥権独立という制度の存在にも拘らず、こうした同質性の存在が、インフォーマルなかたちで政治と軍事の統合を可能ならしめたのである。日清戦争において効果的な政治と軍事の統合が図られたのも、同様の理由によるものであった。そもそも戦時の大本営は制度上、国務と統帥の統合をめざす戦争指導機関ではなく、作戦指導に専念するための純然たる統帥機関であったが、日清戦争では明治天皇の特旨により首相と外相がその構成員に加わり、制度を超越して実質的な戦争指導機関として巧く機能した。
なかでも首相である伊藤博文は軍部に対して終始強力な指導力を発揮して、軍に対する政治統制を貫いた。戦術的な優位よりも講和の実現を優先すべく、伊藤は現地軍首脳が主張した北京・天津攻略作戦に強く反対してこれを退け、それがために山県第一軍司令官は事実上の解任となり、本国に召還された史例はそれを物語るものである。軍と政治が対立項として受け止められるようになるのは、シビリアンとミリタリーの一身的同質性を具有していた藩閥政治家や元老が姿を消し、代わって政党政治の時代に入って“政治=政党政治”の認識が生まれ始めた以降のことといえよう。第三に、建国間もない当時の日本が置かれていた小国的な環境も影響していた。国力が乏しく、列強からの干渉の危険が常に意識されていたこの時期にあっては、軍事的勝利や軍事的な合理性の追求以上に、外交や政略が優先されねばならなかった。こうした厳しい環境が、国務と統帥の分裂回避を必要ならしめたのであった。
3 大日本帝国憲法と政軍分離システムの確立
統帥権独立の定式化
1899年2月11日、大日本帝国憲法が発布され、既に制度化されていた統帥権独立の制度は国法システムにおいて定式化する。この憲法における権力の中心は、いうまでもなく天皇であった。大日本帝国憲法において天皇の大権は4〜16条までに規定されているが、補弼の機関および行動の形式により、学問的には(1)国務上の大権(2)皇室大権(3)統帥大権(4)祭司大権(5)栄典授与の大権の五つに分類された。このうち(2)は皇室の家長として行使するものであり、宮内大臣が補弼する性質のもの、(4)は祭司王として皇祖皇宗、歴代天皇および皇族の霊を祭る性質のもの、(5)は天皇が臣民および皇族に栄典を賜う性質のものである。ここで問題となるのは(1)の国務上の大権と(3)の統帥大権の関係である。
明治憲法はその第55条で「国務大臣は天皇を補弼しその責に任ず」と規定し、国務上の大権については国務大臣が補弼することとされた。そして、この第55条に定められた国務大臣の補弼権には規定上何の制限もないことから、憲法第55条に定められた国務大臣の補弼権には制限がなく、軍令事項にも及ぶという解釈を取ることも可能であった。だが、実際にはそうした解釈・運用は採られず、明治憲法の運用においては、国家統治の大権と陸海軍統帥の大権とを分離し、後者については内閣の職貴の外に置き、国務大臣がその責に任じないという政軍(兵政)分離主義が採られた。
陸海軍統帥の大権とは、軍事全般を指すのではなく、軍事大権を軍令大権と軍政大権に分け、軍令大権のみを指すとの解釈が一般であった。そのうえで、明治憲法第11条の「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」は軍令大権、つまり軍隊を指揮する権限(作戦・用兵)を規定し、第12条「天皇ハ陸海軍ノ編制及ビ常備兵額ヲ定ム」は軍政(編成)大権を規定するものと解し、軍政大権は「軍隊を編成し、軍事に関する諸般の設備を整え、軍事の必要のために国民に負担を命ずる等全て軍事に関する国家統治権の作用」であり輔弼を要するが、軍令大権は国務大臣の輔弼を必要としない趣旨と理解されていった。ここに統帥権独立の制は定式化し、文民統制的な軍制の建議が憲法に盛り込まれることはなかった。もっとも、実際上軍令と軍政の区別は必ずしも明瞭ではなく、特に常備兵額(兵力量)については争いがあり、ロンドン海軍軍縮条約締結の際には海軍軍令部が建艦計画すら統帥権にあたるとして政府の締結方針に反対したことから大問題となった。
また軍政大権だけが一般国務と同様に国務大臣(陸海軍大臣)の補弼の範囲に属し、軍令大権(統帥権)については国務大臣の補弼外で軍令機関の補佐により行うとされたが、統帥権だけが国務から独立するという明文規定が憲法上存在しないため、その法的根拠は(1)明治建軍以来、あるいは古来からの慣習、伝統及び(2)軍隊の本質的な特質といった憲法外の理由に求められた。(1)は憲法制定前の1878年における参謀本部の独立以来、実際に行われてきたことであり、また軍人勅諭において、軍隊に対する天皇直率の原理を宣明したことが統帥権独立の思想的根拠の根本とされた。(2)については、軍の機密性と機敏性、それに作戦用兵という専門技術性の要請が挙げられた。
弱い内閣総理大臣の権限
ところで、これらの大権は憲法上は統治権の総攬者としての天皇が自ら行使することが予定されており、天皇大権の各補弼機関は天皇の下に各々並立し、相互の関係は憲法上定められていなかった。従って制度上、国務を担当する内閣総理大臣は、軍の統帥権に関与することはできず、しかも明治憲法下において内閣総理大臣の地位は陸海軍大臣ら各国務大臣とは同等であった。
憲法第55条を受けた内閣官制(勅令)は、内閣総理大臣を「同輩中の首席」にとめおき、各国務大臣は個別に天皇に補弼責任を負うものとし内閣としての連帯責任を否定した。そのため、内閣総理大臣は組閣の大命を受け各国務大臣を選任できること、各大臣が天皇に上奏する場合および内閣官制第3条に定める場合の行政各部の処分、命令の中止権の3点しか各大臣に優越する権限は認められておらず、各大臣の罷免権もなかった。このように権力基盤が極めて脆弱でありながら、統帥部との間で実質的な総合調整を彼に期待することなど、制度を離れ、当該総理自身が個人的な実力を有する場合や、あるいは総理大臣が現役の陸海軍大将でもない限りは不可能であった。
そのうえ、明治憲法は君主主義を基調とする天皇親政の絶対主義的な論理をとりながら、同時に、立憲君主主義的な一面も内在させており、実際の運用にあたっては、後者の英国流の立憲君主主義が為政者の間では次第に理想像とされていった。それは、天皇に政治責任が及ぶことを恐れたためである。神聖にして侵すべがらざる天皇が権威と権力の象徴としての存在から踏み出して生の政治権力を行使し、その行使に伴う責任を負う事態の出現は、絶対に避けねばならなかった。そのため、政府の決定した最終案はそのまま裁可されるのが通例となり、天皇自身が政策決定にイニシアティブを発揮することはきわめて例外的なケースとなった。つまり明治国家は、制度上あらゆる権力を天皇に集中させ、国務と統帥の最終的な統合は天皇によってなされるべきものとしながら、実際には天皇を権力の象徴にとどめ、権力行使を天皇大権によって正当化された並列的諸機関に委ねるという極めて多元的・分立的な政治ステムを採ったのである。この結果、軍事問題と国政一般の整合を図ることは、理論上も、現実問題においても次第に困難となっていく。さらに統帥権独立の思想は軍の国務からの独立だけでなく、軍内部においても軍令の軍政に対する優位と両者の分裂を招いたほか、陸海軍それぞれが直接天皇統帥に服すという二元並列統帥実態は、陸海軍相互の対立と軍事戦略分裂をも引き起こすこととなった。
陸海軍二元統帥と軍事戦略分裂
1878年に天皇直隷の参謀本部が設けられ、軍令事項を参謀本部の専管事項とし、本部長が機務に参画して親済を仰ぐこと(惟幄上奏権)を定め、陸軍の軍政、軍令機関が分離したことは先に見たが、一方、海軍では1884年に海軍省の外局として軍事部が設置され、海軍卿の下にはじめて軍令専掌機関が設置されている。その後、1886年3月に参謀本部条例が改正され、参謀本部長は皇族を充てること、その下に陸軍部、海軍部を設けることとされ、参謀本部は陸海軍の軍令を管轄することなり、ここに軍令の一元統合が実現した。
次いで1888年には参軍官制を制定し、参謀本部長を参軍と改称、陸軍部、海軍部はそれぞれ陸軍・海軍参謀本部に格上げされたが、89年には早くも参軍官制は廃止され、陸海軍の軍令組織が参謀本部と海軍参謀部に再び分かれてしまった。そして海軍は海軍大臣の隷下に海軍参謀部を置き、海軍大臣による軍政・軍令の一元化を図った。
しかし、海軍力の増大や、大日帝国憲法の施行に伴う国務と統帥の分離の要請、さらには、当時、藩閥政府に対抗して発生した民権勢力は軍事費削減を政府に迫っていたため、軍令権を議会の干渉外に置いて政治的圧力からの回避を図るという意図から、海軍は海軍省から独立した海軍参謀本部の設置を提議した(1893年1月)。
だが、陸主海従の考え方に不満を抱く海軍に対し、陸軍は二元統帥を認めることになるとしてこれに強く反対したため、事態を憂慮し天皇の命により陸海軍首脳の間で協議が重ねられた。その結果、1893年5月19日、海軍軍令部条例制定され、海軍省から分離、独立した海軍軍令部が設置され、海軍軍令部長は天皇に直隷し、惟幄の機務に参じるものとされた。と同時に陸軍の不統一を回避するため戦時大本営条例が制定され、陸軍の参謀総長が平時にあっては陸海軍全軍の大作戦を計画するものとし、戦時に大本営が設けられる場合には参謀総長が天皇の幕僚長となり、海軍軍令部長はその下にあって指揮を受けることとされた(第2条)。
1898年海軍大臣に就任した山本権兵衛は、陸主海従の諸規定改正に強い熱意を示した。折から日露戦争の切迫という国際情勢も加わって、1903年12月、ようやく陸海軍両大臣の妥協が成立し、山県・大山両元帥の名によって戦時大本営条例の改正案が上奏された。改正案では、陸軍参謀総長と海軍軍令部長はともに惟幄の機務に協同奉仕するものとされ、ついに海軍の悲願であった陸海軍軍令機関の対等が明記され、陸海二元統帥が確立する。そして、この二元統帥の調整機関として、同時に軍事参議院が設置された。以後、この体制が1945年の敗戦まで続くことになるが、二元統帥の悪弊から、最後まで陸海軍の統一的戦争指導体制は確立されることはなく、天皇の下に2人の幕僚長が並立することになり、陸海軍相互の不信と対立も解消されることはなかった。
しかも二元統帥体制の確立は戦時における作戦指導の混乱を招いただけではなかった。兵力整備に関しても、陸軍と海軍は独自の道を歩み始めることになる。
即ち、日露戦争直後の1907年4月、明治天皇によって裁可された「帝国国防方針」において、陸海軍それぞれの想定敵国が分裂する事態となって早速それは表れた。1906年、元帥山県有朋は、陸軍中佐田中義一に国防方針案の策定を命じ、寺内陸相から原案を受領後、それをもとに「帝国国防方針案」を起草し、同年10月、元帥として上奏した。そしてこれに基づき12月、奥参謀総長、東郷海軍軍令部長に国防方針の策定が命じられ、陸海軍の協議を経て「帝国国防方針」「国防に要する兵力」「帝国軍の用兵綱領」が策定され、1907年2月に上奏、4月に裁可されたのである。
この「帝国国防方針」の内容は次のようなものであった。
「帝国の兵備は、左標準に基づくを要す。陸軍の兵備は、想定敵国中、我陸軍の作戦上、 もっとも重要視すべき露国の極東に使用し得る兵力に対し、攻勢を取る度とす。海軍の兵備は、想定敵国中、我海軍の作戦上、もっとも重要視すべき米国の海軍に対し攻勢を取るを度とす」。
「以上 述ぶる所を綜合すれば、左の要旨に帰す。
甲 、帝国の国防は攻勢を以て本領とす。
乙、 将来の敵と想定すべきものは、露国を第一とし、米、 独、仏の諸国之に次ぐ」。
一国の陸海軍において、その主たる想定敵国が異なるというのは国家戦略の分裂以外の何ものでもない。当然、この国防方針が策定される段階において陸海軍の間で激しい議論が交わされた。陸軍を代表する山県は、陸海軍がそれぞれ想定敵を異にするのは問題ありとして、国軍として想定敵国の統一を図るべきだとして、海軍も従来どおり、ロシアを想定敵とするよう要請したが、山本権兵衛海軍大将はこれに反対し、海軍として次に備えるべきはアメリカであるとして最後まで譲らなかったのである。ロシアを想定敵にせよといわれても、ロシア海軍は既に撃滅されており、存在しない相手を敵にはできないというのが海軍の言い分である。これに対しアメリカはグアム、フィリピンを占領しているうえに、ハワイを併合しており、パナマ運河開通も迫っていた。両洋艦隊となるアメリカ海軍を想定してそれに備える必要は高いというのがその論拠であったが、もっとも海軍も、ロシアに代わってアメリカが直ちに日本の脅威になるとの切迫感を抱いていたわけではなく、対米戦を望んでいたわけでもでもなかった。
むしろ、その本音は海軍力整備の目標に米海軍を選んだといったほうが適切である。しかも、海軍は海洋を自由航行できる世界共通の戦力であり、艦艇にはロシアもアメリカもない。米海軍に備えるからといってロシア海軍への備えにならないことはないという発想がそこにはあった。またマハン流のシーパワー論を信奉していた山本としては、海軍力の整備こそが覇権国家への道を約束するものと確信していたのである。裁可された「国防に要する兵力」によれば、海軍は戦艦8隻、巡洋艦8隻のいわゆる八八艦隊の整備を決めたのである。海軍は、対米戦は避けなければならないと考えつつも、自らの軍事力整備の拡充をはからんがためにアメリカを想定敵国にしたのであった。
ここに、国軍思想は「南守北進」と「北守南進」に分裂し、以後、陸軍はロシア(北進)、海軍はアメリカ(南進)とそれぞれが異なる思想を抱くことになった。敗戦まで、こうした思想の不統一が統合されることはなく、またそれだけの力を持った国家機関もなかったのである。早くも日露戦争直後に、その後における日本の軍事的自滅の要因が存在していたのであった。陸軍と海軍が史上初めてといわれる統合作戦計画を打ち出したのは、実に敗戦直前の1945年1月の「帝国陸海軍作戦計画大綱」、つまり本土決戦計画であった。もはや北進も南進もなく、本土が戦場となりつつあったからである。東条が遺言に残した軍事問題に関する最後の言葉は「我が国従来の統帥権独立の思想は確かに間違っている。あれでは陸海軍一本の行動は採れない」というものであった。
天皇親政主義と立憲君主主義の乖離
大日本帝国憲法における統治の原理は天皇親政であり、天皇に形式上全ての権力が集中する体制であった。これは権力中心に位置する唯一絶対の存在(天皇)によって統合されるという構図であり、各大権の間に阻誤や対立が生じた時には、それを調整し得る機関は天皇以外に明文上は存在しない。しかし、「天皇の大権を行うは独裁専断に依るに非ず、必ず臣僚の補翼による」(美濃部達吉「憲法提要」)との見解に代表されるような憲法機関が当時の慣例、運用であり、特に大正期以降は天皇が積極的に統合調整機能を果たすということは例外的事態となり、臣下の合意した政策に天皇が真正面から反対することも同様に異例なことであった。天皇は中空構造という歴史的風土によって集権的な権力行使を行うことを求められてはいなかったのである。これを理論化したものが美濃部達吉の天皇機関説であり、大日本帝国憲法の“密教”とも呼ばれる部分である。
こうした乖離は、天皇親政主義と天皇超政主義の折衷がもたらした産物であるとともに、憲法規範等まず西欧に基本となるモデルを捜し求め、そこに日本的意思決定システムの特性を継ぎ接ぎしようとしたことの結果でもあった。このシステムにおけるイデア・規範(建て前)と運用における現実(本音)のズレは、日本社会においてしばしば存在する傾向であり、これが例えば、一方で法律を国民生活にとって真に身近なものとすることを妨げ続け、他方では、日本的社会システムの不明瞭さとして諸外国の懐疑と批判を招く要因ともなる。それはさておき、この明治憲法における規定と現実的慣行の矛盾を結果的に埋めあわせさせることになったのが、元老といわれた非公式集団だったのである。
日露戦争以後、日本も西欧列強と同様に植民地に恒常的に軍隊を駐留させるようになると、植民地経営が国家政策の上で大きな比重を占めることとなり、平時においても国家の基本方針や戦略が軍隊の意向を無視して決定できないようになる。そこで、天皇のみが国務と統帥、国務大臣間および陸海軍の統合機能を保有するといった体制と、天皇自らが積極的に統合機能を行使しないという慣例、運用との間隙を埋めるため、各種機関の設置・活用が必要となってきた。
その一つは枢密院であった。1888年4月30日の枢密院官制と枢密院事務規程の公布によって設置された枢密院は、大日本帝国憲法第55条によると「枢密顧問は枢密院官制の定むる所により天皇の諮詞に応へ重要の国務を審議す」とあり、内閣総理大臣および各国務大臣とともに大日本帝国憲法に明記された天皇の諮問(諮詞)機関である。従って、国務に関する重要な事項については、枢密院へ諮問して、天皇の政治的判断が下されることとなるというのが大日本帝国憲法下の明文上の体制である。しかるに、実際には枢密院がそのような機能を発揮することはなく、枢密院の顧問官は後に名誉職的なものとなった。
次に1898年1月に設置された元帥府だが、これは「元帥府に列せらるる陸海軍大将には、特に元帥の称号を賜ふ」(元帥府条例第1条)、「元帥府は、軍事上に於いて最高顧問とす」(同第2条)とあるように、陸海軍の枠を越えて軍事上における天皇の最高顧問として機能することが求められたが、一定の法律上の職務はなく、定期的に会議を開くこともなかった。最初に元帥府に列せられた陸海軍大将は、陸軍からは小松宮彰仁親王、山県有朋、大山厳の三大将、海軍からは西郷従道であり、まさに、軍部の実力者として天皇の最高顧問にふさわしく、また軍の中において絶大な権威を有し、あたかも軍における元老のような地位であった。しかし、昭和期に入ると、皇族や長老の優遇という意味に変質し、軍事問題に対する統合という意味に変質し、軍部における強力な統合調整機能は次第に失われていった。
さらに軍事参議院だが、これは重要軍務の諮詢に応じる場(軍事参議院条例第1条)で、諮詢を待って参議会を開き、天皇に意見を上奏する(同第2条)機関であり、枢密院と比せられるものである。元帥、大臣、総長および専任の軍事参議官から構成され、従って前3者はその職責上ある程度統帥に関し天皇の補弼に責任を有する者であるため、軍事参議院が機能するには専任の軍事参議官の任命に大きな比重がかかることとなった。だが、これも枢密院顧問官と同じく名誉職化していった。陸海軍合同の軍事参議会が開かれることは希であり、当初期待されていた陸海軍の統合調整機能は果たせなかった(陸海軍のうち一方に係る事項については、陸海どちらか一方の軍事参議会を開くことが可能であり、事実それはしばしば開かれた)。
こうして、内閣、参謀本部、軍令部をはじめ、枢密院、軍事参議会等々天皇の顧問あるいは補弼機関のいずれもが天皇大権の代行機関足りえず、これらの特定機関が他の機関の統合調整を行うこともなく、大日本帝国憲法体制の統合機能不足は非公式または超法規的な存在によって埋められねばならなかった。そしてその機能を担ったのが明治後半〜大正期における元老といわれる集団であり、彼らは次期首相を決定しただけに留まらず、国家存立にかかわる重要な問題に対してある程度の統合調整機能を果たし、憲法上の要請であった政治と軍事(統帥)の二元制に基づく対立問題についても元老が介入して、解決に導いたのであった。
4 非公式システムとしての元老政治
元老を定義すれば、明治維新から大日本帝国憲法の制定により一応の完成を見た日本の国家体制成立に貢献をなし、その権力基盤が確立した後、非公式ポストたる天皇の政治的顧問として、その下問に答え、天皇の大権行使に大きな影響力を行使するようになった政治家(集団)である。1889年11月に伊藤博文と黒田清隆に元勲優遇の詔勅を与えたのを皮切りに、その後、山県有朋、松方正義、井上馨、西郷従道、大山厳の5人を加えて、明治期における元老集団が形成された。さらに、桂太郎、西園公望の2名が大正初期に元老に列せられた。しかしそれ以後、元老の補充はなされず、上記各元老の死去に伴い、日本政治からやがて完全にその姿を消していくのである。
日本史上、彼ら元老が活躍した時代は、第一次桂内閣の誕生(1901年)から最後の元老である西園寺が死去(1940年)するまでの約40年間であった。それ以前においては、明治維新の功労者(元勲)自身が総理大臣の座を占め、国家意志の最終的な統合調整は基本的には未だ内閣において行われていた。このうち、第一次松方内閣以後になると、次期首相の任命について天皇が伊藤、山県、松方、井上、大山、黒田、西郷の7名に下問するようになるなど、後の元老政治システムの原形が形作られていったが、内閣総理大臣は依然として元勲のうちの一人が就任しており、政府と元老とは未分離の状況にあった。だが、第四次伊藤内閣の総辞職に伴い桂太郎が総理大臣に就任。このことは、維新の元勲といわれた政治家が第一線を退き、桂及び西園寺に代表される次世代の政治家に政権を担当させることを意味した。そしてこれ以降、元勲は総理大臣など憲法に定められた政府の公的地位を占めることはなく、純然たる天皇の最高政治顧問(元老)として、いわば大御所的立場から政治に関与することとなる。
日露戦争:元老集団の戦争指導
日露戦争は、国務を担当する内閣と戦争遂行および統帥を担当する大本営、そしてその両者を元老集団が統合することで、比較的理想に近い戦略指導がなされた例であった。日露の関係が緊迫の度を深めていった1903年以降、対露政策決定のために元老会議が頻繁に開かれるようになる。当時存命中の元老は、伊藤博文、山形有朋、松方正義、井上馨、大山厳の5人であった(大山厳は当時参謀総長であったが、元老の資格で参加し、参謀総長としての発言をすることはなかったといわれる。また桂首相および西園寺公望の両名はまだ元老に列せられていない)。もっとも元老だけの会議はほとんど開かれず、元老と内閣の主要閣僚(桂首相、寺内陸相、山本海相、小村外相、曽禰蔵相)との連絡会議、もしくは桂首相が政府側を代表して元老に意見を聴くという形式がほとんどであった。
開戦に至る経緯はここでは触れないが、主戦論に立つ参謀本部と慎重論の元老との間に意見の隔たりがあった。だが、政府と元老との合同会議もしくは首相が事前または事後に元老の承認を得るという形で対露方針は決定され、対外政策の方針は政府および元老が決定するという格好が守られた。陸軍を中心とする軍部が表面に立って、国政を引っ張っていき、ともすれば二重外交といわれたように、陸海軍統帥部が表に現れてこないことは、昭和期の戦争指導と比べて軍部に対する政治側の優位が保たれていたからである。
但し、元老といっても、大本営会議における軍部の決定に関与できる元老は、現役の陸軍大将(元帥)である山形有朋のみであり(もう一人の現役の陸軍大将大山厳は日露戦争開始当時は参謀総長であり、その資格で大本営会議に列席、後満洲軍総司令官として大陸に赴任したため、元老会議等への参加は不可能であった)、陸軍に関する決定はすべて山県と内協議を経た後、山県、首相、陸相、参謀総長、次長の定例会議で決定され、海軍、外交、財政に関するものは、それぞれの機関との調整を経て、大本営会議の場に提出することが通例であった。海軍に関しては、元老であった西郷は既に死去していたものの、当時の海軍大臣山本権兵衛が海軍部内における指導権を確立し、戦争遂行に関して部内をよく統率していた。
講和に関しても、昭和期の陸軍とは異なり、山県および大山の二人の軍人出身の元老が部内の統率力を発揮し、陸軍の独走を抑制した。具体的には、1905年3月の奉天会戦の勝利以降、日本陸軍の戦争継続能力が限界に達すると、当時の参謀総長であった山県は、政府主要閣僚に対して、戦争の前途は憂慮すべき状況にあるとの意見書を出し、また、満洲軍総司令官であった大山も同様の認識から、講和を促進すべきという意見を出し、児玉満洲軍総参謀長を東京へ派遣したように、むやみに戦争遂行を叫ぶことなく、陸軍および日本の国力を冷静に見極めたうえで戦争指導にあたっている。講和条約の締結に際しても、1905年3月から14回にわたり首相と元老が会合を重ねたのである。
こうして、元老の存在が国務と統帥の対立を纏めあげる上で有効に機能したことが、世界の予想を裏切ってこの戦争を日本有利のうちに終結し得た大きな要因であった。元老とは、自らの若いときの経験に基づき、その一身において政治家であると同時に軍事専門家としてのデュアルな思考発揮ができた人材であった。その一身に同質性を具有する彼らは維新の指導者として、自分たちが作りあげた新生日本の限界を身をもって実感していた。組織がすっかり固まり、組織の論理に縛られ、或いはその代弁者となることによってのみ栄達が保障される、セクショナリズムに毒された昭和期の行政官僚や軍人官僚などとは違い、組織の虜になることもなかった。彼らの行動原理は官僚のそれではなく、組織の論理よりも国家の観点と論理を優先させるものであった。
日露戦後の満洲経営
日露戦争の戦争指導において、政府と元老の連携が効を奏し、また、軍部も戦争指導に際して表だって政府の方針に反対することはなかった。戦争終了後、朝鮮半島における以前からの日本の権益を確保し、さらに南満洲は日本の勢力下に置かれることとなり、ここに大陸での本格的な植民地経営という新たな課題が我が国政治上に大きなウエートを以て登場することになる。そして、自分たちが軍事力のみで勝ち取った領土であるとの軍部の誤謬意識から、外地運営のあり方を軸に、以後軍部の政治への干渉及び軍部の政治権力化が急速に進み、陸軍の満洲経営に対する発言力が次第に大きくなり、政府の抑制が効かなくなる事態が発生し始めるようになる。
そもそもポーツマス条約の追加約款では、日露両軍は18ヶ月以内に満洲から撤兵することになっていた。だが、日露戦争後、日本陸軍は部隊を南満洲に駐留させたままで撤兵せず、逆に締結後、日本は関東総督(陸軍大将大島義理昌総督)を新設し、その指揮下に2個師団約1万人の兵力(後の関東軍の前身)を満洲に駐留させるとともに、陸軍は各地に軍政署を設け軍政を敷く姿勢を取り始めるようになる。ロシアによる満洲独占に反対し、その機会均等・門戸開放を主張して英米と提携する形で戦争を戦ってきた日本であるから、清国及び英米両国からもこうした日本の独占閉鎖的な態度に対し抗議の書簡が寄せられていた。そのため、南満洲での軍政を継続させ、事実上満洲の独占を図ろうとする陸軍の行動を憂いた伊藤博文は各元老の了解を取り付け、「満洲問題に関する協議会」を開催させ、児玉源太郎参謀総長を筆頭とする陸軍の独走の歯止めをかけようとするのである。
当時の日本の政治状況は、日露戦争終結後の1906年1月に第一次桂内閣から第一次西園寺内閣になっており、当時の外務大臣加藤高明は門戸解放論に傾き、満洲の軍政継続を希望する陸軍と対立した。同年2月11日加藤外相は伊藤博文を訪ね、この問題を訴えたが、彼の日記には、「数個の件に関して侯(伊藤博文)と議す。就中、最も重要なるものは陸軍側の満洲門戸解放政策に対する態度、即ち其主義が全く陸軍側によって無視されていることであった」と記されている。さらに同月16日、加藤は「伊藤侯の招きに依り大磯に赴く。山県、大山、西園寺の三侯、児玉大将(当時参謀総長)および井上伯も亦会す。南満に於ける陸軍側の態度に関し、半日間を論議に費やす。数件は解決したが、他のすこぶる重要な案件は、児玉大将が熱心に主張する為に解決することが出来なかった」(大磯秘密会談)。結局、加藤外相は鉄道国有化問題を表向きの理由にして、3月に外相を辞任する。
加藤外相辞任後の4月、西園寺首相が満洲を隠密裡に視察し、それと入れ替わるように伊藤朝鮮統監が朝鮮から日本に帰国していた。「日本の軍部は、露国占領当時よりも満洲の門戸を閉ざしている。かかる事情に対し、米英両国厳重な抗議を提出した。宜しく統監の善処をお願いしたい」との駐日英国大使マクドナルドからの書状(3.31付)を伊藤は既に受け取っていたが、一方で、満洲問題については実行に関して軍部と外務省との意見があわず、そのため外国に対する回答も遷延し、外国側の疑惑を招く虞があり、西園寺首相の満洲視察を伝えた山県の書状も届いていた。このような状況の中で、満洲問題の解決に元老伊藤博文が乗り出したのである。
伊藤は、西園寺首相の帰国を待って西園寺に「満洲問題に関する協議会」を開催させた。同会議は5月22日首相官邸で開かれた。出席者は伊藤(朝鮮統監)、山県(枢密院議長)、松方(枢密院顧問官)、大山、井上の各元老、西園寺(内閣総理大臣)、寺内正毅(陸軍大臣)、斉藤実(海軍大臣)、坂谷芳郎(大蔵大臣)、林董(外務大臣)の各大臣、陸軍大将桂太郎、海軍大将山本権兵衛、参謀総長児玉源太郎の13名であった。会議冒頭、伊藤は演説を行った。
「(満洲に軍政を敷き欧州諸国に満洲の門戸を閉鎖しており)かかる状態にては、列国の物議を醸し、ひいては朝鮮の安定に悪影響を招来する虞が大であるので、自分の職責としても等閑に附し得ない。(中略)清国側の官民の不満は憂慮せざるを得ない。若し今日のままに放任したならば、ただ北清のみばかりでなく、21省の人心は、終に日本に反抗するに至るであろう」。
まず自らの情勢認識を述べ、さらに伊藤は続けた。
「(中略)今日露国から譲渡されたものを保持するのは当然で、何人も意義を挟む筈がない。然るに実際の事実は、此範囲外に出つつあるのだ。軍政署の綱領なるものを見ると、若し之を実施したならば、清国人の活動する余地はさらに無い。否、領事といえども活動することはできぬ。(中略)余はここに直言したいことがある。(中略)軍事当局者は、撤兵期間は18ヶ月であるから、明年4月までは戦時中と同様、軍事的措置をとって差し支えないとの解釈だそうである。此の解釈に基づき、或いは種々なる事業に着手し、或いは租税を徴収して居らるるようである。(中略)如此解釈を取らるるのは、余の甚だ了解に苦しむところである。(後略)」
かように伊藤が満洲で排他的に軍政を行う陸軍に対する不信を露にした後、各出席者の討論が始まった。当然、伊藤と児玉参謀総長との対立が会議の中心となる。児玉は、現地の状況は伊藤が指摘するほど悪化していないなどと反論したが、これに伊藤が怒りを顕にして、児玉の主張に鋭い批判を加えていった。
伊藤統監:「余の見る所に依ると、児玉参謀総長等は、満洲に於ける日本の地位を、根本的に誤解して居られるやうである。満洲方面に於ける日本の権利は、講和条約に依って露国から譲り受けたもの、即ち、遼東半島租借地と鉄道の外には何物も無いのである。満洲経営という言葉は、戦時中から我が国人の口にして居た所で、今日では官吏は勿論商人なども切り満洲経営を説くけれども、満洲は決して我が国の属地ではない。純然たる清国領土の一部である。属地でもない場所に、我が主権の行はるる道理は無いし、従って拓務省のやうなものを新設して事務を取扱はしむる必要もない。満洲行政の責任は宣しく清国に負担せしめなければならぬ」。
論議の一部だけを抜粋したが、一連のやり取りを見ると、満洲における日本の権益独占及び軍政継続をめざす陸軍(児玉参謀総長)に伊藤が抑制をかけ、他の元老も伊藤の方針に反対しない態度を取っている。陸軍の大御所である山県の態度も、陸軍と外務省との調整不足が直接の原因であるとの寺内陸軍大臣の見方に近く、表だって伊藤の方針に反対していない。山本海軍大臣は、「軍は政治に従うべし」との方針であった。
結局、児玉が孤立する構図になり、伊藤ら文治派が勝利し、関東総督の機関を平時組織にすること、軍政署を順次廃止することが決定され、軍政継続は解消させられた。この段階では陸軍の外地での独走を抑えるだけの力が元老集団には残っていたのである。だが、元老という重石がなくなると陸軍が独自の大陸経営論をもって政府、外務省と公然と対立し始める。また、南満洲の経緯に関しては、天皇直隷であった総督府が廃止され、代わって外務大臣の指揮を受ける関東都督府制が敷かれたが、総督の大島大将は代わらず、以後の満洲経営は都督府、満洲鉄道、領事館の三頭政治の様相を呈し一元性無きものとなる。
大正期の政治と軍事:同質性の消失と元老システムの動揺
藩閥勢力の後退による支配層内部における同質性の喪失と政党勢力の躍進、近代軍制の確立に伴う軍事官僚の台頭、それに日本の国際的地位の変化等、日露戦争後、それまで政治と軍事の調整を促していた諸要因は徐々に消滅していく。逆に、元老制が次第に衰退へと向かうなか、統帥権独立は軍事と政治の機能分化を加速し、さらには当初想起された意図を大きく離れ、軍部の自立化と政治に対する優越をもたらすマシーンとして機能するようになっていく。
まず、日露戦争と第一次世界大戦が日本を帝国主義列強の一翼に加えせしめたことで、政治優位を不可避ならしめた厳しい国際環境を緩和させるとともに、国防の第一線が大陸に拡大したことは、植民地政策及び大陸政策の形成と遂行において陸軍の比重を高からしめることになった。また、第一次世界大戦から生まれた「総力戦」の概念は国防の概念を拡大させ、もともと不分明な政治と軍事の境界をさらに不明確化させるとともに、両者の重複部分を増大せしめることとなる。他方、国内環境に目を移せば、政治と軍事の機能分化の進行・深化や軍事機構の成熟は政治指導者と軍事指導者との分化を促し、それまでその庇護下にあった藩閥勢力から軍を自立化させることとなった。しかも、政治権力が藩閥勢力から政党勢力へと移行したことの意味合いも大きかった。軍から見れば、軍閥打破を唱え、その特権的制度の改廃を主張する政党は脅威以外の何物でもなかった。そのうえ政党の行動は党派的であるがゆえに、その動きが軍に波及することになれば軍の政治化を招来する危険もあった。
つまり、国務の政党政治化が軍の存立基盤を脅かし、党略が軍のめざす軍事的合理性追求を阻止する可能性をそこに見出した軍部は、党派政治の介入から軍を守るとともに、さらに、あらゆる資源の投入を必要とする総力戦化に対応し、挙国一致の下で各種国家機能の連携・統合を推し進めるにあたって、私的利益の代弁者に過ぎぬ政党ではなく、軍自らがその主体足らんと欲する(陸軍独裁)ようになる。1914年の青島攻略も17〜22年に至るシベリア出兵も、ともにその戦争指導は陸軍参謀本部と海軍軍令部が専掌し、内閣総理大臣以下の文官がこれに関与することはなかった。戦争指導の主導権は確実に軍部に独占化されていった。
ところで1909年の伊藤暗殺後、元老の中では山県の発言力が強まり、さらに1912年9月、明治天皇が崩御して大正天皇が即位すると、当時存命中の元老(山県、松方、大山、井上の4人)に桂太郎と西園寺が加わり、この6人が大正天皇の政治的最高顧問の役割を担うことになる。だがこの時期、陸軍2個師団増設問題で第二次西園寺内閣が瓦解(1912年)、さらに清浦内閣の流産事件等軍の政治干渉が強まっていった。この過程において、制度創設当時、軍権を握る藩閥勢力が、反政府勢力の浸透から軍を守るために考案された統帥権の独立が、いまや軍事官僚を擁し藩閥勢力から自立化しつつあった軍が、党派化した国務から自らの組織と権益を守るための制度へと変質していったのである。また第一次山本内閣がシーメンス事件によって総辞職に追い込まれた(1914年)後、次期総理を天皇に上奏するべく元老会議が何度も開かれたが、松方をはじめ、奏請者からの辞退が相次いだため、結局は1801年以来の行き掛かりを捨てて大隅重信を奏請して大命降下となった。この事態も元老の影響力低下を表す例といえる。
そしてこの大隅内閣の外務大臣になったのが、先の満洲での門戸開放問題をめぐる陸軍との対立から外相を辞した経験をもつ加藤高明であった。大隅内閣の成立直後、第一次世界大戦が勃発する。これを孤立化に向かいつつあった日本にとって天祐であると捉えたのは元老も大隅も同様であったが、大戦に対する日本の政策における加藤の行動はそれまでの慣例を破るものであった。当時、元老は、戦局未だ定かならずとの理由から、英国側に立っての参戦は時期尚早との立場であったが、日英同盟論者の加藤は即刻、英国側に立って参戦すべきだと判断、この問題についての意見調整を図ることなく、政府、元老双方が出席した御前会議において、対独最後通牒を発することを決定してしまうのである。さらに加藤は、外交上の秘密保持という名目で外交文書を元老に送付することもせず、元老は他から入手した文書を独自に翻訳させて元老会議に臨むという有様であった。そのうえ、外交は秘密を要するのであれば口頭で各元老に報告すればよいとの元老側の申し出も拒絶したのである。
当然、元老側は猛反発を見せたが、制度上外交を担当すべきはあくまで天皇とそれを補弼する外務大臣である。そもそも元老の存在は何等法制に基づくものでなく、慣習上の制度であるため、首相または外相が天皇に上奏して裁可を得ると、如何に元老といえどもその方針を偏向することは制度上は不可能となってしまうのである。非公式メカニズムの弱点であった。このように、時代が下るにつれ元老の政治的影響力は低下を続ける。明治維新から早や半世紀、元老達の次の世代が成長し、政治の実権を掌握したことをこれは意味する。
以後、大正時代の政治は元老山県と立憲政友会総裁原敬を中心に展開するが、1922年、大正天皇の病気に伴う摂政設置問題が片付くや原が暗殺され、その3ヶ月後には山県も没した。桂太郎は既に大正初期の「憲政擁護・閥族打破」運動で失脚していたし、山本権兵衛もシーメンス事件で失脚、加藤高明も大正末期に早逝した。そのため、山県没後、元老は(松方の老衰がひどく)実質的に西園寺一人となる。しかし彼は、激しさを増す時代潮流に果敢に取り組もうとはしなかった。
ただ、大正期に入って元老の影響力が徐々に後退し、軍部の政治に対する関係がそれまでの同質的なものから対立的な側面を強めたからといって、必ずしも軍が即、政治に服しなくなったわけではなかった。想定脅威の低下やそれに伴う縮軍ムードの横溢、デモクラシー概念の普及、さらに国民の反軍意識の高まりや軍人の社会的地位の低下等この時期、軍部のレーゾンデートルは大きく動揺を来していた。またこうした時代風潮を背景に、政党勢力が軍部の政治的発言権拡大に反発、1913年には第一次山本内閣の原内相の意向によって軍部大臣現役武官制が廃止され、再び予備役、後備役にまで軍部大臣の資格が拡張された。さらに原敬内閣は1919年、朝鮮および台湾の総督府官制を改正して、総督には文武官いずれをも任用し得るものとし、また結局は実現に至らなかったものの、翌年には原は参謀本部の廃止をも企図している。
このように、政治と軍事の力関係が不安定になり、政党内閣と軍部の対立が本格化したが、漸次軍事力の縮小が進行し、また軍の社会的な影響力低下も加わって、大正期の政治勢力には、軍の専横と政治的関与を阻止する力は未だ残されていた。しかし、その後、政党勢力は、非公式システムとしての元老制度がかつて果たしたような政治と軍事の統合や軍部を抑える力へとは成長し得えなかった。
5 昭和前期:軍部官僚の暴走と自滅
時代が昭和に移るや、ロンドン海軍軍縮条約(1930年)の締結をめぐり、浜口内閣の軍備縮小政策に加藤軍令部長が反発、統帥権干犯問題が引き起こされた。加藤らは、国防兵力量の問題は内閣の輔弼事項外であるとし、第11条のみならず第12条までも統帥権に含ましめるべきだと主張した。第12条の「編制および常備兵額」は議会で審議されて成立する予算と不可分なものであり、国務大臣の輔弼を受けるのは当然のことであるが、野党の政友会までもが党利獲得の意図から海軍の主張を支持し、自ら墓穴を掘る失態を演じた。
さらに世界恐慌の影響から、日本の平和的・経済的発展策は破綻を迎えた。経済外交は期待された成果を挙げ得ず、世界的な保護貿易的傾向によって日本外交は頭打ちとなった。日本が死活的とみなした在満権益は中国の革命外交と衝突し、中国問題は確実に行き詰まりに陥っていった。これに加えてソ連の脅威も強く意識され出したが、政党内閣はこれら外患に効果的に対処できず、社会不安への対応にも有効さを欠いた。このような政党内閣の失政と党派的対立から生じる腐敗が、その権力支配の正当性を損なわしめることとなる。
こうした状況の中で、大正以来の政治の現状に不満を抱いた軍人は政治介入の動きを公然表面化させ、軍部と政治の関係は極めて不安定化し、1931年の満洲事変を契機として、それは破局的段階に入った。政党政治は凋落し、遂に軍部の政治支配が確立されるのだが、その直接の端緒となったのは、一部青年将校らを主体とした国家改造運動や軍人、ファッショ勢力によるテロ、クーデタであり、法制的には「分権制の極大解釈」としての明治以来の統帥権独立と軍部大臣の現役武官制がその武器とされた。2.26事件後の1936年3月9日に発足した広田内閣によって、5月18日には陸海軍省官制が改正され、再び軍部大臣の現役制が復活されたのである。国内的にも国際的にも政治の現状を不満とし、何等かの変革を要望する空気が国内に横溢していたことが、軍部の政治支配に対する一種支援の拠り所となったことも否定できまい。
もっとも、昭和において軍事と政治の関係が破局的様相を呈したそのプロセスは、軍部が上下一丸となって、自らの確固とした政治的意図をもって政党支配等反軍勢力を倒し、もって我が国の政治支配をほしいままにしたといえる程に単純なものではなかった。昭和期においては既に軍内部に派閥と下克上の風潮が蔓延し、もはや軍隊の基本である規律と統制が失われていた。モルトケのいう“浪費的存在”に堕したうえでの暴走の継続が、政治介入という結果を招来したと見るべきであろう。しかも、軍事的合理性の追求や、「戦争並国民生活上の要求を充たす為最善の能率を発揮せしむる」(永田鉄山)という“国家総動員体制”の確立を口実に、軍部は無制限に政治への介入を深める一方で、自らの対処し得ない問題に対しては、それを国防の範囲を越えたものとして、その処理と責任を政治に押しつけた。武人としての姿を失い、徹底的に官僚化した軍人は、国防や軍事の領域を恣意的に伸縮させる一方、政戦略の統合等国策全般の調整や最終的な国家責任をとろうとはしなかった。
そうした政治状況のなか、日中戦争の本格化に伴い1937年11月に陸海軍統帥部に大本営が設置されたが、日清・日露戦争のように元老、内閣総理大臣または閣僚が大本営御前会議に列席するという方式は取られなかった(政府側からは陸海軍大臣のみが大本営会議に参加)。そのため、大本営設置に伴い、大本営と政府との申し合わせにより戦争指導に関する国家意志の最高決定機関として大本営政府連絡会議なる場が設けられた。連絡会議の構成員は、政府側は総理、外相、陸海軍相を正式メンバーとし、時により蔵相、企画院総裁、副総理格の無任相等がこれに加わり、大本営側は参謀総長、軍令部総長を正メンバーとし、参謀次長、軍令部次長が加わるのが通例であった(大本営政府連絡会議は小磯内閣成立時の1944年、に最高戦争指導会議へと改組された)。しかしながら、政府(内閣)、陸軍、海軍三者による「天皇制下の多元的連合体制」の下では、何らの法的根拠も持たずあくまで便宜的産物に過ぎない同会議が、整合性ある国家戦略の策定や国家意志の統合を果たすことは到底不可能であった。
そして太平洋戦争勃発の前年、大日本帝国憲法体制崩壊を見ることなく、西園寺はこの世を去り、ここに政治と軍事の統合機能を果たしてきた元老という非公式システムは完全にその姿を消した。元老システムも政党勢力も、ともに軍事に対する政治の統制を確保することはできなかったのである。統帥権独立が内包する国務と統帥の分裂状態が続くなか、統合主体を欠いたまま戦時体制に移行した日本においては、戦争指導も軍部官僚による統帥優位の作戦指導的なものに倭小化され、欧米流の大戦略や政略的視点からのアプローチは最後まで欠落したままであった。
要するに、明治国家体制下の日本は、政治と軍事の統合的主体を欠き、その初期において機能した支配層の同質性や元老制度等のインフォーマルな統合システムが次第に消失するなか、軍が暴走、しかもその軍自らも自身の総合的・有機的な機能発揮すら行えないままに、敗戦を迎えたのである。但し、大日本帝国憲法体制においても、特定の状況下において天皇自らが主体的に意志決定を行ったケースが例外的に存在した。その状況とは、決定を下す時間的緊急制が高く、かつ、臣下レベルでの意志決定システムが完全に麻揮してしまった場合である。この二つの条件が揃ったのが、2.26事件と終戦の際の天皇裁断であった。ならば、早い段階から天皇が自ら意思決定を能動的に行うべきではなかったのかという問題が残るが、天皇機関説的発想やそれまでの日本的伝統に基づき、事実としてそれは行われなかった。
なお、元老システムの崩壊後、政治の軍事に対する優位を確保しつつ軍事と政治を統合させるメカニズムは消滅し、日本は破滅への道程を歩んでいったが、唯一元老システムに類似した機関として内大臣のポストがあった。内大臣の主な職務は(1)御璽国璽を尚蔵すること(2)常侍輔弼し及び宮中顧問官の儀事を総提することであり、天皇を補弼し、宮中と国務との連絡役を果たすものであった。内大臣設置の経緯を見ると、明治18年の内閣制度創設に際して、当時の太政大臣であった三条実美を棚上げするために設けられた官職であったことからも窺えるように、本来、政治過程において強い影響力を発揮し得るべきものとは考えられず、むしろ宮廷を非政治化することに設置の意図を読んで取ることができる。
だが、元老制度が機能しなくなった昭和期になると、天皇との距離が近いことから、特に木戸幸一が内大臣秘書官長として内大臣府に転じた頃から、軍ファシズムの台頭に対応して一定の政治的機能を発揮するようになった。次期首相の天皇への奏請は2.26事件以降内大臣と首相経験者との合意で決められるようになったこと、また、太平洋戦争末期に内大臣木戸が終戦の根回しを行ったことはその例である。もっとも、内大臣あるいは内大臣を中心とする宮中グループ(近衛、岡田、米内等)の力も限られたものでしかなく、その機能行使も遅きに失した。さらに、これらの勢力も当初は東條ら軍部と結託し、やがて戦局不利となるや一転、軍と一線を画し暗躍するなど、それはかっての元老が発揮した如き統合力も信念も持ち合わせぬ状況対応集団に過ぎなかったというべきであろう。
詰まるところ、昭和期軍部による政治介入の行き着く先は、明治憲法体制の否定であるとともに、軍組織そのものの分裂、崩壊であり、さらには我が国国家システムの壊滅であった。
6 総 括
統帥大権とは、軍隊の指揮命令権であり、軍隊を動かし、戦争を遂行することを目的とする大権である。戦争の実施は勝利を獲得することに目的があるわけで、まさにそれは国家存亡にかかわる重大事項である。軍事作戦において何らの拘束をも受けず、統帥者の自由意志によって軍隊を運用できることをめざして編み出されたのが統帥権独立の思想であり、専ら軍事作戦の機密性、迅速性、特殊性がこれに正当性を与える根拠と解された。だが、時代も大正に入る頃から、この大権の憲法上の保持者である天皇は立憲君主的行動に徹しようとされ、自らの意志表明を控えるのが通例となる。
そこで、大日本帝国憲法の表面的な体制である天皇親政の体面を保ちつつ、各部の整合を図るメカニズムが必要となってくるが、枢密院や元帥府という法律で認められた補弼機関に天皇大権の代行をさせることは法理的にも現実的にも不可能である。それに比して非公式システムである元老は、各政治勢力の統合調整機能という意味で、天皇という中心を侵すことなく、かつ天皇の政治的最高顧問という立場から、天皇の大権行使について一定の代行機能を果たすことで天皇親政という制度的建て前を保持することができた。
しかるに、時代が下るとともに軍隊や官僚といった国家統治の機構が次第に固まりをみせ、国家の運営もそれまでの属人的なものから、組織原理が幅を効かせることになる。そしてこの段階に至ると、国家全体の利益を考えるよりも、セクショナリズムの弊が芽生え出す。そのため、属人的な統合調整システムの元老集団が縮小、消滅した時に、憲法と実際上の二重構造を大局的観点に立って埋める政治勢力はもはや存在しなかった。結果、昭和期における政治情勢が陸軍の暴走により混迷の度を深め、ひいては太平洋戦争を巡り日露戦争当時のような戦略的な戦争指導を効果的に行うことは最後まで出来なかった。
また統帥権独立の制は、政治と軍事を分離、俊別して捉える傾向を助長させ、「餅は餅屋」的に、軍事問題はその途の専門家である軍人に委ねることが至上であるとの誤解を社会全般に生み出し、と同時に、政治家や一般行政官僚の軍事への関与と関心を失わしめ、彼等の軍事問題に対する適切な認識の形成を阻害することにもなった。さらに、軍を政治から遠ざけようとしたことが、軍人に国務の概念と(党略化された)政治とを別物として捉える傾向を生み出した。しかし、本来それは一体的なものであり、国務の党略化は極力自制さるべきものではあるにせよ、それ以前の問題として、社会人である以上、政党政治に対する適切な理解とその受容は、軍人一人一人に対しても当然求められる必須の素養たるべきであった。しかも、全国民を対象とした徴兵によって構成されていることから、国民の政治的、思想的動向は、軍隊内部にも反映せざるを得ない状況に旧軍は置かれていた。
だが、軍人の国政参加や政治的言動を厳しく戒める等厳しい政治的差別主義を採用し、軍人を政治から遠ざけるだけで、プロフェッショナルとしての軍事官僚の養成にあたって、軍人に対する政治教育の重要性は理解されることがなかった。その反面、軍人の政治的要求を汲み上げるための措置が十分に講じられることもなく、政党政治家の多くも専ら軍事問題を政府攻撃の材料として使うに過ぎなかった。避けるべきは軍部の政治介入であり、軍人一人一人の政治に対する認知と理解ではなかったはずが、軍の政治からの隔離が、軍人に対する政治教育の軽視や軍人の政治的発言の封印という副弊をもたらしたことによって、それが昭和期、軍部、軍人の反発を生み出し、かつ、政財界の腐敗に憤った国民の支持をバックに、彼らの政治への介入、支配を誘発させる因子となった皮肉な事実を忘れてはならない。
今日、政治優位の下での政治と軍事の統合を実現するには、軍令機関と政府の対立、並立という意味での統帥権独立の制度はこれを否定されねばならず、明治国家が当初、統帥権独立によって達成しようとした軍の国家への忠誠とその非政治化は、統帥権独立以外の措置やシステムによって担保されなければならない。ここに、文民統制の論理が必要となる所以がある。もっとも、明治国家においては、政治の軍事に対する優位が制度的に保証されることはなかったが、軍部暴走の契機となった統帥件独立の制も、必ずしも軍事の政治に対する優位を保証するためのものではなかった。政治が軍事に優先するか、軍事が政治に有するかは、その時々の国内外の環境や制度の運用ぶりによって大きく左右されるものであった。そして何よりも政治に対する軍事の優位を許した大きな制度運用上の原因は軍部大臣現役武官制に求められよう。だがむしろ、明治憲法体制のより根本的な問題は、表面的には天皇親政を装いながらも、その実態において極めて多元的な連合体制を許した点にあったというべきである。政治と軍事の統合が、制度や公式の機構を超越することによってのみはじめて可能になるという欠陥をシステム自体が内包していたことが公的権限と事実上の責任所在を不分明ならしめたのであり、この所謂無責任体系こそが軍事の政治に対する優位と、軍部の自滅的暴走というまさに無責任な所為に途を開いたのである。
第一次世界大戦を契機として、世界は国家総力戦の時代に入っていった。戦争は軍隊や軍人による戦いから、政治や経済、外交、資源、文化、地政等一国の持つ力の全てを結集せねば勝利を望めない段階へと進んだ。国力と国力が衝突する戦争の時代にあっては、政治と軍事の分離や跛行は許されず、政権を担当する実力ある政治指導者が自国の軍事や経済を統制下に置き、持てる力の全て発揮できる、そのような国家体制や政治のシステム作りが問われるようになった。その代表者がフランクリン・ローズベルトやチャーチルであった。
折から日本では、大正デモクラシーを背景に政党政治への渇望が強まり、政党内閣も誕生した。政党内閣制がさらに発展、成熟を見ておれば、文民政治家が政治と軍事を統べる強力な指導力を発揮できる可能性もあったのではないか。統帥権独立は憲法上の規定ではなかった。政治と軍事を内閣が一体的に掌握できるよう、憲法改正、あるいは改正せずとも憲法解釈を修正するだけで政治主導の国家体制作りは可能であったはずだ。しかし現実の軌跡は、2.26事件によって僅か10年程の短命で政党内閣は消滅してしまった。
一方、軍部は総力戦を勝ち抜くためとして、統帥権独立を根拠に、それをさらに越権するような行動に走り、政治や経済の全てを軍部が統制する軍主導の体制作りを目指すようになる。共産主義を最も強く嫌う軍部でありながら、社会主義的な統制経済をモデルに軍部独裁の政治体制構築に傾斜していったのだ。しかも軍部と内閣の対立だけでなく、陸軍と海軍という軍部内の対立と不協和をも抱えての軍部の暴走であった。維新から明治中期にかけて政治と戦争の双方を自らの体で経験した元勲らとは異なり、昭和の軍人はセクショナリズムの殻から抜けきれない軍官僚であった。彼ら軍官僚の前に、テロと凶行を恐れた文民政治家は膝を屈した。そのような結果、国家の戦略策定能力は著しく阻害され。政治と軍事を統合した整合性ある、そして長期的な国策の構築が不可能となっていったのである。
日本国憲法の時代になり、軍部大臣現役武官制も統帥権独立も否定された。また天皇は国民統合の象徴に退き、他方、内閣総理大臣は大日本帝国憲法時代に比して強大な権力を手に入れたはずである。その限りにおいて、過去の失敗は貴重な教訓として新生日本の建設に活かされたと言えよう。しかるに、最高規範である憲法が戦争放棄と武力の保持を禁じ、政府自ら自衛力の保持さえをも否定しておきながら、その後、同一憲法の下で、軍事力が公然存在する事態を受容せねばならぬ状況が出現するようになった。しかも、戦後日本の最終的な意志決定を行う権力中枢は何処(誰)かという問いかけに明瞭に答え切れる政治状況も現出してはいない。そして、このようないわば戦前とは形を変えての規範(顕教)と実態(密教)の遊離は、戦後日本における政治と軍事の関係にも極めて大きな影響を及ぼすことになったのである。