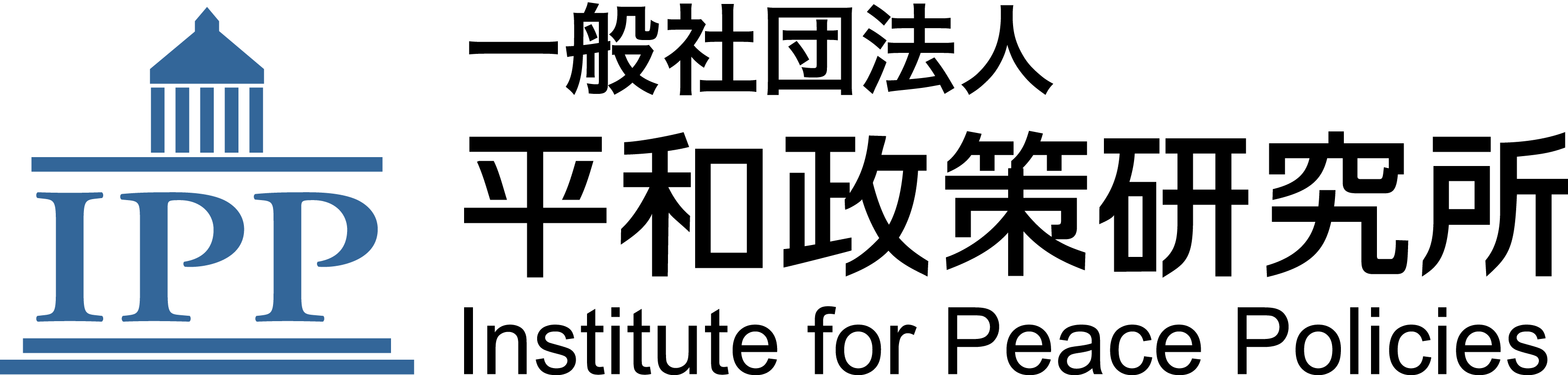1.ウクライナ
東西の接点ウクライナ
ウクライナは旧ソ連邦でロシアに次ぐ第2の大国で、住民の8割近くはウクライナ人、南部を中心に2割がロシア系。1986 年に大事故を起こしたチェルノブイリ原発が北部にある。9世紀から13世紀まで存在したキエフ公国(キエフ・ルーシ)は、ロシア、ウクライナなど東スラブ諸民族共通の国家発祥地である。
だがその後は複雑な歴史を辿り、1667年にはウクライナ西部がポーランド、東部がロシア領となる。18世紀には大半がロシアに入ったが、リビウなど最西部が旧ソ連に編入されたのは第2次世界大戦後と遅い。長くポーランドのカトリック文化圏にあった西部では「欧州の一員」意識が強く、住民の大半がウクライナ語を話す。一方、ロシア系住民が多い東・南部はロシア語使用率が高く、ロシア正教で親露派が主体だ。
こうした歴史や民族、宗教などの違いから、一つの国でありながら国を南北に流れるドニエプル川を挟んで、ウクライナは西部と東部の2つに大きく分かれ、あたかも東西文明接点の様相を呈している。ロシアと対立関係になりやすいのもそのためだ。
旧ソ連圏諸国を再びロシアの勢力下に取り込み、勢力拡大を目指すプーチン大統領は、チェチェンやジョージアに加え、キエフ・ルーシを源流とする兄弟国であり、旧ソ連圏の中で最もロシアに近いが、最も強いライバル関係にあるウクライナにも圧力をかけた。親西欧の意識が強いウクライナのEU、NATO接近を阻み、ロシアの勢力圏に押し留めるとともに、欧米の影響力東進を阻止する狙いからである。
オレンジ革命とロシアのエネルギー圧力
ウクライナでは2004年11月の大統領選挙で、任期満了のクチマ氏に代わり親露派のヤヌコビッチ候補(当時首相)が選出された。だが開票の不正を糾弾する大規模な抗議運動でやり直し選挙が行われ、12月には親欧米路線をとる野党のユシチェンコ氏が大統領に選ばれた(オレンジ革命)。
ウクライナはエネルギーの大半をロシアに依存している。そこでロシアからの離反を阻むため、プーチン大統領はウクライナに供給する天然ガスの価格引き上げや供給を停止する措置に出た。
ロシアの圧力を受けたウクライナでは、06年3月の議会選挙で親露の「地域党」が第一党となり、親露・反露各派の激しい組閣・連立工作が続いた後、8月に親露派を軸とする4党連立内閣(地域党、大統領与党の「我らのウクライナ」、社会党、共産党)が誕生、親露派のヤヌコビッチ地域党首が首相に就任した。そのため、北大西洋条約機構(NATO)加盟や対露政策をめぐり親欧米派大統領と親露派首相の対立が表面化。銀行家出身で政治手腕に欠けるユシチェンコ大統領は、親露派政党(地域党)と政策協定を結ぶ等妥協を余儀なくされた。加えて08年秋の世界金融危機は脆弱なウクライナ経済を直撃。さらにロシアは、ユシチェンコ政権に再び天然ガス供給価格の大幅値上げを通告(09年1月)。またウクライナ経由の天然ガス輸出を2週間停止する等圧力をかけた。
ロシアのクリミア併合と東ウクライナ介入
2010年の大統領選挙では、「革命」に幻滅した国民の支持を集め親露派のヤヌコビッチが当選した。エネルギー、経済、政治の三大危機脱却の期待を背に、ヤヌコビッチ大統領はNATO加盟棚上げ、クリミア半島に駐留するロシア黒海艦隊の基地使用延長に合意するなど対露関係の修復に動いた。またユシチェンコ政権のティモシェンコ前首相を職権乱用容疑で逮捕する等親西欧派への圧力を強めた。
さらに13年11月、ヤヌコビッチ大統領がEUとの経済連携を強化するための連合協定の締結を見送ると、これに親欧米派が反発、大規模な抗議デモが起り、14年2月にヤヌコビッチ政権は崩壊に追い込まれた(マイダン革命)。そしてヤツエニユクを首相とする親欧米の暫定政権が誕生したが、ロシアはこれを認めず、ロシア系住民が多く住むウクライナ東部やクリミア半島では暫定政権への警戒と反発が広がった。こうしたなか、ロシアは軍隊をクリミア半島に展開しウクライナ軍を武装解除した。3月にはロシアへの編入の是非を問う住民投票が行われ、圧倒的多数の賛成を得たとしてクリミア半島を一方的にロシアに併合する(図表1参照)。
国際社会はロシアの対応を強く批判し、国連総会はクリミア併合を無効とする決議を採択、欧米諸国は対露経済制裁を発動し、ロシアはG8から追放された。だが4月にはウクライナ東部のドネツク州、ルガンスク州では親露派武装勢力が政府庁舎などを占拠、クリミアと同様の住民投票の手法を踏襲してウクライナからの分離独立を宣言、ウクライナ政府軍と激しい戦闘に入った。
ウクライナでは14年5月の大統領選挙で親欧米のポロシェンコ政権が誕生し、9月には親露派武装勢力との間で停戦合意が成立したが守られず、その後、プーチン、ポロシェンコに加え独仏の首相も交えた首脳会議の結果、15年2月に二度目の停戦合意が実現した(ミンスクⅡ合意)。
だが、その後も親露派武装勢力とウクライナ政府軍とは断続的に交戦を重ねた。ミンスク合意はドンバス地方で地方選を実施し、親ロシア派に「特別な地位」(高度な自治権)を認めるのが停戦実現の柱になっており、独仏の働き掛けで合意したものの、ウクライナにとっては分離独立状態に法的根拠を与え固定化することにほかならず履行に二の足を踏んでいた。またウクライナでは厳しい緊縮財政や汚職問題、それに東部地域の紛争終結にめどが立たないためポロシェンコ政権の支持率は低迷し、19年4月の大統領選挙ではコメディアン出身のゼレンスキーが圧勝した。
ゼレンスキー大統領はロシアとの直接対話で紛争解決を目指す考えを示し、19年12月には露独仏との4か国首脳会議を3年ぶりに開催し、完全停戦や和平のための政治プロセス再開に合意した。しかし、東部地域に広範な自治権など特別な地位の付与を求めるロシアとは意見の一致が得られず、ロシア寄りの姿勢を見せることには国内の反発も強いため和平実現は遠のいた。
ゼレンスキー氏は東部紛争の解決を優先してきたが、ウクライナとロシアに仏独を交えた4カ国の和平協議は停滞。この状況に不満を抱いたゼレンスキー氏は、米国などより多くの国を巻き込みクリミア奪還を目指す戦略にシフトした。米独仏はウクライナ支持を確認したが、反発したロシアは21年春、また秋にもクリミア及びウクライナとの国境付近に兵力を増強させた。
ロシア・ウクライナ戦争勃発
2022年2月24日、露軍はウクライナへの侵攻を開始した。プーチン大統領は、2000年にはチェチェンで、2008年にはジョージアで、さらに2014年にはクリミアで崩壊した帝国を再建するための戦いに出ていずれも成功させている。ウクライナ侵攻もその延長で、短期にロシアが勝利を収め得るものとプーチン氏は確信していたはずだ。
露軍は一時首都キーウ(キエフ)中心部の15キロ先まで迫ったが、3月下旬にキーウ近郊から撤退を強いられた。劣勢に追い込まれたロシアは戦力を東・南部に集中させ、5月には東部ドネツク州の要衝マリウポリを制圧、7月には東部ルガンスク州の全域を掌握し、プーチン大統領は9月30日、ウクライナ東部と南部の4州を一方的にロシアに併合すると宣言した。
だがウクライナ軍は9月に東部ハリコフ州、11月には南部ヘルソン州を奪還し、23年6月には本格的な反転攻勢に出た。しかし、反転実施の時期が遅れたことや戦力を分散させたため攻勢は失敗。そこで戦局の打開とロシア側に動揺を与えるため、ウクライナは24年8月、ロシア領クルスク州への越境攻撃に出る。ロシアの反撃は遅れ、ウクライナ軍は当初かなり広大な地域を制圧することに成功した。だがその後、露軍が態勢を立て直し反撃に出たため、ウクライナ軍は徐々に後退を強いられている。越境攻撃開始当初、ウクライナ軍は約1300平方キロを制圧していたが、露軍に奪還され1月下旬時点での占領面積は約400平方キロにまで減少している(図表2参照)。
25年1月、戦争の早期終結をめざすトランプ政権が発足した。そのため少しでも有利な条件で停戦交渉に臨むため、ロシア・ウクライナ双方とも占領地域の拡大に全力を挙げている。
ウクライナ世論の変化
22年2月にロシアがウクライナに侵略を開始した頃、ウクライナ国民の大多数はロシアとの徹底抗戦と奪われた領土の奪還を強く主張した。しかし、戦争の長期化と人的物的犠牲の増大に伴い、次第に領土の奪還よりも戦争の終結を認める声が大きくなっている。
昨年12月、ウクライナの調査機関「キーウ国際社会学研究所」が実施した世論調査の結果によると、ロシアによる軍事侵攻をめぐって「和平を即座に実現し、独立を維持するため、領土の一部を放棄してもいい」と答えた人は38%と前回昨年10月の調査より6ポイント増え、2022年5月に最初の調査が行われて以降最も多くなった。一方、「いかなる状況でも領土を放棄すべきではない」と答えた人は前回より7ポイント減って51%。
また戦争の終結に向けた3つのシナリオを提示した質問では、「ロシアが東部の2州と南部の2州、クリミアの占領を続けるものの、ウクライナはNATOに加盟して真の安全保障を得るとともにEUにも加盟する」というシナリオを支持する人が最も多く64%を記録し、このシナリオを受け入れられないとした人は21%だった。この結果からは、ウクライナがNATOやEU入りを果たし、ロシアの将来の侵略を阻止し得る安全保障体制が整うのであれば、ロシアが東部地域の占領を継続している状態の下でも停戦に向けた協議に入ることを容認する国民が半数を超えるようになったことが窺える。
ゼレンスキー大統領は2019年の就任当時、ロシアとの紛争が長期化する中、国民の厭戦気分を背景に、和平、即ち停戦合意の履行に積極的だった。実際、地方選実施に向けてドイツのシュタインマイヤー元外相が提示した打開策も受け入れた。ところが、親露派の分離独立を認めず主戦論を唱える民族派の猛反発に直面する。そもそもゼレンスキー氏はポピュリズム(大衆迎合主義)の政治家であり、ウクライナが抱える経済、汚職などの難問も解決できず、当初7割台だった支持率が2割台に落ち込むと「民族派の人質」(ロシアの識者)となり、一転して失地回復を唱えるようになった経緯がある。
そしてロシア・ウクライナ戦争の勃発後は、徹底抗戦を求める世論に乗りながら終始対露強硬の姿勢を堅持し国民の戦闘意欲を鼓舞してきたゼレンスキー氏だが、ウクライナ支援に熱心だったバイデン政権から米国の深入りを嫌い早期の停戦実現を主張するトランプ政権へと米国で政権交代が起きたことや、停戦を求めるウクライナ世論の変化を踏まえて、今後、停戦協議に参加するなどその政治姿勢を転換させる可能性がある。
トランプ政権発足と停戦協議の始動
そうしたなか、2月12日にトランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が電話で協議し、ウクライナ戦争の終結に向け直ちに交渉を開始することで合意した。次いで15日には米国のルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相が電話協議し、米露首脳会談の準備などのため定期的に接触することで合意した。米露両国は18日にサウジアラビアで外相等の高官級協議を開き、紛争終結に向けて協議することや、交渉を進めるための高位チームを立ち上げることなどで合意した。一方、トランプ政権のウクライナ・ロシア担当特使ケロッグ氏は米露の和平交渉に欧州は参加しないとの認識を示した。これに欧州側は衝撃を受け、フランスのマクロン大統領は英独首相や欧州委員会委員長などを招き、ウクライナ紛争に関する緊急首脳会議を開催したが、停戦案の焦点となっている平和維持部隊の派遣では積極的な英仏と消極的なドイツの温度差が表面化した。
先月24日でロシアの侵攻開始から丸3年。ようやく最大の対ウクライナ支援国である米国がロシアと直接交渉に乗り出した。今後ロシアとウクライナの双方に対しトランプ政権がどのような条件を提示し、それが合意への道筋となるのか、米露首脳会談は何時頃行われるのか、さらに欧州諸国がどこまで停戦協議に関与することになるのかなど、交渉の進め方に世界の関心が集まっている。
2.モルドバ
モルドバはウクライナとルーマニアの間に位置する国で、歴史的にルーマニアとの一体性が強い。ルーマニアと一体であった時代、今のモルドバがあるあたりはベッサラビアと呼ばれていた。公用語はルーマニア語。国民の大半を占めるモルドバ人は民族・言語的にルーマニア人と同系統であり、スラブ人主体の東欧にあって「ラテンの孤島」となっている。モルドバ人のほかには、ウクライナ人とロシア人、それにトルコ系のガガウズ人がそれぞれ5%前後を占める。モルドバの人口は約400万人、国土面積は3万平方キロと岩手県の2倍程の大きさである。
1349年にボグダニア公国が建国され、後にモルダヴィア公国へ発展したが、16世紀にルーマニアの一部とともにモルダヴィア公国もオスマン帝国の支配下に組み込まれ、19世紀には露土戦争(1806〜12年)の結果、ロシア帝国に編入された。第1次大戦後ルーマニア領となるが、第2次大戦でソ連に奪い返され、ソ連邦を構成する15共和国の一つ「モルダビアソビエト社会主義共和国」となった。その後、冷戦末期には東欧革命の影響を受けソ連からの分離運動が活発となり、1989年8月に首都キシニョフ(現在の名称はキシナウ)で60万人が参加する大規模な反ソデモが発生。翌90年の国会選挙で民主派が勝ち、1991年8月に現在の「モルドバ共和国」に名を改め独立を果たした。同年12月21日に独立国家共同体(CIS)に加盟している。その4日後の12月25日、ソ連邦は消滅した。
こうした複雑な歴史経緯から、モルドバ国民にはルーマニアと統合していた時代を国家のアイデンティティに求める人もいれば、ロシア帝国やソ連時代の歴史を重視し、文明的に西欧よりもロシアに親近感を持つ者も多い。2017年6月の世論調査では、57%の者がロシアとの友好、43%が西欧との友好を選ぶが、NATO加盟には65%が反対している。ルーマニアとモルドバは一種の「分断国家」であり、ルーマニア側にもモルドバ側にも国家統一を求める意見はあるが、必ずしも強いものではない。
モルドバのGDPは約120億ドル、所得水準は非常に低く、「欧州の最貧国」と呼ばれる。農業・食品以外に有力な産業がない。輸出の多くはルーマニアやトルコ、EU向けだが、ロシアとの経済的な繋がりも強い。輸出の1割、輸入の2割弱がロシアで占められ、ロシアのウクライナ侵攻前、主要産品のリンゴは95%をロシアに輸出してきた。天然ガスの輸入も100%ロシアに頼り、エネルギー、そして出稼ぎでもモルドバはロシアに大きく依存している。
二つの自治国
モルドバの東部、ウクライナと接するドニエストル川東岸のトランスニストリア地域はかってロシアの軍事拠点で、現在も親露派が支配し中央政府の統治が及んでいない。1990年9月、ルーマニア系民族に主導を握られることを嫌うロシア系住民らは「沿ドニエストル・モルダビア・ソビエト社会主義共和国」を創設、翌年には社会主義を放棄して国名を「沿ドニエストル共和国」と改称し、モルドバからの分離独立を宣言した。
互いに独立を宣言したモルドバと沿ドニエストル共和国の間で戦闘が勃発(トランスニストリア戦争)、ロシアは平和維持軍として露軍をトランスニストリア地域に送り込んで介入し、現地の親ロシア派勢力を支援した。紛争は決着がつかぬまま92年7月に和平協定が締結され、ロシア、モルドバ、沿ドニエストル合同の平和維持軍によって停戦監視が行われることになった。以後、停戦は保たれているが、この地域の法的地位は未解決のままで、沿ドニエストル共和国の独立は現在に至るも国際法的に承認されておらず、この地域に住む推計50万人の住民はモルドバから事実上分離した状態が続いている(図表3参照)。
そしていまも1500人規模の露軍が「平和維持」を理由に駐留しており、沿ドニエストル共和国の北部コルバスナにはロシアの弾薬庫がある。1989年12月の冷戦終結を機に、ソ連が衛星国の旧東ドイツや旧チェコスロバキアから弾薬や武器を回収しこの地に集めた。独メディア、ドイチェ・ウェレによると、火薬の総量は広島型原爆に匹敵し「ソ連の爆発遺産」との呼び名もある。
こうした事情から、ロシアがウクライナに侵攻した2022年2月以降、「次はモルドバだ」(ドイツのベーアボック外相)との懸念がくすぶっている。ロシアは、クリミアに加え、ロシア系住民が多く住むウクライナ東・南部4州の併合を宣言、ロシア領として支配しようとしている。同様の手法で、沿ドニエストル共和国のロシア系住民を取り込んでモルドバ支配に出るのではないかとの懸念だ。その恐れは、対ウクライナ戦争の戦況が膠着するに従って強まっている。
ロシア中央軍管区の副司令官は22年4月、ウクライナ南部を経由し、最終的にはモルドバに到達する戦略目標を発表した。ウクライナ東部のドンバス地域とクリミア半島、そして港湾都市オデッサを含むウクライナ南部を押さえ、そこに沿ドニエストルが繋がれば、ロシアはウクライナを東西で挟み撃ちにして行き詰った戦局を打開できるし、NATOが東に張り出してくることも防げる。
22年4月末には沿ドニエストル共和国が実効支配している地域で爆発が続き、ロシアはそれをロシア系住民に対する攻撃だと非難した。モルドバおよびウクライナはロシアの自作自演ではないかと疑っているが、ロシアは、沿ドニエストル共和国に駐留する露軍兵士に危害が加えられた場合には対応するとして武力行使を示唆した。モルドバ政府への牽制だが、ロシアの介入につながる動きとも受けとめられている。
一方、モルドバ南部に住む少数民族のガガウズ人が89年11月に「ガガウズ自治ソビエト社会主義共和国」樹立を宣言した。モルドバからの分離独立は果たせなかったが、1995年には大幅な自治権を付与されている。ガガウズ人はトルコ系でトルコとの関係が深いが、ロシア正教を信奉しロシア語を日常使うというユニークな少数民族である。
最近ではトランスニストリア地域だけでなく、ガガウズの政情も不安定である。2023年5月のガガウズの首長選挙ではロシアが大規模な介入を行い、無名だったグツル女史を当選させた。24年3月にはプーチン大統領がグツル首長と対面し、関係の強さを誇示している。沿ドニエストル共和国のクラスノセリスキー大統領は16年の就任以来、一度もプーチンと会えておらず、ロシアのガガウズに対する関心の高さが伺える。ロシアはモルドバのEU加盟に反対しているガガウズ人(約20万人)を反政府運動に煽り立て、モルドバ政府に揺さ振りをかけようとしているのだ。
親欧米派政権の誕生
親露派の政権が続いていたモルドバでは2020年1月の大統領選挙で、「行動と連帯(PAS)」の創設者で元首相のマイア・サンドゥ氏がモルドバの「統合と経済の立て直し」を目標に掲げ、親露派のドドン大統領(当時)に勝利した。大統領に就任したサンドゥ氏は、欧州連合(EU)とロシアの双方とも対話を重視してバランスのとれた外交を目指すとしたが、国内のロシア系住民が一方的に独立を宣言している沿ドニエストル共和国に駐留する露軍の撤収などを要求している。またロシアのプーチン大統領と関係を築いてきた前任者と異なりヨーロッパ寄りの政策を進め、国内では親ロシアの野党勢力との対立が強まっている。
サンドゥ大統領は21年1月、隣国のウクライナを訪れ、ゼレンスキー大統領と初めて会談し、ロシアと対立するウクライナとの連携を示した。双方が署名した共同声明では、両国の高いレベルでの対話を再開するとともに、EUへの加盟に向けた協力の強化を確認した。
しかし、ドドン氏の親露派勢力がサンドゥ氏の組閣案を否決するなど抵抗し政権運営に支障が出たことから、サンドゥ大統領は憲法裁判所に議会解散と前倒し議会選の実施を請求し承認された。これを受け21年7月に前倒し議会選が行われた。サンドゥ氏は、汚職の撲滅や言語・文化を共有する隣国ルーマニアとの接近を掲げて支持を拡大。その結果、サンドゥ大統領の与党「行動と連帯」が第一党の座を確保した。これによりサンドゥ大統領の政治基盤は安定した一方、旧ソ連圏での影響力維持に腐心するロシアには大きな痛手となった。22年2月、隣国ウクライナへのロシアの軍事侵攻が始まると、サンドゥ政権はロシアのウクライナ侵略を強く非難、ロシアとの対決姿勢を強めた。またエネルギー分野などでの対露依存からの脱却を図りつつ欧米への接近を加速させ、22年3月にはジョージアと共にEUへの加盟を申請した。
経済の悪化に乗じるロシアの政権転覆工作
ロシアのウクライナ侵攻の影響を受け、欧州の貧困国であるモルドバの経済は一層悪化している。中でもエネルギーに関しては深刻な状況にある。モルドバはウクライナから自国領を通り東欧に至るロシアのパイプラインから天然ガスの供給を受けている(モルドバはそのガスを使うトランスニストリアの発電所から、電力の80%を得ている)が、モルドバの親西側政権に揺さぶりを掛ける目的でロシアが天然ガスの価格を引き上げ、供給量も減らしたため、ガス価格をはじめとする物価高騰や30%前後の高いインフレが発生、さらにウクライナからの難民の急増も加わり、国民生活は圧迫されている。それに乗じて親露派政党SORが主導して政権幹部の退陣や年金の引き上げなどを求める反政府デモが首都キシナウを中心に各地で続発している。
そうしたなか、ロシアがモルドバ国内でクーデターを計画している事実が明らかになった。サンドゥ大統領が23年2月、軍事訓練を受けたロシア人、ベラルーシ人、セルビア人、モンテネグロ人などが政府機関を攻撃して人質をとり、現在の政権を打倒し、ロシアの傀儡政権を樹立しようとしていると述べたのだ。ウクライナの情報機関が傍受した通信から判明したという。親欧米路線を加速させEU入りを目指すサンドゥ政権に圧力を加える狙いとみられ、サンド大統領は対抗措置を取る考えを示した。
これに対してロシア外務省は「全く根拠も証拠もない主張だ」と反論するが、米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は3月の記者会見で、米情報機関が独自に収集した情報に基づくものとして、ロシアがモルドバの現政権を転覆させ親露派政権の樹立を目指しており、具体的な計画として「ロシアの情報機関と繋がりのある関係者がモルドバで抗議活動を起こし、それを利用する形で反乱を作り出そうとしている」とサンドゥ大統領の認識を支持し、「米国は今後も強力な支援をモルドバに提供し続ける」と述べた。
ウクライナに侵攻したロシア軍は首都キーウの攻略に失敗、その後、東南部に攻撃を集中させ、クリミアからオデーサへと占領地域を拡大し、さらにモルドバにまで到達することを狙ったが、これもウクライナ側の抵抗にあい実現は困難となった。そこで謀略戦を仕掛けてモルドバのサンドゥ政権転覆を画策しているものと思われる。
プーチン大統領は23年2月、沿ドニエストル共和国はモルドバの一部だとしてその主権を尊重する立場を示した2012年の政令を撤回した。さらにロシア国防省はモルドバが親ロシア派の分離主義勢力が支配する沿ドニエストル共和国を「武力で挑発しようと準備している」と非難した。そのような事実はなく、モルドバ政府もこれを一蹴したが、これはロシア系住民が狙われているとの根拠のない主張を行いドンバス地方を占領、さらにウクライナ侵略を正当化した際と同じ手法である。
23年5月、サンドゥ大統領は「独立国家共同体(CIS)の首脳会議は今後、モルドバでは開催しない」考えを明らかにした。その一方、6月にはEU加盟国と近隣諸国の連合体「欧州政治共同体(EPC)」の首脳会合を開催し、ロシアと決別する姿勢を強めた。そして12月のEU首脳会議で、ウクライナと共にモルドバの加盟交渉開始が決まった。世論調査では、モルドバ国民の6割がEU加盟に賛成している。サンドゥ大統領は2030年までのEU入りを目指すとし、EU加盟の是非を問う国民投票を行い広く国民の支持を得たいとの考えを示した(図表4参照)。
緊迫するモルドバ情勢と強まるロシアのハイブリッド戦
24年2月、ロシアが支援する沿ドニエストル共和国の指導部が緊急議会を開催し、モルドバ政府の圧力が強まっているとしてロシアに庇護を求める決議を採択した。これに呼応してロシア外務省は「同胞の利益を守ることは常に優先課題の一つだ」とする声明を発表、ラブロフ外相もモルドバのロシア系住民が差別されていると主張し、モルドバがウクライナと同じ歩みを辿っていると述べた。分離主義者がロシアに助けを求め、それを口実にロシアが武力介入したウクライナと同様の動きをロシアが見せたことから、モルドバ情勢は緊迫の度を高めた。モルドバ政府は、圧力を加えているという親露派の主張を真っ向から否定。さらにロシアの脅威に備えるため、3月にフランスと防衛協力協定を締結した。
ウクライナと激しい戦闘を繰り広げているロシアが直ちにモルドバの親露派地域に兵力を送り込む余力はなくその可能性は低いが、ロシアがこの時期に介入の威嚇を見せたのは、秋に予定されているモルドバの大統領選挙が念頭にあったからだ。再選を目指すサンドゥ大統領は親欧米の路線を確実にするため、大統領選挙と同時にEU加盟に関する国民投票も行う意向を明らかにした。また24年6月にはウクライナに続き、EUはモルドバとの加盟交渉を開始した(図表5参照)。
モルドバでは親欧米派と親露派の政治勢力による政権交代が続いてきたが、事前の調査では親欧米派のサンドゥ現大統領が大きくリード。国民の大半もEU加盟を望んでおり、選挙後も親欧米路線が続く公算が大きかった。ロシアはサンドゥ政権の排除やモルドバのEU加盟を阻止すべく、なりふり構わぬ買収や偽情報請工作など様々な謀略戦(ハイブリッド戦)を活発に展開させるようになる。
そうした動きに警戒を強めるモルドバの警察は10月初め、同月20日に行われる大統領選とEU加盟の賛否を問う国民投票に向け、モルドバの親露派勢力が13万人以上の市民を買収していたと発表した。ロシアから送られた資金で、親露派候補への投票とEU加盟反対を働きかけていたとみられる。また9月の1か月間だけでロシアの銀行から1500万ドル(約22億円)以上がモルドバの有権者らの口座に送金されたことも確認された。ロシアに亡命した親露派政党創設者のイラン・ショル氏がこの工作に関与しているほか、ロシアからモルドバ国内の複数の協力者に指示が出されている。
ショル氏は24年4月、大統領選に向けた野党連合「勝利」をモスクワで結成し、モルドバのガガウズ自治州のグツル首長らがこれに参加している。グツル首長は前年にショル氏の支援を受けて当選。モルドバがEUに加盟すれば自決権を行使すると主張し、「独立」の可能性を示唆している。モルドバ政府はショル氏の政党を非合法化したほか、10以上のロシア語テレビ局も「偽情報を流した」として放送禁止処分にしている。首長選での買収の疑いでグツル氏への捜査も進めた。
買収工作だけでなく、ロシアはモルドバの軍高官をスパイとして取り込んでもいる。2021年までモルドバの軍制服組トップだったゴルガン前参謀総長は露軍参謀本部情報総局(GRU)のスパイとなり、04年以降、親露派と親欧米派が対立してきたモルドバの情報をGRUに提供。参謀総長退任後も協力は続き、ウクライナが隣国モルドバで兵器を調達しようとする動き等を報告していたという。ロシアとモルドバの親露派は政権転覆を狙って繰り返し、選挙干渉や反政権デモの扇動、偽情報の拡散など多様な手段を講じている。
大統領選挙とEU加盟の国民投票
大統領選には11人が候補者登録されたが、事実上現職のサンドゥ大統領と親露派政党の支援を受ける元モルドバ検事総長ストイヤノグロ氏の一騎打ちとなった。サンドゥ氏は選挙戦で「国の未来は欧州にある」と述べ、親欧州路線の継続を唱えたのに対し、ストヤノグロ氏は「モルドバにとってロシアも重要だ」と対露関係の改善を訴えた。世論調査によれば、対露依存からの脱却を図りつつ欧州との一体化をめざす現職のサンドゥ大統領の支持率は36%でトップ。親露派政党の支援を受けるストイヤノグロ氏に大差を付けた。EU加盟の是非を巡る世論調査でも、「賛成」(63%)が「反対」(32%)を上回った。
10月20日、大統領選が行われ、同日、EU加盟を国家目標として憲法に明記することの是非を問う国民投票も実施された。大統領選では、サンドゥ大統領が40%を越える得票率で第1位となったが、当選に必要な過半数には達せず、2週間後に第2位のストヤノグロ氏との間で決選投票が実施されることになった(図表5参照)。EU加盟の是非を問う国民投票は、賛成が50.46%、反対が49.54%と僅かながら賛成が上回ったが、サンドゥ大統領やEU、米国にとっては予想外の接戦となった。なぜここまで反対票が増えたのか。選挙戦後、モルドバの警察当局はロシアから買収目的で計3900万ドル(約59億2千万円)が有権者に支払われていたと発表した。警察によると、9月の1500万ドルに続き、10月にも2400ドル以上がロシアの銀行を通じて送金され、約14万の口座で140万件以上の不正な取引が確認されたという。欧州委員会は、モルドバで実施された大統領選と国民投票にロシアが不正な資金提供や偽情報キャンペーン、サイバー攻撃を含むハイブリッド戦争を仕掛け介入したとの声明を発表した。
親欧米派現大統領が決選投票で勝利
24年11月3日、大統領選の決選投票が行われ、サンドゥ現大統領が約54%を得票しストヤノグロ氏を破り勝利した。サンドゥ氏は、選挙戦でモルドバをロシアの勢力圏にとどめるための買収工作が展開された「明白な証拠がある」と主張。ストヤノグロ氏を「モスクワの男」と非難した。
二期目に入るサンドゥ政権の課題は、エネルギー危機への対処である。モルドバはウクライナ経由でロシア産天然ガスを輸入してきたが、12月末にウクライナとロシア間の天然ガス通過契約が失効することで天然ガスの供給が止まり、電力不足から大規模な停電が起きる恐れがあるからだ。ロシア国営ガス会社ガスプロムは、モルドバが過去の債務の返済を拒否していることが供給停止の理由と説明するが、サンドゥ氏はそのような事実はないと否定、「ロシアはウクライナ経由とは別ルートでのガス供給が可能であるにもかかわらず、代替ルートによる供給を拒否している」とロシアを非難した。
モルドバはEU加盟を目指しているが、憲法で中立主義を明記しており外国軍隊の駐留は認めていない。それゆえNATOへの加盟はハードルが高い。改憲して中立主義を放棄すれば露軍の駐留を許す恐れも出て来る。国民の多数も中立を支持しており、NATO入りを目標としているウクライナとは事情が異なる。
そのためロシアが直ちに武力介入に出るとは考えにくいが、政治工作や偽情報などハイブリッド戦を仕掛けサンドゥ政権に揺さぶりをかけ続けるであろうことは想像に難くない。モルドバでは、今年夏に議会選挙が予定されており、親欧米派と親露派の争いがさらに激化することが予想される。
ドイツのベーアボック外相は昨年9月、ロシアに侵攻されたウクライナへの支援は、ウクライナに留まらず、その隣国モルドバが生き残れることを保証するものでもあると述べた。そして「ウクライナに対するあらゆる支援は、モルドバの安定化を促進することも意味する」とし、「もしもウクライナが陥落した場合には、モルドバが次の標的国になるということだ」と指摘し、モルドバ支援の重要性を訴えた。
3.バルト三国
エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は、北方戦争やポーランド分割によっていずれも18世紀からロシア帝国に支配された。ロシア革命ののち独立を達成するが、第二次世界大戦中の独ソ不可侵条約における秘密議定書に基づき相次いでソ連と相互援助条約を締結させられ、ソ連軍の駐留と基地設置を強いられた。1940年にはソビエト連邦に併合され、ソビエト連邦を構成する共和国となる。
半世紀後の1991年、ソ連崩壊の過程で独立を回復。現在は欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)の加盟国となり、西側諸国の一員としてロシアの侵攻を受けるウクライナを強く支持している。過去に併合された歴史を持つことやロシアと直接接する地政的環境から、バルト3国はロシアの「次の標的」になるのではとの危機感を強め、国境管理の厳格化に努めている。
各国とも国境のフェンスの延長や検問所の閉鎖、さらに露軍の侵攻ルートを検討し「竜の歯」と呼ばれる強化コンクリート製の障害物などを設置するなど露軍の侵略阻止の体制を急ピッチで整備している。またNATO諸国と連携し軍事演習を活発に実施するほか、ウクライナへの派兵も検討している。国防費の増額にも前向きだ。トランプ大統領が、NATO加盟国はGDPに占める国防費の割合を目標としてきた2%ではなく5%に引き上げるべきだと主張していることについて、エストニアのペフクル国防相は「西側諸国が国防費を増やさず十分な抑止力を示さなかったため、ロシアによるウクライナ侵攻に至った」と指摘したうえで「ロシアを抑止し、自国民を守る用意を示す必要がある」と述べ、エストニアを含むNATO加盟国は国防費の割合を5%に引き上げるべきとの考えを示している。
さらにバルト三国はロシアへのエネルギー依存を解消する目的で、ロシアの電力網から自国の電力網を切り離し、ポーランド経由で欧州連合側の電力網に接続に切り替えた。これに対しロシアは、サイバー攻撃や貨物機の爆破を狙うなどバルト諸国にハイブリッド攻撃を繰り返している。24年5月上旬、リトアニアの首都ビリニュスのショッピングセンターで起きた火事にはロシア工作員の関与が指摘された。同年7月にはリトアニアから英国に発火性物質が送られ、ポーランドの首都ワルシャワ郊外で起きたトラック火災の原因になった可能性が取り沙汰されている。さらに11月にはビリニュスの空港近くで、ドイツから飛行してきた貨物機が着陸の直前に墜落、同じ月、スウェーデンとリトアニア、フィンランドとドイツをそれぞれ繋ぐ海底通信ケーブルが相次いで断線した。いずれの事故にもロシアの関与が疑われている。バルト三国は他のNATO加盟国とも連携し、監視体制の強化に動いている。
4.中央アジア
ロシアと距離を置くカザフスタン
中央アジアとは、ユーラシア大陸中央部、ゴビ砂漠からカスピ海に至る地域を指す概念だが、今日一般にはパミール高原より西に広がる草原地帯(西トルキスタン)で、9世紀からイスラーム化し、19世紀にはロシアが進出、そして冷戦当時、旧ソ連邦を構成していたカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスの5つの共和国が「中央アジア諸国」として論じられることが多い(図表6参照)。
中央アジア諸国においても、ウクライナ侵攻後、ロシア離れが進んでいる。ウクライナと同様、ロシア系住民を抱える国が多く、ロシアによる併合を懸念するほか、ロシアに協力して西側諸国から経済制裁を受けたくないとの思いからだ。さらに中国が中央アジア諸国への接近を強めており、ロシアよりも中国に傾斜する動きが強まっている。中央アジア最大の国カザフスタンでもそのような傾向が顕著だ。
カザフスタンは、ロシアが主導する旧ソ連圏の軍事同盟「集団安全保障条約機構」(CSTO)や旧ソ連圏経済ブロック「ユーラシア経済同盟」の主要メンバーで、中央アジアの中でロシアにとって最も重要な同盟国である。その一方、カザフスタンはロシアと7600キロの長い国境線で接し、また東・北部には全人口の2割弱にあたるロシア系住民が居住しており、ウクライナと同様の事情を抱えている。
これまでカザフスタンは、ロシア系住民の地域を安定的に保つためにもロシアとの友好関係を維持してきた。22年1月にカザフスタンで原油価格の大幅引き上げを契機に大規模な反政府デモが発生し、長年独裁を振るってきたナザルバエフ氏が失脚した際も、トカエフ大統領は旧ソ連諸国が加盟するCSTOを介してロシアに鎮圧への協力を要請している。
しかしその直後、ロシアがウクライナへの攻撃を開始し、ドネツク・ルハンシクなどロシア系住民の住むウクライナ東・南部4州の独立を強行したことから、同じ論理が向けられる危機を感じ取ったカザフスタンはロシアと距離を置くようになった。そしてロシアのウクライナ侵略や占領地の併合を認めず、また対独戦勝記念日を祝うのを止めたほか、動員から逃れてきたロシア人を多数受け入れている。
23年5月、ユーラシア経済同盟の会合がモスクワで開かれた際、トカエフ大統領は連合国家創設を視野に入れるロシアとベラルーシに言及。ロシアがベラルーシに戦術核の配備を決定したことを踏まえ、「今や核兵器を共有しようとする2国1制度」と揶揄し、カザフスタンはロシアと核兵器を共有する意思はないと明言した。
旧ソ連セミパラチンスク核実験場の放射能汚染の後遺症に苦しむカザフスタンは、「核兵器の廃絶」を重要な外交課題に掲げている。ウクライナやベラルーシと同様、この国もソ連崩壊後に残された核の保有国となった。1994年に他の2国と共に安全保障と引き換えに核放棄に応じる「ブダペスト覚書」を締結したカザフスタンは、核を放棄して非核地帯を宣言し、核兵器禁止条約にも参加している。
またトカエフ大統領は23年9月にベルリンを訪問した際、ショルツ独首相に対し「カザフスタンはロシアの制裁回避・迂回を支持しない。カザフスタンは対ロ制裁の方針に沿った行動を取る」と述べ、「カザフスタンは制裁を遵守するために関係機関と連絡を取っていて、制裁回避を目的とした行動が起きる可能性についてドイツが心配する必要はない」と発言した。トカエフ大統領の一連の発言は、国の主権や核兵器を巡りロシアとの間に一線を引こうとするカザフスタンの立場を明確にさせたものと言える。
カザフスタンと中国の接近も著しい。トカエフ大統領は23年5月中国を公式訪問し習近平国家主席と会談、ビザ(査証)の相互免除で合意している。
一方ウズベキスタンは、独立の当初から、タジキスタンのラフモン大統領の背後にいるロシアに警戒心を持っており、それは1999年2月のカリモフ大統領暗殺未遂事件で決定的になった。そのためウズベキスタンは早くから北大西洋条約機構(NATO)に接近し、あるいは親欧米の旧ソ連諸国協力枠組みであるGUUAMにも参加するなど外交関係の多角化を進めている。
中央アジア諸国の離反防止に奔走するプーチン大統領
中央アジア諸国がロシアから離反する動きを見せるなか、プーチン大統領は各国を自らの陣営に繋ぎ留めるための外交を続けている。2023年10月、プーチン大統領はキルギスを訪問し、独立国家共同体(CIS)の首脳会議に出席した。ウクライナ問題を巡り、国際刑事裁判所(ICC)がプーチン氏に逮捕状を出して以降、プーチン氏の外国訪問はこれが初めてだった。ロシアの求心力低下が指摘される中、プーチン大統領は経済分野などを中心に連携を訴え,各国との結束強化に動いた。しかしCIS首脳会議にはアルメニアが欠席し、逆にロシア離れを印象付けることになった。
翌11月、プーチン大統領はカザフスタンを訪問、トカエフ大統領と会談した。プーチン氏は「両国間の戦略的パートナーシップと同盟関係が成功裏に発展している」と強調し、トカエフ氏も「訪問は政治的、歴史的に重要」と述べ歓迎し、共同声明ではエネルギーや軍事など幅広い分野での協力強化が盛り込まれた。その一方、トカエフ氏は同じ月、カザフスタンを初訪問したマクロン仏大統領と会談しエネルギー分野などでの関係強化を確認。「戦略的鉱物」に関する協力拡大に合意している。
続いてプーチン大統領は24年5月、ウズベキスタンを訪問し、首都タシケントでシャフカト・ミルジヨエフ大統領と会談。ロシアがウズベキスタンに原子力発電所を建設する協定に署名した。同年11月には再びカザフスタンを訪れ、トカエフ大統領と会談。トカエフ氏はウクライナ東部の独立を認めず、ロシアによる侵攻に異を唱えているが、会談後の共同声明では西側諸国の制裁に反対する立場で一致し、足並みの乱れを糊塗している(図表7参照)。
中央アジアで高まる中国の存在感と影響力
中国にとって中央アジアは天然ガスなどエネルギーの供給減であり、一帯一路計画の重要拠点でもある。また中国は、中央アジアを通じてイスラム過激派などの運動や思想が自国に流入することを警戒している。北西部の新疆ウイグル自治区はカザフスタン、キルギス、タジキスタンと国境を接しており、「国内の安定」という観点からも中央アジア諸国との関係を重視している。ロシアのウクライナ侵略で中央アジア諸国が対露警戒感を高め、また西側諸国の制裁の対象とならぬようロシアから距離を置く動きを見せる中、中国は積極的に中央アジアへの進出を図っている。
習近平国家主席は2013年にカザフスタンを訪問した際、一帯一路にちなみ、中国から欧州へと抜ける陸路の輸送ルートを通じた経済圏の構築を目指す「シルクロード経済ベルト」構想を表明。中国と欧州を結ぶ国際貨物列車の運行は年間1万6000便を突破するなど物流の大動脈として注目を集めている。その「シルクロード経済ベルト」構想表明から10年の節目にあわせ、2023年05月、中国と中央アジア5カ国の首脳会議(中国・中央アジアサミット)が陝西省西安で開催された(図表8参照)。広島での先進7カ国首脳会議(G7サミット)と同時期に開催することで西側の連携に対抗し、対中包囲網を強める米国を牽制する狙いがあった。
首脳会議で演説した習氏は、中央アジアと「より緊密な運命共同体を構築する」と強調したうえで、物流網やエネルギー面での協力強化も打ち出し、中央アジアへの総額260億元(約5200億円)に上る資金融資と無償援助を約束。習氏は演説で、自身が提唱し、10年の節目を迎えた巨大経済圏構想「一帯一路」の促進に向け、中国と中央アジアを結ぶ高速道路の整備や、中国—キルギス—ウズベキスタン鉄道建設の協議推進を呼び掛けた。
エネルギー分野では、中国と中央アジアを結ぶ天然ガスパイプラインの増設を進め、石油・天然ガスの取引を拡大するほか、核エネルギーの平和利用でも各国と協力を深める考えを示した。さらに習氏は米欧を念頭に「外部勢力による地域国家の内政干渉に強く反対する」と述べ、中央アジア各国の治安強化を支援するとともに政情不安が続くアフガニスタン情勢に共同で対応することを提案した。そして今後は首脳会議を2年ごとの定期開催にし、次回は2025年にカザフスタンで開くことも明らかにした。会合後に発表された「西安宣言」では、運命共同体」を目指す中国と中央アジアが、経済や文化から国家安全保障まで幅広い分野で協力するとしている。
また習近平国家主席は23年10月、「一帯一路」フォーラム出席のため訪中したカザフスタンのトカエフ大統領と会談し、良好な二国関係呼びかけた。さらに習氏は翌24年7月、上海協力機構(SCO)首脳会議に合わせカザフスタン、タジキスタンを歴訪。カザフスタンではでトカエフ大統領と共に中国からカザフ経由で欧州に至る物流ルートの開通式にオンラインで出席。タジキスタンではラフモン大統領と両国関係を「新時代の全面戦略協力パートナーシップ関係」に格上げすると宣言した。6月には、中国が20年以上前から構想を進めてきたキルギスとウズベキスタンを通る鉄道建設の政府間協定の署名に漕ぎつけるなどロシアの「裏庭」とされた中央アジアで中国は急速に自らの存在感を高めている。
中央アジアでは今後、中国の存在感がさらに強まるものと考えられる。天然ガスの大産出国であるロシアは中央アジアからエネルギーを買うことはないが、中国は中央アジア諸国にエネルギーを依存しており、中央アジアとのエネルギー貿易を今後も拡大させる可能性が高く、レアアースの開発でも協力し得る関係にある。ロシア語に堪能な人が多い中央アジアではロシアに出稼ぎに出るのが一般的だが、中国の賃金がロシアよりも遙かに高くなれば、ロシアに代わり中国に職を求める人も増えよう。こうした中央アジアとのエネルギーや人の密接な繋がりが、中国のプレゼンス増大に繋がるだろう。さらに中国は内政不干渉などとともに、各国の領土の一体性の尊重を強調している。これはロシア系住民の存在を根拠に自国領がロシアに併合されることを恐れる中央アジア各国にとって心強い支援となるからだ。
欧米諸国も相次ぎ中央アジアに接近
中央アジアへの接近を強めているのは中国だけではない。欧米諸国も関与の動きを示している(図表9参照)。ロシアのウクライナ侵略に対し、欧米諸国は対露経済制裁措置を発動したが、中央アジア諸国がその制裁の抜け道になっているとの指摘がなされている。欧米やG7は、半導体など軍事利用が可能な製品の対露輸出を規制しているが、そうした西側諸国の製品が中央アジアの国々を経由してロシアに流れている疑いが強いのだ。事実、中央アジアからロシアへの輸出量は増加しており、軍民両用の製品などがロシアに渡り、武器の生産に当てられているものと欧米諸国は見ている。
そのため、米英やEU等の政府関係者がカザフスタンなど中央アジアの国々を訪問し、対露制裁への協力を迫っている。23年2月にはブリンケン米国務長官がカザフスタンを訪問、中央アジア5か国の外相らとの会談に臨み、経済や安全保障分野での協力を訴えた。ブリンケン国務長官の中央アジア訪問はこれが初である。米国は2015年から中央アジア諸国との会合C5+1を開いているが、この年初めて米大統領が出席している。
また23年11月にはフランスのマクロン大統領がカザフスタンを初めて訪問しトカエフ大統領と会談、エネルギー分野などでの協力強化を確認したほか、同じ11月には主要7カ国(G7)外相会合に中央アジア5カ国が初めて招待され、オンライン会議が行われ連携強化を働きかけた。ドイツも中央アジア5カ国との初の首脳会議を開いた。中央アジアを対ロシア制裁の抜け道とさせないことに加えて、中央アジアにおけるロシアの影響力を削ぐとともに、併せて中国の影響力拡大にも歯止めを掛けたいというのが欧米各国の狙いと言えよう。
総括 真の同盟国を持たないロシアの限界
強いロシアの復活を目指すプーチン大統領は、ウクライナ侵攻後も折に触れてロシア主導の下での旧ソ連圏の結束を訴えている。しかし、2回にわたりロシアと旧ソ連を構成した国々との関係を眺めてきたが、現在、ロシアの影響下にあってロシアと行動を共にするのはベラルーシ一国に過ぎず、これまで結びつきの強かった国々とロシアとの間には深い溝が横たわっている。
旧ソ連を構成した多くの国々は。いまもロシアとの関係を断ち切り難く、また国力、特に軍事力での圧倒的な格差が存在するため、反露反プーチンと受け取られないよう慎重に行動している。ロシアがウクライナに侵攻して以降、そのような警戒心はさらに強まっている。CISやCSTO加盟国として名を連ね、ロシアを正面切って批判する国は少ない。しかしその実態は強者に対する面従腹背に過ぎず、ロシアと友好協力や密接な同盟関係にある国はほとんどない。ベラルーシさえも、今年2月に7選を果たしたルカシェンコ大統領が自身の独裁体制維持のために、より強力な独裁者であるプーチンの支援を必要とするがゆえの連帯であり、信頼と相互理解の上に立つ真の同盟関係とは言い難い。
他の周辺諸国を見ると、
*バルト三国はソ連に併合された当時からクレムリンに対し強い敵意と反感を抱いており、ソ連崩壊後、独立を果たすや早々とEUやNATOに加盟している。またウクライナに続き侵略される事態を想定し、NATOの加盟国と共に軍事的に対処する体制作りを急いでいる。
*ロシアの軍事侵攻を受けたウクライナ、武力衝突が起きたジョージア、それに親欧米路線を進むモルドバはEU加盟を申請し、ロシア圏からの脱却を目指している。
*これに対し、これまでロシアとの関係を重視してきたアルメニアは、ナゴルノカラバフでアゼルバイジャンと対立、その際、後ろ盾としていたロシアの支援が得られなかったことから急速にロシアと距離を置き、欧米に接近するようになった。
*そのアゼルバイジャンも、昨年12月、自国の旅客機がロシアの防空システムの誤射で撃墜された疑いが強まり、しかもロシア側の謝罪がないことにアリエフ大統領が強く抗議し、プーチン大統領との関係が俄かに悪化した。ロシアが罪を認めない限り、ロシアを国際司法裁判所に提訴する予定であると報じられている。
*ロシア系住民を抱える中央アジア諸国では、“ウクライナの再来”による領土併合を恐れロシアと距離をとる一方、中国への接近が進み、運命共同体構築を掲げるまでになっている。なかでもロシアにとって中央アジアにおける最大の同盟国であったカザフスタンのロシア離れは顕著である。
*さらに言えば、ロシアと4千キロ以上の国境線を抱える中国は、反米・多極化・グローバルサウス支持で共同歩調をとってはいるが、価値観を共有する同盟国と呼ぶには程遠い。反米という面で利害を共有はしているものの、中国はウクライナとの戦争で苦しむロシアを尻目に、中央アジアなど旧ソ連圏への影響力拡大に余念がない。
*またロシアはウクライナのNATO加盟を阻止する目的で侵略したが、その結果、これまで中立国であったフィンランドとスウェーデンがNATOに加盟し、NATO勢力の拡大を許すことになった。
現在、ロシアはウクライナとの戦闘を有利に進めており、トランプ政権が仲介に入っても、簡単には停戦に応じず、ウクライナのNATO加盟阻止や占領地域のロシアへの併合を求めるなど交渉条件を吊り上げ、強気の姿勢を当面維持すると見られる。また経済制裁を受けてはいるが、戦争特需の効果や中印へのエネルギー売却によって戦争継続能力はなお健在で、この面ではロシアの底力は侮り難いものがある。
しかしながら、一国の国力を計る際、同盟関係の強固さや友好国の多寡は重要な指標である。グローバルサウスを取り込み、アフリカなど遠隔の途上国に影響力を広げているロシアだが、自国の周辺に信頼に値する同盟国をほとんどロシアは持っておらず、その強権さは見かけほどのものではないことが窺える。
かってエレーヌ・カレール・ダンコースは『崩壊した帝国』(1978年)において、ソ連が民族問題によって崩壊する恐れがあることを言い当てたが、現在のロシアにおいても民族や宗教問題はその強権支配におけるアキレス腱であることに変わりはない。プーチン大統領はチェチェン、ジョージア、クリミアを力で抑え込み、帝国の復権を進めてきたが、いまやウクライナで行き詰まり、その他の多くの旧ソ連構成国への支配や統制も揺らいでいる。
暴力や謀略に頼り、そして常に上から目線で接し、各国と対等な関係を築こうとしないプーチン大統領の政治姿勢では、民族問題の真の解決は到底望めず、たとえ対ウクライナ戦で有利な停戦条件を手に入れたとしても、ロシア帝国の復活は不可能であることを意味している。
(2025年2月19日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)