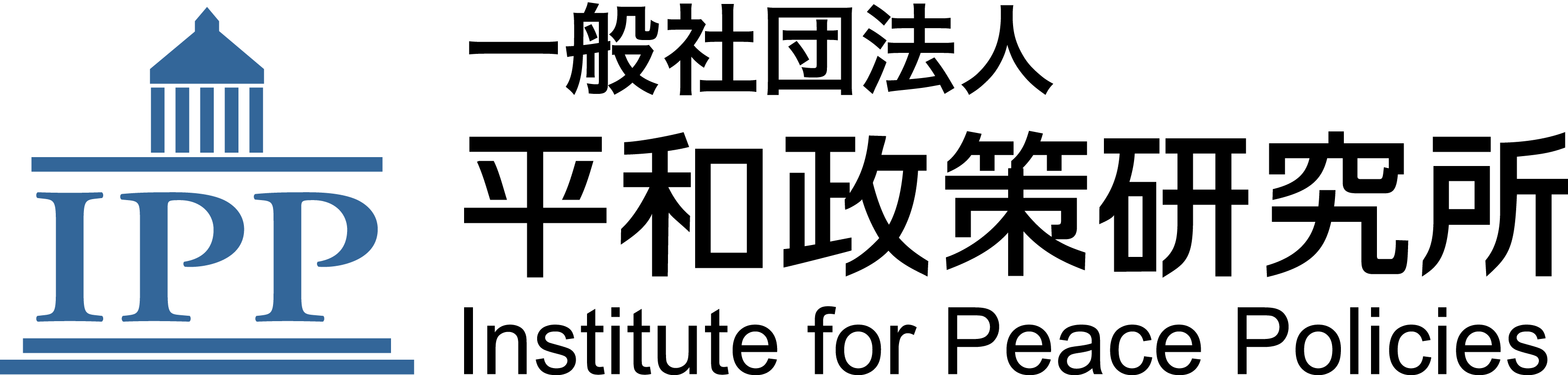はじめに
2010年代から、国際政治における東南アジアの重要性が高まっている。米中の大国間競争が国際政治において決定的な構造とみなされる一方で、東南アジアの振る舞いは単純化して理解される傾向がある。本稿では、大国間競争が顕著に表れるテーマを取り上げながら、東南アジア諸国における政策決定プロセスの事例や、東南アジアを理解する上で前提となる視点など(ただし、情報は2024年6月時点のもの)を紹介したい。
1.国際政治の中の東南アジア
米国と中露の国際認識
今日の国際情勢を理解するにあたって、主流のシェーマがある。米欧日などのG7+が第二次世界大戦後の国際秩序を守ろうとしているのに対して、中国、ロシア、北朝鮮、イランとフーシーなどのイスラーム武装組織がその秩序に対抗しようとしている図式である。これは日本でも広く認知されており、とくに安全保障の分野で語られることが多い。
このような国際認識を公言したのは、第一期トランプ政権の『国家安全保障文書』(2017)である。米国やその同盟国に対する挑戦者として、中国とロシアを修正主義国家・権威主義国家、イランと北朝鮮をならずもの国家と表現し、イスラーム武装勢力にも言及した。
さらに『国家防衛戦略』(2018)では、中国を「周辺国への恫喝と強制により、インド太平洋地域の秩序を再編し、まず地域覇権を握り、やがてはアメリカのグローバルな覇権に取って代わろうとしている」と説明し、米国の対中認識を明示した。
とりわけ、中国による南シナ海の軍事化が問題視されている。米国の対抗策は、QUADに加えて東南アジアの同盟国(タイ・フィリピン)、とくにフィリピンとの安全保障協力の強化と、安全保障パートナー(シンガポール、ベトナム、マレーシア、インドネシア)との協力強化である。ただし、実際のトランプ外交では東南アジア軽視が目立ち、東南アジア諸国からのアメリカに対する信頼は低下した。
バイデン政権も、大国間競争が国際関係の基本構造であるという認識を継承した。『国家安全保障文書』(2022)では、米中間の競争が基本的枠組みだという認識や民主主義と独裁の競争という視点が全面に打ち出された。この競争を前提とした上で、自由で開放的で安全で豊かな世界を維持するための米国の役割が一層重要であると述べられている。
中国とロシアの国際認識に関しては、2022年2月に行われた中露首脳会談の共同宣言がわかりやすい。中露は世界における権力の再分配が起きているという基本認識を持っている。同宣言は米欧について、一国主義的で暴力に訴えて各国の内政に干渉して独自の「民主的な基準」を他国に押し付け、イデオロギーに従ってブロックを作るなど冷戦的なアプローチをとる米国のリーダーシップは立ち行かなくなる、などと批判している。
中露は国連と安保理が重要な役割を果たす多極的な国際関係を目指すと述べている。米国が提示するような民主主義対独裁というような世界観に真っ向から反対し、米国の覇権に異議を唱えている。
東南アジアをどう捉えるか
米中間の競争が世界の基本認識となっていく中で、東南アジアの戦略的な重要性が高まっている。
まず、ASEANは経済的に重要な地域である。1990年代以降の経済統合によって、関税はほぼ撤廃され、域内投資も飛躍的に拡大している。人口は約6.7億人(2022年)、その過半数が生産年齢人口で、人口ボーナスはほとんどの国でしばらく続く。
2010年から2022年までの地域の経済成長率は4.4%、コロナパンデミックを踏まえると高い成長率である。2022年には世界第5位の経済圏にまで成長し、消費市場と生産拠点の両面で、ASEANのプレゼンスは高まっている。
加えて、ASEANの地政学的な重要性も高まっている。東南アジアはシーレーンに沿って広がった地域であり、とくにマラッカ海峡はシーレーンのチョークポイントである。
中国は2010年頃から南シナ海における海洋行動を活発化させた。九段線内は中国の海だという主張は法的根拠に乏しいが、中国海警や海軍、民兵などが他国の排他的経済水域や領海に侵入し、漁船や監視船に攻撃を加える事件が多発している。
中国の問題行動に対して、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、フィリピンなど南シナ海で主権を主張している国々がどのように対応するのかという問題は、各国の領有権の問題を超えて、開かれた海を維持できるのか、国際法秩序を守れるのかというより大きな課題に直結する。
東南アジアの経済的かつ地政学的な重要性に鑑みて、米国はオバマ政権以来、ASEAN諸国に秋波を送るようになった。オバマ政権期に、東南アジアのほとんどの国が数十年ぶりに米国大統領を迎えた。これ以降、米国は南シナ海沿岸国との安全保障分野における協力を加速させた。
日本でも、東南アジア重視の外交政策へのシフトが起きた。第二次安倍政権が発足して最初の訪問国はベトナム、タイ、インドネシアだった。その後も、安倍首相と岸田外務大臣(当時)がASEAN10カ国を早々に訪問した。
一方で、中国も同様に東南アジアへの関与を強めた。ウィリアム&マリー大学のAidData’s Global Chinese Development Finance Datasetにもとづく2021年の報告書によれば、2000年から2017年の間に中国からのODAを受け入れた上位25カ国の中には、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、ベトナムなどが入っている。
他方で、中国はOOF(Other Official Flows)というODAの基準に達しない政府資金を、ODAよりも大きな規模で供与している。OOFの上位25位以内にはインドネシア、ベトナム、ラオス、マレーシア、カンボジア、ミャンマーがランクインしており、中国の援助受け入れ国として東南アジアが重視されていることがわかる。
また、ASEAN諸国の要人との往来頻度を日中で比較した場合、ほとんどの国で中国との往来数のほうが多い。メディアを通して、日本の首相が東南アジアの要人と会っているニュースを頻繁に耳にするようになったが、中国は日本以上の頻度で活発に交流している。
ただし、例外はフィリピンとミャンマーである。フィリピンでマルコス政権が発足して以来、南シナ海を巡って中国との対立が続いており、大臣級以上の会談の頻度は前政権とは比べ物にならないくらい低い。一方、日本とフィリピンの安保協力はマルコス政権のもとで加速した。
ミャンマーに関しては2021年のクーデター以降、中国が正大臣を送ることも受け入れることも控えている。中国が国際世論のリピテーションを気にしているからだと考えられるが、官僚レベルの会合は頻繁に開催している。
東南アジアを巡る主流の問い—「米中の間でどう振る舞うか?」
大国間競争が国際政治において決定的な構造とみなされるなかで、日米や中国は東南アジアに対して働きかけを活発に行っている。デイビッド・シャンボーは著書の中で「2つの大国の間で東南アジア諸国はどう舵取りをするのか」という問いを投げかけている。この問いは過去十数年間、安全保障サークルや研究者の間でトレンドとなっている。
この問いに対しての一般的な答えは、中小国は自国の規模、エリートの中国に対する距離感や恐怖心、あるいは経済的紐帯などを考慮して、「ヘッジング」「アコモデーション」「ソフトバランシング」「バランシング」「リスキフィケーション」を選択するというのが主流の答えである。シャンボーは著書の中で、米中を両極としてASEAN10カ国がどちら寄りであるか、わかりやすく明示している。彼の表によれば、全体的に中国寄りの国が多い。
これは複雑な現実を単純化した見方であり、日本でも浸透しているように見える。さらに単純化して、「東南アジアには権威主義国家が多いから、中国に親近感を感じる」という論調さえ耳にすることがある。ここまでくると、もはや客観的な事実に反している。
東南アジアに権威主義的国家が多いのは事実である。社会主義のベトナムとラオスには野党が存在しない。カンボジアでは政府が野党を解散させたので事実上の一党独裁である。ミャンマーでは軍事政権と反政府勢力の間で内戦が続いている。
インドネシアとフィリピンは、長らく選挙民主主義に分類されていた。しかし、ジョコ政権とドゥテルテ政権が法律や大統領令によって言論の自由や結社の自由を制限したことから、選挙権威主義に分類されるようになった。
シンガポールでは独立以来、与党の人民行動党が政権を握っており、言論の自由、結社の自由、情報の自由が制限されている。最近はデジタル社会に対応した言論統制を実施している。しかし、このような権威主義体制のシンガポールは、ウクライナ戦争を巡る対ロシア経済制裁を早々に実施した。「権威主義だから中露寄り」という単純な構図は現状認識を歪めてしまう。
2.競争の最前線からみる東南アジア
米国のデリスキングと各国の政策
トランプ政権は追加関税措置の導入や輸出入管理、投資や金融規制の強化を行った。輸出管理改革法が2018年8月に成立して以降、中国の通信機器、通信業者、半導体メーカー、建設業者などがエンティティリスト入りした。
エンティティリストの対象は米国の国家安全保障、もしくは外交上の利益に反する活動を行っている企業や個人である。東南アジアでリスト入りしている組織の数(2023年末時点)の上位3カ国をあげると、マレーシア(45)、シンガポール(32)、タイ(9)である。一方でトランプ政権がデカップリングを始めてからリスト入りした数はマレーシア(2)、シンガポール(10)、タイ(3)である。このことから、東南アジアの法人も規制対象になってきたことがわかる。
2010年代の中頃までは「経済は中国、安保は米国」という線引きが容易だった。しかし、トランプ政権が経済安全保障を本格化させたことで、東南アジア諸国は経済と安保の狭間で厳しい選択を迫られるようになった。
たとえば、各国が5Gを導入するにあたって、主な選択肢はファーウェイあるいはノキア・エリクソンである。ファーウェイに関しては、同社の機器を使う国や組織の情報が中国共産党によって利用されるのではないかというリスクが問題視されてきた。
東南アジア諸国ではシンガポールがノキアのみを採用しているが、多くの国はファーウェイもノキアも使用している。ここでは、フィリピンとマレーシアにおける5G導入の経緯を紹介する。
フィリピンでは、4つの企業(Globe,Smart,Dito,Now Telecomm)が5Gを提供している。Globeはノキア、Smartはノキアとファーウェイ、Ditoはファーウェイ、Now Telecommはノキアと提携している。
Globeは通信大手で、2019年にファーウェイと合意を交わしたが、米国の圧力を受けて上院公聴会が行われた後にノキアに切り替えた。Smartは二社と提携しているが、実際はファーウェイで提供している。
Ditoはドゥテルテ前大統領が訪中時に第三の通信事業者の設立について習近平に提案した後に作られた。設立者はデニス・ウィというダバオ出身の華人ビジネスマンで、ドゥテルテ前大統領が選挙に出る時に資金提供している。Ditoは2020年9月にフィリピン軍基地内に通信基地を建設すると発表し、2021年3月にはファーウェイの機器を使用すると表明した。
Now Telecommは第四のプレーヤーで、メル・ベラルデが2020年に設立した。彼はフィリピンの勝訴となった仲裁裁判所の判決で決定打となった地図を、ロンドンのオークションで落札した人物である。ベラルデは2023年にハリス副大統領からノキア技術による5Gネットワーク支援の約束を取り付けた。
以上の経緯からわかるように、フィリピンがファーウェイとノキアの両方を使っている理由は、企業による分権的な決定の結果でしかない。「米中の間でどう立ち振る舞うか」という政府による合理的計算などは見当たらず、むしろ政府は全体をコントロールできていない。
マレーシアでは、マハティール首相がファーウェイ採用を決定していたが、2019年に米国からの圧力を受けた。マハティールは「技術水準や価格の面で、中国には比較優位がある」と述べ、押し切ろうとした。政府はナショナル5Gタスクフォースを立ち上げて専門家を招集したが、そこに安保の専門家は一人も呼ばれなかった。
しかし2021年7月には政府は一転し、エリクソンによる5G導入を発表した。合わせて、財務省所有の企業が設立され、ここが5Gのインフラやすべてのスペクトルを独占することも決定した。価格の高さや透明性の欠如により、民間事業者や野党議員は強く反発した。
その後はアンワール現首相が透明性の欠如を理由に5G導入の見直しを発表して、ファーフェイ採用の可能性にも言及した。他方、民間のCelcomはファーウェイとの契約を独自に進めている。2024年6月の時点で、政府の方針は何も決定していない。
5G導入にあたって、マレーシアでは5Gネットワークの独占を巡る対立が展開しているだけで、安全保障を巡る積極的な議論などはほとんど見られない。フィリピン同様、マレーシア政府が米中の間で合理的に選択するという現実は見られない。
ウクライナ戦争を巡る投票行動
ウクライナ戦争を巡って、国連総会では6本の決議が採択された。東南アジア11カ国の投票行動を比べてみたい。
6本全てに賛成したのはミャンマーとフィリピンの2カ国である。ミャンマーはすべての決議で共同提案国にもなっているが、例外的な事例である。軍事政権以前のNLD政権時に任命された国連大使が本国の指示を無視して投票しているからだ。賛成5回・棄権1回というのが東チモールとシンガポールである。
ベトナムとラオスは賛成ゼロ・反対1回・棄権5回である。ストックホルム国際平和研究所のデータ(TIV:2010年〜2022年)によれば、各国において武器輸入に占めるロシアの割合がベトナムで80%、ラオスで52%である。この二カ国に関しては武器調達でロシアに依存しているためにロシアに配慮した投票行動だったようにも見える。
しかし、インドネシアも武器調達の11%をロシアに依存しているので決して小さな数字ではないが、投票は賛成3回・棄権3回なので、ロシアに配慮したとは考えにくい。逆にタイは武器調達で最もウクライナに依存している(15%)が、賛成2回・棄権4回のように、ウクライナに配慮しているわけではない。
経済関係に目を向けてみると、各国の輸出入総額に占めるロシア・ウクライナの割合は1%に満たない。ブルネイだけは例外でロシアから原油を輸入しているが、投票では賛成2回・棄権4回である。
また中国は東南アジアで経済的に圧倒的な存在感をもっているが、6本の決議に関して中国と全く同じ投票行動をした国はいなかった。
行動は同じだが「意図」は違う
東南アジアを含めたグローバルサウスという国々の外交行動を理解する際に、武器調達や貿易の依存度を説明の枠組みとして用いることがある。経済的な動機が外交行動を決定するという考え方は「合理的な国家」という概念を前提にしており、客観的な事実から行為者の動機を推論するのは昨今の国際政治理論の主流である。
しかしマックス・ウェーバーが述べたように、行為者がその行為に与えている意味を理解することがより重要であり、客観的な事実の観察だけでは現実を理解する上で不十分である。
文化人類学の大家であるクリフォード・ギアスはまばたき(ウィンク)を例に、行為の背後にある意図の重要性を説明した。ある人は合図としてウィンクをする。別の人はチック症の症状として、非自発的にウィンクをしてしまう。また別の人は、そのチック症の人をバカにしてウィンクを真似している。更に別の人は、左目のウィンクがうまくいかないからと、ウィンクの練習をしている。現象としてみれば4人全員がウィンクをしているが、ウィンクをしている理由・意図は全く違う。
「行動は同じだが意図は違う」という事例は、ウクライナ戦争における対ロシア制裁でも見られた。
シンガポールは非常に早い段階でロシアの銀行4行の資産を凍結し、軍事運用される可能性のある物品の輸出も禁止した。行動はG7+と同じだったということができる。しかし、意図の部分において、シンガポールは米国を暗に批判した。
バイデン大統領は対ロシア制裁にあたり、「自由を守るために戦う」と議会で語った。一方、リー・シェンロン首相は「我々はウクライナの問題を民主主義対独裁という戦いで捉えてはいけない。この捉え方では、自動的に中国はロシア側となってしまうからだ」という旨を語っている。
同じことはウクライナ戦争を巡る国連総会の議決にもあてはまる。我々は投票行動の背後にある各国の意図に注目すべきである。以下に、東南アジア諸国がウクライナ戦争に関連して国連で語った内容を紹介する。
タイは、「国連は本来多国間主義の組織であるにも関わらず、複雑な状況を善と悪の二項対立で単純化し、透明性、中立性、包括性を欠く組織になりつつある」と述べて、いくつかの議決を棄権した。
ロシアの人権委員会メンバーシップ停止に関する決議においては、シンガポールとマレーシアは「国連人権委員会による独立の調査を実施し、ロシアによる人権侵害の状況について客観的な証拠が出てきてから議論すべきであり、国連総会の場で決議を通すべきではない」と主張したうえで棄権した。
インドネシアは「ウクライナであれ、パレスチナであれ、それ以外の地域についてであれ、紛争状況に対して、ダブルスタンダードを適用すべきではない」(*23年10月のガザ危機勃発以前の発言)と主張した。つまり「イスラエルの武力行使には沈黙、ロシアのウクライナ侵攻には非難轟々」という西側諸国のダブルスタンダードを批判した。
ラオスやベトナムは冷戦中に代理戦争の舞台となった国々として、大国間戦争に巻き込まれる悲惨さについて語った。
東南アジアは経済発展が著しく、主要都市はまさにグローバルシティばかりである。しかし、植民地支配で受けた傷は決して癒えておらず、多国間主義が侵害されることに敏感である。国家建設の歴史、成功体験や失敗体験をふまえた世界観ともいうべきものを、各国が持っている。6本の決議に関する東南アジア諸国の投票行動を、経済や武器調達といった構造要因からのみ説明しようとするのは、このような視点を軽視した見方である。
南シナ海問題におけるマレーシアの政策転換(ブレ)
最後に、「米中の間でどう振る舞うか」という政府の合理的計算とかけ離れた事例として、マレーシアの南シナ海問題への対応について紹介する。
オバマ米国大統領がリバランス政策を表明した際、マレーシアはすぐに支持を表明した。その後、米軍との共同軍事演習が増加し、航行の自由作戦への支持も表明した。米国との安保協力を進める一方で、中国との安保協力も緩やかに前進させた。マレーシアは米中の両国との良好な関係構築に努めていた。
しかし、この風向きは2016年に突如として変わってしまった。仲裁裁判所が同年7月にフィリピンの全面勝訴の判断を下した直後、マレーシア外務省は裁定について「留意する」という弱い声明を発表した。同年9月にはナジブ首相が中国を訪問した際に「(仲裁裁判は)フィリピンの一方的な手続きによるもので、強制するメカニズムはない」と述べた。さらにナジブは同年11月に「南シナ海に非当事国が関与することは非生産的である。問題解決は二国間で行うべき」、「大国は小国を公正に扱うべき」、「第二次世界大戦の戦勝国に牛耳られてきた国際秩序を修正すべき」といった趣旨の意見を、中国の新聞に論説として掲載した。ナジブの主張は米国を批判する中国の論調に合致していた。
一方で、同年12月に当時の国防大臣は「アメリカは当事者である」と述べ、南シナ海に展開中の米艦船にヘリコプターで着陸するというパフォーマンスを披露した。このように、他の閣僚や与党議員たちも南シナ海でエスカレートする中国の行動に懸念をもっていたが、次第に沈黙を余儀なくされるようになった。
2018年の選挙でナジブが下野した後、国会では南シナ海問題における議論が再び活発になり、南シナ海におけるマレーシアの権利を国連で主張するようになった。
以上のように、マレーシアの外交政策は2016年に大きくブレたが、この背景にはナジブ個人の問題があった。中国は経済的窮地に陥っていたナジブに多額の援助を提供し、対外政策に影響を与えることに成功した。
ナジブは2009年に首相になり、1MDB(マレーシア開発公社)という政府系の投資会社を設立した。1MDBはマレーシアを中所得国の罠から引き上げることを目的とした組織だったが、2014年頃から深刻な債務問題や資金流用疑惑を抱えるようになった。2015年7月には1MDB関連会社からナジブ個人の銀行口座への26億リンギの送金疑惑が浮上した。一連の不祥事に対して、与野党の議員や記者・弁護士らが情報公開を求めたが、ナジブは逮捕や党籍剥奪で応酬した。
このとき、ナジブに手を差し伸べたのが中国だった。李克強首相が2015年11月にマレーシアを訪問し、両国は中国によるマレーシア国債の買い増しと不採算事業となっていたエネルギー会社の買収などで合意した。2016年には東海岸鉄道やパイプラインプロジェクトの契約を交わした。予算を意図的に大きく見積もった分、ナジブはその一部を1MDBの返済に回した。
マレーシアの外交政策の転換(ブレ)は米中競争下における合理な判断ではなかった。マレーシアのように、首相の個別利益が国家の主権を優越するという状況は中小国ではしばしば見られる。このような国々には以下のような特徴があげられる。外交政策の決定権が首相・大統領に集中し、そのリーダーがメディアや議員による政府批判を封じ込める仕組み(メディアコントロール、党公認剥奪など)を持っており、かつリーダーの国内での権力がパトロネージの分配に依存している。ここでリーダーに資源を提供する大国が現れれば、国内政治のブレは現実的となる。こうした事態は、民主主義でも起こりえるもので、権威主義か否かは必ずしも重要な要素とはいえない。
3.東南アジア諸国を理解する視点
私たちが東南アジア諸国を理解する場合、以下の2点が重要である。
第一に、各国には歴史的に形成されてきた外交ドグマがある。ほとんどの国が大国に支配された歴史を持ち、大国への不信感と多国間主義への信頼を強く持っている。とくにムスリム・マジョリティの国では西欧的価値観に対する反発が強い。
余談だが、西欧的価値観との違いは南シナ海問題でも見られる。多くの東南アジア諸国は、自国の行動が国際秩序にどのような影響を与えるのかという発想をあまりしない。南シナ海の問題は法の支配に直結する問題であるが、東南アジア諸国からは中国の言動は既存の国際法秩序への挑戦であるという見方をあまり聞かない。
第二に、シンガポールを除く東南アジア諸国の国内政治は資金需要が高い。リーダーの不沈がパトロネージの分配に依存し、外交政策過程がリーダーに集中している場合には、外交はリーダーが利用可能な資金の問題に直結する。ナジブのように中国のシャープパワーが効いてしまえば、外交政策が180度変わりうる。
最後に、以上を踏まえた上で東南アジア諸国が中国寄りだと言われる理由を紹介する。
まず、東南アジア諸国の外交ドグマは、国際秩序を修正すべきという中国が発するメッセージと親和性が高い。「自由民主主義を押し付けるな」「国際社会を大国が牛耳るな」という中国の主張には、東南アジア諸国も概して賛同している。
また、中国の資金供給には透明性が求められないため、腐敗したリーダーが国益よりも個別利益を優先して中国にすり寄ることがある。
一方で、中国がたゆまぬ外交努力をしていることも理解しておく必要がある。中国の大使館関係者が研究所を訪ねることがあると聞く。そこの研究員が持っている情報やネットワークが有益だと判断すれば、彼の家族の誕生日にプレゼントを送るということまでやるのが中国である。中国の地道な外交努力を軽視してはいけない。
(2024年6月21日に開催されたIPP政策研究会における発題内容を整理して掲載)