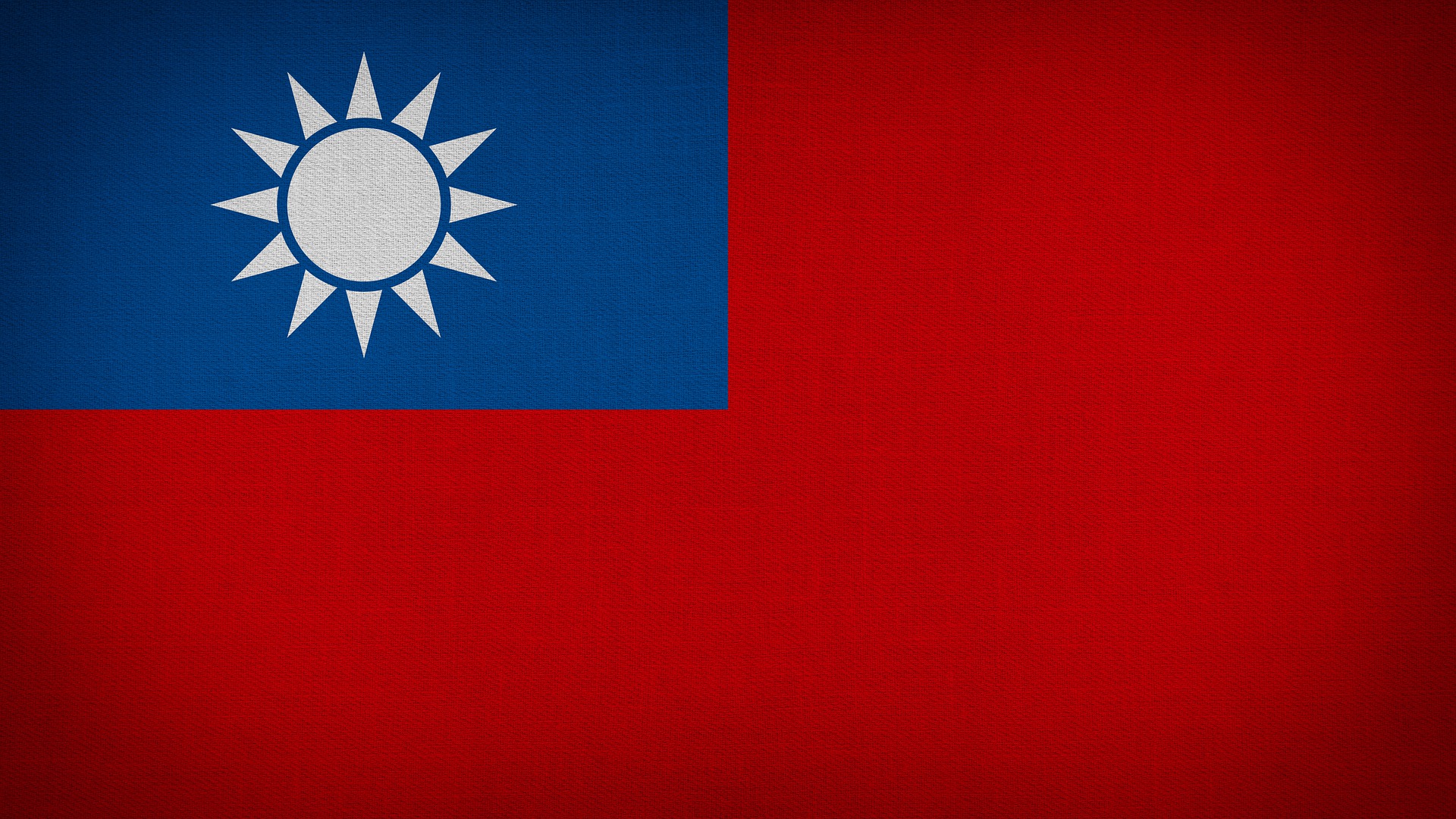2022年10月、中国共産党第20回全国代表者大会(20大)および第20期一中全会が開催され、新たな中央委員会委員などが選出され、第3期習近平政権がスタートした。とくに政治局常務委員人事で習近平は、68歳定年という党内不文律を破った人事処置を行い、自らに近い李強、蔡奇などを新たに任じて、「習近平一強体制」を印象付けた。
そこで、激変する国際環境の中で、新たに出発した習近平政権の特徴を確認したうえで、今後の米中対立の行方を展望しながら、日本の対中戦略について考察する。
1.第20回中国共産党大会の特徴
開催前から予想されていた通り、今回の共産党大会では習近平の長期体制が公式に認められたことが最も重要な点である。ただし、習近平が掲げた目標とそれを実現するための方法に関して、習近平一人に任せていいのかという課題は残っている。というのも、当初予想されていた、個人崇拝の強化や二つの確立、習近平思想など習近平専政体制を容認する文言が、党規約の改正において盛り込まれなかったことからも窺われる。
これまで習近平政権が維持してきたゼロ・コロナ政策について、最近不満が高まり、緩和を求める声が全国に広がる中、上海では「共産党退陣せよ」「習近平退陣せよ」といった共産党独裁制批判まで現れた。このような抗議の声が出たのは初めてで、習近平としても大きな衝撃を受けたと思う。
また今回の党大会では、台湾に対する武力行使に関して初めて「文字化」された。習近平による口頭での政治報告(党中央委員会報告)の中には、台湾への「武力行使」という言葉はなかったが、その政治報告全文の中には「台湾に対する武力行使」が明確に記されていた(注1)。
表現的には、西側にも配慮して、「『平和統一、一国二制度』の方針は両岸の統一を実現する最善の方法」だとしつつも、(台湾問題は中国にとっての核心的利益であるから)「われわれは、最大の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的な統一の未来を実現しようとしているが、決して武力行使を放棄せずあらゆる必要な措置をとるという選択肢を残す」と述べた。
中国の歴代政権は、台湾に対する武力行使に踏み切るに当たって、次の三つの条件を挙げている。
①台湾が独立を主張した場合
②外国軍隊が台湾を助け、(内政)干渉した場合
③台湾で大混乱が発生し、台湾の警察権だけでは収拾不可能な場合
しかし、政策として武力でもって台湾統一を図ることも辞さないと明確に述べたのは、習近平が初めてであった。この意味でも、習近平が長期政権の基盤を固め、台湾への武力行使を明記しながら、国内外に方針を明示したといえる。
そのほか、昨今の中国経済が(ゼロ・コロナ政策によって)芳しくない現状を直視しながら、国民と政府は運命共同体だと唱え、国民にアピールしている点も、今回の特徴と言える。共産党体制のもと、今後も経済運営がうまくいくのかという点については、楽観できない。
2.習近平政権の権力基盤
習近平政権は、どのようにして権力基盤を固めて来たのだろうか。
まず、「虎もハエも同時に叩く」というスローガンに見られるように、大物幹部も例外なく、共産党の汚職腐敗の撲滅に向けて力を注いだ。
革命により人民中国を建国させたことを共産党支配の正統性の根拠として中国は、共産党独裁体制を築いてきた。その体制は、特権階級(9000万人の共産党員)が14億の人民の上にあぐらをかいている構図だ。共産党は5年ごとに党大会を開催し、中央委員を選び、その中から政治局員が選出され、その上に党総書記政治局常務委員7名が立つ巨大なピラミッド構造となっている。
鄧小平は、(毛沢東時代の失敗に鑑み)政治局常務委員の集団指導制をつくり、それ以来、その方針にもとづき政治運営がなされてきた。しかし習近平は、第1・第2期までの間は、政治常務委員に共青団のメンバーが多数を占めていたことから、さまざまな領導小組(委員会)をつくり、そのトップを自らが兼任して自分の考えに沿った素案を準備し、それを政治常務委員会にかけて追認させる仕組みを整えながら、独裁体制を着々と準備してきた。
今回の党大会で7人の政治局常務委員のうち、李克強・首相(67)、栗戦書・全人代常務委員長(72)、汪洋・全国政治協商首席(67)、韓正・副首相(68)の4人が退任となった。党幹部定年68歳に達していなかった、李克強、汪洋も退任となった。
李克強は、共産党青年団(共青団)に属しており、習近平とは立場を異にしていた。共青団は7000〜8000万人おり、中央政府・地方政府などあらゆる組織の中の中枢部に配置されていて、共産党内では強力なパワーを持つ集団だ。ところが、党大会での胡錦涛元主席の退場劇や今回の人事に象徴されるように、共産党組織の中で重要な位置を占めていた人々が、最高権力機関の中で少数派になってしまった。
このようにすっきりしない問題を内在させたまま、第3期習近平体制がスタートしたのである。
3.米中対立の行方
今後も米中対立状況は、緩和することはないと思う。バイデン政権は、中国を「最大の競争相手」と位置付けている。ただ、「最大の敵」とは表現していないところをみると、バイデン政権は中国と本格的な戦争をしようというつもりはないということだろう。
一方、中国はどう見ているか。
第二次世界大戦後、米国は圧倒的な経済力と軍事力を背景に、「世界の警察官」として世界の共通ルール形成に主導的役割を果たしてきた。それゆえ欧米諸国は、(世界の国々は)世界共通の秩序・ルールに従うのが当然だというわけだが、中国の立場からすると、そのルールは「窮屈だ」というのである。つまり(欧米諸国の価値観やルールとは)違った(中国のような)価値観やルールもあるのに、それを無視することは内政干渉だと見る。そして中国は、その秩序・ルールに同意したわけでもなく、それを押し付けられるのは困るという。逆に力を持てば、その秩序・ルールを破ってもいいという感覚がある。これが、米中間における根本的な価値観の相違である。
世界の超大国米国とそれに追いつこうとする中国との関係について「トゥキュディデスの罠」と言われることがよくある。米国の立場から言うと、(追随する中国にいつ追い抜かれるかという)一種の「不安」がある。第二次世界大戦後、米国は世界の覇権国・超大国として世界をリードしてきたが、それが脅かされており、それは米国にとって耐えられないような思いにもつながっているのではないか。バイデン政権は「中国は最大の競争相手」とは言っているが、実質的に中国は米国にとっての「最大の敵」といえる。
中国は2001年12月にWTOに加盟したが、その自由貿易の恩恵を最も受けた結果、世界一の貿易量を誇る国になった。その過程で中国は、「世界の工場」となるために、世界の先端技術を「ぱくって」いった。その一つが、5Gの実用化、半導体技術などの先端情報技術であった。しかし、のちになってそのことに気づいた米国を中心とする西側は、それを阻止すべく中国に対抗するようになった。
現在の中国の技術力は、基盤となる基礎研究体制は別にして、量子通信を実現させるなど相当高いレベルに達している。欧米諸国のように基礎研究の上に建てられた科学技術ではないが、それをあなどることはできない。
そこで米国は、先端技術を中心としたサプライチェーンを分断するデカップリングを進めようとしている。しかし中国は中国で、そうした対応にもめげずに、うまく立ち回ろうとしている。例えば、中国に入ってくる欧米の企業に対して中国政府は、中国企業と合弁会社をつくって事業を展開させ、そこから先端技術を入手していく。
このように米中関係は、世界の覇権をめぐって争っており、その戦いに決着がつくまでは対立の激化は継続することだろう。
4.中国の脅威の本質とは
中国は、建国100周年である2049年までに、世界の最前列に立つことを最終目標に掲げている。米国をも脅かすほどに大きくなった中国だが、2022年12月に岸田政権が閣議決定した「安保3文書」で「これまでにない最大の戦略的挑戦」と記された中国の脅威についてどう考えたらよいだろうか。
(1)強大な軍事力
一般に、脅威は<脅威=能力×意図>として表される。
能力の分野で見ると中国は、すでに科学技術の高度化により優れた武器を生産し備えている。とくに核戦力の中距離弾道弾については、米露両大国がINFで中距離弾道弾相互に削減する中で、中国の独占状態といってもいい。射程距離でみると、米国まで届くICBMはほどほど保有しているものの、中国はこれに注力しているわけではない。その代わり、射程距離500〜5500キロの(グアムを射程距離内に収める)中距離弾道弾を増強しており、米国本土ではなく(日本、在日米軍基地など)周辺国に対する大きな脅威となっている。米国にとっては、それらは直接的な脅威でないので、日本など周辺国の感じる脅威感とはずれが生じやすい。
海軍力について、東アジア地域の海洋に展開している米海軍と中国海軍を比較すると、艦艇や潜水艦の数では中国が上回っている。これだけの軍事的な能力を有している中国は、その意図次第で極めて大きな脅威になると見ざるを得ない。
(2)「力」への強い執着心
次に、意図について考えてみよう。これまで中国が、日本に対して攻撃の「気配」を見せたことはなかった。もし中国の指導者が、追い詰められれば、一気に攻撃の「意図」を持つことも十分あり得る。というのは、中国の世界に対する影響力、支配欲に関しては、近代に半植民地化された不幸な歴史体験があったからだ。
中国の歴史は、分裂と統合の繰り返しであった。統合して大きな勢力をもつ王朝が現れても、何百年かすると混乱をきたして、また群雄割拠し、その中から力の強い者が現れ、再び統一をするという歴史の反復であった。それゆえ中国人にとっては、力が強ければ何でもできるという思考の遺伝子が形成されてきた。
一方、ヨーロッパは中世時代の後の王権時代に宗教戦争を経験しながら、17世紀にウェストファリア体制が形成され、本格的な主権国家の時代を迎えた。その基本は、国の大きさにかかわらず、各国の主権は尊重され、国境線は守るべきで、自衛のための戦争は認めるが侵略戦争は認めないという考え方である。日本は、近代史においてはそのような考え方に追いつかず大陸を侵略したりしたものの、少なくとも第二次世界大戦後は、欧米諸国と同じ近代国民国家の考え方に従って歩んできた。
ところが中国には、これまでウェストファリア体制に基づく近代国家の経験がなかった。中国の歴史的経験からすると、力があるものは拡大していくという考え方が基本であった。しかしアヘン戦争など、西欧列強(日本を含む)のアジア進出により中国(清朝)は(半)植民地化され、塗炭の苦しみを味わう近代史を経験することとなった。
その結論として、中国人は力がなければ(強者に)やられてしまうという教訓を骨身にしみたのであった。逆に言えば、力さえ持てば大きく出ていけるという思い込みがある。中国人の潜在意識の根底には、そのような意識があって、それがさまざまな場面に表れてくる。例えば、尖閣諸島や南シナ海へ進出であり、自分たちの主張が通るまで力を発揮して推し進めていく。
このように、欧米諸国が近代国民国家体制の中でもってきた考え方とは違った考え方で運営されている国家が中国だということであり、これはわれわれにとっての「脅威」になると思う。しかも、そのような考え方で運営されている中国が、すでに世界一流の高度な武器を備えているのである。
(3)宇宙覇権をめぐる争い
ところで、米国が世界最強国と言われることの一つに、宇宙を一手に握っていることが挙げられる。米国はさまざまな偵察衛星を周回させながら、地上の細かい情報まで把握して、世界戦略を展開している。例えば、北朝鮮におけるミサイル発射の動向把握、ウクライナ戦争におけるさまざまなロシアの動きなど、宇宙から偵察し情報を把握し分析している。それゆえ現在の覇権争いは、宇宙をめぐる争いという側面が顕著になりつつある。
国際宇宙ステーション(ISS)は、1988年に日米欧の政府間協定によってスタートし、現在は、米国、ロシア、日本、欧州、カナダなどが15カ国参加する多国籍共同プロジェクトである(ウクライナ戦争によりロシアは、24年以降撤退すると表明。また2022年1月にステーションの運用許可が2030年まで延長された)。
中国はISSへの参加を拒否し、独自の宇宙ステーション建設に取り組んでいる。中国の天宮計画で運用中の「天宮号宇宙ステーション」は、2021年4月に開始され、2022年中に建設が完成するとされている。
電磁波空間、サイバー空間などにおいても中国の技術力はかなり高度化している。それに加えて中国は、平時において、いわゆる「三戦(心理戦、世論戦、法律戦)」を展開しながら自国に有利な環境を造成しつつある。中国の脅威は、物理的破壊力を持つ戦力のみならず、人間の心理の中にまで食い込みつつある。
5.日本の対中戦略
(1)国益を重視したうまい「立ち回り」
日本は、自分の立ち位置を十分理解することがまず必要であろう。日本列島は、ユーラシア大陸から海洋に出ていこうとする大陸国家(中国、ロシア)に対して、大きく手を広げて阻んでいるような地形になっている。この地政学的条件を考えると、中国やロシアにとって日本(列島)は、邪魔な存在と映る。
また日本一国で、日本国土と近海を防衛するには限界がある。日本の防衛は、日米同盟に依拠することを基本としている。昨今議論されている防衛費のGDP2%をつぎ込んだとしても、日本国だけで防衛の役割を十分果たすことは難しい。
一方、経済面では中国のマーケットに大きく依存している。よく考えてみると、中国の巨大な市場は、日本による長年の対中ODAによってつくられたマーケットともいえる。その中国市場には、欧米をはじめ世界が進出しているが、日本は米国への気兼ねから、中国とのかかわりに躊躇する面もある。このバランスをどうするかを考慮しながら、防衛を考える必要がある。
中国を見る見方として、中国の人権弾圧、傍若無人な海洋進出などを感情的に反応するのではなく、中国市場あっての日本の経済という側面がある以上、「賢く、うまく立ち回る」必要がある。とくに非常に難しいのが対米関係のかじ取りだ。中国に言いがかりをつけられない形で、柔軟に対応しながらも、同盟国米国の核の傘はしっかりと確保しておくという基本姿勢である。
ただ言えることは、単純に「中国悪玉論」で済む話ではないということ。米中関係の間を日本がうまく取り持つということが、日本の安全保障(国益)にも役立つのではないだろうか。
(2)多国間枠組みとしてのインド太平洋構想
昨今、「アジア版NATO」という話もよく聞くが、日本は海洋国家に徹して、インドやオーストラリアなど含めたインド太平洋構想という枠組みの中で、中国の暴発を「静かに」抑え込んでいくことが重要だと思う。インド太平洋構想やクワッドは、将来、アジアのNATOになりうるのではないかと思う。
ただし感情的な「中国敵視政策」は問題がある。米国が対中強硬策を主張しても、それにYesと頷きながらも、日本の国益を踏まえて外交的にこうしたらさらによいと進言するような外交を展開したらよいのでへないか。
今一番大事なことは、国民が安全保障に関する考え方を深めて目覚めることである。日本は天然資源に乏しく、人口過剰な条件にあるので、経済面では中国とはうまく立ち振る舞うという賢さを持った姿勢もないといけない。その点で、感情的に反中感情を表に露わに訴えて防衛力強化を主張するのではなく、大言壮語しなくても国民がしっかり理解できるような方法で知らせて理解してもらいながら進めていくことが重要と考える。
(3)台湾有事・台湾危機への対処
「台湾有事は日本有事」という言説はその通りだ。南西諸島は台湾の近距離にあるわけで、台湾が有事になった場合、南西諸島を含め日本がその紛争に巻き込まれないという保証はない。
ただ、よく理解しておくべき点がいくつかある。日中国交正常化にあって日本は、「中華人民共和国政府が唯一の合法政府であることを承認」したので、それを大前提として対中政策を考えないといけない(注2)。
一方、米国は、米中国交正常化に際して、「中国は一つである」と認めつつも、「平和的解決をすべき」との条件を付けた(注3)。その条件をもって、米国は台湾に武器を売ることができ、中国(北京政府)による武力行使による台湾統一には反対するとはっきり主張できるのである。しかし日本は、そのような条件を付けなかった。
米国のように条件を付けない平和条約を結んだ日本が、台湾に対する中国の武力行使に口出しをすることは容易ではない。しかし米国は、台湾に武器などを売るだけではなく、周辺海域での自由航行作戦を展開しながら、中国に対しては「米国の基本姿勢(=「中国はただ一つ」)は変わらない」と「見え見えのウソ」を述べている。つまり「中台が一つにまとまるに際しては、あくまでも平和的手段によってまとまるべきだと念を押す。しかしそれに違反すれば、米国としては対抗措置を講じざるを得ない」というのである。
バイデン大統領が2022年5月に訪日したとき、記者から「台湾を守るため軍事的に関与する意思があるか」と問われ、「イエス、それがわれわれの責任だ」と即答した。米歴代政権は、有事の際の対応を明確にしない「戦略的曖昧さ」戦略を取ってきたのに、バイデン大統領が踏み込んだ発言をしたが、そのあと、ホワイトハウス当局者は、「われわれの政策に変更はない。大統領は、台湾海峡の平和と安定に関するわれわれの責任を強調した」と説明した。このような巧みな対応を日本も参考にしたらよいのではないか。
それでは「中台統一は平和的でなければならない」という文言を共同声明に入れなかった日本の場合、台湾有事に関して主張するにはどうするか。南西諸島は日本の領土であり、排他的水域にミサイルに打ち込まれては困るという主張はよいのではないか。
(4)ウクライナ戦争の影響
中国は、ウクライナ戦争後のロシアの状況、つまりウクライナ戦争をしたことでロシアは欧米諸国からの経済制裁を受けたが、それを注視している。中国の現在の悩みは、ゼロ・コロナ政策を緩和した後、感染が急激に増えてどうなるかという点とともに、それとも関連して中国経済の落ち込みである。
中国は、2022年度のGDP成長率の目標を5.5%に掲げたが、第3四半期(7〜9月)の成長率は3.8%だった。経済成長をどう達成するかに関して、習近平は焦りがあると思う。台湾への軍事行動に出た場合、国際社会から厳しい経済制裁を受けとんでもないことになりかねないという予測も当然していると思う。
日本政府は、対ロシア制裁で、欧米と共に経済制裁に足並みをそろえつつも、石油・天然ガスプロジェクト「サハリン2」では制裁除外期間を設けて資源の輸入を可能にした。中国に対しても国益を踏まえた現実的な対応をやるべきではないか。
経済問題は、習近平政権にとって大きな課題だ。現在の中国の内外情勢を見ると、いい材料はない。長い将来を考えたときに、アフリカ諸国からの信頼を得られるか。国際社会から受けて厳しい状況にあるロシアの事例は、習近平にとっては大きな教訓ともなり得るので、中国の暴発を防ぐ抑止力になりうるのではないか。
中国が、現在のような経済大国になれたのには、WTO加盟による自由貿易と途上国条項による優遇の恩恵を受けた結果だ。中国の経済は、長所であると同時に、弱点でもあるわけで、そこをうまくついていくことで抑止力の効果を効かせることも一つの考え方である。
今日の社会はSNSなどの情報通信の発達により、国家が制御できない分野がでてきて、国家の力にも限界が見えている。かつて中越戦争(1979年)で中国軍はベトナムに侵攻したわけだが、陸続きの国への侵攻でありながら、うまくいかなかった。それ以来中国は、対外戦争はやっていない。
軍隊が海を渡って侵攻する場合、まず制空権を抑えなければならない。台湾軍をやっつけるには、海からは強襲上陸が必要だが、簡単ではない。米軍も第二次世界大戦の沖縄戦や硫黄島戦で強襲上陸にかなり苦労した。攻撃した側の方が、圧倒的に犠牲者が多い。中国が台湾侵攻するときに、どれほどの犠牲者を出すことに堪えられるかだ。ゼロ・コロナ政策に対しても抗議運動が起きた。いまはSNSなどを通じて、現場の情報が即座に伝わってしまう。
そのような情況を総合的に勘案したときに、中国による台湾有事はそう簡単には起きないのではないか。しかし、習近平が窮地に追い込まれたときには、台湾は無理でも澎湖島などに侵攻して、台湾解放の第1報を達成したと宣伝することもあり得る。そのような政治的利用の中での台湾有事がありうると思われる。
つまるところ国際安全保障の緊迫化を迎えて、日本は安全保障のため日米同盟への依存を強めながらも自衛力の充実に努め、小資源・島国の地勢からは経済的には中国市場も重要である。
米中関係激化のすう勢にあって、日本は対中国益は日米間で違いがある現実をふまえて、両大国間の過熱化を防ぐべく、外交を中心に安定した日米中関係構築の努力が重要になってくる。
(2022年12月13日、采訪内容を整理して掲載)
<参考>
注1)「中国共産党第20回全国代表者大会」における報告より抜粋(2022年10月16日、新華社HP)
一、過去5年の活動と新時代の10年の偉大な変革(抜粋)
「台湾独立」勢力による分裂活動と外部勢力による台湾の事柄への干渉というゆゆしき挑発を前に、われわれは徹底して分裂反対・干渉反対の重要な闘争を展開し、国家の主権と領土保全を守って「台湾独立」に反対するわれわれの確固たる決意と強大な能力を示し、祖国の完全統一を実現する戦略的主導権をいっそう強く握り、一つの中国を認める国際社会の枠組みをいっそう強固なものにした。国際情勢の急激な変化を前に、とりわけ外部からの威嚇、抑制、封鎖、極限の圧力を前に、われわれは国益を重視して国内政治を優先させることを堅持し、戦略的不動心を保ち、闘争精神を発揚し、強権を恐れないという確固たる意志を示し、闘争の中で国家の尊厳と核心的利益を守り、わが国の発展と安全の主導権をしっかりと握った。
十三、「一国二制度」を堅持・整備し、祖国の統一を推進する(抜粋)
台湾問題を解決して祖国の完全統一を実現することは、中国共産党の確固不動の歴史的任務であり、すべての中華民族の人々の共通の願いであり、中華民族の偉大な復興を実現する上での必然的要請である。新時代における党の台湾問題解決の基本方策の貫徹を堅持し、両岸関係の主導権と主動権をしっかりと握り、祖国統一の大業を揺るぐことなく推進する。
「平和的統一、一国二制度」の方針は両岸の統一を実現する最善の方式であり、両岸の同胞および中華民族にとって最も有利である。われわれは一つの中国の原則と「九二年コンセンサス」を堅持し、それを踏まえて、台湾の各党派、各業界、各階層人士と、両岸関係・国家統一について幅広く踏み込んで協議し、共同で両岸関係の平和的発展と祖国の平和的統一のプロセスを推進していく。広範な台湾同胞との連帯を堅持し、祖国を愛し統一を目指す台湾島内の人々を揺るぎなく支持し、共同で歴史的大勢を把握し、民族の大義を堅持し、「台湾独立」に断固反対し祖国統一を揺るぐことなく促進する。偉大な祖国は永遠に祖国を愛し統一を目指すすべての人々の強固な後ろ盾である。
両岸同胞は血のつながった「血は水よりも濃い」家族である。われわれは終始台湾同胞を尊重し思いやり、彼らに幸福をもたらしている。引き続き両岸の経済・文化の交流・協力を促進し、両岸の各分野の融合発展を深化させ、台湾同胞の福祉増進につながる制度と政策を充実させ、両岸がともに中華文化を発揚するよう推進し、両岸同胞の心の通い合いを促すことに力を注いでいく。
台湾は中国の台湾である。台湾問題の解決は中国人自身のことであるため、中国人自身で決めるべきである。われわれは、最大の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的統一の未来を実現しようとしているが、決して武力行使の放棄を約束せず、あらゆる必要な措置をとるという選択肢を残す。その対象は外部勢力からの干渉とごく尐数の「台湾独立」分裂勢力およびその分裂活動であり、決して広範な台湾同胞に向けたものではない。国家統一・民族復興という歴史の車輪は着々と前へ進んでおり、祖国の完全統一は必ず実現しなければならず、必ず実現できるのである。
注2)「日中共同声明」より抜粋(1972年9月29日)
二. 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三. 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
注3)「ニクソン大統領の訪中に関する米中共同声明」より抜粋(1972年2月27日)
米国側は次のように表明した。米国は,台湾海峡の両側のすべての中国人が,中国はただ一つであり,台湾は中国の一部分であると主張していることを認識している。米国政府は,この立場に異論をとなえない。米国政府は,中国人自らによる台湾問題の平和的解決についての米国政府の関心を再確認する。かかる展望を念頭におき,米国政府は,台湾から全ての米国軍隊と軍事施設を撤退ないし撤去するという最終目標を確認する。当面,米国政府は,この地域の緊張が緩和するにしたがい,台湾の米国軍隊と軍事施設を漸進的に減少させるであろう。