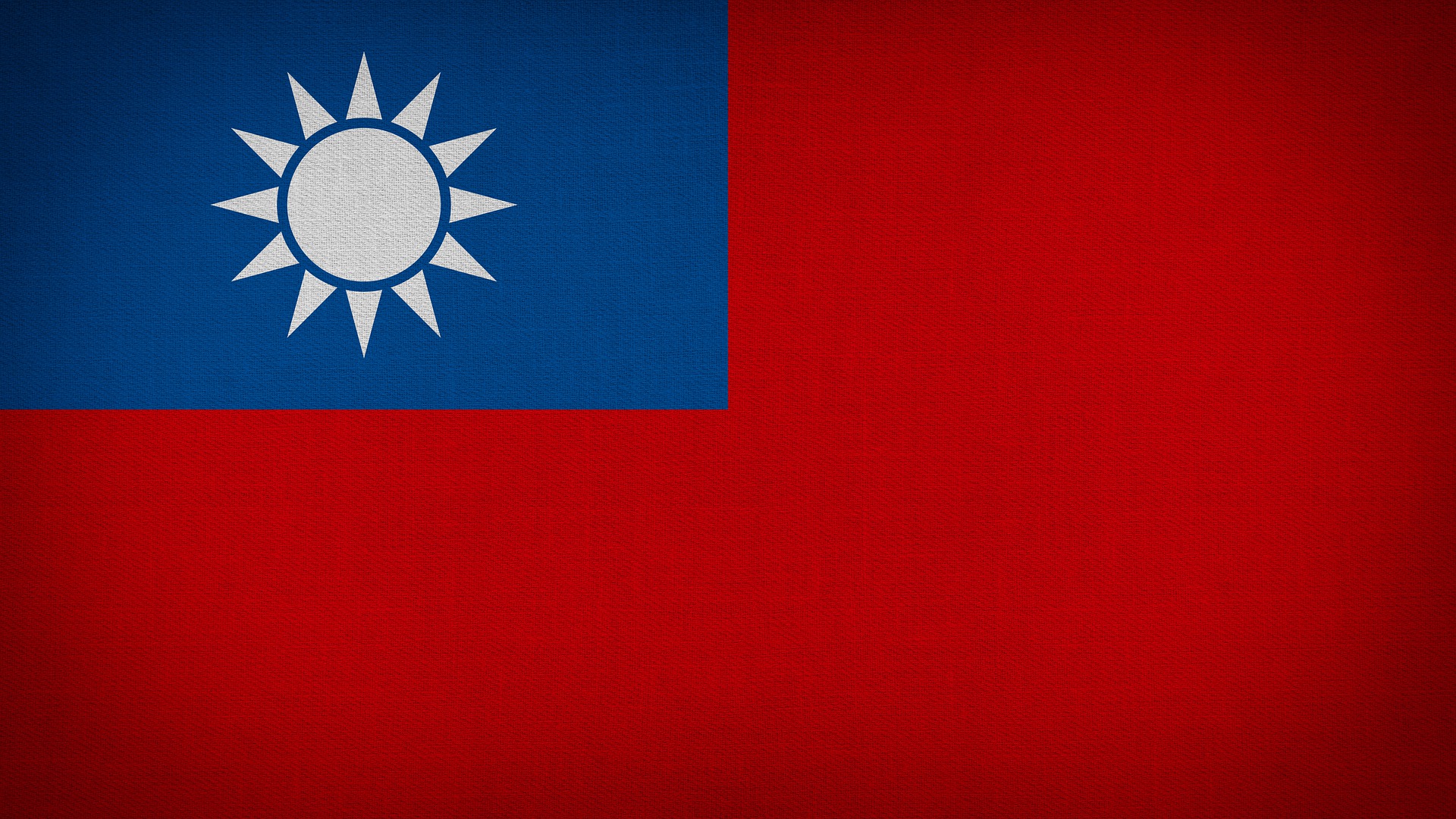はじめに
先の「台湾問題を考える(1):台湾問題の複雑さと曖昧さを理解する」で見たように、米中国交回復後もアメリカは台湾と友好的な政治経済関係を維持してはきたが、台湾が大陸中国から武力攻撃を受けた場合、台湾防衛のために米軍を投じるか否かについては明言を避け続けている。中国との国交正常化に伴い台湾と関係を断行した際、アメリカは国内法として台湾関係法を制定し、台湾防衛のための防衛的な兵器の供与は約しているが、台湾有事の際、台湾防衛のための軍事的コミットメント(米軍の介入)については「適切に対応する」と答えるにとどめ、実施の有無について明らかにしていない。
過去、台湾海峡を挟んで中国が台湾に対する大規模な軍事力の行使に出て、台湾が支配する離島を占拠、奪取し、あるいは台湾を恫喝し国際緊張を高めたことが三度ある。そこで、この三回の台湾海峡危機の際のアメリカの対応ぶりを振り返り、検証することによって、近い将来起きるのではないかと懸念されている台湾有事におけるアメリカの対処の姿を考察する際の参考としたい。
1.国民党政権の台湾移転
日本が第二次世界大戦で敗北するや、第二次国共合作は反古とされ、中国共産党と国民党政府との内戦が再開された。大戦末期、アメリカのローズベルト政権が採る対中政策は、蒋介石の国民党政権〈重慶政府〉を正式の中国政府と認め、これを通じて対中援助を行うが、中国共産党も含めた新たな統一政府を作るため斡旋の労をとる用意はあるというものであった。ローズベルト急死後、大統領に就任したトル−マンもこの考えを受け継ぎ、蒋を中心とした統一政権作りと内戦の回避を対中政策の基本とした。
しかし、大戦終了後、国共両党の間では戦後における政権構想や投降日本軍の受入れ手続き等をめぐって対立が絶えなかった。国共両党の休戦と統一促進をめざすトル−マン政権が斡旋に動いた結果、国民党の指導性を承認し、共産党独自の武装を放棄する代わり、政治協商会議という党派間協議の場を設けることで合意が成立した(双十協定)。だがその後も共産党と国民党の小競り合いは収束することなく、逆に対立は激化していった。
トルーマン大統領は1945年12月、国共双方の武力衝突の停止と中国の平和的統一を呼びかける大統領声明を発表するとともに、マーシャル将軍を大統領特使として中国に派遣した。ソ連の対中進出と中国の分裂という事態を避けるため、中国の民主化と早期統一を急がねばならないと判断したからである。このマ−シャルミッションは国共両派から信頼を得ることに成功、46年1月に一旦は国共停戦協定が成立する。しかしその後も両派の抗争は続き、軍事力による事態の解決をめざす將介石の国民党軍は東北部に進出し、7月以降共産党への全面攻撃に打って出た(国共内戦の再開・本格化)。
当時、国民党は米式装備の正規軍200万人を含む430万人の軍隊を指揮し、中国の全人民の7割を支配していた。これに対し中国共産党は120万人の兵力で、未だ人民の3割程度の支持を得ているに過ぎなかった。それゆえ、この3対1という彼我勢力比を踏まえ、蒋介石は3か月から半年で中共軍を撃滅できると判断したのである。
だが、数的な優勢にもかかわらず、その士気の低さから、マーシャル特使は国民党の勝利には懐疑的であった。事実、内戦当初は延安を制圧する(47年3月)など国民党は優位に戦闘を進めたものの、経済政策の失敗も加わり徐々に中共軍の前に後退を強いられるようになった。一方、中国共産党は46年5月の5・4指示(「土地問題に関する指示)によって、大地主の土地・財産を没収して貧農に与えるなど土地改革を進めることで農民の支持獲得に成功し、48年春以降戦局の巻き返しを図った。
こうした事態を踏まえ、トルーマン政権の内部では、蒋介石政権への支援打ち切りの意見が大勢を占めるようになり、中国内戦に本格介入する意志は既に失せていた。48年も後半に入ると、遼瀋、淮海、平津の三大戦役はいずれも中共軍が勝利を収め、旧満洲や中国の北部、東部を制圧。数的優勢を保っていた国民党軍も共産側への寝返りなど内部崩壊が進み、中共軍300万に対して国民党軍は290万に減少していた。そして49年1月中共軍は北京に無血入城を果たす。4月から5月にかけて南京と上海を占領した後、10月1日中華人民共和国の建国を宣言し、毛沢東が主席に就任した。
一方、台湾に逃れた蒋介石は中国大陸を統治する正当性が共産党ではなく国民党にあることを主張し、機が熟せば再び中国大陸に反攻し、自身が「正当な統治者」として復帰することを切望し、大陸沿岸に所在する島嶼や離島を大陸反攻の重要拠点と位置付けていた。しかし、1949年12月から1950年8月までの間に、舟山群島(上海付近)、海南島(広州・海南付近)、萬山群島(広州・澳門付近)等の離島が中共軍の攻撃を受けて次々と陥落、放棄を強いられた。
勢いづいた中共軍は、国民党政権(国府)に残された離島の大陳列島、南兜島、金門、馬祖への侵攻のみならず、台湾本島への侵攻準備も進めようとしていた。中国共産党は「台湾解放」(制圧)を実現する上で、まず厦門方面から金門を攻略し、同島に台湾本島侵攻のための部隊を台湾海峡へ展開させる拠点を築くことを企図していた。また過去に国府軍に敗戦した地である金門を攻略することは、中国共産党の名誉を回復するのみならず、国府にとっての象徴的かつ戦略的な拠点を奪う機会ともなり得るものであった。
そのような状況にも関わらず、国府は「半年整備、一年反攻、三年成功」という大陸反抗実施の目標を掲げ、残された離島(大陳列島、金門、馬祖など)や澎湖諸島、台湾本島の防衛態勢を整えつつ、一刻も早い大陸反攻を実現するための態勢を整えることを急務とした。
2.変転するアメリカの台湾政策
大陸における中国共産党の勝利が確実になったことをふまえ、米国務省は1949年8月に「中国白書」を発表し、アメリカの対中政策を次のように説明した。
「不幸にも避けることのできない事実は、中国における内戦の不吉な結果が、アメリカ政府の力の及ばないものであったということである。我が国が、できる限りの力で、何をしたところで、中国の内戦の結果を変えることはできなかったであろう。我が国がこれ以上貢献すべきことはもう何もない。それは、我が国が影響力を行使しようとしてもできなかった、中国内部の力関係の結果であった。」
国民党の敗北はアメリカの支援不足に問題があったからではなく、国民党内部にはびこる腐敗が原因であり、敗北というよりは内部崩壊と見るべきであること、また一切の軍事経済援助を打ち切るとの見解を明らかにし、以後台湾問題を中国の国内問題として処理する方向を示した。
さらに49年12月、トルーマン政権は国家安全保障会議において「アジアに関するアメリカの立場」と題する報告を承認し、台湾への軍事不介入、対中貿易の限定的容認、中ソ離反戦略による中国のチトー化などの戦略を決定する。翌1950年1月、トルーマン大統領は、「アメリカは中国に介入せず、今後国民党政権に対する軍事援助や助言等を行わない」との中国内政不介入の声明を発表し、国共内戦に巻き込まれることを回避する姿勢を明確にした。しかるに同政権の方針は、朝鮮戦争の勃発で一変する。
1950年6月25日、北朝鮮軍が38度線を超えて南進、朝鮮戦争が勃発した。台湾は日本からフィリピンを経て豪州へと至る太平洋沿岸島嶼連鎖(the pacific off-shore island chain)(極東防衛ライン)の重要拠点である。そのため共産主義勢力のさらなる拡大を防ぎ、台湾を中国共産党の手に墜ちる事態を防ぐ必要から、6月27日、トルーマン大統領は声明を発表し、米海空軍の韓国支援を指示するとともに、日本を母基地とする米海軍第7艦隊の機動部隊を台湾海峡に常時展開させ、警戒監視任務に就かせることで、中共軍の台湾侵攻を阻止する考え(台湾海峡中立化構想)を明らかにした。そして30日には米地上軍の投入を命令し、ここにアメリカのアジア不介入の戦略は180度転換することとなった。なお中立化構想には、国民党政権に対して中国大陸への反抗作戦の実施を牽制する意図も込められていた。
3.アイゼンハワー政権と第一次台湾海峡危機
1952年の大統領選挙では、共和党候補のアイゼンハワーが勝利した。アイゼンハワー政権はトルーマン政権雄の封じ込め政策を消極的だと批判し、共産勢力への攻勢を強めるべきとする巻き返し政策を提唱した。そのため前政権の台湾海峡中立化政策を見直し、蒋介石の解き放ち政策を唱えるなど国府の大陸反攻を是認する姿勢を示した。
1953年6月、蒋介石総統との会談でラドフォード統合参謀本部議長は、国府が大陸反攻作戦に具体的に着手する場合、米軍は国府軍との協同部隊の編成を検討する用意がある旨伝え、中共に圧力をかけている。また53年8月にはランキン米大使と葉公超外交部長が会談し、葉が大陳列島について、台湾本島との位置関係から生じる防衛の困難性から、アメリカの支援を求めた。これに対しランキン大使は、米政府は国府が離島、特に大陳列島を保持するためのあらゆる自主努力を行うことを望んでいる旨述べた。
こうした米側高官の言動から、第一次危機が発生する直前の時期、アイゼンハワー政権は国府が大陳列島を含む離島の防衛を自主積極的に強化することを推奨する立場を採っていたことが窺える。さらにアイゼンハワー政権は、国府による大陸反攻についても支持し、大陸反抗作戦における離島の戦略的価値を認め、離島保持のための態勢強化を進言している。
そうしたなか、1953年7月に朝鮮戦争の休戦が実現した。だがその直後の9月3日、中共軍は金門島への砲撃を開始する。第一次台湾海峡危機の勃発である。この事態を受け、アイゼンハワー政権は国府と米華相互防衛を締結する。これは、アメリカの台湾防衛コミットメントを強化した措置に見えるが、実際には、この危機を境にアメリカの国府に対する姿勢は変化し、以後、離島防衛への関与を回避するとともに、国府による大陸反攻の動きを抑制させるようになった。
危機の発生を受け開催された国家安全保障会議では、国府が兵力を展開させている離島をどう評価するかについて、関係者の見解は分かれた。しかし、リッジウェイ陸軍参謀総長ら陸軍を中心とする離島防衛消極派がラドフォード統合参謀本部議長やカーニー海軍作戦部長、トヮィニング空軍参謀総長ら海空軍幹部の離島防衛積極派を抑え込んだ。またやはり陸軍出身のアイゼンハワー大統領も、国府が支配する離島には、中共軍の奪取を阻むためにアメリカが軍隊を送り込むだけの価値はない。その結果、アイゼンハワー政権は危機の勃発を境に、国府による離島防衛を支持していたそれまでの方針を転換させ、離島防衛にアメリカは積極的介入しないとする新たな政策を打ち出した。
だが国府、特に蒋介石総統は、このアメリカの政策転換に不信感を募らせ強く反発した。なぜならば離島における国府軍の兵力・態勢の強化を促してきたのはほかならぬアメリカだったからである。特に大陳列島については、アメリカから「大陸反攻」への後押しを受けたことで、国府は国府軍の中でも選りすぐりのエリート部隊を配備していた。
国府側の不満を解消するため、ロバートソン極東担当国務次官補はランキン大使に宛てた覚書の中で、米華間の防衛条約を締結する必要であるとの見解を示した。これをきっかけに米華間で相互条約締結の議論が始まった。米政府には、防衛条約を締結することで、中共に対して金門ならびにその他の離島にさらなる攻撃を強行すれば、アメリカが介入する可能性もあることを示唆し、国府への攻撃・進攻を牽制し、抑止する狙いがあった。
その一方、国府に対しては、防衛条約という公的な枠組みを通じてアメリカが国府に関与することで、大陸反攻に繋がるような過度な軍事行動を抑制する意図も込められていた。米側は、同盟関係を結んだ以上、大規模な紛争を回避するため、中共からの攻撃を受けた場合も、国府が一方的に自衛と判断し軍事行動に出ることを認めず、アメリカとの事前の合意が必要との考えに立っていた。
1954年12月4日、米華相互防衛条約が締結されたが、米側は条約に金門・馬祖をはじめ大陳列島などの離島を防衛の適用範囲に含め明記することを認めなかった。その一方で「台湾本島と膨湖諸島」を防衛の対象とし、その他の地域への同条約の適用については「別途双方の同意に基づく」と規定された。アメリカは、条文の表現を曖味にすることでヘッジをかけたわけだが、国府の離島防衛に積極的にコミットしたくないとの思惑が読んで取れる。
相互防衛条約の締結交渉が重ねられている間、54年11月11日から中共軍の空軍部隊による大陳列島及び大陳列島の北部に所在する一江山島への攻撃が始まった。さらに翌55年1月10日には、中共軍地上部隊が島嶼部への上陸作戦を開始した。国府は米華相互防衛条約に基づきアメリかに軍事介入を要請したが、アメリカは軍事介入を拒絶しただけでなく、逆に一江山島を含む大陳列島の放棄を蒋介石に迫った。そのため同月18日には一江山島が陥落する。
翌19日、国府の葉公超外交部長はワシントンを訪問し、ダレス国務長官と離島、特に大陳列島に対する対応方針について協議した。この会談でダレスは葉に対し、大陳列島からの国府軍兵力の撤退を求めるとともに、金門島防衛のための米軍の支援を明確にするとの意向を伝えた。金門島に対する協同防衛の姿勢を明確にすることと引き換えに、国府側から大陳列島からの兵力撤退を引き出そうとしたのである。しかし蕗介石はこの提案を拒否し、大陳列島放棄断固拒否の姿勢を表明した。
蒋介石にとっては、大陳列島を支配統治することで、対岸にある浙江省を国府が統治しているとの名目が立てられた。また台湾本島を防衛するうえで、国府軍による台湾海峡のコントロール拠点であり、かつ本島防衛の緩衝地帯として大陳列島を保持防衛する必要があったのだ。だが、大陳列島は台湾本島から220海里離れており、そのため戦闘に際しては列島に近い中共軍に対して国府側の作戦機が到達するには長時間を要し、また大陳列島に駐留する部隊への後方支援も困難であった。また一江山島を失い大陳列島周辺の制空制海権を失ったこともあり、大陳列島の死守は非常に厳しい状況にあった。さらに米政府は、大陳列島からの国府軍の撤退を米海軍が護衛することを交換条件にして、国府の譲歩を迫った。
そのため国府は、不本意ながらも確保困難な大陳列島を放棄することによって、戦略的により重要な金門・馬祖防衛に対する確約をアメリカから引き出すことに期待をかけた。2月7日、国府は、新たな国際共産主義集団の侵略に抵抗するため、大陳地区の駐屯兵力を金門・馬祖などの重要な離島へ移転、兵力を集中させ、台湾本島ならびに膨湖列島、金門・馬祖等の防衛任務に充てるとの方針を発表し、2月8日から大陳列島に展開中の兵力ならびに居住する住民の移送・撤退作戦が開始され、2月25日までに作戦を完了させた。
この第一次危機を通して、台湾本島及びその近隣島嶼については米華相互防衛条約で防衛の対象とするが、国府の狙う大陸反攻作戦に加担し、米中の対立へと事態が拡大することを極力回避するというアイゼンハワー政権の方針が明らかになったといえる。同政権は当初、共産勢力に対する巻き返しを唱えたものの、実際の外交政策はトルーマン時代の封じ込め政策と変わることがなかったのである。そして、大陳列島を放棄したものの、国府が米政府から金門・馬祖防衛の確約を得ることは出来なかった。
4.第二次台湾海峡危機
第一次台湾海峡危機を契機に、1955年8月から米中両国の大使級会談が開始されることとなった。しかし、この会談においてアメリカは、中共に対し国府に対する武力不行使の明確な誓約を求めたが、中共側はこれを拒否した。またアメリカは対中禁輸解除や新聞記者交換にも応じない等強硬な姿勢をとり、中共側も、当初は対米関係改善の意欲が高かったものの、国内における反右派闘争によって急進派路線が強まったことから、結局、大使級会談は確たる成果もなく57年12月に停止してしまう。
そして、中共の態度が再び硬化し、1958年6月頃から金門・馬祖両島において国共両軍の衝突が頻発するようになり、7月に入ると両軍間で空中戦が行われ、国府の航空機が撃墜された。こうした台湾海峡の動向に関しアイゼンハワー政権が7月14日に開いた国家安全保障会議では、中共が離島を攻撃する可能性は十分にあり得るものと見積もられたが、アメリカが国府の離島防衛に積極的に関与する意思を表明することによって中共やソ連に誤ったシグナルを送ることを懸念し、台湾支援のメッセージは発表されなかった。
その後、アイゼンハワー政権がレバノンへの出兵を行った直後の1958年8月23日、中共は厦門方面から金門島への大規模な砲撃を仕掛けてきた。この日だけで中共軍の砲撃は5発を超えたといわれ、死傷者は500人以上にのぼり、金門島は封鎖状態に陥った。また200機余りの戦闘機を投入して馬祖島への機銃掃射を実施した。第二次台湾海峡危機の勃発である。
米華相互防衛条約では、金門・馬祖島が同条約の対象に含まれるか否かは明確でなかった。そこで金門・馬祖島への砲撃に対してアメリカがどのように反応するかを探ることが、中共の狙いであった。また第一次危機において大陳島からの撤退が実行されたように、米政府が国府に圧力を掛け、国府軍の金門島などからの撤退を促すことに期待をかけてもいた。一方国府は、全門・馬祖を保持することは大陸反攻を実行するうえでも、また台湾本島を防衛するうえでも必要と考えていた。
8月27日、蒋介石総統はアメリカに対し、米華相互防衛条約に基づき軍事介入するよう要請した。また金門・馬祖島への攻撃は台湾全体に対する直接的な脅威であるとの声明を発表するよう米側に求めた。これに対しアメリカは、金門・馬祖防衛にコミットし米軍が軍事介入するか否かについては曖昧な姿勢を示したが、9000万ドルの軍事物資供給や在台湾米軍へのF-100F戦闘機の追加配備を実施、また第七艦隊を台湾海峡近海に派遣するとともに、国府軍による金門島への補給物資海上輸送のための護衛に当たった。
但し中共に対する挑発を避けるため、直接的な交戦に繋がるような軍事行動は控え、米軍の護衛区域は公海上に限定された。アイゼンハワー大統領は8月14日の国家安全保障会議で、改めて国府による離島防衛が戦略的に無意味であると批判し、ダレス国務長官も国府が金門・馬祖島を大規模な兵力展開拠点として保持していることについて不快感を示した。
そのため9月に入りダレス及びアイゼンハワーは相次いで、金門・馬祖への砲撃を超えて中共が台湾本島を含む極東の安全を脅かす行動に出るならば、アメリカはそうした事態を容認せず軍事介入も辞さずと表明し中共を批判牽制したが、金門馬祖への米軍の介入については言及を避けた。10月にはマケルロイ国防長官が台湾を訪れ蒋介石総統と会談し、大規模な金門・馬祖駐留兵力削減の必要性を伝えた。しかし第一次危機の際、国府は米側の要請を容れ大陳列島放棄を決したが、金門・馬祖防衛に対するアメリカのコミットメントが得られなかった経緯もあり、蒋介石は金門・馬祖に対するアメリカのコミットメントがない限り、放棄や兵力削減には応じないとの姿勢を崩さなかった。
そうした中、10月21日から3日間にわたり、訪台したダレス国務長官と蒋介石の会談が4回行われた。ダレス国務長官は、大陸反抗の放棄と離島駐留国府軍の削減・非武装化を求めたのに対し、蒋介石総統はそれを拒否し、当初議論は平行線が続いた。しかし23日の会談において、第二次危機における戦闘が停止した後でという条件の下で、国府は金門・馬祖から1万5千〜2万人の兵力を削減し、その見返りにアメリカは国府の金門・馬祖駐留部隊の火力を増強させるために武器供与を行うとの合意が成立した。この合意は、国府に兵力の削減を強いるものではあったが、なお兵力の大部分は温存されるため、大陸反攻実現の余地は残され、また台湾本島防衛にも寄与する措置と受けとめられた。これに対し米側には、国府による中国への挑発を緩和させる意味合いがあった。
10月23日に公式発表された「蔣介石・ダレス共同コミュニケ」 では、「金門島及び馬祖島の防衛は、台湾及び澎湖諸島の防衛と密接に関連している」ことが明言された。これによって、アメリカが金門・馬祖に対する防衛的関与を行なう方針が公式に示され、中共側の軍事行動に対する牽制が図られた。国府は、アメリカから金門・馬祖防衛の確約は得られなかつたが、アメリカによる金門・馬祖の防衛と台湾本島・膨湖諸島の防衛が密接に関係していることを初めて明文化させることに成功した。
また共同コミュニケには「中華民国政府は、中国本土の人民に自由を回復することがその神聖な使命であると考えている。中華民国政府は、その使命の基礎は中国人民の心の内にあり、かつ、この使命を達成する主要な手段は孫文の三民主義を実行することであり、武力の行使ではないと信じている」との表現が盛り込まれた。国府の大陸反攻の主要手段を「三民主義」とし、武力に頼るものではないと認めることは、蒋介石が固執する大陸反抗によって中共との大規模紛争に巻き込まれる危険を回避したい米側の意向に添うものであった。
1958年10月25日の「再び台湾同胞へ告げる書」の発表を通じて中共は、金門島などへの上陸作戦を行なわない意向を示した。中共は、金門島へ向け偶数日のみに砲撃を行い、奇数日には砲撃を行なわないことを宣言するとともに、米軍が国府軍の護衛を行わない限り、空港や港湾、船舶などを攻撃しないという立場を表明した。これによって、第二次台湾海峡危機は急速に終息へと向かった。その後、中共による金門島への向けての限定的な隔日の砲撃は、1979年1月1日まで20年余りにわたって象徴的に継続されることになった。
5.米台断交後の関係と第三次台湾海峡危機
最後に冷戦後に起きた第三次危機に目を向けよう。1995~1996年に起きた第三次台湾海峡危機は、米中の国交正常化後、即ち米台間に国交がなくなり、両者の間に安全保障条約も存在しなくなった状況下で起きたものである。
ただ、米台断交後、台湾との非公式関係を維持するための枠組みしか整備しないカーター政権の姿勢に反発した米議会が、アメリカによる台湾の安全保障への関与を強化する規定を盛り込んだ台湾関係法を1979年4月に成立させた。同法は、非平和的手段によって台湾の将来を決定しようとする試みは、西太平洋の平和と安全に対する脅威であり、アメリカの重大関心事と見做し、対応策として防御的兵器の台湾への売却が規定されたほか、台湾人民の安全やアメリカの利益に対する危険について、大統領は議会に通告し、憲法の定める手続きに従い、適切な行動をとることとされた(台湾関係法第3条C項)。ただし米華相互防衛条約ではその適用対象地域が「台湾及び澎湖諸島、但し相互の合意によって決定されるその他の領域」(第6条)と規定されていたのに対し、台湾関係法では台湾と澎湖諸島だけが対象で(台湾関係法第15条1)、大陸沿岸諸島は含まれていない。
1995年春、台湾の李登輝総統は母校コーネル大学の同窓会に私人として出席するため、アメリカへの入国許可を求めた 。しかし米政府はこれを認めず、5月3日国務省は声明を発表し、もしアメリカが李登輝の訪米を認めれば、たとえそれが私的訪問であっても「アメリカと台湾の非政府間関係、中国との政府間関係の一つの極めて重要な基礎を損なうことになる」と説明した。クリストファ−国務長官も国連で銭其琛外相に対し、アメリカが李総統に入国ビザを与えることはないとの意向を直接伝えていた(4月17日)。ところが声明からわずか3週間後の5月22日、クリントン政権は一転して李総統の非公式入国を認める措置を決定する。
前年、李登輝総統の南米訪問の帰途、乗機がホノルルに立ち寄った際に、クリントン政権は彼の入国を認めなかった。そのため機内に一晩中留まることを余儀無くされ李登輝がこの措置に抗議するというトラブルが起きていた。94年の中間選挙で台湾支持派の多い共和党が上下両院で多数を支配するようになり、外交に対する議会の影響力が強まった。先の声明を覆しての訪米許可にも、こうした議会や台湾ロビ−の圧力、それにマスコミの報道も影響していた 。
95年6月7日、李登輝統はロスアンジェルスに到着、予定通り同窓会への出席を果たしたが、当然のことながら中国はこの決定に強く反発し、遅浩田国防相の訪米延期等高官の相互交流を中断したほか、駐米大使を本国に召喚、アメリカの次期中国大使の承認にも応じない等一連の報復措置を打ち出した。また中国は、コーネル大学における李登輝の「全力を尽くして不可能なことにチャレンジしていく」という発言を、台湾の独立を目指す決意表明と受けとめ、公式報道機関である「人民日報」は4日連続して李登輝を非難攻撃、米台批判のキャンペーンを展開するとともに、中国軍が台湾を仮想敵とした初の弾道ミサイルの射撃演習を実施した(7月21~26日)。この演習には、独立傾向を強める台湾を牽制し、潜在的な独立派と見做した李登輝の総統再選に歯止めをかける狙いがあることは明らかだった。
その後8、10、11の各月にも台湾付近の海域で中国軍は三度軍事演習を行い、俄かに緊張が高まった。これに対しアメリカは12月に空母ニミッツを二度にわたり台湾海峡を通過させ、中国を牽制した。米空母が台湾海峡を通過したのは、実に1969年以来のことであった。
米中関係が悪化する一方で95年8月末には米中次官級会談が再開され、10月末にはニューヨ−クでクリントン・江沢民会談が行われ、関係修復の動きも出始めた。しかし96年3月に台湾初の総統直接選挙が行われた際、再び中国は15万人の軍隊を集結させ、台湾周辺と福建省沿岸で、海空軍合同の実弾射撃訓練やM9型地対地戦術ミサイルの発射、さらに馬祖島に近い福建省平潭島付近での三軍合同による上陸演習など三波にわたって大規模な軍事演習を実施した(3月8~25日) 。台湾における総統選挙を妨害、攪乱させることに加え、アメリカの出方を窺うこと、独立あるいは現状維持を求める声が強まりつつある台湾に対して、主権保全の中国の決意を誇示すること等がその狙いであった。中立系香港紙「早島日報」によれば、北京の軍事関係者は、台湾当局が分裂活動を継続するならば、中国軍は台湾の周辺海域20か所にミサイルを撃ち込み、全島を封鎖する用意があると発言(3月8日)、台湾への威嚇を強めた。
これに対し台湾側は厳戒態勢をとり、アメリカは西太平洋に展開中の空母インデペンデンス主力の機動部隊に加え、ペルシャ湾から急遽空母ニミッツ基幹の機動部隊を急行させ、空母2隻(インデペデンス、ニミッツ)を含む大部隊を台湾近海に派遣して、中国の動きを抑止、牽制した。「中国は台湾問題を平和的に解決すべきである」とのアメリカの意思を中国に正しく知らしめるとともに、台湾に対する軍事挑発行動はアメリカの利益に対する脅威となり、アメリカは自らの利益を守るために十分な軍事力を有していることを中国に示したのである。
アメリカの強い姿勢には、米国内の事情も影響していた。大統領選挙を意識して共和党がクリントン政権の対中姿勢を批判し、台湾との関係格上げヤ李登輝総統の公式招待などを要求、議会においても下院では369対14の圧倒的多数で、中国の台湾進攻、封鎖に対してアメリカが台湾を防衛する決議が可決された。そのためクリントン政権としても米国内向けに強い対中姿勢を見せる必要に迫られたのである。米空母群のプレゼンスは、台湾民衆の心理を安定させるうえで効果があったといえる。日本政府も「我が国の領海に極めて近い場所でもあり、万一の不測の事態も懸念している」と憂慮の念を示した。
このアメリカの強い対抗措置に中国は強い衝撃を受け、対話による問題解決へと動いた。中国は米艦隊の派遣を非難し、遅浩田国防相の3月訪米を再度延期させてアメリカに対する不満を表明したが、その後、オランダのハーグでクリストファー国務長官と銭其琛外相が会談(96年4月)、米側は「一つの中国」政策の堅持、台湾とは政府間関係を発生させないこと、またこれまでの三つの米中共同コ69体ミュニケの遵守を確約。しかもクリストファー国務長官は、外相会談前に対中最恵国待遇の延長を発表するなど柔軟な姿勢を打ち出した。
こうした米側の動きは、大統領選挙を控えるクリントン政権が、これ以上の中国との関係悪化を恐れたことや、北朝鮮問題で中国の協力を必要としていたためである。96年7月にはアンソニー・レーク安全保障担当大統領補佐官が訪中する。これは1994年以来、アメリカの最も地位の高い人物の中国訪問であった。米中の広範な協力関係進展を訴えたこのアンソニー・レークの訪問を境に、過去1年にわたって続いた両国の緊張状態は緩和へと向かった。
この第三次台湾海峡危機は、台湾への軍事侵攻や領土の併合を意図してのものではなく、台湾へのアメリカの肩入れを牽制するとともに、李登輝総統選挙の妨害と台湾で強まりを見せる独立志向の阻害を目的として中国側が起こしたものであったが、李登輝は再選を果たし、またアメリカが台湾防衛のために強い軍事的な措置に出るなど、結果的に中国の狙いは失敗に終わったといえる。
中国としては大規模な軍事演習を繰り返し、その威嚇効果を期待したが、台湾も米政府も、台湾の封鎖や進攻、上陸作戦を実行するだけの軍事力が中国には備わっていないことを十分に承知しており、その知見が中国の威嚇効果を減殺させたのである。むしろ中国軍の演習を通して、台湾と中国軍の戦力の格差を露呈させることになった。
中国軍の保有する戦闘機の大部分は1950年代に旧ソ連が使用していたミグー17、19、21のコピーか派生型で退役時期を過ぎており、ロシアから輸入した近代的なスホーイ27などはほんの僅かに過ぎなかった。中国軍の上陸作戦能力も、最大2個師団程度(2~3万人)と見積もられており、また海軍力についても近代化や増強政策が緒に就いたばかりで、例えば潜水艦は第二次世界大戦中のドイツのUボートを基本にしたロメオ型やその派生型を保有する程度であった。近代化の進む台湾に対して軍事的な優位を確保できておらず、まして米中の軍事バランスでは圧倒的に米側の優勢にあった。当時、台湾海峡の制海・制空権は、台湾及び米軍が握っていたのである。
しかるに、それから四半世紀が経過し、現在懸念されているのは、単なる台湾政治への妨害ではなく、「一つの中国」を唱える中国が実力行使に出て、台湾を支配併合する危険である。また冷戦終焉後の30年間に米中の軍事バランスは中国の優位へと大きく変化しつつある。特に米空母を目標とした対艦ミサイル戦力の強化を中国は進めており、著しい空軍力や潜水艦、さらには渡河戦力の増強なども考慮すれば、第三次台湾海峡危機の時のように、アメリカとしてもその母機動部隊を軽々には台湾海峡近海に投入することが容易ではなくなっている。
6.総括
米中和解が実現する以前、アメリカは冷戦戦略の一環として、国府と安全保障条約を締結し、本島及び澎湖諸島の防衛コミットメントを明らかにしたが(戦略的明確性)、大陸沿岸諸島の防衛については終始明確なコミットを避け、逆に国府にその放棄を迫った。中共軍の攻撃を受けた場合その防御が困難なこと、離島防衛のために国府が軍事力を大規模に投入すれば中国との全面紛争に発展し、さらに米軍が介入することで米中の全面戦争へと事態が一層エスカレートすることを恐れたためである。また国府は沿岸離島を大陸反抗の拠点と位置付けていたのに対し、アメリカは離島防衛の価値を認めず、紛争拡大の危険が大きい国府の大陸反抗も認めようとしなかった。
一方、米中和解後アメリカは、台湾関係法を軸に台湾の現状維持とその防衛のために関与する政策をとってきた。ただ防御兵器の提供以上の関与については、台湾関係法も米華相互防衛条約の規定と同じように「憲法の規定に従って適切な行動を決定する」と曖昧化されている。
もっとも、第三次台湾海峡危機に際しては、中国軍の軍事的威嚇が台湾への侵攻・制圧を目的とした行動ではなかったものの、台湾に対する軍事的恫喝の阻止と攻撃抑止のために、アメリカのクリントン政権は異例とも言える二つの空母機動部隊を台湾海峡に投入、展開させ、軍事的な解決も辞さずとのシグナルを中国に送り、台湾防衛の意思を明確化させた。ともすれば中国に対して融和的と評されていたクリントン政権がこの時期、そうした強い軍事的対抗措置に出た背景に、議会をはじめとする米国内の台湾支援の世論が大きく影響していた事実は見落としてはなるまい。
米台断交後、相互防衛条約は破棄されたが、新たに制定された台湾関係法が台湾へのアメリカのコミットメントを保証する機能を果たしており、断交の前後でアメリカの台湾政策が劇的に変更されることはなかった。それと同時にアメリカは断交の前も後も、戦略的な曖昧さを基本とする点でも変化が見られない。台湾の防衛に関与し、台湾の現状を維持することにアメリカは利益を見出しているが、防御的武器の提供以上に、どの程度の軍事的コミットをするのかについては終始曖昧な姿勢を堅持しており、曖昧性の戦略を堅持することによって中国の行動を牽制、抑止する政策を続けている。
しかし、冷戦終焉直後は東アジアにおいてなお圧倒的な軍事的優位を保持していたアメリカも、現在、そのレゼンスは低下する傾向にある。それとは対照的に、中国は一貫して軍事力の強化を続けており、第二列島線を設定し、その以西の軍事的支配を強固なものとすることによって、西太平洋に対する米海軍の接近を阻止するとともに、台湾への武力侵攻を成功なさしめるための態勢を確保しつつある。
そのような軍備増強を背景に、中国が近い将来、台湾に対する威嚇や独立の阻止にとどまらず、「一つの中国」の実現に向け、台湾の制圧をめざし軍事侵攻に踏み切るのかどうか、また攻撃を仕掛けた場合、どのような作戦を展開させるのか、さらにまた中国軍の台湾攻撃という事態が生起したならば、現在のバイデン政権が第三次台湾海峡危機の際にクリントン政権が示したような、あるいはそれ以上に積極的な米軍による軍事行動に踏み切り、台湾防衛のためのコミットを明確化させるのかどうか、が注目される。
(2021年11月21日)
参考文献
本稿作成に際し、以下の論文を参考にさせていただいた。謝意を表します。
石川誠「『ダレス・蒋共同コミュニケ』再考」『日本台湾学会会報』第3号。2001年河原昌一郎『米中台関係の分析:新現実主義の立場から』(彩流社、2015年)
松本はる香「第二次台湾海峡危機をめぐる米台関係の展開 —蔣介石の意図と対応の分析を中心に— 」『愛知大学国際問題研究所紀要』第155号、2020年
吉田有「台湾における『離島防衛』の意義:第一次・第二次台湾海峡危機を中心に」大学評価学位授与機構提出修士論文、2017年12月