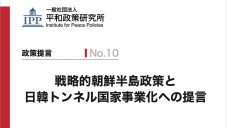1.ポストコロニアリズムの時代と慰安婦問題
これまで30年近く慰安婦問題にかかわる中で、以前著した著書以降、新たな知見も出て来たので、そうしたことも含めて慰安婦問題に関する認識の変遷をまず述べたい。
慰安婦問題は1990年代にイシュー化したわけだが、その背景には冷戦が終結して、植民地支配についての見直し(ポストコロニアリズム)が出てきたことがある。つまり冷戦時代は、北朝鮮との厳しい緊張関係もあって過去の問題にきちんと目を向けることができなかったが、冷戦後はそうした状況から解放されて、植民地支配問題に改めて目が向けられるようになったのである。そしてそうした流れと相まって植民地時代に被害を受けた女性(元慰安婦)が名乗り出やすい環境が整った。また韓国国内状況としては、この時代に海外留学経験もある高学歴の女性が活躍するとともに、80年代以降女性の人権に関心が注がれるようになった。
慰安婦問題をめぐる主張では韓国の声ばかりが大きい印象もあるが、その論理や運動、訴訟は日本の学者や運動家も連携し ている。こうした連携は主に日韓の左派市民知識人連帯によって進められてきた。 こうした政治的な色彩や主張は慰安婦問題が出てきた初期においてはさほど目立たなかったが、2000年代以降、よりはっきりと表れてきた。
慰安婦問題がなかなか解決に至らない現状について、その背景について考えてみたい。
(1)間違った理解
2021年2月、米国の学者が慰安婦は契約をむすんで戦場へ出て行ったとする論文を出して物議を醸したが、そもそも慰安婦をどのように理解するかこそが最も重要である。
韓国において慰安婦問題を最初に提起したのは、梨花女子大学の英文学専攻の尹貞玉教授だった。尹教授は、慰安婦問題に関心を持った80年代に日本各地を始め、東南アジアや南太平洋地域などに生存していた元慰安婦の人たちを訪ねてインタビューをし、その内容をまとめて韓国のハンギョレ新聞にルポ記事を載せた(1990年1月)。翌年には元慰安婦が初めて公に声をあげ、 日本でも衝撃を与えた。強制連行されたという日本の記事が再び韓国に跳ね返るようなこともあった。
そのルポの中で尹教授は、慰安婦の状況を「強制売春」という言葉で表現した(ただし、慰安婦を「挺身隊」という言葉で説明していて、このとき尹教授は挺身隊として動員された同級生のことを慰安婦になったものと勘違いしている。それでいて同じルポの中で(兵士と慰安婦の関係について)「人間と人間としての交流もあった」と記してもいる。
1990年代の韓国の新聞では、いまなら非難されかねない微妙な表現が普通に使われていた。例えば元兵士と台湾まで出かけて霊魂結婚式を挙げたという記事をも中央日報など大きなメディアに出ていたのである。しかし2000年代以降、議論が大きく変わった後はそうした事実は忘れ去られてしまった。つまり早くも「記憶の忘却」が行われていたのである。
尹教授は、概念としての慰安婦を「日本帝国による朝鮮民族抹殺政策」の一つ、つまり植民地の女性をターゲットにした犯罪だと理解していた。それは、70年代に出された在日の金一勉や千田夏光の本の影響ではなかったかと思う。そして尹教授のこうした考え方が、その後、韓国挺身隊問題対策協議会(現、正義連)の基本的な考え方となった。尹教授とともに挺対協の共同代表を務めた李効再・梨花女子大学教授(1924〜2020年)もこうした考え方を共有していた。李教授は文大統領によって生前に青瓦台に招聘されたこともある。
初期挺対協の代表らが考える「朝鮮民族抹殺政策」とは、「再生産」(妊娠出産)を不可能にするような政策で、さらに過酷な待遇を「耐えられなければ死ね」とするも同じで、「生き残った人は捨てたり殺したりした制度」(「朝鮮植民地政策の一環としての日本軍慰安婦」『日本軍「慰安婦」問題の真相』1997)と考えられていた。割合初期から政策=制度という言葉が使われたが、「制度」とは慰安婦動員が「組織的、体系的」であると理解する言葉でもあり、裁判において慰安婦動員が「不法」であるべく使われた概念でもあった。しかし、慰安婦の病気や不妊は(動員の)結果であって目標ではない。ここに最初のボタンの掛け違いがあった。
ちなみに、尹教授は植民地時代に過ごした10代の頃、日本人警察に家に押し入られたことがあったそうで、そのような体験が日本に対する恨み・怒りの背景にあるようだ。
こうして尹教授は、「慰安婦制度は植民地女性をターゲットにした」と考えたが、かなり長い間慰安婦関係者たちには日本人慰安婦のことは認識されなかったり、無視されたりした。そうしたことも慰安婦動員の本質を読み間違えさせた原因となった。そうした90年代の認識は、(中身は微妙に変化しても)現在に至るまで変わっておらず、慰安婦問題に関わる学者や支援団体の共通認識として維持されている。
例えば、やはり挺身隊問題対策協議会の90年代後半から2000年代半ばまでの代表だった鄭鎮星教授やその弟子たち(ソウル大学人権センターグループ)が著した『連れていかれる、捨てられる、私たちの前に立つ』という本のタイトルにもそうした視点は濃厚で、同じコンセプトで展示会も開いている(2018年)。
このとき鄭教授などのグループは、ミャンマーで慰安婦の「虐殺」映像を見つけたとしてメディアに大々に発表して注目を集めた。しかしそうした死が虐殺死か玉砕に巻き込まれた死か爆撃死なのかは定かでない。連合軍との(空爆の)戦闘地域でもあったが、こうしたことによってメディアを含む韓国の人々はますます日本に対する憎悪を募らせている状況である。
実は、慰安婦強制連行説を「学問」的に支えているのはむしろ日本・在日の学者である。挺対協は、100人以上の元慰安婦の証言を集めて8冊の証言集を出しているが、それを見ても、軍人が(力ずくで)連行したという証言は圧倒的に少ない。私の考えでは、その軍人にしても、軍属扱いされて軍服に近い身なりができた紹介人や業者のことではなかったかと思う。
日本の学者では、慰安婦問題に関連して吉見義昭が『買春する帝国』(2019)、金富子が『植民地遊郭』(2018)をそれぞれ著しているが、タイトルとは裏腹に結論はやはり強制連行説となっている。強制連行—強制性と言葉や意味するところを少しずつ変えてきた結果でもある。「強制連行」は不法行為だから、日本はその「法的責任」を取るべきだという長年の主張である。
80年代までは慰安婦に関するルポのような本はあっても学者の「研究」はないに等しい状況の中、声をあげたのが韓国をはじめ元植民地や占領国の女性だったため、研究が後から追いつき、慰安婦とは日本軍の敵や捕虜のような存在として刻印されたのである。
当時はまだ植民地支配や帝国主義のしくみについてしっかりした理解も少ない時代だったせいもある。植民地支配に抵抗する人々が弾圧され殺された事例は多くあったが、植民地とは支配者にとっては良くも悪くも使用すべき(生かすべき)「資源」であった。そのためにも包摂する必要があり、包摂と排除の間を行き来する。そうした隠微な側面を持つ植民地支配という仕組みが十分理解できずに、慰安婦も偏った理解をされていたのである。
そのように包摂・管理すべき対象でもあるわけで、搾取やたやすい殺害の対象でもあったが、態度は一様ではなかったのである。しかしそうした二重性や多様性は慰安婦をめぐる認識を作っていく中で捨象され、慰安婦を語る際「一部の全体化」「少数の多数化」やさらに「一般化」が起こった。
本格的に植民地支配、帝国主義の問題を向き合った時そうした傾向があったのは、そうした問題を積極的に考えた主体がやはり過去において体制側(日本政府)によって抑圧された左翼・反体制派の流れを引き継ぐ人たちだったからでもある。韓国でも、植民地支配や1965年の日韓基本条約を問い直す動きが始まったのは90年代だが、その流れの中には、昨年亡くなった朴元淳ソウル市長や姜昌一駐日韓国大使などもいた。朴市長は、ニュールンベルク裁判を参照しつつ慰安婦問題を東京裁判で処罰できなかった問題として位置付けていた。
(2)政治の介入
90年代初めに日朝国交正常化の動きがあった。時期を同じくして韓国では慰安婦問題が起こり、北朝鮮はそれについて「不法行為だから日本政府は賠償をすべきだ」と主張した。こうした論理を支えるような形で、同じ頃に韓国併合(植民地支配)を不法とみなそうとする問題提起が本格化し始めた。
そうした主張をした人の中には日本の弁護士や学者もいた。そのひとりである戸塚悦朗氏は80年代から国連を舞台に人権・労働問題を扱い、90年代には挺対協と連帯しながら彼らの運動を支えてきた。北朝鮮でも同様に日本の植民地支配の不法性を訴える論文を発表する法学者が現れた。
1992年には韓国や北朝鮮の元慰安婦の話を聞く東京国際公聴会が開かれ、その後も南北の関係者たちはソウル、平壌、北京やヨーロッパで会合を持った。冷戦崩壊のおかげでそれまで会うことのなかった北朝鮮と韓国は在日朝鮮人を媒介としてその後の連帯へと進んでいった。
一方、同じ頃に進められていた日朝国交正常化交渉の中で、北朝鮮は韓国の1965年方式ではなく、植民地支配への賠償という方式で行うべきだと主張した。こうした認識を挺対協も共有し、強制連行—不法—賠償という枠組みが、慰安婦問題支援者や学者の間でも定着するようになる。戸塚弁護士が自分で作って国連で提起したとする「性奴隷」という概念はそうした認識を支える強力な認識となった。特に南北の支援者や関係者の国連を舞台とする連帯は、冷戦終結後の世界に本格的に対等したナショナリズムやポストコロニアリズムの動きと並行するものでもあった。
例えば、鄭鎮星は「(北の支援団体は)事実上政府の一部分」といい、辛恵洙は「朝鮮人強制連行調査団の(朝鮮人の)国籍は北朝鮮」「緊密に協力し合う関係」などと発言している。
またのちに挺対協の代表となる尹美香は早くもこの時期に「北朝鮮は政治的に日本に対応しながら戦争犯罪賠償を確実に受け取ろうとしている。今は……賠償を受けるに十分な主体的な力量が整った」と発言した(1992年)。この主張の基本骨格は、今日に至る30年間変わっていない。理論的に「不法」の正当性を訴えるため、北朝鮮は日本と朝鮮は当時対等な「交戦国」であり、日本による朝鮮半島支配は「占領」であったと主張した。この認識はやがて韓国でも共有されるようになった。
慰安婦問題が長らく「戦争犯罪」と言われた背景にはこうした過程がある。そしてこうした考え方が、昨今の慰安婦をめぐる韓国の裁判を支えてもいる。実際、支援者の一人である韓国の法学者・都時桓は、のちにある論文の中でそうした主張が「北朝鮮の対日協商力」を高めるための主張だったと述べた。
ただ実際には、「日朝平壌宣言」(2002年)で北朝鮮は韓国(1965年)方式と変わらないやり方で日本との関係回復を進めるかのような態度を示した。そういう意味で、もしこのとき日朝国交正常化がなされていれば、東アジアが今日のような葛藤局面になることはなかったかもしれない。
2005年に『和解のために』を出したときに、批判者たちから「なぜ北朝鮮のことに言及しないのか。この本は日米同盟に益するものだ」と非難された。あの本は韓国に生きる存在として日韓のことを考えてみた本だったので、どうしてそのような批判をするのかよく分からなかった。今になってようやくそうした非難の背景が見えてきたのである。
(3)同時代の受け止めと西欧の二つの誤解
次に90年代の初め以降支援者たちが国連の舞台で慰安婦問題を訴える過程を見て見えてきたことについて述べる。
先述した戸塚弁護士は、国連を舞台に活動する中で、オランダの法律家ヴァン・ボーヴェン氏の助言を受けたという。ボーヴェンは、70年代から国連人権事務局につとめ、当時人権委員会に所属していた。彼は、スマラン事件(注:日本軍占領中のオランダ領東インド、現在のインドネシアで日本軍の軍令を無視した一部の日本軍人がオランダ人女性を収容所に集めて強制買春させた事件)を知っていて、朝鮮人慰安婦問題もそれと同様のものとして理解した。さらに、支援者たちは当時の国連では同時代に起こったユーゴ内戦やアフリカで起きた部族間強姦事態を朝鮮人慰安婦問題と同じ出来事とも理解した。
挺対協や日本の支援者たちの訴えが奏功して、1994年に国際法律家委員会の調査と報告書が出された。慰安婦問題を戦争犯罪と考えたため日本では裁判所に持っていかれ、多くの法律家が関わったが、こうした歴史への法の介入は、ひとえに慰安婦問題を「強制連行」=戦争犯罪と理解した結果だが、そうした対応が国際レベルでも行われたことになる。しかし問題自体への理解が不十分なまま法至上主義を掲げたことによって問題は単純化され、結果的に解決も難しくした。裁判はどちらかの勝ち負けとして結論を出すわけだが、 歴史問題は多様な面を持っており、「法」 によって単純に割り切れるような性質のものではない。
国際法律家委員会や国連の調査に応答した北朝鮮慰安婦の証言は、(首を切られた、子供が殺されたなど)他の証言に比べても異質で極端なものだった。そうした証言は国連のクマラスワミ報告書などにも反映されている。オランダを含む西欧諸国は、日本と交戦した関係であるから、そうした証言をそのまま受け入れやすかったともいえる。
以上のようなさまざまな誤解や欺瞞、そして忘却が続き(内部理解と外部への発信の齟齬、植民地・被占領国の使い分け、90年代に許容された認識の忘却など)、今日に至っている。一方、慰安婦の支援団体やそれを支える学者の主張は、その後の知見によって少しずつ変化しているが、そうした変化は、公になかなか発信されないか、概念やその中身が変わるのみで、初期の中心(強制連行・強制性=不法)主張は変わっていない。このことが今日の最大の問題ではないかと思う。
2.戦時動員をめぐる認識
(1)政治的植民地化の中の労働移動
戦時動員、いわゆる徴用工問題についてである。当時のいろいろな資料をみると、朝鮮人労働力の移動に関してはさまざまな形があったことが分かっている。
20世紀の初めごろから日本にやってきた朝鮮人が日本に渡ったのにはさまざまな理由があったが、一つにはできるだけ安い労働力を必要とした近代資本主義の法則に支えられた面があった。それはまた、初期の経済的植民地化から政治的植民地化へと向かう過程での労働移動でもあった。
朝鮮人が日本で最初に働いた場所が炭鉱であったのは象徴的だ。その後、彼らは工場、飛行場などでも働くようになるが、彼らが身を置いた空間が近代産業を支えるエネルギー・物質・インフラづくりの場であったことは、朝鮮人労働が日本の近代産業をまさに底辺から支えたことをも示している。
しかも移動した朝鮮人たちの多くが、「耕作すべき土地を持たない農民」(鄭惠瓊「日本帝国と朝鮮人労働者供出」ソニン、2011年)だったことは、近代産業への農民投入を意味する。多くの証言が語る過酷な体験は、そうした「不経験なる」異空間体験であり、徴用者たちの経験が単なる肉体的な苦痛を超える悲惨な体験となった理由はそこにもあった。
(2)徴用の国家性
徴用は、労働現場のためになされたことであるから、企業が責任主体のように見える。しかし、すでに多くの研究が指摘しているように、徴用とは明らかに(日本)国家が主導したことだった。それは、動員のために国家総動員法や国民徴用令などの法令が作られ、それに基づいて人が集められたことが証明している。
当時の「改正国民徴用令解説」には、「即ち大東亜戦争をあくまでも闘ひ抜き勝ち抜く爲の根幹であり、原動力である軍需生産の画期的増強を期する爲、(中略)(改正勅令を)内地は(1943年)8月1日より、朝鮮、台湾、樺太及び南洋群島などの所謂外地は一カ月後の9月1日より、それぞれ実施することにした」(伊藤武夫『改正国民徴用令解説』1944年7月)と記されている。
30年代以降、朝鮮労働者が急激に増えた背景には、朝鮮の貧困などの理由のほかに、女性の坑内労働禁止、囚人労働廃止、坑内における馬使用廃止などがあり、一般に言われるような、日本の青年たちが戦争に動員されて労働力が不足したためだけではなかった。つまり、朝鮮人の日本流入は、単に日本人男性の労働力補充というような意味だけではなく、それまで「日本の最下層に代わっての投入」という構図があった。
またよく官斡旋と徴用は違うと言われるが、当時の資料や本には同じようなものだと記されている。例えば、1941年の総督府の徴用者向けの激励・叱咤の手紙には、「帰りたいと言っているようだが、それは皇国臣民としてあるべきことではない」などの言葉が見られる。
(3)強制性について
数年前に韓国と日本で『反日種族主義』という本が出て、「差別はなかった」との言説が主張され始めた。しかしそれも単純化し偏った見方だと思う。賃金支払いに関して言えば、 日本人と朝鮮人で差別がなかった時期・空間もあったかもしれないが、そうでない時期や区間もある。また激しい暴力が行われるなど、差別の隠微な構造があったことは確かであるから、そうしたことを見ないで「差別はなかった」とする主張には賛同できない。
朝鮮総督府は日本人と「賃金は勿論其の他の処遇においても、全然内鮮人間に差別はありません」(朝鮮総督府労務課監修「国民徴用の解説」)と断言したが、炭鉱をはじめとする徴用の場は、はじめから差別を伴う空間だった。そもそも日本人は「炭鉱や土建工事場で重労働をしなかったし被徴用者もそうした場所に配置されなかった」(外村大『朝鮮人強制連行』2012年)のである。
南洋群島での体験記をみると(趙ソンユン『南洋群島に生きる—朝鮮人松本の回顧録—』2017年)、マリアナ諸島において島民を管理する立場にあった朝鮮人自身が、自分は同じ立場の日本人よりも弱い立場にあるとの意識、つまり「二等国民」としての自覚を持っていた。またある人は、「徴用者のロマンがあった」と主張するが、それが無差別の証拠にはならない。
当時、植民地の日本人官僚の手記も出ているが、そこには「一つの郡で10人集めるのも難しかった」と記されている。それは朝鮮の人々は行きたくなかったということにほかならない。担当官は、警察や教師、行政官を使って説得してもらったという。それをもって「強制はなかった」とすることはできないだろう。
徴用に行かせる人を選ぶ位置にいた国民徴用官はかなり恣意的に弱い立場の人々を行かせたようである。そうした面について自覚されていなかったのではないか。日本側にしても、「この人を連れてきても果たしてちゃんと働けるのか」との懸念をもち逡巡していたという。それを外村大は「徴用されない差別」と表現した(前掲出)。
歴史の多様な面はそれぞれしっかり見届けるべきであるが、全体として言えば、植民地支配という構造——支配者と被支配者という不平等な関係の中で行われていたことは共有されるべきだろう。
(4)法至上主義の問題点
法至上主義の法律家たちは90年代半ば以降今日まで、(徴用工の問題は)法によって解決せよと主張してきたが、最近その姿勢に変化が見られる。もちろん裁判を通して解決を求めるのだが、そこに政府も関与すべきだと政府の役割に期待を寄せて始めている。しかしそれは矛盾ではないかと思う。
これまで彼らは個人請求権の存在を根拠に裁判を起こして補償を求めてきたわけだが、日韓両政府が向き合い(個人請求権を抹消して)新たに財団をつくり、22万人に及ぶ被害者に金銭的補償をすべきだというのである(『反日種族主義』の立場の人たちは、徴用工に対しては何もしないという立場である)。しかしこのようなやり方は矛盾に満ちている。問題に対する両国民の広い理解と共通認識なしに進められた日韓の慰安婦合意(2015年)頓挫から、「性急な処理」の失敗の教訓を学ぶべきではないかと考える。
数年前に文喜相・元国会議長が提案した解決案もあるが、これも当事者たちの不一部に反対されている。また中国人と日本企業の間で和解をしたやり方もあるが、中国のケースとは異なるので朝鮮人徴用工の問題に当てはめていいとは思わない。
10年程前まで日本政府は、徴用工の名簿や厚生労働省の資料などを提出するなど、この徴用工問題で韓国側にかなり協力していた。ところが、2012年の李明博大統領による竹島上陸などを契機に関係が急激に悪化しそうした協力関係は途絶えたままである。
日本政府の基本姿勢は、1965年の日韓基本条約をもって過去の問題はすべて解決済みという立場である。韓国の中には、その条約を破棄してもう一度条約を結ぶべきだとの強硬論を主張する人もいるが、私はそうは思わない。60年前に行われたことは良くも悪くも時代の限界を帯びる。問題があるからといって当時のことを全否定することは誰のためにもならないだろう。当時の諸限界や努力を共に見ながら「今を生きる」私たちが主体となって、より良い現在と未来を作るための思案をすべきではないか。
3.主体と構造
今日、多くの人は「植民地支配は悪かった」と考えている。植民地支配において支配する側と支配される側の間には、明らかに位相の違いとそれによる差別構造があった。一度関係の不平等さが制度的に固着すると、差別は当然視される 。
例えば、日本国内の朝鮮人には選挙権があったが、植民地(朝鮮半島)にいる日本人には 選挙権がなかった。それは「内地」優先の施工によるもので、戸籍中心主義によるものだった。
植民地支配は差別の構造を固定化し、そこには差別された人々の苦しみが存在する。いま起きている慰安婦や徴用工の問題を告発する人たちは、そうした構造のみを問題にしている。しかし、厳しい構造の中にあっても、その苦しみから逃れようとする人は必ずいるし、それを助けようとする支配者(加害者)側の人もいる。また、そうしたことがあって初めて確固とした構造を壊すことができる。
太平洋戦争のとき(私の知人である日本人の)父親は衛生兵として野戦病院で働いていたという。負傷者が次々と運ばれてくる中には当然朝鮮人もいた。戦況によっては薬やものが不足するさなか 、日本人であれば無意識に日本人を優先的に助けようという気持ち(見えない差別)が作用するだろう。しかしその人は差別しないように努力して対応したということだった。
このような例は少数かもしれないが、少数の声に耳を傾けるのは(植民地支配の)構造(の認識)を変える行動につながる可能性がある。動かない支配・被支配の構造の中で人々はどのように構造を壊すべく考え、行動したのか。私が『帝国の慰安婦』の中で紹介した事例も、そうした、構造に抗う主体を示したく呈示した。そうした努力こそ国境を超えて引き継ぐべき「普遍の価値」と思うからである。
このような主張をすると、植民地支配の構造を批判するつもりでそればかりを見て逆に守る位置にいる人々は「構造を崩す試みだ」と批判する。しかしこうした構造と主体の両方を見ることで初めて植民地支配の構造を明らかにすることができる。例えば、100人のなかで90人が差別して残り10人が差別しなかったとしても、そのことを無視することはそこに存在した崇高な魂を葬り去ることになる。構造を無視することにはならないのである。
4.近未来に向けた解決の試案
以上の認識をもとに、今後どのような形で歴史認識問題にかかわる出来事に対応していくべきかについて考えてみたい。
(1)慰安婦問題
慰安婦問題については、2015年の慰安婦日韓合意についての正しい理解と意義の確認への努力が必要である。韓国では、この慰安婦日韓合意のなかで謝罪やお金の支給が行われたこと自体が一般にあまり知られていない面がある。
文在寅大統領は、慰安婦日韓合意について、「和解・癒やし財団」を解散させたが合意は破棄しないなどと、あいまいな態度を取った。リーダーのしっかりした見識と共にメディアの役割が望まれる 。
また慰安婦の場合は、(徴用工と違って)法の外側に置かれた存在だった。そもそも不法という概念が適用できないという点も留意しておくべきだろう。
(2)戦時動員問題
先述したように、戦時動員(徴用工)問題に関連して、日韓両政府間には(関係がこじれるまでの間)協力的な関係があった。例えば、戦時動員に関する名簿の引き渡し(厚生省、法務省)、遺骨返還や海外死亡者追悼式(日本関係者の参列)、日本鋼管の解決金支給(410万円、1999年)、不二越の挺身隊への解決金(3000万円、2000年)などである。そこでまずはそのような協力を再開するところから始めてはどうか。
また、いまだなされていない作業を始めるというアイディアもある。例えば、数万人分ともいわれる当時の郵便通帳口座に残っていた金額を変換して支払いを進めることである。
両国の政府が倫理的な考え方でもってこの問題に関心を注ぐなら、この問題を契機として両国が関係改善の出発点にできるかもしれない。しかもすぐにでも実現可能なことなのである。
(3)関東大震災の惨事
2年後の2023年は関東大震災から100周年を迎える年ということもあって、これに関連したさまざまな声が出始めている。関東大震災における朝鮮人虐殺という問題は、ある意味で慰安婦や徴用問題よりもっと深刻な面を孕んでいると思う。それは普通の人々の日常的な差別感情が攻撃として表れた事件であり、そうした意味で(国家ではなく)一般人による惨事であった。
そういう意味で、そうした問題認識とともに今一度きちんと向き合うべき事柄と考える。 そうした過程で、差別感情とは何か、植民地支配とは何だったのかについて、共に議論することも可能になるだろう。歴史認識問題が提起されると、すぐにお金(補償金)のことが注目されがちだが、どのような向き合い方がいいのかは、むしろ議論と理解と記憶のプロセスから自ずと出てくるだろう。いつか、日本の朝鮮半島植民地支配全般についての日本国民の考えを国会決議の形で聴ける日を待ちたい。
(4)長期的に行うべきこと
まずは植民地支配の構造解明を後続作業としてさらに続けていくことである。植民地支配の構造には、見える支配・被支配の関係だけではなく、見えない支配の関係があるので、そうした複雑多様な面をしっかりと認識することである。
例えば、在韓日本人妻など、日本人の被害問題も議論されるべきだ。多くの日本人妻は、他ならぬ朝鮮人徴用工と結婚した。そして、朝鮮人の夫による暴力や貧困を経験した。日本人引揚者の問題も両国で議論されるべきだ。さらに、そもそも植民地統治や統治下での日常についての研究やその成果の共有も必要だ。
戦後日本のこと「継続する植民地主義」として(戦前と)変わっていないと批判する見方もあるが、戦後日本のことがほとんど知られていない韓国に、そうした見方ばかりが伝わって、ますます嫌悪や憎悪を膨らます構図がある。
これまでの両極端の立場を乗り越えていくために、加害に関しても被害に関してもこれまで見えてこなかった事実をも見届け、多様な認識を形成しうる空間として、例えば「日韓歴史克服センター」のようなものを日韓共同で設立することを提案したい。過去に試みられた歴史共同委員会は失敗に終わったが、新たな知を生み出しオープンに共有することで状況は変わりうるだろう。
(2021年9月16日に開催された政策研究会における発題内容を整理して掲載)