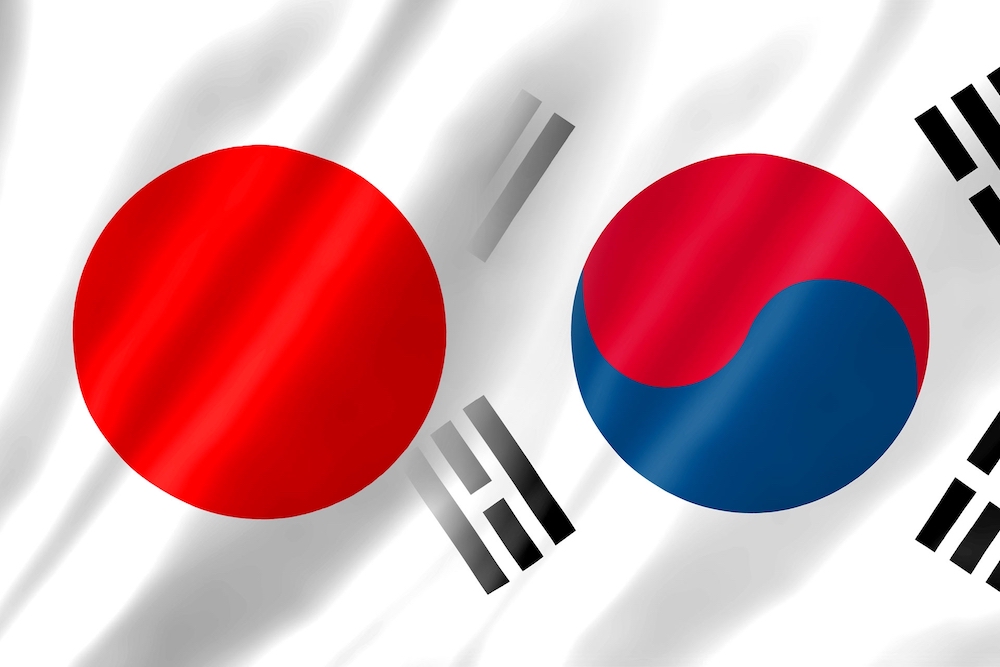第1部 政策評価からの視点
1. 経済指標から見た日本経済の現状
(1)経済成長率とその時期区分
日本は、戦後GHQ(連合国軍総司令部)による占領政策を受け、1951年にサンフランシスコ条約によって主権を回復したが、その間、1950年6月に朝鮮戦争が勃発した。この戦争は、韓国にとっては悲劇であったが、日本にとっては戦争特需によって経済復興を成し遂げるきっかけとなった。実際に、1955年の『経済白書』では「もはや戦後ではない」と謳われ、このころから本格的に「高度経済成長期」が始まり、1973年第一次オイル・ショックまで続いた。1956年から1973年までの高度成長期の平均経済成長率は9.1%で、目を見張るものだった。
その後のバブル経済崩壊までの期間(1974〜90年)は、平均成長率4.2%を維持する「中間成長期」となった。1970年代日本は、二度にわたるオイル・ショックを上手く乗り越えることが出来たのであるが、バブル崩壊後にも、その「成功体験」に基づいた経済政策を続けてしまった。すなわち、少子高齢化やデジタル化など経済社会が大きく変化する中にありながら、過去の栄光にとらわれて適切な経済政策がとられなかったために、その後の経済低迷期を迎えるようになったのではないかと考える。
バブル崩壊後1991年から2021年までの約30年間は、平均経済成長率が0.7%と低迷した。1990年代が過ぎると日本では「失われた10年」と言われたが、さらに2010年頃になると「失われた20年」と言われ、今日では「失われた30年」とまで言われている。私は、バブル経済崩壊以降の期間を「成長喪失期」と呼んでいる。
(2)GDPの推移
もう少し詳しく見てみよう。1970年代は名目成長率が12.8%と非常に高かったが、70年代前半は狂乱物価とも言われるほどの物価上昇があり、実質成長率は4.4%だった。80年代は名目成長率6.2%(実質成長率4.7%)を維持したものの、90年以降は低迷し続けた。第二次安倍政権は(2012年12月〜2020年9月)ではアベノミクスを進めたものの、それほど高い成長率にはつながらなかった。
主要国家の名目GDPについて、1990年以降の推移を比較すると(1990年値=100とし、2020年と比べたもの、IMF統計)、日本はこの30年間で約1.5倍増えるに止まった反面、韓国は約6倍に増え、中国は37倍も増えた。欧米諸国も2〜3倍に増えている。日本と中国を比較してみると、2010年に日本は中国に追い抜かれ、IMF(国際通貨基金)の2022年10月の推計によると、2022年のGDP規模は日本が4.3兆ドルであるのに対して中国は20.3兆ドルで、中国が日本の4.7倍に上っている。
(3)賃金・所得水準の変化
次に平均賃金指数の推移を見てみたい。経済開発協力機構(OECD)の統計に基づき、1990年値を100とした2020年の数値を比較してみると、日本は100を僅かに上回る程度でほぼ横ばいだが、韓国は190(つまり、1.9倍増加)、英米は140(1.4倍増加)だ。平均賃金(年収)においては、2015年に日本は韓国に抜かれ、話題にもなった。
購買力平価でみた一人当たり国内総生産(GDP)を所得水準とみなし日韓を比較すると(ドル・ベース、世界銀行統計)、1990年は、日本が19,973ドル、韓国が8,355ドルで、2.4倍の開きがあった。ところが2018年には、日本42,202ドルに対して韓国43,044ドルと逆転し、2020年には日本42,390ドル、韓国45,226ドルと差が開いた。
一人当たり名目GDPの日韓倍率(日本/韓国)で、その変化を見てみよう。日本の高度経済成長期の最後の年であった1973年に、日本は韓国の9.8倍(3,998ドル/407ドル)で最も差が開いていた。その後、日韓の所得倍率の差は次第に縮小していき、2021年には1.1倍(39,301ドル/35,004ドル)までに縮まった。
(4)日本の実質賃金低下と所得階層分布
最近の前年同月比の名目および実質賃金の増減率を見ると(2021〜22年)、名目賃金は若干増えているものの、実質賃金は21年末からマイナス状態となっており、22年末には−4%台にまでに減少した。名目賃金はあまり上がってないのに、2022年2月ロシアによるウクライナ侵攻もあり、原油や原材料などが高騰したことが大きな原因である。
所得階層別の人口分布を考慮した場合、低所得層の人口が多いため、中央値の所得水準が平均所得よりも低くなるのは、多くの国に共通の現象であり、日本も同じである。2019年の厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、1世帯の平均所得は552万円、中央値所得は437万円であり、全世帯のうち、平均所得以下が6割余りを占めている。
懸念されるのは、日本では所得水準が増加しておらず、年度ごとの分布を比較したとき、中央値が1994年505万円から2019年374万円に大幅に低下していることである。これは低所得層が非常に増えていること、言い換えると格差社会が進行していることを意味する。
ジニ係数を見てみると、当初所得ジニ係数は、1990年の0.4334から2017年の0.5594に増えて不平等が進んでいるものの、政府の再分配施策後の所得ジニ係数は、1990年0.3643から2017年0.3721とほぼ同じ数値で推移している。これは再分配政策の結果不平等の改善度が上がっていることを指しているが、実態はそう簡単ではない。所得がほとんど増加していない状況の中で、再分配前の所得不平等度は高くなっているからだ。
日本の不平等を如実に述べる短い新聞のコラムを紹介しよう(鷲田清一「折々のことば」『朝日新聞』2023年1月6日)。
「“社会が不平等になればなるほど不平等が見えづらくなる”と韓国で教鞭をとる社会学者朝比奈祐揮氏は言う。彼は収入の不平等度が近接している日韓で、日本社会の「不平等への寛容さ」が際立つことに着目する。そして韓国とは違い、不平等を前提のように受けとめるうち、各層の生活領域が「隔絶化」し、異なる環境にある人々への関心や想像力も縮小していくと危ぶむ」(「ソウルと東京でミレニアル世代に聞いた不平等と不公平」『世界』23年1月号)。
2.政策評価から見た日本経済低迷の原因
次に、「成長喪失期30年」の間、なぜ日本経済が大きく低迷したかについて、産業政策、財政政策、金融政策の観点から分析する。
(1)総論
既に述べたように、第一次オイル・ショックのあった1973年、日本の所得水準(一人当たりGDP)は、韓国より10倍近く(9.8倍)も高かったが、その後縮小して来た。韓国の高度経済成長の期間は、朴正熙政権時代からアジア金融危機まで(1963〜97年)で、日本(1956〜73年)のおよそ2倍に及び、日韓の所得水準の差は縮小に転じた。つい2018年には、購買力で表した韓国の所得水準が日本を追い抜くことになった。
現在の日本社会において、若い世代は韓流や韓国アイドルに抵抗なく溶け込んでいる半面、とくに中高年の男性世代は、今でも「日本が韓国より上」という固定観念を持つ人が少なくない。しかし、日韓の現実を直視して、時代が大きく変化していることを自覚する必要がある。これまでの日韓関係は、「非対称的関係(あるいは垂直関係)」であったが、いまや日韓の所得水準がほぼ同じレベルになってことに見られるように、「対称的関係(あるいは水平関係)」になった。このことは、韓国の専門家である木宮正史、箱田哲也などの認識とも一致している(鞠重鎬編著『日韓関係にあるべき姿』)。
日本経済は、1991年にバブルが崩壊して成長が止まった「成長喪失期」に陥り、現在も続いている。その結果、日本経済の国際的位置づけが格段に低下した。それはGDP、平均賃金、製造業生産性などの指標が明確に証明している。それにもかかわらず日本では、日本国内の指標に基づいた数値を中心に報道される傾向があり、世界の中の日本の立ち位置の低下に気付いていない人々も多いようだ。
日本の成長喪失期の原因については、「経済政策の誤謬と民間部門の萎縮がもたらした合作」と総括できよう。日本経済の展望は、マクロ的には今の大胆な金融緩和を正常に戻す「出口戦略」が成功するか否か、ミクロ的にはデジタル化の進行にうまく対応できるかどうかにかかっていると考えられる。日韓関係の改善は、両国経済の活性化や日本社会の閉塞感からの脱出にも役立つだろう。
以下、政策ごとに詳しく見てみよう。
(2)産業政策
①閉鎖的思考のツケ
日本の産業政策において、官僚集団が産業の発展に大きな役割を果たしたことは否めないが、その反面、組織の閉鎖性の問題が露呈している。日本企業や政策当局は、技術流出を憂慮するあまり、閉鎖的な産業政策を展開し、企業行動もそれに追随してきた。
例えば、1990年代、液晶テレビ分野ではシャープが世界を席巻していたが、シャープは技術流出を恐れて、三重県亀山市に閉鎖的な工場を構え、「メイド・イン亀山」で勝負に出た。それに対して、韓国・台湾・中国などの電子企業は、世界から進んだ技術を取り入れる戦略に出た。その結果、内向きだったシャープは、世界を見据えた海外企業の戦略に負けて衰退し、台湾企業に吸収されてしまった。
日本の他のデジタル企業も韓国・台湾・中国に後れを取り、その格差はさらに広がった。デジタル企業の盛衰は、日本の内向きの閉鎖的モデルに比べ、外部との意思疎通を図った開放的モデルが、より大きな成果を創り出してきたことを物語っている。
経済産業省などの政策当局も、デジタル化潮流への迅速な対応には至らなかった。世界を巻き込んだオープンな政策に転ずるよりも、日本の技術が流出されないように守るということに力点が置かれた。日本が内部固めに走り足踏みの現状維持をしている間、他国の企業に先を越された格好であった。
日本企業は、組織内に定められた規則の下で協業するアナログ産業、例えば、アナログ機械の集大成と言える内燃自動車製造をはじめ素材・部品・装備産業などに強みを発揮してきた。デジタルの進展は日本企業の立ち位置を相対的に低下させてきたし、今後もその流れが続くかも知れない。例えば、自動車産業界においてEV(電気自動車)化が進む潮流の中、デジタル化が遅れている日本の自動車産業は試練を受けることになると思われる。
昨今、グローバル化とデジタル化が同時に進み、世界の流れが急速に変わってきた。日本人はその変化を言葉で理解できても、その対応に向けた意思決定を行い実行に移すことはなかなか難しい。日本の大学ですら前例主義に阻まれて、飛躍的な変化に呼応する体制ができていないことを実感する。
こうした変化に応じた対策が出来ないことに伴う、ロスは非常に大きい。非生産的な時間または無駄な時間をより生産的なところに回すことが出来れば、もっと大きな成果が挙げられるはずだ。
②政治との関係(経済安保)
米中対立やロシアのウクライナ侵攻は、企業の技術と国の安全保障とを結び付ける「経済安保」を前面に出すことに、拍車をかけている。中国やロシアでは、民主主義・市場経済とは違う政策運営や政権交代のやり方がとられている。米中対立やロシアのウクライナ侵攻後、デカップリングと称した連携解消の動きが進んだ。とは言え民主主義・市場経済の国々同士で安全保障の名目で経済活動を縛ることは望ましいとは言い難い。
安倍政権は2019年7月、韓国大法院(最高裁判所)の徴用工判決への事実上の報復措置として、韓国を対象に輸出規制措置を講じたことがあった。政治や歴史問題を経済領域にまで巻き込んだことは、日韓関係を悪くしただけではなく、日本経済にも望ましくない結果をもたらしたことが明らかになっている。その意味からすると、2023年3月16日の日韓首脳会談で韓国向けの輸出規制措置の解除を決めたことは良い方向と言える。
日本の強みとされてきた製造業は、1990年代までその生産性において、OECD諸国の中で上位を占めていた。ところが、2000年代以降、次第に順位を下げ、最近は37カ国中16位と中位レベルまで落ちてしまった。日本の強みをどう生かすかが問われている。
個人レベル、企業レベルでは、政治的なことにあまり振り回されずに、自由な交流を盛んにし、相手を尊重するスタンスが日韓経済の活気づけに一翼を担うことになろう(詳しくは、鞠重鎬編著『日韓関係のあるべき姿』第3章参照)。
(3)財政政策
①高度成長を前提にした社会保障制度の設計
財政政策の対応失敗も、成長の足かせとなった。
日本で1973年は「福祉元年」と言われ、この年に先進的な社会保障制度を整えるようになった。当時は、少子高齢化の急速な進行についてはあまり意識しておらず、経済成長率も高く続くと想定して、社会保障制度を設計した。そのような想定の下、日本政府は分厚い給付の社会保障制度を設計したが、あいにく「福祉元年」の直後に高度成長は幕を閉じた。
経済成長が鈍化した結果(成長喪失期)、税収も低迷することになり、国の借金を増やすことになった。歳出に占める日本の社会保障費の割合はヨーロッパ諸国と比べればまだ低いものの、その額は大幅に増え研究開発費や教育などへの配分を圧迫させることに至った。今は研究開発や教育などの政策経費の割合がOECD諸国の平均以下になっている。
バブル崩壊後に本格化した少子高齢化の進行は、巨額の社会保障財源を必要としたが、経済成長は低く税収も増えなかったために、社会保障関係費をまかなうには国債発行に頼らざるを得なかった。その国債は、「特例国債」であったが、その後も続いて「特例」が特例ではなく常態化してしまった。
社会保障財源は、保険料や税収を用いるのが通常であるが、日本ではその財源が足りなかったために、多額の赤字(特例)国債を発行して充当することが国家債務を累増させた最も大きな原因となった。その背景には、設計時に高い成長を見込んで設けられた社会保障制度の下、老年層への給付水準が厚く支給される仕組みを作った政策ミスがあったと言える。
結果、それが世代間の受益・負担感の不公平をもたらすとともに、成長を阻害する方向へと働いた。世代間の不公平を是正する(動学的な最適化を図る)ことも、政府の重要な役割の一つであるが、今日の日本は世代間の不公平が大きいという問題を抱えている。
②無駄な公共支出
国家債務の累増は、少子高齢化の影響だけではなかった。1990年代初めにバブル経済が崩壊するや、莫大な国債発行に基づく緊急経済対策や総合経済政策など、大型財政支出・減税政策が行われたが、それらの政策による所得増大への効果は乏しかった。大量の国債発行に基づくその場しのぎの「注ぎ込み政策」では、景気の低迷から脱することはできないことが判明されたとも言える。つまり、付加価値の高い情報通信技術(ICT)産業への構造転換を伴う改革の推進ではなく、利用度の低い道路、展示場、会議場、休養施設の建設など、無駄な公共支出が多かったからであった。
政府支出が増加したとき、どれだけ国民所得が増えるかを測る尺度に「政府支出乗数」(国民所得の増加分を政府支出増加分で割った値)がある。その値が大きければ大きいほど、乗数効果が大きいとされる。逆に、乗数効果が低いことは、政府支出の経済成長への寄与度が低く、税収もあまり増えないことを意味する。
無駄な公共支出は、政府支出による所得増加効果の小さかったこと、すなわち、乗数効果の低い非効率的なところに財政資金がふんだんに使われたことに他ならない。そのような無駄遣いも国の借金を増やした一因となった。要するに、財政政策の対応失敗も、成長喪失をもたらす方向へと尾を引くこととなった。
③国民負担率の上昇
1965年から2020年にかけて一般会計歳出の主な項目ごとの構成推移の変化を示すと、以下の通りである(財務省資料、以下同じ)。
・社会保障関係費 14.7%⇒ 34.9%
・文教及び科学振興 13.3%⇒ 5.4%
・国債費 0.3%⇒ 22.7%
・地方交付税交付金等 19.2%⇒ 15.4%
次に、1970年から2021年にかけて国民負担率の変化は次の通りである。
・対GDP比国民(租税+社会保障)負担率 19.7%⇒ 33.8%
・対国民所得比潜在的国民(租税+社会保障+財政赤字)負担率 24.9%⇒ 60.7%
これらを見ても、国民負担率が大きく上昇している背景には、社会保障関連費や国債費の大幅な増加があったことが分かる。その反面、文教及び科学振興への歳出の割合は、1965年13.3%から2020年5.4%へ大きく下がったことがうかがえる。
日本の所得税・法人税・消費税など国税の推移を見てみよう。バブル崩壊まで(1990年代初め)は、法人税や所得税の税収が増えていたが、それ以降は低迷している。これらの所得課税とは異なり、1989年に3%で導入された消費税の税率は、1997年に5%、2014年に8%、19年に10%と順次引き上げられ、その税収は右肩上がりに増えて来た。
私の恩師で、政府税制調査会長も務められた故人石弘光・一橋大学名誉教授は、「かつての日本の財源は所得税中心であったが、その後の社会変化により所得税中心の負担だけでは日本の税体系はもたないため、所得税と消費税のバランスを取ってやるべきだ」という趣旨を主張しておられた。まさにその通りになっている。
日本の対GDP比国家債務残高も256.9%(2021年)と財政収支が悪化の一途をたどっている(IMF統計)。先進諸国と比べても、日本の国家債務残高の対GDP比はずば抜けて高く(例:米国133.3%、英国108.5%、イタリア154.8%など)成長への足かせになっている。コロナ禍により一般歳出がさらに増えたことは周知の通りである。
社会保障給付費について見てみる。社会保障給付費が急激に増え始めたのは、実は「福祉元年」と言われた、1973年からだった。現在では、社会保障給付費の総額が、132兆円(2020年)を超えている(厚生労働省資料)。一方、介護職員の不足も切実な問題と浮上した。社会保障給付費が膨張するに伴い、公共事業など他の政策経費を圧迫している。財政政策による経済成長の達成が厳しくなったことを意味する。
(4)金融政策
「大胆な金融政策」といわれる「異様な」金融緩和の運用によって、円安が加速した。それによって株価の上昇などプラスの面があったことも事実であるが、それ以上に深刻なことは、「大胆な金融政策」の帰結として国際的に見たときの日本経済の位置づけの低下である。
日銀は、「買いオペ」(日銀による国債の買い入れ)によって、通貨量(マネーストック)を増やす量的緩和を主な政策とし、国債の約半分を保有する最大保有者になった(2022年9月末時点で、50.3%)。日銀が政府の財政を支えているものの、問題は日銀の国債や株式の買い入れが民間の経済の実態と乖離している点である。
例えば、日銀は、株価下落を防ぐために株式市場に介入し、証券市場における筆頭株主として、ETF(上場投資信託)の買い入れを通じて、資金を供給し円安と低い金利を維持することに徹してきた。このような日銀の異例の介入による「官製株価」の影響が大きくなると、株式市場が実体経済とかけ離れてしまう恐れがある。
財政や金融政策は、所得水準、雇用、物価など多岐にわたって影響を及ぼすため、政策効果を簡略にまとめることは難しいが、結局は、所得水準にどのような効果をもたらすかに帰着する。アベノミクスの実績として、高い求人倍率などが挙げられるが、所得水準が高くなったわけではない。とくに日本の所得水準をドル換算で表すと、その真の姿が浮き彫りになる。アベノミクス直前の2012年に48,633ドルであった1人当たりGDPは、2022年には39,243ドルにまで、9,390ドルも下落している。
2013年3月より実施されたアベノミクスの所得水準への効果は、「国際的に見たときの日本経済の位置づけの低下」と集約できる。円建てで見れば現状維持のようにみえるが、上述のドル建ての所得水準の変化からわかるように、その大幅な低下が如実に現れている。
日本の所得水準が低下した原因は政府の経済政策の失敗だけではない。日本企業や家計の受け身的な態度も経済を足踏みさせた要因であった。日本企業は、2021年度時点でGDPにも匹敵する516.5兆円の内部留保(法人税や配当を支払った後の利益)を積み上げている(財務省「法人企業統計」)。企業が内部留保を多く抱えていることは、高収益の投資先を見つけ出していない証左でもある。資金供給が豊富だが資金需要(つまり、投資)が少ないと、金利が下がる動きにつながる。
受け身的な傾向は企業だけではなく、家計も同様であった。2021年末の時点で、家計金融資産は2,023兆円に上り、そのうち現金・預金の保有が1,092兆円と過半を占めているが(54%)、株式・投資信託の保有 が占める割合は14%に過ぎない(2021年3月末現在)。それに対して、家計の金融資産のうち株式・投資信託としての保有は米国が51%、欧州(ユーロ圏)が28%となっており、日本とはその保有パターンが逆になっている。
日本企業の内部留保の多さや家計の現金・預金保有の割合が高いことは、日本企業や家計が挑戦的な投資に消極的であることを浮かび上がらせる。このような状況下にあるため、最近日本政府は、「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げて投資を促している。
今後「大胆な金融政策」をどう転換させるかという「出口戦略」の課題が出てくる。黒田東彦・日銀総裁に代わって新総裁になった植田和男氏にとって、これまでの日銀の政策を適切に評価した上で、出口戦略が構築できるかどうかが問われている(後述参照)。
(5)三つの政策の関連性
これまで述べてきた産業・財政・金融政策は、政策間の相互関連が強い。
「産業」政策を「財政」政策と絡んで見てみよう。自民党政権は農漁村地域を支持基盤とするところも大きいため、地元企業への「財政」援助もやぶさかではない。農漁村地域では高齢化が急激に進行しているために、一人当たりの福祉財政支出も増えているが、その財源の多くは国債発行によって賄われてきた。
これらの「産業」・「財政」政策は「金融」政策とも深く係わる。地元産業への支援や福祉支出の多くが国債発行を財源として行われ、かつ国債発行の大半を日銀が間接的に引き受けるという「金融」政策が支えているからである。
タテ社会の特性を持つ日本では、組織の頂点といえる国の政策決定に、国民は抵抗できず(あるいは、抵抗せず)に従おうとする傾向が強い。そのため、失敗した政府政策に対し、国民の牽制は弱くて済むきらいがある。典型的な例として、いわゆるコロナ禍に係わる「アベノマスク」の配布政策が挙げられる。同マスクの製作・配布・保管などに、政府予算の無駄遣いや非効率性が随所に現れたが、その責任追及や効率性の高いところへの軌道修正はできないでいた。
開かれた考え方と間違ったことへの牽制力が、堅実な社会を作り上げる。
3.日本経済の課題と展望
日本経済が足踏み状態または停滞から抜け出すためにはどうすべきか。マクロ経済とミクロ経済の面から考えてみる。マクロ面からは、「出口戦略」に成功するか否か(大胆な金融緩和からスムーズに抜け出せるかどうか)である。ミクロ面からは、「デジタル化」の波に上手く対応できるかどうかである。
(1)「出口戦略」に成功するか
まず、「出口戦略」が成功するか否かが、日本経済に重要な転機となると考えられる。出口戦略とは、現在の大胆な金融緩和政策から抜け出し、正常な金融政策に戻すことを意味する。
正常でない現今の金融政策が続くことになると、いずれ破綻しかねない。自国通貨(円貨)のたが外れの増加は、自国通貨への国際的な信用失墜をもたらすからだ。買いオペ(債権の買い入れ)による金融緩和を際限なく継続することは、長期的に経済の健全な発展を阻害する。
経済構造改革とともに、国家債務の縮小または金融引き締めに絡む「出口戦略」の成功如何が、今後の経済政策展開のカギとなろう。黒田総裁の後任となった植田和男・日銀新総裁は、当面金融緩和を続けると表明した。それは出口戦略の遅れをも意味する。出口戦略の操縦がうまく効かないと、日本経済は今よりも一層厳しい局面を迎えることになるかも知れない。
大胆な金融緩和は、国債の買い入れという形で国家財政と密接な関係を持ちつつ行われてきた。出口戦略は、その逆の金融引き締めであるため、国家債務残高をどのように減らしていくかに直結する。金融引き締めは、金利(利子率)を上げる方向へ働く。そのため、膨大な国債残高を抱える日本政府としては、国債の利払い費が膨らんでしまい財政を圧迫することにつながる。国債の利払い費がかさむと、それだけ教育や公共事業支出など裁量的支出への余裕がなくなる。つまり、出口戦略の実施が「財政硬直化」を生じさせかねない。
正常な経済政策の運用に戻るには、利子率の機能がうまく働く(または政策変数として利子率が機能する)ことが求められる。利子率が0%に近く、投資コストがほとんどかからない状況が続いてきたにもかかわらず、日本企業が投資をためらっているのは、リスク回避性向が高いことを示している。利子率ゼロの状況下でも投資をためらっているところで、利子率が上がるとしたら、さらに投資を控えてしまうことを政策当局は恐れているのかもしれない。正常でない金融緩和政策と相俟って、日本企業の内向き行動も経済成長への期待を削いでいるわけだ。
岸田政権は、「新しい資本主義実現」を掲げ、「成長と分配の好循環」を打ち出したが、その実現は至難の業である。経済理論上、分配と成長は逆の方向に動きやすいという相反関係(trade-off)があるからだ。2022年5月に出された「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)では、プライマリー・バランス(基礎的財政収支)の2025年度黒字化目標が外された。つまり借金頼みの政策を続けることの意味だが、今まで同様のことを進めて果たして、分配と成長の好循環が達成できるかどうか。
政府は、出口戦略が財政硬直化を深化させ経済の低迷を一層進行させるのではないかと恐れている。現在の政策基調のままだと経済の展望は明るくない。成長を高め税収を増やす道筋が求められるが、成長エンジンを稼働できないでいることに問題の深刻さがある。
出口戦略の際、日本経済に強い衝撃を与えるハード・ランディングで景気の急な失速になるか、それとも経済への衝撃が和らぐソフト・ランディングになり、正常な経済政策の運用に取り戻せるかが肝要な課題としてのしかかっている。
(2)アナログ志向の日本企業とデジタル化への課題
次に、デジタル化対応への遅れである。日本政府はデジタル庁を設置してデジタル化を進めようとしているが、本来デジタル化は民間部門がリードする形で進んでいくもので、政府が音頭を取ったからと言ってすぐに進むものではない。実際に、デジタル庁の予算の大半は、マイナンバーカード推進費用や庁舎レンタル費用などに充てられており、本来のデジタル化推進の筋道とは離れているところが多い。
1990年代初めまで世界をリードした日本の電子産業は、今は世界競争に負け、半導体や情報通信技術(ICT)を主とするデジタル分野ではかなり遅れている。デジタル産業は失敗も多くリスクも高いが、成功すればアナログ産業よりも付加価値が大きいという特徴がある。デジタル化への対応が喫緊の課題であるにもかかわらず、日本企業は既存のアナログ的な考え方の下、パイの奪い合い商戦を繰り広げているところが多かった。
2020年初めからの新型コロナ・パンデミックの影響により、オンライン空間上の家庭内消費が大きく増加したため、企業は家庭内消費の選択肢を増やし企業実績の向上に取り組んできた。とはいえ、リスク回避傾向の強い日本企業は、デジタル化への対応に積極的とは言い難い。今後付加価値の大きいデジタル化への波に乗り遅れてしまうと、パイ(所得)を大きくする力が弱まり、日本経済の立ち位置はさらに低下しかねない。
デジタル化進行の機会を逃さず、世界でのプラットフォーム構築を強めたのが米国企業である。その代表例が、アマゾンやアップルのような米国の大手デジタル企業であり、その力を存分に発揮し業績を伸ばしてきた。世界主要企業の時価総額からしても、仮想取引空間やデジタル化における米国企業の強さが如実に現れている。
世界主要企業の時価総額ランキングを見ると(2022年1月時点)、1位のアップル、2位のマイクロソフトから10位までのうち、米国以外の企業は、サウジアラムコ(3位)と台湾のTSMC(10位)だけである。日本は、16位のサムスンよりさらに下位の29位にトヨタ自動車がようやく入っている。
現在の自動車の車種は、まだアナログ対応の内燃エンジンの車が多数を占めている。とはいえ、今後EV(電気自動車)の時代を迎えたときに、果たしてトヨタなど日本の自動車企業がデジタル型のEVにうまく対応できるかが懸念される。日本が内向きのアナログ産業にこだわる限り、他のデジタル先進国の企業と日本企業との格差はますます開くことになるだろう。
岸田政権もデジタル化への対応を進めようとさまざまな施策を打ち出している。ところが、アナログ志向の強い日本だけに、デジタル化の促進にスピードを出し切れるかが問われている。というのも、デジタル化は民間の自由な発想が尊重され、その発想を育てる環境が整わないと真のデジタル化にはつながらないからだ。
伝統的に日本の経済政策の推進は、「官がこしらえ主導し、民がそれに追随する」という「官製民追」のやり方がとられてきた。今後は、それとは逆に、官が民をサポートすることに徹し、国際的にも実績を伴うスタンスで、民の活躍の場が広がるようにすることが肝心であろう。
(3)国際競争上の懸念材料
さて、国際競争上の懸念材料について幾つか指摘しよう。
まず、日本企業の価値が伸び悩んでいることだ。世界の主な取引所の上場株式時価総額の変化を見ると(2011年と2021年の比較)次のようになっている。
・ニューヨーク証券取引所 2.4倍(28.44兆ドル)
・ナスダック市場 6.3倍(24.32兆ドル)
・上海証券取引所 3.4倍(7.96兆ドル)
・ユーロネクスト 3.2倍(7.73兆ドル)
・東京証券取引所 2.0倍(6.48兆ドル)
上記の上場株式時価総額の変化から見るように、日本の場合、株価を日銀が支えている「官製株価」という色合いがあるにもかかわらず東京証券取引所の上場株式時価総額がここ10年間他の国と比べてその伸びが小さいことがわかる。それだけ、日本企業の価値が増加していないことを表すと言えよう。
次に、日本では共働き世帯数が増えているが、世帯収入は増えていないことである。むしろ1995年以降低減傾向がみられる。実質家計最終消費支出を見ると、2005年以降ほとんど増えていない。家計の収入が増えていない分、消費も増えておらず貯蓄額も変化があまりない状況下にある。
第3に、20〜30代の若者が、将来への不安を大きく抱えていることである。とくに老後への不安の反映として、「今後の収入や資産の見通し」「現在の収入や資産」に関する悩みが50%を越えている(「国民生活に関する世論調査」より)。
第4に、国家・地域間の競争の際コミュニケーションの道具になれる英語力の低迷である。日本は2011年には44カ国中14位(上位から32%。つまり、100のうち32位)であったが、2022年には111カ国中80位(上位から72%。つまり、100のうち72位 )にまで低下した(国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」統計)。
最後に、労働移動の硬直性である。日本は終身雇用の伝統もあり、同じ会社に長年勤務する傾向が今でも強い。たとえば、2019年調査では同じ会社に10年以上勤務する人の割合は45.8%でイタリアに次いで高く、韓国(21.5%)と比べても2倍以上の高率だ(労働政策研究研修機構統計より)。長期勤続にはアナログ技術の蓄積や職の安定性というメリットがあるが、労働市場の流動性(労働力の柔軟な移動)が弱いというデメリットもあることを認識しておく必要がある。柔軟な労働移動ができないために日本社会では、自分の生産性に見合う賃金を得ることが難しいという歪みも潜んでいる。
4.総括
日本経済の「成長喪失期30年」は、「政策の誤謬と民間部門の萎縮がもたらした合作」であったと総括できよう。タテ社会の特性を持つ日本では、失敗した政策に対し、国民の牽制は弱くて済むきらいがある。日本の経済政策運用は「閉鎖的な政策実施が行われるとき、批判的な牽制力が働かないと経済は停滞する」ことを如実に示していると言える。「開かれた考え方と間違ったことへの牽制力が、堅実な社会を作り上げる」という教訓を再認識すべきであろう。
閉塞感が漂うとき、その閉塞感を打破し真の発展を進める方法が、新しい横風を入れるやり方である。例えば、韓国のダイナミズムを横風として取り入れ、日本の蓄積された知識・資本・技術を活用するやり方は、日本経済の活性化にもつながり、韓国経済にも便益をもたらすに違いない。オープンな視点に立ち、他国の良いところを受け入れて活用し、自国の足りないところを補うことが賢明な方法であろう。
第2部 日韓の考え方の比較
1.日韓の考え方の三つの軸
私は来日以来、日本と韓国社会を理解するための鍵となる概念をさぐってきた。以下は自分なりに考え抜いた末、日韓の考え方の特徴づけに有効な柱となる鍵を整理したものである(詳しくは拙著『フローの韓国、ストックの日本』参照)。
1)フローの韓国 vs.ストックの日本
2)デジタルの韓国 vs.アナログの日本
3)「広く薄く」の韓国 vs.「狭く深く」の日本
以下、それらについて簡単に説明しよう。
(1)フローの韓国 vs. ストックの日本
和辻哲郎の『風土』では、地政学的な位置がその地域・国の文化や人々の考え方に大きな影響を及ぼすと力説する。
日本は、アジア大陸の東の果てにあり、歴史的に大陸文化の終着地であった。大陸からの文化は、終着地である島国に留まり「蓄積(ストック)」される傾向を帯びる。つまり、日本は地政学的にも「ストック社会」の特性を持ちやすいわけだ。
ストック属性の社会では、既存のことをあまり変えようとせず、またそれをすぐになくそうともしないため、「静的な」属性が強く表れる。ストック社会の日本は、良いこと(例えば、技術・知識・資本など)も積みあがる半面、悪いこと(例えば、国家債務、繁文縟礼など)も蓄積される。かつ日本は静的で安定的な社会ではあるが、閉塞感に陥りやすい恐れがある。
一方、韓国は地政学的にも、朝鮮半島という大陸・海洋をつなぐパイプ(管)のような場所にあり、それらの文化・文物が流れていく(フローする)ところに位置する。韓国は「フロー社会」としての特性を持ちやすいわけだ。韓国のようなフロー社会では、周辺の情勢に影響を受けやすく、既存のことを変えやすい。かつ、活発に動こうとする「動的な」属性が強い。このような特徴もありフロー社会の韓国では、悪いことも良く変えるが、良いことも壊したりする傾向があり、不安定になる恐れがある。
以上に述べたストックとフローの特性は、一方が善で一方が悪という善悪での判断ではなく、それぞれの長所と短所という特徴を示したものであることに注意していただきたい。
(2)デジタルの韓国 vs.アナログの日本
日本でもよく知られているが、韓国人の性格を表すものに「パリパリ」(速く速く)という言葉がある。「パリパリ」の行動パターンはデジタルの速い変化に適応しやすい側面を持つ。またデジタルの激しい変化はフロー属性と相性が良い。
ここでデジタル企業や産業の事柄を指摘して見よう。デジタル企業は、巨額の富を手にし、他の企業との格差がつきやすく、浮沈も激しい。そのため雇用の不安定性も高い。さらにデジタル産業は、世界経済の情勢に大きく依存する傾向が強く、少数の成功者に富が偏りがちであるため、相対的な剥奪感に陥りやすい。
アナログの特徴の目立つ日本はどうだろうか。連続量で物事を示すアナログは、徐々に積み上がっていくストック属性と相性が良い。アナログ技術に多く依存する機械・部品・素材・装備産業は、長い期間を掛けた蓄積技術に支えられる。日本の技術は、繊細な感覚や経験で培われた「暗黙知」を通じて磨き上げてきた要因も大きい。
日本では歴史的に「一所懸命」が謳われ、自分の居場所における技術蓄積を重んじてきた。今後も蓄積技術のアナログ産業では頭角を現すだろう。ただし、デジタル化という現代の潮流のなか、生産性の低いアナログ分野にこだわり過ぎると、経済発展の足かせになる恐れをはらむことになろう。
数列に譬えてみると、日本は1, 2, 3, 4,…と自然数的な変化として段階的に進歩することを好む。ところが、デジタル化は、20, 21, 22, 23,…(あるいは1, 2, 4, 8,…)の数列のように2の自乗倍で増えていく飛躍的変化をもたらす。日本人は飛躍的変化をあまり馴染まない傾向がみられる。
デジタルとアナログが相反するもののように見られがちだが、実はそうではない。デジタル液晶画面を想定しデジタルとアナログとの関係を示してみよう。デジタル液晶画面に曲線を描く際、枡形の画素を用いて表す。液晶画面の画素を増やしていくと、その曲線のギザギザの程度が細かくなり、曲線の部分が滑らかなものに近づいている。そうなるとしても、依然としてデジタル曲線の奥にはギザギザが残ることからすると、デジタル曲線は厳密に言えば滑らかな連続のアナログ曲線にはならない。(それはデジタルの世界が、0と1の「断続」の性質を持つ二進法の表記を用いて世の中の文字や記号に対応させ、「連続」のアナログ曲線を表現しようとするからである。)
つまり、デジタル技術の進歩があり、液晶画面の画素数を増やしていくことは滑らかな曲線に近づけていくことを意味する。「デジタルの究極はアナログ」とも言えるわけだ。
(3)「広く薄く」の韓国 vs.「狭く深く」の日本
「広く薄く」の韓国と「狭く深く」の日本の特徴について、「韓国人と日本人が論争になったらどちらが勝つだろうか」という譬えをもって示してみよう。
論争対決の初期段階では、韓国人が日本人を圧倒する雰囲気になりやすいだろう。あれもこれも知っているが如く、自分の知識を力説する韓国人は少なくないからだ。一方、日本人は、「出る杭は打たれる」ことを嫌うために、「あ、そうですか? それは知りませんでした」という態度が多いだろう。
日本人の場合、自分がある程度知っているとしても、担当や専門分野ではないと、答えを控える人も少なくない。それに対して韓国人は、ある程度知っているとしたら、それについてしゃべりたがる傾向がみられる。
つまり、瞬発力の発揮も韓国人が勝り、短期戦の勝負は韓国人が判定勝ちになろう。とはいえ、日本では急な横やりが少ないため、リズムが乱れず集中できる環境が韓国よりも整っていると言えよう。
長期戦になった場合はどうか。回を重ねることになり、ある特定分野の深い議論を交わすことになると勢いは逆転する。「広く薄く」の関わり方の多い韓国人は、長時間あるいは特定分野に集中する習性が日本人よりも浸透していないからだ。
「一所懸命」に慣れてきた日本人は、自分の分野により深く携わる傾向が強い。「継続は力なり」「オタク」のように一つに没頭することに、韓国人は敵わない感じがする。つまり、長期戦は日本人が勝つ可能性が高い。
では団体戦の場合はどうか。日本人は、専門以外の周辺知識が不足している印象があるが、高い専門性を持つ人々がまとまって団体をなすと、集合体としての力が強くなり、韓国としては対抗しづらいところがある。戦争のような非常事態が発生し、「国のために」というスローガンの下に集まることになると、日本は集団として大きな力を発揮する。しかし韓国は、集結した力を発揮するのに一苦労し、意見がまとまらず分裂してしまうこともしばしば生じる。つまり、団体戦は日本の勝になりやすい。
とは言え、タテ社会の縛りの強い日本であるだけに、普段は専門知識の横断的な活用が円滑になされていない場合が多く、普段の集団としての力は一種の潜在力として隠れている。
2.目指すべきは?
上記のような違う特徴の持ち主である日韓が、目指すべき方向性はどうだろうか。
(1)三つの軸の接点探し
まず、フローの融通性とストックの安定感を併せ持つ、というストックとフロー感性の兼備が求められる。次に、デジタルの便利さとアナログの安心志向を調和させることである。これからの社会は、デジタルとアナログの融合がより力を発揮する時代が到来するだろう。第三に、「広く深く」の追求である。夏目漱石の論を借りると、「広く深く」を目指すには、「実直な経験と読書」が有効に働く。
(2)相互活用戦略=JK網の構築
タテ社会の日本は、多様な分野の専門知識が十分に活用されていないことが多い。そこで「横つなぎ」効果を発揮するには、ダイナミック性の強い韓国を活用(または韓国と連携・協力)する方法が考えられる。韓国としても、横つなぎの役割により、日本の蓄積技術や知識を活用することが望まれる。要するに、日本は韓国を、韓国は日本を活かす戦略が互いに有効に作用する。
相互活用戦略の有効性は、縦糸と横糸の譬えでも表現できる。日本は「タテ糸」にぶら下がろうとする意識が蔓延し、ヨコ糸の結び目の力が働きにくい。韓国は、ヨコ糸を広げようとする力が日本よりも旺盛であるが、タテ糸による技術蓄積が乏しく、あっちこっち飛びまわろうとする。タテ糸とヨコ糸を紡いだ「JK網」を作り世界市場に臨む方が、得るものが多く経済活性化にもつながる。
(3)異種交配論
大多数の日本企業は、異種組織との交差的交流は得意でもなく、関心も薄い。ソフトバンクの孫正義社長は「異種交配が進化を生む」と言っているが、日本企業のほとんどは彼の事業方式を真似することすら難しいところがある。しかし、より優れた発展のためには、「異種組織との横的交流」が求められる。 孫社長の言葉を借りると、「異質的な部類や違う業種と一緒に仕事をしていると、新しい発想や躍動感が生まれ、仕事の達成時間が短縮される」。
(4)東洋の直観と西洋の論理
日本では、「直観」や「なんとなく」といった感性的なことが重んじられるが、それだけでは「論理」という大事な側面が抜け落ちてしまう。「直観」と「論理」の両方を備えることの重要性について、アップル社の創設者であるスティーブ・ジョブズを挙げて推察しよう。
西洋の「論理」(ロジック)の世界に馴染んでいたジョブズは、若い時インドに旅行しながら直感の世界を味わおうとしたし、日本人の禅僧に師事して禅を学んだこともある。アップル製品には、そのような創業者の経験が活かされた「東洋の直観と西洋の論理」が組み合わさったところがあり、アップルの本質的な強みとして働いてきたと言えよう。
(2023年2月15日、IPP政策研究会における発題内容を整理して掲載)