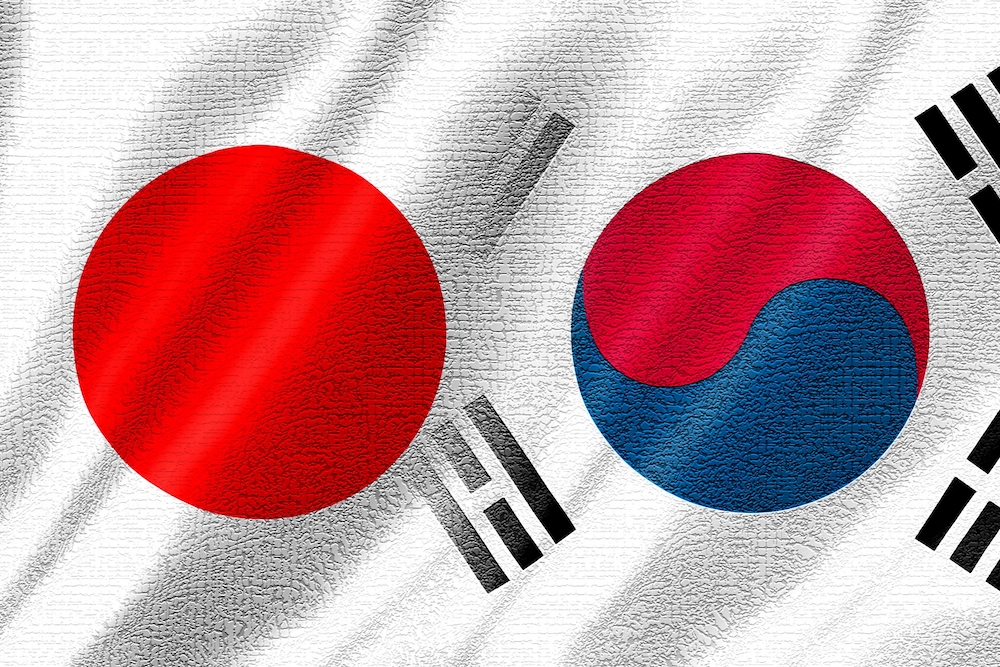序:現代のグローバルな問題系
現代におけるグローバルな問題系と言った場合、個々人の立ち位置によっても違ってくるだろうが、多くの人々の共通の問題系としては、地球環境破壊、蕩尽、差別、搾取、収奪、戦争、暴力などが挙げられると思う。そのようなさまざまな問題系の中で、一体何が「悪」だろうか。思いつくままに対比する形で列挙してみよう。
資本主義←→脱成長?社会主義、共産主義?
植民地主義←→内発的発展
科学革命←→匠、自然主義、天台本覚思想
一神教←→仏教、神道
普遍主義←→多様性、特殊論
原理主義←→相対主義
理性←→感性、身体、霊性
デカルト(二分法)←→アニミズム
主客の分離←→主客合一
文明←→文化
進歩←→循環、還流
西洋←→非西洋
個人←→共同体
現代の価値観で言うと、前述の対比のうち、おおよそ左側=悪、右側=善と見なされ、右側が悪に対する対抗軸となりうるものと考えられている。
例えば、資本主義に対する社会主義や共産主義が善かどうかについては、疑問を呈する人も多いであろう。しかし最近、斎藤幸平著『人新世の「資本論」』が何十万部も売れるなど、(日本では社会主義や共産主義を信奉する人はほとんどないと思うが)、脱成長やSDGs批判を考える枠組みとしての社会主義に対して、その復活を狙っているような傾向が現れている。
もちろん前掲問題系の中にはきれいな二項対立にはならないものもあるが、このような対比的思考は、本当に正しいのだろうか。この視点は、現代の中国や韓国をどう見るかということともかなりリンクしている。つまり「対抗近代(Counter-Modernity)」という強力な動きから現代の中国や韓国を見つめなおすことで、その本質をとらえることができるのではないかと考えている。
1.対抗近代
(1)近代への「反発」と「あこがれ」
いま、洋の東西で同時に起きているのは、「対抗近代」とでもいうべき動きである。ヨーロッパは、自らが生み出した「近代」という思想に対して甘く見すぎているのではないか。つまり、「近代が終わった」などと甘く見ているようでは、現代のグローバルな問題系を正しく捕らえることはできない。「近代」にはあらゆる問題系が入りこんでいると言ってもいいだろう。
近代というのは、欧米と日本が主役となった時代であり、地球上のそれ以外の地域は「近代」によって支配されてしまった時代であった。逆に支配されてしまった側(欧米と日本以外の世界)から言えば、近代とは「怨嗟の近代」であった。そしてヨーロッパの欺瞞性がいま、あらわになりつつある。ヨーロッパは近代をつくったにも関わらず、あたかもそこから逃げようとしている、あるいは米国にすべてを丸投げしようとしているかのようにさえ見える。
欧米は自らの「成功」と、東アジアの「失敗」を対比したがる。例えば、歴史問題について言うと、フランス・オーストリア・ポーランドなど隣国が比較的寛容であったこともあり、ドイツだけではなくヨーロッパ全体が歴史問題をうまく解決できたのに比べ、東アジアでは失敗したと(欧米諸国は)考えている。しかし私は、むしろ逆に東アジアの成功と欧米の失敗があらわになりつつあるのではないかと見ている。つまり、欧米では、移民問題、資本主義の暴走など、欧米の失敗が顕著になりつつあり、現在の世界は、それを隠蔽しようという欧米の戦略の崩壊過程であるといえる。
「対抗近代」は、近代に痛めつけられた側の考えだが、そこには「近代への反発」と「近代へのあこがれ」が混在している。非西洋諸国は、一度は思い切り自由になり、欲望を解放し、自然を破壊し、豊かになりたいという近代的欲望を抱くわけだが、その欲望を過小評価してはならない。今日、そうした彼らの欲望をSDGsなどの美名によって押さえつけてはならない。近代で主役になり、自然を破壊し、植民地支配した側が、後発の途上国が同様の道(近代化)をたどろうとするときに、それをどうやって(どのような論理で)押さえつけることができるのかということである。非西洋諸国も欧米のようにグローバリズム(近代化)をやりたいが、それができないのなら、反近代の道を選択せざるを得ない(例えば、イスラーム普遍主義)。いずれにしても、非西洋諸国の動きは、「近代への反発」であると同時に「近代へのあこがれ」ということになる。
(2)中国・韓国と日本の違い
中国は、いま思想的に「対抗近代」の軸を模索している。一つは、儒教の世界思想化である。儒教が世界思想であるということを広く打ち出そうとしている。もう一つは、かつて中国は自らを「途上国」と規定していたが、いまや「大国」と称するようになった。途上国とは、近代の側(欧米)には入らないという意味だが、中国はいま「近代を経済的に成し遂げた対抗近代の大国」として、自国を打ち出そうとしているのである。
韓国はどうか。韓国は(民主主義、資本主義の観点で)すでに先進国のレベルに達しているが、近代の側(先進国)につこうか、あるいは対抗近代の側(近代を糾弾する側)につこうかで迷っており、分裂し混乱している状態だ。韓国政治で言うと、文在寅政権側の左派は後者(対抗近代)であり、保守派は前者(近代側)といえる。
それでは日本をどう見るべきか。地理的には東アジアに位置しているものの、日本人の世界観は、中国人や韓国人のそれとはだいぶ異なる。日本は、群島的な文明を持つ。群島的文明は、中国の大陸的文明から見ると、「非文明的=非大陸的」(文明がない状態)となるが、私は「群島的文明」があると見ている。なぜ日本は非文明的に見えるのか。それは(演繹的な大陸文明に対して)群島的文明が帰納的だからだ。日本に文明があると考えているのは日本人だけで、東アジア的な大陸文明観(中国・韓国)からいうと、日本は非文明的としか見えない。
とくに日本の家族システムは、東アジア的文明から見ると非文明的に映る。人類社会の最小単位である家族がどのような成り立ちをしているかが、(文明を序列の視点から見る中国文明においては)その社会の文明的序列を考える上で重要なポイントとなる。儒教的意味での厳しい性倫理を体現していない日本の家族システムは、非文明的で、不潔で、乱雑に見えるのである。
ある比較家族史学の専門家の話によると、韓国の比較家族史の専門家に「日本は乱倫だ」と言われショックを受けたという。中国や韓国の家族システムから見ると、日本の家族システムは乱倫と言わざるを得ない面がある。例えば、養子を姓の違う家から取ることを厭わず、いとこ同士の婚姻があり、兄の死後弟が兄嫁と結婚する習俗などがある。これらは儒教的な性倫理からすると、非常に非文明的なのである。
また韓国の比較家族史の専門家は、「韓国の家族システムは文化的であるのに対して、日本のそれは生物的(≒動物的)だ」とも述べた。このような認識は、中国や韓国の学者の中に、現在でも厳然と存在している。それを蔑視・差別だということも難しい。家族という最も基本的で、身近で、根本的単位について、彼らは自分たちの社会のありようこそが、文明的に最も高いと考えているので、彼らに対してそれを差別だからやめろということは難しい。
併合植民地時代に朝鮮の同族部落(同じ姓の人たちだけが集住する集落)に対して、当時の日本は「朝鮮の家族システムは原始的だ」と理由づけして、日本式の家族システムに変えようとした。当時、日本は自分たちの家族システムこそ素晴らしく、序列的に高く、韓国の家族システムは文明的に低いという価値観を持っていた。こうした思考は非常に危険だ。
人類の家族には多様な形態がある。エマニエル・トッドは世界のさまざまな家族形態を学問的に分類してはいるが、そこにはやはりフランス的な家族形態が文化序列的に優れているという価値観が根底に潜んでいる。
中国や韓国から見ると日本が非文明的だと見えてしまう根本には家族の問題がある。なぜかというと、家族は性の問題と直結しているからだ。性のタブーをどこにおくか。日本の家族システムには近親相姦を根本的に否定しないという考え方があり、それが中国や韓国からすると非文明的に映る。しかし「非文明的」というのは、あくまでも括弧付きのものであって、大陸文明的=儒教文明的でないという意味での規定にすぎない。日本人は、「生物的」に生きているわけではなく、「日本文化的」に生きているのである。日本文化的に生きていることを、生物的に生きていると規定することは、根本的に危険なことである。
(大陸文明である)中国や韓国の発想は、シャーマニズム的でもある。シャーマンとは超越的な天と地を垂直的に結ぶ存在であるがゆえに、シャーマニズムはあくまでも垂直的概念だ。韓国は、土着的なシャーマニズムと朱子学の影響で大陸的文明の傾向が強い。一方、<アニミズム>には、シャーマン的存在はない。
2.<アニミズム>
(1)日本的<アニミズム>
一般に理解されている「アニミズム」は、(英国の人類学者エドワード・バーネット・タイラーが唱えた)森羅万象にはアニマ(anima;生命・魂の意味)、生命エネルギーが宿っているという世界観だが、私はそれと< >つきの<アニミズム>とは全く異なる思想であると考えている。
それでは私の考える<アニミズム>(以下、<アニミズム>と表記)とは何か。
<生命とは、偶発的なものであり、いつどこに生命が立ち現れるのかは、演繹的に決まっているのではなく、共同体の成員の共同主観によって帰納的に判断されるのだ>という考えである。
これ(人、木、石など)が生きているか、生きていないかは、演繹的に決まっているのではない。例えば、この石の定義はこうだから、その定義に基づけばこの石はこのように位置づけられるから「生きている」あるいは「生きていない」のだと、演繹的思考様式によって意味づけするのではない。この石とあの石を比べた時に、こちらの石の方が神々しいから、この石は生きている(神)が、あの石はありふれた石に過ぎないと考える。
共同体の成員がよってたかって、過去からの知識と経験を重要視しながら、「この石は神であるが、あの石は神でない」と帰納的に決めていく。日本の神道は、もともとこのような考え方を基礎にしていたと思う。
日本の神は「八百万の神」と言われるが、すべての森羅万象が神だと考えているわけではない。日本的<アニミズム>とは、すべての森羅万象が神だというのではなく、この石は神だが、あの石は神ではないというように区別する。みんなで合議して決めていくプロセスを大切にする。合議の結果、これが大切なものだとなれば、それを特別視するのである。
日本ではアニミズム思想に基づき木を切らないということはない。日本人の自然尊重の考え方は、自然を大切にするから自然そのものである木は一切切らないといったタイプのものではなく、この木は切ってもいいが、あちらの木は切ってはいけないと、弁別・区別する。これが日本的<アニミズム>なのである。この点が重要だ。
(2)偶発的生命と美的感性
さきほど示した<アニミズム>の定義の中にある「偶発的」とは何か。(演繹的思考ではないので)何が生命であるかはわからないから、みんなで合議して決めていこうという世界観である。しかしそのようなやり方で政治を行うと、非常にややこしくなる。現在の日本政治はまさにその典型だが、ああだこうだとみんなで考え議論するばかりで、結局は結論が出ない。演繹的ではないからだ。前提とすべき道徳、原則、前例を決めてかかれば、結論を出しやすいので楽だろう。日本の政治は「前例主義」とよく言われるが、そうではない。本当に前例主義であれば、もっと簡単に結論を出せるはずだ。むしろ日本は、世界に冠たる合議主義といっていいだろう。いつまでも議論を続ける。
エマニエル・トッドは、「日本人をずっと観察してみたが、何かを結論を出して行動することが嫌いで、いつまでも議論をしたい人たちだ」と言った。日本に民主主義がないというのは間違いで、ずっと<アニミズム>的民主主義をやり続けてきたのである。
日本的<アニミズム>には、統合的、普遍主義的、全体的な世界観が欠如している。何が根本的基準であるかが不明であり、第一の基準が何で、第二の基準がなんだというように、基準の階層構造が全くないために、行き当たりばったりに、ずっとわけのわからない議論を続ける。
日本的<アニミズム>の考え方とは対極にある考え方に、スピリチュアルなものからすべてが階層的に出てくるという考え方がある。それは宗教にもなるだろうし、民主主義のやり方にもそのようなものがあると思う。
例えば、ドイツ憲法は、まず根本的な憲法的原理があって、そこから一切のことを導出するという考え方である。ドイツ憲法はその第1条で「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、保護することは、すべての国家権力の義務である」という根本原理を示し、あらゆる原理はそこから演繹的に導き出されてくるのである。しかし日本人にはそのような発想がなかなかできない。そのため普遍主義や一神教的宗教がなかなか浸透しない。日本人はいつでも部分的・帰納的に考える。
日本的<アニミズム>は、合議(の決定)に参加できない人をなかなか包摂しにくく、村八分的に排除されてしまうという同調圧力的傾向を強く持つ(他者の排除)。普遍主義的な人権・博愛・平等・人道などという抽象的観念よりも、ひととひととのふれあいという感性によって共同体をつくっていこうとする日本的<アニミズム>は、同調圧力が強いだけではない。今回のコロナ禍のような緊急事態においては、手間暇をかけて帰納的にボトムアップでものごとを決めていく日本的<アニミズム>のやり方が、非効率的で後手後手の対策に終始してしまうという欠点をさらけ出した。
人間関係や組織、共同体、国家を理念的に把握することが苦手なので、抽象的理念を振りかざして迫ってくる相手(例えば、戦前の全体主義理念や、近年の韓国の歴史認識論争など)に対して、きちんと抵抗したり応答したりできない。つねに帰納的に、<アニミズム>的に考えているからだ。
ものごとを普遍主義的な理念ではなく、美的な感性でとらえるだけで生きていける、というのが日本的な生き方だ。そのような日本的<アニミズム>の信念は大変強靭ですばらしいが、それなりの弱点も持つ。これは付け焼刃的なものではなく、1000年以上の歴史のある強靭な世界観である。
ただ、そのことに負の価値を与えるだけでなく、私としては、普遍主義的で超越的な価値をもとに社会をつくっていくという大陸文明的なやり方とは異なる、群島文明がもつ「もうひとつの世界観」の可能性に賭けてみたいと考えている。
日本的<アニミズム>は、かつて梅棹忠夫が『文明の生態史観』で唱えたことと若干似ている。梅棹の場合、中国・ロシア・インド・中央アジア(第二地域)は他成的に文明が生成発展したが、日本と西ヨーロッパ(第一地域)だけは自成的に文明が生まれたと考えた。私はそれをもう少し思想・哲学的に表現した。すなわち、大陸文明は普遍主義的、超越的な価値をもとに演繹的に社会をつくるが、群島文明は構成員それぞれが考え、議論して帰納的に決めていく社会である。
3.三つの生命
(1)肉体的生命・霊的生命・美的生命
私が考える三つの生命を整理すると、次のようになる。
<第一の生命>=生物学的生命、肉体的生命
私という存在に一個だけあるとされている生命である。肉体的な生命、生物学的な意味での生命である。
<第二の生命>=霊的生命
キリスト教でパウロのいう「霊による生命」、神を信じることによって永遠に生きるスピリチュアルな生命である。中国哲学でいう「気」もそうで、永遠に生きる普遍的で霊的な生命だ。「気」とは、物質なのではなく、霊的物質を意味する。
中国では、物質の根本である「気」がスピリチュアルな面をもつと理解したために、西洋のデカルトの物心二元論のように、霊と(スピリチュアルな面を持たない)物質とにはっきり分離できなかった。加えて、分解の仕方においても、アトムのような最小単位形式に分解せず、五つ(五行)にまでしか分解しなかった。そのため歴史的に近代科学の発展がみられなかったのではないかと思う。
日本仏教に関して言えば、とくに浄土真宗では永遠に生きる霊的生命を「阿弥陀信仰」として信仰した。(キリスト教伝来以前に)阿弥陀信仰が普及したことが、日本にキリスト教信仰がなかなか根付かなった理由の一つではなかったかと思う。
<第三の生命>=美的生命
先述した日本の<アニミズム>的生命である。実体がなく、どこに立ち現れるか、どこに美が立ち現れるかわからない、偶発的生命である。
(2)客観的生命・主観的生命・間主観的生命
別の言葉で表現すれば、次のようになる。
<第一の生命>:客観的生命、相対的生命、物質的生命、個別的生命
<第二の生命>:主観的生命、絶対的生命、宗教(精神)的生命、普遍的生命、非物質的生命、集団的生命
おそらく人類は、肉体的な生命の消滅に対する虚無感、生命があまりにも簡単に消滅してしまうことに対する悲しみや苦しみから、「これとは違う生命があるはずだ」ということを考え出したのだろう。どの文化圏にもおそらくそういうものはあると思うが、最も強力なタイプの非肉体的な生命というのは、キリスト教における「霊のいのち」という規定だろう。
新約聖書「ヨハネによる福音書」6章63節にすでにその規定は出ているが、それを最も完璧に定式化したのは、パウロによる「霊のいのち」という概念である。パウロは次のように説明した。あなた方が両親からもらった肉体的な生命というのは有限であるけれども、神によって与えられた「霊のいのち」は永遠に生きるのだ。この「永生する生命」の魅力は、その後、人類をとらえて放さない。
だが、キリスト教にはもうひとつの伝統があった。それはパウロではなく、イエスのキリスト教である。そもそも新約聖書に記されたイエスの奇蹟とは何だったのか。病気を治したり、湖の上を歩いたりしたというのは、作り話なのか。そうではない。
奇蹟とは、その場に居合わせた人々が、イエスが病人を癒したり湖の上を歩いたりするのを、まさにこの目で見たという驚きの記録なのである。そこにいた人々が全員、まさに共同主観的に、イエスが偶然そのような行為をする知覚像を立ち現わした、という主張なのである。
つまりこれは、イエスの周囲に神々しい<第三の生命>が偶然に立ち現れたという意味なのである。キリスト教の歴史では、ともするとパウロ的な霊(スピリット)による<第二の生命>の宗教性が強く語られがちだ。だが、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンやアッシジの聖フランシスコ、エックハルトやキルケゴールのように、イエス的な<第三の生命>の宗教性を強調する者も絶えず出現してきた。
<第三の生命>:間主観的生命、偶発的生命、「あいだ」的生命
人類にとってもともとは、<第三の生命>こそが、本当の「いのち」であったのではないかと思う。<第三の生命>の方が、原初的な生命観であって、むしろ<第一の生命>は、のちに発明された観点だと思う。ところが人類は<第一の生命>を発見してしまったために、原初的な生命観(<第三の生命>)を捨ててしまった、あるいは軽視してしまったのではないか。
動物を飼っている人は、この点について理解しやすいかもしれない。飼い犬に、おまえの生命は何かと聞いて、もし犬が答えられた場合、「自分の体に一個の生命が宿っている」とは言わないと思う。犬を観察すると、飼い主が帰ってくると飛びついてくる。これが犬にとっての「いのち」だ。それを「犬は飼い主が帰ってきて嬉しがるという行動をしている」と記述するのは、近代に入ってからのことである。犬にとっていつ飼い主が帰ってくるかはわからないが、突然(偶発的に)帰ってきたので、ぱっと喜んで尾を振りながら出迎えたのである。これが「いのち」であり、動物の世界だけでなく、人間世界にもこういう「いのち」はあった。
生物(人類)の発生史から言うと、<第三の生命>、<第一の生命>、<第二の生命>の順序で、「いのち」が発見された。ところが、近代以降、ほとんどすべてが<第一の生命>になってしまった。ここに問題がある。
(3)ひとつひとつのいのち・すべてのいのち・あわいのいのち
あるいは、つぎのような分類も可能だろう。
<第一の生命>:ひとつひとつのいのち、このもののいのち、それ自体のいのち
<第二の生命>:すべてのいのち、(個別性を)のりこえるいのち
<第三の生命>:あわいのいのち、立ち現れるいのち
犬ががぱっと立ち上がって飛びついてくる「いのち」。英語圏でlifeという言葉を使うときも、この<第三の生命>観が生きていると思う。例えば、サッカーの試合を評して、「この試合は生きている」「この試合は死んでいる」「この試合は生き生きとしている」「あのシュートがいのちを与えてくれた」などと表現することがある。これは単なる比喩ではなくて、人類が太古よりもっていた生命感覚を忘れずに、いまだに持っていることの証左でもある。そうでなければそうした現象を「いのち」と表現しない。
スポーツや芸能についてわれわれは、「これは生き生きとしている」「この役者のしぐさがいのちを与えた」などとも表現する。これこそが本当の「いのち」である。血圧や血糖値などに示される医学(生物学)的な意味での「いのち」は、どこかで終わってしまう。近代によって支配的になった第一の生命観によって、社会の統治がしやすくなった半面、人間の発想ががんじがらめになってしまった。冒頭に述べた対抗近代の宗教的な側面(たとえばイスラームの伸張)には、この第一の生命による支配に対抗するという意味がある。
(4)孔子の「孝」は<第三の生命>
私は以前、『新しい論語』(ちくま新書、2013)で、<第三の生命>という新しい概念を提唱し、孔子の新たな解釈を示した。孔子のいう「仁」や「孝」は、私の分類でいうと、<第三の生命>のことであった。
孔子は、弟子に孝とは何かと聞かれ、次のように答えた。
息子が父親の体のことを中心に養ったりすることは、人間でなくてもできる。孝においては、そのような<第一の生命>が重要ではない。お父さんと息子の間に「敬」というすばらしい雰囲気が立ち現れれば、それこそが「孝」なのだ。つまり<第三の生命>が孝なのである。
ところが、孔子の死後、「儒家」という思想集団が形成された。孔子が生きている間には、儒家という集団はなかった。孔子の弟子の曾子という人の系統から、親から子どもに連綿と引き継がれる生命というものは永遠だという考え方がでてきた。これが儒家の唱えた孝という生命観で、戦国時代になると、個人的・肉体的な生命つまり<第一の生命>を乗り越える何らかの別のタイプの「永生する生命」があるということが唱えられるようになった。儒家は、戦国時代に巨大な統一帝国をつくるために資することのできる言説を孔子の思想から抽出して、孝を天という超越性と結びつけて編集しなおした(『孝経』)。それゆえ、『孝経』は孔子の<第三の生命>的な孝を<第二の生命>的に変質させたものである。
実は、孔子は孝を天と結びつけたことはなかった。孝とは、父祖と子の間に立ち現れるいい雰囲気、いのちのことをいう。孔子の観点から言うと、先祖のために供え物を捧げることが孝ではない。しかし儒家の観点になると、孝が天と結びつくために、『礼記』や『孝経』に書かれているような儀式や体を傷つけてはいけないなどの教えが出てくるのである。
<第三の生命>は、和気あいあい、もののあわれ、アウラ(Aura、ベンヤミン)などと同様に、あいだのいのちのことを言うのである。あるいはもう少し広範な言葉で言えば、「美」となるだろう。それらは譬喩ではなく、生命そのものなのである。
このような考え方が、日本的<アニミズム>の根幹にある。これを理解することは、非常に難しい。昨今の日本人は、肉体的な<第一の生命>が「いのち」だと思い込んでしまっている。
どこに美しさ、アウラ、いのちが立ち現れるかわからないが、一瞬だけでも人と人とが面と向かって、人とものが見つめ合って、「ああ、あいだに<いのち>が立ち現れている」と思った瞬間、その瞬間の喜びだけで生きていけるという感覚を技として生きて行く。これが重要である。
逆に言えば、私たちの生は、政治権力と普遍的宗教とに、それほどぎりぎりまで追い詰められているのである。政治権力は<第一の生命>を掌握しようとし、普遍的宗教は<第二の生命>を支配する。前者は近代側、後者は対抗近代側を代表する。このことが私たちの生の閉塞感を増幅させているのである。いま、そのような自覚がなくてはならない。
4.日本の美意識と生命感覚
日本文化は、もともと生命を普遍的には定義しなかった。日本に律令体制が定着しなかったのは、基本的に生命を普遍的・演繹的・本質主義的に定義する、そして統治して収奪するようなタイプの思考、世界観が、群島文明たる日本には合わなかったからだろうと思う。
日本では平安時代以降、「をかし」「あはれ」「幽玄」「わび」「さび」「いき」などの美意識が独自に発達した。この動きの全体をひっくるめてひとことで言えば、それは「普遍から特殊へ」という運動だったと思う。
そしてそれは「生命とは何か」という問いに対しても、日本文化の特殊主義から応答したものだったのではないか。中国や朝鮮半島からの強い影響を受けて飛鳥時代から奈良時代にかけて花開いた仏教文明、儒教文明、道教文明の洗礼を日本文化は吸収した。
それらの文明は、それぞれの仕方で人間、社会、世界、歴史、生命などを論理整合的に高次のレベルで説明している。日本文化は、それらの普遍的な説明体系を積極的に受け入れ、あるもの(例えば、奈良仏教における華厳・唯識など)は学問的に純粋化し、別のあるものは習合させて神道という宗教的枠組みに溶け込ませたりした。
それらの思想界の大きな動きと密接にかかわりながら、日本文化の底流においては、中国的・インド的な大宗教(仏教・儒教・道教)とは異なる、原始的な土着信仰の世界観がつねに脈々と生き続けてきた。それをひとことで言うなら、<第三の生命>観なのである。
そしてこれは、仏教や儒教、道教が日本に流入する前の、原始的な<アニミズム>の生命観に源流を持つものだった。大宗教は普遍性を標榜するので、つねに生命を普遍的に説明する。儒教や道教で言えば、それはひとつの「気」の働きによるものであるし、仏教で言えばそれはすべて「輪廻するもの」であり、輪廻から脱することが解脱=さとりである。
ところが原始的な信仰には、そのような普遍的で整合的な「生命の定義」がない。とくに日本的<アニミズム>において生命とは、偶発的に立ち現れる現象なのである。
「をかし」や「あはれ」というのは、そのようなアニミズム的な<いのち>つまり<第三の生命>を、清少納言や紫式部という平安時代中期の貴族階級に属する女性が言語化した言葉なのである。
これは<いのち>なのであるから、極端に言えば彼女たちにとっては、「をかし」や「あはれ」という感覚を自然や人間関係、社会において感じ取ることさえできれば、それだけで生きていけるという信念があったのだろう。
一般に「をかし」とは、「こころひかれる、おもむきがある、風情がある、かわいい」などという意味を表わす客観的・批評的な美意識であり、「あはれ」とは、「しみじみとした情趣」を表わす美意識とされる。いずれも日常のふとした瞬間に立ち現れる偶発的な情感である。
それを簡潔に説明すれば、「あはれ」とは、あいだのいのち(<第三の生命>)が立ち現れたことを意味し、「をかし」とは、あいだのいのちが立ち現れる予感がするという意味になる。それゆえ、紫式部と清少納言は仲が悪く、紫式部は、清少納言について「なんか知的な女ぶっていて、いやだ」と表現していた。それは清少納言が「をかし」を重要視したためだ。
清少納言は、あいだのいのちが立ち現れる場面をいろいろ調べて、その一つとしてたとえば「春はあけぼの」と言った。つまり自分の感性を全開にしていると、もしかするとここに、<いのち>がぽっと立ち現れるかもしれないという予感がする、それを清少納言は「をかし」と表現したのだ。彼女は、いろいろと吟味し、立ち現れる蓋然性を推論する思考様式のタイプなので、はたから見ると知的に見える。
一方、紫式部は、どういうときに<第三の生命>が現れるだろうかという推測が重要ではなく、現れた瞬間の驚き(偶発性)が重要だと考えた。紫式部も「をかし」を使ってはいるが、どちらかというと「あはれ」を多用するのは、ここに<第三の生命>が思いがけずにぽっと現れたという驚きを重視したからである。清少納言のように、いつも「春はあけぼの」が最もあいだのいのちが立ち現れる予感がすると言っているようでは、知的なふりをしているだけの女性に過ぎないと紫式部は考えた。「あはれ」と「をかし」の関係は、単なる感傷性と客観性の次元の問題ではないのである。
それは<いのち>を感じ取る深さ(あはれ)と浅さ(をかし)の関係でもあるし、感傷的に感じ取る(あはれ)のか、知的に感じ取るのか(をかし)の違いでもある。また<いのち>への距離感(あはれは没入し、をかしは離れる)でもあるが、根本的には<いのち>への接近の前後関係(をかしが前段階=予感で、あはれが後段階=生成)なのである。
※ここまでの叙述は拙著『群島の文明と大陸の文明』(PHP新書、2020年10月)との重複が多いことをご寛恕いただきたい。
5.日韓関係を考える視座
(1)甘すぎる日本の韓国認識
私は近著『韓国の行動原理』(PHP新書、2021年7月)の中で、韓国の行動原理について詳しく述べたが、ここではその一部を紹介する。
この二十数年の間に、日本人の朝鮮半島認識の質は、全般的に言えば、飛躍的に高くなったと思う。それ以前は主に、朝鮮語・韓国語を解しない学者や評論家たちが、偏ったイデオロギーによって「分析もどき」をしていただけと言ってもよい。例えば、北朝鮮は(地上の楽園で)すばらしい、韓国は軍国主義でダメだというように、信念体系を表出することが多く、何らかのエビデンスに基づいた議論ではなかった。
ひとことで言って、二十数年前までの日本における韓国・朝鮮認識は、政治的メッセージそのものであり、実態とは乖離しており、認識というよりは信念体系の表現であったといってよい。そして今日でも、日本の韓国認識はある意味で客観的にはなったが、非常に甘すぎると思う。韓国はある面で、日本よりも先を行っていると言ってもいい。嫌韓や韓国を下に見る人たちは、あっと驚くような事実を知らないといけない。
(2)二項対立による韓国認識
韓国を正確に認識するにはどうすればよいか、韓国の主役はだれなのか。
韓国政治を思想・哲学からみると、東学と北学の軸があって、そのダイナミズムのなかで韓国の政治・社会が動いている。東学は道徳性を重視し、北学は合理性を重視するが、その二つの軸のせめぎ合いによって、韓国のダイナミズムが生まれている。
また対抗近代の観点から言うと、(ダイナミズムと表裏一体の)韓国の混乱は、近代と対抗近代の対立によって生じている。つまり、帝国主義が支配した側につくのか、対抗近代(被支配)の側につくのかという軸を中心に対立が生まれている。この点の理解が重要である。
明治以降の日本近代は朱子学化したために、大陸文明的、演繹主義的な世界観を持つようになり、それ以前の群島文明が大きく破壊されてしまった。日本で最も大陸文明的なのが左翼の人々で、徹底的に演繹的にものごとを考える。
韓国人は道徳志向性が強くよく道徳を叫ぶが、それは彼らが道徳的だからではなく、道徳が重要だとの認識があるからなのである。道徳を叫ぶことと道徳的に生きることとは、まったく別問題だ。ところが日本の左翼の人は、韓国人は道徳を叫ぶから道徳的民族だと思い込んでしまった。そして韓国人が「日本人は不道徳だ」と叫んでいるのだから、日本人は不道徳だと思い込んでしまった。道徳を叫ぶ人が、道徳的なわけではない。もちろん道徳的なこともあるが、私の経験からしても、道徳を叫ぶ人は道徳的でない人が多い。韓国人が、道徳的でないと言っているのではない。韓国人が道徳を叫ぶことと、道徳的に生きることとは、別問題という点が重要だ。
日本の左翼は、在日、朝鮮人が道徳的で日本人が不道徳という視点を死守してきた。このような考え方は、むしろ韓国・朝鮮人を蔑視しているといえる。日本の植民地統治に対して、朝鮮人はすべて抵抗心を持っていたかといえば、そんなことはない。左翼は自分たちの目的のために歴史を画一化してしまった。
このような二項対立(道徳的な韓国・朝鮮と不道徳的な日本という認識)は、歴史について何も語らないだけでなく、虚偽の歴史を捏造し、韓国人・朝鮮人・在日の生の多様性と主体性を無化して、それを単なる利用対象としてしまった。これこそ蔑視ではないか。
(3)嫌韓派言説の特徴
またこれと対抗するかのように、日本保守側の「朝鮮半島認識」にも、蔑視の領域に属するものが多い。それを尖鋭化したのが、いわゆる嫌韓派の言説だが、これには民主的な社会の公的空間において到底容認できないレベルのヘイト的なものが多く、実に嘆かわしい。
嫌韓派の主張には、論理的に正しい部分もあるが、それがヘイト的になると、許されるものではない。それほどでなくても、保守側の認識は、韓国・朝鮮を蔑視、軽視したり、あるいは日本の論理に従えという枠組みが多く、これはよくない。
伝統的に日本人が持っている韓国・朝鮮への強い差別意識の土台の上に、この二十数年のあいだに蓄積された客観的で高度な朝鮮半島認識が都合よく加味されているのが、この嫌韓的言説の特徴である。つまり嫌韓派は、この二十数年の間に日本で蓄積された、右でも左でもない客観的な認識を表面的に取り込むことによって、あたかも自分たちの認識は客観的であるかのように思いこんでいる。しかしここに陥穽がある。ここには洞察はなく、自分に都合のよい知識の断片をパッチワークしているだけだ。
嫌韓派の多くは、「日本は法治がしっかりしている立派な民主主義国家だが、韓国は情治や人治しかできず、三権分立もできていない前近代の国」という認識を持つ。これは部分的には正しい。つまり高度の学問的、客観的知識によってある程度サポートできる認識だといえる。だが、この枠組みが過度な信念体系になってしまうと、あきらかな誤謬の領域に突入し、日本の国益にも著しく反する認識となる。
自分たちが韓国を蔑視・軽視したいという、根本的な欲望のままを表出するのではなく、それに客観的・学問的な認識を加味して、自分たちの言説を構築している。それゆえこれらの主張は強く、なかなかひるまないのである。
(4)日韓で異なる「市民」概念
「市民」「民主主義」「歴史」「道徳」「法」などの語彙を、日本語と韓国語は共有しているが、これらが「両社会で同じ意味内容を持つ」と誤解するとき、日韓の対立が大きくなると考えている。両国がいわゆる「体制の共有」をしたあと、むしろ摩擦が増大化しているひとつの理由は、そこにある。
韓国での市民概念は、「エリートから民衆へ」(80年代)、「民衆から市民へ」(90年代)と変化し、そこで後期資本主義に遭遇して市民がグローバル化、情報化した。これに対して日本では、「エリートから大衆へ」(60年代)、「大衆から中間層へ」(70年代)へと推移し、その後グローバリゼーションの時代を迎えて、これに逆行した内向き化の傾向を深めた。
韓国では「わが国の市民は権力」と言われ、政権よりもむしろ市民の「世論」の方がパワーを持つ局面がしばしばある。これに対して日本では、「プロ市民」という言葉があるように、政治変革を促す市民パワーに対して、国民の冷淡な目が存在する。むしろ日本の市民運動は、政権交代のような大イシューではなく、日常生活と密着したこまごました課題解決にその本領を発揮しているというのは、日韓比較社会学における常識である。
私は韓国の「市民」の淵源は儒教的な「士大夫」にあると考えている。近代への移行期に社会の「総両班化」が進行したという歴史も介在している。両班というのは、伝統的な儒教的支配層である。
これに対して日本の「市民」の淵源は、江戸時代の農村における「自治」にあると考える。近代における社会の「総中間層化」が、それを一般化した。
逆に言えば、韓国には法的な「自治」の概念が薄いのだが、これは儒教的王朝体制の遺風という側面が強いだろう。そして日本には道徳志向的な「反権力」の概念が薄いのだが、これは封建体制の遺風という側面が影響しているのであろう。前近代が儒教的王朝社会(朝鮮)だったのか、封建社会(日本)だったのか、の違いが大きいのである。
(5)法と道徳
このように考えると、「現代社会をつくるうえで、何が最も重要なメルクマールとなったのか」という問いに対して、韓国は王朝的(儒教的)伝統によって「道徳」が最も重要だったといえるし、日本では封建的(非儒教的)伝統によって「法」が最も重要視されたのだといえるかもしれない。
このことを裏打ちする事実として、韓国社会では反道徳的行為への生理的嫌悪が最も強いのに対して、日本社会では反遵法行為への生理的嫌悪が最も強いということが挙げられるだろう。自治は、「自分たちの作った掟を守る」ということにおいて成立する。だが道徳は、一度つくられた法や合意による安定性を破壊する力を持つ。
日本近代の大日本帝国憲法下においても、すでに法実証主義的なメンタリティが強く、これを強力な官僚機構の支配が下支えしてきたが、このことによって民主主義の機能不全という事態が継続して起こる。民意が官僚にブロックされてしまい、政治に反映されにくいのだ。
これに対して韓国では、道徳的志向的なメンタリティが強いため、「汚濁にまみれている現実の歴史より、理想的な仮想道徳歴史(バーチャル・ヒストリー)のほうが重要だ」という朱子学的な歴史観の専横が浸透し、これによって民主主義(道徳的理想を実現させるシステムだと韓国では考えられている)への過信が過剰化するとともに、それへの深い失望や絶望も同時に進行する。
このような私の仮説は、発表した数年後から、日本でも一般化するようになり、昨今では「日本は法を重視し、韓国は道徳(国民感情)を重視する」という共通認識を持つようになった。
しかし、この認識を安易に一般化してしまうと、大きな問題が生じる。私のこの認識には韓国に対する蔑視や軽視の視線は介在していない。ところが日本の嫌韓派は、この認識をよりどころにして、韓国を蔑視している。
「韓国では道徳が重視される」という場合、法は道徳によって簡単に破られるのではない。つまり、法と道徳のあいだに緊張関係がないのではない。むしろ強い緊張関係がある。法が軽いゆえに破られるのではなく、道徳が強いがゆえに破られるのである。「日本と違って韓国の民主主義は法を軽視するのでレベルが低い」と単純に考えることは危険だ。
韓国は法を軽視し、法に疎いのか。そうではない。韓国の法的な交渉力は、グローバルなスタンダードに照らし合わせて、極めて高いレベルにある。むしろ紛争においては日本が完敗する可能性すらある。それは、日本のリーガル精神よりも韓国のそれのほうがずっと進んでいるからなのである(具体例は、紙面の関係で省略するが、詳しくは前掲書参照)。
(6)グリーバンス国家
世界はいま、法的な安定性という意味でも、大激動期に入っている。19世紀から20世紀前半にかけて支配と被害を受けた側(対抗近代の側)がいま、正義を取り戻そうとする運動をグローバルに展開しており、国際的な司法もそれに呼応しつつある(移行期正義の問題)。つまり、法の世界がいま、「正義の回復」というメガ・イシューをめぐって攻防している。すなわち、「法の道徳化」という現象がグローバルなレベルで起っているのだ。これは韓国人が最も得意とするベクトルである。
日本人も動体視力を鍛えて、世界における新しい法的秩序の生成現場をみつめ、それに主体的に参与しなければならない。もしそれができないならば、日本は「主権免除」というような古い観念のみにしがみつく、守旧勢力としてのみ認識され続けるしかない。
私としては、もうひとつ別のまなざしも持つべきだと考える。もし日本が国際的にじゅうぶん尊敬される国家たろうとするなら、政府も法律家も専門家も、例えば、「主権免除こそが唯一の解」と声高に合唱するだけでなく、「(徴用工問題の)裁判において問われていることは、二国間の紛争に関してどのような法的・思想的意味を持つのか」という問題に対して、包容的な見解を披歴してもよかったのではないか。
この問題には、韓国の国家アイデンティティが深くかかわっている。韓国人が自分たちの国をどのように規定しようとしているかを、私たちはきちんと分析すべきだ。「グリーバンス(grievance)」という言葉がある。「不平」「不満」「苦情」などといった意味だが、これがいま、きわめて重要な概念である。何に対する不平不満なのか?「近代」に対してである。
近代という時代にヨーロッパと米国、日本がほぼ世界を独占してしまった。19世紀から20世紀前半にかけて、植民地支配、世界戦争、自然破壊、産業資本主義、科学技術などによって地球上の人間の生活を根本的に変えてしまった主役が、欧米と日本であった。
この「呪われた近代」に対抗する思想とパワーが、「対抗近代」とでも呼ぶべき形をとって、非西洋・非日本の地域で勢力を拡大している。
韓国はかつて植民地支配された主要国家・地域のなかで、戦後に先進国になった国家の先頭を走っている。本来はそのことに大きな自信を持って、先進国の陣営の一員として責任を持ってふるまうべきなのである。国際法の秩序を守り、「合意は拘束する」「主権免除」の原則を尊重するのは、その基本中の基本であろう。
しかし、冒頭で述べたように、韓国は先進国としての責任を担って歩んでいけばいいのか(つまり近代側の勢力になるのか)、それとも「グリーバンス国家」として先進国に対する不平不満を訴えるべきなのか(つまり、対抗近代側に与するのか)、大きく揺れている。かつての帝国主義勢力と同じ陣営に入りこむことを、「被害者国」として、潔しとしない。
とくに文在寅政権は、「グリーバンス国家」の側面ばかりを意識してきた。自分たちはいまや資本主義の最先端の国家であり、自然破壊もしているし、他国に対する経済的搾取もしている。日本や欧米に文句が言えない立場になっている現実は見ようとせず、植民地支配されたことによる傷を訴えるだけの国家として、グローバルな「グリーバンス国家群」の代表になろうという野心を持っている。
「グリーバンス国家」としては、「合意は拘束する」という国際法の大原則を守ること自体が、欧米および日本による帝国主義時代の支配や搾取を肯定することになってしまう。過去の「悪法」や「悪条約」は積極的に否定することが、過去に被害を受けた国家群を代表する英雄的行為だと考える。
日本と韓国はいまや、世界の中心から出てくる価値を優等生的に学んで自国に普及させるような国家ではない。近代と脱近代のさまざまな価値を再検討し、「現代のグローバルな問題系」に立ち向かう国家でなくてはならない。その際に、<第一の生命><第二の生命>を中心に据えてきた西洋中心の価値観を変えていかなくてはならないのである。現実の国際関係が、哲学や生命観と密接に関係していることを認識すべきである。
(2021年7月1日に開催されたIPP政策研究会における発題内容を整理して掲載)