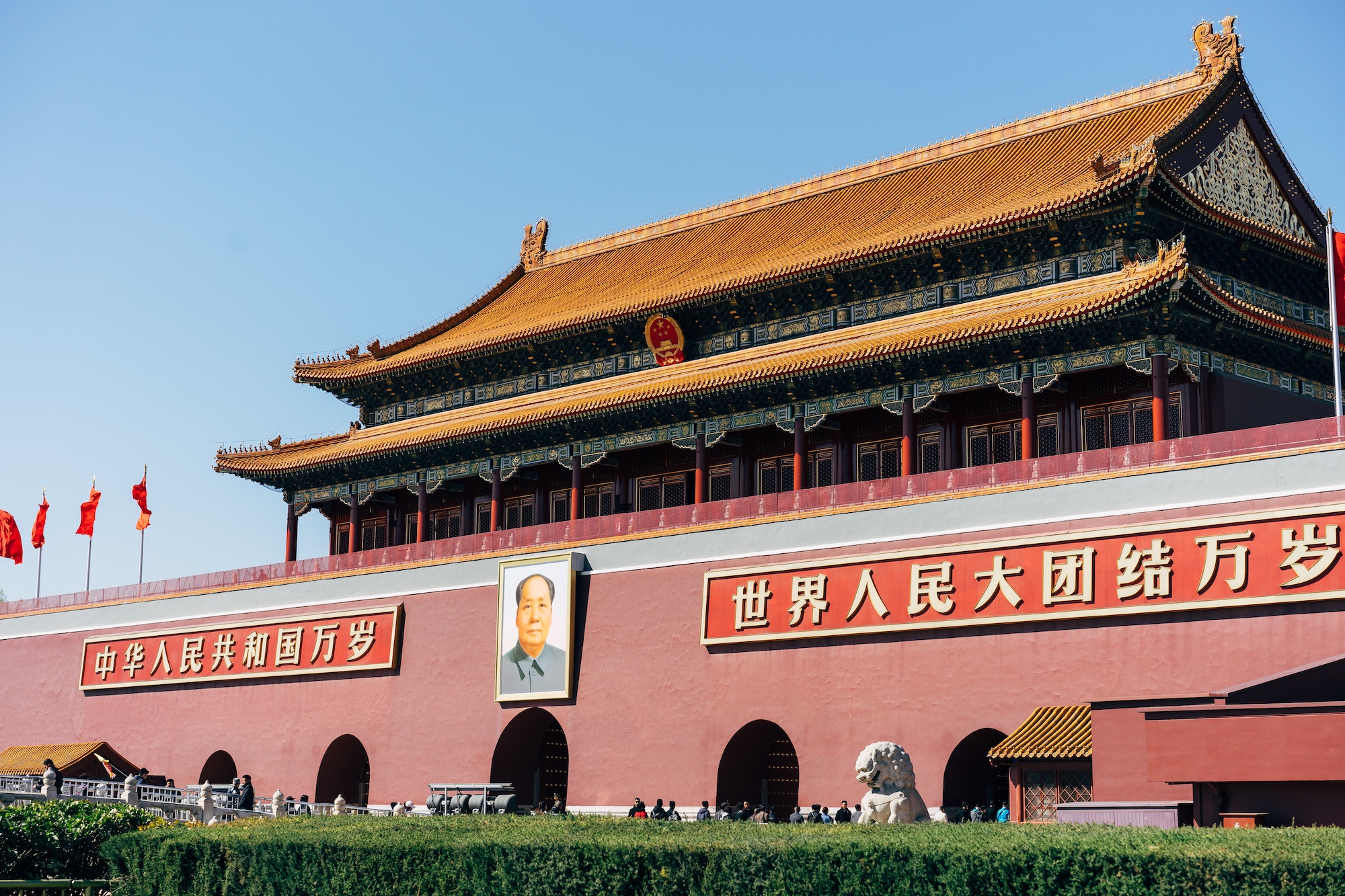はじめに
2024年2月1日に非常事態宣言が半年間延長された。実に5回目の延長である。ミャンマー軍によるクーデター発生から3年が経過したが、収拾の兆しは見られない。
国軍は同月、徴兵制を実施すると発表した。4月から月5千人ずつを訓練し、年間6万人の新兵を要請する計画である。国軍の事情として人手が足りない。一方で、国民は国軍を信頼しておらず、内戦に動員されることに反発している。教育機会や就業機会を求めて、隣国のタイやバングラディシュへ逃亡する国民が後を絶たない。
本稿では、2021年クーデター前後の状況とその後の国内外の動向を概観し、泥沼化するミャンマー情勢の行方について考察する。
1.2021年クーデターはなぜ起きたのか
ミャンマーの特殊性
まず、ミャンマーという国家について簡単に紹介したい。
地理的な特徴としては、ミャンマーは東南アジアで2番目に大きな国土を有し、5つの国(タイ・ラオス・中国・インド・バングラディシュ)と国境を接している。政治経済の中心地は平野部で、周辺の山岳地帯には少数民族が数多く暮らしている。天然資源が豊富で、ヒスイなどを中国へ輸出している。
地政学的には、ミャンマーは中国にとって重要な国である。中国がインド洋への直接経路を持つために一カ国だけを通ろうとすれば、現実的な選択肢はミャンマーかパキスタンだろう。ミャンマーについては雲南省からミャンマーを北東から南西に縦断する鉄道や道路、パイプライン建設などの計画が1990年代からあがっていた。2000年代にパイプラインが完成し、中国は今も原油や天然ガスをミャンマー西部のラカイン州から送っている。他方で鉄道と道路の建設計画はほとんど進んでいない。ミャンマー軍が中国を警戒しているのが大きな要因である。また、2010年代に進んだ同国での経済改革と民主化のなかで、日本が鉄道を含めたインフラ開発支援の主体として浮上してきた。インド太平洋の安全保障環境を重要視したことで、ミャンマーとの良好な関係構築が日本政府にとって外交的な目標になっていたことも関係しているだろう。
経済面では、ミャンマーの潜在力はしばしば言及されるが、実際の国内総生産(GDP)はまだまだ小さい。東南アジアでいえば、ラオスやカンボジアと同じ規模である。一昔前は、CLMV諸国(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム)が東南アジアにおける成長株と言われていたが、ベトナムは大きく成長し、フィリピンに迫る勢いである。カンボジアとラオスも毎年ある程度の経済成長を遂げているが、ミャンマーはクーデター以降に著しく落ち込んだ。もうCLMVという括り方に有用性はないだろう。
ミャンマーの政治史は現在のミャンマー情勢を理解する上で重要である。ミャンマーでは1948年の独立以来、軍事政権による統治が50年以上を占めている。独立後に議会制民主主義として出発したミャンマーは1958年にクーデターを経験したが、当時の選挙管理内閣は選挙後に政権をスムーズに明け渡した。1962年のクーデターで社会主義的な軍事政権が発足し、1988年のクーデターで別の軍事政権が発足した。2011年から軍事政権と民主主義的政権が共存するようになったが、2021年のクーデターで軍事政権に舞い戻った。
ミャンマーでは、憲法が機能していた期間が短いのも大きな特徴である。最初の憲法は1948年施行後、1962年のクーデターまで存在した。12年後の1974年に新たな憲法が制定されたが、1988年のクーデターで憲法は再び反故にされ、23年後の2011年に次の憲法が施行された。
2021年クーデター後、憲法が機能しているとはいいにくい。非常事態宣言が5回も延長されるなど、国軍がやりたいようにやっていると言わざるをえない。政治史を踏まえると、ミャンマーでは統治体制や国民の権利などの基本原則について、国家的な合意が形成される段階にまで至っていない。
クーデターに至る経緯
クーデターが起こった2021年2月1日は、前年11月に実施された総選挙後初めて議会(下院)が招集される日だった。同選挙ではアウンサンスーチー率いる民主化勢力が圧勝した。国軍は選挙の不正を訴えており、1月28日から政府と国軍の間で、複数回の交渉があったという。
国軍が交渉時に要求していたのは選挙管理委員会を入れ替えること、選挙の不正を調査すること、議会招集日(2月1日)を延期することの3点だったと聞く。アウンサンスーチーらは選挙に問題はなかったと主張し、国軍との間で膠着状態が続いていた。政府は1月31日に、議会を2月1日に招集することを宣言して国軍の要求を実質的に拒絶した。国軍は周到に準備してきたクーデター作戦を実行に移し、2月1日未明に、アウンサンスーチー国家顧問や側近のウィンミン大統領をはじめとする政権の閣僚ら(軍人を除く)、NLD(国民民主連盟・与党)の幹部らを拘束した。国軍は一発の銃弾も使わずにクーデターを成功させたわけである。
ミャンマーでは総選挙が5年に一度実施され、小選挙区制である。2020年総選挙ではNLDの獲得票は6割程度だったが、上下両院ともに約8割の議席を獲得する大勝利となった。これは2度目の勝利である。2011年の民政移管後初めての総選挙が2015年に実施され、そこでもNLDは大勝していた。国軍はアウンサンスーチー政権(憲法上の規定で大統領になれないので国家顧問)の発足を想定していなかったように思う。ミャンマーは大統領制だが、議院内閣制のように議会与党が大統領を選出する。NLDが大統領を選ぶことができるので、政権と議会はアウンサンスーチーのもとで統合された状態にあった。政府の通常の立法活動では、NLDが過半数を持っているので、法案を通す力があった。
一方、国軍は大統領や議会とは別に、自律的に存在している組織である。最高司令官人事は軍の中で決定する。また憲法上の規定により、議会の4分の1の議席は現役軍人に割り振られている。治安に関わる大臣のポストは最高司令官が指名した人物が務め、この人事についてはアウンサンスーチーらが関与することができない。憲法改正には議会で4分の3よりも多い賛成を得た上で国民投票にかける必要があるが、議会の4分の1は国軍の議席であるから、国軍が同意しない限り、憲法を変えることはできないという設計になっている。
このように、5年前の総選挙以来、国軍とアウンサンスーチー率いる民主化勢力はそれぞれにストレスを溜め込んできた。特に国軍最高司令官のミンアウンフライン将軍はアウンサンスーチーに対する恨みや嫉妬が強いという。1990年代のアウンサンスーチーは基本的に自宅軟禁で、刑務所生活そのものは短かった。しかし現在のアウンサンスーチーは首都ネピドーにある刑務所に収容されているといわれている。
クーデターの原因
クーデターに至った大きな要因としては、指導者間の相互不信が第一にあげられる。より根本的には、国軍と民主化勢力との国家観の違いをあげることができる。 国軍は、軍が政治に直接関与しなければ国を安定させることはできないと考えている。実際にミャンマーでは独立以来、いつもどこかで武装勢力と国軍が戦ってきた。ミャンマー政府が全土を統治したことはいまだかつてない。
民主化勢力は、国軍が政治関与をしない文民統制下で軍事作戦をすべきだと考えている。軍が政治に関わるので国内が安定しないという発想である。両者の国家観は水と油のように全く相容れない。5年間にわたって政権をともにしてきたこと自体が奇跡的だったのかもしれない。
その他の要因としては、国軍の利権確保である。軍事政権が1962年から50年間も続いたので、軍系列企業の利権はかなり大きかったと言われている。2016年にアウンサンスーチー政権が発足して民主化が進行したことで、国軍の利権は確実に減少した。軍事政権時代には、現役・退役の軍幹部が大臣の約9割を占めていたが、アウンサンスーチー政権で閣僚に入った軍人は3人だけだった。
また、ミンアウンフライン将軍には自分が大統領になりたいという野心があった。2020年6月に定年(60歳)を迎えたが、定年を5年引き伸ばして大統領の座を狙っていた。しかし、同年11月の総選挙では軍に近い政党が大敗したことで、大統領になれる見込みはなくなった。将軍の野心がクーデターの背景にあるのではないかと言われている。
2.危機への発展
反クーデター運動から革命運動へ
国軍のクーデターに反発して反クーデター運動が各地で起こった。クーデターから1週間後には、第一都市のヤンゴンでも街頭デモが起こった。当時はコロナ禍で外出制限がかかっていたが、老若男女がマスクを付けて街頭に集まった。市民的不服従運動が公務員を中心に広がり、彼らは仕事を辞めるなどボイコットした。
アウンサンスーチーやNLDの幹部らは拘束されたが、NLDの中堅議員は残っていた。彼らはタイとの国境地域へ逃亡し、21年4月に国民統一政府(NUG)を樹立した。
抵抗に対して、国軍は当初ゴム弾や放水車を使った群衆管理レベルの対応をみせたが、やがて実弾を発砲し、逮捕者を拷問した。22年には政治犯の死刑執行も断行している。
アウンサンスーチーといえば、非暴力闘争の民主活動家だったが、NUGは2021年9月に非暴力闘争を離れて「自衛のための戦争」を宣言した。あくまで自衛のための武装闘争とのことだが、武力衝突は拡大した。
国軍側は最高司令官のもとで統制が十分に取れているというわけではない。国軍では自国民に銃を向けたくないという理由で脱走兵が増加した。抵抗勢力が国軍への協力者を攻撃対象としたことで、混乱が生じた。
一方、抵抗勢力側には緩やかな統一戦線が形成された。NUGとその軍隊に当たる人民防衛軍(PDF)というグループ、軍と長年戦ってきた少数民族の武装勢力の一部、軍に抵抗する若者、これら三者の連携である。NUG&PDFは軍事経験に長けているわけではない。少数民族の武装勢力はPDFや抵抗する若者たちをトレーニングしている。組織的に行動をともにするわけではないが、国軍への抵抗で共闘が実現している。
国軍の当初の計画では、クーデターを起こしてから一年間を非常事態宣言で統治し、その後は総選挙を実施して、親軍政権を樹立する目論見だった。しかし、武装闘争が広がり、抵抗勢力側には緩やかな統一戦線まで成立したことで、総選挙実施の目処は一向に立たない。
ミャンマー紛争の特殊性
ミャンマーでは1988年のクーデターの際にも大規模な反対デモが起こったが、国軍は約2週間で鎮圧した。今回の紛争は以前の反クーデター運動とは強度が全く違う。
2021年クーデター以降、国内の紛争地図も様変わりした。2021年以前からミャンマーでは国軍と少数民族による武力衝突が起こっていたが、主な場所は北東部や西部だった。2021年以降はマンダレーなどの中心部やヤンゴンなどの南部で武力衝突が発生する一方で、西部では大幅に減少した。中央平野でそれまで紛争が少なかったザガイン管区やマグウェ管区で紛争が激化しており、国内避難民も増加している。後述するように、2023年に入ってから少数民族地域で軍に抵抗する勢力が攻勢を強めており、中央平野を中心とする軍事政権の統治領域が周辺部から徐々に削られていっている状態である。
また、ミャンマー紛争の特殊性は、利害関係者の多さにある。米国のACLED(シンクタンク)が2023年に出した’Conflict Index’によれば、ミャンマーでは紛争に関わっている集団が他の地域(シリア、メキシコ、ウクライナなど)に比べてはるかに多い。数多くの集団が紛争に関わり、国軍に抵抗するという点でネットワークを築いている。以前はアウンサンスーチーというカリスマを中心に非暴力的に軍と戦うというのが主流だったが、今は明確なリーダーがいない。指揮命令系統が複数あって分断したり連携したりしているため、仮に停戦や和平を目指すにしても利害調整は困難を極めることになるだろう。
経済政策の悪手と経済制裁の余波
クーデター以前、世界銀行は今後のミャンマーのGDP成長率を、他の東アジア・太平洋諸国の予想平均値より高く見積もっていた。しかし、2021年2月にクーデターが起こったことで、同年はマイナス18%の経済成長を記録し、その後も低成長を続けている。
クーデター後、貿易赤字は悪化し、海外援助は停滞した。日本でも新規の援助はすべて停止し、既存の援助だけを残した。人権問題を理由に、欧米からの経済制裁は少しずつ拡大し、一部企業はミャンマーから撤退した。紛争地に海外からの直接投資がくるはずもない。世界的なインフラの影響で、チャット安や外貨不足も生じている。
悪化する経済状況のなかで、国軍がとった経済政策は弥縫策に過ぎなかった。ミャンマーの経済問題が政治問題ゆえに発生していることは自明であるが、国軍にとって彼らの考える安全保障問題は他のどんな問題よりも優先される。さまざまな国家の機能や利害の間で均衡が働くような仕組みがないため、今後も国軍が政治的に妥協する可能性は低い。
縫製業など一部の輸出産業は好調だが、全体的な停滞感は強く、回復の兆しは見られない。ただし、ミャンマーの経済の中心は国軍の実効支配地域で、経済がすぐに破綻することはない。低空飛行を続ける見通しである。
3.新たな展開と行き詰まり
10・27作戦
2023年10月27日から、三兄弟同盟による軍施設への一斉攻撃が始まった。三兄弟同盟とはミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)、パラウン民族解放軍(TNLA)、アラカン軍(AA)の3つの武装勢力からなる。
MNDAAは2009年の戦闘で国軍に占領されたコーカン地域を今回、奪還した。TNLAも活発に攻撃し、軍に奪われていたナムサン地域を占領することに成功した。その他、ラカイン州北部(ヤンゴンより西部)、カヤー州(ヤンゴンより東部)、チン州(ヤンゴンより北西部)、ザガイン州(ヤンゴンより北部)でも連鎖的に戦闘が激化した。中央部から離れた国境地域の軍の拠点が200以上も武装勢力に占拠された。
武力衝突の増加は、ACLEDのデータにも顕著に表れた。2023年11月の武力衝突数を前月と比べた場合、シャン州北部では4倍以上、ラカイン州では2倍以上に膨れ上がっている。ただし、武力衝突そのものはこの3年間、主要な管区では収まることなく継続している。
今回、中国との国境地域における戦闘も激化したが、戦闘に際して中国政府は黙認した。黙認の要因には中国の国内問題が関わっている。中国との国境地域に、BGF(国境防衛部隊)というミャンマー軍の一部のような民間武装勢力が治める地域がある。国家権力ではなく武装勢力が治めている地域だが、ミャンマー軍の後ろ盾があるので治安も悪くない。この地域に、中国からオンライン詐欺の拠点が多数移ってきた。中国ではオンライン詐欺の被害が年間3〜4兆円ともいわれており、深刻な社会問題になっている。中国政府は以前から、オンライン詐欺の拠点を潰したいと思っていたが、ミャンマー軍は全く対応しなかった。今回、MNDAAがその地域を攻撃してくれたので、中国政府は黙認したといわれている。
抵抗勢力の戦術・戦略
抵抗勢力の戦術は当初、ゲリラ戦で国軍が入れない地域(解放区)を作っていくのが主流だった。この戦術は一定の成果を収めており、国軍の部隊が進出できない地域が特にミャンマー北部に広がった。それが最近は国境地域の軍施設が抵抗する反軍勢力に占拠されることが増え、さらに将兵の拘束や武器の鹵獲なども起こっている。フェイズが変わってきているようにみえる。
紛争が長期化し、戦線が拡大しているので、国軍は国境地域の拠点を維持できなくなりつつある。兵員不足に対応するために国軍は徴兵制を発表したが、徴兵が順調に進むとは考えにくい。兵士になることを望まない国民が多いだろうし、短期の訓練で戦地に送り込んでどうにかなるものでもない。
中国との国境地域であるシャン州の北部では、中国による停戦調停によって武力衝突が減ってはいる(交渉は現在も継続中)。しかし、中国の介入はあくまで中国の利益に関わる範囲に限定されるだろうから、ミャンマー全土への影響は限定的だとみている。
抵抗する勢力は、長期戦を視野に入れている。長期的には国軍は軍事力の回復に失敗して、形勢は時間とともに抵抗勢力有利になっていくというのが抵抗勢力側の見立てである。周辺地域を押さえた上で時間をかけながら中央部の制圧を目指すという戦略である。
国内政治の行き詰まり
国軍と抵抗勢力の戦力を踏まえると、短期的に決着がつくことはなさそうである。抵抗勢力は国境地域で優位に立っているが、中央の権力を転覆できるほどではない。彼らの士気は高いが、装備が不足している。特に国軍が制空権を握っているので、民主化勢力は実効支配の地域を拡大しにくい。統治する主体がはっきりしない紛争地域は、社会が混乱しやすく、経済的も停滞する傾向にある。
国軍は装備では圧倒しているものの、組織力や士気が低い。抵抗勢力によって奪われた土地を取り戻すと公言しているが、派兵する軍人がいないため、防衛戦をじりじりと下げている。国軍は民主化勢力を「テロリスト」に指定しており、混乱の原因は「テロリスト」にあると主張し続けている。その「テロリスト」を鎮圧するまで、非常事態宣言を何度でも延長するだろう。
非常事態宣言下で国家の三権がミンアウンフライン将軍に集中し、すでに3年が経過した。独裁化と既成事実化は長期化するほどに進んでいく。国軍は仏教ナショナリズムなどの愛国心に訴えて、軍事政権の正当性を作ろうとしているが、国民からの人気は相変わらず低い。比較的安定している都市部でも軍事政権への嫌悪感は強い。
4.国際社会の動き
国際社会の行き詰まり
国際社会の足並みは危機直後から揃っていない。英米EUなどは圧力路線を取っている。国際法違反(人権侵害)に対する標的制裁を順次拡大させたが、軍の行動を変えるまでには至っていない。
関与路線を取っているのはASEANである。ASEAN首脳はミャンマー軍事政権と5項目について合意するなど対話に努めてきた。しかし、ミャンマー軍政がまともに履行しなかったこともあり、ASEANの首脳会議や外相会議に国軍の指導者は出ることができない。
軍事政権を事実上追認しているのが中露である。特にロシアは軍事政権との良好な関係を歓迎しやすい。ミャンマーとの間に国境上の問題がない上、ミャンマー軍はロシア製の兵器を使用している。中国は隣国なので、紛争の早期終結を第一に願っている。国軍が首都や経済の中心地を押さえていることから、中国も軍事政権との良好な関係構築を基本に考えている。
軍事政権には国連大使がいるが、国連の場で他国の大使から徹底して非難されたこともあり、姿を見せなくなった。その後はガザ紛争が勃発したことで、ミャンマー紛争は国際社会の関心外になってしまった。
日本に関する詳細は後述するが、圧力路線と関与路線の間のような立場である。
経済制裁の余波
アメリカはクーデター直後、連銀にあるミャンマー政府資産10億ドルを凍結した。その後は16回(本報告時点)に渡って標的制裁を拡大させた。制裁対象は2024年2月時点で40を超え、そこには国軍の関係者や国営企業だけでなく、国営銀行も含まれる。1990年2000年代にも、アメリカは軍事政権を対象に経済制裁を実施したが、当時はシンガポールの民間銀行でドル決済が可能だった。しかし、今回は同銀行もミャンマーへの送金業務を停止しているので、民間企業も含めて経済活動が非常にやりにくい。
ただし、今回の制裁にも穴がある。中露に加え、インド・タイがミャンマーとの取引を継続している。とくに、ミャンマーの輸出入総額では中国・タイが全体の半分を占めるので、両国が加担しない経済制裁には必然的に限界がある。ミャンマーは中国・タイへの天然ガス輸出によってある程度の外貨を稼ぐことができる。
上述のように、ミャンマー軍は中国を警戒している。特にミンアウンフライン将軍が中国を信用していないので、中国ミャンマー経済回廊(CMEC)の鉄道・道路建設計画はなかなか進まない。しかし、現状の国際的な孤立を打開するために、中国有利にディールが成立することもありえる。もちろん、政治的混乱の収拾が必要条件となる。
武器に関しては、全取引量の半分以上を中国が占める。2000年代からロシアとの関係も強化しており、ロシア製の戦闘機も購入している。対露関係は今後も強化していくだろう。
日本とミャンマー
日本は2011年以降、対ミャンマー支援を拡大してきた。2019年にミャンマーが受け取った政府開発援助(ODA)において、日本が全体の3分の1以上を占めるほどだった。
日本政府が対ミャンマー支援を拡大してきた理由は主に二つである。一つには、対ミャンマー支援を強化することで、ミャンマーの外交・経済が中国一辺倒になることを防ぎたいという戦略的意図があった。
2000年代のミャンマーは対米関係が険悪だったこともあり、顕著に中国寄りだった。2010年代にミャンマーが対米関係を改善できたことをきっかけに、日本や韓国などの企業がミャンマーにこぞって進出した。ミャンマーでは、軍や民主化政党、一般企業をはじめ、国家をあげて日本への信頼が厚い。日本の防衛省はミャンマーで文民統制を実現するために、ミャンマー軍の士官候補生へ訓練なども支援してきた。
もう一つは経済的な理由である。日本の製造業は東南アジアにおいて軒並み強いが、ミャンマーは例外だった。日本企業が安い労働力を求めてタイを起点にミャンマーへ進出することを、日本政府は大いに後押しした。
2017年のロヒンギャ危機後、欧米諸国はミャンマー政府を非難したが、日本はミャンマー政府に寄り添った。共に問題解決を図ろうとするなど、ミャンマーを国際社会につなぎとめる努力をした。
しかしクーデターから3年経ち、2011年以降の日本の投資や外交努力はほとんどが水泡に帰した。クーデター後には新規の案件をやっていないので、事業規模はますます縮小している。2022年度の日本における対ミャンマー事業規模は対インドネシアの100分の1以下にまで落ち込んだ。日本とミャンマーの関係は、すでに質的にも量的にも大きく転換しているといってよい。
2011年に軍主導で民政移管を実現して以降、多くの国がミャンマー支援に前のめりだった。一昔前にはベトナム支援ブームがあったので、ミャンマー支援においても「バスに乗り遅れるな」という雰囲気が主要国を覆っていた。
2021年のクーデターを実際に予測するのは難しかったといわざるをえない。しかし、ミャンマーの憲法には軍の独立性や政治関与が明記されており、民主化が容易でないことは明らかだった。過去の軍事政権に関するレビューが、米国政府においても不足していたといわれている。
日本には、政治的リスクを軽視して経済に注力する傾向がある。クーデター後も、日本政府や企業関係者からはミャンマー情勢を楽観視する声がしばしば聞こえた。タイでは軍事政権下で政治的不安定が続いても経済的には支障がなかった。「ミャンマーでも情勢がある程度落ち着いてから総選挙を実施すれば、経済的に問題はない」と考えていた日本人関係者は少なくなかった。
5.今後の行方
考えられるシナリオ
今後のミャンマー情勢では、主に四つのシナリオが考えられる。
第一のシナリオは、軍が抵抗勢力を鎮静化して軍管理下の選挙を実施した上で親軍政権が誕生するというものである。このシナリオでは政治的かつ経済的な困難が継続する可能性が高い。実施される選挙は公正性に欠けるため、欧米はもちろん日本も選挙結果を歓迎できず、制裁が緩和されるとは考えにくい。また、誕生した親軍政権は国軍の傀儡のようなものなので、国民からの支持も得られないだろう。現状の軍事政権同様に、合理的な政策立案も期待できない。
第二のシナリオは、抵抗勢力の抵抗が持続したまま、現状の軍事政権が継続するというものである。上述のように、紛争が長引くほど、ミンアウンフライン将軍による独裁化が進む。すでに軍人への賄賂などが相当に増えており、町中の警察官の行動を抑制する仕組みさえない。裁判所やメディアが機能しない状態が長く続けば、国軍と国民の溝は深まるばかりである。
第三のシナリオは抵抗勢力と国軍側で対話と和解が成立し、自由で公正な選挙を実施したうえで新たな権力分有が成立するというものである。このシナリオは、抵抗勢力が国軍の権限をある程度認めなければ成り立たないので現状では起こりそうにない。
第四のシナリオは紛争が激化して、国家が実質的に破綻するというものである。軍は経済的かつ軍事的に厳しい状況にあり、長期的にも現状の打開は容易ではない。もともと電力事情は悪かったが、さらに悪化している。このままミャンマー軍は公共財を提供できなくなり、国家として体をなさなくなるシナリオである。一方で各地の武装勢力はその地域で自立して独立国家のようにふるまうようになる。
現状は第二(軍事政権の継続)と第四(国家破綻)の間にあり、そのまましばらく続きそうだが、依然として不確実性は高い。現状をみて「こうなる」とはっきり予想できる人の言うことは怪しむべきだろう。上記以外では、抵抗勢力による革命が成功する可能性や、現状の軍事政権が政治的に安定する可能性もどちらも低いと考えている。
国際社会の働きかけと日本の難しい舵取り
軍事政権に対する国際社会からの外交的働きかけは非常に少ない。大きな理由は、ミャンマー軍は孤立主義志向が強く、他国の干渉を毛嫌いするからだ。抵抗勢力の背後に他国の介入があるのではないかとさえ不信している。ミャンマーでは冷戦後も軍事政権が長期間続いてきたこともあり、国軍は冷戦思考に凝り固まっている。
安保理は暴力の停止について、2022年12月に決議を採択した(中国・ロシア・インドは棄権)。国際社会の目標は、政治的決着の前に停戦実現にむけて、国軍にどう働きかけていくかになる。
また、国内避難民が300万人に達すると言われている。彼らにどうやって支援を届けるのかが喫緊の課題である。タイはASEANとは別に動いており、対ミャンマー外交では鍵を握っている国である。
日本外交の舵取りは非常に難しい。日本政府はASEAN支援を打ち出してはいるものの、実質的にはミャンマー問題への関与から徐々に後退している。国軍の指導部には戦争犯罪の責任者という疑惑があるので、現政権との関係改善はミャンマー国民との信頼関係を壊しかねない。さらに、改善したところで日本の国益に叶うような変化を軍政に期待することはできないだろう。
一方で紛争が長期化するほど、ミャンマーの外交関係が中露に偏っていくことが懸念される。冒頭に示したように、ミャンマーは中国にとって海洋安全保障のための要衝である。さすがの中国といえども、紛争地域で長期のインフラプロジェクトに投資することはできないが、それでも、長い目でみれば欧米日の関与がないミャンマーは御しやすいだろう。
現状では、ミャンマーでの混乱は10年以上続く可能性さえ考えられる。地政学的には中国の影響力が徐々に増大していくことは避けられない。昨今の中国政府は軍事政権に慎重に接しているが、中国人ビジネスマンは相変わらずミャンマーへの進出を進めている。国軍としては中国以外のオプションがほしいところだが、他の選択肢にはロシアかインドしか見当たらない。実際に、インドとミャンマーは海軍の合同演習を実施している。国軍はインド洋への中国の影響力を抑えていきたいだろうが、今後の情勢次第では中国有利に交渉を進める可能性も否めない。ミャンマーを取り巻く情勢はクーデターから3年経過した今でも不確実性が高く、引き続き注視が必要である。
(2024年2月21日に開催されたIPP政策研究会における発題内容を整理して掲載)