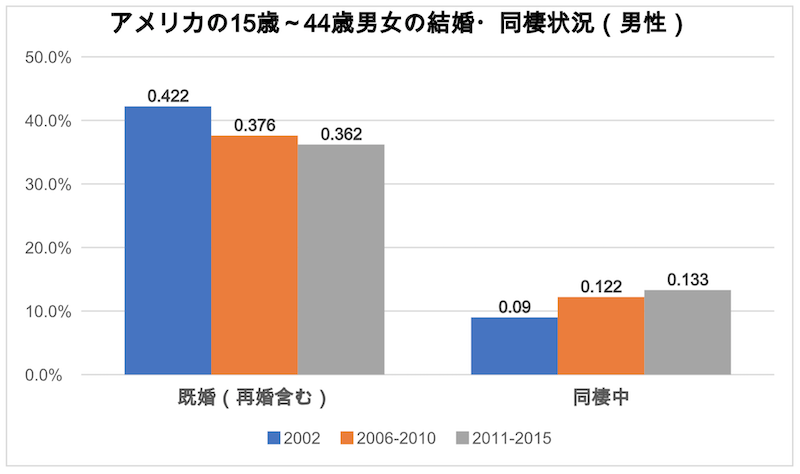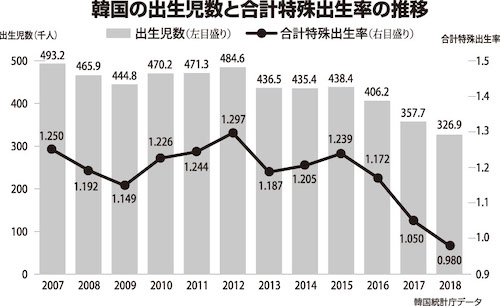地方は人材不足で悩んでいる
私は仕事柄、日本の各地を訪問し、現地の教育委員会の方々や地元の方々と話をする機会が多くある。長期間にわたって同じ自治体を訪れることも多く、そうやって関係が深まれば深まるほど、話題になるのは「今日の講演」ではなく、「今、この町では…」「この街の将来は…」ということである。ただ、残念ながらその多くは明るい話ではなく、「なんとかしないといけないんだが、人材が……」と言う話である。
世界も人材の育成を鍵と思っている
この人材の育成について、台湾、シンガポール、香港などのアジアの国や地域を訪問すると強く感じることがある。私が訪問しているところは、特に優れた教育をしていると自負しているところが多いからかもしれないが、その優れた施設や設備、取組などに私が感嘆していると、「私たちの国は小さい。だから人だけが資源なのです。だから教育に投資をしているのです」という言葉が返ってくる。
この“教育への投資”について、文部科学省は、日本の教育に対する公財政支出がOECD諸国の中で最低水準であると指摘している。教育再生実行会議も同様の指摘をしたうえで、「教育は投資」であり、「税を含め社会全体で財源確保を図るべき」と述べている。ただ、財務省(2019)は、教員1人当たりの児童生徒数は主要先進国と遜色なく、OECDの平均水準にあると主張している。その主張の是非は別として、少なくとも財務省の言い方からは、教育に対して最大限の投資をしようという姿勢は感じられない。世界、とりわけアジア諸国が人材育成にエネルギーを注いでいる中で、日本が立ち遅れてしまうことを懸念する。
育てた子どもがコミュニティの担い手となる
先ほど様々な自治体が人材の不足で悩んでいると述べたが、こうした傾向は、地方に行けば行くほど、自治体の規模が小さくなればなるほど、強いように感じる。例えばある自治体の教育長は、「この子は優秀な子だと思って一生懸命教育しても、そうした人材は東京や大阪、あるいは県庁所在地に出て行ってしまい、帰ってこない。もちろん、そこで是非頑張ってもらいたいと言う気持ちはあるが、一方で、せっかく育てた人材が地域から出て行ってしまったら、地域はどうなるんだという思いもある。だから都会に行くなということではないけれど、何かおかしい、と感じることがある」と話されていた。
こうした腹を割った話の最後は、「勉強ができるとかできないとかが問題ではない。変な劣等感を持たず、コミュニティに積極的に参加し、みんなと協力して問題を解決していけるような若者が町に残れば、コミュニティは魅力を増し、一度は都会に出ていった若者たちも戻ってくるんじゃないかと思ったりする。だからすべての子供を本当に大切に育てていくことが必要なんだ。」というようなところに落ち着く。
私は、実はこのことがきわめて重要だと思っている。ある地域で育った子どもたちは、やがて大人になり、そのかなりの割合が、生まれ育った地域や近隣に居住し、そのコミュニティの構成員になっていく。そのことを踏まえれば、「そのコミュニティを構成し、そのコミュニティを担うことのできる、その町に是非とも住んでほしい人材を育てる教育」が求められているといえると思うのである。
コミュニティの担い手は全人的に成長した人材
では、コミュニティにはどのような人材が求められるのだろうか。どのような人が地域に住んでいてほしいのだろうか。学力の高い人だろうか?
そうではないであろう。恐らくは、隣人は「いい人」であって欲しいと願うだろう。そう考えたとき、教育が目指すのは「全人教育」であるという方向性がみえてくると私は思う。
私の専門ではないので誤解している部分もあると思うが、全人教育と言う言葉は、日本では玉川大学を創設した小原國芳氏が大正デモクラシー期に提唱した教育理念である。小原氏は、学問、道徳、芸術、宗教、健康、生活の6つの領域に対応する真・善・美・聖・健・富と言う価値を調和的に身に付けた人格を育む教育を全人教育と捉えていた。
こうした教育理念は、日本だけのものではない。例えば香港のある学校では、知性・身体・職業・心理・社会・精神の6領域を設定し、その領域に応じた価値を身に付ける教育を目指している。知性や健康・勤労の精神・市民としての責任・仲間との関係・モラルを身につけることが全人的発達(Whole Person Development;WPD)であり、教育の目的である。
私の専門は生徒指導・教育相談(スクールカウンセリング)だが、この領域でも全人的成長を促す包括的支援ということが強調される。その強調点は国や文化によって違うが、私は、身体・パーソナリティ・社会性・学業・キャリアの5領域を想定して、その発達を促す教育と捉えている。体も心も健康で、社会性に富み、学び続ける姿勢を持ち、職業的に自己実現している人間を育てる教育ということである。
具体的な問題を解決していくうえで、学力や知性は重要な役割を果たす。問題が深刻化・複雑化する21世紀には、高度な知性と専門的能力がきわめて重要になることは疑いようがない。しかし、新型コロナ感染症にかかわるさまざまな問題が生じる中、戦っているのは、医師や政治家だけではない。看護師の方々、福祉の現場で働かれている方々、その他にも自分の身を危険にさらしながら頑張っておられる方々がいる。その職業意識の高さ、高度な社会性には脱帽しかない。
つまり、コミュニティの良い形成者、Good Citizen(良い市民)とは、単に学力の高い人ではない。全人的な成長を果たした人なのである。
地域コミュニティの命運は地域に愛着を持った人材育成で決まる
しかし、「体も心も健康で、社会性に富み、学び続ける姿勢を持ち、職業的に自己実現している人間」が地域コミュニティに積極的に関与するとは限らない。では、こうした人が地域に関わろうとする条件は何だろうか。
T.ハーシという人は、人が社会集団につながる理由として、4つの社会的絆(Social Bond)があるとした。それは、①愛着(attachment):人との情緒的のつながり、②投資(commitment):関わることで生じる得失の計算、③巻き込み(involvement):参加せざるを得ない外面的な絆、④信念(belief):規範観念の4つである。
しかし、現実に今の社会を見ても、「地域に関わったとしても、特にプラスにもならず(②)、かえって巻き込まれて面倒だし(③)、そもそも強制されるべきことではない(④)」と考える人たちは少なくないのではないだろうか。つまり、4つの社会的絆の②③④は、ほとんど人を地域に結びつける力にならないということである。たとえ「いい人」であったとしても、これでは地域の力にはならない。
では、人を地域に結びつけるものは何だろうか。それは、「人との情緒的繋がりを意味する愛着」である。投資・巻き込み・信念は、愛着を土台として初めて機能するものであり、この「情緒的繋がり」を作ることができるか否かが、地域コミュニティが実質的に機能するかどうかの分かれ目になる。
沖縄にはエイサーという伝統的な芸能がある。盆の時期に祖先の霊を送り迎えするため、地域の青年団が長い間練習を重ね、当日には地域を練り歩く。私も初めてその踊りを見たときに、感動を覚えた。「この感動はいったいどこから来るのだろう」と考えた時、私なりの答えは、太鼓の音や踊りだけではなく、地域に誇りをもつ地域の仲間が、まさに一体となって踊るところにあるのではないかという結論に至った。まさに、愛着である。
私も青森の出身だが、ねぷたの時期になると、ねぷたを引き、太鼓をたたいたシーンが思い出され、「故郷に帰りたいなあ」というノスタルジックな思いに駆られる。こうした行事や芸能を通じて形成される地域愛は、地域コミュニティの土台となる。
ただ、こうした伝統芸能や行事がない地域もあるだろう。しかし、重要なのは行事や伝統芸能ではなく、愛着である。愛着は、「時間の共有」「空間の共有」「仲間との感情の共有」がもたらすものである。だから、集団生活や自然体験などを一定期間体験したりすることは、地域に親近感を持ち、地域を大切にしようとする感情につながる。
21世紀の地域コミュニティを切り拓くすばらしいアイデアや企画は多くあるし、今後も生まれてくるであろう。しかし、そのアイデアや企画を生かすには、そのコミュニティを大切にしたいという「愛着」が地域住民にあることが前提になると言うことである。
全学校的アプローチ−人材育成はコミュニティを挙げて
最後に、Whole school Approach(全学校的アプローチ)という考え方を紹介したいと思う。この言葉は、世界中で使用されていて使われ方も多様だが、私なりに言えば、「学校に関わるすべてのリソースをフル活用する」ということである。つまり、学校が抱える課題に対して、学校コミュニティに関わるすべてのメンバーが関与し、解決を目指すアプローチと言うことである。すべてのメンバーとは、教師はもちろんだが、児童生徒、教師、保護者、地域の多様なメンバーが関与する。
イギリスである学校を訪問した際に、学校理事会制度を詳細に学ぶ機会があった。日本にも学校評議員会という類似の制度があるが、その権限には大きな違いがある。たとえばイギリスの学校長は基本的に公募制なので、理事会が学校長を選ぶ。つまり、イギリスの多くの学校の理事会は、人事権も予算権、さらには学校教育の改善計画やカリキュラムの決定権をももつ強力な組織なのである。この理事会は、保護者・教職員・教育委員会・保護者・地域代表等から構成されていて、地元の経済界の人材も加わることが推奨されている。実際の人事や予算やカリキュラムは理事会に選ばれた校長が検討していくことになるが、最終決定は理事会の権限である。
私が注目したいのは、イギリスの学校理事会の権限の大きさではない。それよりも、学校の在り方は、校長や教師だけではなく、保護者も、地域の代表も、経済界の人たちも加わって決定しているということである。実際、私が訪問した学校では、学校理事会に生徒会長が出席し、意見を述べるということを知り驚いた。つまり学校に関わるすべてのリソースが関わって学校を作るということなのである。
総社市の事例
私は、さまざまな自治体と連携して、学校改革に取り組んでいるが、その際には、ここまで書いてきた考え方に沿った形で提案をしている。その一例として、ごく簡単にではあるが、岡山県総社市のケースをご紹介する。
1994年、総社市で、ある中学生がいじめを示唆するメモを残し自殺を図った。「二度とこのようなことを繰り返さないでほしい。現在いじめを受けている子どもを救ってほしい。」というご両親の訴えを真摯に受け止め、総社市は、総力を挙げて生徒指導と教育相談に取り組みはじめた。以来総社市は、毎年20を超える不登校対策事業を行い、市の独自予算でスクールカウンセラーを増員するなど、他市にはない取組を進めた。その結果、学校内の暴力行為やいじめは大きく減少した。しかし、その一方で不登校は当時の国の発生率を大きく超え、厳しい学校の指導に学校での居場所を失った子ども達は、地域で不良行為を行うという状況があった。
私が関わるようになったのは、こうした状況下の2010年からである。このとき私は、教育委員会の方々とお話を聴き、状況のアセスメントを行い、いくつかの方針を立てた。それは次のようなことであった。
1)不登校支援も重要だが、最重要課題は安心で安全なだけではなく、「誰もが行きたくなる学校」を作ることである。それは「豊かな情緒的交流による愛着の形成」が鍵になる。
2)不登校になった子どもの適応支援と並行して、不登校にならないですむパーソナリティや対人関係能力を育む成長支援を組み込むことが重要。
3)この町の子どもはいずれこの町の子どもになる。だから、幼児と児童、児童と生徒、生徒と大人という縦の繋がりをつくり、情緒交流を活性化する。それはこの町への愛着を深め、未来のこの町の担い手を育てることになる。
4)助け合うこと・支え合うことを学校の教育活動の中心に据える。すなわち、学力と同時に全人的成長をはかる学校教育を創造する。
5)以上の活動方針は、このコミュニティのすべての人たちに知ってもらう必要がある。したがって、学校の活動は、地域の掲示板、商店街での掲示、回覧板等でどんどん発信する。
6)この町の学校教育は、教師だけではなく、この町の人たちと共に作るべきである。したがって教育の方向性は、この町の子どもに関わるすべての人たちによって決めるべきである。
こうした方針の下、私は、まずは「市の目指す教育」をみんなで考えることに取り組んだ。具体的には、市内の保育所(園)と幼稚園、小学校、中学校の保護者約8,000人対象のアンケートを行い、その集計結果を踏まえ、保護者や商工会議所、警察署、主任児童委員、有識者などで構成される検討委員会で検討して、「この町の子どもをどのような子どもに育てるのか」という内容を9つに絞り込んでもらった。
ここから、総社市の改革はスタートした。取組の詳細は省くが、2019年度中学生の不登校発生率は3.65%だが、総社市で育った子どもの不登校発生率は1%を切った。不良行為等で警察に指導を受ける子どもの数は約200人から10人台へと、約95%減少した。学力も岡山県でトップになり、毎日が楽しく充実しているという子どもの数は約10年にわたって現在も増加し続けている。地域からの苦情は大幅に減少し、むしろ学校への感謝の連絡や学校への協力や支援の申し出も多く寄せられるようになった。
2018年7月、総社市は西日本豪雨災害の中心的被災地になった。交通網は寸断され土砂で家々が埋まる中、総社市の高校生約2000人のうち、1000人を超える高校生たちがボランティアに立ち上がった。被災した子ども達も多かったことを思えば、信じられない数字である。豪雨災害という地域の課題に、地域を愛する教育と、全人教育の中で育った子ども達が協力して立ち向かい、解決していったのである。
「地域の課題は地域で、地域の人材が解決する」のである。「待っていれば“オカミ”が解決してくれる」わけではない。もちろん完璧な実践などあり得ないが、総社では10年続けた全人教育が地域の課題の解決の最先端で活躍した。この事実が皆さんの参考になれば幸いである。