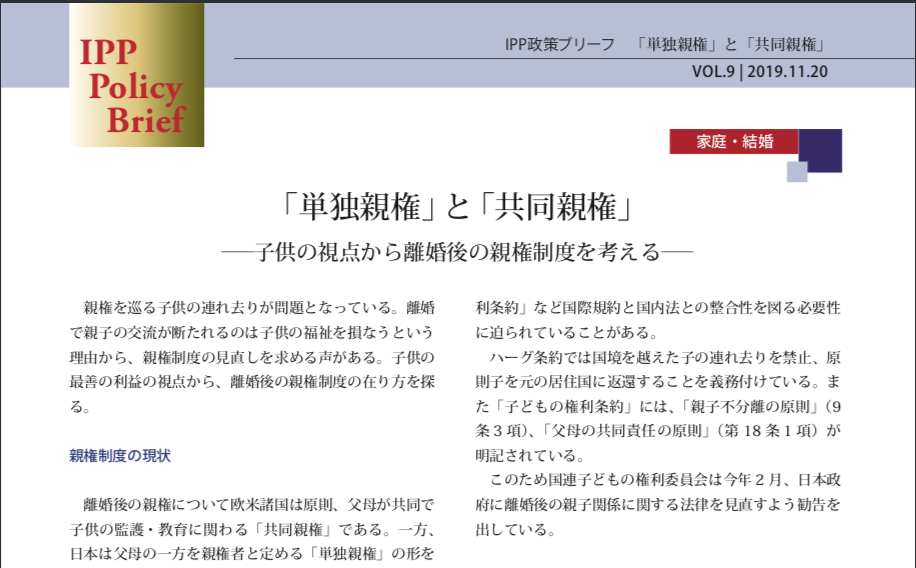1.児童虐待防止対策の強化に向けた政府の「緊急総合対策」
学問を通して虐待死予防に貢献する
2003年以降の警察や厚生労働省からは、毎年100人前後の児童虐待死があると発表されてきた。実の親が我が子を殺害するのだから、その数字の背後には凄惨な光景が想定される。
ただ、2018年7月末に政府が重い腰を上げて「児童虐待防止の緊急対策」をまとめたのは、そのような社会的事実を把握したからではない。6月初めに警察が公表した目黒の結愛ちゃんのあまりにも無残な虐待死(3月に死亡)により、国民の大半が大きな衝撃を受けて、政府に「何とかせよ」と迫り始めたことが直接的な契機になった。
遅きに失するとはいえ、もちろん何もしないよりはずっといい。いたいけな5歳の子どもが残した「ひらがなの文章」に号泣した国民は数多い(資料1)。同時にこの子が二度と書けない世界に旅立ったことで、続報に接するたびにやりきれないというネットでの書き込みが急増する。私もその一人である。
この児童虐待死こそは、高齢期の研究で最近話題になってきた「ウェル ダイイング」(well dying)とは真逆の「ワースト ダイイング」(worst dying)の象徴である。前者が、患者の残された人生の価値やQOLをいかに高め、どのようにして穏やかな死へ導くかについての内容(wellの比較級betterに届かない)であれば、後者は親が無力で無心な自らの子どもを殺害するという最悪の最上級(badのworst)の言葉である。
幼児虐待死では無力で無心な子どもには何の罪もなく、すべては大人の責任である。それを社会全体で反省して、直接の加害者である親を厳罰に処すべきという主張も当然である。ただ、曲がりなりにも社会学からの「少子化する高齢社会」の研究を正業としてきたわが身であれば、その反省に停まらずに、学問を通して児童虐待死の予防に貢献できる途を探求したいと願い、8年が過ぎた。
政府による「緊急の重点対策」のうち組織面については、児童虐待に関連が深い2つの組織間の情報共有や連携、および専門担当者の増員が謳われた。すなわち政令指定都市間や都道府県を超えた各地の児童相談所(以下、児相)間の情報共有、そしてもう一つは児相と警察との情報共有を打ち出し、児相の専門性の強化を優先するとされた。都道府県を越えた広域的な児相間の協力関係の強調に加えて児相と警察との連携も、目黒事件の反省に基づくのであろう。信号機の設置にしても食品添加物の規制にしても、誰かが犠牲者になり、世論が過熱しないと、政治も含めた社会システムの改変に結びつかないのは、日本の社会特性ですらある。
児童福祉司を増員できるか
専門担当者として児童福祉司については、2016 年度~2019 年度の現行プランでは確かに550 人程度の増加しか計画されていなかったから、今回の緊急対策ではその4倍程度の増員になる。2017 年度の配置実績は3253 人だから、完成年度には5200人ほどの児童福祉司が業務を担うと予想される。
「児童相談所の体制強化」として児童福祉司の2000名の増員の費用は、一人の年間給与を500万円、保険などの支払いや業務費用の増加を500万円とすれば、2000人で一人当たり費用が1000万円として、その予算合計は年間200億円程度である。これで年間100人(16年度は77人)程度の児童虐待という殺人が減少して、次世代の一人としてきちんと生育するようになれば、国民の大半は納得しよう。
なにしろ効果が疑わしい少子化対策年間予算は2018年度で4兆6000億円(『平成30年版 少子社会対策白書』178頁)であり、他にもたとえば地球温暖化対策と称した無意味な「低炭素社会づくり」を軸とした環境保全経費予算は、2015年度で実に1兆7997億円(『平成30年版 環境白書』240頁)も計上されているからである。
費用よりも危惧されるのは、児童福祉司が大学の心理学や社会学の課程を修めれば得られる資格ではなく、児童福祉法にいう任用資格となっている点にある。各自治体が毎年実施している公務員試験に合格し、一般行政職採用後に児相へ配属されるか、市民課や環境課などから定期の人事異動で児相に勤務して、一定期間の職務経験を経なければ、児童福祉司になれない。このルート以外には、医師、社会福祉士、精神保健福祉士の資格所持者もいるが、児童福祉の実務経験が必要になることは同じである。
任用資格条件が制約となり、2022年までに児童福祉司2000人の増員は困難と思われるが、都道府県の児相と政令指定都市の児相合計で全国に現在約200カ所あるので、たとえ増員できても一カ所平均では10人しか増えないことになる。これでは膨大な業務を抱える児相にとっては焼け石に水に近い。このような実情を知った上での「緊急総合対策」なら、その本気度が疑われる。
なぜなら、政令指定都市のデータで作成した図1のように、現在でも児童福祉司一人当たりの受け持ち相談件数は飽和状態に近いからである。福岡市の110件は論外としても、北九州市、仙台市、札幌市が80件を超えている。中央値は60件くらいであろうが、一人で毎月60件の相談、実態調査、児相チームでの情報共有、アセスメント作成などの業務は1日に3件ずつの件数をこなすことになり、今ですら仕事の限界を越えている。そしてこれは都道府県の児相でも同じ現状にある。
「早期発見と早期対応」
その他、児相内での児童心理司と保健師の増員でも事情は変わらないから、専門職員の増加は簡単ではない。たとえば2016年厚生労働省の「児童相談所強化プラン」では、2019年度には児童福祉司2人につき、児童心理司1人以上を配置するとされていたが、未達成に終わる見込みである。ただし日本全体で数的に余裕のある弁護士に関しては、報酬次第で配置が可能かもしれない。
このように、各種専門家の養成は短期間には無理なことを承知の上での「緊急総合対策」なのであろうが、その目標設定はいちおう評価できる。
その他、たとえば一時保護に関しては、「保護所の個室化」や「里親委託」など「個別性を尊重した一時保護」が強調された。また児童虐待の「早期発見と早期対応」の重要性が繰り返され、いままであまり機能していなかった自治体の「要保護児童対策地域協議会」(要対協)の役割が特に強調された。しかし「要対協」の構成機関には児童虐待の専門性に欠けるところも多い。たとえば札幌市では30構成機関だが、厚労省が想定する構成機関も、「児童福祉関係」が11機関、「保健医療関係」が7機関、「教育関係」2機関、「警察司法関係」が2機関、「人権擁護関係」が2機関、「配偶者からの暴力関係」が1機関となっており、総計が25機関になる(厚生労働省ホームページ2018年7月25日)。そのうえ、「地域の実情に応じて幅広い者の参加」が可能であるとしている。
いくら集まってもほとんどの機関の児童虐待への対応能力は、児相の高水準とは比較にならない。また25機関の代表者が一堂に会するための日程調整の雑務は膨大なものになるはずである。「緊急対策」ではそのあたりの配慮は皆無のままである。そのような事情から、「要対協」はこれまではほとんど開店休業状態にあった。
その実態として、「北海道新聞」の「子どもを守ろう」連載記事によると、道内で2008年度から2017年度の10年間で少なくとも27人の子どもの虐待死があったとしていて、そのうち検証報告書は4件しかないと報じた。このうち札幌市児童虐待関連で3件の報告書があり、うち1件は私がほとんどを執筆して、他の1件も最終的な取りまとめの責任者となった。両方の経験では「要対協」の会議はなかった。それ以外の2件の報告書作成でも「要対協」は開かれなかった(「北海道新聞」2018年7月24日)。「緊急総合対策」では「要対協」強化が謳われているが、ここで指摘した問題点にどう応えるのかは書かれていない。
家庭への立ち入り、警察との連携
組織面とは別にもう一つの運用面での重点は、虐待通告を受けても48時間以内に子どもに会えない場合、「立ち入り調査を実施」することを明記して、さらに必要に応じて警察などの「援助要請」ができるとしたところにある。同時に、「保育所などに通っていない子どもの情報を自治体が集約し、所在の確認」を目視により速やかに行うことがあげられた。
しかし、この警察との情報共有、協力、連携は言うは易しく、行うのは非常に困難である。なぜなら組織目標が異なるからである。児童虐待に関する警察業務は、虐待が疑われる全事案を児相に通報することであるが、児相では独自の判断で警察に情報提供する事案を決めてよいからである。これまでにも多くの場合、警察への通報情報には「重大な案件」しか選ばれていない。このギャップに加えて、警察の本来の業務は事件化した児童虐待の捜査と加害者の逮捕になるが、児相では子どもの家庭復帰や家族支援を優先する傾向をもつ。そのため、私は児相から児童虐待関連の業務のみを警察に移して、「子ども交番」を提起した(金子、2018b)。
一番の根拠には、法的には2008年から可能になった強制的な「臨検」(立ち入り検査で子どもの安否確認を行う)は、北海道内でも10年間全く行われてこなかったことが挙げられる。児相がこれをやると、虐待家庭の親との関係が修復不能になるからという理由による。これは分かるが、その結果、虐待死が繰り返されてきたことを思えば、そろそろ制度変更も視野に入れたほうが良いと考えたからである。
しかし、作文した限りでも政府が「緊急総合対策」を行うのであれば、いずれも結愛ちゃんを始め、毎年100人前後(後述するが、小児医学会の推計では350人)も虐待死させられた児童の無念を考えると、年内といわず行政得意な表現の「可及的速やかに」すべての取り組みを開始してほしい。
「緊急総合対策」に対して、新聞各社の反応は好意的だが、軒並み以下のような判で押した結論を社説に書いている。「児童虐待の防止に即効薬はない」(毎日新聞2018年7月23日)、「特効薬はない」(朝日新聞2018年7月25日)、「児童虐待防止に、何か一つの特効薬はない」(日本経済新聞2018年7月26日)、「児童虐待対策に即効薬はない」(京都新聞2018年7月26日)。もちろん、「要対協」問題への視線もなく、独自の対策などは何も書かれていない。
これでは新聞特有の口癖である「国民の知る権利」を満たしていない。「特効薬」や「即効薬」がないことはこれまでの数多くの事件で証明されている。だからといって、言論機関としてその程度の「結論」は社説に書くには値しないであろう。科学的な研究成果への目配りがもう少しあれば、「特効薬」の断片くらいは見えるはずである。
2.科学の力で虐待防止の「特効薬」の成分を見つける
毎日1人が虐待死する現実に対して
マスコミ人は「取材」というが、私たちが「調査」と呼ぶ一連のデータ収集と分析をきちんと行えば、新しい事実が浮き彫りになる。現に日本小児科学会の細かな分析で年間虐待死が警察や厚生労働省の100人前後ではなく、350人程度という新しい数字が確認された(溝口史剛ほか、2016:668)。350人では、毎日一人の子どもがその親から殺害されたことになる。この事実を報じただけでは不十分であり、その方法と内容にまで踏み込んだ解説がマスコミでもほしい。そしてこのレベルに届いてこそ、国民は知る権利を満喫できるであろう。
私も社会学の方法により、15年以上の全国統計データ分析と札幌市での15年を超える時系列的調査を通して、いくつかの新しい動向をまとめたことがある(金子、2013;2014b;2016;2018a)。これらも共有しつつ、マスコミもまた独自の情報源を通して、科学調査以外の「特効薬」の成分の一部になるような新事実を報道してほしい。
私は40年にわたり、理論と学説を学ぶ傍ら、実証的な方法で「少子化する高齢社会」と命名した日本社会の断面を調査して、分析して、提言する手法により、社会学の教育と研究に微力を尽くしてきた。児童虐待死は少子化研究における一つの応用問題であるから、家族論だけではなく社会調査法と地域社会研究も融合させた総合的観点を堅持するしかない。
「虐待統計」の変容
たとえば、週刊誌でも新聞各社の報道や社説でも全く触れられないテーマの一つに、「虐待統計」の変容問題がある。具体的にいえば、「家庭内DVを心理的虐待に算入する」とした2013年度の警察庁通達がもたらした全国的な混乱について、マスコミも含めた社会全体の無理解がある。なぜなら、札幌市でも通達以前は全体の15%だった心理的虐待が、14年度以降は60%を超え、時系列の比較が不能になったからである。全国統計の心理的虐待でも、13年度は38%だったが、16年度が52%に急増したという結果があり、ここにも同様な問題が感じとれる。社会学からみれば、「家庭内DV=児童の心理的虐待」という変更はあり得ない。
なぜなら、これまでの心理的虐待とは、「タテの加害行為」だけを取り上げて、「親からの子ども」に対する暴言(生まれてこなければよかったなど)、言葉による脅し、子どもからの親に向けての言葉の無視、親による兄弟姉妹間での差別などを含んでいたからである。
ところが夫婦間の家庭内DVは「ヨコの加害行為」である。「DV目撃」は「タテの加害行為」ではないし、まして子どもが不在の時や眠っている時のDVは「目撃」すらできない。
このように「タテの加害行為」と「ヨコの加害行為」とでは、心理的虐待として合算してもデータの質が異なる。柔道三段と将棋四段を合計して七段というのは冗談だが、「タテの加害行為」としての「親からの子ども」に対する暴言と「ヨコの加害行為」としての「家庭内DV」目撃間には、それほどまでにデータの質が相違する。
データの質の違いに配慮しないままに、警察庁が「DV目撃」を心理的虐待として統計に加えた結果、それまで合計では6割を超えていたネグレクトと身体的虐待の実態が見えにくくなった。子どもの命を直接奪う行為はこの両者に含まれる。反対に、新しい統計法で過半数となった心理的虐待で、児童が命を落とすことはほとんどない。そのために、虐待数が増えても児童相談所は虐待家庭への緊急介入としての「臨検」を行わず、虐待がうわさされる親との関係構築を最優先する道を選択する。その結果としての手遅れが繰り返されてきた。
ただし、もちろん家庭内DVは放置されていい問題ではない。速やかに警察などが介入して解決したいが、それをすべて「心理的虐待」として数えていいのかという疑問を、繰り返し私は提出してきたのである(金子、2016;2018a;2018b)。
ネグレクトと身体的虐待予防を最優先に
要するに、児童虐待研究の最大の課題は虐待死を出さないために、大人に何ができるかの解明にある。従来の統計方法によるデータを活用すれば、その可能性が強いネグレクトと身体的虐待予防のための事前介入こそが最優先される対応ではないか。
札幌市の事例で、両者間の相違を見ておこう。新方式の統計方法では、2017年度札幌市の身体的虐待は15%程度になる(図2)。この数字は2012年度の16.8%、2013年度の21.9%と比較しても、大きな違いはない。最大の違いはネグレクト率にある。旧方式の13年度のネグレクト率は60.2%であったが、14年度は30.5%にまで半減した。代わりに13年度15.9%の心理的虐待が14年度では55.6%になり、単年度で実に3.5倍増になった。
事情が分からなければ、札幌市では「タテの加害行為」であるネグレクトをやめた虐待親が多くなり、言葉の暴力と「ヨコの加害行為」としてのDVによる心理的虐待が急増したと考えるはずであるが、これは完全な誤りである。それはなぜか。
幸いなことに、札幌市児童相談所では従来の方法での統計も作成してきたので、それを使って明らかにしておこう。図3では、ネグレクトが依然として過半数であり、児童虐待死の原因として8割を占める身体的虐待が16年度も30%に上り、身体的虐待とネグレクトの合計が80%を超えていることが分かる。新旧どちらのデータに依拠すれば、最終目的である児童虐待死予防の効果を高める議論の素材が獲得できるか。
従来方式の統計結果を使えば、コミュニティレベルで高齢者中心のネグレクトに対処する防止活動を継続する意義は依然として存在する。ネグレクトが過半数であった札幌市では、民生委員を始め町内会、子ども育成会、まちづくり推進協議会などの主力である高齢者によるネグレクト防止のコミュニティ活動を長い間展開してきたが、この意義は依然として大きいと評価していい。
主たる虐待者として「父親」が急増した理由
次に、4種類の児童虐待において、「タテの加害者」である虐待者の内訳はどうか。
図4は4つのカテゴリー、実父、実父以外の父親(以下、義父と略称)、実母、その他(義母を含む)間の推移である。念のために札幌市児相の提供により各年度の被虐待者数を記せば、その合計は2011年度が437人、2012年度が435人、2013年度が402人であり、家庭内DVが新規に加算された2014年度になると1159人に急増して、以降は2015年度が1480人、2016年度は1798人、2017年度が1913人である。
何も知らずにこの合計数だけの変化を追うと、札幌市では2014年度から児童虐待が3倍増になったとまとめざるをえない。統計の恐ろしさを講義で示すにはいい素材だが、現実的な児童虐待防止の現場では混乱だけしか残らない。警察ではDV一件ごとに書類作成して児相に送付するが、その細かな作業による労力の代償として、大きな過ちを引き起こした。なぜなら、児童虐待総数とともに加害者像までも変えてしまったからである。この反省もまた警察をはじめどこからも聞こえてこない。
図4から、14年度から加害者像が変容して、7割を占めていた「実母」犯人像が壊れて、「実父」と「義父」(実父以外の父親)の合計が6割を超えたことが分かる。児童虐待も都市文化の歴史の一翼を占めるから、たった1年で劇的に加害者像が変わることはない。
繰り返してきたように、ネグレクト中心で虐待者が確認されていた13年度までは、主たる虐待者である「実母」の比率は70%を超えていた。しかし14年度以降は、それまで15%前後しかなかった「実父」が45%に急伸したうえに、「義父」でさえも10%前後を占め、合計で「父親」が主たる加害者の比率が60%前後に増加した。
この結果からも、一般市民はもとより、児相に人事異動してきた職員でも理由がわからないまま、札幌市の「父親」が急に狂暴になり、児童虐待の主犯になったと勘違いをするはずである。もとよりそれは統計上のマジックなのだが、この全国的な混乱について警察庁は無言のままであり、5年が過ぎようとしている。
家庭内DVと心理的虐待の統計
警察が確認した家庭内DVは一件ごとに書面で児童相談所に送り、それが心理的虐待に算入されるから、素材としてはその個票しかない。今回札幌市児相の地域連携課地域連携担当係の特別のご協力により、すべての個票を個別分析していただいた結果、図5が得られた。なお、実数的には図2の「心理的虐待」(59.5%)にほぼ対応する。
まず、「心理的虐待」は家庭内DVという「暴力目撃」を含むか含まないかに大別される。17年度の札幌市の1139件の「心理的虐待」は、児童虐待総数1913件のうち59.5%を占める。このうち「暴力目撃」を含む実数が933件でその比率が81.9%、13年度までは「心理的虐待」であった「暴力目撃以外」数は206件(18.1%)となる。警察庁通達がなければ、札幌市の「心理的虐待」は21%にとどまり、児童虐待総数でも1213件に減少する。
その2017年度個票分析からは、いくつかの重要な統計的事実が確認できる。一つは、従来の「心理的虐待」に属する家庭内DV「目撃以外」(子どもへの暴言、差別、親に向けての子どもの発言の無視など)では、「実父」と「義父」の合計が50%、「実母」と「その他」(義母を含む)も50%となった。
しかし、家庭内DV「暴力目撃」ではDV加害者のうち「実父」が71.9%を占めて、「義父」8.3%を加えると、実に「父親」の加害者率は8割に達した。俗にいう「親父がおふくろをなぐる、ける、引きずり回す」などのイメージにこれは合致する。
反対に、DV加害者のうち「実母」が15.5%からは、何が浮かんでくるか。包丁や刃物を使って亭主に迫る様子か。手もとの物を投げる行為か。「その他」(義母を含む)を加えると、警察が把握したDV全体では、男から女への一方的な加害行為だけがDVなのではなく、逆方向の加害行為が2割存在していた。これもまた、正しい統計的分析結果による事実であり、これまでの警察発表でもマスコミ社説でも皆無の情報である。
統計情報は科学的な論理に合致して初めて有効であるが、これまで見てきたような異質のデータが混在したままでは、その適切な利用は難しい。
警察からの虐待通告が肥大
さて、児童虐待予防の筆頭は早期発見に尽きるが、そのための基本情報として「児童虐待通告経路」のデータがある。当然ながらここでも時系列データが使えず、2014年以降の変化にとまどう。データ収集に際しては、通告経路の選択肢自体に家族親族、近隣、知人、福祉施設、医療機関、警察、学校が含まれるので、統計的分析を行うには少しまとめたうえで、総合的な判断を行うことになる。
札幌市の場合、各年度の通告件数は、11年度が710件、12年度が940件、13年度が998件であったが、これまでと同じく14年度は1256件と急増した。そしてこの総数増加は15年度も続き、総数は1366件、16年度が1398件、17年度が1494件と増加の傾向が鮮明である。
14年以降の内訳は図6で示した。DVを心理的虐待として児相に通達する警察は「通告経路」でも断然第1位になった。要するに従来の統計手法では、札幌市の通告経路は「近隣・知人」の「コミュニティルート」の経路と「警察」と「学校」を一緒にした「アソシエーションルート」の経路に大別されていたのであるが、DVを統計に含むようになって「近隣・知人」からの「通告経路」が細くなり、「警察」からの通告ばかりが肥大してきた。そしてこの傾向は全国の児童相談所で顕在化した。
警察が児童虐待通報経路の筆頭になったとして、それが児童虐待防止に何を残したか。そのルートが肥大しても、児童虐待死の予防とは直結していない。むしろ現場の混乱と時系列的研究を不可能にさせるという「意図せざる効果」を引き起こした。このデータの持つ意味を、警察庁担当者もマスコミ社説執筆者も熟慮してほしい。
「児童虐待の通告経路」を市民レベルで周知して、通告意識を喚起するには、「近隣・知人」からの通達である「コミュニティルート」の掘り起こしが不可欠である。元来札幌市の通告経路は、類似の神戸市と福岡市と比較しても分かるように、「コミュニティルート」が半数を超えており、「学校・警察その他」としては3割程度しかなかった(金子、2016:199)。すなわち、政令指定都市人口でいえば、横浜市、大阪市、名古屋市の次に位置する札幌市、神戸市、福岡市では、4割から5割の「コミュニティルート」が筆頭にあり、3割程度の「警察・学校その他」という「アソシエーションルート」が第2位という構図が2013年まで続いてきた。
全体を総合すると、「コミュニティルート型」(家族・親族、近隣・知人の合計)と「アソシエーションルート型」(学校・警察、福祉施設、医療機関の合計)が半々であったという歴史がある。その意味で、児童虐待死予防には警察だけのルートよりも、「コミュニティルート」でも「アソシエーションルート」でも可能な限りの児相への通告を期待してきたのである。これが2014年に大幅に変容したまま現在に至っている。
3.児童虐待の背景に家族機能の消滅
家族変容への対処が必要
児童虐待の防止には、これまで触れてきたように、虐待親(毒親とも表現される toxic parentsの訳)への非難に止まらず、「コミュニティルート」と「アソシエーションルート」の通告経路の拡充を含めて、社会全体での虐待防止の取り組み方を作り直すことが先決である。その前提に現代日本の家族変容への対処がある。
本来家族には、固有の子育て機能として「子どもの社会化」がある。生まれた子どもは、家族の中で言葉を覚え、規則を知り、多くの知識を身につけて、大きく育ち、社会的な存在になる。それを最初に導くのは、基本的には親とその家族である。
ところが、日本社会ではこの数十年間で徐々に小家族化が進行した。平均世帯人員は、住民基本台帳レベルで見ると1955年の4.90人が、2017年では2.23人にまで低下している(表1)。国勢調査でも国民生活基礎調査でも類似の方向にある。
構造が変化すれば、並行して機能も変わる。構造面での小家族化は家族機能を縮小させ、家族が継承してきた家風としての伝統や規範なども衰退させる(金子、1995)。老幼病弱の保護、子どもの社会化、娯楽機能、宗教機能など本来の家族機能は成員数に比例しがちであるが、平均世帯人員が2.23人では家族力に限界があり、高齢者の介護も看護も在宅治療もままならず、要介護高齢者の大半が施設入所や病院への入院となる。その結果、高齢者の入院期間が長くなり、とりわけ後期高齢者の医療費は増加する(金子、2103:131-165)。
家族には、「稼ぎと消費」という経済機能だけではなく、「高齢者や子ども、病人や弱者の保護機能」、「子どもを育てあげる社会化機能」、「家族全体での娯楽の機能」、「宗教機能」などがあったが、小家族化はこうした家族機能を縮小させ、消滅させた。
この延長線上に児童虐待の背景が浮かんでくる。「子どもの社会化」と「親のパーソナリティの安定化」という家族の二大機能は、日本家族でもこの70年間、かろうじて残ってきた。
ただし、失業、貧困、病気、離婚などが複合原因になり、家族がもつ社会システムとしての企業や職場、学校、地域などとの結びつきを切断された親の一部が、児童虐待に走るようになったのである。
離婚したあと、女性が別の男性と子連れ再婚して悲劇が起きる例も多い。「親のパーソナリティの安定化」は、一定の収入の下、夫婦間でも親子間でも親密な相互作用が続かなければ、実現できないことである。
また、「子どもの社会化」は、その親が祖父母世代から、時代の文化や規範、道徳や伝統を受け継いで、次世代の子どもに伝えるという三世代間に関連する機能である。
例えば、母国語や社会の規範や規則を子どもに教える。それらを学びながら子どもは社会的存在へと成長する。しかし虐待家族では、そういう過去からの伝達が切れ、その子の未来までも奪ってしまう。
虐待の増加はシステムとしての家庭が壊れ始めていることの徴だと考える。自分の子であるにも関わらず養育放棄をして、食べさせない、病気なのに医者に連れて行かない。この代表的ネグレクトは身体的虐待とともに、児童虐待死の二大原因になっている。
アメリカの社会学者T・パーソンズ(1902~1979)が、家族内の役割構造について「道具性」と「表出性」を用いて、理論的にその内容を要約している。道具的役割とは、端的には働いて収入を得るということである。パーソンズの時代は父親の役割と言っていたが、現代は働く母親も増えて父親とは限らない。いずれにしても、家族には道具的役割が必要である。一方、表出的役割とは、食事の世話や入浴や看病などの行為全般である。
育児に際しては、道具的役割と表出的役割が不可欠である。実際、歴史的にもどこの親でもこれを連綿と行ってきた。最も大切な親役割は「子どもを育てる」ところにあり、つまりネグレクトしないことである。ところが、虐待家族ではそれが乏しい。
ネグレクトは、家庭の外からは見えにくい。それでも幼児が暗くなってベランダに放置されていれば、通行人や近所の人が気づき、児相や警察に通報するであろう。そこで虐待を止められるかもしれない。つまりネグレクトの発見と予防が、深刻な虐待防止につながると私も含めて多くの人が判断してきた。
「早母」により高まる虐待の可能性
従来からも、児童虐待の原因と背景について、親の貧困や疾病、家庭内暴力の連鎖など様々な論点が出されている。これらはいずれも正しいところがあるが、その他として私が札幌市で検証報告の際に気づいた虐待要因が二つある。
一つは繰り返し指摘してきたように、本来は「ヨコの加害行為」である家庭内DVを、従来は「タテの加害行為」のみだった心理的虐待に強制的に算入させたことによる混乱がある。
もう一つは20歳未満の出産者を「早母」と定義すると、以下の動向が把握できる。厚生労働省の社会保障審議会がまとめた日本全体で集計された検証報告を読むと、第1次報告(2003年)から9次報告(2013年)までの統計で、虐待死者総数218人のうち100人が0日・0か月、つまり生まれて1か月もたたずに亡くなっている。早母は全体の26.3%を占めていた(社会保障審議会児童部会『第9次報告』2013)。また第10次から第13次までの累計虐待死者141人中、表2のように早母率が27.0%になっている(『第13次報告』2017)。
統計的にみると、明らかに「早母」のほうに虐待の可能性が高い。目黒区での被害者である結愛ちゃんの母親は19歳で出産していた。私が2013年に検証報告した札幌市の事例でも、母と長女がともに17歳の出生経験を持ち、この連鎖が家族での児童虐待死を引き起こした。
もちろん注意しておきたいが、「早母」になる人が全て子どもを虐待しているわけではなく、統計上の比率が高いと分析しているだけである。
一方この60年間で男女ともに初婚年齢は5歳以上高くなっているが、日本全国の20歳未満出生の比率は1.3%前後で推移してきた。この期間の「早母」率は不変だったのである。
この1.3%を「児童虐待加害者実母」の早母率27.0%と比較すると、違いは歴然としている。つまり現実の事例として、20歳未満で母親になったケースのほうが虐待の可能性が高くなっているのである(表3)。
こうしたデータ比較を踏まえて、児童虐待予防として、可能な限り「早母を控えよう」という提言ができないものか。データを揃えて、このことを中高校生の前で繰り返し紹介するのは、児童虐待予防の意味がある。18歳になれば結婚が認められる。ただ、本人が十分に社会化されていない段階で子どもができると、俗に言う「子どもが子どもを生む」ことになり、子育てに行き詰まって、虐待に走ることになりかねない。そうしたことも考慮したうえで、結婚や出産を長い人生の中で描こうと大人が反省や経験を語ってもいいのではないか。
「緊急総合対策」や「新聞社説」では見落とされている重要なデータから、「特効薬」に近づくための予防方法も工夫される。本節では、その手がかりがいくつかのデータ分析から得られた。
4.虐待死を防ぐための提案と「子育て共同参画社会」づくり
あまりに低い「社会的養護費用」
まずはお金の問題から始める。周知のように児童虐待に関連が深い予算である「社会的養護費用」において、日本はその割合が非常に低い。すなわち、社会的養護を「虐待を防止・対応・自立支援をする」と理解して、「社会的養護費用/名目GDP」(P、protection)をいくつかの国と比較してみると、表4が得られる。
GDPの総額は国によっての違いはあるが、それでも日本におけるPの比率の低さは著しいものがある。Pをいくつかの国と比較してみると、アメリカやカナダは2.6%、ドイツは0.23%だが、日本はわずか0.02%である。実際の金額も1000億円程度しかない。合計した少子化対策費用年間4兆6000億円、生活保護費用年間4兆円と比較しても、1000億円では少ないことが分かる。
目黒の事件の教訓として、施設の充実とともに人材を増やすべきという意見も多く出ている。既述したように、児童福祉司1人につき60件の事案を担当すること自体の深刻さがある。「緊急総合対策」では「児童福祉司」2000人が打ち出されたが、政治もマスコミも日本人全体も、行政改革とは公務員を減らすことだと理解してきたために、200億円程度の増員に止まるのならば、事態の改善は容易ではないであろう。
「子ども交番」の設置を
児童虐待に関して警察と児相との連携や情報共有は簡単にはできないという見通しの中で、それに代わる方式として専門職が常駐する「子ども交番」の設置を主張した(金子、2018b)。具体的には児童相談所から虐待対応業務のみを切り離して、警察にそれを移管して「子ども交番」を設け、専門家を増員するという計画である。虐待の通報を受けて確認のために家庭訪問をする際も、児相よりも警察のほうが親と話しやすいし、効果が高いだろうという判断からである。児相の「臨検」が実行されないままに、各地での虐待死させられた児童の無念を思うと、しかも事実としては殺人事件であるから、警察が動いたほうがいいと考えたのである。
ただし「子ども交番」には、児童福祉司だけではなく、心理カウンセラーやソーシャルワーカーなど子どもに対応できる専門家に職員として常駐してもらう。これもまた行政改革であり、次世代の軸となる子どもを虐待から守るためならば、1000億円単位の予算増も国民から支持され、意味のある組織改編になるはずである。
「適切な親役割モデル」
虐待死につながるネグレクトの原因には、大都市特有の小家族化、家族規範の弱さ、離婚率の高さが複合している。だから、ネグレクトの補償因子である「適切な親役割モデル」、「十分な収入が得られる就労状況」、「適切な支援システムの存在」などが児童虐待予防政策の基幹になる。札幌市では、「適切な親役割モデル」や「適切な支援システムの存在」に有効な三世代同居率が、政令指定都市では最低ランクの2.2%しかなかった(図7)。
その状況下では「適切な親役割モデル」の家族内継承と「適切な支援システム」が社会的に見ても不十分であった。そのため、札幌市ではそれらの機能を地域社会のネットワークや行政やNPOなどで代替させる政策が優先されてきた。これは三世代同居率が低下傾向にある政令指定都市全体にも通用する対応になる。ネグレクトの予防対策として、家庭内では「適切な親役割モデル」、職場での「十分な収入が得られる就労状況」、近隣と児童相談所や「子ども交番」などからの「適切な支援システムの存在」などが考えられよう。
もちろん、三世代世帯であれば全てうまくいくというわけではない。祖父母が虐待に加担している事例もある。それでも祖父母世代が近居か同居していたほうが子育てノウハウを子ども夫婦に伝えられるし、子育て支援ネットワークも広がる。可能性として救いの手が多くなり、「子育て共同参画社会」が見えてくるのである。
社会全体で子どもを育てる仕組み
開始されてまもなく20年になる介護保険は、要介護高齢者を家族だけでは支えきれない現状から、社会全体で支援する仕組みとして国民からは高く評価されている。この理念を活かして、子どものための仕組み作りを20年前から主張してきた。
家族が小さくなり、弱くなる傾向を変えるのは難しい。それを受け入れながら、今の子どもたちが次の世代をどう育てるか。皆の力で育てるならば、今後は「子育て共同参画社会」になる。
そこでは介護保険に類するような仕組み、「子ども保険」と呼ぶ人もいるし、私は「子育て基金」と表現しているが、そういう仕組みを持った社会を「子育て共同参画社会」と命名してきた。そして子育ても介護も社会全体で担っていくことが、実は児童虐待や高齢者虐待の予防ないしは減少につながると考えている。それと、虐待をした親をただ責めるのではなく、親が置かれた状況をしっかりと認識しておくことも重要であろう。
目黒の児童虐待死をはじめ虐待死の報道に接するたびに、その悲惨な場景が浮かぶ。多くの国民が同じ気持ちであると思う。ただ私たち大人は、涙の次にこのような不幸をなくす努力を始めないと、結愛ちゃんをはじめとした虐待死させられた子どもの無念さに応えられない。
児童虐待予防へ向けた9項目の提案
私は、社会全体で取り組むべき予防に直結する対応として、次の9項目を提案したい。これらもまた「特効薬」の成分となるはずであり、国民各層での議論のたたき台にしてほしい。
(1)児童虐待死は殺人罪とする。
(2)20歳未満で出産する「早母」、その相手の「早父」の危険性を義務教育段階で周知徹底させる。
(3)就学前の児童の小児科検診を2か月おきに国費で行う。
(4)児童虐待対応のみは児童相談所から警察に移管して、交番に虐待防止担当を新設して、「子ども交番」として虐待対応に専念する体制を整える。
(5)その職員はすべて心理カウンセラーやソーシャルワーカーなどの有資格者とする。
(6)「子ども交番」は、予防介入を通して被虐待児の救出に全力を尽くす。
(7)虐待されている児童の一時保護期間を2か月から5年間に延長して、その育児施設を国費で速やかに造る。
(8)延長判断は家庭裁判所だけではなく、「子ども交番」が中心になり、学識経験者その他の専門家の意見を聞いて、行う。
(9)立法、司法は、虐待死させられた児童の人権を最優先の判断軸として、加害者には厳罰を科す。
漱石『草枕』の中に「住むに甲斐ある世」という言葉がある。社会学という学問は、「住むに甲斐ある」社会をつくるためにあると私は考えて、微力をつくしてきた(金子、2018a)。
目黒の結愛ちゃんの虐待死によって、何とかしなければならないと考えている国民は多いはずである。社会の仕組み、風潮がどこかおかしいと感じる人も多いであろう。それを単に感情的にではなく、また「特効薬がない」と嘆かずに、学術的ないくつかのデータ分析から具体的な提言までもっていきたいという願いがある。
児童虐待の防止は、制度改革や地域での子育て支援とともに、やはり家族政策が中心となる。家族機能が低下してきたところに、児童虐待や高齢者虐待という問題が出てきた。小家族の機能を改善するために、「住むに甲斐ある世」に次世代が近づくために、学問の無力さを感じつつも、できるだけのことをやっていきたい。
【参考文献】
Forward S., 1989, Toxic Parents, Bantam. (=1999 玉置悟訳『毒になる親』毎日新聞社).
Helfer, M. E., Kempe, R. S., and Krugman, R.D., 1997, The Battered Child(5th ), The University of Chicago Press. (=2003 坂井聖二監訳 『虐待されたこども』 明石書店).
Herman, J. L., 1997, Trauma and Recovery, HarperCollins Publishers, Inc. (=1999 中井久夫『心的外傷と回復』<増補版>みすず書房).
Horn, P.V., and Lieberman,A.F.,2011,「DV目撃の子どもへの心理的影響ならびにその治療」Jenny, C.,(ed.), Child Abuse and Neglect, Elsevier, Inc. (= 2017 日本子ども虐待医学会監訳『子どもの虐待とネグレクト』金剛出版):800-826.
金子勇,1995,『高齢社会・何かどう変わるか』講談社.
金子勇, 2013, 『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.
金子勇, 2014a, 『「成熟社会」を診断する』ミネルヴァ書房.
金子勇, 2014b, 『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会.
金子勇, 2016, 『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房.
金子勇, 2018a, 『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房.
金子勇, 2018b, 「児童虐待死防止のため何をすべきか」(『En-ichi』 No.333 圓一出版): 4-10.
環境省, 2018, 『平成30年版 環境白書』日経印刷.
Miller-Perrin, C. and Perrin, R., 1999, Child Maltreatment, Sage Publication. (=2003 伊藤友里訳『子ども虐待問題の理論と研究』 明石書店).
溝口史剛ほか, 2016, 「パイロット4地域における、2011年の小児死亡登録検証報告」『日本小児科学会雑誌』120巻3号:662-672.
内閣府,2018,「平成30年版 少子化社会対策白書」日経印刷.
夏目漱石,1929=1992,『草枕』岩波書店.
Parsons, T. & Bales, R. F., 1956, Family: Socialization and Interaction Process. Routledge and Kegan paul. (=1981 橋爪貞雄ほか訳『家族』黎明書房).
札幌市子ども未来局, 2017, 『「札幌市子どもの貧困対策計画」策定に係る実態調査』同局.
札幌市児童相談所編,2018,『児童虐待ハンドブック』同相談所.
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会, 2017, 『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について第一三次報告』(二〇一七年八月) 同委員会.
日本社会事業大学社会事業研究所編,2016,『平成26年度厚生労働省児童福祉問題調査研究事業:社会的養護の国際比較に関する研究』同研究所.
本研究は「JSPS科研費 JP15K03903」の助成を受けたものである。