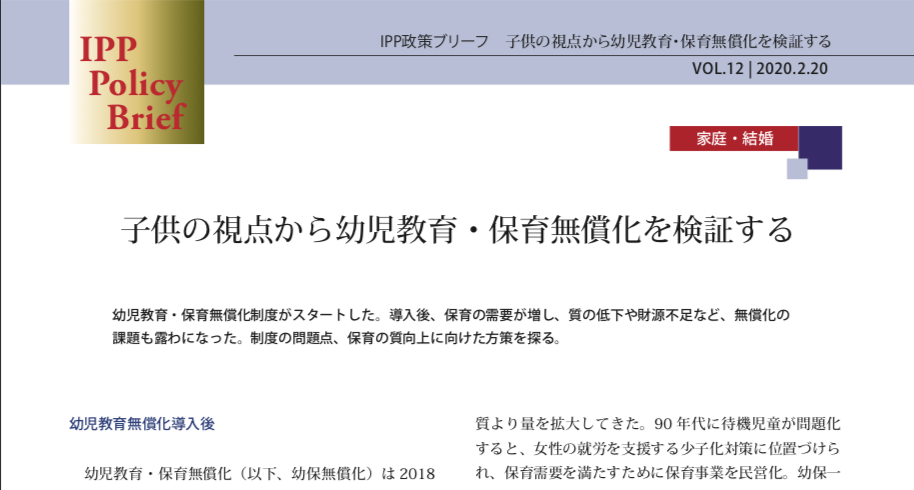1 問題意識
「変化の側面」に軸足を置く家族論
「子ども家族支援」について、最初に私の問題意識をいくつか提示したいと思う。
一つは、私の研究分野は家族社会学、家族心理学、家族福祉の領域に軸足を置いているが、家族論における“バランスの悪さ”を感じることである。家族現象には時代と共に「変化していく側面」と「変化しない普遍的な側面」があると考えている。しかし、家族論は、変化する側面に軸足を置いた研究が大半である。例えば、家族社会学の研究領域の一つに「家族変動論」がある。家族変動は、形態変動(家族の形の変動)と機能変動(家族機能の変動)の二つに分かれるが、どちらかというと形態変動の議論が主流で、機能変動に関する議論はあまりない。
それに加えて、変化によって生じる負の側面はあまり自覚されることはない。例えば、家族の「個人化」や「多様化」という形態変動の議論は盛んだが、「家族との情緒関係」という機能変動の側面はすっぽりと抜け落ちている。「個人化」や「多様化」に対して「情緒関係」への関心が低く、疎かにされてしまうというバランスの悪さを感じる。
共感性が後退した人間社会
また、霊長類学が専門の山極壽一氏(京都大学総長)は、主にゴリラの社会に見られる「家族の論理」、サル社会に見られる「集団の論理」を例に、今まで人間の家族は「家族の論理」と「集団の論理」を絶妙なバランスで運営してきた、と述べている。しかし今日、人間社会がサル化、つまり「家族の論理」より「集団の論理」に偏っているのではないかと語っている。集団の論理というのは、要するにボス支配の社会である(『「サル化」する人間社会』集英社インターナショナル)。
また山極氏は、人間社会で共感性が後退していると指摘している。共感性は、共食行動、共同養育によって生まれる、と。つまり、現代社会では共食行動や共同養育が失われ、共感性が育たなくなっているというわけである。もちろん、こうした変化を肯定的に捉えるか否定的に捉えるかで、議論の展開が変わってくる。肯定的に捉えるとすると、人間のサル化や共感性の後退は進化という時間軸の中で起こった必然ということになる。それに対して、否定的に捉えると、人間の本質、あるいは普遍的な家族のあり方から人類は後退していることになる。人間が人間でなくなっているという認識である。以上は、「変化する側面」からの議論である。
他方、「変化しない側面」は、次のようなイメージになる。佐伯啓思氏(京都大学教授)の『反・幸福論』(新潮新書)の一節を引用する。
「家族はふたつの軸が交差することで成り立っています。ひとつは、夫婦であり、これは血筋も家系もまったくことなる男女がつくる横の軸で、もうひとつは、親子という血を共通にする縦の軸です。夫婦の横軸を延長すれば、異なった背景をもつ夫と妻それぞれの家族や親族が出現し、親子の縦軸を延長すれば、父母、さらには祖父母、そして、子供から孫という系譜が出てきます。つまり、家族というものは決して閉じた世界ではなく、二重の意味での他者と遭遇せざるをえない。一つは、異なった文化的背景を持つ集団との遭遇であり、もうひとつは異なった世代との遭遇なのです」。この記述は家族の、肯定的で変化しない側面を示している。
続けて佐伯氏は、「『家族などという窮屈なものに縛られるのはいやだ。家族から逃れたら、もっと自由に生きて、自分のやりたいことができる』というとしたら、それは違う、といいたい。生きてゆくことは、いずれ多かれ少なかれ他人とかかわることで、社会(ソサイアティ)とはいずれ他者との交流のことなのです」。
「だから、本当は、家族こそがもっとも基本的な社会であって、そのもっとも基本的な社会生活をうまくやれなければ、しょせん、本物の社会にでてもなかなかうまくゆくはずはありません。その意味で、確かに家族というものはたいへんに大事なのです」と述べている。
折り合わせる力が落ちた現代の家族
また「家族とは最も激しい軋轢の場なのです」とも指摘している。家族は軋轢や葛藤が生まれやすい場であるが、山極氏の言葉を借りれば、家族の論理と集団の論理を絶妙なバランスで折り合いをつけてきたということになる。しかし、現代の家族はそうした軋轢を折り合わせる力が落ちてきている。そのことが今日の様々な家族問題の出現の背景にあるのではないか。
加えて、現代社会は「私事化社会」である。これを、一部の人は「自己を最優先することは善である」と考えている。しかし、子育てというのは自己を最優先することができない行為である。場合によっては親が一部犠牲を払う行為である。そうすると、そうした犠牲的な側面と、自己を最優先するという価値を折り合わせなければならない訳だが、今の家族にはその力が落ちているというわけである。これは実際に児童養護施設で聞いた話だが、母親が友達からカラオケに誘われる。本人は行きたい。ところが、子供がぐずってしまう。そうすると、ぐずる子供とカラオケに行きたいという自分の気持ちに折り合いをつけなければならない。しかし気づいたら子供に手をあげていた。現代社会ではこうしたことが日常的に起こっている。軋轢や葛藤というのは、人間が生きていく上でのキーワードの一つでもあるが、今日の社会はそれをあえて回避する傾向にあり、そのことが今日の家族問題の背景にある。言い方を換えれば、「関係性を生きる力」のようなものが相対的に後退しているという言い方もできる。
情緒関係が子どものウェルビーイングを高める
二つ目の問題意識は、「家族との情緒関係がキーになる」ということである。以前、「子どものウェルビーイング(well-being、身体的・精神的及び社会的に良好な状態)」について中学生を対象に調査したことがあるが、当初は「家族生活の充実」が子どものウェルビーイングを高めるだろうという仮説を設定した。しかし結果として、この仮説は実証できなかった。そこで「家族との情緒関係」を媒介変数に設定し、「家族生活の充実は、家族との情緒関係が肯定的に内面化されているときのみ、子どものウェルビーイングを高める」という命題を立て、これは実証できた。つまり子どものウェルビーイングには家族との情緒関係がキーであることが分かった(畠中宗一・木村直子『子どものウェルビーイングと家族』世界思想社)。これは私にとって非常に重要な知見で、もっと広く知っていただきたいことである。
例えば、子どもが一時的にドロップアウトしたり家出したりすることがある。その時に家族の元に戻ってくる力、平たく言えば「絆」ということになるが、家族との情緒関係が肯定的に内面化されている子どもたちは戻ってくることができる。しかし、絆が形成されていない子どもたちは、糸の切れた凧のようにそのまま社会に浮遊していく。
家族支援の目的は親の負担軽減か?
三つ目の問題意識は「家族支援の目的は親の負担の軽減か?」である。利便性、快適性、効率性を追求する社会では、「負担の軽減」が目的になっている。実際、家族支援は親の負担を軽減することだと認識する人が圧倒的に多いと思う。私も、結果として親の負担軽減になることを否定はしない。ただ、家族を支援する目的は親の負担軽減以上に、親子がしっかりと向き合うことができる環境を整えることではないかと考えている。
近年の子育て支援や保育政策は、「サービスの授受関係」(サービスを受けるか受けないか)に転化されているのではないか。その結果、様々な問題も起きている。しかも大人の自己実現と子どものウェルビーイングという二つの命題があるとすると、今の子育て支援や保育政策は大人の自己実現に偏っているのではないか。そうではなく、親の自己実現と子どものウェルビーイングを同時に満たすようなシステムのあり方を探求していくべきではないかと考える。これは1990年代後半、イギリスのチャイルドマインダー(家庭的保育の専門職)の研究をしていた時に強く実感したことである。
チャイルドマインダー
イギリスのチャイルドマインダーには紆余曲折の歴史的経緯があるが、なぜチャイルドマインダーが選ばれているかと言うと、まず子ども、そして親、親を雇用している企業、さらにコミュニティー、これら四つの主体にとっての問いを設定し、最終的な折り合い点を探して判断した結果だということである。こうした政策アプローチは非常に重要だと思う。どこか一点に焦点を絞ると、親が犠牲になったり、地域が混乱したりといったことにもなる。
チャイルドマインダーは保育ママに近い制度で、要するに家庭的雰囲気の中で少数の子どもを預かって対応していくというやり方である。イギリス社会では、労働者階級の71%がチャイルドマインダーを活用している。残りの約3割のうちの1割が公立保育所を、2割弱が民間の保育園を利用している。
チャイルドマインダーという言葉は、ウェブスター・ディクショナリーやランダムハウス・ディクショナリーでは1966年に、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーでは、1972年の補遺版に初めて登場した。100年以上前から存在しながら、チャイルドマインダーという言葉が辞書に現れるまで時間がかかっている。このことは、イギリスが階級社会であることを現している。要するに、労働者階級でもさらに底辺の移民によって多く利用されていたことが、反映されている。
その後、虐待による死亡など、家庭内でチャイルドマインダーに関わる事件や事故が起きる。そうした事件や事故に歯止めをかけるため、マインダーとしての適格者に登録してもらって質を担保するよう、地方政府が行政指導を進める。死亡事故という悲しい歴史を経て、1989年にはイギリスの児童法の中に盛り込まれる。また全国チャイルドマインダー協会(NCMA)が設立され、里親制度とチャイルドマインダーをリンクさせるような枠組みが国の提案で発足する。現在は、全国職業資格(NVQ)という資格一覧にも正式に位置づけられている。質の保証がしっかりとできて、社会で一定のステータスを確保した制度となっている。私は日本でもこうした制度が普及することが望ましいと考えている。きちんと質を担保していけば、有効な制度ではないかと思う。
「共同保育」の視点が希薄化
四つ目の問題意識は「共同保育という視点の希薄化」である。先ほども、保育の場がサービスの授受関係になっているとお話ししたが、保育所を利用する場合でも、「預ける者と預かる者」という関係ではなく、「保育士と親による共同養育」という視点が重要である。 親が子どもを迎えに行った時、担当の保育士から子どもの1日の様子を聞く。親は聞いた内容を手掛かりに、子どもとコミュニケーションを取る。これは共同の子育てである。親は子どもを保育園に預けて、夜はご飯を食べさせて寝かせるだけではない。親は養育の責任者であって、地域の支援を受けて共同で子育てをしている。その点を自覚すべきである。
2 社会変動が家族のあり方に及ぼす影響
「富裕化社会」の命題
次に、社会変動が家族のあり方に及ぼす影響について考えてみたいと思う。
社会科学というのは、社会のあり方が個人や家族に影響を及ぼすという発想をする。社会変動には様々なキーワードがある。例えば、「戦争」「自然災害」「経済変動」「グローバリゼーション」「高度情報化社会」「超高齢化社会」「富裕化」等である。
ここでは「富裕化」を取り上げる。富裕化をキーワードに現代社会を見た時、現代社会は利便性、快適性、効率性を追求する社会というイメージがある。もう一つは、生産的で課題達成型の価値観を重視する社会と捉えることができる。
では、こういった特徴を持つ富裕化社会は、どういった命題を持っているだろうか。
1番目の命題は、「富裕化は私事化を育てる」である。富裕化の議論をする時は貧困社会を対比すると理解しやすいだろう。貧困社会とは、共に生きるとか一緒に助け合わなければ生き残れない社会である。他方、私事化は経済が豊かになっていくことと関係している。村上泰亮氏が「高度に分業化した社会は、新しい個人主義を育てる」と述べている(『産業社会の病理』中央公論新社 1975)が、「富裕化は私事化を育てる」もこれと同じ意味である。
2番目は、「富裕化社会では、私事化の肥大化と規範の希薄化が反比例の関係で出現する」である。これはデュルケームの社会分業論のキーワードになっている。私事化と規範の関係を考えてみると、例えば戦前の社会では天皇制が規範として機能していた。戦後は民主主義、平等主義、個人主義という社会の中で、規範は希薄化し、逆に私事化が肥大化していった。私事化と規範というのは振り子のようなものである。規範が一定の拘束力を持つ社会では、私事の自由は低くなる。現代社会は私事化が肥大化している社会であるから、逆に規範の力が弱くなっている。第一次安倍内閣の時に教育再生会議が創設されたが、これは要するに規範を学校教育に取り戻そうという試みであった。
3番目は、「富裕化社会は、対人関係に抑制的に機能する」である。先ほど軋轢と言ったが、現代はそういう関係に直面しなくても生きることができる社会である。例えば、引きこもりの子どもは親からお小遣いをもらって、コンビニに行って、自分が食べたいものをレジに揃えて、お金を払う。それを持ち帰って自分の部屋で食べる。それを繰り返せば生き残ることができる。何もコミュニケーションを取る必要はない。しかし、貧困社会でこのようなやり方は不可能に近いだろう。だからマクロに見た場合、豊かな社会が引きこもりの予備軍を背後で支えているという解釈もできると思う。
「関係性」を喪失させる富裕化社会
4番目の「富裕化社会は、関係性や繋がりを喪失させるように機能する」と5番目の「富裕化社会は、情緒を育む基盤を喪失させるように機能する」は、3番目の命題のバリエーションである。つまり、富裕化社会は関係性や繋がりを喪失あるいは希薄化させるように機能する。関わらなくても、きちんとした人間関係を営まなくても、生きていける社会だから、結果として関係性や繋がり、さらには関係性を生きる力も相対的に落ちてくるというわけである。
また、5番目の命題は、本来は、縦と横、斜めの人間関係を重層的に生きることによって、しなやかな情緒が作り上げられていく。つまり軋轢や葛藤に対して生き抜く力である。しかし、そういうものが保障されていない。まして家族社会学では個人化や多様化といった形態変動に軸足を置いており、研究量が最も少ないのは情緒に関する研究である。
6番目は、「富裕化社会を維持・存続させるために格差が意図的に容認される」である。例えば下請け、孫請けの存在によって、本体の企業活動が維持されるという構造は、我々の社会の中にインプットされている。
さらに7番目は、「富裕化社会は、グローバル資本主義への参入によって格差が増幅される」である。2000年代初め、小泉政権の登場前の段階から格差はあったが、あくまで一定の小さな範囲で収まっていた。そこからグローバル資本主義に踏み出して、格差が一気に拡大していったと一般的に認識されている。
そして8番目が、「富裕化社会は、実存的空虚感を増幅させる」である。「実存的空虚感」というのは、ビクトール・フランクルの概念である。例えば、小説家を志す人が、苦労して、りんご箱で物書きをしていた時期は勢いがある。その後、賞を取ったり印税が入ってきたりして生活が安定し書斎を持つようになると、途端に筆が進まなくなるといった話を聞いたことがある。つまり、一定の緊張感や物が不足する位の感覚が、人間が生きていく上では必要なのではないかという命題である。
以上の結果、富裕化社会、すなわち生産的・課題達成型の価値観が重視され、利便性・快適性・効率性を志向する社会では、葛藤を伴う関係性を生きることが敬遠されることになる。結果、ますます関係性を生きることが困難になるという悪循環に落ち込んでいくということである。
もう一つ、今年3月に亡くなった精神医学者の吉川武彦氏は次のように述べている(『「引きこもり」を考える-子育て論の視点から』NHKブックス)。吉川氏は、親が持っている規範に押し込む形での育児(規範押し込み型)や、子どもの欲求を親が先取りして対処してしまう育児(欲求先取り型)を行った場合、子ども自身が葛藤する機会を奪われることになると主張している。結果として、葛藤場面に弱い子どもが再生産される。これは引きこもりの臨床研究から導き出されたものである。
3 子ども家族支援の場合
現代社会には、葛藤をはらむ面と葛藤を経験しないですませる面がある。親の思いは、「子どもにしんどい思いをさせたくない」ということかもしれないが、結果としてそのことが子どもの生きる力を弱くしている。やはり背中を押す、自立を促していく力が、親の側にも弱いということではないか。
付け加えると、サービスの授受関係というのは保育だけではない。教育も最近はそういう枠組みで認識する人が多いように思われる。しかしサービスの授受関係では、本来の教育は成り立たないのではないか。結局、商行為の中で作られたロジックが、保育や教育といった領域を侵食しているということである。そういうことにもっと感受性を持って、問い直していくべきではないかと思う。
4 子ども家族支援の課題
「関係性を生きる力」を改善する
さらに、従来の子ども家族支援施策は、環境を改善することが支援の目的となっていた。私が所属する社会福祉分野の基本的な考え方は、与えられた環境を改善していくというものである。それは私も否定しない。ただ、現在の政策も環境を改善するという目的で作られてはいるが、その政策の効果があまり見えてこないということも理解すべきだと思う。言い換えると、主体的な側面に焦点が当てられることはほとんどなかったということである。つまり環境という客体条件を改善していくのが従来の福祉政策だったわけで、そのこと自体は否定しないが、それに加えて主体の側にも働きかける必要があるのではないかと考える。主体の側というのは「関係性」ということである。「関係性を生きる力」をきちんと育んでいく、そうした力の維持・回復を支援するというイメージである。客体条件を改善しながら、同時に関係性を生きる力も改善することによって、重層的に施策が展開されることで有効な支援策につながっていくと考えている。
「関係性を生きる」というのはどういうことかというと、他者を受容し、自己の思いも伝えることができる。これが相互性の中で展開される現象である。例えば、一般に感情労働(看護師など医療関係、保育士、教師などが、他者に様々な配慮をすること)を多用すると本人のメンタルヘルスが悪化するという研究がある。クライアントに対して配慮をし過ぎることで、ケアする側が燃え尽きてしまうという意味である。ただし、他者との関係性を生きる力が高いと、感情労働を多用してもメンタルヘルスが悪化しないという調査研究もある。つまり他者との関係性を生きる力がメンタルヘルスに良い効果を与えるということである。
私は、関係性を生きることの困難が家族病理現象の背景にあると考えている。関係性を生きる力が弱いために、親子関係にしてもきょうだい関係にしても、簡単に問題が起きてしまうのではないか。
これと関連すると思うが、家族への情緒関係が肯定的に内面化されるためには、親から愛されているという実感が重要である。これは臨床の世界では常識である。そのため、児童養護施設などでは、職員をはじめ多くの大人が親代わりになって子どもに精一杯の愛情を注ぐ。今年7月、摂食障害の第一人者である小児科医の生野照子氏にお話を伺う機会があった。生野氏は、摂食障害の治療は難しいが、医者や親だけでなく様々な職種の人が肯定的なメッセージを多く発していくことが回復につながっていくと言われた。しかし、現在の医療の現場では、そういうことができる環境が保障されていない。つまり、正しい答えが分かっていても、財政的な問題などでそれが実行できないこともある。そこをどうクリアしていくかが課題である。
人類にインプットされた共同養育のDNA
それから、霊長類学、脳科学、認知科学などを総動員した明和政子氏(京都大学教授)の研究によると、人類が生き残るために子育てと生産活動をどのように折り合わせるかという課題は共同養育によって対処されてきた。例えば、ゴリラの出産は5年に1回だという。人間は毎年でも可能である。そうすると子育てと生産活動をどう折り合いをつけていくかという時、家族や親族を含めた、あるいはコミュニティーを含めた共同で子育てをしていくという枠組みを持たなければ対応できないというメッセージである。
ママ友の集まりをやると、人がたくさん集まるという。それはもともと人類にインプットされた共同養育のDNAが反応しているからではないかと明和氏は指摘している。しかし、現代社会の子育ては、個人化を前提にしたシステムを採用している。人類にインプットされた共同養育というDNAと、個人化を前提とした子ども家族支援システムにズレがあるのではないか。育児不安や産後うつ、その先にある虐待という現象の拡散は、共同養育という戦略を失った結果ではないかというわけである。
ママ友の集会に多くのママたちが集まるという現象は、人類の進化の中でインプットされた共同養育のDNAが反応しているのではないかという認識は、子ども家族支援のパラダイム変換を考える時、一つの有効な提案ではないかと考える。それぞれの地域社会の文化型に応じた共同養育というシステムを工夫することが課題となるように思う。
(本稿は、9月27日に開催した政策研究会の発題をもとにまとめたものである。)