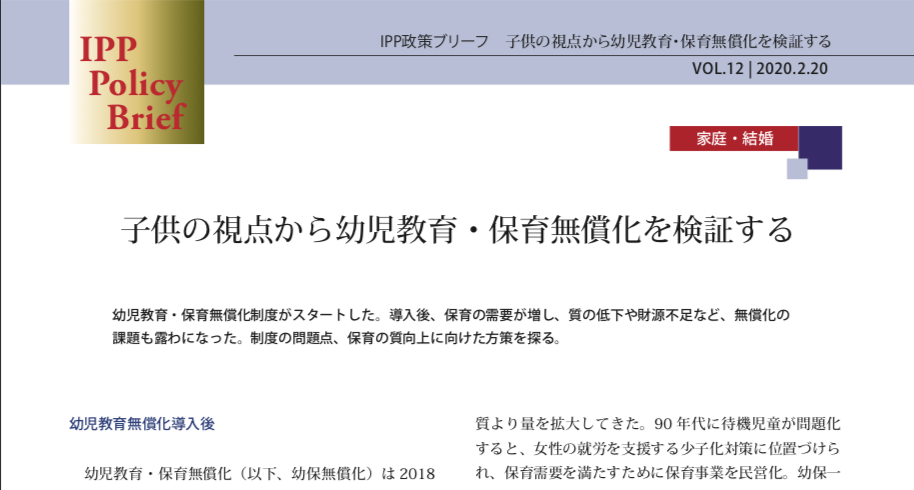はじめに
2017年9月29日、日本学術会議が「性的マイノリティの権利保障をめざして」と題する提言(注)を発表した。同提言は、日本国憲法24条の規定に反し、性的マイノリティの婚姻の権利を求めるなど、問題の多い内容である。なぜ、このような提言が出されたのか、法学的な視点で考察を行っていきたい。
1.法律家の陥りやすい思考の落とし穴
「法律家には非常識な人が多い」、「モラルを軽視し、権利ばかりを重視している」といった批判が少なからずある。例えば、学校が荒れるので校則を厳しくしようとしたら、表現の自由の権利侵害にあたると法律家から言われたという話を聞いたこともある。
長い間、法律の世界に身を置いてきた研究者の一人として、このような提言が出される理由として、法律家が陥りやすい思考の落とし穴があるのではないかと思う。すなわち法律家独特のリーガルマインド、法的思考である。
そこで法律家が陥りやすい思考の落とし穴として、3つの点を指摘したい。一つ目は法が持つ弱点である。二つ目は、近代法が成立した背景から、個人主義・自由主義・平等主義、さらには自己決定至上主義に陥りやすい傾向があること。三つ目として、法におけるダブル・スタンダードである。
法の弱点
法には弱点、不得意な分野がある。法律は社会を支えるルールであるため、その社会に生活するすべての人に適応し、公平に対処しようとする。そのため、多種多様な一人ひとりの人間を抽象化して把握してしまう面がある。
例えば、AさんとBさんという人がいる。Aさんは背が高く、一流企業に勤めているが、少し我儘で旅行好き。Bさんは背が低く独身、話が上手でスポーツ万能、ゴルフが趣味である。AさんとBさんは、外見、職業、性格、趣味が違っていたとしても、憲法学者は二人を同じ日本国民と考える。また、Cさんは21歳の女子大生で、おっちょこちょい。Dさんは18歳の女子高生で、考え方も行動もしっかりしている。しかし、民法学者はCさんを成人、Dさんを未成年者と考える。このように法律家は、人間を抽象化して捉える傾向がある。
アメリカ社会を見てきた経験から、アメリカのケースを見てみたい。アメリカは1800年代半ば、南北戦争で黒人が奴隷から解放されたが、その後も学校、バスの乗り場が別だったり、事実上選挙権がなかったり、差別は続いていた。1950年代から公民権運動が起こり、黒人の選挙権が認められ、実質的平等が実現する。
次に1960年代以降、男女差別撤廃を主張する女性の権利運動が盛んになった。さらに60年代末には、大人と子どもとの法的権利も差別があるということで、子どもの権利運動が生まれた。もちろん、白人と黒人、男性と女性は同じ成人で同等である。ただし、大人と子どもはまったく同じ存在と言えるのかという点は考慮する必要があると考える。
例えば、妊娠、出産できるのは女性だけである。男女の違いに目を向けず、法的に同等の権利を与えれば平等かというと、そういうわけではない。大人と子どもとなると、特に子どもは身体的にも精神的にも成長していく存在である。いくら子どもに権利があると言っても、3歳から自己決定をさせることが正しいかどうか。例えば、栄養バランスの良い食事をとらないと体に悪いという最低限の知識がないまま、子どもに好きな物だけを選ばせてはうまくいかない。自己決定を優先させると、権利はもらえるが子ども自身の利益には必ずしもならないわけである。
法律家が人間を抽象化するときは、よく注意しなければならない。アメリカの一部の過激な人たちは、自由、平等に簡単に向いてしまう。
法律家だけではなく、法の弱点と言うべき、不得意な分野がある。一般的にほとんど認識されていないが、何か問題があると法律をつくって問題解決しようとする、法万能主義に陥りやすいことである。
結果的に、法は人間関係を壊す面がある。例えば、アメリカの著名な法学者ジョセフ・ゴードンステインは「法には、人間関係を悪くすることはできても、良くすることはほとんどできないという難しさがある」と書いている。考えてみると、「近所の人と仲よくしてください」という法律が規定されても、実現は不可能である。逆に裁判になると、往々にして人間関係が壊れることになる。大学の法学部の模擬裁判でさえも、1カ月くらい口を利かなくなるという話がある。同じような意味で言えば、法律でどんなに虐待を禁止しても、それだけでは虐待はなくならない。
もう一つ、法の弱点として、「権利か義務か」という二重構造になることを指摘したい。法は道徳と違って、強制力がかかってくる。違反したら懲役刑になる場合もあり、民事では損害賠償が生ずる場合がある。
ただ日常生活で考えると、お金を貸す行為も必ずしも義務があるから貸しているわけではない。相手が親友だから、家族だから、困っているから力になりたいということもある。そういう一般人に対して、法律家が権利と義務しか言わないのは非常に違和感がある。
売買契約を例に挙げると、売り手のAさんは代金を受け取る権利とモノを引き渡す義務がある。買い手のBさんはモノを受け取る権利と代金を支払う義務がある。法律上はAさんの権利義務、Bさんの権利義務というように個人に焦点を当てた一面的な見方しかできない。そうなると売買契約前のAさんとBさんの人間関係、状況を見渡せないし、見渡す必要がないというのが法の欠点ではないかと思う。
特に法律家は、人間関係における縦関係の感受性を排除しているという弱点がある。個人を中心に考え方を組み立てるのは得意で、個人の権利義務を中心に思考をすすめる。そうなると伝統の重要性、先祖がいるから私がいるという感覚がない。しかも、将来の子孫についての思いやりも少々欠けているところがある。将来世代のことよりも現実に生きている個人が何を望んでいるのか、今の私たち個人に関心を持っているのが法律家の特徴である。
そうなると自分で自己決定できる人はいいが、例えば赤ちゃんや障害を持った人、寝たきりの人、いわゆる社会的弱者と言われる人たちや、これから生まれてくる将来の子孫については後回しになってしまうことになる。
近代法が成立した背景
二点目として、近代法が成立した背景について、ヨーロッパを中心に法体系の歴史を簡単に触れておきたい。まず古代法から始まり、中世法、そして近代法が生まれてくる。
古代法は、小さい村々が点々と存在していた時代、比較的顔の見える少人数社会で適用されていた法である。
その後、人口が増加し、大きな国家が誕生する。中世はフランスのルイ14世のように国王が絶対権力を握っていた時代である。この時代の中世法は、権力者の道具として使われていた面が強かった。身分制度によって貴族と平民では同じ罪を犯しても刑罰が違っていた。親の仕事を継がないといけない、引っ越しをしてはいけないとか、国王が日常生活まで細かく決めていた。不平等、不自由な面が多かったのは事実である。
ゆえに中世の絶対王政国家が倒れた後に、近代法が生まれることになる。その象徴的な出来事がフランス革命である。近代法に変わっていくとき、あまりにも不平等で不自由な中世法への反発から、個人を重視する価値観、自由と平等が望まれるようになった。ここから、個人主義、自由主義、平等主義が近代法の大原則となった。
現在の法律も、個人主義、自由主義、平等主義の3つが規定されている。実は現代の法律は現代法とは言わず、ひとくくりで近代法と言われている。近代法は中世法への反発として、例えば個人を抑圧するギルドといった、個人以外の集団的なものは廃止し、国家と個人、国民という形をつくっていくようになった。
平等も個人の自己決定も悪いことではないが、200年以上経過した現代は、個人、自由、平等が絶対的価値となって、助け合いの場である家族、宗教、地域といった、グループの力が衰退してきている。実際、現代社会では自分さえよければいいという、自己中心の風潮が強くなった。
法律家は自由、平等を極限まで拡大する傾向がある。個人の自己決定を何よりも重視し、権利の実現を何よりも良きことと捉えていく。それがマイノリティの権利を主張する流れになっている。
法におけるダブル・スタンダード
法律家が陥りやすい思考の落とし穴の三点目として、法におけるダブル・スタンダードを指摘しておきたい。場合によって、法は倫理的な基準を引き下げてしまう面があるということである。
具体的なメカニズムは、次の通りである。法には、できる限り多くの人に一律に適応する基準がある。ただ、時には法に適応しない気の毒な事例が出てくる。例えば、日本では禁止されているが、子宮のない女性は赤ちゃんが産めないので、代理母という方法で子どもを持つことができる。しかし、先ほどの自由と平等の観点から、気の毒な女性が利用できるのであれば、誰でも利用できるようにした方がいいと法律家は考えるのである。
アメリカは代理母合法の州もある、ただ代理母制度を誰でも利用できるということは、合法なら誰でも利用していいということになる。仕事が忙しいし、出産は面倒くさいし、お金もあるとなると、代理母を利用しようと考える人もいる。もし障害児であることが分かったら堕胎するという特記事項を付けて契約をする。
妻はいらないが、跡取りとなる子どもはほしい。美人で頭が良くて健康な人に代理母になってもらって、自分の子どもを産んでもらうということも現実になる。病気で気の毒な人の為に開発された医療技術が、合法的に誰でも使える手段になる。このように、適応範囲を広げることで、普通の基準になってしまうというところに、法が陥りやすい問題点がある。
2.性的マイノリティの権利保障に関する問題点
次に、提言では「教育機関における性的マイノリティの権利保障の課題」「雇用・労働における性的マイノリティの権利保障の課題」をあげている。これについて、法律の分野で特に子どもを中心に研究してきた経験から、4点の問題提起をさせて頂きたい。
性的指向は、個人の自由の問題か
第一は、性的指向は個人の自由の問題なのかということがある。法律家は、その人の外見、職業、性格、好みに関係なく、一国民としてできるだけ個人の自由を保障することが平等であると考える。
提言の3「婚姻の性中立化(性別を問わないこと)に向けた民法改正の必要性」に、「個人の利益を否定するに足りる強力な国家的ないし社会的利益が存しない限り、個人の婚姻の自由を制約することは許されない」と規定している。
つまり、個人の利益を否定するに足りる強力な国家的ないし社会的利益があることを具体的に証明しない限り、法律家としては問題がないなら異性愛も同性愛も同じという方向に行きやすい。
ただ、異性愛も同性愛も単なる個人の自由、好みで片付けられる次元の問題なのだろうか。動物は雄と雌が性行為を通して子孫を残す。そのために発情期があり、必ず雄と雌がセットで存在する。しかし、人間は高等動物なので生殖と性的指向を切り離してもいいのではないかと一部のリベラルな法律家は考える。それが、提言の記述、「今日の社会では、法制度上、婚姻と生殖・養育との不可分の結合関係は失われ、婚姻法は主として婚姻当事者の個人的、人格的利益の保護を目的とするものになっている」に表れている。
しかし、そもそも婚姻と生殖・養育を切り離すことができるのだろうか。不妊治療に関する法では、同性愛者が生殖補助医療を使って子どもを持つことを望んでいるという点が問題点として指摘された。自然の摂理から言えば、男性同士、女性同士のカップルには子どもは生まれないからである。
確かに生殖補助医療の進歩により、代理母に依頼して、第三者の精子、卵子によって子どもをつくることが可能になった。しかし、生まれてきた子どもに与える影響はどうなのか。男性同士のカップルが代理母に自分たちの子どもを産んでもらうとすると、父親が二人いて、血のつながった母親が世界のどこかにいるという状況になる。
提言では、「婚姻と生殖には不可分の関係はない」と言っているが、同性同士のカップルが自分たちの子どもがほしいという状況になると、やはり婚姻と生殖は不可分の関係があると考えざるを得ない。
かつて、夫はいらないが子どもがほしいという女性が、生殖補助医療で子どもを産んだケースがある。生まれた女の子は成人になったとき、「母親は自分をかわいがってくれたが、父親が存在しない人生になったことは許せない」と証言していた。医療技術の進歩に子どもも巻き込まれてしまう現実がある。
同性カップルと異性カップルではどう違うのか、いくつか文献等で指摘されている点があるので紹介する。①カップルでいる期間が短い。一生涯続いている関係が少ない。②決まった相手以外とも性交渉する。③一度に複数の人と性交渉する。④エイズなど性感染症に罹りやすい。⑤暴力行為の割合が高い。⑥うつ病等の精神的問題を抱えている割合が高い。⑦薬物乱用、アルコール中毒等の割合が高い。⑧育てている子どもに対して性的虐待をする割合が高い。
同性カップルと異性カップルが違うと主張するのであれば、それなりの客観的説得的データが必要になってくる。しかし、説得力ある客観的データ、調査がないのが現状である。
また生殖補助医療の場合、生まれた子どもたちにどういうハンディがあるのかということも考慮すべきだ。日本では慶應義塾大学が日本で最初に生殖補助医療をスタートさせた。当時は、生殖医療の法律が追い付いておらず、医学生から精子を採取し、医療に使った。生まれた子どもには自分の父親が分からないということで問題になった。
技術が進むと、社会は技術を実用化させる方を応援する。平等という観点からすると異性も同性も同じということになるので、反論するにはそれなりのデータがあって初めて可能になる。しかし、今日の自由・平等の流れに逆行する研究は科研費もつきにくいのが実情である。
婚姻制度とは何か
次に婚姻制度のあり方について、提言は「婚姻の性中立化」の方向性を示している。つまり、今日の社会では、婚姻と生殖・養育との不可分の関係はない、婚姻は婚姻当事者の個人的、人格的利益の保護を目的とするものになっている、という主張である。
アメリカの同性婚支持者は、結婚の本質は性別に関係なく二人の人間が自らの幸福の為になされる私的で親密で情緒的な関係であると解釈している。つまり、婚姻制度はカップル自身の為だけに施行されるというわけである。
もし本人同士が良ければそれでいいという論理で推し進めていくと、一夫多妻でも、実の親子でも、5歳の女の子でも本人が良ければ結婚してもいいということになる。確かに、すべての夫婦に子どもができるわけではない。しかし、家族の原点は男女がペアで子孫をもうけることにある。できるだけ子どもの視点に立って、実の両親に大人になるまで育ててもらえるシステムが、本来の婚姻制度の本質ではないか。同性婚に反対する人は、結婚を子どもの利益、ひいては社会の利益のために、カップルによる性行為、出産、子育てを社会的に承認するものだと考えている。
異性同士のカップルが社会から結婚を承認されて初めて性行為を許され、生まれた子どもを大人になるまで育てる義務が課せられる。また生まれた子どもにとって、誰が本当の両親かを知る権利が保証され、できるだけ血のつながった両親に育ててもらうことによって、生まれてくる子どもと実の両親とのつながりを強化する。婚姻と生殖・養育は不可分の関係にあり、生まれた子どもを社会でサポートする制度だと考えられる。
そうなると、同性同士では子どもは生まれないので、婚姻は男女間でしかなし得ない。単なる個人の権利、性的指向の問題と割り切るべきではあるまい。つまり同性カップルと異性カップルでは実質的な違いがあるということになると、婚姻はマイノリティの人権の問題とは言い切れないのではないか。
同性婚を婚姻と認めると、異性婚と同じように子どもを持つ権利を主張するようになる。生殖補助医療を使って子どもを持つことになると、その子どもは自分のルーツが分からないという事態が起こるのである。
子どもたちの生育に最適な環境とは何か
三点目の問題として、子どもたちの成育に最適な環境とは何かという点を指摘したい。男女の性に違い、“区別”がある以上、相応の役割分担があると考えるのが自然ではないか。例えば、女性である母親は子どもに寄り添い、話を聞いて共感してあげることで子どもの自尊心が育っていく。それに対して、男性である父親は子どもに社会とのつながり、ルールを厳しく教え導く役割がある。つまり、厳父慈母という考え方である。
ところが、同性婚の支持者は、男性二人でも女性二人でも、親として役割が果たせると考えている。男性である父親と女性である母親の役割が本当に同じなのか、本質的な部分で違いはないのか。この点を明確にしていく必要がある。
ところで、アメリカの同性婚関係の訴訟を調べると、原告だった同性カップルが別れてしまっているケースが少なくない。カップルが存続する期間が短い傾向がある。
日本ではマスコミの影響もあってか、離婚が子どもに与える衝撃や不利益について一般的に十分認識されていないように思う。アメリカでも離婚など大したことはないと言う人はいるが、離婚に関する研究も数多い。
親は簡単に取り替えることができない存在である。仮に同性カップルが良い親であったとしても、異性間に比べて関係が短期に解消されたり別の相手とカップルになるということが多くなると、その不利益を子どもが受けなければならない。子どもの養育環境としては大きな問題である。幼い子どもにとって両親は自分の世界のすべてである。ところが父親が突然いなくなり、今度は別の男性が父親として目の前に現れる。子どもは新しい親に簡単には打ち解けないこともあるし、学力に問題が生じるといった不利益も指摘されている。
社会への影響は
四点目として、性的マイノリティの権利保障が行われていったときにどういう影響が社会に生じるのかという点がある。
実際に提言を作成した法律家の方々は、権利保障を実現できてよかったと考えているかもしれない。しかし、私は逆の意味でかなり大きな影響があると考えている。
例えば男女に差がない、ひいては父親と母親に差がないと考える。アメリカでは一部の人は父親と母親は同一だから片親でいいという人もいる。生殖補助医療を利用するから、父親は必要ないし、子どもにとっても父親は必要ない。頭が良くて金髪で目が青い人の精子を持ってきて子どもをつくっても、子どもに不利益はないと言えるのか。同性同士の結婚が認められると、男女の差、父親と母親の差はないということが社会的に認められてしまう方向につながりかねない。
血がつながった両親に子育てをしてもらう必要性が同性カップルにはないので、「子どもが生まれてきてくれてありがとう」という感謝の気持ちより、頭がよく、外見もいい子どもをつくってあげたという、親のエゴにつながっていくのではないかと懸念している。
学校教育では、同性同士も異性同士も権利は同等ということになり、同性同士も結婚できることを教えないといけなくなる。逆に、異性カップル、同性カップルの違いを教えること自体が違法になるのではないかと思う。
アメリカでは、実際に宗教関係の問題が起こった。教義に基づいて同性カップルにプログラム提供や支援をしなかったという理由で損害賠償を請求されたり、政府からの補助金が打ち切られた例がある。マサチューセッツ州で100年以上養子縁組斡旋をしていた「ボストンカトリック基金」という団体が、同性カップルへの斡旋をしなかったという理由で活動停止に追い込まれている。
家族法の視点で考えると、家族自体は法が作り出したものではない。法以前に家族は存在していた。実際、日本では同性同士が同居することが禁止されているわけではない。アメリカも禁止されているわけではない。なぜ、同性愛者が権利を主張するようになったかと言うと、アメリカの事例では同性カップルの一方が亡くなった時、同性では遺産相続が承認されないということがある。亡くなった時に多額の贈与税を支払うことになるのは不公平だとして裁判が起こった。
税金に関して、家族同様の親しい関係では配慮してもいいというケースもあるが、少なくとも婚姻に関しては弱者である子どものアイデンティティに関わる問題だと私は考えている。提言にあるように、簡単に生殖と婚姻・養育は切り離してはいけない問題ではないかと思っている。
近代法は「私」という個人を中心に組み立てられ、論理が展開される。中世法への反発もあり、自由、平等、自己決定を最大の価値と位置づけてしまったことで、結婚し子どもが生まれて、その子どもが健全な家庭で順調に社会人として一人前に成長し、さらにその子が結婚し、孫が生まれるという形で世代が続いていくという、人間としての大きな流れが見えにくくなっている。これが今日の同性婚の問題を引き起こしていると言えよう。
さらには、法が持つ人間を抽象化する思考が、男女の差をたいしたことではないと矮小化する方向につながっている。一番の懸念は、同性愛者の権利保障の主張が高まるなか、法律家が法的根拠をもって彼らの主張に加勢していることである。結果的に、声を上げることができない子どもたち、私たちの子孫にしわ寄せがいくのではないかと懸念している。
家族法関係の学者は生殖と婚姻・養育は不可分の結合関係ではないと、個人の権利保障に重きを置いてきた。それが現状は、離婚率が上昇したり、シングルマザーが増加したり、精子卵子の売買が可能になり、外国で代理母に子どもを産んでもらうようになっている。
児童虐待も離婚も増えている。子どもが精神的にも成熟していく時期に不安定な家族環境のなかで育つという現状を考えると、マイノリティの法的保護以上に、社会的弱者である子どもの利益の保護を優先すべきだろうと考える。そのためにも安定した健全な家庭を法や社会がしっかりサポートすることが重要になってきている。
3.終わりに―同性婚の法制化の流れを変えるために
憲法24条の「婚姻は両性による」の解釈に関して、この条文は同性婚を排除しないと主張する学者もいる。一方、憲法に家族条項を設けるべきだという学者もいる。
裁判になると、憲法判断に関しては、最高裁の意向が働くことになる。現状は多数派の解釈として同性婚は認められていないというのが大勢である。ただ、条文は必ずしも「男女間の異性による」と明確にしているわけではない。そうなると今後、解釈で変わる可能性がないとは言えない。
最高裁は常識的な感覚があり、家族を大切にするという視点を持っていると思う。日本の大半の国民は家族を大事に思い、同性婚を普通だと思っている人は少ない。個人の為の結婚ではなく、子どもの為に一生懸命に家族を守るという人が多い。
これまでの判例を見ると、学者よりも実務の裁判官・判事の方が非常に常識的な判断をするイメージがある。ただ私が大学に入学した頃から、司法試験の受験者が変質したように感じている。昔は沢山専門書を読んで自らの思考力で受験をしていたが、受験の為の予備校が司法試験に効率よく合格させることだけを考えて、論点、学説、理由づけ等を丸暗記させるようになり、最近の判例を読んでいると、日常の感覚と乖離している悪い面が出ている。
国民世論が同性婚に反対であっても、一部の声の大きい人が影響力を持つようになったり、国会議員のなかに家族より個人を主張するような法律家が入ってくると、変わってきてしまう懸念はある。
電通の調査によるLGBTの人口比率7.6%という数値も、一般国民の感覚からすると高すぎるという気がする。LGBTの人口比率の数値の大小に関係なく、目の前に明らかな害、問題点が見えないとすれば、法律家はできる限り性的マイノリティの自由と平等を拡大する方向に思考が行ってしまう。
まず、子どもたちが同性婚で不利益を受けるということを実証できるエビデンスを集める努力をすることが重要である。個人的プライバシーの問題があって簡単ではないが、アメリカでも研究が行われている。
婚姻は個人の問題にとどまらない。子どもが育つ環境を守ること。そのために考えるべき課題は多い。
(本稿は、2017年12月26日に開催したIPP政策研究会の発題を整理してまとめたものである。)
(注)日本学術会議「性的マイノリティの権利保障をめざして-婚姻・教育・労働を中心に」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t251-4.pdf#search=%27