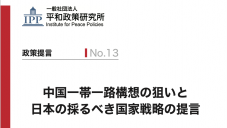はじめに
来年2019年5月には「平成」の一時代を終えて、新しい天皇陛下を迎えることになるが、これをきっかけに日本における天皇の存在について、あるいは政治制度としての立憲君主制について、国民が考えるきっかけになればと思う。近代の歴史を振り返ってみても、フランス革命はいうに及ばず、ロシア革命などに見られるように(立憲君主制ではない)君主制(王政)の多くが倒された。
とくに第二次世界大戦後は、君主制国家において政治的民主化を推進していくと、かえって自分の首を絞めるようなことになりかねないという「国王のジレンマ」に、(とくに中東諸国の)王たちは直面するようになった。
事実上エジプト最後の王となったファルーク1世(Farouk Ⅰ)は、ナセルのクーデタによって王位を追われる4年前(1948年)、次のような言葉を残している。
(最後まで生き残る王は誰か?と聞かれて)「世界中が騒乱の中にある。いずれこの世には5人の王しか残らなくなるだろう。イングランドの王、スペードの王、クラブの王、ハートの王、そしてダイヤの王である」。
つまり、最後に残る王は、トランプの4枚の王とイングランドの王のみだというわけだ。
現在、世界には国連加盟国中(日本の天皇制も含めて)28カ国の君主制の国がある。これに英国女王が国家元首を兼ねる「英連邦王国」15カ国を合わせると43カ国となるが、それでも国連加盟国全体の五分の一に過ぎない。ところが今から100年ほど前の第一次世界大戦終了直前ごろの世界では、むしろ共和国の方が少なく、世界の大半の国々が帝国や君主制の国であった。
この100年で世界は大きく変化した。それでは将来、君主制(王政)はなくなっていく運命にあるのか。そこで英国を例に取り上げながら、立憲君主制の現状を考察し、そして英国王室とも関係の深い日本の皇室、天皇制のあり方にも触れてみたい。
1.立憲君主制国家としての英国
(1)君主制の種類
まず君主制の種類について、ドイツ出身の米憲法学者カール・レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein、1891~1973年)の研究をもとに簡単に説明しておく。
君主制には、大きく次の二つがある。
1)世襲君主制:
一定の家族や王朝の成員が継承秩序に従って代々位を引き継いでいく君主制。有史以来の君主の多くは、世襲君主制によって位を即いてきた。
2)選挙君主制:
一定の選挙方法によって君主を選んでいく君主制。例えば、中世から近世にかけて欧州中央部に君臨した神聖ローマ帝国で、大小350ほどの聖俗諸侯たちの頂点に立つ皇帝は、その中でも有力な7人の選帝侯(17世紀末からは9人)による選挙で選ばれた。現在では、マレーシアがこれに該当し、スルタンを有する9つのヌグリ(州)の間で輪番制で5年ごとに国王を互選で選出している。
そして、前者の「世襲君主制」は、さらに3つに区分される。
1-1)絶対君主制:
ルイ14世の時代のフランス王政に代表される統治形態で、絶対的な支配者、すなわち法から解放された王が、神意の命じた権利によって思うままに統治でき、神に対してのみ責任を負う。
1-2)立憲君主制
19世紀のプロイセン王国に代表され、「国王は君臨し、かつ統治する」体制である。すなわち国王が統治者であると同時に、支配権の所有者ともなる。ここでは王権と議会という二つの国家機関が並存し、レーヴェンシュタインの言葉を借りれば、その「合奏」が立憲君主制の本質となる。
ただし、国王の背景には軍隊・警察・行政がついているために、国王と議会が対立した場合には、権利の推定はつねに国王に有利に働く。それゆえ絶対君主制に転じることも容易である。
例を挙げれば、19~20世紀のドイツ諸国、第一次世界大戦後のブルガリア、ルーマニア、ギリシアなどである。
1-3)議会主義的君主制:
19世紀の英国で確立され、ベルギーなどのベネルクス諸国、スウェーデンなどの北欧諸国でも採用され、「国王は君臨すれども統治せず」の体制となる。立法は議会に委ねられ、行政は議会内で多数派を形成している政党の信任を得た内閣によって担われる。
このように21世紀の今日の世界では、君主制を採る国の多くが「議会主義的君主制」の下で統治しているか、それに近い形で君主制を継続させている。レーヴェンシュタインが定義づけた「立憲君主制」は、今日のわれわれから見れば、専制主義的な側面が強く、それゆえ後に軍部や民衆から倒壊させられた。本稿で主に見ていく君主制国家の統治形態は、議会制民主主義に基づくものであり、「議会主義的」という表現は当然となる。そこで、レーヴェンシュタインが「議会的君主制」として意義づけたものを含め、ひろく「立憲君主制」(constitutional monarchy)と呼んで、議論を展開したい。
(2)英国議会の伝統
英国は、「君臨すれども統治せず」といわれる立憲君主制の母国とみなされている。英国政治を象徴する言葉に、「議会/国会(parliament)」があるが、それでは英国政治史において、この議会と王権の関係は歴史的にどのように繰り広げられてきたのだろうか。王権と議会がせめぎあいながら発展してきたというのが、英国の政治史であった。
英国の議会の歴史を遡ると、今から1000年ほど前の924年に、アゼルスタン王がキリスト教の聖職者(聖)と諸侯たち(俗)を合わせて100人ほど召集して「賢人会議」を開催したのがその嚆矢とされる。
その後、いわゆる「ノルマン・コンクエスト」によって1066年、フランス・ノルマンディの貴族がイングランド王として戴冠し、ウィリアム1世(在位1066~1087年)となった。これ以降、欧州大陸に主たる所領を有するイングランドの王が登場するようになった。王にとっては、フランス(欧州大陸)が<主>で、イングランドはあくまでも<従>の位置づけに過ぎなかった。そしてフランスを基盤として遠征に出るために、イングランドは資金集めの場のような存在で、「海峡をまたいだ王」とも言われた。
ヘンリ2世(在位1154~1189年)は、その在位35年余りの中、イングランドにいたのは僅か13年足らずに過ぎなかった。それ以外の歳月は、ノルマンディやアンジューなどを巡回しながら、所領の支配に苦心していた。言葉を換えて言えば、それほどイングランドを不在にしていたので、イングランドの統治については現地の賢人たちに任せざるを得なかった。さらにフランスでは、他の諸侯たちとの争いもあって、自分の領土防衛の資金を集めるために、イングランドの賢人会議にそれを具申した。
またイングランドでは、たびたび王位継承争いが起きたので、賢人会議を召集して彼らの意見を聞いて次期国王を決めた。
このようにして10世紀以降、300年間ほどは、フランス等と比較しても、英国では(王権よりも)議会の方が発言力を持っていた。一方、フランスではこの間、男子嫡子が切れることなく誕生したので、王位継承の争いはあまりなかった。その上、ジョン王(在位1199~1216年)のように、フランス国内にあったイングランド王の所領がフランス王に奪われることもあり、その結果、(英国とは対照的に)フランスでは王権が伸張するようになった。
ところで、当時の賢人会議の賢人たちは、みなフランス語で話をしていた。議会のことをフランス語でparlement(後の「高等法院」)と言うが、ジョン王のころからブリテン島を中心として島国化する過程で、そのフランス語を語源として英語のparliamentが生まれた。
そして英国では議会の力が伸長していき、14~15世紀ごろまでには、貴族院と庶民院に分化していく。それらの議会の機能としては、王の諮問に答えるとともに、税金を負担した。
英国政治史において、テューダー朝のヘンリ8世(在位1509~1547年)などは、以前「絶対王政」といわれた。しかし、最近の歴史学研究では、フランスのルイ14世に代表されるような、王が何でも自由に権力を振るえるような意味の絶対王政は英国にはなかったとされている。ヘンリ8世は、ローマ・カトリックに反抗してイングランド国教会を創設したことで有名であるが、これにしても、ヘンリ8世が自分勝手にしたのではなく、貴族院・庶民院に諮り法律(上訴禁止法、国王至上法など)に基づいて創設したのだった。英国政治史においては、議会は不可欠の存在であった。
(3)大衆民主政治における君主制
次のステュアート朝の時代には、絶対王のような存在になろうとする王が出てきたが、彼らの運命は哀れなものだった。例えば、チャールズ1世(在位1625~1649年)は清教徒革命によって斬首となり、ジェームズ2世(在位1685~88年)は名誉革命によって追放されてしまった。議会との衝突は、王にとって<命を懸けた戦い>を意味するほどのものだった。
名誉革命(1689年)以降、今日に至るまで、毎年議会が開かれてきた。一方、フランスでは、英国の議会に相当するのは「全国三部会」であるが、1614~15年から1789年に勃発したフランス革命までの175年間、1回も開かれなかった。その上、貴族やカトリック教会の聖職者等はすべて免税特権を享受していたために、庶民の不満が鬱積して爆発し、大革命へと繋がっていった。英国とフランスにはこのような違いがある。
18世紀にイングランド王は、ドイツ北部の出であるハノーヴァー朝に代わった。彼らは故郷のことばかりが頭にあって、イングランドのことをないがしろにするような有様だった。そのためイングランドの政治は、現地の大臣たちに任されるようになった。その延長線上に、「議院内閣制」(責任内閣制)が生まれて、18世紀半ばには定着するようになった。そして王の立場は、「君臨すれども統治せず」の形となり、19世紀までにはそれが確立していく。
その後、議会政治は政党組織として整備されていき、大英帝国最盛期のヴィクトリア女王(在位1837~1901年)の時代には、保守党(トーリ党)・自由党(ホイッグ党)の二大政党制にまとまっていった。そして20世紀前半には、労働党が加わり三党体制となったが、現在では、さらに再編されて保守党と労働党の二大政党体制に落ち着いていった。
選挙権も徐々に拡大して行き、第一次世界大戦後には男女普通選挙制度が実現する(1918・1928年)。貴族政治(aristocracy)の時代から大衆民主政治(mass democracy)の時代への転換である。
そしてジョージ5世(在位1910~36年)の時代に第一次世界大戦に遭遇した。19世紀のナポレオン戦争の時代は、戦争にかかわるのは(貴族出身の軍人・将校、義勇兵など)国民の数%程度でしかなかったが、第一次世界大戦は「総力戦(total war)」だったので、国家総動員体制となり、徴兵制が敷かれ、女性も勤労動員させられた。
そういう時代を迎えると、君主制といえども国民の支持なくしては成立し得ない。ところが欧州諸国では、そうした時代の変化についていけず(ハプスブルク家、ドイツ帝国、ロマノフ王朝、オスマン帝国などの)帝国や王家は次々に倒されていった。さらに第二次世界大戦後には、イタリア、ブルガリアなどで王政が廃止された。しかしそのような中で英国は、ジョージ5世以来、国民の支持の基づく立憲君主制を維持し続け、今日に至っている。
2.英国女王陛下のお仕事
ジョージ5世以降、(国民の支持に基づく立憲君主制として)定着していく中で、女王陛下の役割がどのようなものであったのかを考察しながら、立憲君主制の実質的な意義について考えてみたい。
立憲君主制の基本は、行政については政府が、立法については議会が各々の役割と機能を果たしていくことであるが、国家元首(head of state)としての女王陛下エリザベス2世(Elizabeth Ⅱ、1926~ 、在位1952~ )は、どのようなお仕事をされているのか。
まず日本の憲法にある国事行為に類することである。例えば、国会の開会、議会制定法の裁可、各国外交官の接受などである。
写真(略)は、英国議会の開会式における女王陛下である。92歳の女王陛下は、1.5キロほどもある王冠をつけて、貴族院の長い廊下を歩かれて議会の玉座に座られ、15分余りの施政方針演説をされる。
現在の日本と違うのは、国軍の最高司令官、イングランド国教会の最高首長としての役割である。また議会開会中に、女王陛下は、毎週水曜日の夕方に首相との定期的な会見を行い、国政にも直接参与する。その内容は門外不出であるが、そのときどきのイシューに関して率直に意見を述べられるという。
そして英国君主の役割には、次の三つがある。
①連合王国の君主(England、 Scotland、 Wales、 Northern Ireland)
②英連邦王国の元首(Canada、 Australia、 New Zealandなど15カ国の女王陛下)
③コモンウェルスの首長(Commonwealth:53カ国からなる)
3.現代にも残る英国君主の影響力
(1)コモンウェルス諸国首脳会議(CHOGM)
何と言っても英国の影響力の強みは、大英帝国以来の遺産である。ヴィクトリア女王時代に英国は、世界の陸地の四分の一近くを支配したが、20世紀の二度の世界大戦を経て、とくにアジア・アフリカにおいて多くの国が独立を果たし、英国の支配領域は縮小した。しかし旧英国植民地の国々の多くは、独立後も「旧英連邦諸国」すなわち「コモンウェルス」に属している(現在、53カ国が加盟)。かつては英国と旧英連邦諸国とは<縦の上下関係>であったが、現在は<横の平等な関係>として再構築されている。
そもそも「旧英連邦諸国」は、エリザベス女王が戴冠式を終えた翌1953年、インドのネール首相などが音頭を取って、コモンウェルスの継続とその首長に英国女王陛下がなるべきだと主導して始まった。最初は9カ国からスタートし、加盟は各国の自主に任されたが、その後ほとんどの国が加盟した。
そのスタート時から60年代前半ごろまで、世界における英国の国力は低下していたものの、英国政府の頭の中はかつての大英帝国時代の発想から抜け出られないままであったから、旧英連邦諸国をロンドンに呼び集めて「コモウェルス諸国首脳会議」(CHOGM=Commonwealth Heads of Government Meeting)を開いていた。ところが、1960年代の英国は、EC(EEC)加盟問題でぎくしゃくし、さらに経済の低迷が続き、当時「英国病」と揶揄されるほどだった。ハロルド・ウィルソン首相が1968年に「スエズ以東から英国陸海空軍を順次3年以内に撤退させる」と表明したことは、英国の国力低下を象徴する言葉だった。
これによってコモンウェルス内の英国の立場が急激に低下することになった。この結果、旧英連邦諸国の関係もフラットなものにして、加盟国が輪番制で2年毎に「コモンウェルス諸国首脳会議」を開催することになった。その新しい体制での第1回会議が、1971年シンガポールで開催された。その後、カナダ(1973年)、ジャマイカ(1975年)、イギリス(1977年、女王陛下即位25周年を記念してロンドン)などと続いていった。最近では、今年2018年4月に、久々にロンドンで開催された。
この間、女王陛下は、71年は諸事情でシンガポールに行けなかったが、その後は毎回出席している。ただ、近年高齢になられたこともあり、2013年のスリランカでの会議は(遠方との理由で)欠席されチャールズ皇太子が代理出席された。
いまや女王陛下もかなりの高齢となられたので、次の首長を誰にするかを決めることになった。1953年にネール首相のリードによって首長になられて以来、今日までその立場に立っているが、それは「世襲」という意味ではない。コモンウェルスの首脳たちの合議によって決めることになっている。今回の会議(2018年4月)で、全加盟国の賛同を得てチャールズ皇太子を次期首長に据えることが決まった。
(2)CHOGMの役割と影響力
加盟国53カ国の首脳が集まる会議には、どのような意味があるのだろうか。最初から数えれば、60年以上の歳月が経過しているわけだが、この間、コモンウェルスの意義について何度も議論を重ねてきた。領土・国境・通商問題などハードの政治的問題ではなく、より大きな問題について、とくに21世紀に入ってからはグローバルな問題について議論するようになった。例えば、人権問題や環境問題である。いくつか例を挙げよう。
1979年にコモンウェルス諸国首脳会議(CHOGM)が、アフリカで初めてザンビアの首都ルサカで開催された。ザンビアの独立の父と言われるカウンダ大統領(当時)が議長となり、この回の議題を選び、その筆頭に上げたテーマが南ローデシアにおける人種差別問題だった。南ローデシアも旧英国領であったから、当初はコモンウェルスに加盟していたが、国内の人権問題で加盟諸国からの内政干渉を避けて65年に脱退した。しかしザンビア(旧北ローデシア)やタンザニアなど周辺国の首脳たちは、この問題を懸念しており、そのためにカウンダ大統領は議題に取り上げたのであった。
当時、英国ではサッチャーが首相に就任したばかりのころで、しかも直面する喫緊の課題は英国病といわれた経済の建て直しであったから、アフリカ問題にはほとんど関心を示さず、参加する気持ちもなく代理として外相を派遣しようと考えていた。
そこでエリザベス女王は、CHOGMが始まる前に、世界の衆目を集めるべく、タンザニアやマラウィなど周辺諸国を公式訪問され、最後に首脳会議に合わせてザンビアに入られた。そうなると当然首相も参加せざるを得ない状況になり、結局サッチャー首相も参加することになった。
会議は通常3~4日間開かれるが、サッチャー首相がアフリカ問題に関心がないことは他のアフリカ諸国の首脳たちは知っていたので、初日の会議では白い眼で彼女を見ていた。ところが、初日の晩餐会のときに、会場の隅にいたサッチャー首相をエリザベス女王が、参加しているアフリカ各国の首脳に紹介して回った。彼らとの対話を通してサッチャー首相は、南ローデシアの人種差別問題の深刻さを痛感し、翌日の会議の冒頭ではこの問題の解決に向けた決意を表明するまでになった。その後、同年末までに黒人と白人双方の代表をロンドンに招いて、ランカスター・ハウス協定としてまとめあげ、翌年春には黒人にも選挙権が与えられるようになった。さらに(今では悪名高いが当時は独立の英雄だった)ムガベが初の黒人首相となって、独立国家を導いた。
この実績を第一段階として、次により難しい問題の解決に繋がることになった。すなわち南アフリカ共和国のアパルトヘイト問題である。そのころサッチャー首相は、米ソ冷戦の絶頂期ともいうべき時期であったから、その問題に傾注していて、アフリカ問題は余りタッチできなかったものの、エリザベス女王が自らの各国首脳との深いつながりを活かしながら、さらにはコモンウェルス以外の世界の首脳たちともコミットして、まずは永年投獄されていたネルソン・マンデラの釈放に尽力された。実際、1990年2月にマンデラが釈放され、その後はアパルトヘイトの廃止、マンデラ大統領誕生(1994年)と続いていった。
コモンウェルス諸国首脳会議は、すぐに何かを決定して行動するという類のものではないが、毎回定例的に会議を重ねていくこと、顔をつき合わせながら人脈を築いていくことが(ソフトの力)、いざというときに「ハードの力」となり得るのである。
近年は、そうした人権問題に加えて地球環境問題も大きなイシューとなっている。加盟国の中には太平洋のツバルなど、地球温暖化や環境問題と深刻に直面している国も少なくない。今年(2018年4月)の会議では、女王が音頭を取って、加盟国の中でもっと森林を増やす努力をすることが諮られた。
(3)王室外交の効用
女王陛下は、これまでの在位期間に40回以上外遊をされ、世界120カ国を歴訪された。日本には、1975年に初めての英国君主として公式訪問された。
王室外交の極意は、その「連続性」「継続性」にある。チャーチルは次のような趣旨のことを述べた。
「戦後の英国は国力が相対的に低下したとはいえ、①米国との特別な関係、②欧州との関係、③コモンウェルスとの関係という三つの輪(サークル)の中間に位置しているのは英国だ。この強みを活かして一流国としてやっていく」と。
英国は、この三つの輪の中で、政府が動くだけではなく、女王もまた動いてきた。
エリザベス女王が最初に会った米大統領は、トルーマンだった(このときは王女)。そして女王に即いてから最初に米国を訪問したとき会ったのが、アイゼンハワー大統領だった(1957年10月)。
その1年前、56年10月にスエズ危機が起きたとき、英米関係がぎくしゃくした。英国のマクミラン首相(当時)は、アイゼンハワー大統領とは戦友であったから、そうした人間関係も活かしながら、英米関係の修復に努めた。それに加えて、前述のように、エリザベス女王が訪米して同じように戦友であったアイゼンハワー大統領と会って、英米関係の回復に努力されたのだった。
1961年にケネディ大統領が誕生したが、その年生まれたのがオバマ前大統領だ。オバマが政治家になろうと夢見たきっかけの一つが、自分の生まれた年に尊敬するケネディが大統領になったことだったという。オバマ大統領は、2011年に英国を公式訪問し、バッキンガム宮殿で女王陛下から接遇を受けた。彼にとっては伝説のような歴代大統領とも直接会ってこられた女王陛下にお目にかかれたことで、非常に尊敬のまなざしで女王陛下を見つめていた。
このように、エリザベス女王は、歴代米大統領をはじめとして、世界各国の首脳たちと永年にわたる深い関係を築いてきた。そうした連続性は、外交においても大きな力を発揮する。それは任期や定年といった区切りのない君主ならではの外交といえる。
(4)諸団体の長としての実質的な役割
国内的に見ると、ヴィクトリア女王の時代から、慈善団体をはじめとした各種団体の長としてかかわっている。例えば、環境保護、野生動物保護、都市環境整備、老人福祉、障碍者福祉、青少年教育、貧困撲滅、医療の進歩、科学芸術の振興など、王室全体では3000を超える団体を支援している。日本と違い、陸海空軍などの組織とのかかわりもあるが、それらは小さな部分に過ぎない。
しかもそのほとんどがお飾りとしての位置ではなく、毎回例会や会議に出席して長の役割を果たしている。2017年5月に、エディンバラ公爵(女王陛下のご主人)が翌月96歳となられることを考慮して、単独の公務からの引退を表明された。しかしその時点で、エディンバラ公爵は実質的な各種団体の長を785も務めておられた。
エディンバラ公爵は、カナダの近衛騎兵隊の連隊長を務めておられるが、同連隊の新しい連隊旗ができるのでそれを連隊パレードに出席して直接授与すべく、2013年に現地を訪問された。その翌日には、軍用機で英国に戻り、ウィンザー城に直行された。そのときアラブ首長国連邦のハリファ大統領が国賓として訪英されたので、女王陛下と一緒にその接遇をするためだった。このように今でも現役として活動している。
このような王室の活動について、以前から多くの英国民が知っていたわけではない。1997年のダイアナ妃事故死をきっかけに王室に対する見方が変化していった。国民は、税金によって王室がまかなわれていると信じているが、実際はそうではない。王の所領からの上がりを一旦議会に預けてそれを王室費として使っている。表面的には、政府予算に計上されているので、税金の一種と見られてしまう。そうした背景には、広報活動の不足があった。
ちょうどそのときにダイアナ妃の事故死に伴う王室バッシングが起き、しかもインターネットが普及し始めた時期でもあったから、そうした新しいメディアを活用しながら、王室の広報に力を入れ始めたのだった。多くのご公務内容の紹介、年間活動報告書の作成などを通して、国民に王室の真の姿を知らせていった。
そうした努力の末に、2012年女王陛下の在位60周年記念式典(Diamond Jubilee)を、多くの国民の温かいまなざしの中、盛大にお祝いすることができた。1990年代には非常に冷たい視線を浴びせられていた王室であったが、そうした15年余りの努力によって、国民からの評価を大きく改善したのであった。
英国の立憲君主制は、ジョージ5世のときからの教訓として、国民の支持があってこそ存続できるというものだ。ただ国民の世論や情緒は時代とともに変化していく。それに応じて、王室のあり方も変わっていかなければならない。何も知らせなくても国民は分かってくれるだろうというあぐらをかいたような態度は今では無理で、王室の活動を一から国民に分かってもらえるような努力が必要なのである。
4.日英君主のきずなと象徴天皇のゆくえ
(1)日英王室の交流史
日英の王室外交の歴史を簡単に振り返ってみよう。
明治維新の翌年(1869年)、近代最初の国賓としてヴィクトリア女王の次男アルフレッド王子が来日された。同王子は、オセアニア歴訪の後、日本に立ち寄ったのである。このときアルフレッド王子は延遼館に宿泊されたが、当時は宮中晩餐会もなかった。
1881年には、のちのジョージ5世が兄エディとともに来日した。二人とも海軍軍人であり、世界周遊訓練の途中に日本を訪問したのだった。そのとき明治天皇から厚い接遇を受けた。その後、1921年、裕仁皇太子(昭和天皇)が欧州歴訪に発たれ、最初の訪問地が英国だった。明治天皇から接遇を受けたジョージ5世が、今度は彼の孫の裕仁皇太子を接遇した。ちなみに、この直後に(1923年)日英同盟は解消されてしまう。
やがて太平洋戦争になると、日本は英米と敵国同士となって戦ったが、戦後は双方の王族同士の交流も進めながら徐々に和解に向けて進んでいった。1971年には昭和天皇の英国を含む欧州歴訪があり、その返礼訪問として75年にエリザベス女王が来日された。このようにして今日までの日英関係がある。
(2)戦後処理と天皇制
天皇制に関するGHQの戦後処理の方向性については、象徴天皇制として存続させることになった。GHQは欧州の法律には余り詳しくなかったが、英国のコモンローについては理解していた。その結果、英国の「君臨すれども統治せず」の立憲君主制を範として、日本の天皇制を残していくべきだとの方向に(マッカーサーをはじめとして)まとまっていった。さらに象徴としての天皇制にも英国の立憲君主制の影響があった。
今上天皇は皇太子時代に、慶応義塾塾長の小泉信三(1888~1966年)の薫陶を受けられ、いろいろな本を一緒に講読された。その中でも、英書で最初から最後まで通読したのがニコルソン著King George V(『ジョージ5世伝』)であった。小泉は、立憲君主はどうあるべきか、英国でも立憲君主の鑑とされているジョージ5世の人生を振り返りながら、戦後の象徴天皇のあり方について、明仁皇太子に考えて欲しかったのだろうと思う。今上天皇ご自身も、小泉信三との思い出を聞かれたときに、この本を通読したことが「最も記憶に残っている」と述べておられた。
国民に寄り添う君主のイメージは、ジョージ5世が初めてであった。第一次世界大戦当時、道徳的に国民のリーダーとならなければならないとの自覚を持っていたジョージ5世は、贅沢な暮らしはしてはいけないと考えた。そこでバッキンガム宮殿の照明は最小限とし、風呂もお湯は5-6センチにとどめ残りは水を使い、4年間バッキンガム宮殿ではアルコール禁止、晩餐会もアルコールに代えて水を使用し赤肉も禁止(一方、フランスの大統領官邸では贅沢な振る舞いがなされていた)、などの態度を取られた。このような姿勢は国民にも広く知られた。さらに戦争で負傷した兵士の病院慰問300回、工場勤労動員の慰問300回、連隊の兵士慰問450回などもおこなった。
英国の叙勲においては、王が直接全員に勲章を授与する。ジョージ5世は大戦中の4年間に実に5万人以上に授与した。そうした王の態度を見た国民は、ジョージ5世を「国父」と見るようになった。こうした内容をその伝記を通じて学ばれた今上天皇は、国民に近づき国民と同じ目線に立つという思いをもつようになったのではないか。
(3)英王室にとって特別な存在としての天皇
英国にとっても日本の皇室はある意味で特別な存在である。それを推し量る目安として、英国の最高勲章であるガーター勲章の天皇への授与がある。もともとこのガーター勲章は、1348年に創設された英国最高位の勲章で、ガーター騎士団の騎士団章として授与される。キリスト教に由来するので非キリスト教徒には与えられないものだった。しかし長い歴史の中にあっては、そうでない場合も出てきたが、それは極めて例外的なことであった。
そのような例外のひとつが、日露戦争に勝利して第二次日英同盟を結び、真に対等のパートナーとなった明治天皇へのガーター勲章の授与だった(1906年)。その後、大正天皇(1912年)、昭和天皇(1929年)、今上天皇(1998年)にも授与された。ただし、昭和天皇は、太平洋戦争で敵国となったために一旦剥奪されたが、1971年に欧州歴訪のときに復活した。ガーター勲章の670年の歴史の中で、一旦剥奪されたのに復活したのは、昭和天皇のケースのみで、非常に珍しい。またエリザベス女王が授与された非キリスト教徒へのガーター勲章は、今上天皇が唯一ということになる。
(4)皇室外交の意義
このような150年に及ぶ日英王室の関係史がある。宮内庁は「皇室外交」という言葉を使わず「皇室による国際親善」と言っているが、実質的には「皇室外交」である。天皇陛下をはじめとして、皇族の方々が世界を回ることの意義は、いまさら言うまでもないことであろう。
これに関連して、昭和天皇崩御の直後に、その特集号として出された『文藝春秋』に掲載された高坂正尭氏のことばを紹介する。
〝会う〟ということが、外交政治には大切なことなんですね。会うことによってお互いに信頼関係を築き上げる。ところが政治家の場合には、会ったら何らかの成果をあげなければならないという制約がある。天皇さんはそんな必要がない。仮に十回会うとしたら、五回ぐらいは特にどうという話話をしなくても全くかまわない。そもそも外交というのは、会えば必ず結論が出るというものではないのですから、それでいいんです。そういう意味では国と国との関係を非政治化し、とくに政治的意味合いがなくても、お互いに関係を続けていくために天皇さんは大変ありがたい存在ですね(高坂正堯『文藝春秋』1989年3月特別号より)。
日々の政治家や外交官による外交をハードの外交とすれば、王室による外交はソフトの外交ということになろう。ソフトの外交は、ハードの外交とは違い、直接条約の締結等の具体的な成果につながるわけではないが、永年の一貫した形の積み重ねによって、しかも同じ人間が行うことによる、伝統に基づく「継続性と安定性」(continuity and stability)があり、それが政治や外交に与える影響は決して小さくはない。そのような存在としての王室は、共和制とは違い、現代の混沌とする世界政治の中にあって、ひと味違った役割と機能をもっているのではないかと思う。
(本稿は、2018年5月17日に開催した「IPP政策研究会」における発題内容を整理してまとめたものである。)