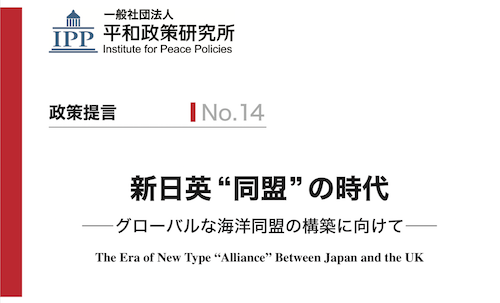はじめに
2017年8月31日、来日したイギリスのメイ首相は元赤坂の迎賓館で安倍首相との日英首脳会談に臨んだ。それに先立ちメイ首相は同日、神奈川県横須賀市を訪れ、海上自衛隊最大のヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」に乗艦した。同行した小野寺防衛相はメイ首相に対し、旧日本海軍が保有していた巡洋艦出雲に触れ、「出雲はイギリスで造られた軍艦で、日露戦争で活躍した」と同艦の戦績を披露し、「日露戦争はそのおかげで勝つことができた」と挨拶した。これを受けメイ首相は「我が国と日本は長きにわたり協力してきた。防衛問題において、私たちが協力を益々強化していることが本日のこの訪問で示されている」と述べた。この日、メイ首相は首相官邸で開かれた国家安全保障会議(NSC)の特別会合にも参加している。
それから4カ月後の17年12月14日、ロンドンで2+2(外務・防衛担当閣僚協議)が開かれ、翌15日に小野寺防衛相は英海軍の招待を受け、イギリス南部の軍港ポーツマスを訪れ、最新空母「クイーン・エリザベス」を視察した。同空母は一週間前に就役の記念式典が行われたばかりで、小野寺大臣の訪問は外国の閣僚としては初のクイーン・エリザベスへの乗艦・視察であった。視察後、小野寺防衛大臣は、同空母がアジア太平洋地域に展開した際には、海上自衛隊の護衛艦「いずも」と共同訓練を実施したいとの意向を明らかにした。
一連の日英両国の最高首脳や防衛担当閣僚相互の緊密な交流は、近年における日本とイギリスとの急速な接近を象徴する出来事と言える。東アジアでは北朝鮮による核・ミサイル脅威の増大や中国の著しい軍備強化及び周辺海域での覇権的行動の増加が、ユーラシア西部では、ロシアによるクリミアの一方的な併合やシリア内戦への関与をはじめとする中東での影響力拡大、さらにバルト諸国への威圧など挑発的な行動が続いている。2017年の世界の軍事費が、冷戦終結後最高となるなど、今日の世界情勢は冷戦の終焉以来最も緊張が高まっており(1)、両国の接近もこうした動きと無関係ではない。
1.新日英“同盟”の胎動
(1)日英接近の背景
「名誉ある孤立」から対米関係基本の外交へ
近世以来、イギリスの外交政策は勢力均衡の原則を基本としてきた。如何なる国とも恒久固定的な同盟関係に立たず、平時は大陸情勢から超然としつつも(名誉ある孤立)、ひとたび覇を唱える強国が欧州に出現し、英本土にその脅威が迫る恐れが生じた場合には、他の欧州の大陸諸国と連携して覇権国家に対抗しその影響力拡大を阻止し、イギリスへの圧迫を回避するのがこの国の伝統的な外交手法であった。
17~18世紀、ブルボンとハプスブルクの両王家が大陸における覇を競った際、イギリスはその間に介在し、両者を競わせることで覇権国家の出現を阻止するとともに、大陸諸国が互いに牽制拮抗している隙に乗じて、自らは海外に進出し植民地支配の体制を確立した。フランス革命期には対仏大同盟を主導し、革命思想とナポレオンの覇権獲得を阻んだ。新たな大国が出現すれば昨日の敵も今日には味方となり、味方の国が台頭し始めれば明日には再び敵対する柔軟な外交政策を展開するイギリスには、「永遠の敵も味方もなく、ただ存在するのは自らの国益だけ」(宰相パーマストンの言葉)であった。
もっとも19世紀末のドイツの急速な台頭が転機となり、20世紀に入るとイギリスは日英同盟や三国協商の締結を余儀なくされ、外交上のフリーハンドは制約を受けることになった。そして二度の世界大戦には勝利するが、国力は疲弊し、さらに戦後は多くの植民地を喪失し、18世紀以来築きあげてきた覇権国家の地位をアメリカに譲りわたすことになる。そのため冷戦下のイギリスは、NATOの一員として西欧防衛体制に加わるとともに、「特別関係(special relationship)」と呼ばれるアメリカとの緊密な関係を外交の基本に据えた。欧州の大戦に際し二度もアメリカを引き込み、その圧倒的な軍事力でドイツの野望を挫いたのは自分たちの功績とイギリスは自負しており、戦後、NATOの枠組みを立ち上げ、欧州防衛にアメリカを招き入れたのもイギリスの役割が大きかった。特別関係を活かし、アメリカをヨーロッパ問題にコミットさせ、また時に対立しがちな米欧の橋渡し役を任じることで、自らの存在感や影響力を維持しようとするアプローチである(「招待による帝国」)。
アジア太平洋地域への関与を深めるイギリス
かように、対米関係を重視するイギリスではあるが、現在では欧州統合の推進役としての役割も期待されている。だがこの国には従来から大陸諸国と一線を画そうとする傾向が強く、フランスに対する対抗心や対独警戒心も相当に根強い。またイギリスには国家主権への強い拘り、それに古くから自由主義重視の思想が根付いており、超国家的な枠組みによって国家主権が制約されることには否定的な意識を持っている。そのためEECの発足当初イギリスはこれに加わらず、敢えて独自のEFTAを創設してEECに対抗した。しかしその後、経済低迷への危機感から、1970年代にはEEC加盟を果たしたが、イギリス国内の加盟反対論は根強く.ウィルソン政権は75年に加盟の是非を問う異例の国民投票を行わねばならなかった。またサッチャー政権はヨーロッパ単一市場には参加したが、国家主権・通貨主権の保持を主張し続け、共通通貨や「社会憲章」の導入に抵抗し、共通農業政策のイギリスヘの重負担を批判し続けたのである。
しかし、イギリスが欧州における地域統合の動きと一線を画している間、EU(欧州共同体)の国際政治経済に占める役割は年毎に高まり、それに伴って欧州統合の牽引役であるフランスやドイツの発言力は強まっていった。特に冷戦後、中・東欧諸国が加盟して拡大EUが誕生したことで、ドイツの存在感は飛躍的に増大するようになった。欧州においてイギリスの存在をアピールするにはEUへのコミットを強めねばならないが、そうすればイギリスは行動の自由を奪われ、逆にEUから距離を置けば、フランスやドイツの影響力はさらに強まり、イギリスはその風下に立たされかねない。
このジレンマから抜け出すには、大英帝国の時代と同様、再びイギリスは欧州域外への関与を強め、グローバルパワーとして行動することで自らの存在感を誇示する必要がある。折しも、アジアでは中国が急速に台頭し、経済的にも軍事的にも覇権的な行動を顕著にしつつあり、ユーラシアの西部地域では、ロシアの脅威が顕在化しつつある。クリミアの一方的な併合やウクライナ、バルト三国への威圧、さらにシリア内戦への介入で中東地域に積極的に進出するとともに、欧米諸国に対してサイバー攻撃やフェイク情報による謀略活動などを多用するロシアと欧米の関係は冷え込み、いまや「冷戦の再来」とも称されている。
中国やロシアの攻勢に対抗し、イギリスがその信条とする民主主義の政治システムや海洋の自由を礎とする自由貿易体制を擁護するためにも、イギリスはアジア太平洋地域への関与を強めるなどグローバルに活動しなければならない。国際情勢に対するこのような認識から、キャメロン政権(当時)が2015年に策定した「国家安全保障戦略」では、海洋国家との連携、特に日本との関係強化が打ち出された(2)。
さらにその後、国民投票によってイギリスはEUから離脱する途を選んだ。イギリス自身にとっても予想外といえるこの決定を受け、イギリスは離脱後、対欧州との関係で生じる経済的政治的な損失を、欧州域外との関係を強化することで補う必要に迫られている。1967年にスエズ以東からの撤退を決意し、アジア太平洋地域への関与・展開を放棄して以来半世紀を経て、イギリスは再びその外交戦略を転換させ、アジア回帰の姿勢を強めつつある。中露を牽制しつつ、経済的躍進が続くアジア太平洋地域との関係を強化するため、イギリスはアジアへと舵を切ったのだ。この入亜戦略を進めるうえで、イギリスが自らにとって最適のパートナーとして選んだのが日本である。
欧州との関係強化を図る日本
一方、同じ時期、日本ではユーラシア大陸を越えて欧州との関係を強化する動きが出始めていた。安倍政権は台頭する中国をいわば遠交近攻政策によって牽制するとともに、わが国が国際政治の舞台から埋没することのないよう、「積極的平和主義」を打ち出し、日本の政治外交の活動領域を欧州へと拡大させる戦略を推し進めている(対欧戦略的提携外交)。NATOとの安全保障協力の推進や対英・対仏関係の強化等がその代表であるが、これまでの同盟関係の歴史や経済的繋がりの強さなどから鑑みれば、対欧戦略連携の核となる国はイギリスをおいてほかにはないことは明白である。
また北朝鮮の脅威の増大や中国の覇権主義的行動が懸念される一方、トランプ政権の誕生で、自国中心政策や孤立主義化が懸念されるなどアメリカの対東アジア政策は読みづらさを増しており、日本としては日米安保体制に加えて、準同盟国とも呼び得る友好国として、イギリスへの関心と期待が高まりを見せている。
日本とイギリスの間にはユーラシア大陸を挟んで5400海里という広大な距離の隔絶が存在するが、かような国際情勢と国益判断から、両国は軌を一にして互いに相手国への接近を図り、新しい形態の“同盟”関係(New Type of “Alliance”)の構築に動いているのである。
(2)新日英“同盟”構築に向けた動き
新しい形態の“同盟”=包括的な安全保障協力同盟
「新日英同盟」といってもその意味するところは、100年前の同盟概念と今日のそれとではその目的や構造が大きく違っていることに留意しなくてはならない(秋元千明2018)。
この新しい同盟関係について、日本では「准同盟」などとも呼ばれるが、英国では、「同盟の新しい形態(New Type of Alliance)」と呼ばれることがある。従来の「同盟」とは、日米同盟やNATOのように、利害を共有する国同士が協力して共通の敵に立ち向かう「軍事同盟」のことを指していた。しかし、このような旧来の軍事同盟は近年、人道支援やテロ対策、平和維持活動に利用されるようになり、目的も構造も大きく変化してきている。「同盟」を軍事同盟として限定的に解釈するのはもはや時代遅れの感がある。
とくに旧来の同盟と最も大きな違いは、戦争に備えた同盟ではないという点である。同盟である以上、軍事的な協力関係があることはもちろんだが、この新同盟はむしろ平和時に大きく機能する。海洋安全保障、テロ対策、サイバー・セキュリティ、インテリジェンス協力、人道災害支援、平和維持活動、防衛装備品の共同開発など、多様化する安全保障のあらゆる分野で包括的に協力し合うことがその主な目的である。
例えば、日本の警察庁は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、2012年にロンドンでオリンピックを経験した英国の警備態勢やテロ対策に高い関心を持っている。そのため、ノウハウの提供を求めて、英内務省やロンドン警視庁との協力関係を進めている。このように、さまざまな安全保障問題に対して日英が協調して取り組むことが新しい同盟の根幹であり、東京オリンピック、パラリンピックに向けた日英協力は将来の「新日英“同盟”」へ向けた一つのステップになるのではないかと思われる。
「アジア・欧州において相手国の最も重要なパートナー」に
新日英“同盟”とも呼び得る日英両国の新しい形態の同盟関係の構築に向けた、最近の動きを追ってみよう。日英が戦略的に接近を始めたのは、2012年のことである。同年4月に野田・キャメロン両首相の首脳会談が開かれ、「世界の繁栄と安全保障を先導する戦略的パートナーシップ」と題する共同声明が発表された。この声明では「日英両国は、アジア及び欧州それぞれにおいて、相手国の最も重要なパートナーであ」り、東アジアの不安定性及び不確実性の問題について協力し対処すること、両国間の安全保障及び防衛分野における協力及び関与を拡大することが方針として示された。また防衛装備品の共同開発・生産を早期に開始することでも合意が成立し、6月には防衛協力のための覚書が取り交わされた。次いで14年5月の日英首脳会談での合意に基づき、翌15年1月にロンドンで初の日英による2+2(外務防衛担当閣僚会合)が開かれた。この協議では、テロとの戦いや平和貢献などでの協力をうたう共同声明と付属文書が採択され、自衛隊と英軍による共同訓練の実施やサイバー攻撃対処、軍縮・核不拡散に向けた連携などがうたわれた。
グローバルな戦略的パートナーシップ
16年1月に東京で開催された第2回の日英2+2では、海洋進出を強める中国への対応が協議され、南シナ海で一方的に人工島の造成を進めている中国に対し「大規模な埋め立てなど威圧的、一方的な行動に反対し自制を求める」とする共同声明を発表している。併せて、尖閣諸島をめぐり中国船が領海侵入を繰り返している「東シナ海の状況への懸念」も表明された。この会合に参加した岸田外相が、ウクライナや東・南シナ海における中露の一方的な現状変更の試みに対する日英の連帯を呼びかけたのに対し、イギリスのハモンド外相は「日本は我が国にとってアジアで最も緊密な安全保障パートナーである」と応じた。
そして冒頭に触れたように17年8月メイ首相が来日し、安倍首相との首脳会談後に発表された「安全保障協力に関する日英共同宣言」では、アメリカの最も緊密な同盟国である日英両国は「アジアおよび欧州におけるもっとも緊密な安全保障上のパートナーとして、ルールに基づく国際システムを維持するため指導力を発揮していく」こと、また日英の安全保障協力の包括的な強化を通じて、「安全保障上のパートナーシップを次の段階に引き上げる」方針が打ち出された。併せて発表された「繁栄協力に関する日英共同宣言」および「日英共同ビジョン声明」では、貿易・投資の拡大など両国の経済パートナーシップの強化や新たな経済協力枠組みの構築を急ぐことなどが示された。
さらに17年12月にロンドンで開かれた第3回目となる日英2+2では、「グローバルな戦略的パートナーシップ」と名付けた共同声明が発表され、日本がアメリカと共有する「自由で開かれたインド太平洋戦略」が日英両国にとっても共通の利益であること、また日英のグローバルな安全保障上のパートナーシップを次の段階へと引き上げる」と宣言し、日英両国はアメリカと並び、お互いを自らの実質上の同盟国(準同盟国)と位置づけ、両国の安全保障協力をさらに深めていく方針が明確にされた。
(3)日英防衛協力体制の進展
①日英海軍の情報交換、部隊間協力・交流
このように日英両国の戦略的連携の枠組み作りが進められるなか、日英の軍事的連携や協力関係も大きな前進を見ている。まず2015年2月、英海軍の連絡士官サイモン・スティリー中佐が日英海軍の情報交換、部隊間協力・交流に関する連絡調整のために自衛艦隊司令部に派遣された。海上自衛隊と英海軍は、ソマリア沖・アデン湾で海賊対処活動を実施する多国籍部隊で協力関係にあるが、海上自衛隊が米軍以外から連絡官を受け入れたのは、これが初めてである。ステイリー中佐は横須賀に拠点を置く米第7艦隊の連絡官も兼務し、日米英三国海軍の連携が進むことになる
②航空自衛隊と英空軍による共同訓練
2016年1月の中谷元防衛大臣とファロン国防相との日英防衛相会談では、航空自衛隊と英空軍による共同訓練の実施が決まり、同年10月下旬から11月にかけて、三沢基地で航空自衛隊のF-15、F-2戦闘機と英空軍のタイフーン戦闘機部隊による領空防衛や艦船攻撃などの共同訓練ガーディアンノース16が行われた。これは、航空自衛隊が日本で行う米軍以外との初の共同訓練であった。この訓練に参加するため、英空軍機は1万海里におよぶ距離を飛行して日本に到着。11月2日の訓練では、航空自衛隊の2機の複座型F-2の後部座席に航空幕僚長と英軍参謀長がそれぞれ乗り込み、訓練に参加している。
③日英物品役務相互提供協定(ACSA)
2017年1月、日英両政府は自衛隊と英軍が食料・燃料などの物資や輸送・修理などの役務を融通し合える物品役務相互提供協定(ACSA)を締結した。日本が締結したACSAとしては、アメリカ、オーストラリアに続く3例目で、欧州諸国ではこれが初である。
④武器・技術の共同開発
武器・技術の共同開発においても、日英両国の接近が急速に進んでいる。
⑤防衛装備品・技術移転協定
先述した12年の首脳会談における武器共同開発の早期実施合意を受け、13年7月には防衛装備品・技術移転協定が発効し、日英二国間の防衛装備・技術協力の基盤が整備された。2014年には新型空対空ミサイル、16年には防弾チョッキなど個人装備品に関わる共同研究がそれぞれ開始された。さらに17年には、将来型戦闘機(F-2後継)の共同研究を進めることでも合意が成立している。
⑥日英情報保護協定
情報分野では、2014年1月に日英情報保護協定が発効し、情報共有の体制も整備された。
2.地政学と海洋同盟
(1)覇権をめぐるランドパワーとシーパワーの闘争
海洋国家と大陸国家による覇権争奪の歴史
自由と民主主義を基調とする我が国は、日米安全保障体制に基づきアメリカとの緊密な同盟関係の維持発展を国家戦略の礎としているが、北東アジアの平和と安定の確保や緊迫した北朝鮮情勢に対処すべく、日米に韓国を加えた日米韓の連携強化に努めている。また安倍政権は、わが国と海で結ばれているASEANやオーストラリアなど、大洋州諸国との関係を重視するとともに、中国の軍事・経済両面の覇権主義的な行動に対抗するため、「自由で開かれたインド・太平洋戦略」を打ち出し、インドやスリランカなどインド洋海洋諸国との連携を強めている。
こうした動きに加えて、今般、ともに海洋国家である日本とイギリスが戦略的な連携を深めることは、近世以来の史的な潮流から眺めれば故なき試みではなく、むしろ必然の経過というべきものである。[大航海時代以後の世界史とは、海洋国家と大陸国家による覇権争奪の歴史であり、その時々に勢力を強めた大陸国家が海洋国家の世界支配を打ち破ろうとしたが、最終的には常に海洋国家が勝利を収め、大陸国家の挑戦を退けてきた。21世紀の現在にあってもこのセオリーは機能しており、]中国やロシアという大陸勢力の膨張と覇権主義を防ぐため、自由と民主主義を基調とする海洋諸国が広域な同盟を築こうとする試みが歴史の摂理に叶うものである。このことを理解するには、大陸国家と海洋国家の対立から覇権闘争の史的メカニズムを説く地政学が参考になろう(末尾参照)。
マハンの「シーパワー(海洋権益)理論」
地政学では、海洋の支配に発展の途を求める海洋国家と、領域支配の拡大に生存と繁栄を見出す大陸国家に国家を大別する。両者の力関係については、海洋支配による海洋国家の大陸国家に対する優位を説くシーパワー論と、反対に大陸国家の優越性を強調するランドパワー論が存在する。
海洋支配が国家発展の重要な鍵であると主張する立場は古くから存在し、例えばヘロドトスの『歴史』に拠れば、例えば東方ペルシアの勢力拡大にギリシアが対抗するための方途としてヘカタイオスは海上制覇の必要性を説き、アテネのペリクレスもdemocracy(民主政)と並びthalassocracy(制海)の重要性を強調したことがトゥキディデスの『戦史』に記されている。制海の概念はその後ビザンチンやイスラームの学者に継承され、十字軍以降西ヨーロッパの知識人、為政者に伝えられ、受け継がれていった。特にイギリスでは、ベーコンが「海上を支配することは、君主国の要諦である」と指摘する等海洋支配に対する認識は深く、後世自らの実践を通してその意義の大きさを世界に知らしめることになった。そして国家による海洋支配の重要性は、19世紀末、イギリスを継承する海洋国家アメリカの海軍軍人アルフレッド・セイヤー・マハンによって「シーパワー(海上権力)理論」として体系化された。
『海上権力史論』を著したマハンは、海洋の利用を自己のために確保し、敵の海洋利用を拒否するために作用する一切の政治・経済的、社会的、地理的・自然要因の総計をシーパワー(海上権力)と捉えた。それは、海洋の一部または全部を支配し、利用し得る力である以上、軍事力たる海軍力が大きな役割を担うが、それだけでなく、平時における商業交易にかかる力をも含むものである。そして一国のシーパワーを構成する重要な要素としてマハンは、強い海軍力、商船隊、海外基地の三つを指摘するとともに、シーパワーの隆盛を左右する要因として、次の6点を挙げている(3)。
①地理的位置(海岸がシーレーンに面する島嶼性)
②自然構造(湾口に富む海岸線)
③領土の規模(資源と富を供給できる領土的基盤)
④人口(必要な船員を供給できる人口基盤)
⑤国民性(海洋的志向と船乗り生活への適正)
⑥政府の性格(進取的な海洋政策を推進できる政府形態)
マッキンダーの「ハートランド理論」
マハンのシーパワー論に対抗し、ランドパワーの持つポテンシャルの高さを指摘したのが、イギリス人ホールフォード・マッキンダーである。彼は先述の論文「歴史の地理的回転軸」及び『デモクラシーの理想と現実』(1919年)において、人類史はシーパワーとランドパワーの闘いの歴史であるが、地球上にはシーパワーの及ばぬ広大なユーラシア大陸(ランドパワー)が存在し、ユーラシア大陸の枢要地帯(ハートランド)に位する者は、その力をもって海洋国家をも支配することが出来ると主張した。
マッキンダーは、クレタ島はギリシアに、ギリシアはマケドニアに圧倒され、ローマ時代のブリテン島はヨーロッパ大陸を制したローマ帝国の下に屈し、そのローマも中欧のゲルマン民族によって滅ぼされた史実を、グローバル普遍的な公理として把握する。そして、ユーラシア大陸内部で北極海へ注ぐ河川の流域並びにカスピ海、アラル海へ注ぐ河川流域で、軍艦が遡行できず、海上権力の及ばない地域をハートランドとし、世界をハートランド、内側孤状(クレッセント)地帯(ハートランドを囲む地帯)、外側孤状地帯(ユーラシア大陸の外側に散在する大小の島々で、アメリカ、アフリカ南部、東南アジア~大洋州を連ねるライン)の三つに分け(図-1参照)、ハートランドは人口も少ない不毛の地だが、鉄道網の発達により次第に潜在的力量を増し、強大なランドパワーの中核となり、いずれは内、外孤状地帯を制するであろうと主張した。つまり、「東欧を支配する者はハートランドを制し、ハートランドを支配する者は世界島(ワールドアイランド:ユーラシア及びアフリカ)を制し、世界島を支配する者が世界を制する」というのである(4)。
もっとも、マッキンダーの真意は、大陸国家の台頭に警鐘を鳴らすことにあった。彼は20世紀における陸上交通機関の進歩や海上権力イギリスの衰退に着目し、ハートランドを擁するロシアこそ最も恐るべき陸上権力であるとして、ロシアが内側弧状地帯に進出することを警戒するとともに、ドイツがロシアと提携する危険性を警告する目的でこの理論を唱えたのである。
だが、皮肉にもマッキンダーのハートランド理論は、「国家は、それ自体成長する一つの生き物であり、成長するにあわせて食物(生活圏)を与えてやらないと衰弱して死んでしまう」というラッツェルのレーベンスラウム(生活圏)理論と併せ、ドイツ陸軍少将カール・ハウスホーファーによって、領土の拡張と天然資源の獲得を通じてアウタルキー(自給自足)の確立をめざすナチスドイツの侵略正当化のための理論へと変質させられていった。ハウスホーファーは、国家は自己の生存発展のために一定のエリアを生活圏として確保し、自給自足に必要な資源や産業を支配する権利を有するとし、世界を①アメリカが支配する汎アメリカ②日本が支配する汎アジア③ドイツが支配するヨーロッパとアフリカを併せた汎ユーラシア④ロシアが支配する汎ロシアの四つの総合地域(Pan region)に分割することを提唱し、大陸国家と海洋国家の理論を、持てる者と持たざる者の対立論にすり替えたのである。
スパイクの「リムランド」理論
マッキンダーのハートランド理論に対し、リムランド論を唱えた人物にアメリカ人のスパイクスマンがいた。その著『平和の地理学』(1944年)で彼は、人類の歴史をハートランドを扼するランドパワーと海洋を支配するシーパワーの拮抗と見るのは単純で、ランドパワーとシーパワーとが接触するハートランド周辺のユーラシア大陸沿岸地帯を重視し、ここをリムランドと名づけた(図-2参照)。これは、マッキンダーの提唱した内側弧状地帯にほぼ匹敵する地域である。
リムランドは降雨量が多く農耕に適し、人口稠密で大きな発展可能性を秘めている。ハートランドの特色である政治的統一と力の集中化が見られずリムランド地域は多くの独立国家に分立しているが、もしこのリムランドを統合するパワーが出現すれば、ハートランドもシーパワーもこれに対抗できず、「リムランドを支配する者はユーラシアを制し、ユーラシアを支配する者は世界を制するであろう」ことから、シーパワー勢力はハートランド勢力にリムランドを支配させてはならないとスパイマンは主張したのである(5)。
(2)シーパワーの優位とリムランド確保の重要性
近現代史は、海洋勢力と大陸勢力の抗争史
大航海時代の到来によって幕が開いた近世史は、海洋勢力と大陸勢力の抗争史であった。そして、その時々に覇を唱える大陸国家が海洋国家に挑んだものの、いずれの国も最終的には海洋国家によって退けられ、覇権国家の座を勝ち得たのは、ポルトガル~スペイン~オランダ~イギリス、そしてアメリカとすべて海洋国家であった。大陸国家の場合、ライバルとなる国が隣接するか自国周辺に控えており、海外に雄飛する際の障害となった。また各国とも強大な陸軍を擁しており、大陸国家間の戦いに勝って海洋への進出を果たすためには、陸海軍の両方を整備せねばならなかった。この重負担が海軍の整備に専念できる海洋国家との戦いで大きなハンデとなった。ロシアやドイツ、ソ連の挑戦をイギリスやアメリカが退けたのは、この両国がリムランド、即ち中東やアフリカ、アジアの各地に多くの植民地や同盟国を擁し、大陸勢力の進出を食い止めることができたからである。
このような現実の国際政治の経緯展開を眺めると、諸説の中でもスパイクスマンの仮説が最も歴史の真理を突いたものといえよう。第二次大戦後における自由主義と共産主義の対立も、それまでの大陸、海洋両国家間対立の延長線上で捉えることができる。カーター政権の国家安全保障担当大統領補佐官だったズビグネフ・ブレジンスキーは、米ソの対決を「海洋大国と優勢な大陸国家の間の、大昔からの伝統的といって差し支えない紛れもなく地政学的な衝突の系譜に並ぶものだった。この意味で、アメリカはイギリス(さらに溯ればスペイン、オランダ)の後継国であった。一方のソ連は、ナチスドイツ(遡れば神聖ローマ帝国、プロシア、ナポレオン時代のフランス)の後継国であった」と述べている(6)。新冷戦の時代、CIAのレイ・クラインは全海洋同盟構想を説き、西側諸国の繁栄は中東石油の安定供給とシーレーンの確保にかかっており、この西側生命線に対する共産勢力の脅威に対し、海洋国家は一丸となって抗さねばならないと主張した。冷戦をリムランドの争奪戦と捉えたのはイギリスの国際政治学者コリン・グレイも同様で、彼は地政学的見地から対ソ封じ込め政策の正当性と必要性を訴えた(7)。そして封じ込め政策が功を奏し、アメリカがソ連の中東やアフガニスタン、アフリカへの進出を阻みリムランドを掌握したことによって、冷戦は西側の勝利で終わったのである。
リムランドをめぐる大陸国家連合と海洋国家連合の闘争
海洋国家の優位とリムランド支配の重要性に関する法則は、21世紀の現在においても妥当する。米国防省は4年ごとに国防政策の見直しを行っているが、その2001年版(「QDR2001」) において、アフリカからバルカン半島~中東、コーカサス、南アジアのアフガニスタン、インド・パキスタン、さらに南シナ海から台湾海峡、そして朝鮮半島に至る弓状のエリアを、紛争が多発し国際情勢を流動化させる「不安定の弧」と名付けた。また先のブレジンスキーも、コーカサス~カスピ海~中央アジアに至るユーラシア周縁部は世界で最も不安定であり、かつ地政的に極めて重要な地域であるとして「危機の弧」と呼んでいる。それらはいずれも、スパイクマンがリムランドと名付けた地域と概ね合致するものである。
ユーラシア大陸の南を東西に横切るこのラインは国際政治上のホットスポット(中東紛争、印パ紛争、中台紛争、南北分断の朝鮮半島) であり、活発な国際テロ活動を行っているイスラーム原理主義勢力が拠点とする地域でもある。NPT体制に挑戦し、核保有をめざし、あるいはめざした国(イラク、イランやパキスタン、インド、北朝鮮)も全てこのベルト上に所在している。この地域を誰が掌握するかによって、国際政治の動向や覇権の行方が大きく左右されることは明らかである。そして現在、中東やユーラシアの東部で攻勢に出ているロシアとともに、リムランドへの勢力拡大を最も強力に推し進めているが中国である。習近平政権が掲げる一帯一路構想は、リムランドの支配を目指す戦略にほかならない。
大陸・海洋両勢力の抗争も、現代では特定の大国どうしの二国間闘争にとどまらず、複数の国家を包含した国家連合間の対決となる傾向にある。冷戦時代における東西両陣営の対立がそうであったし、現下の覇権闘争も、中国・ロシアの大陸国家連合と日米英豪などの海洋国家連合が凌ぎを削る構図を見せている(coalitionの時代)。両勢力の衝突が地球規模に拡大したこと、軍事だけでなく政治経済文化などソフト、ハードの両面を含む総合的な力と力の対決となってきたこと、相互依存の進展や情報通信革命の影響でパワーの拡散が進み覇権国家の強大さが低下しやすいことなどがその理由である。
ロシアや中国は、世界の各地域で武力の行使も伴う威圧的な力の行使によって一方的に現状を変更し周辺諸国に脅威を与えている。大陸勢力(ランドパワー)が日増しにその影響力を拡大させつつある状況に適切に対処し、その膨張を食い止めるためには、海洋勢力もこれまで以上の広域な同盟体制を築く必要がある。太平洋に位置する日本と大西洋国家のイギリスが手を組み、アメリカとともに両大洋を対象とする広域同盟を築き、ユーラシア大陸勢力の膨張、リムランドへの進出を食い止めること、それが新日英“同盟”に期待される役割である。
3.近代日本の発展と英国:日英連携の歴史
(1)ロシアの南下膨張と日英同盟:帝国外交の神髄
「岩倉使節団」とイギリスを主とした「お雇い外交人」
これまで、日本とイギリスの戦略的な関係強化に向けた動きが急ピッチで進んでいる状況とその背景、それに海洋同盟構築の必要性を概観してきたが、そもそも近代日本の発展はイギリスとの交わりに端を発したといっても過言ではない。戦後における日本の政治経済や外交、特に安全保障政策については、日米安全保障体制に代表されるように、アメリカとの関係が極めて強いが、明治から大正期にかけて、日本の基軸同盟国はイギリスであった。
「君がより遠くを見る程、より先の未来を見通すことができる」と述べたのはヘンリーフォードであるが、来るべき新日英“同盟”の時代を控えて、この新たな戦略的枠組みをより発展させ、かつ有効に機能させるためにはどのような点に留意し、配意すべきであるのか。この問題を考えるにあたって、過去に目を向けることも無駄ではあるまい。歴史を遡り、かつて日本外交を支える大黒柱であった日英同盟について、その歴史的な背景や意義、そして廃棄に至った原因を考察し、新日英同盟の未来を考える資を得たい。
明治新政府は、発足直後の1872年7月、岩倉使節団をイギリスに派遣した。岩倉使節団とは、1871年から1年9カ月にわたり米欧に派遣された「特命全権大使遣欧使節団」のことで、使節団長を務めた岩倉具視の名前をとり、俗に「岩倉使節団」と呼ばれる。リバプール経由でロンドンに到着した使節団は、ロンドン、リバプール、マンチェスター視察を経てスコットランドヘ向かう。その後、再びロンドンに戻り、11月にドーバーからカレーに渡りフランスに入るまでの122日間、一行は政治制度をはじめイギリスの国家運営システムや、産業革命の成果といえる近代的な工場、造船所等の産業諸施設を実に幅広く見て回っている。随員久米邦武が著した『米欧回覧実記』からは、イギリス発展の秘密を探ろうとする一行の情念が伝わってくる。
人を送り出す一方、新政府は近代化を進める助っ人として、イギリスから多くの専門家や技術者を招聘した。1874年当時の“お雇い外国人”国籍を見ると、総計503人中イギリス人は全体の半数を超える269人と圧倒的な一位を占めており、工部省、文部省、海軍省が多くのイギリス人を雇っている。近代海軍の建設を急ぐ日本海軍は英海軍に範をとり、1870年にイギリス式に軍制を統一し、ダグラス中佐をはじめイギリス人の教官や技師、船舶設計者、造船工を招聘するとともに優秀な若手をイギリスに派遣・留学させた。日本海海戦を勝利に導いた東郷平八郎やその参謀秋山真之もともにイギリス留学・駐在組であった。
渡日した多くのイギリス人のなかには、日本アルプスの名付け親で、日本考古学の父とされるウイリアム・ゴウランドもいた。グラバー邸に名を残すトーマス・グラバーは、スコットランド出身の実業家。横浜港湾施設を作り上げたのも、スコットランドの技師であった。彼らの貢献で軍事、鉄道、逓信、運輸等多くの分野でイギリスを範とする我が国の近代化が進んだ。1891年には、日本に関心を持つ学者や外交官らによってロンドンに日本協会(The Japan Society)が作られ、日英の民間交流も始まっている。
明治政府を支援したイギリス
明治新政府が成立するも、未だその基礎が定まらなかった時期、日本がイギリスから受けた好意斡旋は日本のその後の発展に極めて貴重なものであった。征台の役(1874年)の際、軍事輸送に耐えるだけの船舶を持ち合わせていなかった日本政府はアメリカに援助を求めるが、局外中立を名目にアメリカは支援を拒否した。一方、政府顧問であったイギリス人キャプテン・ブラウンは自ら香港に赴いて外国船13隻を購入したほか、軍事輸送船団の組織にもあたった。3年後に起きた西南の役でも、ブラウンが徴用し整えた輸送船によって明治政府は九州に兵を送り、内乱を鎮圧することができたのである。
その後、1894年に日清戦争が勃発すると、イギリスは局外中立を宣言した。もっとも日本軍の連戦連勝を受け、英国の政府も世論も日本に好意的であった。またこの年には日英通商航海条約が結ばれて、領事裁判制度が撤廃された。ロシアの南下を警戒するイギリスが日本の東アジアにおける軍事力を評価して条約改正に応じたもので、以後、列国がこれに続き、不平等条約の一部撤廃が実現する。日清戦争後、日本は露独仏の三国干渉を受けたが、イギリスはこれに荷担せず、むしろ三国の動向について日本に情報提供するなど友好的であった。
程なくロシアが満洲・朝鮮に露骨な進出の気勢を示すや、これに対抗すべく1902年に日英同盟が締結される。条約の内容は、締結国が他の1国と交戦した場合は同盟国は中立を守り他国の参戦を防止すること、2国以上との交戦となった場合には同盟国は締結国を助けて参戦することを義務づけるものであった。「名誉ある孤立」政策を捨て、イギリスが敢えて極東の小国日本と同盟を結んだ背景には、ボーア戦争の泥沼にはまり、自ら極東におけるロシアの膨張を阻止する力を失った事情が指摘できるが、世界の海を支配する大帝国と対等な同盟を結んだことで日本の国際的地位は一挙に高まり、日本人は朝野ともに日英同盟を大歓迎で迎えた。当時ロンドンに留学中だった夏目漱石は、醒めた目で同盟締結を受けとめているイギリスと熱狂を以て迎えた日本を比較し、慨嘆する手紙を書き送っている。
日露戦争を背後で支援
同盟の締結から2年後に日露戦争が勃発する。イギリスは表面的には中立を装いながら、情報提供や軍艦の購入、さらに露海軍への協力拒否でバルチック艦隊の極東回航を遅延させるなど日本を大いに助けた。日本海軍の保有する戦艦全6隻は、すべてイギリス製であった。戦費調達でもイギリスは協力的だった。ロンドンに赴いた日銀副総裁高橋是清は、弱小国日本に関心を示さない当地の銀行家を説得して回り、苦労の末に日本国債の販売に成功する。英米の支援もありロシアとの戦いに辛勝した日本は、日英同盟を延長する(1905年)。第二次日英同盟では、条約の適用範囲が清国と朝鮮半島からインドにまで拡大され、イギリスのインドにおける特権と日本の朝鮮に対する支配権を認めあうとともに、清国に対する両国の機会均等が定められた。さらに締結国が他の国1国以上と交戦した場合は、同盟国はこれを助けて参戦するよう義務付けられた(攻守同盟)。1910年にはロンドンで日英博覧会が開催され、大相撲が披露されるなどイギリス人の対日関心も高まった。
(2)中国・太平洋をめぐる日英の衝突
アジアの権益拡大を狙った日本
しかし日露戦争後、ロシアの脅威が低下するに伴い、イギリスにとって日英同盟の価値は低下していく。対露関係を改善(英露協商)し、イギリスはドイツの脅威に備える。日本の経済発展を警戒し始めたアメリカも、この同盟を嫌うようになった。日米戦が起きた場合、アメリカはイギリスを敵に回さねばならなくなるからである。そのため第三次日英同盟(1911年)では、ドイツの脅威を対象に加える一方で、アメリカが交戦国の対象から外された。
1914年、第一次世界大戦が始まり、日本は日英同盟に基づき、連合国の一員として参戦した。欧州への兵力派遣に日本は消極的だったが、英側の強い要請を容れ、海軍は12隻の駆逐艦を地中海に派遣し、ドイツ潜水艦の掃討や輸送船団の護衛に当たった。またドイツに対処すべくアジア太平洋地域から多数の艦艇をヨーロッパに引き上げざるを得なかったイギリス海軍は、制海権の空白を埋めるため、東シナ海におけるドイツ仮装巡洋艦の撃破やドイツ極東艦隊の太平洋・インド洋での活動制圧を日本に期待し、日本海軍はよくこれに応えた。だが、アジアの権益拡大を狙う日本は、軍事行動を海上作戦に限定するよう求めるイギリスの要請に従わず、陸軍は山東省にあるドイツの根拠地青島を、海軍はドイツ領南洋諸島を占領した。さらにヨーロッパでの大戦の隙を突いて日本は21カ条の要求を中国につきつけ、これが中国だけでなく英米の反発をも買うことになった。
日英同盟破棄で基軸同盟国を失う
大戦後のワシントン会議で日本は英米仏と四か国条約を締結し、それに伴い日英同盟は破棄された(1921年)。日英の特殊取極は国際連盟の集団安全保障理念と両立し得ないというのが表向きの理由とされたが、日本の台頭を強く警戒し、また世界最強のイギリス海軍と第三位の日本海軍に挟撃され、日米開戦となった場合対英戦をも覚悟しなければならない事態をアメリカが嫌ったことが同盟を解体に追い込んだ主因であった。日本は更新を望んだが、アメリカの意向に加え、露独の脅威が消滅したことでイギリスも条約の必要性を認識しなくなっていた。日英同盟が廃止に追い込まれた結果、日本は覇権国家との基軸同盟関係を失うことになった。また四か国条約と同じ年に結ばれた海軍軍縮条約で、米英日の主要艦保有比率が5:5:3とされ、日本の軍部には不満が残った。日本海軍を牽制する目的で、1921年イギリスはシンガポールに海軍基地の建設を決定する(1938年完成)。
それでもワシントン体制の下で東アジア情勢は安定的に推移したが、中国市場を巡る日本と英米の対立は次第に先鋭化する。満州事変勃発後、国際連盟はイギリスのリットン卿を長とする調査団を編成し、事変の究明に動いた。リットン報告書作成にあたりイギリスは日中両国に対し慎重で中立的な立場を採ったが、日本軍が万里の長城を越えて黄河に侵攻したため連盟は対日批判を強め、反発した日本はこれを脱退する。改訂された帝国国防方針(1936年)では、初めてイギリスが日本の仮想敵国に組み込まれた。日中全面戦争が始まるや、蒋介石政府を支援する英米両国と日本の関係はさらに険悪となった。それからわずか5年の後、日本は同じ海洋国家である英米との戦争に突入し、やがては国を亡ぼすことになった。日英同盟の破棄は、日本、イギリス、アメリカいずれの国にとっても不幸な結末となったのである(8)。
(3)日英同盟体制崩壊の教訓
海洋国家との連携を拒絶し、大陸国家に接近して墓穴
イギリスからアメリカへと覇権国家の座が移り変わるなど国際政治の枠組みや構造が大きく変動する20世紀前半の過渡期において、日本は国際秩序の動向を完全に読み誤り、利害を共有し得る海洋国家英米との連携を拒絶、敵対し、逆に地政環境を異にするドイツやロシアといった大陸国家に接近、その野心と思惑に振り回され、さらには目先の派手な行動に幻惑され、自ら墓穴を掘った。
要すれば、日英同盟を失ったことが、近代日本の大きな転換点であった。現状維持勢力との絆をなくした日本は、激動する世界情勢に翻弄され、流浪を続けるうちに、いつしか大陸勢力に取り込まれ、世界秩序に対する危険な挑戦勢力の一員と化し、破滅への道程を歩むことになったのである。現代に生きる我々は、この誤りを決して繰り返すわけにはいかない。
日英同盟の破棄から1世紀近い歳月が経過した。現在の国際情勢には、当時と近似するものがある。世情海洋国家アメリカの影響力低下が叫ばれ、他方、大陸勢力である中国やロシアの行動が活発化している。中でも中国は、一帯一路に代表される大規模な経済外交を展開するともに、軍事力の急速な拡大を背景に周辺地域への影響力を強めている。それゆえ、早晩覇権国家の座がアメリカから中国に移り替わるであろうから、日本はアジアから後退するアメリカよりも同じアジアに位置する中国との関係をより重視すべしとの言説も散見される。
しかし、自由や民主主義を基盤とする日本は、同じく開かれた社会政治体制を基盤とする海洋国家との連携を生存の基本とすべきである。また交易によって生きていかねばならない日本は、自由貿易を旨とする海洋国家と共存共栄を図ることができるのであって、抑圧と専制の政治体制を取る大陸国家とは利害が一致することはない。日本を大陸勢力の側へと取り込むことは、海洋勢力英米からそのアジアにおける最大の盟邦を奪い取ることに繋がる。これは、アメリカのアジアからの後退やその影響力の排除を望む勢力にとっては願ってもない状況であり、さらにはアメリカにとって代わって大陸勢力が海洋に進出する絶好の機会を与えてしまうことにもなろう。
中国による日英離反工作の存在
いま一つ、日英同盟体制崩壊の歴史で見落としてならないのは、中国による日英離反工作の存在である。中国は日英同盟の危険性をことさらに誇張し、その廃棄の必要性をアメリカやイギリスに執拗に訴え続けた。中国が働きかけたのは、外国政府だけではなかった。中国は、ワシントン会議など公の場にとどまらず、董顕光等の反日ジャーナリストや在外華僑を動員し、日英同盟の本質が中国侵略のための同盟であること、また日本の領土的野心を著しく助長するものであるとして、アメリカやイギリス、カナダなどの政府だけでなく各国の世論にも巧みにアピールし、中国への同情心をかうとともに同盟反対の機運を盛り上げ、日英同盟破棄に追い込んだのである。日本と他の海洋国家との連携を遮断し、日本の孤立化を画策する手法は、現在でも行使される恐れがあり、こうした大陸勢力の動きには十分な注意を払わねばならない。
4.新日英“同盟”の意義と重要性
(1)アメリカの影響力の相対的低下を補完
ここで、日英が構築を急いでいる新日英“同盟”の意義を纏めてみよう。まず、海洋国家の日本とイギリスが連携、同盟関係を築くことは、海軍をはじめとする中国軍の急速な増強に伴いアメリカの西太平洋・東アジア地域における相対的な影響力の低下を補う上で大きな意義がある。
(2)自由貿易体制の地球的規模での拡大
軍事面での意義にとどまらず、EUから離脱するイギリスが新たな経済機会を得る狙いから今後TPPへの参加に踏み切れば、自由貿易体制の地球規模での拡大に道を開くことになろう。
(3)大陸勢力の覇権膨張的な行動をグローバルに抑止
日米、米英に加え、日英の軍事、経済、情報等幅広い協力関係を構築することによって日米英三国からなる地球規模の海洋同盟が誕生すれば、ロシアや中国という大陸勢力の覇権膨張的な行動をグローバルに抑止し、リムランドを自由と民主主義の敷衍する開かれた地として守り抜く体制が整うことになる。
(4)情報大国であるイギリスから戦略情報を入手
わが国の安全保障能力の向上という面では、情報大国であるイギリスとの同盟関係を築くことで、日本は中東や欧州、さらにロシアに関する戦略情報を入手することが期待できる。日本から遠隔な地域の情報はこれまでは専らアメリカ頼りとなりがちであったが、欧州に位置するイギリスからの中東、アフリカ、ユーラシア情報の獲得によって、アメリカ一辺倒ではない複眼の視点で国際情勢を捉えることが可能となる。イギリスを介して、日本とNATOとの軍事交流や情報交換もより緊密化するであろう。
(5)日米関係の強化を促す触媒の役割
新日英同盟の存在は、日米関係が弱化する事態の回避にも資するものである。アメリカを唯一の基軸同盟国とすることに不安や懸念が出始めている現在、日本が歴史的にも民族的にも、それに地政的、戦略的にもアメリカに最も近い同盟国であるイギリスとも同盟関係を築くことは、日米同盟関係をより盤石なものとなす触媒の役目を果たすであろう。
(6)日米安全保障体制の永続性を担保
新日英同盟はアメリカの日本切り捨て、中国接近という悪夢の到来を防ぐ力も持っている。自由と民主主義を国是とする日英両海洋国家の連携は、日本の重要性と戦略的な価値をアメリカに再認識させる契機となり得る。中国ではなく日本こそアジア太平洋における最良のパートナーであることをアメリカに自覚させ、日米安保体制の永続性を担保する力を、この新同盟は持っているのだ。
(7)武器・軍事技術の共同開発によるビジネスチャンス
新日英“同盟”は、資本や軍事技術における日米の圧倒的格差がもたらす弊害を補い是正する機能も期待できる。日米安保体制は日本の基軸同盟であるが、日本とアメリカの国力の開きは大きく、武器・軍事技術の開発では圧倒的な資本と技術力を擁する米企業に太刀打ちできず、対等なビジネスの関係を築きにくいという問題点がある。支援戦闘機F-2の日米共同開発を巡って、日本企業が期待したアメリカの高度技術の提供が受けられず、しかも生産ラインの確保でも不利な条件を強いられたことは記憶に新しい。それに比べると日本とイギリスは国力、国情が近似しており、武器・軍事技術の共同開発に際しても、背丈の近い国同士ゆえに対等な協力関係を築きやすい利点がある。
そもそもイギリスが日本との防衛協力に積極的になった背景には、2011年12月に日本政府が武器輸出三原則を緩和し、同盟国であるアメリカ以外の国との武器の共同開発に途を開いたこと(「防衛装備品等の海外移転に関する基準」に関する内閣官房長官談話)が影響していた。イギリスは、新世代レーダーや複合材など日本の先端技術に魅力を感じており、 また海上監視能力の向上を検討していることから、日本が開発した対潜哨戒機P-1やC-2にも関心を寄せている。日本としても、アメリカの同盟国であるイギリスとの共同開発や武器輸出であれば国内の反発も少ないことから、航空機の販路拡大を狙う日本企業にとってイギリスは良きパートナーとなり得る。イギリス防衛産業の技術を日本企業が取り入れる機会も増えるであろう。既に日英の間では化学防護服や防弾チョッキなどの個人装備品の共同開発が進んでいるが、莫大な開発投資を必要としない分野で、互いの企業が得意な分野を提供しあえば、裾の広いビジネスチャンスを生み出すことも可能だ。
5.新日英“同盟”の機能発揮のための五つの施策
新同盟体制の整備構築に向けた日英両国の取り組みは、今後さらに積極加速化していくであろうし、またそうあらねばならない。もっとも、ユーラシアの両端に位置するという日英両国の距離の遠大さもあり、新日英“同盟”をより円滑、効果的に運営していくために留意すべき幾つかのポイントにも触れておきたい。アメリカの国際政治学者スティーヴン・ウォルトは「なぜ同盟は持続又は終焉するのか」という論文で、同盟が長きにわたって機能し存続し得る条件として、①「脅威認識に齟齬や変化が生じないこと」に加え、②「覇権的な統率力の発揮」や③「同盟の制度化」④「信頼性の保持」⑤「イデオロギー的連帯の存在」といった要件を挙げている(9)。
(1)脅威認識に齟齬や変化を生じさせない
まず①に関しては、同盟国間で脅威に対する認識が一致していることは、同盟の形成及び維持存続の前提条件である。日本とイギリスの双方にロシアという共通脅威が存在していたことが日英同盟を生み出し、また同盟が有効に機能し得た最大の要因であった。しかし日露戦争の終結後、ロシアの脅威が低下し、それに代わって欧州ではドイツの脅威が顕在化したこと、さらに第一次世界大戦後はドイツの脅威も解消され、その間のアジアにおける日本の大陸や太平洋への進出が欧米に警戒心を生み出すことになった。こうした共通脅威の消失や脅威認識の変質が日英同盟の破棄に繋がった。
新日英“同盟”及び日米英の海洋同盟の運営にあたっては、加盟各国間のコミュニケーションを常時密にし、中国やロシアに対する認識の相互確認や擦り合わせが頻繁に行われなければならない。なお、国家にとっての脅威は一般に対象国の「能力×意図」によって評価されるが、21世紀にあっては、「能力」はかってのように軍事力だけでなく、経済力をはじめITなどの情報技術力や社会システムの発信力などソフトを含む多面的包括的な力として把握する必要があろう。
(2)覇権的統率力の発揮
次に「覇権的統率力の発揮」とは、強力な同盟の盟主による覇権的な力の行使が同盟に耐久性を与える根源であるとするもので、同盟の持続には、同盟の盟主による同盟維持への強い関与と自己犠牲も辞さない覚悟が必要ということである。日英の新同盟はそれ自体で独立完結したものではなく、日米英三国のトライラテラルな枠組みの一辺を形成するものであり、その中で覇権的な統率力を発揮するのはアメリカである。日英両国は、ともすればアメリカが内向き、孤立化の途を歩みかねない国であることに留意し、自国第一主義に陥り、海洋同盟の盟主、覇権国家としての自覚と振る舞いを忘れぬよう太平洋・大西洋の両方面から絶えずアメリカに働きかける必要がある。そのためにも日本とイギリスは距離の隔絶を克服すべく緊密な協議を重ね、国際情勢に対する認識の一致や意思疎通の円滑化に努める必要があるのだ。
(3)同盟の制度化
第三の「同盟の制度化」とは、国際情勢に対する認識を共有するための協議の場を設けたり、軍事計画や兵器の調達、危機管理等を共同で行う同盟国間の正式な組織の設置、さらに同盟の意思決定ルールの整備に取り組む必要性である。単に枠組みとしての同盟関係が存在するだけでは、自国の安全は全うできない。同盟国間のコミュニケーションを円滑化し、認識の一致や不断の利害調整に努めなければ、相互の間に不信感や猜疑心が芽生え、あるいは対抗勢力がその間隙を突いて同盟の分断を図る恐れもある。現在、日英の間では2+2や事務レベルの協議の場が設けられているが、外務・防衛関係者が相手国に常駐する連絡オフィスや常設協議機関の創設も今後の検討課題であろう。そのような協議のための組織を設置することは、脅威認識の一致を図る上でも重要である。同盟の制度化のレベルが高い程、外的脅威の広範な変化にも拘わらず、同盟は持続することになるのだ。
(4)信頼性の保持
第四の「信頼性の保持」であるが、同盟国間の「信頼性」とは、相手国に対して約束を果し得る物理的な能力または自国の利益を犠牲にしても約束を果たすといった支援意志についての評価で決まることが多い。日露戦争の史訓に即していえば、条約明記の義務にとどまらず、日露戦争に際してイギリスは盟邦日本に対して陰に陽に手を差し伸べた。
例えば、海戦前、日露の軍艦購入競争が行われた際、イギリスはチリ発注の戦艦2隻をロシアが入手しかけたと知るや、直ちに即金でこれを買い取り日本に提供した。またアルゼンチンがイタリアで建造中の戦艦2隻を日本が入手できるよう支援したほか、この2隻(日進、春日)の日本への回航をイギリス自らが担当した。しかも重巡洋艦キングアルフレッドを護衛につかせ、ロシア艦隊を威嚇し回航の安全を確保している。さらにイギリスは、黒海艦隊の東航を阻止し、バルチック艦隊との合流を妨げたほか、極東に向かうバルチック艦隊の各地での入港を妨害、また高性能のカーディフ炭の購入を拒否するなど様々な手段を用いてバルチック艦隊の移動を妨害した。財政面でも支援の意思を示している。日本の戦費の8割近くは公債で賄われたが、アメリカとともにイギリスは外債の引き受け手であった。
新日英“同盟”の運営にあたっても、共同訓練の実施やPKO、海賊対処、南シナ海での監視、武器の共同開発など軍事面での英軍と自衛隊との緊密な協力関係構築は当然のことながら、政府全体、更には民間企業も含めたより幅の広いレベルで日英両国が相互に支援の意思と準備のあることを示す姿勢が肝要であろう。終戦直前、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し、対日参戦に踏み切った。現在でも日本人の対露認識や好感度が低調なのは、この国に対する不信感が未だに払拭されないためである。過去の実践や約束の順守などはその国のナショナル・ブランディングの高低を左右するだけでなく、同盟の維持安定にとっても極めて重要な要素なのである。
(5)イデオロギー的連帯
最後の「イデオロギー的連帯」とは、価値観やアイデンティティの共有により、自国がより大きな政治的な共同体の一部に統合されたと考えた場合、その国は同盟から抜け出ようとは考えなくなり、外的な環境が大きく変化しても国益を再定義しなくなるという指摘である。2017年に発表された「安全保障協力における日英共同宣言」では、日英両国が「自由、民主主義、人権及び法の支配といった基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナー」であることが、冒頭に明記されている。さらに同宣言は、法の支配に基づく国際秩序を維持する重要性を強調し、「力や強制により緊張を高めようとし、あるいは現状を変更しようとする如何なる一方的な行動にも強く反対する」ことをうたっており、日英、日米の海洋同盟が普遍的な価値を擁護し、その守護神役を引き受ける共同体であることを互いに認識しあうことは、同盟の存続を図る上で大きな意義を持っているのだ。
6.グローバルな海洋同盟の誕生:SLOC Pentagon
フェーズ1:日米安全保障体制と米英同盟
現在、枠組みの整備が進められている新日英“同盟”が完成すれば、日米にイギリスを加えた日米英の連携により、グローバルかつパワーバランスが最も安定的なトライアングルな海洋同盟が誕生する。また新日英同盟と、既に整備が進む太平洋・インド洋に位置する海洋諸国間の同盟との連携協力体制も整えば、ここに世界の三大洋を包含する史上初となる海洋同盟のグローバル化が実現することになる。
この地球規模の海洋同盟は、5つのフェーズからなる重層的なメカニズムを形作るものである。即ち、グローバル海洋同盟の礎石となる第一フェーズは、太平洋地域においては、日本生存のための基軸同盟である日米安全保障体制が、大西洋地域にあっては、特別関係(Special relationship)と称される米英同盟がこれに当たる。太平洋・大西洋の両洋における安全保障メカニズムにとって最も重要な枠組みである。
フェーズ2:日米韓三国の連携と協力
第二フェーズは、太平洋地域においては、朝鮮半島南部に位置し、海洋勢力と大陸勢力のまさに接点を構成する半島海洋勢力の韓国を日米同盟に加えて日米韓三国の連携と協力の枠組みである。
フェーズ3:ハブスポーク型からネットワーク型の同盟網へ
第三フェーズは、アジア太平洋地域安定化のための同盟であり、これまでのアメリカと西太平洋に所在する諸国との二国間の安保枠組みを、ヨーロッパのような複層的な構造に発展昇華させることで生まれる海洋同盟であり、ハブスポーク型からネットワーク型の同盟網へと作り替えていくことで、西太平洋及び東アジア地域の海洋の安全と航海の自由の確保をめざすものである。これは日米安保体制及び日米韓の戦略的連携を核としつつ、日米韓それぞれが台湾やASEAN諸国、オーストラリア、ニュージーランド、さらに南太平洋諸島国家との二国間及び多国間の関係を深めることによって、これまでの硬直的なハブから柔軟で弾力性の高い(resilient)メッシュ構造の海洋同盟を構築しようとするもので、ASEAN+3やARF、2+2などの場を活用して、鋭意その構築に向けた動きが進められている。大西洋地域にあって、太平洋地域におけるこの第二、第三のフェーズに相当する安全保障上の枠組みが、北大西洋条約機構(NATO)である。
フェーズ4:太平洋・インド洋海洋国家連合
これら三つのフェーズに加えて、近年その整備が急がれているのが、太平洋域内諸国間の同盟にインドやスリランカなどインド洋周辺諸国を加えた太平洋・インド洋にまたがる海洋国家連合である。これは、西太平洋を南北に連ねる海洋同盟にインド洋~南シナ海~南太平洋と東西に延びる海洋国家の連携を図ろうとするもので、安倍政権が提唱し、アメリカのトランプ政権がその実現を強く支持、参加している「自由で開かれたインドアジア太平洋戦略」や、当研究所が提言しているアンカー型の広域海洋同盟構想を受けたものである(2017年度IPP政策提言「環太平洋文明の繁栄確保の枠組み」参照)。
とくにインド・太平洋地域は、英連邦諸国が多く、英国はオーストラリア、マレーシア、シンガポール、ニュージーランドと「5カ国防衛取極(FPDA)」という安全保障関係を結んでいるほか、一部の英連邦諸国とも個別に安全保障関係を結んでいる。
そこで日本としては、そうした英連邦諸国とのネットワークとともに米国、アセアン、インド、オーストラリアなどとの協力関係を強化しながら、「インド太平洋戦略」をさらに具体化し強化していくことに繋がる。とくにオーストラリアは、10年以上も前から日本とは「准同盟関係」にあるので、この地域の重要なパートナーとなっている。
その意味で、日本と英国の関係強化とは、二国関係に狭く捉える必要はなく、むしろインド太平洋地域の英連邦諸国(オーストラリア、ニュージーランド、インド、マレーシアなど)のネットワークも活用するものとして認識しておくことが重要である。
フェーズ5:新日英“同盟”によりグローバルな海洋同盟構築へ
今般、新日英“同盟”の体制が構築整備され、こうした1~4の海洋国家間の連携が更に大西洋地域にまで延伸拡大されることによって、五つのフェーズからなる重層的な“自由と発展、安全保障のための世界的枠組み”が完成する。この地球規模の海洋同盟の存在によって自由民主主義陣営は、攻勢的覇権的な姿勢を強めている中国やロシアといった大陸国家に全方位全周的に対抗することが可能となる。要すれば、新日英“同盟”の誕生は、地球規模の海洋同盟構築の総仕上げの役割を担っているのであり、如何にこの同盟が重要であるかが理解できるであろう。
図-3が示すように、日米英三国主導の下、他の海洋諸国を包含した世界規模の海洋同盟は、5角形の姿を呈することになる。機能的にも5段階でかつその形態も五角形であることから、制海やシーレーン(Sea Line Of Communication: SLOC)を地球規模で確保するこの海洋同盟は、SLOC Pentagonと呼ぶことができよう。SLOC Pentagonは国際安全保障実現のための海洋同盟であり、自由貿易維持発展のための海洋同盟でもある。また大規模な地震や津波などの自然災害への対処や救援復興、海賊行為の取り締まり、さらに海洋汚染の防止等海洋環境の確保にも寄与することが期待される。
7.海洋国家日本の使命と責務
(1)日本よ、海洋国家イギリスの後継者たれ
大航海時代の到来によって幕が開いた近世・近代の歴史は、ヨーロッパ大西洋地域がその中心地であった。しかし、世界の中心はいまやヨーロッパ大西洋からアジア太平洋へと移動した。そのため、ランドパワーの攻勢を阻止するには、アジア太平洋地域に所在する海洋国家が、かつての米英の役割を担う必要がある。大西洋・太平洋の両洋に面するアメリカは、引き続き海洋の自由や自由貿易体制の維持など自由世界の守護神であり続けているが、対テロ戦争に疲弊したことなどから、その力には陰りが出始めているとの指摘もなされている。
アメリカ一国のシーパワーだけでランドパワーに対峙することが難しくなりつつあるとすれば、アメリカのシーパワーを補完するパートナーの存在が不可欠となる。そのため、アメリカと協力し、アメリカのシーパワーを補うべく、東アジア、さらにはインド洋に所在する海洋諸国家間の連携(coalition)、即ち海洋同盟の構築が急がれているが、その中核を担うのは日本を置いてほかにはない。
大西洋地域においてアメリカとイギリスは特別な関係(special relationship)を保ち、世界秩序の維持安寧に取り組んできた。その枠組みを、21世紀には太平洋地域において日本とアメリカが築かねばならない。つまり日米同盟には、かつての米英同盟の役割を果たすことが求められているのだ。言い換えれば、アメリカの協力者である日本がこれまでイギリスが担ってきた世界秩序維持の任務を背負うということであり、日本が海洋国家イギリスの後継者たらねばならないということである。
(2)日本がイギリスから学ぶべき三つの「K」
海洋大国へ脱皮するための知恵とノウハウをイギリスから学べ
いうまでもなく日本とイギリスはともに島国であり、海洋を通しての交易を国家発展の基盤とする海洋国家である。ユーラシア大陸の両端に位置し、地政面での類似性も高い。また両国は歴史的にロシアや中国という大陸国家を脅威としてきた点でも共通している。さらに、日本もイギリスも議院内閣制度を基礎とする成熟した民主主義国家であるだけでなく、ともに王室・皇室を抱く立憲君主国家としての長い歴史を誇っている。先に見たように、明治~大正期には日英同盟を軸に強い連携関係を維持してきた。そのうえ、礼儀正しさや、武士道(騎士道)の精神、他人のプライバシーを尊重する姿勢や人見知りするシャイな性格など日本とイギリスには、文化や政治システム、歴史、国民性など海洋国家としての地政的類似性にとどまらない多くの共通項が存在している。
かように、様々な面でイギリスと相似た日本は、イギリスの後継者となり得る潜在的な条件は十分に満たしているといえよう。ただ、日本にはイギリスのように海洋覇権国家として君臨した経験はない。そのため、日本がイギリスと同様にアメリカから頼られる真の海洋パートナー、世界国家として成長していくうえで、近年の日英接近はまさに絶好の機会といえる。日英新同盟の枠組みを通して、日本が海洋大国へと脱皮するために必要な知恵やノウハウをイギリスから吸収できるからである。1世紀の時を経て再びわが国の同盟国となったイギリスから日本が学ぶもの、学び取るべきものは多いが、ここでは長きにわたり海洋帝国として世界をリードしてきたイギリスの伝統や国柄に焦点をあわせ、幾つか重要な項目を指摘したい。
「海洋性に対する認識と自覚」
日本がイギリスの後継役を果たすにあたって、まず学ぶべきは、イギリス人の気質や国民性に関わるものだ。それは、三つのKで纏めることができる。一番目のKは「海洋性に対する認識と自覚」である。日本もイギリスも島国であり、海洋を通して発展の途が開かれているが、イギリスの方が、日本よりも自らの海洋国家としての特性を明確に意識してきた。そして、冒険的精神を発揮し勇躍大海原に乗り出すとともに、海外との交易、シーパワーの強化を国策の主軸に据えてきた。それが3世紀にも及ぶパクス・ブリタニカの時代を築き上げる原動力となったのである。
他方、日本の場合は、古代~飛鳥、室町~江戸初期、明治時代と海洋性を前面に打ち出し海外に雄飛する時期もあり、かつその時代に繁栄を遂げたが、いつしか閉鎖孤立の環境に舞い戻り、鎖国的な国柄に陥ってしまう傾向が強い。日本は海洋国家の資質を備えながら、その実態は沿岸国家に甘んじてきた。外国との交易を通して繁栄の途を探らねばならない日本ならば、イギリスが打ち立てた航海自由と自由貿易の大原則を我が哲理と認識し、いまいちど海洋国家としての途に舵を取らねばなるまい。
「開放性」
二つ目のKは「開放性」である。イギリスは古くから自由を愛する国である(10)。権威や権力に対する国民自由尊重の国柄がマグナカルタや世界初の身分議会の誕生、さらに他国に先駆けて市民革命の先鞭を切る国へと導いていった。自由を重視する国是は、外にも内にも開かれた国風を生み出した。イギリスには今日でも世界中から多くの留学生が学びに来る。研究者も同様であり、企業家や資本家の多くもイギリスをその活動拠点としている。外国の人々が皆イギリスを目指すのは、この国が世界に開かれた国家である証左にほかならない。ともすれば日本人は、自分たちだけのミクロコスモスを形成し、日本人には住みよいが、外国人にとって馴染みにくいコミュニティを作り上げてしまう。世界国家を目指すならば、日本も開かれた国となるべく、コスモポリタンの意識を持つ必要がある。必要ならば海外からも優秀な人材を積極的に受け入れ、また自らも海外へと巣立ち、国境を越えた交流を深化させる必要がある。
「経験主義と持続性の尊重」
そしてイギリス国民の伝統である「経験主義や継続性の尊重」が、学ぶべき三番目のKである。現実主義や実際性の重視と言い換えても良い。日本人もイギリス人と同様、実利性に富む民族だが、歴史の重要性に対する認識が浅い。イギリスの現実主義は中庸を重んじる意識でもあり、自らの過去を全否定するような浅薄愚劣な行為には走らない。現実的であることは、歴史の継続や過去との一体性の上に現在を生きることであり、それが近視眼に陥らず、長期的な視点で物事を見る力を養うことに繋がるのである。長い歴史を誇るにも拘わらず、日本は幕末、先の大戦と幾度か目先の難局を切り抜けるため自らの手で自らの過去を捨て去ってきた。過去との断絶を容認するに留まらず、積極的に自身の過去を否定、打ち消し、罪悪視してそれを封印さえした。この姿勢が、国家民族の歩みに大きな跛行を引き起こし、価値観の混乱や民族アイデンティティの崩壊を招いている。
現在は、過去の蓄積の上に成り立っている。新しいものに臆病になる必要はないが、継続や伝統を踏まえたうえでの新規性の受容がその国らしさを生み出し、そこから他の国や他の民族には見られぬ独創性も宿るのである。継続性を尊ぶ国民性から、イギリスでは歴史教育が非常に重視されている。近代日本の官僚制はドイツに範をとり法学教育を重視したが、オックスフォードやケンブリッジ大学では歴史教育を尊び、将来のエリートに対して戦略的な史眼を養う教育を施している。それゆえ高級官僚には歴史に精通した人材が多い。過去の失敗から未来を生き抜く叡知を歴史から学ぶ訓練を受けているからである。
(3)日本がイギリスから学ぶべき政治大国としての「叡知」
政治・外交のシステムと術
いまひとつ、日本がイギリスから学び取る必要があるのは、政治大国としての叡知に関わるものだ。その第一は政治・外交のシステムや術にある。古くは議院内閣制、最近も影の内閣やマニフェスト等日本はこの国に民主政の範を求めてきた。イギリスには、安易な民主主義礼賛ではなく、君主制や寡頭制も抱き合わせた混合政の発想を重視する伝統がある。大衆民主主義は、ともすればポピュリズムや大衆迎合に陥る危険性を内包している。権威と権力を分立させたイギリスの立憲君主制度が政治に安定をもたらしてきた事実を、日本人はいま一度知るべきであろう。
外交分野でも吸収すべき事柄は多い。例えばイギリスが巧みに操る交渉・駆け引きの技である。バンドワゴン一点張りではなく、国益実現のためには敵対国にも接近し、あるいは他国の力を巧みに取り込む能力にイギリスが秀でているのは、均衡やバランスの視点から力を眺めるからだ。国際関係が複層多重化している現在、力に対するこの国の柔軟な発想を学び取らねばならない。
情報を重視するイギリスの姿勢
政治的叡知の二つ目は、情報を非常に重視するイギリスの姿勢である。限られた国力のなかで最大限の外交成果をあげるには、相手の周辺を嗅ぎ回るのは姑息で潔くないとの日本人独特の美学は捨て去り、情報の収集・分析、活用の体制を構築しなければならない。先進国の中で未だにわが国だけは本格的な情報組織を持ち合わせていない。新日英“同盟”は情報大国への脱皮を促す好機である。日英の情報交換ルートを活用し、イギリスの例に倣い、諜報活動も含め、戦略レベルの情報の収集と分析が行える情報組織を国家の中枢に設けるべきである。
国家指導者(政治家)の育成・教育
第三は、国家指導者(政治家)の育成、つまり教育である。戦後の日本で優秀な政治家が生まれないのは、一億中流意識と形式重視の平等主義が蔓延り、エリートの育成が等閑にされてきたからだ。反対に、イギリスが常に戦争に勝ち続け、衰退の中でも大きな影響力を保持し得ているのは政治家の質が高いからであり、それはエリートの育成が教育の重要な任務となっているためだ。金や閨閥がなくとも政治を志す有為の人材を政界に送り出すシステムを、イギリスは確立させている。
国難を救い得る真のナショナルリーダーには、①エリートとしての自負と責任感(ノブレス・オブリージュ)、②物事に動じない胆力、それに③私利私欲や世俗的な権勢に身を滅ぼすことのない禁欲克己の精神力が備わっていなければならない。ジェントルマン教育を通して、イギリスはそのような才を身につけた人材を生み出してきた。紳士道(ジェントルマンシップ)は中世の騎士道が起源とされるが、我が国にもそれに類した士道の伝統がある。現代に適う新たな士道教育を興し、三要件を兼ね備えた人材の育成に、いまや国家の総力が傾注されねばならない。
終わりに―新日英同盟は世界の平和と発展実現のための要請
イギリスに縁のある個人や企業でつくる日英協会は、桜の木1000本をロンドン中心部のロイヤルパーク(王立公園)等英国各地の公園に植える計画を進めている。日英友好の象徴的な事業として桜を育て、アメリカの首都ワシントン・ポトマック河畔の桜並木のような名所をイギリスにつくる構想だという。
「当地昨今吉野桜の満開、故国の美を凌ぐに足るもの有之候。大和魂また我国の一手独専にあらざるを諷するに似たり」
これは、山本五十六がワシントン駐在武官当時、故郷の恩師に送った絵葉書に添え書きした一節である。ともに世界を代表する海洋国家である日米の友好を、そしてアメリカを決して侮ってはならないことを、山本は繰り返し説いていた。
しかし、不幸にしてわが国はその後、山本の思いとは反対に、時の勢いに流され、全体主義の大陸国家に幻惑され、同盟国の選択を誤まるという致命的なミスを犯してしまった。その結果、英米を敵とし太平洋を挟んだ大戦争へと突き進み、明治以来営々と築きあげてきた国家を亡ぼしてしまったのである。
我々は二度と同じ失策を繰り返してはならない。日本が同盟を組むべき相手は、ロシアや中国といった抑圧的な体制を取る大陸国家ではなく、自由で開かれた海洋国家である。日本は、自らの海洋国家としての地政的属性を自覚し、他の有力な海洋国家との連携と協力を深化させ、自由や民主主義、人権の尊重など普遍的な価値を擁護するとともに、自由貿易体制の機能する開放的な政治社会体制を維持発展させなければならない。それはただ日本の国益に益するだけでなく、世界の平和と発展を実現するための要請でもあるのだ。
東京の千鳥ヶ淵は、都内でも有数の桜の名所で、毎年春先には花見の行楽客で賑わいを見せている。この地が現在のような桜の名所となったのは1898年のこと、第六代駐日イギリス公使サー・アーネスト・サトウが、現在はイギリス大使館となっている公使館の前に桜を植えたのがその起源とされる。赴任地をこよなく愛したサトウに続き、後年大使館の敷地内にも多くの桜が植えられた。さらにその桜が東京市に寄贈されたことから千鳥ヶ淵での桜の植樹が盛んになり、公園として整備されるに至ったのである。1998年にはイギリス大使館前の正門前に、サトウの桜植樹100周年を祝す記念碑が建てられた。
さあ、今度は日本がイギリスに桜を植樹する番だ。ポトマックと同様、毎春ロンドンのハイドパークにも日本の国花である桜が咲き薫り、イギリスの新たな名所となる頃、日米にイギリスを加えた壮大な海洋同盟は、太平洋からインド洋、さらには大西洋地域をも包含し、まさに地球規模で自由と民主主義・そして平和を担う世界同盟へと発展しているであろう。
<参照:地政学の誕生>
「世界史は陸の国に対する海の国の戦い、海の国に対する陸の国の戦いの歴史」であり、巨大な鯨リバイアサンと、同じく強大な陸の野獣ビヒモス(『ヨブ記』40~41章)の戦いである。」
これはドイツの政治学者カール・シュミットの言葉だが、パワーを巡る世界規模の闘争を大陸国家と海洋国家の対立の視点から捉えるのが「地政学(Geopolitics)」である。地政学の名が歴史に登場したのは20世紀初頭のことであるが、「国家の政策はその地理によって決まる」(ナポレオン)という言葉があるように、地理と国家発展の関係は古くから考察の対象とされ、紀元前5世紀、ヒポクラテスの『空間、水利、立地概論』の中に既にその萌芽が見られる。ヘロドトスは『歴史』において、アリストテレスも『政治学』第7篇で、それぞれ気候と政治的自由の関係について語っており、アリストテレスの理論を受け継いでモンテスキューは地理、気候と国政の関係を論じている。
そして19世紀後半、政治的統一を成し遂げたドイツでは、愛国主義や膨脹気運の盛り上がりを背景に、政治地理に対する関心が高まり、その中で政治学と地理学を合体させて生み出されたのが地政学であった。最初に「地政学」という言葉を用いたのは、1901年に『レーベンスラウムとしての国家』を著したスウェーデンの地理学者ルドルフ・チェレンとされる。イギリスでも、1904年にハルフォード・マッキンダーが「歴史の地理的回転軸」という論文を発表し、これが契機となって以後、種々の理論が提唱され、地政学というタームは広く人口に膾炙するところとなった。上からの近代化と富国強兵政策によって力をつけたドイツやロシアといった大陸国家が、当時世界を支配していた海洋国家イギリスの覇権に公然と挑むようになってきた。しかも産業革命による軍事技術の発達や動員兵力の拡大に伴い、両勢力の争いはかってない激しさとグローバル化の様相を見せていた。こうした時代背景の中で、地理的要因の政治に与える影響を重要視する地政学への関心が高まったのである。
その後、後述するように、ナチスが自らの勢力拡張を正当化するための道具として地政学を用いたことから、第二次世界大戦後、地政学は学問の世界から追いやられ、わが国でもこれを頭ごなしに否定する風潮が一般的となった。現実主義の国際政治学理論を体系化したハンス・モーゲンソーは地政学を、「地理が国家の力を、したがって国家の運命を決定する絶対的要因と見做すえせ科学であり、机上の政治的空論」としてその学問性を否定した。確かに地理という単一の要因に圧倒的比重を置き、しかも決定論あるいは運命論的に覇権の遷移を断定する姿勢には問題がある。モンテスキューは「アッティカの不毛な土地が、アテネの民主政治を生み、ラケダイモンの肥沃な土地が、スパルタの貴族政治を育てた」と述べ、環境こそが文化を規定するという環境決定論を唱えたが、文化や社会は受動的に環境に従属するばかりではなく、能動的に環境に対応するものである。同じ地理的環境の下にあっても時間的な経過の差異によってその文化や社会構造は異なるし、逆に環境は違っても類似の文化社会が生成する例も多い。
しかしながらその一方で、モデルスキーが説いているように「近世における覇権国家は、全て制海権の獲得に成功したシーパワー国家であ」り、1500年以降の世界史が海洋国家の大陸国家に対する優位で推移したこと、そして「覇権国家の交代は、シーパワーに係るパワーバランスの推移と連動している」ことは紛れもない史実である。大陸国家ソ連に対する海洋国家アメリカの勝利で幕を閉じた冷戦も、海洋国家対大陸国家の闘争という史的パラダイムの延長上で捉えることができる。地理的要因の影響力を絶対視する発想は慎むべきだが、地理的環境と国家の属性・親和性や、地政環境が国家の発展を加速させあるいは逆に障害ともなってきた現実を軽視すべきではなく、国家戦略や外交政策の在り方、同盟国の選択などに際して、地政的なファクターは十分に考慮されねばならないのである。
●注釈
(1)ストックホルム国際平和研究所の発表によれば、2017年の世界の軍事費は前年比1.1%増の1兆7390億ドルで、1人あたり230ドル(約2万5千円)。これは2011年の1689億ドルを上回り、1989年の冷戦終結後で最高となった。軍事費世界1位のアメリカが6100億ドルで前年比14%の減となったのに対し、2位の中国は推定2380億ドルと2倍強に増えている。
(2)「アメリカとの特別な関係は、我が国の安全保障にとって最も重要であ(り)・・・我が国は、EU加盟国、それに日本のような地球規模の同盟国と緊密な関係を保持している。」
HM Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom, November 2015, p.14.
(3)アルフレッド.T.マハン『海上権力史論』北村謙一訳(原書房、1982年)及び『マハン海上権力論集』麻田貞雄編訳(講談社、2010年)23~4頁。
(4)ホールフォード・J・マッキンダー『デモクラシーの理想と現実』曽村保信訳(原書房、1985年)177頁。
(5)ニコラス・スパイクマン『平和の地政学:アメリカ世界戦略の原点』奥山真司訳(芙蓉書房出版、2008年)97ー104頁。
(6) Z.ブレジンスキー『ゲームプラン』鈴木康雄役(サイマル出版会、1988年)15頁。
(7) Ray S.Cline,World Power Trends and U.S.Foreign Policy for the 1980s(Boulder,Westview Press,1980), p.181, Colin S. Gray,The Geopolitics of Super Power(Kentucky, The Univ. Press of Kentucky, 1988), p.193.
(8)「アメリカがイギリスを強要して日英同盟を破棄させたことは、アメリカの対日政策にとって果たして成功であったかどうかということである。・・・・当時の情勢からみて実際のところ、アメリカに対する日英の攻撃などということはおよそ考えられないことであって、それを信じるとすればそれは時勢をわきまえない非常識というべきものであり、また何か含むところがっての言動としか思われないからである。・・・・・もしも日英同盟が更に長く存在していたならば、日本においては官僚と海軍との強い力によって陸軍に対して十分なチェック体制を取ることができたであろうし、・・・独伊枢軸と一体化しようとする陸軍の冒険に対して強いブレーキをかけることができたに違いない。・・・・当時においては日英の合同勢力を離間して、確かにその成功を収めたといい得るであろうが、しかしこれを今日から見るならば決して成功とはいいがたい」黒羽茂『日英同盟の軌跡(下)』(文化書房博文社、1987年)136~8頁。
(9) Stephen M. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survival, Vol. 39, No.1 (Spring 1997), pp.156-179.
(10)「英吉利(イギリス)という国は大変自由を尊ぶ国であります。それほど自由を愛する国でありながら、また英吉利ほど秩序の調った国はありません。実をいうと私は英吉利を好かないのです。嫌いではあるが事実だから仕方なしに申し上げます。あれほど自由でそうしてあれほど秩序の行き届いた国は恐らく世界中にないでしょう。日本などは到底比較にもなりません。しかし彼らはただ自由なのではありません。自分の自由を愛するとともに他(ひと)の自由を尊敬するように、子供の時分から社会的教育をちゃんと受けているのです。だから彼らの自由の背後にはきっと義務という観念が伴っています。」三好行雄編『漱石文明論集』(岩波書店、1986年)127頁。
●参考文献
アントニー・ベスト『大英帝国の親日派』武田知己訳(中央公論新社、2015年)
ウォルター・ラッセル・ミード『神と黄金:イギリス、アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか』寺下滝郎訳(青灯社、2014年)
内山正熊『現代日本外交史論』(慶應通信、1971年)
H.J.マッキンダー『マッキンダーの地政学:デモクラシーの理想と現実』曽村保信(原書房、2008年)
河野収『地政学入門』(原書房、1981年)
鹿島平和研究所編『日本外交史6第一回日英同盟とその前後』(鹿島研究所出版会、1970年)
鹿島平和研究所編『日本外交史8第二回日英同盟とその時代』(鹿島研究所出版会、1970年)
鹿島平和研究所編『日本外交史9第三回日英同盟とその時代』(鹿島研究所出版会、1970年)
加瀬英明『イギリス 衰亡しない伝統国家』(講談社、2000年)
黒野耐『大日本帝国の生存戦略』(講談社、2004年)
黒羽茂『日英同盟の軌跡(上・下)』(文化書房博文社、1987年)
関栄次『日英同盟:日本外交の栄光と凋落』(学習研究社、 2003年)
曽村保信『地政学入門 改版』(中央公論新社、2017年)
藤井信行『「日英同盟」協約交渉とイギリス外交政策 』(春風社、2006年)
ニコラス・スパイクマン『スパイクマン地政学「世界政治と米国の戦略」』(芙蓉書房出版、2017年)
ニコラス・スパイクマン『平和の地政学:アメリカ世界戦略の原点』奥山真司訳(芙蓉書房出版、2008年)
平間洋一『日英同盟』(PHP研究所、2000年)
平間洋一『日英同盟』(KADOKAWA、2015年)
細谷千博・イアン・ニッシュ監修『日英交流史1600~2000 1~5』(東京大学出版会、2000~01年)
マリー・コンティヘルム『イギリスと日本』岩瀬孝雄訳(サイマル出版会、1989年)
宮永孝『日本とイギリス 日英交流の400年』(山川出版社、2000年)
宮原靖郁「日本はなぜ日英同盟を持続させたのか : 国際政治学の仮説を援用して」『戦史研究年報14号』(防衛研究所、2014年3月)
●関連研究会
君塚直隆「立憲君主制の国際比較―象徴天皇制のあり方と今後の日英関係」2018年5月17日
平間洋一「日英同盟再考―近現代史からの遺訓を求めて」2018年5月30日小谷賢「英国に学ぶ日本のインテリジェンス」2018年6月13日
秋元千明「多層な安全保障協力の構築と『新日英同盟』―今後の日本の外交防衛政策」2018年7月13日