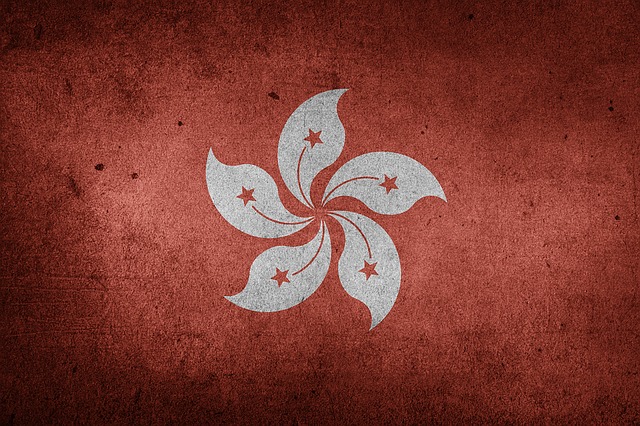1.中国研究の陥穽と必要な視点
我が国の中国研究の多くは、これまでは文献研究が中心で、「(生身の)中国人とは何か」にまで至らずにいたように思う。そのことが、日中間の長い交渉の歴史を見ても中国(人)の振る舞いの狙いを捉えられず、的確に交渉し対応することができなかった、主たる原因ではないかと感じる。
中国は、人口で日本の約12倍、国土面積で日本の約27倍もある大きな国だ。単純化していえば、中国人1人に対して日本人10数人が一致して立ち向かって行くような気概がないと、本当はうまくやっていけないのではないかと、最近痛感している。圧倒的な人口比を前にしては、小手先の議論は、それが精緻であるほどに実効性は期待できそうにない。
米国初代大統領ジョージ・ワシントン(在位1789-97年)が辞任する際辞に述べた「訣別の辞」の中に、次のような一節がある。
「国家政策を実施するにあたってもっとも大切なことは、ある特定の国々に対して永久的な根深い反感をいだき、他の国々に対しては熱烈な愛着を感ずるようなことが、あってはならないということである。(中略)他国に対して、常習的に好悪の感情をいだく国は、多少なりとも、すでにその相手国の奴隷となっているのである。これは、その国が他国に対していだく好悪の感情のとりこになることであって、この好悪の感情は、好悪二つのうち、そのいずれもが自国の義務と利益を見失わせるにじゅうぶんであり、(中略)好意をいだく国に対して同情を持つことによって、実際には、自国とその相手国との間には、なんらの共通利害が存在しないのに、あたかも存在するかのように考えがちになる。一方、他の国に対しては憎悪の感情を深め、そこにはじゅうぶんな動機も正当性もないのに、自国をかりたて、常日ごろから敬意をいだいている国との闘争にさそいこむことになる・・・(以下略)」
下線部分にあるように、好悪の感情で相手国を見ると、すでに(その時点で)その国の奴隷になっているというのである。これは韓国との関係にも当てはまると思う。中国の将来はダメだとか、偉大な国だとかといった好きとか嫌いとか言った価値判断を前提にした議論をしがちなのは、われわれがあまりにも中国という国に捉われ過ぎている証左ではないかと思う。
また、日本で中国を論じる場合、(日中という)二国関係を前提にすることが多い。一方、中国の立場は、多国関係の中の一つとしての日中関係というスタンスだ。その違いのゆえに、日本人の対中国観には目に見えない「バイアス」がかかってしまっている。そのバイアスを取り除いて、つまり客観的に中国を見ることの必要性を強調したい。
ここで、興味深い言葉を紹介しよう。アウンサン・スーチーの熱烈な支持者であるベネディクト・ロジャーズの著書に『ビルマの独裁者 タンシュエ-知られざる軍事政権の全貌』(白水社、2011年)がある。当時、熱烈で盲目的な親中派として欧米からは蛇蝎の如くに批判されていたタンシュエの発言として、ロジャーズは同書で紹介している。そのうちのいくつかを挙げておくと、
「中国との関係は保身のため以外の何ものでもない」
「永遠の敵とか、永遠の友人とかいうものは存在しない」
「中国が好きだから仲良くしているのではない」
いま振り返ってみるなら欧米の経済制裁を前にしたミャンマーが生き残るためには、中国を頼るしかなかったということだろう。好意的に表現するなら背に腹は代えられぬ、である。いま欧米諸国は、ロヒンギャ問題に“民主的対応”を見せないアウンサン・スーチーに苛立ち責める。だが、いまや彼女は一国の指導者なのだ。ならば現在の彼女に、ここに挙げたタンシュエの発言を語らせるようなことがあってはならない。
一帯一路を推し進める習近平政権にとって、ミャンマーは地政学的に必要不可欠だ。であればこそ彼女を自らの側に傾斜させる意味からも、欧米諸国による彼女への批判は“歓迎”すべきことだろう。
単に表面的な言動に基づいて批評する前に、その国がどのような状況に置かれているのか。その国と日本との関係はどうなのかという点を、好悪や善悪などの感情的な価値判断を抜きにして、冷静かつ客観的に分析すべきである。
2.一帯一路前史
私はかつて1983~85年と88~92年の間、駐タイ日本大使館で外務省専門調査員として仕事をしたことがあった。私は本来の任務であったタイの内政分析の傍ら華人・華僑研究を進めたが、その際、冷戦が終わったにもかかわらず華僑・華人分析の多くが冷戦時代の視点から一歩も抜け出ていなかったことを特に奇異に感じたのである。そこでタイで発刊されていたほとんどの華字紙(新聞)を毎日読んで分析してみた。当時、「華字紙はメディアとしては不適。読む価値もない」というのが一般的な評価だった。だが、じつは生きた現地情報の宝庫だったのである。つまり華字紙は「華人社会の生きた動向録」だった。
死亡追悼広告を例にとると、80年代にはタイ国内の親戚縁者や関係者向けだったものが、80年代末から90年代になると、中国大陸、台湾、香港、米国、欧州の親戚までが追悼広告を出すようになった。つまり対外閉鎖から開放へという中国の変化を背景に、華人の活動範囲はタイの国境をいとも簡単に超えてしまい、地球規模で拡大していたのである。
本題に戻るが、タイの雲南省出身華人を束ねる雲南同郷会を多くの雲南人が訪問している記事を、華字紙が頻繁に伝えていた。当時、バンコクの雲南会館のトップと親しくしていたことから彼の許を頻繁に訪れていたが、彼の家でバンコクの華人とは思えない一群の雲南人を紹介されたことがある。雲南省政府の対外交渉担当者で、陸路バンコク入りしたとのことだった。
彼らとの会話から、中国を見る際に、これまでのように海路や空路からだけでは実態は捉え難いと気付かされたのだ。つまり中国と東南アジア大陸部とは陸続きであればこそ、陸路も視野に入れ中国と華人社会――さらに言うなら華人社会を通じた中国とアセアン諸国との関係を捉えることが肝要である、ということだ。じつは中国西南部の4省と東南アジア大陸部の北部一帯は、東はベトナム中央高原から西はインド東北部まで続いている標高300メートル以上で250万平方キロ余の広大な緑の丘陵地帯の一角を形成しているのである。
J・C・スコット(イェール大学教授)が新名称「ZOMIA」(『ゾミア 脱国家の世界史』みすず書房 2013年)と呼ぶこの一帯を中国が大改造しようと構想したのは、今から30年前の天安門事件前後だった。以来、この試みは営々と続いている。もちろん自国の都合からではあるが。
(1)中国・西南開発構想
1990年代初頭、中国では遅れた西南地域(雲南、四川、貴州)をどう開発すべきかとの議論が持ち上がった。その中で西南地域は長江を経由して上海地域と繋がっている点を考慮して、西南地域の原材料を上海地域に輸送して開発につなげるというアイディアが出されたが、最終的に「西南開発構想」としてまとめられた。これには鄧小平など当時の中央政府幹部も全員賛意を示している。
西南開発構想とは雲南省を軸に中国西南地域を東南アジアと結ぶというものだが、実は中華人民共和国成立以前から、漢民族は中国西南地域を経由して恒常的に東南アジアなど熱帯地域に向って移動(南下)していた。「漢族の熱帯への進軍」と呼ばれる民族大移動である。こうした歴史的経緯を考えると、西南開発構想とは漢民族に生得的に備わった民族的性向への復帰を意味しているようだ。
この構想を含めた広範な議論の中に、「欧亜大陸橋構想」があった。これは西南地域を東南アジアと連結させ、最終的にはシンガポールからロンドンまでを鉄道路線網で連結していこうという壮大な計画だった。これこそ一帯一路構想の原型だろう。
一般に一帯一路構想は、習近平国家主席が政権を握った後に発表された構想だと考えられている。だが、西南開発構想から欧亜大陸橋構想へと進む経緯を考えるなら、習近平政権登場の遥か以前に一帯一路構想の原型があり、そこから出発し構想を着々と現実化させながら現在に至っていることが判るのだ。以上の経緯を、次に挙げる資料をもとに説明したい。
(2)西南開発構想の基本設計
1993年にバンコクから飛行機で昆明に行った折、昆明の空港でたまたま「大西南対外通道図」(雲南省交通庁航務処製、作:昆明市測絵管理処製図印刷、1993年)という地図を買った。雲南省政府と昆明市が共同で作成し、「部外秘」の3文字が印刷されていた。
この地図の興味深い点は、東南アジアの大陸部改造計画を示していることである。例えば、昆明からハノイ経由でハイフォン(ベトナム北部の港湾都市)まで在来線を使って鉄道を敷く。この路線は南方に延伸され、インドシナ半島を南に一周してバンコクに至る。次は昆明から南下しラオスとの国境を越えてビエンチャンに入り、タイのバンコクに至るルートだ。残る1本は、ミャンマー国境の瑞麗を通り、マンダレー、ヤンゴンを経由してバンコクに至るルートである。この3ルートの終着点であるバンコクから、マレー半島を南下してシンガポールに向う。
また3本の大きな河川(ホン川:ベトナム、メコン川、サルウィン川:ミャンマー)は、拡幅工事を施して水上運送ルートとして利用する。さらに航空路線が地図には引かれているが、当時はまだ就航していないものであり将来予定ということになる。まさに鉄路、陸路、水路、空路を含めた東南アジア大陸部改造計画図であった。
この地図の裏面には、次のような記載が見られた。これは大西南対外通路図の基本構想ともいうべきもので、昆明を基軸として東南アジアの各地を経由して、外部に向かうルートを描いている。代表的ルートの基本構想を見ると、
■昆明⇒(公路)⇒小橄欖堰⇒(水路:メコン川)⇒チェンセン(清盛)⇒(公路)⇒バンコク
■関係国:ミャンマー西部、ラオス、タイ、マレーシア北部、シンガポール
■建設概要:昆明⇒小橄欖堰の現有公路拡張/南得堰⇒ホワイセイ(会晒)の水路警備・拡張/港湾設備整備
■建設等級:公路は二級、水路は五級航道
■建設期間:公路は5年、水路は3年
■建設資金:公路は17億元、水路は1.67億元
■運送能力:1年当り600万トン
■総距離:公路は1650キロ、水路は429.3キロ
■輸送コスト:1トン当り公路は288・9元、水路は192・8元
「大西南対外通道図」で構想されている別ルートの数例を示すと、
■ルート①昆明⇒(鉄道)⇒小橄欖堰⇒(水路)⇒チェンセン⇒(公路)⇒バンコク
■ルート②昆明⇒(鉄道)⇒河口⇒(水路)⇒ハイフォン⇒(海路)⇒ダーナン(ベトナム中部の港湾都市)
■ルート③昆明⇒(鉄道)⇒盈江⇒(水路:イラワジ川)⇒ヤンゴン⇒(海路)⇒アデン(イエメン)
ここで興味深いのはルート②とルート③だ。前者は仏領インドシナを拠点にフランスが、後者は英領ビルマ(当時)を経由してイギリスが、共に19世紀末から20世紀初頭にかけ雲南省に足場を築き清国を南方から侵そうとしたルートを逆向きに辿る点だろう。このように見ると、「西南通道図」が示す東南アジア大陸部を舞台にした一帯一路構想は、一面では今から1世紀ほど昔のイギリス、ルランス両国による植民地支配の現代版と見做すこともできそうだ。
(3)セルデンの中国地図
17世紀前半の英国の政治家・海洋法学者・歴史家J.セルデン(John Selden、1584~1654年)は、ある中国人船員から1枚の中国地図を受け取る。その地図(横1メートル縦2メール)は、1654年にオックスフォード大学附属ボドリアン図書館に寄贈された。それが「セルデンの中国地図」と呼ばれる南シナ海を中心にした一種の航海図である。
原図を分かりやすく書き換えたのが図1(右)だが、航海ルートを見ると、福建省・泉州から出発してマニラ、ブルネイを経て、バンタム(注:ジャワ島西部の現バンテン)に至る。また地図の中に文字が記載されており、そこにはカリカット(インド南西部の現コージコード)からアデン(イエメン)への航路なども記されている。当時、中国人はアデンを1つの拠点として中東世界と結びついていたことが十分に推測できる。
さらにさかのぼれば、明代の武将・鄭和(1371~1434年)は、東南アジア、インドを経てアフリカ東部まで艦隊を率い「鄭和下西洋(鄭和の西洋下り)」と呼ばれる大航海を数回にわたって実施している。ちなみに中国では鄭和に関する研究書が大量に出され、その5~6年後に、一帯一路構想が発表されている。鄭和研究と一帯一路の一例からも、学術界が政治に密接に関連しているゆえに、中国では学術界の動きが次代の政治の方向性を暗示していることを指摘しておきたい。
3.近代中国の対外開放と中国人
(1)習近平国家主席におけるアメリカのイメージ
習近平国家主席は1953年の生まれであるから、毛沢東主導の下、大躍進政策(1958~61年)が行われていたころは小学校低学年で、文化大革命時代(1966~76年)は中学・高校時代であった。習近平は父親(習仲勲、1913~2002年)が文化大革命時代に政治批判され失脚したために苦労したといわれる。そのころさかんに出されていたポスター(図2)があるが、それは彼の世代の米国に対するイメージを象徴しているように思われる。

ポスターには、日本人、朝鮮人、アフリカ人、ベトナム人、中東のアラブ人、アルバニア人などが描かれている。このポスターが示す時代環境にドップリと漬かっていた習近平世代は、「全世界の人民は団結し、侵略者の米国と一切の走狗を打倒しよう」というイメージで米国をみていたのではないか。つまり習近平国家主席は、日本の戦争中の「鬼畜米英」に相当する雰囲気の中で育ったといえる。若い頃に反米を叫んでいた人が、急に親米的感情に豹変するものだろうか。こうしたイメージの問題も、指導者の政策に少なからず反映しているのではないか。
習近平世代の次の世代(60年代生まれ)は、幼少期に紅小兵(紅衛兵の下の世代の毛沢東擁護のための戦闘的革命組織)として暴れまわったはずだ。70年代生まれは文革末期から対外開放初期の激動時代にかけ幼少期を送っている。
共産党政権トップの任期は2期10年を基本とするだけに、50年代生まれ、60年代生まれ、70年代生まれと10年ごとに違っている政治・社会環境が今後の権力構造や政権の性格・政策・人事などにどのような影響を与えるのか。世代が権力の動向に及ぼす影響を注視しておくべきではないか。
(2)近現代中国における2回の対外開放
私は、近現代において中国は、少なくとも「対外開放」を2回経験したと考えている。1回目がアヘン戦争だが、敗戦の結果として結ばざるを得なかった南京条約(1942年)によって清朝は、英国の軍事力(砲艦)により無理やり世界市場に引きずり出されてしまった。2回目が1978年の鄧小平による対外開放である。このときは中国が自ら進んで世界市場に「闖入」した。現象面から見れば、両者とも同じく閉じていた市場を世界に向けて開放したわけだが、その動機は180度違っていた。
この2回の対外開放の最大の違いは何か。対外開放の結果、米英独仏露日などのプレーヤーが中国という広大な市場をめぐって争奪戦を繰り広げた点は同じだろう。だが、両者の間には大きな違いがある。1978年の対外開放の場合、前回のプレーヤー達に中国共産党という“辣腕プレーヤー”が加わったのだ。そのため、中国以外の力で中国をハンドリングすることが極めて困難になってしまった。自分の理屈・利害を基準に、しかも近代で味わった屈辱を晴らすことを掲げて行動する中国に対し、世界はどのように立ち向かうべきか。いま世界が問われているのは、貿易戦争とか先端情報技術をテコにした世界覇権といったレベルを超え、これからの世界秩序に中国をどのように位置づけるべきかといった世界史的課題であることを痛感する。
さて、鄧小平の対外開放政策については、主として経済面から論じられることが多いが、それだけでは不十分である。いや有態に言うなら、むしろ危険ではないか。とくに対外開放政策によって中国が東南アジアの華人・華僑社会と繋がり、ヒト・モノ・カネのネットワークが有効理に働いている以上、華人・華僑社会を中国と結びつけて――ある面では一体化したものとして考えるべきだ。
日本の東南アジアへの企業の進出の歴史は長いが、現地の企業人と話して痛感する点は、いまでも日本人は東南アジアの人々を下に見ている点である。1970年代から80年代以降、日本が東南アジア諸国に大きな影響力を持つことができたのは、実は中国が毛沢東の考えに従った対外閉鎖していたからではないか。“祖国”が国境を固く閉じていたからこそ、東南アジアの華人・華僑企業家は(中国と連携できず)日本企業に目を向けるしかなかった。ところが中国が1978年に対外開放政策を展開し始めると、彼らの目は日本から中国へと転じるようになった。
華人・華僑にとってのルーツである「中国」とは、われわれが無意識に口にする<中国=中華人民共和国>ではなく、いわば地上には存在しない幻の「中国」なのである。
華人・華僑企業家が中国でビジネスを展開する場合、中国側は「愛国同胞」という基準を持ち出す。ここに華人・華僑ビジネスのカラクリが見られる。中国側が求める「愛国」と、華人・華僑側が打ち出す「愛国」とは異質なのだ。もちろん中国側が掲げる「国」は中華人民共和国だが、華人・華僑側のそれは自らのルーツに繋がる幻の中国である。「愛」と「国」の2文字を共有しながら、その内実は異なる。だが双方に利益となればそれでいい。これが「双嬴(ウィン・ウィン)関係」の実態ではないか。
香港最大の企業集団・長江実業グループの創設者である李嘉誠が「中国市場はもうダメだ。習近平政権は長くない。中国市場から資金を引き上げる」と語ったと伝えられ、これを根拠に中国崩壊論がまことしやかに語られたことがあった。だが、それは、そう語る人の“期待値”が多分に込められた議論というものだろう。
李嘉誠はあくまでもビジネスマンであるから、儲かるところには投資するが、儲からないとなればさっさと資金を引き上げる。事実、彼は香港や中国本土から資金を引き上げはしたものの、香港の地下鉄の巨大プロジェクトには資金を戻して再投資している。さらにマレーシアの港湾建設にも膨大な投資をしている。華人・華僑の企業家たちは、中国の将来がどうだという議論を根拠に経済行動をするのではなく、(短期的なスパンで)中国市場で儲かるかどうかを判断基準としてやっているのである。だから彼らの投資傾向を基準に中国情勢を軽々に語ることは、やはり危険と言わざるを得ない。
4.皮肉に満ちた米中関係
(1)米国の対中観の変化
19世紀以降の米中関係を振り返ってみると、米国人の心の奥には、遅れた中国をなんとかして普通の国にしたいという思いいれがあったように思う。米国の建国の父祖たちは、かつてヨーロッパから北米新大陸に渡ってきたときに、多くのインディアンを犠牲にしたわけだが、そのことに対する「原罪」のような意識が、無意識の世界に潜在しているのではないか。その裏返しとして、先述したような中国に対する思いいれとなって現れているように思えてならない。
中華人民共和国成立から1978年の改革開放前までの中国は、毛沢東思想で固く“武装”され、イデオロギー的獰猛さを誇示し、「打倒米帝国主義!」を声の限りに叫んではみたが、とどのつまり世界的影響力はほとんどなく、友邦国はアルバニアとアフリカの小国のみであった。国際共産主義連帯を掲げて海外に進出しては見たが、文革期に友好関係にあったタンザニアとザンビアの間に鉄道を建設した程度であった。文革末期の1970年代半ばにカンボジアに毛沢東主義原理主義ともいえる“原始共産制国家”を妄想したポル・ポト政権が出現したが、客観状況を無視した時代錯誤の過激さゆえに崩壊している。
毛沢東の時代、中国国内では「日本帝国主義打倒!」と声高に叫ぶデモが繰り返されていたが、あくまでも中国国内のできごとに過ぎなかった。譬えてみれば、巨大な後楽園球場の中で叫んでいるようなものだ。中国に「戸締りをして家族マージャン(盛り上がっているのは自分たち家族だけ)」という俗諺があるが、まさにこのようなものではなかったのか。つまり中国は米国を「張り子のトラ」と揶揄気味に評していたが、じつは「張り子のトラ」は米国ではなく中国自身だったのだ。
だが改革開放後、中国は毛沢東思想の頚木から脱し、グローバル貿易による経済発展に路線を転じ、世界製造業のエンジンとなり、米国が進めたグローバル経済の最大の受益者となった。
華人・華僑にとってこれほどいいことはなかった。昔から中国人は「四海為家(世界中が我が家)」という言葉が物語っているように「グローバリゼーション」を実践しており、機会を求めて海外に移住していった。国家主席時代の江澤民が国民に呼びかけた「走出去(海外に飛び出せ)!」がそれである。彼は指導者として国民に海外移住、いわば民族移動を奨励したわけだ。歴史的に見て、漢族は移動を重ねて生活空間を拡大してきた民族なのである
じつは毛沢東政治は対外閉鎖で国民の海外との接触(もちろん、それまで行われていた海外移住も)を厳禁する一方、戸口制度によって国民の国内移動を禁じた。つまり毛沢東政治が有効理に機能した背景には、国民の国内外への移動厳禁という措置があったということを忘れてはならない。中国には「木は動かすと死ぬが、人は動かすと活き活きする」という格言があるが、まさに毛沢東の時代は「木を動かし、人を動かさない」政治が行われていたわけだ。
鄧小平は、この毛沢東の手法を逆転させた。かくて多くの中国人が合法・非合法にかかわらず中国を「走出去(とびだ)」したのである。敢えて誤解を恐れずに言うなら、現代世界の不安定の要因の1つは中国人の国内外への移動を解禁した鄧小平の“大英断”にあったといえるだろう。
そして中国は、グローバル経済の発展によって得た資力を背景にして、世界覇権(一帯一路構想、南シナ海進出、宇宙開発、月衛星探査など)の獲得に極めて意欲的になっている。その結果、米国にとってかつては「張り子のトラ」でしかなかった中国が「現実的脅威」に変質したのである。
ここで次の言葉を噛み締めておきたい。
「過去50年間、東南アジアにおける安全保障のモノサシとなってきた多くの協定は、中国共産主義者の拡大に対する防波堤として立案されてきた。これまで米国を地域の安全保障の要とみなしてきた東南アジア諸国は、今や北京との関係強化の必要性を主張するようになってきた」(Donald Greenlees、 “ASEAN Hails the Benefits of Friendship with China”、 International Herald Tribune、 Nov. 1、 2006)。
ここに述べられたように、「北京との関係強化の必要性」の温度差はあるにしても、アセアン諸国の中で、現実的には反中親米の国は一つもない。この点を見落とすべきではない。
地図(図略)の色のついた国(ネパール、ブータン、ラオス、カンボジア、ブルネイ、韓国)が親中である。
昨年の春節のブルネイ旅行で宿泊したホテルで出会ったブッフェ・スタイルの朝食時の光景を思い出す。大声で騒々しく食事する一群がいたが、最近訪日するような(マナーのよくなった)中国人ではない。広西チワン族自治区からの旅行団だった。中国内でも最貧に属するこの地域においても、4泊5日の海外旅行を楽しめるほどに豊かになったということだろう。
春節におけるブルネイ旅行という事実は、中国は経済発展によって(北京、上海などの大都市や沿海部だけではなく)こうした貧しい地域の人々までその恩恵が及び生活水準の底上げが進んでいることを意味している。中国のように大きな国は、日本のようなスピードで生活水準が上がることはない。だが、それでも20年、30年をかけて着実に経済発展の恩恵が及び、豊かな生活の裾野は確実に広がっているのだ。
(2)中国の勢力拡大
写真(図3)は5年ほど前に雲南省西南端一帯を旅行した際、ミャンマーのチャオピューから昆明をつなぐパイプラインが敷かれる様子を写したものだ。このルートは、かつて太平洋戦争時に「援蔣ルート」といわれたルートと重なるものであり、天然ガスと石油の2本のパイプラインが敷かれ、延々と続いていたのには驚いた。「援蔣ルート」ならぬ「援習ルート」とでも言うべきか。

次にインド洋を中心とする海洋図(図略)を見て戴きたいが、ここにプロットされたところが現在中国が押さえているといわれる港湾である。それを(東から西に)列挙すれば、パラオ、ブルネイ、ダーウィン、チャオピュー、チッタゴン(バングラデシュ)、ハンバントータ(スリランカ)、モルディブ、グワーダル(パキスタン)、ドゥクム(オマーン)、ジブチ、ハイファ(イスラエル)、トリエステ(イタリア)など。これに対し米軍の基地は、グアム、シンガポール、ディエゴガルシア(インド洋)、バーレーン等に過ぎない。これを見ただけでも、中国の勢力拡大の様子がよくわかると思う。
最近、中国による「債務の罠」ということがよく言われているが、どこの国の指導者もその辺を分からないままそうなっているのではなく、ある程度わきまえながら中国と交渉をしているのではないかと思う。つまり「債務の罠」の存在を知りつつも、中国と契約をせざるを得ない状況にあるというのが、より正確な表現だと思う。「中国に騙されてはいけない」との“忠告”を受け入れさせるだけの力(外交力、軍事力、経済力など)を、はたして我われの側が持ち合わせているのだろうか。
例えば、ドイツは中国と深く結びついている。ドイツが親中のメルケル政権だからそうではなく、じつは歴史的背景――言い換えるなら対中ビジネスに賭けるドイツが長い時間を掛けた“営々たる努力”があるのだ。日清戦争後に四川省に初めて日本人が入ってみると、省都・成都にはドイツ製品があふれんばかりであった。当時から、中国人はドイツ製品に対し安くて頑丈というイメージを抱いていた。そうイメージ付けるために、ドイツ企業は工夫を重ねていたのだ。それが現在にまで繋がっていると思える。このような歴史的視点から掘り起こし、現在のドイツと中国の関係を見直してみる必要がありはしないか。

日中戦争の激戦地であった中国雲南省西南部にある芒市に行ったとき、図4のような看板を数多く見た。「インド洋から最も近い都市」という芒市のキャッチコピーといったところか。日本人の視点に立てば、芒市は中国の西南最深部の都市に過ぎない。だが視点を変えれば「インド洋から最も近い都市」になる。
こういう視点をわれわれ日本人ももつべきではないか。国の辺境とは、これを反対側から見れば他国に最も近い。言い換えるなら辺境は2つの勢力圏・文化圏の真ん中に位置するわけだ。

ミャンマー国境と接する雲南省の瑞麗という都市の国境関門前の広場の一角に、「三龍汇瑞(三匹の龍が瑞麗に集うの意)」、「上海、滇緬、史迪威(上海、雲南省・ミャンマー、スティルウェル)」と記されたカンバン(図5)が置かれていた。つまり上海を起点とする国道320号線、雲南・ミャンマーを繋ぐ道路、スティルウェル(第2次大戦末期、雲南・ミャンマーに展開する日本軍制圧を目的に東インドのレドからミャンマー北部のフーコンを経て昆明を結んだ戦略道路。発案者のスティルウェル将軍に因んでスティルウェル公路と呼ばれる)の3本の道路を3匹の竜に譬え、3本の竜が瑞麗で1つに結び合っている――双頭の竜ならぬ3頭の竜――という意味だ。
ここは国道320号線の終点でもある。片側4車線の道路が一直線に走っている道路だ。やや想像を逞しくするなら、近い将来、陸路によって上海からマンダレーを経由してヤンゴンまで行くことが可能となるだろう。中国人は万里の長城に象徴されるように、費用対効果を度外視してもとんでもない事業をやってしまう民族だから、このようなことも不可能とは言えない。
とはいえ今や中国から自家用車を運転して陸路でタイを訪れ、個人観光を楽しむ時代である。上海からヤンゴンまでの長距離ドライブも、遠い将来の“夢物語”というわけでもなさそうだ。
(3)中国の言論戦と広報戦略
トランプ大統領といえば「アメリカ・ファースト」だが、習近平国家主席の頭には「超英趕美」(英国を超え、米国に追いつく)というスローガンがあると思う。これ自体は、1950年代末に毛沢東が客観情勢を無視して推し進めた急進的社会主義化政策の「大躍進政策」で掲げられたスローガンである。当時、毛沢東は鉄鋼生産に異様なまでに執着しており、世界第2の鉄鋼生産国・英国を追い越し、世界第一の米国に追いつくことをスローガンに掲げたのだった。しかし結果は無残なものだった。習近平国家主席の頭の中には、少年時代に声を限りに叫んだであろう「超英趕美」の4文字が消えることなく刻まれているのではないか。最近話題になっている「中国製造2025」は、「超英趕美」の現代版といえるだろう。
2018年11月にパプアニューギニアの首都ポートモレスビーで開催されたAPEC首脳会議の折、ペンス米副大統領は、「米国は相手国を締め付ける“帯”や一方通行の“路”を押し付けたりはしない」「われわれは相手国を借金漬けにはしない」などと喧嘩腰で(中国に)応じ、7兆円規模(最大600億ドル)のインフラ投資資金の提供を申し出た。
それに対して習近平は、「歴史が示すように、衝突は冷戦、武力による戦争、貿易戦争のいずれの形であっても、そこから勝者は生まれない」「経済・貿易の保護主義政策は世界経済のバランスを崩し、健全な成長の妨げとなる」と言葉巧みに応じた。
ちなみにかつて毛沢東は「銃口から政権が生まれる」といったとされるが、実は彼は腹の中ではペンによって権力を奪取するという言論戦を狙っていた。つまり「槍桿子(テッポウ)」と連携した「筆桿子(ペン)」の戦い、つまり巧妙なメディア戦略は伝統的なものであり、見過ごすことはできない。日本の新聞報道では、この2人の発言に対して、ペンス副大統領の発言にはあまり拍手はなく、習近平の発言には会場から拍手があったとされる。
5.東南アジア諸国の現状
日本では東南アジア諸国について、親中か反中かの二分法で色分けする傾向がみられるが、実態はそう単純ではない。どこの国の指導者も、自国の国益が大事であって、そのために大国である米国や中国を利用しようと考えるはずだ。
ここではタイとマレーシアの状況について簡単に紹介したい。
(1)タイ
タイでは、今年(2019年)3月に総選挙が行われたが、軍政勢力が政権を維持する見通しだ。これまで過去5年間にわたり暫定政権が続いたのはなぜか。この政権の要が、経済担当のソムキット副首相で、「タクシンの知恵袋」といわれ、タクシノミクスといわれる経済政策のほとんどを立案した人物だ。現政権は「タクシン抜きのタクシン政策」とも呼べるような経済政策を推進し、将来的には地域大国化を狙っていると思える。そこで政策達成へ向けての費用対効果から、一帯一路に相乗りしようという思惑が見え隠れする。
東南アジアの鉄道路線には、昆明からビエンチャンを経て、バンコクに至る路線――これを中国は「泛亜鉄路(中線)」と呼ぶ――がある。昆明=ビエンチャン間は現在建設中だ。メコン川を挟んでビエンチャンの対岸に位置するタイ側のノンカイからバンコクまで高速鉄道を走らせるという計画は、2011年に成立したインラック政権でも推進されたが、2014年のクーデタによって政権を掌握したプラユット暫定政権によって一旦は白紙に戻された後に再スタートしている。
中国の立場からすれば昆明からビエンチャンまででは意味がなく、バンコクまで結びたいと考えている。一方、タイとしては将来の経済発展を考えれば是非とも必要な物流幹線だが、可能な限り安価での建設を目指したい。両国にとっては必要不可欠な構想鉄道路線建設をめぐって、マラソン交渉が始まった。互いが互いの手の内や狙い目を知り尽くしているだけに、熾烈な駆け引きが展開されてきた。
2019年4月末に北京で一帯一路国際会議が開かれたが、プラユット暫定首相は経済担当のソムキッド副首相やドーン外相など連れて同会議に参加し、メコン川を渡る鉄道橋建設に関する覚書を中国とラオスとの3カ国間で取り交わした。高速鉄道建設に向けて1歩前進と言ったところだろう。
現在タイが考えている経済開発構想はEEC(東部経済回廊)、SEC(南部経済回廊)であり、これらをリンクさせるインフラ建設だが、地政学的にも一帯一路にリンクさせるのが最も経済効果があろうというものだ。
いまから5年ほど前の太田国交省大臣(当時)の時代に、バンコクとタイ北部のチエンマイを結ぶ高速鉄道の建設について基本合意をしたことがあった。当時、日本では「日本の技術力が評価された結果で、中国に勝った」との論調がみられた。しかしチエンマイの先は行き止まりで、産業らしきものは何もない。仮にバンコクからチエンマイまで莫大な資金を投入して高速鉄道を建設したとして、観光客を呼ぶだけで果たして採算がとれるだろうか。このプロジェクトに異を唱えていたタイの専門家は、同路線の建設資金回収にはす早くて300年、悲観的な見解では600年かかると見ていた。いわば壮大なムダということになる。
またタイのバンコクとカンボジアのプノンペン間の鉄道についても、未開通状態だったアランヤプラテート(タイ)=ポイペト(カンボジア)間が45年ぶりに開通した(2019年4月)。
さらにタイは、中国が進めている広東省・香港・マカオを含む「粤港澳大湾区経済構想」にも結びつけようとしている。この結びつきは、いまから15年ほど前にタイや中国でも議論が重ねられていたが、地政学的な利点などを把握したうえで、この地域を客観的冷静に見ていくとそうならざるを得ない状況にあるように思われる。
いずれにしても、タイとしては地域大国を目指しつつ、中国との一帯一路に相乗りした方が有利だと考えているようだ。
(2)マレーシア
2018年5月に“超親中派”のナジブ政権が倒れ、新たにマハティール政権が誕生した。前政権の放漫財政がもたらした財政危機打開を最優先課題に掲げた同政権は、建設費用が高額過ぎることなどを理由に前政権が中国と結んだ東海岸鉄道建設プロジェクトを凍結した。かくて「一帯一路はマレーシアで頓挫した」などの声も聞かれた。だが、マレーシアが経済発展を進めるためにはインフラの建設・整備は必要不可欠であり、可能なら必要最小限の費用で建設を進めたいところだろう。そこで中国と再交渉を行った結果、2019年4月にマハティール政権は、規模を縮小して建設費も抑えて建設計画の再開を決めたのである。ちなみにマハティール首相も、2019年4月の一帯一路国際会議には出席している。
一帯一路を貫徹させるためにはバンコク発の鉄道を、マレーシアを経由してシンガポールに繋げたい。これが中国側の究極の狙いだろう。一方のマレーシアは将来の経済建設を考え可能な限りの低予算で物流ルートを完成させたい――双方の思惑を交錯させながら、外交交渉は展開されるものだろう。
最後に
宮崎滔天(1871~1922年)が、明治29年(1896年)12月15日の「国民新聞」に「暹羅に於ける支那人」というタイトルで寄稿した文章がある。
「一氣呵成の業は我人民の得意ならんなれども、此熱帯國(注:タイのこと)にて、急がず、噪がず、子ツツリ子ツツリ遣て除ける支那人の氣根には中々及ぶ可からず」。つまり短兵急に物事を考えるべきではないということだ。
また勝海舟(1823~99年)は次のように語ってもいる。
「日本人もあまり戦争に勝つたなどと威張つて居ると、後で大変な目にあふヨ。剣や鉄砲の戦争には勝つても、経済上の戦争に負けると、国は仕方がなくなるヨ。そして、この経済上の戦争にかけては、日本人は、とても支那人には及ばないだらうと思ふと、おれはひそかに心配するヨ」(『氷川清話』講談社学術文庫、2003年)
この2人の言葉を、現在の日本がおかれている状況の中で、かみしめてみるべきだろう。現在の一瞬の局面、一時の利害得失だけを見て判断するのではなく、中国にコミットしてきた周辺諸国や欧米諸国の歴史を直視しながら、そこに地政学的な要素をも加味した上で中国観を設定しつつ、対中政策を考える必要があるだろう。時務情勢に関する精緻な分析・議論もさることながら、今求められているのは歴史観に裏打ちされた大局観であると深く思う。
(2019年4月25日、IPP主催「政策研究会」における発題内容を整理して掲載)