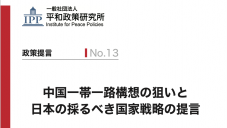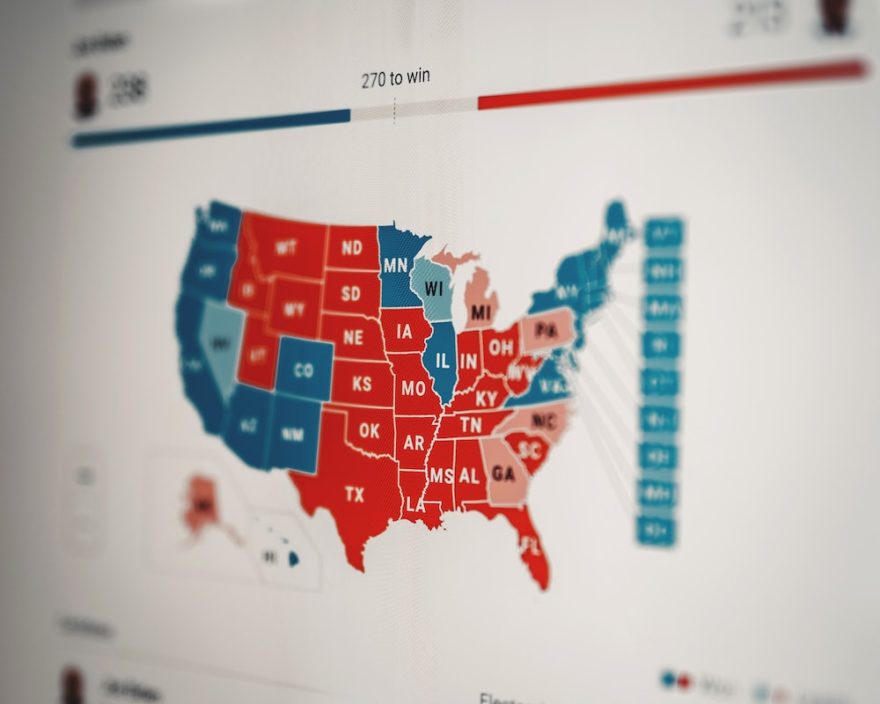はじめに
2018年3月に、ワシントンを訪れて現地の中国に対する雰囲気が大きく変化したことを確認することができた。これまで20年ちかくワシントンに足を運んできたが、米国の対中認識はここ1~2年で急速かつ全面的に悪化したといえる。他方で、この間、中国の研究者などとの会合に出席して感じるのは、そのような米国の対中姿勢の変化に中国人が非常に戸惑っているということである。つまり、彼らは米国の変化を理解できていない。
2018年は、将来、歴史的転換点として記憶される一年ではないかと思う。米中関係の劇的な変化を「発火点」として、その波紋が世界に拡散していきながら、世界も変わりつつあるのではないか。その当初、米中関係の変化は、それがトランプ個人に起因するものなのか、あるいは米国社会の変化に基づくものなのか、「不確実」だったと認識されていた。そこで米中対立が確実な変化なのか、さらにはもはや後戻りできないものなのか、その点について議論してみたい。
日本にとって米国と中国は非常に重要な関係国であっていわば「大環境」である。米中関係の大変化は日本の対外政策はもちろん、東アジア地域、ひいては全世界に大きな影響を与えることになる。しかし、変動期はいろいろなことが制約されると同時に、逆にいろいろなことができるチャンスでもある。それゆえ変化にだけ目を奪われることなく、物事の本質を見極めて対処する必要がある。そこで、こうした状況をもとに、一定の独自性・主体性をもっている日本が、今後どのような形で外交を展開することができるかについて考え、地域への影響も併せて考察したい。
1.不確実性の拡大
(1)トランプ政権をどう見るか
トランプ政権については、これまで多くの分析がなされている。最近、ボブ・ウッドワード著『FEAR 恐怖の男―トランプ政権の真実―』(日本経済新聞出版社、2018年)を読んでみたが、危険な政策決定が日常化していることが書かれていた。著者が描くトランプの性格をまとめると、「自己愛や破壊衝動が非常に強く、皆が大切にしているものを壊したくなるようなところがある」「直感的・衝動的な言動を止められない」「基本的に家族以外ほぼ誰も信用しない」「仕事面ではイエスマン以外は基本的に排除する」「敵対者を作り、それを攻撃していくというやり方をとる」「国内でも国外でも、まず緊張を高め相手を混乱させて不安に陥れ、最後には(米国にとって)最もよいと思われるディールをする。自分は世界で最も優れたディール・メーカーだと信じている」というところであろう。
あのボブ・ウッドワード(現・ワシントン・ポスト紙副編集長)が綿密な取材を元に書いた本なので、それなりの信憑性がある。トランプ大統領に対して、米国のエスタブリシュメントの多くはついて行くことができず、共和党の中にもトランプの大統領就任に拒否反応を示した人もいた。トランプ政権内の高官には、エスタブリッシュメントが閉め出される一方で、トランプと「関わりの深い人」に加え、これまで聞いたことのない「山師」のような人々が混じっている。
対中国政策に関わるトランプ政権の有力スタッフを何人か見てみよう。
カリフォルニア大学アーバイン校教授で、現在、国家通商会議ディレクターを務めるピーター・ナヴァロは経済学者だが、赤根洋子訳、飯田将史解説『米中もし戦わば――戦争の地政学』(文藝春秋社、2016年)など対中政策に関連した著書がある。ただし、彼の著書の原著を手に取ればわかるが、推薦文を書いている人の中に、まともな中国研究者はほとんどいない。つまり、彼自身は中国研究者から「キワモノ」扱いされている。しかし彼の主張は、中国を追い詰める手段を繰り出しているトランプ政権の対中政策の中心にあるようである。
ロバート・ライトハイザー米通商代表は、かつてレーガン政権で米通商代表次席代表を務め、日米貿易摩擦で日本に鉄鋼の輸出自主規制を受け入れさせた通商問題の強硬派であり、対中通商交渉の中心人物である。ジョン・ボルトン国家安全保障問題担当大統領補佐官は、ブッシュ政権時に軍備管理・国債安全保障担当国務次官や駐国連大使などを務め、北朝鮮問題や中東問題で強硬派として名を馳せた人物で、「彼がトランプ政権に入れば朝鮮半島は戦争になるだろう」と言った人もいたほどだ。
その一方で、ウィルバー・ロス商務長官やスティーブン・ムニューシン財務長官など穏健派も若干はいるが、全体的には対中強硬派の人物が政権に重用されているという状況である。つまり、トランプ政権は、常識的かつ穏健な対中政策を大統領に提示して、大統領がそれを選択するという可能性が極めて小さい政権である。
(2)超党派的な対中認識の変化
2018年秋の米中間選挙の結果、下院は民主党が多数党となったが、民主党も中国に対して強い不満を抱いている人が多い。中国への見方が厳しいのは、共和党政権だけではないのである。この不満は、当初不満であったが、それが行動に変化し、行動が拡大しつつある。問題は、中国に対して強硬に接するかどうかではなく、どのような強硬策をとれば有効であるか、という違いしかなくなっている。
クリントン政権やオバマ政権で東アジア政策を担当したカート・キャンベル元東アジア・太平洋担当国務次官補は、『フォーリン・アフェアーズ』2018年4月号で、「対中幻想に決別した新アプローチを―中国の変化に期待するのは止めよ-」と題する論文を発表し、米国の対中関与政策が事実上失敗したと論じて話題を呼んだ。彼に対する批判の大部分は、気がつくのが遅すぎたというものであった。
米中貿易戦争であるが、10%や25%というトランプ政権の対中制裁関税の税率は、通商問題の専門家からみても尋常ではなく、実際に大幅な制裁関税引き上げを行うと米中双方ともにダメージを受ける可能性が高いとされている。したがって、トランプ政権の初期において、その常識外れの対中政策に賛成する人は、ほとんどいなかった。ところが、実際に制裁関税を引き上げて制裁を実施し始めてみると、米国の雰囲気は超党派的に「中国を叩け」の潮流に変わってしまった。一体何がそうさせたのか。
実は、トランプが登場する以前から、米国内には中国のやり方や政策について不満をもっている人が多数を占めていた。しかし中国に対していろいろと主張してもなかなかその通りにはならないことが多く、専門家も米国が主張通し続けることについて、半ば諦めムードであった。ところが、そのような米国社会の雰囲気・常識がトランプの対中強硬策によって、あたかも魔法が解けたように変わり、中国に対して言いたい放題主張することができるようになってしまった。あるいは「魔法にかかってしまった」と表現した方がいいかもしれない。米国人の心の中にあった対中不満を、トランプが解き放つ(unleash)役割を果たしたといえる。
付言するが、トランプによるリベラルな価値観に対する攻撃も同様である。ポリティカル・コレクトネス(PC)を守るため言いたいことも自由に発言できない社会になってしまったと感じながら「我慢を強いられていた」と感じていた白人男性たちが、トランプの暴言によりカタルシスを味わっているのである。トランプの登場をきっかけに、多くの領域でこのような現象が次々と波状的に起きている。
つまり、トランプはあらゆる「パンドラの箱」を開けてしまったのである。米中関係という外交の分野でもそうなった。さらに米国に限らず、世界の他の国々おいてもトランプの対中強硬策の展開を契機に、中国に対してこれまでより強めの主張をできるようになりつつある。
米国では、これまでペンタゴン(国防総省)の対中認識は厳しかったが、ウォール街(金融経済界)は親中的であるというように、必ずしも一枚岩ではなかった。ところが、安全保障コミュニティや経済界かにかかわらず、学界、文化界などあらゆる領域で、対中認識が悪化しつつある。それまでは対中強硬策を主張しても、それに対して誰かが必ず中国を擁護・弁護してきたが、そういう勢力がほぼいなくなってしまった。
このままでは、中国は技術的・経済的にアメリカを追い越し、欧米が中心となって作り上げてきた国際秩序を破壊し、その権威主義的な価値観を世界に拡めていくのではないか、という不安が、爆発したのである。
もしもパンドラの箱から「妖怪」が出てきたとすれば、この潮流は「不確実性」の話ではなくなる。仮に次期大統領にトランプ以外が当選したとしても、米中対立の構造は、「中国をどうたたくか」だけを違いとして、リレーのように繋がっていくのではないか。
(3)米中の戦略的対立の構造化
昨今の米中関係は「貿易戦争」と呼ばれているが、その本質は「貿易」なのか、あるいは「戦争」なのか。貿易であれば、相互の利益確保のために話し合いをして妥協点をさぐって決着することになる。「戦争」であれば、多少互いに傷つきあってもいいからどちらか一方が勝つところまで戦うということになる。米国は今、中国と相互利益の最大化を図ると言うよりも、中国をねじ伏せようとしており、「貿易戦争」と呼ぶのがふさわしいと思う。
問題は、これは単に対中貿易赤字を削減するかどうかにとどまらないことである。むしろ、関税引き上げは、中国を包括的に屈服させるための手段なのではないか、ということである。
ここで中国への不満の実例を挙げてみよう。まずは「不公正貿易」であるが、中国は世界貿易機関(WTO)の枠組みでは、いまだに発展途上国として、優遇策を得たまま自由貿易を享受している。そしてその経済は、国家主導であり、経済の主要部分は国有企業が握っている。
「国家による市場経済への介入」だが、中国では国有企業が特権的な地位にあるので、いくらでも政府が国有企業に融資でき、さまざまな活動が可能だ。南シナ海の島嶼の埋め立ても国有企業がやった。普通に考えるとこのような島嶼を埋め立てたところで儲からない。同様に、東シナ海で石油や天然ガスを採掘しているのも中国の国有企業である。なぜ日本の企業がやらないかといえば儲からないからである。しかし中国の国有企業は採算を度外視して、ものすごいスピードでやることができる。日本の戦時中の南満洲鉄道株式会社(満鉄)のような国策会社を思い起こせばよい。
中国は、国家がインターネットを攻撃的に利用している。サイバー攻撃により、企業の情報を窃取し、自国企業の「イノベーション」に利用していると言われている。「知的財産権の軽視」に関しては、あまりに事例が多くて、説明もいらないほどである。2017年に中国は「国家情報法」を施行して組織や個人に「必要な協力」を義務づけている。国家が認定した必要な情報なら、中国の組織や個人は国家に提供する義務があるのである
その一方で、中国自身は「ネット鎖国」を強化している。中国ではGoogleやLINEが使えない。VPN(Virtual Private Network、仮想専用回線)を使えば外部環境に接続できるが、それでも長続きしないし、そのユーザーがどのようなサイトを閲覧したかがすべて監視されている。例えば、台湾のサイトに行こうとすれば、「これは違法サイトの可能性がある」と表示されて遮断されてしまう。現在多くのビジネスはインターネットを通じて行われているが、中国国内のインターネット空間に外から入り込むのは自由ではない一方で、中国は世界でやりたい放題である。
中国は、ロシアとならんで、既存の統治領域を、武力を背景にして変更する可能性がある国である。尖閣諸島、南シナ海の島・礁、台湾など、中国にしてみれば当然の「失地回復」なのかもしれないが、外から見ればそれは現状の国際秩序に挑戦する「拡張主義的政策」である。
しかも、中国は他国からの批判を絶対に受け入れない。それどころか、自国の影響力を拡大するために、買収、脅迫、事実上の経済制裁、フェイクニュースを使った世論操作など、相手国・地域の状況に合わせて、やりたい放題の工作をしている。「シャープパワー」という概念はもともとロシア向けに考案されたが、すぐに中国分析に適用されるようになった。
経済でアメリカ越えが見えてきているのに、中国国内では自由が制限され、人権弁護士が大量に拘束され、少数民族が極端に抑圧されている。経済的な格差は広がる一方であり、環境悪化は空前のレベルに達し、空気も水もその安全を信じることができない。こんな発展モデルを、中国は対外的に堂々と誇り高く宣伝している。米国は中国の発展に巨大な支援をしてきたにもかかわらず、である。つまり、中国に関係するあらゆる領域でその影響を受けている人たちが、ついに「中国のやり方は受け入れられない」と声を上げ始めたのである。したがって、多少極端な手段をとっても、中国を止めなければならない、という点で、米国国内が直感的に一致しつつあるのである。
2.戦略的対立の構造化=米中新冷戦の時代
(1)「新冷戦」の始まり
「米中新冷戦」時代を迎えるようになった引き金は、2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会と考えられる。
習近平総書記は、同大会で過去5年間の歩みをもって中国は世界に対して「発展の加速だけでなく自らの独立性の維持も望む国々と民族に全く新しい選択肢を提供し、人類の問題の解決のために中国の知恵、中国の案を出していることを意味する」と豪語した。かつて冷戦期にソ連が、西側とは違う全く新しい発展モデルを世界に提供したとした先例に類似しており、第19回党大会の習近平報告が「新冷戦開始」の宣言であると言っても過言ではない(田中明彦、2018)。
最近、中国の国力や対外的な影響力の強さについて中国人に尋ねると、「中国はそれほど強くない。米国や日本の方がもっと進んでいる」との答えが返ってくる。昨今は米中対立局面の影響もあり、中国人は「謙虚」に振舞おうとしているのかもしれない。これまでの中国の主張と行動をみていると、その意図が何なのか分かりにくいところがあった。
中国は、宣伝に限ると「青天井」でやる傾向がある。党中央宣伝部は、指導者のスピーチの内容などを、意図や現実をはるかに超えた、誇張された内容にしてしまうのである。中国人は、「白髪三千丈」的な誇張に慣れているので何とも思わない。とくに現在の体制下では、政府批判もできないし、多様な意見の表明も困難な社会であり、政府からはやりたい放題の自画自賛の宣伝だけが発信される。ところが同じ宣伝内容を英語に翻訳してを対外的に行うとどうなるか。
今回の第19回党大会では、大会後に党中央宣伝部が主導して米国に広く理解してもらおうと党大会の内容をそのまま英訳してワシントンで紹介した。つまり、簡単に言えば「米国の時代は終わり、これからは中国の時代だ。これは歴史の潮流であり、世界はこの現実を理解し尊重すべきだ」という内容を平気で米国人に話したのである。こんな話は米国人が最も嫌う内容であり、非常に評判が悪かった。
中国に、長期的に米国に取って代わって覇権を握る戦略を有する人がいるのは確かである。ところが、実は中国内部は複雑で、外部からは戦略に従って着々と世界進出を展開していると見えるのだが、内部では意外にも混乱や分裂もあって、走りながら考え、自分たちがやった成功も失敗も後になって取り繕い、「これは戦略だった」と正当化することさえある。
振り返ってみれば、明治維新以降の日本にも似たようなところがあり、後の歴史家には「日本は明治維新のころからアジア制覇の計画があった」と分析した者もいた。ところが、実はそんなものはなかった。現実には出たとこ勝負で、「やってみたら成功した。その結果次の目標が見えた」という繰り返しで拡大していった。ところが世界が日本を見る目はどんどん厳しくなり、ついには米国から極端な石油禁輸を受け、日米開戦に到ったのである。
「中国はこんな意図を持ってこんな行動をとっている。その証拠に、彼らの文献の中にこう書かれている」などと、日本や欧米人研究者に指摘されている。中国人自身は、はたと気がついてみたら世界中が「中国の真の意図は覇権主義だ」という見方で凝り固まっている状況に直面してびっくりしている。米国ワシントンに派遣された多くの中国人研究者は、「なぜこうなってしまったのだろうか」とみなショックを受けて帰ってきている。中国との対決を既に決めてしまった米国人に、いまさら「協力しましょう」と申し出たところで、彼らはそれにやすやすと応えることはないだろう。
中国が、「能ある鷹は爪を隠す」という戦略で、先進国を騙して出し抜き、超大国への道をまっしぐらに突っ走っていたのに、その意図がついにバレて、米国からの牽制を受けていて、それが米中の「新冷戦」である、という理解も、大筋で間違ってはいないだろう。しかし、そのストーリーだけで全てを語るのは、おそらく誤っている。もしもそれが正しいなら、中国はあと10年「爪を隠」して、アメリカを凌駕してから牙を見せるのがもっとも合理的であったのに、そうしなかった。中国人には米国をよく理解していなかったのである。学問的に見れば、現実の中国はもっと複雑である。しかし、もう遅い。「新冷戦」はすでに始まってしまった。
(2)米国の対中認識・政策の変化
2018年に入ってからの米国の対中政策の変化を具体的に見てみよう。
まず、『国防戦略報告』(2018年1月)では、中国とロシアを明確に「現状変更国」と定義し、さらに「中国は一方で南シナ海の島・礁を軍事化しつつ、もう一方で隣国を経済手段で脅迫する侵略的競争相手である」と明示した。
中国が最もいやがる台湾問題についても、『国家安全保障戦略』(2017年12月)で、「われわれは、われわれの『一つの中国政策』を追求する」と明言し、台湾との協力的な関係を維持することを宣言した。ここでいう「われわれの『一つの中国政策』」(our one-China policy)とは、われわれ(米国)のバージョンであり、中国のいう「一つの中国原則」(one-China principle)ではないという意味である。それに加えて台湾関係を強化した。この文言は、中国が最も嫌うものだ。米中国交正常化以来、米国は米中関係は重要だと、緊張が高まるたびに自分に言い聞かせてきたが、まさに今その「呪文」が解けてしまったのである。
2017年12月には、「2018会計年度国防授権法」が成立したが、これは、台湾海軍と米海軍の艦艇による軍港相互訪問の復活に関して考慮する(consider)よう求め、米国の軍事演習に台湾の軍隊を招待すること等を、議会に報告するよう求める内容になっている。これまで緊急事態や災害救助などで米軍機が台湾に着陸したことはあったが、今回の法律では緊急案件ではなく、経常的な軍艦の停泊を想定しており、米台間の軍事関係の大幅な向上を意味している。実際に、同法成立後の10月18日、米海軍所属でワシントン大学に貸し出されている科学調査船トーマス・G・トンプソン号(Thomas G. Thompson)が高雄港に停泊した。これは米国議会の面子を保ちつつ、中国を挑発しないぎりぎりの行動であったと考えられる。
2018年3月、「台湾旅行法(Taiwan Travel Act)」が制定された。この法律は、閣僚級高官および将官級軍人の台湾訪問や台湾高官の米国訪問を許容(allow)や奨励(encourage)することが定められている。しかも、この法律では、台湾のことを「country」と記している部分さえある。中国国内には報道されていないようだが、もし報道されたら対米戦争を叫ぶ声が大きく盛り上がってしまうかもしれない。
こうした対中圧力は、中国の行動に影響を与えつつある。2018年6月ごろまで中国は、台湾の周囲に軍用機や軍艦を周回させていた。18年7月に米第7艦隊が台湾海峡に入り台湾を一周した後には、そのようなことがほぼなくなった(注:12月末に再開された)。
米国にはこのようにたくさんの対中カードがある。米国が本気で中国と対立した場合には、中国内で米国と徹底的な対抗を唱えて実施すれば、経済的なダメージは底知れない。そこまでエスカレートはさせたくないというのが中国の本音であろう。
(3)米中関係の二つの基礎の崩壊
前述のような米中の緊張関係がコントロールされている状況かといえば、必ずしもそうとは言えない。
ギデオン・ラシュワン氏が2018年3月12日の『フィナンシャル・タイムズ』で書いたある記事によると、米中関係の二つの基礎、すなわち①米国の自由貿易維持と、②中国も経済的に豊かになれば民主化するという二つの前提が、ついに崩れてしまったという。トランプ米大統領は中国からの鉄鋼とアルミニウムの輸入を制限するため、制裁関税を課す大統領令に署名した。他方中国の全国人民代表大会は、国家主席の任期を2期10年までとする規制を撤廃する憲法改正案を採択した。中国は民主化に完全に背を向けたのである。
米国は将来、自由貿易堅持に戻るかもしれないが、それにしてもトランプ大統領のやり方のように乱暴な形で自由貿易体制が崩れていくとは想像もしていなかった。さらには、米国の意図する改革がすすまなければ、米国のWTOからの脱退さえ不可能だとはいえない。
習近平の集権化と独裁化はすでに習近平体制スタート時から徐々に進んではいたが、国家主席の任期制撤廃はその「最後の麦わら」のような意味があった。中国人はそう思わないかもしれないが、憲法を変えてまで終身独裁制を可能にしたことは、米国が中国にかけてきたあらゆる期待が消えたことを意味する。中国では国内的にずっと行われてきた延長線上のことに過ぎないと認識されているが、海外の認識はそうではなく、大きな転換点であると見えるのである。これによって対中関与政策(engagement)は終焉したとされ、これが冒頭で述べた「歴史の転換点」に繋がってくる。
(4)技術覇権をめぐる戦争
このように「米中貿易戦争」を考えてくると、米国が赤字減らしのためにやっているのか、それとも戦略的競争の手段としてやっているのかがわかってくる。むしろ、米国政府の一部では、米中の「新冷戦」を戦う立場に立ち、米中経済のデカップリングが必要だと考え、安易な妥協が成立しない方がいいとさえ思っている。たしかに、米国は、中国がほぼ妥協不可能な項目を挙げて交渉している。
3,700億ドル以上ある対米貿易黒字を中国はどうやって減らすのか。これは北朝鮮の非核化より難しいのではないか。北朝鮮の非核化は、非核化をやったことにするという「芝居」も可能であるが、貿易統計は芝居ができない。そもそも不可能な数値目標を米国は中国に突き付けている。中国が「では何をやればいいのか?」と聞き返しても、米国はそれに答えられないかもしれない。
米中貿易戦争は、包括的かつ長期的に続き、米中の戦略的対立の一手段、一局面に過ぎないと考えた方がいい。もちろん、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ政権にとって貿易赤字を減らしたいのは当たり前だが、それだけではない。実際に関税引き上げをしかけたことで中国が降参して大幅に譲歩するのであれば、同じ手段を使って、安全保障など他の領域でも中国を締め上げることができると米国は考えるはずである。そうなれば、米国は、現在自分が有している比較優位を使って、中国を引き続き締め上げていくべきという結論になるだろう。
米国にとって貿易に勝るとも劣らず重要なのは、技術覇権の維持である。安全保障に関わるハイテクや通信インフラで、中国が米国を凌駕しつつあり、これに、米国が優位なうちに対抗しなければならない。一つには、2018年8月に対米外国投資委員会(CFIUS)による企業審査の厳格化を求めた「外国投資リスク審査近代化法」が成立し、これによって米国企業への合併・買収と対米投資の制限が加えられた。米国は、米中関係だけをターゲットにした法では、欧州や日本などが抜け穴になりかねないとして、二次的制裁をも視野に入れ、中国包囲網を構築しようとしている。
2018年12月初めにカナダでファーウェイ・テクノロジーズ(華為技術)の孟晩舟最高財務責任者(CFO)が逮捕されたが、同時期、日本政府もファーウェイおよびZTE(中興通訊)の政府調達からの排除の方針を発表し、ソフトバンクもファーウェイとの関係を見直した。このような中国に対する厳しい動きが世界に広がりつつあり、中国内部では動揺が広がっている。これは、実際に中国のイノベーションにとどめを刺す政策であると同時に、短期的にも心理戦として非常に効果的である。
中国では現在、貿易統計などさまざまな経済統計が発表されなくなったという。また、2018年の経済成長率が、実際には発表されている数字よりもはるかに低いという情報もある。さらに10月ごろに行われると見られていた中国共産党中央委員会第四回全体会議(四中全会)が、18年12月になっても開催されていない。いわゆる改革・開放以来、共産党の大型会議が遅れて開催されるのは極めて珍しく、過去20年間では2012年の中国共産党第18回全国代表大会のとき、尖閣諸島問題の対応のため遅れて同年11月に開催されたケースくらいしかない。米中交渉で何が起きるか分からないという緊迫した状態が続いているのであろう。
(5)米中貿易戦争のタイムライン
そもそも、米中貿易戦争のタイムラインを見ると、米国は思いつきでやっているのではなく、早い段階から中国の貿易慣行などの調査を進めてきたことがわかる。「中国のやり方は不公正な慣行であり、何度も申し入れしたにもかかわらず、現在も続いている」との裏付けを取った上で、米国は制裁関税措置を発動しているのである。今までであれば、対中制裁をやれば米企業にも相当のダメージがあるから怖くてできず、ブラフのレベルにとどまっていた。しかし米国は、今度本気で中国を締め上げている。
米国が2、000億ドル分の制裁関税をかけた時に、中国側は600億ドルの報復関税しか対抗できなかった。それはそもそも相手から輸入している規模が米中ではぜんぜん違うためである。世界の貿易収支は、最大の貿易黒字国が中国で、最大の貿易赤字国が米国という構造になっている。米国は中国からしか輸入できないものは制裁関税を低くしたままに据え置き、他国からでも買えるものには制裁関税率をいくらでも上げることができる。中国だけが負けるか、米中双方が負けるか、どちらかしかない。双方が負ける場合にしても、負け幅は中国の方が大きいだろう。しかも、中国が報復のために、手持ちの米国財務省が発行する国債を投げ売りしたら、ドルが暴落し、中国がためこんだ富の価値が半減し、自らも経済危機に直面する。こう考えると米国は圧倒的に有利である。
しかし、中国人にこの話を会議で持ち出すと、「負けが決まったわけではない。中国人は我慢強い」と反論される。確かに、王岐山国家副主席は「中国人は草を食ってでも一年やっていける」と発言したことがあった。その意図は、米国人はわずかな打撃さえ我慢できないはずだから、中国が我慢し続ければ、いずれ自ら強硬策をやめるはずだ、というものである。しかし、中国人は本当のところどこまで我慢強いのだろうか。民間企業はどうか。豊かな生活しか知らない若者たちは我慢できるのか。中国経済に対する自信が失われたら、その瞬間に彼らはお金を持って中国から逃げ出そうとするかもしれない。中国人の言説は、いくぶんか「強がり」の要素が入っている。こう見ると、いま中国はまさに改革開放以来の「空前の危機」に直面しているということになる。
(6)「新冷戦」とは何か
現在の米中貿易戦争が単なる「不確実性」ではなく、構造化した戦略対立の一部に過ぎないとなれば、米中の「新冷戦」をどうとらえるべきか。何が「新」なのか。
20世紀以降、米国の覇権に挑戦した国はいくつかあった。まずは、ドイツと日本の挑戦であり、これは第二次世界大戦によって敗戦させられた。次は、第二時世界大戦後のソ連であり、核兵器の時代に入ったため、米ソは熱戦に到らず、冷戦という国家対立の形態が生まれた。冷戦は、単なる国家の利害対立ではなく、自由民主主義・資本主義と社会主義のイデオロギー対立という側面もあった。ソ連は、その硬直した経済システムと過大な軍事支出が災いし、ペレストロイカによる立て直しに失敗して崩壊した。
そして、最後の挑戦者は戦後の日本であった。日本は、米国の同盟国で緊密な経済パートナーであり、旺盛な貿易と投資で米国の経済覇権を動揺させた。バブル経済期の日本は、米国経済に接近し、ニューヨークのロックフェラー・センターの買収等、多くの不動産買収に乗り出すなど驕り高ぶっていた。最終的には円高に誘導されてバブルが崩壊し、その後の失われた二十年を経験することになった。現在は、米中に次ぐ三番手となり、世界をリードするITのプラットフォーマーもいない。最終的に日本の経済的台頭は、米欧の協調と米国による通商交渉などでうまく抑え込まれてしまった。
中国もソ連同様核兵器国なので、米中対立は熱戦に到らず、冷戦になるだろう。それではソ連と中国が同じかといえば、そうではない。当時ソ連は、米国との間に緊密な経済関係はなく、人的交流もなかった。ロシア人が米国の大学や企業の研究室に入り込んで技術を「窃取する」という状況ではなかった。ところが現在の米国は、中国人留学生なしに大学の研究が考えられないほど多くの留学生が入り込んでいる。これは米国に限られた問題ではなく、世界中どこでも中国人留学生だらけである。経済的関係が密接で、人的交流も深いというように、相互関係が厚みをもっている米中の状況は、米ソ冷戦時代とは全く違う。
日本の場合は、米国に安全保障を依存しているので、結局日本は決定的な対立を避けてきたし、究極的には妥協を強いられてきた。この点が今の中国とは、根本的に違う。中国は、米国を仮想敵としているし、何かあれば米国との対立をいとわずに報復をする。こう考えると米国は、過去に経験したことがないような相手と冷戦を戦うことになる。それは新しい戦略的な競争相手である。
かつてソ連を相手にしたように中国を次から次へと叩いていくと、米国や周辺国は返り血を浴びることになる。それはできないということになるだろう。他方、かつての日本のように、最終的に言うことを聞いてくれる同盟国ではない。つまり、米国が戦う「新冷戦」は、可能な限り自分への被害を生まないよう、緩急をつけた中国潰しになるであろう。この密接な経済関係は、中国から見れば「経済のデカップリングなどできるはずがない」という過信につながるが、他方で米国から見れば「ソ連とは違って、関税を上げれば中国は音を上げるはずだ」という確信につながる。「新冷戦」は、自由貿易を葬るプロセスと表裏一体になるのである。
(7)トランプ政権の対中戦略
それでは具体的なトランプ政権の対中観についてみてみる。トランプ大統領は、この点に関して包括的に述べたことがないが、2018年10月4日にペンス副大統領がハドソン研究所で行った演説にそれが包括的に述べられている。それには、①中国製造2025、②米国企業買収、③軍事的優位を確保し米国を追い出す、④尖閣・南シナ海軍事化、⑤航行の自由作戦を物理的に邪魔、⑥米国の善意を利用して軍事大国化、⑦人権弾圧・強権化、⑧ネット鎖国、⑨オーウェル的世界の完成、⑩宗教迫害、⑪チベット・新疆での迫害、⑫アジア・アフリカでの「債務外交」、⑬港を租借後軍事化、⑭無条件で腐敗した政府を援助、⑮中米・カリブ海諸国を台湾と断交させる、⑯外国への世論操作、米国の選挙への介入、等が含まれている。
以上の項目の中には、若干怪しいものも含まれているが、中国の専門家の目で見ても、おおむね間違いではないといっていいだろう。
2018年12月2日に米中首脳会談が行われ、90日以内に技術移転強要の中止、知財保護、非関税障壁・サイバー攻撃中止、サービス・農業の市場開放要求等が中国に突きつけられた。ただ、90日の期限は3月1日までであるとされた。交渉と内部調整の時間が2019年2月いっぱいまでしかないとすると、旧正月に当たる中国にとっては対応が非常に難しい。しかも3月にはまた全人代が控えている。この時期に米国が更に制裁を積み重ねたら、習近平政権は窮地に追いやられるかもしれない。
ここで中国の戦法で興味深い点が見えてくる。中国は真の交渉相手である米国に対して(叩けば自分がやられてしまうので)正面きって叩くことができない。そこでウィーク・カウンターパートを叩くのである。数年前米国が韓国に終末高高度防衛ミサイル(THAAD)を配備したとき、中国は米国を批判せず、(韓流禁止、ロッテグループへの不買運動、韓国団体旅行の取り止めなどで)韓国を叩いた。米国で台湾を支援するような法律ができると、台湾と外交関係がある国を3つ続けて断交させ、自ら外交関係を樹立した。2018年12月6日のカナダ政府によるファーウェイの孟晩舟の逮捕にしても、中国は在中カナダ人2人を拘束し、孟晩舟の身柄の引渡しを要求した。
このことは、中国が米国に対して、有効な手段を持っていないことを意味する。だからこそ、米国は中国の足下を見て、妥協不可能に近いことを要求し、妥協に動いたところを潰すというようなことをやってきた。一方中国は、これに対して何とか米国と妥協して対応しようとしているが、逆に少しずつ孤立していっている。ただし、あまりにも追い込まれた場合には、対米強硬派が台頭してくる可能性さえある。
それでは中国の対米交渉における妥協可能性はどうか。共産党一党独裁体制の中国にとって、国家の根本であり、社会主義の名残ともいうべき国有企業と産業政策は、中国にとっては発展の要であり、これを捨てることはできない。サイバー攻撃や知的財産権の「窃取」という問題も、これで生活している人が何十万人も、あるいはもっと存在する。一時的に緩めることはあるかもしれないが、完全にやめることなど習近平政権にとっては不可能であろう。そもそも、やめる以前に、そうした活動をしてきたことを認めることさえできないはずである。中国は、米国の罠にしっかりとはまったまま、交渉に臨んでいるのである。
加えて、今後二年間は米中関係にとって非常に重要である。トランプ大統領は次期大統領選挙を睨んで、中国をねじ伏せて完全に勝利して再選を狙うのか、それとも中国とうまくディールして経済的利益を引き出し国民にその成果をアピールしたいところだろう。中国は米国に譲れるところは譲りうまくディールして利益もそれなりに確保するというシナリオを狙っていると思う。米国は、いったん中国とのディールをしても、「中国は約束を履行していない」などと文句を言い出し、すこし時間をおいてまた圧力をかけていくのではないか。
3.米中関係の将来シナリオ
(1)四つのシナリオ
ここで、中長期の将来の米中関係を展望するために、米中関係の将来シナリオを一種の思考実験としてやってみたい。
シナリオ・プランニングの方法論によると、最も不確実かつ最も重要な要因を二つ導き出し、最も振れ幅の大きいものをかけ合わせると、四つの異なる未来が描ける(図参照)。横軸は、米国の対中強硬策が堅持されるか(右)、妥協されるか(左)であり、縦軸は、中国が対応を成功させるか(上)、失敗するか(下)を示している。4つの象限の説明は以下のように、理解を助けるために過去の事例を使って類比する。
A/Bのケースは米国次第で決まる。
Aのように、米国が強硬策を堅持すればそれはかつての米ソ冷戦のような、徹底した対立になるし、Cのように米国が手を緩めれば、これまでの米中対立の延長戦にすぎなくなる。実はトランプ政権が現在のまま強硬策で行くかについては怪しいところがある。それは対北朝鮮政策でもそうだったが、トランプ大統領は2017年に、金正恩委員長を「ちびのロケットマン」などと批判していたのに、半年もしたらシンガポールで首脳会談を行って握手していた。これと同様に、トランプが、短期的な利益を得るため、中国との間で一気にディール成立を狙う可能性は排除できない。ただしいくら妥協してディールを成立させたとしても、約3、700億ドルの対中貿易赤字がすぐになくなるわけではないので、すぐにまた強硬策へと回帰することがあり得る。これまでの米中関係は強硬策と関与策とを繰り返してきた歴史で、今回はその拡大バージョンともいえる。
C/Dのケースは、中国経済が悪化し、挫折・崩壊の道を歩むというものである。
Cは中国経済が相当悪化し、世界がこれを救済するケースである。日本も救済のため手を差し伸べ、米国もそれに異議を唱えない。なぜなら中国経済が崩壊した場合には、世界への波及的影響が余りにも大きいからである。2018年10月に安倍総理が訪中して、通貨スワップ協定を結んだことでわかるようみ、中国経済が不安定化することは、日本にとってそもそも脅威なのである。Cの状況を譬えるならば、1989年直後の中国を巡る状況に似ている。天安門事件が起きて改革開放が挫折したが、日米両国は、ソ連や東欧の前例のように中国共産党を潰すことはしなかった。むしろ、当時のブッシュ政権や日本政府は、鄧小平の改革・開放を信じて、中国に手を差し伸べ、中国共産党政権を助けたといってもよい。
Dのケースは、中国が経済状況の悪化によって崩壊しそうになっても一切助けず、中国共産党が倒れ民主化するのを待ってから初めて手を差し伸べる。これはソ連崩壊後のロシア支援に似ている。
A、B、Cのケースは、我々はすでに似たような事例を経験済みだが、CとDの場合、世界的な経済危機が起きるかもしれない。ただ現在の中国はまだ多くの外貨保有があり、対外貿易依存度が10年前よりだいぶ低下しており(GDPへの貢献度は20%未満)、内需拡大や貿易相手国の多元化など、政策手段はまだある。
現在の展望として蓋然性が高いと考えられるのは、AとBを揺れ動くシナリオである。冷戦と言っても、米ソ冷戦時代とは違い中国経済があまりにも世界と密接に結びついているために、強硬策を貫くこともしにくいから、緩急を繰り返すことになる可能性が高い。その意味では、A/Bは(程度の差こそあれ)ほとんど同じといえるかもしれない。
またC/Dにしても、中国経済がいつ挫折するかも、中国共産党がいつ倒れるかも誰にもわからないし、Cかなと思っている間に中国共産党が倒れてしまうとか、あるいはDを貫こうとしていて、経済危機があまりにひどく、我慢しきれずに助けてしまうということもあり得るだろう。そう考えると、実は、このシナリオは4つではなく、A・BまたはC・Dの2つであると考えた方がよいかもしれない。そのシナリオを大きく分けるポイントは、中国経済がどれだけ持ちこたえられるかによるということだ。
(2)日本への影響
以上のシナリオに示すように、日本を含め多くの地域が(米中新冷戦の)影響を被ることになる。一般に米中関係が悪いと、基本的に中国は(台湾関係を除いて)周辺国との対外関係を良くしようと努力する。台湾に対しても、米国に口実を与えないよう、露骨な圧力を控えるようにする。
最近の日中関係を見てもわかるように、日中関係は改善の方向にある。もちろん日本があまり本気で中国との関係改善をすると米国から突っ込まれることにもなりかねない。また現在の日米関係は、日米物品貿易協定(TAG)交渉など懸案事項もあって不確実性が高い。そこで日本としては、中国との関係をきちんと持っておいた方がいいということになる。
次に、前節で述べたA~Dの4つのシナリオについて、日本の対応を考えてみる。
A:対米中「二股外交」
日米関係は安全保障を基軸とするために対米追随の原則に変化はないが、経済的な利益では中国との関係を諦めない。かつて1960年代の日本は、安全保障は対米依存だが、国交がなくても中国との経済関係を追求していくという政経分離政策を取っていたが、それと似て、米国をちらちら見ながら可能な限り中国との経済関係を維持するということになる。
B:日本は米中双方との関係安定化に尽力(現状の延長線上の外交政策)
このケースでは、米国も中国と妥協するわけだから、米国が一時強硬策に出たとしてもその本気度は分からないし、日本としてはむしろフリーハンドで対中外交を展開することができるかもしれない。米国が対中強硬策に出たとき、日本はそれを利用して対中政策を有利に展開すべきだし、他方で米国が緊張緩和を選択するときに、対中政策で突出すべきではない。
C:対中関係を強化し、独自または国際協調で中国経済を救済
中国経済が悪化して、米国がそれを放置している状況である。ここで、中国共産党政権が存続する状況下で、対中経済支援を実施することは、国論を二分する可能性がある。これは1989年の第二次天安門事件直後に類似している。日本は、対中経済援助を再開し、天皇訪中まで実現させて中国を救う側に立ったが、その後中国は強大になって、日本に牙をむいたからである。共産党にまだ「改革派」が存在し、将来民主化するだろうという期待を、日本がもう一度持てるかどうかがカギとなるだろう。
D:日本経済への影響は甚大、対中政策は米国との協調
これは、中国共産党が政権を握っている限り、決して彼らに救いの手をさしのべない、ということであるから、第二の敗戦・引き揚げにも相当する大混乱・大変動となる。そもそも、「新冷戦」の類比で言えば、米国は、中国との戦いに勝利することが目的なのであるから、倒れそうになっている中国を救ってはならない(むしろ積極的に潰せ)ということになる。中国で体制移行が始まり、民主化が確実になるのを待ってから米国や国際社会とともに支援をすることになる。これは、冷戦後のロシア支援に類似している。
中国の隣国であり、深い関係を持つ日本としては大混乱が必至であるDよりも、中国の改革を促すCを願うことになるのではないだろうか。現実に中国経済が挫折する場合、対中支援を行うことにならざるを得ないが、かつての歴史的経緯を思い出して支援をためらう人もいるだろう。
現在の「新冷戦」状況が昂進することを考えれば、A/Bの対応策を早急に立てる必要がある。他方で、中国経済がおかしくなれば、現実的に日本にとっても困難が伴うから、特にC/Dのケースについて、いろいろなシミュレーションをして対応策を想定しておく必要はあるだろう。
4.東アジア地域への影響
最後に、地域への影響を考察するが、まず日中関係をみてみたい。
ここ10年余りの日中関係を振り返ってみると、2008年ごろは関係が良好であったが、2010年ごろから中国艦船が尖閣諸島に接近するようになった。これは2012年の日本政府による尖閣諸島国有化宣言に端を発するできごとではなく、それ以前から中国は計画に従って行動してきた。長い期間にわたり政府開発援助(ODA)などを含め、これだけ中国の発展のために尽くしてきた日本に対して、中国はこのような形で報いている。日本の中国に対する感情は、あきらかに冷め切っている。しかし、中国が日本にとって重要な隣国である現実は変わらない。
米中「新冷戦」の時代を迎え、「冷戦の論理」は米中だけに限られることではなく、必ず地域にもじわじわ波紋を広げていくことだろう。例えば、米国が北米自由貿易協定(NAFTA)の仕切り直しをしたときに、非市場経済国とのFTAを結ぶことを制限するいわゆる「毒薬条項」が加わった。ロス商務長官は「これから米国と貿易協定を結ぶ場合は全てこれを入れる」と述べている。
2018年秋に日米首脳会談により合意されて始まった「日米TAG(日米物質貿易協定)交渉」が始めるとこの条項を呑まされる可能性がある。そうなると現在進行中の日中韓自由貿易協定(CJKFTA)や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)は、中国を入れる限り結べなくなる。日本としては、「新冷戦の論理」を盾にして「毒薬条項」を呑まされたらどうすべきか、対応を考えておく必要がある。1つの考え方としては、中国抜きの経済圏を構築することであるが、中国はそれを非常に警戒している。
もう1つの考え方は、「毒薬条項」を中国に不公正な制度の変更を迫るテコにすることである。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)なみにサービス部門や農業分野の国際競争力向上に繋がるとともに、強制技術移転の禁止や国有企業の規律・ルール規定などの設定により、中国の行動を変えていくきっかけにもなり得る。現在、中国国内の改革派は、米国からの外圧をテコにして、CPTPP参加を目指し、そのことで中国経済をさらに自由化させることを考えている。
「毒薬条項」のような「踏み絵」は、米欧、米韓、米台などいろいろな国にも広がっていくだろう。日本は、それに対して、中国の変革を促しつつ、中国抜きの枠組みも模索する、という二段階の態勢をとるべきであろう。日本はまだ力があるから対応策もあるが、弱小国にとっては米中の狭間に立たされ、どちらにつくかの選択を迫られるような苦しい局面も出てくるに違いない。
韓国の場合、中国内に製造業の拠点が多くあるし、対北朝鮮問題も加われば、なおさら苦しい場面が出てくるだろう。現在の文在寅政権は、南北関係の改善プロセスに陶酔しているところがあるが、米中対立が抜き差しならぬ状況になった場合、中国が北朝鮮に対して制裁緩和や支援を続ける可能性もあり、核・ミサイル開発問題の解決が難しくなるだろう。国際社会が願う方向での北朝鮮問題の解決は、あくまで米中が協力してこそ可能だからである。
台湾は、対中貿易依存度が非常に高いので、さらに厳しい状況に直面するだろう。すでに対米輸出が多い製造業の中には、中国においた製造拠点を他の国に移転しようと動き出しているところもある。しかし中国は撤退するときに課税清算がかけられるため、中国から他に移転するのも容易でない。しかし台湾も、究極的には安全保障を米国に依存しているで経済的には苦しみつつ、米国についていかざるを得ないだろう。
東南アジア諸国も、米中による分断によって深刻な影響を受けるだろう。米中対立の局面において東南アジア諸国連合(ASEAN)が団結して何かをやるということが、ますますできにくくなるだろう。ASEANの外相会議や首脳会議では、中国問題が議題に上ると共同宣言が出しにくくなくなってきた。これからは国際会議で米中が対立する議題を話し合うと、共同宣言を出せないということがしばしば起きるだろう。
アジアの問題は長い時間をかけて解決してきたが、このようにいろいろな場面で米中対立を原因とした分断が深まっていく可能性が高いだろう。
おわりに
今後、米中対立は長期化していくだろう。4つのシナリオを頭の体操として考えてみたが、それぞれにふさわしい対応があり得る。できれば日本は第一次冷戦期でも独立性があったように、できるだけ自分のフリーハンドを維持しつつ、米国の圧力をうまく利用して、中国の言動を変えていくことを追求できる「チャンス」と認識して取り組むべきである。米中関係がいかなる方向へ進んでも、地域に国々は選択を迫られて板挟みになる。これは国家レベルでも企業レベルでも避けられない。今後、米中関係はより悪化していくことを念頭に置いて、さまざまなシミュレーションをして準備しておくべきだろう。
(本稿は、2018年12月14日に開催した政策研究会における発題内容を整理してまとめたものである。)
<参考文献>
梅本哲也『米中戦略関係』千倉書房,2018年。
田中明彦「貿易戦争から『新しい冷戦』へ―中国台頭で変容する国際システム―」,『中央公論』2018年11月。
津上俊哉『「米中経済戦争」の内実を読み解く』PHP新書,2017年。
松田康博「米中冷戦で空前の危機」『週刊東洋経済』2018年12月29日-19年1月5日号。
ハイデン,キース・ヴァン・デル他,西村行功訳『入門シナリオ・プラニング―ゼロベース発送の意思決定ツール―』ダイヤモンド社,2003年。
Bob Woodward, Fear: Trump in the White House, New York: Simon & Schuster, 2018.(ボブ・ウッドワード著,伏見威蕃訳『恐怖の男―トランプ政権の真実―』日本経済新聞出版社,2018年)。
Peter Navrro, Crouching Tiger:What China’s Militarism Means for the World, Amherst: Prometheus Books, 2015.(ピーター・ナヴァロ著,赤根洋子訳『米中もし戦わば―戦争の地政学―』文藝春秋社,2016年)。