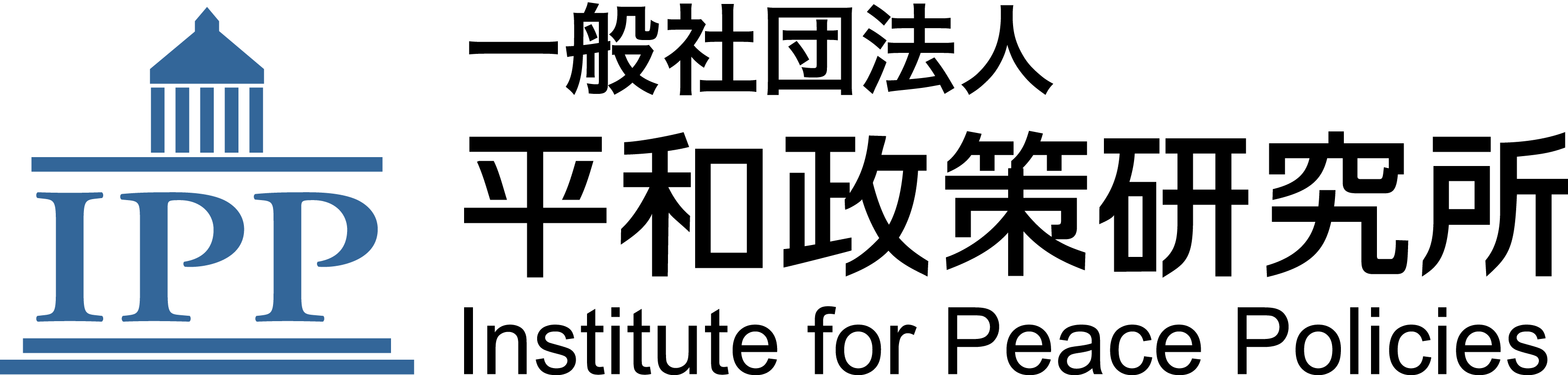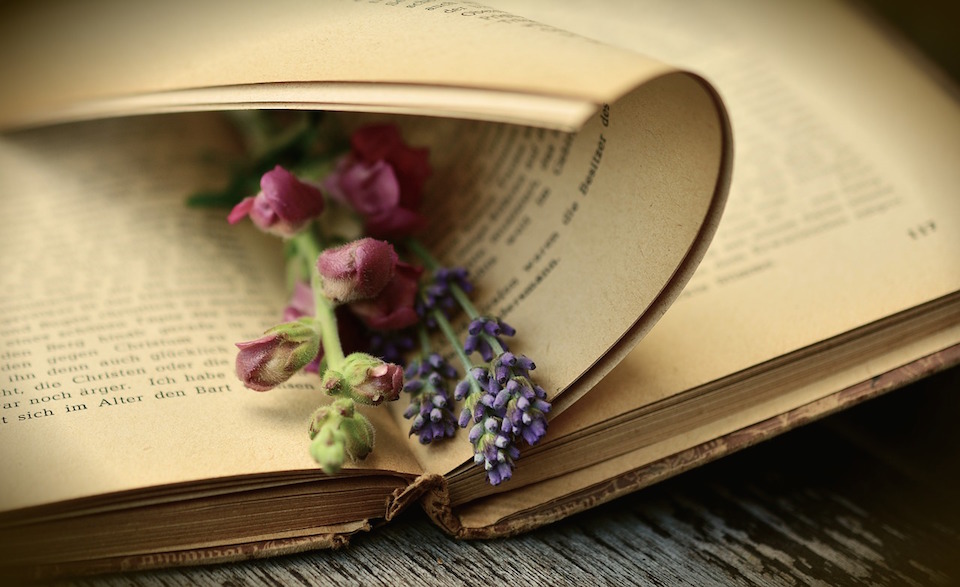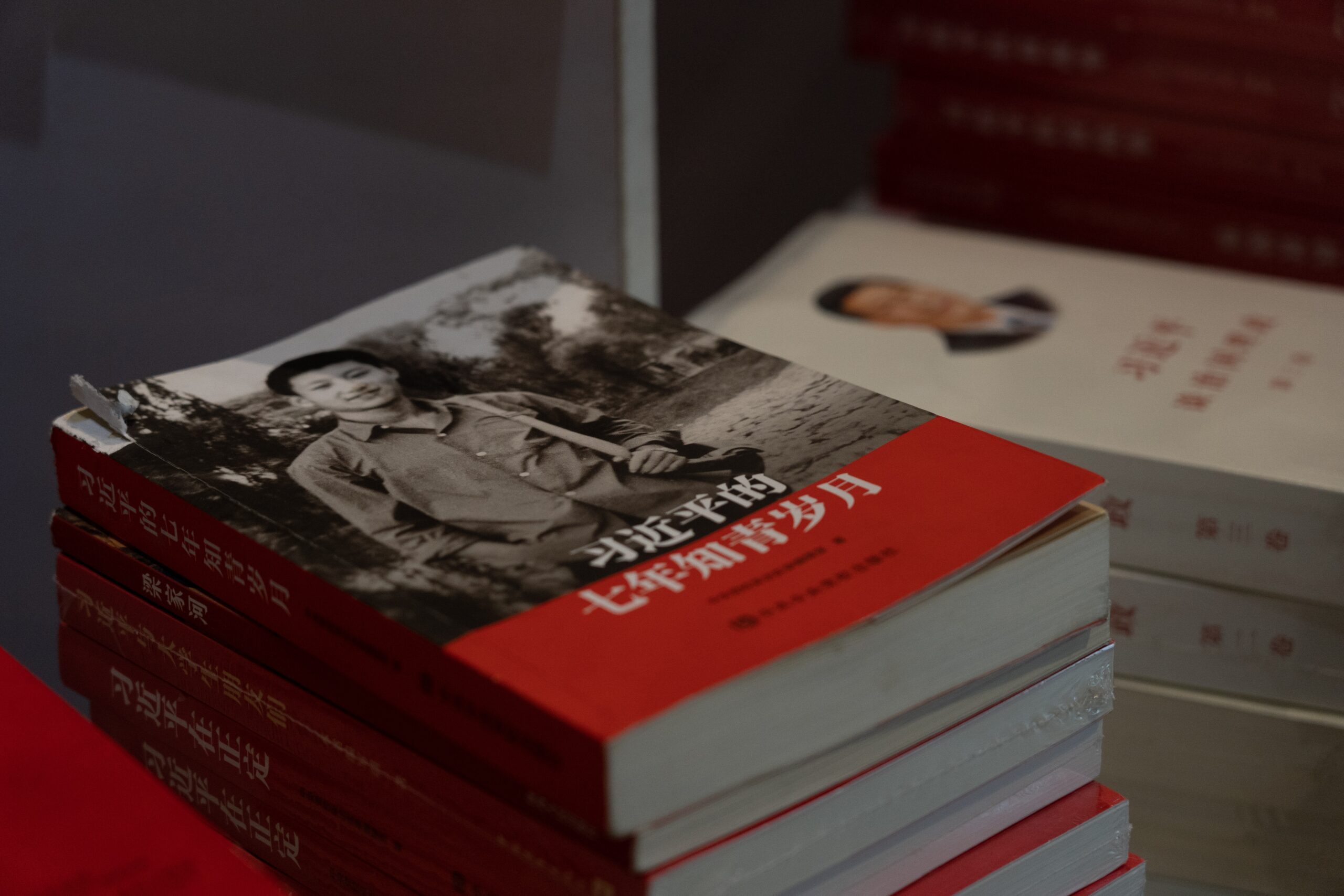はじめに
2024年3月に『「一帯一路」を検証する:国際開発援助体制への中国のインパクト』(明石書店)を出版した。本報告は同書の内容に沿っており、特にインフラ建設の分野に焦点を当てている。インフラ建設は中国の台頭が目覚ましい分野であり、近年まではアジアにおいて日本が圧倒的に優位であった分野である。中国と日本の案件を比較しつつ、その実態や課題について紹介あるいは問題提起したい。
1.中国・日本のインフラ輸出戦略
中国の経済的台頭
2000年時点では、日本と中国のGDPが世界に占めるシェアはそれぞれ15%と4%であったが、2010年にはどちらも約9%とほぼ同じになり、2022年には日本が4.2%、中国が17.7%となった。わずか20年の間に、日本と中国のシェアは完全に逆転してしまった。これは当然ながら、国際開発、国際経済に大きな変化をもたらしている。
輸出額については、2008年に中国が世界最大の輸出大国となった。これと関連して、外貨準備額についても2007年に中国が日本を抜き、世界最大の外貨準備額を持つ国となった。この国際収支上の余剰が、世界とりわけ途上国に流れている。中国が日本のGDPを抜いた2010年頃から約14年の間に、中国の対外援助支出が急拡大した。
「三位(四位)一体」の海外進出
中国の対外援助支出は、外交部・商務部の無償・無利子借款、中国輸出入銀行の優遇借款、その他様々なスキームからなる。中国が途上国における経済的プレゼンスを拡大する際は、対外援助支出だけでなく貿易額、直接投資、対外経済合作契約額の拡大が合わせて進行している。中国の多くの援助・融資案件は、中国企業が請け負うことが義務付けられている「中国企業タイド」である。そのため、中国企業が進出し中国人労働者を連れてきて途上国の事業を行うという形で、援助・貿易・投資それから労働者の輸出という四つが一体となって拡大してきた。援助・貿易・投資を一体的に行うことを「三位一体」の経済協力と言うが、中国の場合は「四位一体」の海外進出ともいえるだろう。
2013年には「一帯一路構想」を打ち出し、地理的な一帯一路を超えて中南米やアフリカも含む世界中で関連事業を拡大させてきた。こういった中国の海外進出は、途上国にとっては多様な資金源の追加あるいは選択肢の拡大につながっている。
中国の政府開発資金(ODF)の推移
中国はOECDに加盟していないためODA統計はない。中国の経済協力の規模については様々な推計があるが、早稲田大学教授でJICA北京事務所長でもあった北野尚宏氏が非常に詳細に推計をしている(図1)。「二国間:無償・無利子借款」(青色)と「二国間:優遇借款」(赤色)の一部がODAに相当すると推測されている。また、「多国間:国際機関出資金・拠出金」(緑色)もODA部分ということができる。
図1のグラフを見ても明らかなように、中国の対外経済協力額で特に拡大しているのは、非ODA部分である。これを「その他政府資金(OOF)」と言い、それがかなりの部分を占めている。中国国有銀行が貸し付ける類のもので、ODAと比較すると金利が高かったり、返済期間が短かかったりする。
中国は対外経済協力の金額あるいは事業の内容については公表していないが、近年米国が相当な資金と人的資源をつぎ込んで詳細なデータを収集している。米国には世界各国から留学生や若い研究者が集まっているので、彼らが現場へ行って様々なデータを収集しており、そういうところからかなり詳細なデータを得ることができることが背景にある。
日本政府のインフラ輸出戦略
1970年代から2000年代まで、円借款でのインフラ建設・輸出支援により、日本は特にアジアのインフラ分野で大きな存在感を持っていた。しかし2000年代後半以降、特にインフラ分野において中国がドナーとして急速に台頭することで、日本の存在感は次第に低下していった。
その様な状況に対して日本政府も様々なインフラ輸出振興策をとってきた。安倍政権は2013年3月に内閣官房に「経協インフラ戦略会議」を設置し、同年に「インフラシステム輸出戦略」を策定した。また2015年5月には「質の高いインフラパートナーシップ」を発表し、2016年5月のG7サミットで「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」を打ち出した。2019年6月のG20大阪サミットでは日本が主導した「質の高いインフラ投資に関するG20原則」が承認された。
「質の高いインフラ」というのは物理的に質が良いという意味では必ずしもなく、日本政府は①プロジェクトの経済合理性、②開放性、③透明性、④借入国の債務維持可能性といった要件を満たすことが必要だとしている。そういった立場を明確にすることで、日本のインフラ建設支援の方が中国に比べて良いというメッセージを出して中国に対抗している。
インフラ分野における中国の競争力
しかし、例えば野村総合研究所のレポートによれば、日本企業はリスク評価能力や技術力、国際信用力などにおいて依然として優位にあるが、中国企業は資金量、意思決定の速さ、多様な気候・施工条件でのプロジェクト経験、新興国でのプレゼンスなどに非常に強みを持っている(野村総合研究所、2017:49-50)。
また、中国のインフラ輸出は、中国政府借款の供与の際にOECD/DAC(開発援助委員会)のアンタイド・ルールに従わず中国企業タイドで資金供与する点で特徴的である。その一方、日本の円借款による途上国のインフラ建設支援事業についても、現地での調達を中国企業が受注するケースが多くなっている。競争入札において価格、速さ、柔軟な交渉などの点で優位性があるとされる。近年では、国際競争入札に参加しても価格面で到底太刀打ちできないことから、日本企業が応札すらしない事例もある。
日本政府およびJICAは、日本企業タイドで日本企業の受注を支援する枠組み(STEP円借款1)を作って活用しようとしてはいるものの、DACルールにより利用は低所得国に限定され、円借款の大半はアンタイドとなる。その結果、中国企業が受注する事例が多くなっている。
図2は主要ドナー(中国、日本、世界銀行、アジア開発銀行(ADB))の東南アジア11カ国に対する「政府開発資金(ODF)」額の推移である。この政府開発資金(ODF)には政府開発援助(ODA)だけでなくその他政府資金(OOF)が含まれている。そのため、多様な経路があり正確なODA額を把握しにくい中国からの資金についても、一体的な統計を見ることができる。
先述したように一帯一路はグローバルな枠組みであるため、中国は対外経済協力の半分程度の金額をとりわけアフリカにつぎ込んでおり、アフリカにおいては中国が圧倒的なプレゼンスを持っている。他方で、アジアにおいてはまだ日本、世界銀行、ADBがそれなりのプレゼンスを持っている。2018年頃までは中国の資金が日本や世界銀行の2倍くらいの規模だったが、2019年以降は中国の比率が下がっており、むしろADBの資金供与額が大きくなっている。その理由は後で詳述するが、マレーシアやミャンマーなどで大型案件の見直しが相次ぎ、全体として新規融資に慎重になっていることがあると考えられる。
2.中国・日本のインフラ支援の事例
以下にいくつかの事例を取り上げて、そこから見える実態あるいは教訓や課題について検討する。
(1)フィリピン
中国・日本による鉄道巨大案件
日本は長年にわたってフィリピンに対する最大のODA供与国であり、民間の直接投資に関しては米国が最大の投資国であり続けている。しかし近年は、中国との経済的な関係が拡大している。
日本はフィリピンで、DACにより低所得国において調達を日本タイドにすることが容認されているSTEP円借款(本邦技術活用条件)の枠組みを活用し、4000億円を超える鉄道整備事業を進めている。これはマニラ首都圏の道路の慢性的な渋滞の緩和を目指す事業である。北方のブラカン州マロロス市とマニラ市ツツバン間を新たに整備する「南北通勤鉄道事業」(2015〜21年)が約2,400億円、さらに南北通勤鉄道を北方と南方に延伸する「南北通勤鉄道延伸計画(第一期)」(2018年〜)が約1,600億円である。それと並行して、フィリピン鉄道訓練センターを設立し、鉄道運行能力を向上させる技術協力プロジェクト(2018〜22年)も実施してきた。さらにADBと協調融資を行って、ADBが鉄道システム(線路)を支援して日本は鉄道車両を支援するということも行っている。
これまで様々な国で円借款事業の評価をしてきたが、通常の事業は大きい場合でも数百億円であり、4,000億円という規模は非常に突出しているといえる。おそらく様々な政治的・外交的な理由が背景としてあると考えられる。これらの事業に追加して、マニラ首都圏の地下鉄事業(2017〜22年のフェーズ1で1,045億円)がSTEP円借款で進められている。さらなる借款の検討が表明されており、合計金額は6,000億円となる。
中国政府は2004年頃からフィリピンとの関係を強化しており、マニラ「南北通勤鉄道延伸計画」のさらに北側を支援してきた。2007〜14年に、北部鉄道第1期・1区を中国輸出入銀行のバイヤーズ・クレジットで支援し、計画金額4億ドルに対して実績1億8,000万ドル、融資条件は20年返済・8年据置・3%金利というものであった。2区についても5億ドルの融資が合意されたが、2012年にキャンセルされている。汚職問題が表面化したことが原因の一つと言われている。
その後、2018年に習近平国家主席がフィリピンを訪問した際、様々な援助案件が約束された。鉄道についても、首都圏—ルソン島南端間の長距離鉄道とスービック—クラーク貨物鉄道が合意され、合わせて約4,500億円規模の案件となっていたが、ドゥテルテ政権末期にいったんキャンセルされ実現していない。
これは南シナ海の領土をめぐる紛争などの外交的関係の悪化が原因かというと必ずしもそれだけではなく、フィリピンは日中を天秤にかけてできるだけ良い借款条件を引き出そうとしてきた。日本の場合は金利が1%ぐらいだが、中国の場合は通常6%、低くて2〜3%ぐらいなので、借款条件交渉で中断しているというのが実態であろう。2022年の大統領選挙を受けてボンボン・マルコス政権が誕生し、2022年7月16日付のロイターによれば、マルコス大統領はこの借款契約について再交渉するように運輸省に指示した。官民パートナーシップを通じた民間資本の活用など、他の資金調達オプションも検討しているという。
(2)東ティモール
港湾整備:ODAか民間資金か
東ティモールは2002年に独立した新しい国である。日本は独立後の東ティモールに対してODAにより様々な支援を行ってきた。ただし、最大の支援国はオーストラリアであり、旧宗主国のポルトガルやEU、米国の支援も大きく、日本はこれらの国に次ぐ規模である。他方で、中国は東ティモールと最初に国家承認をして外交関係を結んだ国である。その後、中国はとりわけ政府の庁舎等の建設を無償援助で積極的に支援してきた。政治的にアピールする案件が多いといえる。
日本は東ティモールの港湾整備に対して、ODA(無償資金協力)で継続的な支援を行なってきた。首都ディリ港の緊急改修計画(2006〜10年、約15億円)で老朽化した港を改修し、ディリ港フェリーターミナル緊急移設計画(2016〜18年、約22億円)では、3隻のフェリー着桟に対応する旅客ターミナルの整備を行った。
他方で、近年では民間資金を利用した官民連携での資金調達手法が世界的に広まっており、世界銀行が技術支援をして、仏企業が資金を出し、それを中国企業が受注した事例がある。ディリから20キロほど西に行ったところのティバール港の貨物専用の新港整備である。
東ティモール政府は、あえて異なる開発手法を採用したと考えられる。日本はこれまで無償資金協力で支援をしてきたが、近年は民間資金を使いながらインフラ支援をするという手法が広まってきており、これまでの伝統的な支援手法が本当に効率的かどうかは、検討する余地があるだろう。
国道整備:日本の円借款を中国企業が受注
また、道路整備分野においても注目すべき事例がある。東ティモールにおける唯一の円借款事業「国道1号線改修事業」(2012-2017-2019、約71億円)である。東ティモールは一人当たり国民所得が比較的高いのでSTEP円借款は使えず、国際競争入札になったという経緯がある。公示入札では、日本企業の応札はなく、中国企業2社が建設工事を受注した。コストの高騰により、当初の国道1号線の工事区間のうち西側をJICAの円借款、東側をADB融資で整備することになったが、JICA融資部分、ADB融資部分のいずれも中国企業が建設受注した。コンサルティング部分は日本企業であったが、その企業は工事完成前の2017年に撤退し、受注した中国企業主導で道路整備がなされ、2019年に完成した。
中国企業が現地に駐在して工事を行い、そこで中国人労働者が働くという状況で、地元の人は中国による支援であると勘違いしていたという記事が毎日新聞(2017年8月2日)に掲載された。これを政治外交的な面で問題視する見方もあったが、JICAとしては入札で最も効率的に工事をする会社を選んだわけで、特に問題はないという見解であった。また、建設された道路も質の悪いものではなく、むしろ質の良いものだと見受けられた。
東ティモールに限らずJICAはこれまで多くの途上国で円借款によって道路整備を支援してきた。しかし近年では道路建設を日本企業が受注することはなく、アンタイドの円借款の競争入札で受注するのは中国企業ないし中国企業を中核とした現地企業との合弁での事業が大半となっている。
(3)カンボジア
最大支援国としての日中の逆転
日本は1992年のUNTAC(国連カンボジア暫定統治機構)以来、カンボジアの新しい国づくりを熱心に支援してきており、2009年までは最大の支援国だった。しかし中国が日本のGDPを抜いた2010年に、カンボジアにおいても中国が最大支援国となった。中国はOECDに加盟していないため正確な援助額は不明だが、カンボジアではカンボジア開発協議会(CDC)が統一的に統計を取っているので、中国の援助額についても正確な数値を把握することができる。
図3は過去30年間の主要ドナーによるカンボジアへのODA 供与額の推移をまとめたものである。それによれば、近年では中国の援助額は日本の3〜4倍の規模となっている。2020年および2021年は日本のODAが急増しているが、これはシアヌークビル港の整備事業への巨額の円借款があったほか、COVID-19対策として保健分野に多額の支援があったためである。日本政府も中国に対抗して対カンボジアODAを増やす努力をしたようにもみえる。
図4は主要国別の投資認可額の推移をまとめたものである。それを見ると、中国の投資額が圧倒的な状況であることがわかる。直接投資の資金規模はODAの約10倍であり、経済的なインパクトは援助よりも直接投資の方が格段に大きい。
日中のインフラ整備による相乗的な開発効果
中国は特にシアヌークビル周辺の開発を手厚く支援してきた。シアヌークビルはプノンペンの南方で、そこに続く国道3号線沿いには中国系企業が多く進出している。また、中国は同じくプノンペンからシアヌークビルに伸びる国道4号線沿いに走るカンボジア初の高速道路の建設を、民間資金を活用した手法で支援した。その結果、国道4号線を使って6〜7時間かかっていたのが、2時間程度に短縮された。
中国は他にもリゾート開発やホテル、カジノなど観光分野への不動産投資や、交通運輸分野やエネルギー分野に関連する企業の投資など、様々な開発事業を行っている。また、縫製業などの労働集約産業への投資も顕著である。リアム海軍基地の改修拡張も中国が請け負い、中国の軍艦も寄港するようになっている。これらは中国の圧倒的な経済的プレゼンスの拡大を象徴する事例といえる。
日本も長年にわたりシアヌークビルの港湾整備・機能拡張を継続的に支援してきた。シアヌークビル港緊急リハビリ事業(1999年)、緊急拡張事業(2004年)、多目的ターミナル整備事業(2009年)、コンテナターミナル整備事業(2017年)、新コンテナターミナル拡張事業(2022年)など、25年の期間に複数のプロジェクトを実施しており、支援額の合計は1,000億円に達する程の規模である。
シアヌークビルの港湾は今後の経済発展の基礎的インフラとしてますます活用されるだろう。支援額について日本は中国に抜かれたわけだが、カンボジアからすれば日本と中国双方の支援を活用し自国の経済発展に繋げているといえる。
日中の役割交代を象徴する事例が、プノンペン郊外の2つの橋である。日本は内戦時代に破壊されたプノンペン郊外のチュルイ・チョンバー橋を、1992〜95年の3年間で再建した(約30億円での無償援助)。この橋はカンボジアにおいて重要なインフラであり、日本がカンボジアに最初に支援した案件の一つであった。2017〜19年には約25億円の無償援助で改修工事も実施した。
経済発展に伴う交通量の拡大に対応するため、中国は2010年にこの橋に併設する形で新たな橋の建設を表明した。約30億円の優遇バイヤーズ・クレジットを供与し、中国企業によって建設が進められ2014年に完成した。融資条件は、20年返済(7年猶予)、金利2%であり、ODAのカテゴリーに含まれうるものであった。
現在カンボジアに行くと、ほぼ同じ仕様の日本支援の橋と中国支援の橋が並んでいる。これを日中の役割交代を象徴するものと見ることも、あるいは日中が競争しながらカンボジアの経済発展に貢献していると見ることもできるだろう。
シアヌークビルの開発やプノンペン近郊の橋の建設は、日本支援事業と中国支援事業が補完関係と相乗効果を持ちうる良い事例として捉えることもできるだろう。
(4)スリランカ
支援国中国の台頭と債務の増加
日本は2009年までスリランカに対する二国間ドナーとしては最大の支援国であったが、中国の融資・援助が急増して2010年以降は中国が最大支援国となっている。スリランカの内戦終結の前後に、当時のラジャパクサ政権は国内の人権問題で国際社会から批判され一部援助を停止される事態が生じていた。そのタイミングで中国はスリランカに対する支援を強化していき、スリランカは大幅に中国に依存するようになっていった。
象徴的な案件として、2011年にコロンボの中心部に中国が無償援助で建設したマヒンダ・ラジャパクサ国立劇場が完成した。他にも、2013年にはハンバントタの国際空港、コロンボ港南ターミナル、バンダラナイケ記念国際会議場の改修、コロンボ—空港間の高速道路の開通などが相次いだ。中国による最大の案件として注目されているのが、コロンボ・ポートシティ事業である。コロンボの海岸沿いに新たな金融・保険・運輸などの総合的なビジネス拠点を建設する巨大事業である。近年の経済危機や債務危機でも中断はしておらず、2030年の完成を目指して進んでいる。
図5はスリランカの対外債務の国別比率の推移を見たものである。2010年に中国が日本を追い越して最大の二国間ドナーとなった後、やがて中国が最大の債権国となった。
中国と日本による港湾支援
中国による案件は様々あるが、特に国際的な注目を浴びたのがハンバントタ港の事業である。ハンバントタはスリランカ南部に位置し、中東からアジアへの仕入れの観点から重要な地域であり、中国にとってはエネルギー資源のルートという観点からも戦略的な重要性を持つ。ハンバントタはラジャパクサ前大統領の地元でもあり、その政権下で多くの事業計画が進められた。
ハンバントタ港の事業は中国輸出入銀行の借款やバイヤーズ・クレジットにより支援された。第1期の工事は2007年に合意され2010年に完成した。融資条件は金利6.3%、返済期間17年(猶予期間4年)であった。ところが返済が滞り、債務を削減する代わりに港の運営権を中国企業に99年間渡すという取引がなされ、それが「債務の罠」であると国際的に非難された。それもあり、第2期は金利2%程度、返済期間19〜20年(猶予期間6〜7年)というODAの範疇に入るような融資条件で合意された。
実は日本もスリランカの港湾整備には長年関わっており、コロンボ港の整備には1980年から約30年間に渡りかなりの円借款を供与してきた。コロンボ港には日本の尾道造船が出資する船舶修理を担う企業もある。また、スリランカ北東部のトリンコマリー港の24時間運用に対応する機能拡張支援を、2017年に無償資金協力で支援した。トリンコマリー港周辺に工業団地をつくる構想もあったが頓挫している。近年、日本とインドが参画することで一時合意していた新しいコロンボ港の拡張事業が、中国企業に発注すると変更された事案も発生し話題となった。
日本にとっても中国にとってもシーレーンは非常に重要であり、両国ともインド洋を取り囲む港の整備に様々な形で資金を投入している。日本は島国なので、例えばマラッカ海峡が封鎖されても少し遠回りしてロンボク海峡を使うということができるが、中国の場合は南シナ海を管理してシーレーンを確保しなければ、インドシナの陸路を使うしかない。そういった事情もあり、客観的に見ると中国にとってシーレーンの確保は日本以上にセンシティブであると考えられる。
日本の対スリランカ外交の積極化
中国が港湾事業を担うケースが増えているのに対し、2015年頃から日本もスリランカ外交を積極化している。日本政府は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想をかかげており、スリランカに対する外交の積極化もその一環であり、経済的な考慮と安全保障上の考慮の両面があると考えられる。
例えば日本は2016年にスリランカに対する無償資金協力「海上安全能力向上計画」に合意し、スリランカ沿岸警備庁に巡視艇を供与した。その頃から要人の往来も活発化し、2018年1月には河野外務大臣(当時)が日本の外務大臣としては15年ぶりにスリランカを訪問した。同年8月には小野寺防衛大臣(当時)が日本の防衛大臣としては初めてスリランカを訪問し、コロンボ港、ハンバントタ港、トリンコマリー港を視察した。2017年以降は自衛隊艦船が毎年トリンコマリー港に寄港しており、海上自衛隊とスリランカ海軍との共同演習も始まった。そこにはオーストラリアも加わっている。
日中は経済インフラ整備だけでなく、この地域の海洋の安全を巡ってそれぞれがイニシアチブをとろうとしている。中国のハンバントタ港建設支援については、インドを取り巻くいわゆる「真珠の首飾り戦略」についての疑念も指摘されている。日本政府は、必ずしも中国への対抗を意識したものではないとしているが、FOIP政策の一環としてスリランカ外交を積極化していると考えられる。
(5)エジプト
カイロの東西における中国・日本の支援
エジプトではカイロの東西で日本と中国がそれぞれ巨大案件を支援している。
日本のODA事業で最大のものの一つは、大エジプト博物館の建設である。これには約842億円の円借款が出されている。大エジプト博物館はカイロの西の方にあり、近くにはピラミッドもある。岸田首相(当時)は2023年にエジプトを訪問した際に、それらに向かう交通手段となる地下鉄の整備にも、1,000億円を上限とする円借款を供与すると表明した。これは同地下鉄整備事業の第3期で、第1期からの3回にわたる円借款の合計額は約1,737億円となる。
他方で中国はカイロの東における新首都建設事業を全面的に支援しており、その資金の大半を融資している。また、カイロから新首都に繋がる重要な交通手段であるLRT(高架鉄道)の建設も支援しており(1,240百万ドル、約1700億円)、第1期および第2期の工事は2022年秋に完成し、すでに運行を開始している。
客観的・中立的に見ると、日中がカイロの東西で巨大案件を競っているようである。実際のところはわからないが、エジプトが日本と中国からの支援をうまく使い分けながら開発を進めているとも捉えられる。エジプトは他にもドイツ、フランス、イギリスからも鉄道やモノレールに関する様々な支援を受けており、バランスを取りながらうまく支援を受けるという意味では、非常に外交力があると見ることもできるだろう。
3.中国関連事業の課題と変化
中国関連事業の中断・見直し
中国は、途上国に対して行う対外経済協力事業について、中国にとっても相手国にとっても利益のあるwin-winの関係であるとしている。それに対して、中国にとって必要な資源の確保、あるいは輸出の拡大という経済的な利益を中心としているという批判や、事業に対する住民の反対や環境への悪影響を無視しているという批判がなされてきた。さらに、スリランカのハンバントタ港プロジェクトのように資金返済のめどが立たなくなった場合に、欧米や日本は債務の繰り延べや一部帳消しといった対応をしてきたが、中国は債務を減らす代わりに港の運営権を取得するなど、二国間での取引を優先しており、そういったやり方に対して他の支援国は強く批判をしている。
しかし近年、そういった中国の事業が相手国の政変あるいは政権交代、そして政権交代とともに表に出てくる住民の反対運動や環境破壊への批判によって、中断あるいは見直しを迫られる事例が頻繁に出てきている(表1)。
先述したスリランカのハンバントタ港は、2015年にラジャパクサ政権からシリセーナ政権に交代した際に事業を見直して第2期の計画は縮小したものの、既に借りた債務を返済するめどが立たず、債務を減らす代わりに港湾の管理運営権を中国に渡した。
マレーシアでも2018年にマハティール新政権が発足した際に、中国が支援するマレーシアの巨大プロジェクト「東海岸鉄道」を中断して見直した。既に建設工事が進んでいたため、その後再開されたが、予算は削減され事業は縮小された。
シエラレオネでは、中国からの融資を受けて首都近郊に空港を建設する計画があったが、2018年の政権交代により新大統領がこの建設計画を中止した。
親中と言われているパキスタンですら、2018年にカーンPTI新首相が就任した際に、カラチとペシャワルを結ぶ鉄道の改修事業の規模削減が行われた。
ミッソンダム(ミャンマー)の中断
最後にそうした事業見直しの典型的な事例として、ミャンマーのミッソンダムの事例を紹介する。ミャンマーは2021年2月に生じた軍事政権によるクーデターが問題となっているが、本事例はそれ以前の出来事である。1988年の民主化運動の弾圧以降2011年の民主化までの間、ミャンマーは国際的に孤立しており、中国への依存が過度に進んでいた。民主化以前は中国が軍事政権を支援していたが、民主化後にいくつかの主要事業が見直された。
代表的なものが、ミッソンダムの事業である。2009年の合意以降、建設が進められたが、ダムの建設によって水位が約100メートル上がり約1万1,000人の住民が移転を迫られるとされた。また、その発電量の90%は中国側に送電され、ミャンマー側に供給されるのはわずか10%とされていた。軍事政権下では建設反対の声は完全に無視されていたが、民主化されたことでそれらが表に出てきて中断されるに至った。他にもチャウピュー港湾整備事業や銅鉱山事業など、中国による大型案件がいずれも中断されたり、規模が削減されたりした。
表1で見たように、ミャンマーに限らず、政変や民主化によって事業が上手く立ち行かなくなったり、途上国側が中国からの多額の借り入れを警戒したりということは他の国々でも生じた。中国としてもそうした国々への投資については慎重になっている。その結果、図2(主要ドナーの東南アジアへの政府開発資金(ODF)額)で示したように、近年の中国によるODF額の減少につながっている。様々な国で巨大事業が頓挫する現実に直面して、中国がより慎重な姿勢をとるようになったことが基本的な原因だと考えられる。
「質の高いインフラ」への変化の兆候
かつては中国が提供するインフラは「質が高い」とはいえなかったが、近年はかなりスタンスが変わってきている。中国政府や国営企業が、相手国での事業に伴う環境問題や住民移転の制約をより認識し始めた兆候もあり、環境アセスメントや住民対策、また事業審査・採算性の判断などをより慎重に行うようになっている。環境アセスメントについてはカナダの企業など、第三国に委託する事例も出てきている。
また、中国が世界銀行・IMFに対抗して独自につくったアジアインフラ投資銀行(AIIB)の融資案件を見てみると、半分くらいは世界銀行やアジア開発銀行との協調融資である。協調融資案件では、環境・社会的インパクトのガイドライン(場合によっては調達ガイドラインも)を共有しており、これを国際規範に対する歩み寄りと捉えることもできる。ただしAIIBは長年世界銀行・IMFやADBなどを管轄してきた「国際協調派」である中国財政部が管轄しており、影響力は限定的であることも念頭に置いておく必要がある。
2019年4月の「一帯一路・国際協力ハイレベルフォーラム」にて、習近平国家主席は一帯一路に関わるインフラ事業について「国際ルールや標準を幅広く受け入れることを指示する」、「質が高く、価格が合理的なインフラ設備を建設する」などと語っている。中国側も、事業にあたっての適切な資金計画の判断や経済合理性に基づく決定をより重視するようになっていると考えられる。
これは国際的圧力によるものか、あるいは中国自身が国際的な貢献をより意識し始めたためかというのが一つの論点である。かつて、日本は経済大国になる過程で同様の国際的な圧力を経験し、あるいは日本自身の国際的な貢献意識の向上により援助スタンスを変更してきた。中国も今後援助ドナーとして「成熟」するにつれ、国際援助コミュニティとの協調を重視するようになるのではないかという仮説もありえる。しかし中国は日本ほどリベラルな変化を遂げているわけではなく、おそらくは事業実施上の実務的な必要に迫られて変化しているというのが、一つの見方である。 いずれにせよ中国の事業は、開放性・透明性・持続可能性についてまだ課題があるため、日本は国際基準としての「質の高いインフラ」を引き続き主張すべきであるが、これによって日本企業の受注につながるわけでは必ずしもないだろう。むしろ、日本のインフラ輸出拡大以上に、中国を国際ルールに引き込み、中国による事業を国際公共財に押し上げることが重要である。インフラ建設の国際ルールの普及と定着、より良い開発を進める国際的取り組みを推進し支援する観点から、こうした方針を堅持し、中国を国際的な基準に取り組む努力をすべきである。
また近年はODAだけでなく民間資金を活用して途上国のインフラ開発を推進する形が増えている(あるいは推奨されている)。競争力を失ってきている分野のインフラ輸出をODAで支援すべきかどうか、検討が必要であり、民間の効率性原理にゆだねることも必要かもしれない。また、将来の有望分野への支援をより強化する方向へ舵を切るという方針もありえるだろう。
途上国債務問題への対応
欧米日の国際援助コミュニティは、2000年に重債務貧困国(HIPCs)への債務帳消しを行い、その後は主として無償援助の形態で行うようになった。ところが、ちょうどその頃から中国がこうした国々への借款を増やし始めた。途上国にとっても中国の資金は魅力的であった。結果として、中国は国際援助コミュニティの債務帳消しにフリーライドして多額の融資を供与し、自国の経済的利益を追求したといえる。
10〜15年経過して、中国による大規模事業の融資資金も返済困難となり、「債務の罠」と言われる状況が生じている。その結果、中国も債務返済繰り延べや部分的な債務の帳消しに応じざるをえなくなっている。アフリカに対しては、商務部の無利子借款について一部の国で帳消しにしている。
2018年の中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)では、アフリカ諸国の債務持続性に配慮する旨の宣言を行っている。また2020年のG20では、返済免除・繰り延べの表明をし、エチオピア・ジブチ鉄道に対する融資期間が10年から30年に延期された。チャド、モザンビークに対する借款の債務再編の報告もあった。2020年五中全会では第14次5カ年計画にて「国際的慣例と債務持続可能性原則に基づき融資体系を健全化」することが表明された。
しかしながら中国が債務返済交渉を二国間で行っている点が問題とされている。スリランカの事例のように事業の運営権を中国側に渡すこととバーターで債務を削減することも二国間交渉で決められた。各国が融資をしている状況で、一国だけがその債権を取り返すというのは国際ルールに反する。中国は新興ドナーということで、欧米日が主導している国際的枠組みとは距離を置く政策をとってきていた。しかし、途上国債務問題は「国際公共財」であり、巨大な債権国となった中国は途上国債務の再編について国際ルールと歩調をそろえることは不可欠である。「抜け駆け」や「フリーライド」は許されず、中国に対する国際金融界からの圧力は非常に強くなっている。
中国財政部はそういった状況について比較的理解があるが、中国国内には対外経済援助に関連する様々な主体があり、すべてが必ずしも理解を示しているわけではない。自国の経済的な利益を優先して考えている姿勢が見られるのも事実である。
したがって、何らかの形で中国を債務問題対応の国際的枠組みへ引き込む努力をすべきである。決して容易ではないが、例えば、世銀・IMFにおける投票権(拠出比率)の拡大とバーターで取引をするとか、あるいは環境、貿易、安全保障など他の問題とリンク(連携)させながら取引するということもあり得る。また、中国国内で中国財政部などの国際協調派の発言力を高める努力を地道に行うというのも一つの方法ではないかと考える。
中国の経済協力政策をどう捉えるか
最後に中国の近年の経済的な台頭とそれに伴う国際開発における影響力の拡大を見ると、かつての日本の経済協力と類似しているという議論もある。そもそも援助・貿易・投資の「三位一体」というのは1970〜80年代に当時の通産省が推進していたアプローチであるし、教育・保健分野を重視する欧米的な援助と比べインフラ支援を重視する点、借款中心である点、多国間の枠組みよりも二国間援助による国益の追求を重視する点、タイド援助が多い点なども類似している。
日本は1990年代にODA事業による環境破壊や住民移転で非難された時期があり、その後「環境社会配慮ガイドライン」を整備したわけだが、中国はそれに遅れること15〜20年で同じような道を辿ってきているように見える。
また援助に関わる汚職の問題についても、1980年代半ばにフィリピンのマルコス政権が倒れたのち、日本の商社や企業がマルコス政権の高官などに賄賂を送っていたことが表沙汰となり、国内外から非難された。OECD/DACでも1989年以来、反汚職に取り組み、日本も1998年に「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD外国公務員贈賄防止条約)」に署名、翌年に発効し海外での贈賄防止について措置を講じることとなった。これはミャンマーにおける中国の事例と重なる。
中国も現在、その様なプロセスを経験(学習)している途上であると考えられる。したがって、中国自身がこれまでの進め方ではうまくいかない現実に直面して、自国・企業の利益保護を追求する上でもスタンスを変えて、国際協調路線に転じる可能性もあるのではないかと考える。ただし、実務レベルではある程度そういった現状がわかってきたとしても、中国の場合は党執行部が最終的に判断しないと動かないので、中国の自主的な変化を期待しながらも、様々な形で圧力をかけるというのが、国際開発に関連した対中政策の方向性ではないかと考える。
(本稿は、2024年10月11日に開催した政策研究会における発題を整理してまとめたものである。)
1 本邦技術活用条件(STEP)の円借款とは、「インフラシステム輸出戦略(平成30年度改訂版)」において、競争力の向上等を図るべく制度改善を行ったもので、本制度により「我が国の優れた技術やノウハウを活用し、開発途上国への技術移転を通じて、我が国の『顔が見える援助』を促進する」ものとして日本タイドとされている円借款のことである。
参考文献
稲田十一(2024)『「一帯一路」を検証する—国際開発援助体制への中国のインパクト』明石書店。
稲田十一(2020)「ドナーとしての中国の台頭とそのインパクト−カンボジアとラオスの事例」、金子芳樹・山田満・吉野文雄編『一帯一路時代の ASEAN−中国傾斜の中で分裂・分断に向かうのか』(第7章)明石書店。
交通経済研究所(2018)『運輸と経済』(特別号「一帯一路」をどう読み解くか?」)12月号。
中国総合研究・さくらサイエンスセンター(2019)『一帯一路の現況分析と戦略展望』科学技術振興機構。
野村総合研究所(2017)「インフラ輸出における日中の競合と補完」『知的資産創造』11月号。
廣野美和編(2021)『一帯一路は何をもたらしたのか』勁草書房。
山田順一(2021)『インフラ協力の歩み−自助努力支援というメッセージ』東京大学出版会。
AidData (2021), Banking on the Belt and Road Insights from a new global dataset of 13427 Chinese development projects, A Research Lab at William & Mary.
Hurley, John, Scott Morris, Gailyn Portelance (2018), Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective, CGD Policy paper 121.
Kitano, Naohiro and Yumiko Miyabayashi (2020), Estimating China’s Foreign Aid: 2019-2020 Preliminary Figures, JICA Research Paper.
Lowy Institute (2023), Southeast Asia Aid Map: Key Findings Report. seamap.lowyinstitute.org
Moramudali, Umesh and Thilina Panduwawala (2022), Evolution of Chinese Lending to Sri Lanka Since the mid-2000s: Separating Myth from Reality, China Africa Research Initiative (Briefing Paper), No.8.
Ngin, Chanrith (2022), The Undetermined Costs and Benefits of Cambodia’s Engagement with China’s Belt and Road Initiative, ISEAS Perspective Issue, No.84, 23 (August).
Parker, Sam, Gabrielle Chefitz (2018), Debtbook Diplomacy: China’s Strategic Leveraging of its Newfound Economic Influence and the Consequences for U.S. Foreign Policy, Harvard Kennedy School.