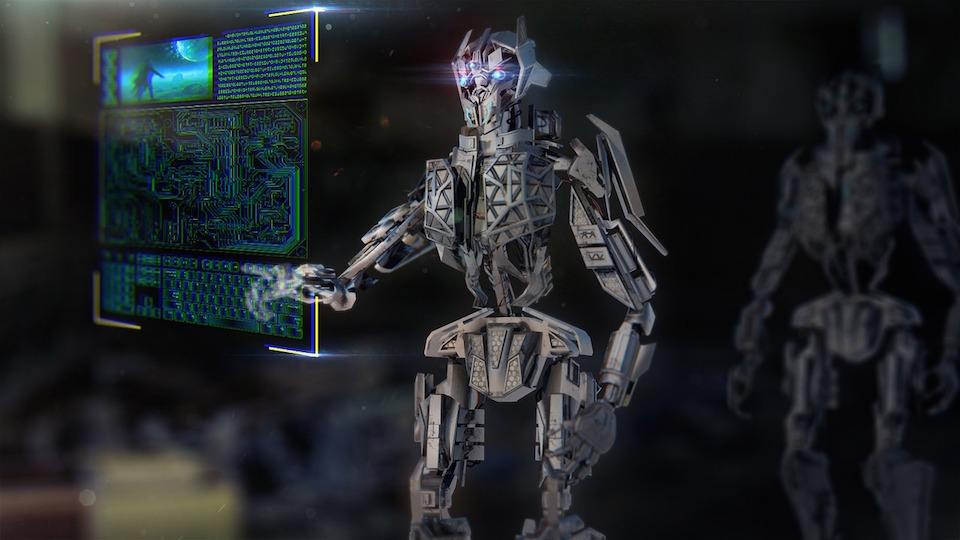はじめに:「作戦術」思考について
まず「作戦術」思考について考えるために、第二次世界大戦(太平洋戦争)における日本軍の戦いを取り上げてみたい。
開戦前の日本は、「対米戦争は長期戦になると負ける」と予想していたので、真珠湾攻撃の目的を、国家レベル(特に海軍)では「短期決戦・早期講和」に置いていた(一方、陸軍は持久戦を目指していた)。その作戦遂行のため海軍は、「米海軍太平洋艦隊の主力を撃破して、太平洋における戦力バランスを日本に優位にする」意図で真珠湾攻撃を行うべきであった。
ところが実際の真珠湾攻撃では、空母機動隊の編成も、実施した作戦も、象徴的に「日本軍が真珠湾を攻撃した」という実績づくりになってしまった。確かに真珠湾攻撃作戦そのものは大成功であったが、それが国家の戦争目的にどのように寄与したかという点から見ると、その評価には疑問が残る。
米国との早期講和のためには、真珠湾に浮かぶ敵艦船の破壊のみならず、遊弋していた米空母を捜索して損耗させることや、真珠湾周辺の石油備蓄基地などを破壊することによって、太平洋正面での米海軍の行動再開を困難にしておくことが必要だった。
そのために日本海軍は、遊撃撃滅作戦を展開したわけだが、その作戦は本来持久戦になる性格のもので、国家レベルの戦争目的とは両立しないものだった。その点から言えば真珠湾攻撃は一挙撃滅を目指した短期決戦型攻撃と言えよう。しかしながら、実際の攻撃では、第二撃を加えることなく、早々と引き返してしまった(そもそもの攻撃部隊の編成が反復攻撃などに不向きであった)。
(戦前は統合司令部がなかったのでやむを得ない面もあったとはいえ)このように戦略と戦術の間をきちんとつないで考える思考(システム)=「作戦術」がどこか欠けていたように思う。
「作戦術」という概念と用語を最初に使用したのはソ連であったが(20世紀初頭)、米国がそれを取り入れたのは1980年代で、そのきっかけはベトナム戦争の敗戦だった。
ベトナム戦争で米軍は、個々の戦闘(戦術レベル)では常に勝利し、敵に対して損害を多く与えたものの、戦争には勝利できなかった(戦略レベル)。その後米国は、この戦争でなぜ負けてしまったのかについて長年にわたって研究してきた。
敗因の一つは、軍事部門が考えて実行すべきことを政治レベルが行ってしまったことにあった。軍事の専門外の政治家が軍事作戦に関与し過ぎ、まるで第二次世界大戦のドイツ軍のような情況となってしまったのである。
具体的に言えば、当時のロバート・マクナマラ国防長官(ハーバード大学でMBAを取得し、フォードのCEOを務めた経済人)は、ベトナム戦争において米軍を指揮するに際して、民間企業の経営管理手法を用いたのである。
当時の米国の戦略レベルの目的は、「ベトナム全土の共産化阻止と国際共産主義の拡大阻止」であったが、戦術では、その目的に直接寄与しない、敵兵の死体や捕虜数、奪った兵器数などを目標として設定し、目標を達成する都度成果としてカウントした。その結果、そのような成果を挙げれば挙げるほど、戦争の悲惨な映像がメディアを通じて全世界に発信され、反戦ムードが米国内で高まり、ついには(米国世論という「重心」をやられて)戦争継続が困難になってしまったのであった。
以上のような例に見られるように、国家レベルの戦略と現場レベルの戦術に齟齬が生じてしまうと、組織の目標達成が難しくなる。米ソはそうした課題を研究した結果、戦略と戦術の中間に、「作戦」というレベルを設定し、戦略がしっかりと個別の戦術に反映され、戦略目標に寄与する内容になっているかを調整する技術を置いたのである。これが「作戦術」である。
現在の日本社会においても、この戦略と戦術をつなぐところが弱いのではないかと痛感している。一番のトップの考え方もいいし、現場も強いのだが、その間をつなぐ形としての全体最適化がうまくいっていない。結果的に非常に効率の悪いことをやってしまう。無駄なことに資源を投資することをできるだけ少なくすることが何より重要ではないか。こうした観点から、日本の安全保障政策を見つめ直してみたい。
1.明治維新と国防
戦前の日本は、(日清戦争の結果割譲された)台湾の統治に続き朝鮮半島を支配して大陸への足掛かりとし、さらに満洲国を建国させて関東軍がその運営にも関与していた。当時の日本は、なぜそのようなことをしたのだろうか。
日本は欧米によって開国させられ、明治維新を迎えた。明治新政府は、欧米列強と不平等条約を結びつつも、富国強兵の道を歩み、やがて欧米列強から半主権国家、半資本主義国家として扱われ、不平等条約を押しつけられた。
開国の直後から、朝鮮半島をめぐって清国と対立するようになり日清戦争へと発展した。当時日本は、朝鮮半島をめぐって、その背後にある清国とロシアの進出をどうやって阻止することができるかが、国家としての重大課題だった。つまり清国とロシアの圧力に対する緩衝地帯の設定と、大陸からのブロック体制の構築を考えたのである。一方、欧米列強に対しては、関税自主権を回復し自分達もその仲間入りを果たしたいという願望を持っていた。
日清戦争では戦争に勝利はしたものの、三国干渉(1895年)によって遼東半島を返還させられた。翌年(1896年)ロシアは、東清鉄道の敷設権を獲得し、1898年には遼東半島の旅順・大連の租借を認められた。その後、日露戦争が勃発すると(1904年)日本は、多数の死傷者を出しつつも旅順要塞を陥落させることに成功し、日本海海戦ではロシアのバルチック艦隊を撃破した。
そうした情勢の中、日本は(三次にわたる日韓協約により)1910年に大韓帝国を併合して朝鮮半島を支配するようになり、1911年には長年の悲願であった関税自主権を回復して欧米列強との関係を高めることができた。
実は満洲国建国もロシアの南下をいかに阻止するかという国家レベルの戦略の一環であった。日露戦争後の1905年10月、桂太郎総理は、中国の満洲権益を狙っていた「鉄道王」と呼ばれた米国の企業家E.H. ハリマンと、満鉄経営のための共同所有を約束した「桂・ハリマン協定」(覚書)を結んだが、小村寿太郎外相の強い反対により破棄されてしまった。米国との戦争(日米戦争)は、中国大陸市場をめぐっての利権争いが根本に存在していたと思う。また当時日本陸軍は、満洲で40万の英霊が亡くなっているのだと主張して、満洲での権益を手放そうとはしなかった。国家の目指す安全保障に向けた政策ではなく、手に入れた権益を守ることだけに集中しがちであったといえよう。
このように日本人には貧乏根性があるのか、一度手に入れた権益は二度と手放さないところがあるようだ。満洲の扱いに見られるように、一庶民の感覚で国家運営をすべきではないと思う。
満洲事変(1931年)を起こし満洲国を建国(1932年)させて日本はその利権を得るなど大陸進出を露わにしたために、ロシアとの間に軋轢が存在した。ノモンハン事件は、国境をめぐる紛争だったが、ロシアはウラジオストクだけではなく遼東半島も狙っていた。ノモンハン事件で日本は、国境紛争に専念してしまったが、本来は西(ノモンハン地域)と東(ウラジオストク)、北の3方向からの攻撃に備えるべきだった。そもそも日本はロシアの意図を正確に理解していなかったのではないかと思われる。
2.戦後の東アジア情勢
1949年に米国務長官に任命されたアチソンは、(共産主義封じ込め政策を継続し)1950年1月、日本・沖縄・フィリピン・アリューシャン列島に対する軍事侵略に反撃するという「アチソン・ライン(不後退防衛線)」の演説を行った。しかしこのアチソン・ラインに台湾・朝鮮半島などが含まれなかったこともあって、(中国とソ連を後ろ盾とする)北朝鮮が南侵して朝鮮戦争が勃発した(1950年6月)。朝鮮戦争では、中国軍(人民義勇軍)が参戦したし、ソ連空軍も参戦したと言われている。そのような情勢の中、米国は韓国を防衛することとなった。
マッカーサーが罷免された後、米国は「ここ(朝鮮半島)でやっていたことは、戦前の日本がやっていたこと(大陸からのブロック体制構築)と同じことをやっていたのではないか」と考えた。
大韓民国という国は、(見方によっては)北朝鮮があるおかげで、しっかりした国になったと言えるかもしれない。韓国は米韓同盟を結ぶことによって安全保障を手に入れた。結果的に朝鮮半島が、日本にとって安泰化したのである。すなわち、どうやったら朝鮮半島が中国、ロシアに取られないかという発想から免れることができたのである。
台湾も、その地政学的位置は、中国が太平洋に進出していくためのルートを抑える要になっている。
第二次世界大戦で日本が敗戦したあと中国大陸では国共内戦が始まり、やがて劣勢になった蒋介石をはじめとする中華民国政府は1949年に台湾に逃れ、大陸は(満洲を含めて)中華人民共和国の支配地域となった。その後、米国が台湾関係法(1979年)を成立させることによって台湾は米国の関与が及ぶようになった。
考えてみると、中国が旧満洲地域(東北三省)を支配してくれたことや、中ソ紛争など中ソ関係があまりよくなかったことによって、日本は安全保障上の有利な条件を得ることができたといえる。戦後日本は、こうした防衛体制をほぼ米国に任せてきた。明治新政府が考えた「富国強兵」政策のうち、「強兵」の部分を米国に任せることによって日本は「富国」に専念することできた。
冷戦時代は、米ソの二極体制であった。対ソ抑止(ワルシャワ条約機構を含む)においては米国とNATOがその役割を果たしており、日本は日本単独で対ソ抑止を行うような立場役割ではなかった。(仮にソ連の攻撃があればそれを)どのように対処していくかのみを考えれば良かったのである。抑止(戦略)をやろうにも、冷戦体制の下で日本ができる状況にはなかったのである。
こうした東アジアの現状を見ると、戦前に日本がやろうとした大陸に対するブロック体制を、戦後はみごとに米国が代替してくれたと言える。
現在の東アジア地域は、日米同盟、米韓同盟、台湾関係法、米比相互防衛条約など、二国間同盟が基礎となった安全保障体制となっているが、米国がハブになってほぼ全体を管理監督しているという状況である。
ロシア、中国、北朝鮮という大陸陣営に対して日本は、米国をひきつけながら、韓国や台湾と共にこの地域の安全保障体制を創っていく最も重要な位置にある。つまり歴史的に見ると、100年前の日本の位置付けに戻ったような状況になっているといえる。
3.アジアの安全保障体制
(1)安全保障関連法の整備と事態対処
ここで安全保障関連法との関係で、事態対処の枠組みがどう変遷してきたかを見てみよう。
先述したように、米ソ冷戦時代の日本は、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態を想定しながら、個別的自衛権をもって対処することだった。
その後、朝鮮半島有事など、日本の周辺地域で平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などが発生したときに対処するために「周辺事態法」が1999年に成立した。そこにおいては、冷戦時代の個別的自衛権の発動に加え、(とくに朝鮮半島有事を想定した)周辺事態への対処、具体的に言えば、米軍への後方支援活動が合法化され自衛隊が日本の領土外での活動が可能となった。
2004年には武力攻撃事態や緊急対処事態などに際して国民の生命・財産の保護を目的として国民保護法が成立した。
そして2015年には安全保障体制の整備に伴い、周辺事態法を見直し、重要影響事態法となった。ここではとくに台湾有事を想定しつつ、存立危機事態への対処として集団的自衛権を行使できるようにした。しかし、国民保護法の修正はなされなかった。
日本は専守防衛型なので、相手の出方次第でこう構えるという発想だ。武力事態対処法でも自衛隊法でも、事態認定をしてから、行動をするという体制になっている。事態認定という発想は、きわめて警察的だ。犯罪か?事故か?など、現場がどうなっているのかという現場情報を収集してから認定する。しかし戦争はそうはいかない。戦争は相手の国家意思の問題であるから、われわれが危ないと考えたらこう行動すると決めて動き出さないといけない。結果的に、それが抑止となる。専守防衛でも抑止を重視するのであれば、このように考えるべきだろう。
(2)台湾有事
2022年8月2〜3日に、ペロシ米下院議長が訪台した直後、中国政府は猛反発し、8月4日から台湾周辺海域で人民解放軍が重要軍事演習を開始した。また2024年5月20日に頼清徳が台湾新総統に就任した直後、中国軍は台湾周辺海域で軍事演習を行った(図表3)。
もし中国軍が、武力侵攻して台湾を占領しようとすれば、当然、米国は奪回行為をするであろうし、日本も存立危機事態に応じた対応をすることになる。米軍の海空戦力を考えると、中国軍が台湾だけを死守しようとしても、周辺からやられてしまうために、中国軍としては図表4にある位置まで守らないと防衛できない。つまり中国軍による台湾への武力侵攻時には、その戦域は拡大することになる。
また東シナ海は150メートルほどの水深なので、中国軍の潜水艦がその能力を発揮して米海軍に対応するためには、第一列島線から太平洋に出て行かなければならない。台湾を軍事的に奪取占領しても、その占領状態を維持できないのでは意味が無くなる。
(3)対中軍事バランス
米中露の核弾頭数を比較してみると、現在、米露は1500発前後で、中国は500発強(2023年5月時点)、対抗できる状況にはない。しかし、2034年ごろには米露に匹敵する数を保有することになるだろうと予測されている。
ただし、核弾頭のストックとローテーションを考慮すると、中国が米国に対抗できるまでにはまだまだと思う。この点で、中国軍による本格的な台湾攻撃力はそれほど喫緊とは思えない。しかし脅しやグレーゾーンの攻撃には注意を払う必要がある。
それではそのような中国に対して、責任ある地位に置かれた日本はどのように食い止めていくべきか。
米日台の戦力を合わせた形で中国と比較して検討してみたい(図表5)。総合数値で比較すると、中国軍4.0に対して米日台軍は3.5と見られる。
米国の中距離弾道ミサイルは、INF条約(注:2019年に米国は条約を破棄)により地上発射型ミサイルは保有しておらず、海洋配備型戦力だけと考えると抑止力として算定できないので、表では空白になっている。
日本が三文書を発出したことにより、それを補完する役割が出てきた。また韓国軍は、対北朝鮮対応の余力があるとみられるので、それ(対空戦力)をこちらに回すという考え方もある。日本は韓国との関係構築はアジア全体の安全保障態勢維持の観点から考えるべきであろう。
(4)戦争目的からの視点
先の大戦における日本と米国の戦争目的を比較してみよう。
日本の戦争目的は、民族平等の実現、植民地の解放、資源保有のための自由貿易体制、中露の南下を阻止することなどであった。ところが日本は、敗戦により国は荒れてしまったが、その後の僥倖もあって戦争目的が戦後ほぼ実現されることになった。満洲地域にしても、中国が支配してくれたおかげで一種の緩衝地帯とすることができた。
一方、米国の戦争目的は植民地の確保、ドイツがソ連と組んで強国となることの阻止、中国市場の獲得の3つであっただろう。ところが、他の欧州列強のように植民地体制を持ちたかっただろうが民族平等思想によって実現できなかったし、ヨーロッパではドイツの膨張を阻止することができたものの、中国では何も得るものがなかった。米国は戦争目的達成よりも日本に対して徹底的に勝つことにこだわり、結果的に戦争目的からは遠ざかってしまった。
国民の意思を反映していくような政策をしたたかに進めるには、武力によるのではないやり方でやる方がよいと思われる。明治政府が掲げた富国強兵の「強兵」をしないで戦後「富国」に特化して取り組んだ道は、冷戦期における安全保障環境においては、ある意味で悪くはなかったのではないか。
トランプ大統領は、就任当時、ドイツと日本に対して各地域での役割を果たすべくやるべきことをしっかりやれと言って政策を進めた。100年ほど前の1900年当時の日本は、中露の進出を抑えるためのブロック体制の構築が重要課題だった。戦後は、それを米国が一手に引き受けてやってきたと見ることもできる。米国の国力や軍事力を利用しつつ、この体制をどううまく維持し、発展させていくか、これが現在の日本にとっての役割だ。もともと日本がやるべきであったことでもあり、したたかにうまくやっていくべきだろう。
4.さいごに:「敵味方」の発想から「共存」の発想へ
米国の考え方は、敵か味方かという二元論的発想が強い。トランプ政権のころ、北朝鮮を攻撃して金正恩政権を崩壊させようと考えたことがあった。それが本当になされた場合、北朝鮮はテロ培養国家になってしまったかもしれない。中東地域やアフリカではテロ組織が本来の国家とは別組織として活動をするようになって国家やその周辺地域を不安定に陥れている。
譬えてみると、西洋医学はウィルスなどをやっつけてしまうが、その後、新たな変異株のウィルスが生まれてくるので、いたちごっこだ。二元論的思考は、世界の安全保障秩序を悪循環にしているようにもみえる。
べき論で考えるのではなく、存在するものを支えつつ、方向を間違えないようにもっていく。周辺に悪い存在がいるから軍事力増強をやるという単純な発想ではなく、悪くなる可能性があるのであれば、それを悪くさせないコントロールする力を持つ。やられるからやるのではなく、やられないようにすることがより賢明なやり方ではないか。
中国は共産党独裁体制の専制国家ではあるが、国としての「体」を成しているために、テロ発生を抑止していると見ることもできる。西洋列強の植民地政策は搾取型だったために、植民地が独立した後、テロ培養国家に変貌しやすかった。一方、日本の植民地支配は同化型だった。その結果、朝鮮民族など日本への恨みを持つようにはなったが、テロ培養国家にはならなかった。
もちろん、現代世界において独裁体制は問題が多いことはその通りだが、一方でテロを培養しない状態を維持することの方が、むしろベターなのではないか。うまく抑止効果を発揮させつつ、完全な敵にもしなければ、完全な味方でもないという政策もありうるのではないか。欧米のように、悪はつぶせという二元論でやるのではなく、日本が第一責任者であれば、「共存」の道をどう探っていくかを考えることが重要ではないかと思う。
かつて冷戦時代は壁をつくり分離することで共存することができた。しかし、現代は一歩間違えばカオス化する、敵対化する脆弱な世界にあるので、「共存」を図るのである。ただ独裁国と共存するためには、完全な敵味方の発想ではないものの、ある程度の力と手段を自前で持っておかなければならない。全てを外国に委ねておくという発想は安易な考えだと思う。
共存の世界は、ある意味で民法的発想の世界ともいえる。刑法の世界は、どちらが正しいかで決着をつけるが、民法の世界はそうではなく、紛争を終わらせるという発想だ。
例えば、自分が買った土地に公然と住んでいたが、後にその契約が無効だったことが判明したケースを考えてみよう。(この場合は民法上の「善意」という自分に所有権が無いことを全く知らず過失もないケースにあたる)。10年間公然と平和にきちんと住んでいた上、相手も本来の権利を主張しなかったので、住んだ人の土地として時効取得が認められるのである。権利を正しく主張する人のための民法である。自分の権利を主張しなければならず、現状を無秩序にしたくないという発想でもある。
国際社会は、どちらかというと、民法的発想である。現在の世界は、国の大きさに関係なく、どの国も同じ主権国家として平等だ。主権国家間の紛争は、無条件降伏させ主権をゼロにするようなことはできない。主権国家は対等だという発想に立った場合には、どちらかをやっつけるという発想よりも、相互の権利を認め合い、共存していく、できればそれをうまく解決していくという民法の精神こそが、国際社会の平和を保つ方法ではないかと考える。
先の不透明な時代にあってゼロから始めて形を創っていくためには、意志力を持った人材が必要だ。答えのある問題ばかり解いてきた人たちは、有能な官僚であり法律の枠内で確実に仕事をすることには長けてはいるが、どのような国家ビジョンをもってどの方向にいくのかを考えることは不得手だ。意思を具現化して行く過程において、この問題をどう考えるか、どうやったらできるか、この情況に対してどうするか、などをしっかり考えることのできるトレーニングをしないと、そのような人材は生まれない。そしてそのトレーニングは個人に委ねるのではなく、組織的に教育していく仕組みが必要である。
(2024年8月6日)