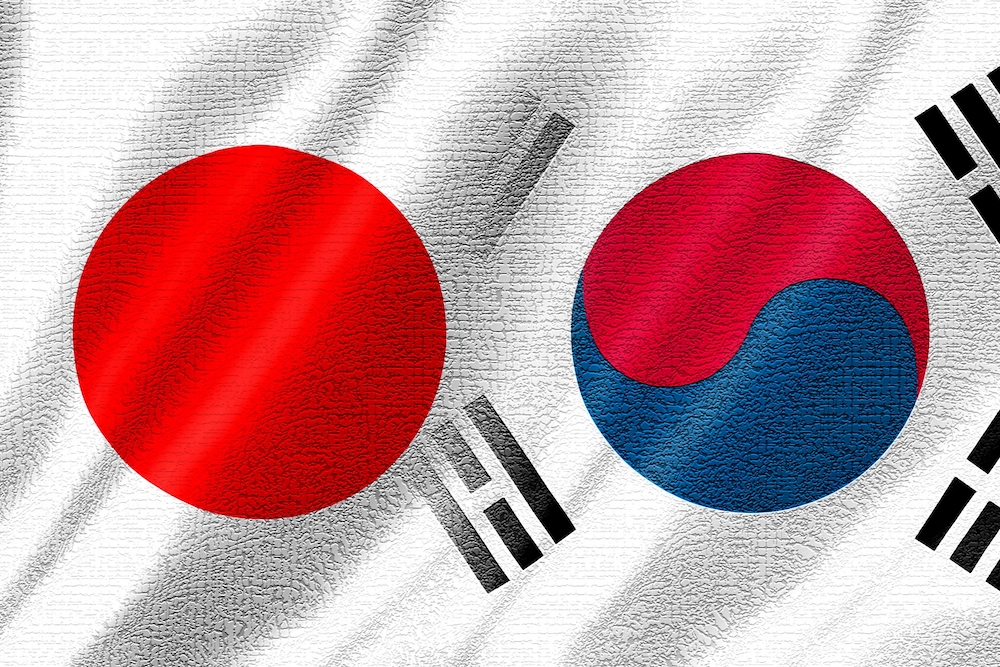現在、日韓関係は歴史問題をはじめ、さまざまな局面で不理解と誤解が高じて収拾がつかないほどになっている。ここで紹介する朝鮮儒教思想の見方を通して、韓国人の対日観を考える上で、その淵源にあるこの民族の思考方式についての理解のヒントになればと思う。
1.韓国人の著した朝鮮儒教史にみる対日観
20世紀に韓国人によって漢文で書かれた朝鮮儒教通史としては、張志淵『朝鮮儒教淵源』(1922年)、河謙鎭『東儒學案』(1970年)、李丙燾『韓國儒學史』(1988年)などがあるが、ここではこの中で一番最初に書かれた張志淵『朝鮮儒教淵源』の、とくに印象的な冒頭の部分から紹介してみたい。
張志淵(号・韋庵、1864-1921年)は、ジャーナリストとして名を馳せた人物で、彼は1905年に日本との間で結ばれた日韓保護条約に関連して、自身が創刊に関与し当時社主になっていた『皇城新聞』に、「是日也放声聲大哭」という題の論説を発表して日本の政策を批判したため、逮捕投獄された。張志淵は、『朝鮮儒教淵源』の著者としてより、むしろこの事件との関連で知られていると言ってもいいかもしれない。
張志淵は、啓蒙思想家であったが、旧来の伝統的儒教式の教育を受けて科挙を受験し、進士試に及第した人物である。そのような張志淵の著書『朝鮮儒教淵源』の冒頭には、次のような文章が置かれている。
爾雅曰、太平之人仁、太平者東海名、即指吾東方也、吾東方之人、其性仁善、故南蠻北狄西戎、皆從虫從犬、惟東方稱夷、夷者弓人也
(大意)爾雅に次のようにある。・・吾が東方の人は、その性が、仁善であり、南蠻北狄西戎には、皆虫や犬の字が入っているが、ただ東方のみ夷と称している。夷は弓人である。
『爾雅』の記述を利用しながら、四夷の中で(東夷以外は)、その漢字表記の中に「虫」や「犬」に相当する文字が入っているが、東夷(=朝鮮民族)には「虫」や「犬」等の文字が入っておらず、「弓の人」であり、他の中華の周辺民族とは違うとし、その独自性や優秀性(⇒「其性仁善」)を強調して述べたのである。
そして朝鮮の歴史、とくに『史記』などに見える「八條之教」によって国民「教化」を行ったという箕子に言及し、次のように述べている。
檀君之季、殷太師箕子避周以來、以洪範九疇之道、教化東方
(大意)檀君時代の末に、殷の王族箕子が周を避けて来て以来、洪範九疇之道をもって東方を教化した。
箕子とは、中国古代の殷から周への易姓革命が起きたときの、殷の王族の一人で、子爵という爵位をもっていたために、箕子と呼ばれた。檀君朝鮮の末期に、周王朝を避けて箕子が朝鮮半島にやってきたが、「洪範九疇」によって朝鮮の人々を教化したという。
それでは「洪範九疇」とは何か。「洪範」とは大きな教えという意味で、その内容が『書経』に載っている。その「洪範九疇」について張志淵は、次のように述べている。
洪範者即易象之原理、而儒教之宗祖也、自古聖帝哲王修身齊家治國天下之大經大法、皆具於洪範一書
(大意)洪範とは、即ち易象の原理で、儒教の大本である。古より聖帝・哲王の唱える修身齊家治国天下の大経・大法は、みな洪範の一書の中に備わっている。
韓国の国旗は太極旗であるが、その図案は『易』の原理で描かれている。洪範九疇は、『易』の原理、儒教の根本の教義であり、箕子はそれを(殷を滅ぼし、周を建国した)周の武王に伝えるとともに、朝鮮にももたらした。そして「八條之教」によって人々を教化したことは、『史記』にも記されているが、張志淵はそれを「洪範九疇」と読み替えたと考えられる。
ちなみに、『史記』には八條の内、三つしか記載されていない上、その内容も「人を殺した者は死をもって償う」などといった刑法規定のようなもので、儒教の教化とはあまり関連がない。
其八條雖遺缼失傅、然孔子賛易曰、箕子之明夷、明夷者其道明於東方也、然則朝鮮雖謂之儒教宗祖之邦可矣
(大意)八條の教えは失われてしまったが、孔子は易に注釈をつけて「箕子の明夷」と述べた。明夷とはその道を東方の朝鮮で明らかにしたという意味で、したがって朝鮮は儒教の宗祖の国と言ってもよいであろう。
『易』明夷の解釈にことよせて、朝鮮が「儒教宗祖之邦」と言ってもよいとまで断言してはばからない。確かに、孔子が生まれる以前に、儒教の根本の教義が朝鮮に伝わっていたことになるのである。張志淵は、ジャーナリストとして近代啓蒙主義的な考え方を身につけた人物であったにもかかわらず、自国の儒教の歴史を振り返って記述するとこのようになる。
是故論語孔子乘桴浮海之志、有欲居九夷之語、盖謂吾東是儒教舊邦、故夫子欲如箕子之布教行道而有是言也
(大意)したがって論語にあるように、孔子は海に浮かべたいかだに乗って出かけてしまおうと述べた。また九夷に住むことを欲するとも言った。出かける先の九夷とは朝鮮、儒教の国のことである。孔子が生まれる以前から箕子によって伝えられた儒教の教えの根本が朝鮮にあるから、孔子も行きたがったのだ。
『論語』にみえるように、中国で「道」が行われないことに対する孔子の嘆きの言葉も、箕子が朝鮮で成功したことにあやかろうとして、海外に行ってしまいたい、九夷(東夷)にでもおろうかと、述べたものだとされる。この解釈は、当時の朝鮮王朝では通説であった。
ただし、残念ながら、孔子の(朝鮮への)東来は実現しなかった。このことについて次のように述べている。
向使孔子果然浮海而志、如箕子之斷行傳教化于吾東、安知吾東一域爲孔教根據之邦、而廣吾東於天下也耶、惜乎、其拘於時勢而終不果行也
(大意)仮にもし孔子が本当にいかだに乗って東方にやってきて、箕子が朝鮮を教化したのと同じようにしていたら、わが朝鮮の地域は、孔子の教えである儒教の根拠の国になっただろう。残念ながら、それは実現しなかった。
こうした内容が、自国の儒教に対する一般的な朝鮮儒学者の見解であった。張志淵は、孔子を朝鮮儒教史の中に取り込みたかったのであろう。
『朝鮮儒教淵源』の冒頭に、上述のような内容がおかれていることに、張志淵の自国の儒教の伝統に対する矜持を窺うことができるが、また、著作年代を考慮すると、無念にも「庚戌国恥」(日韓併合)を経験させられた近代知識人のナショナリズムが、儒教の伝統と結合して、このような形で表出していると考えることもできよう。ただ、このような形の矜持は、朝鮮後期の多くの知識人が小中華の誇りとして共有するものでもあったのである。
現代韓国においても、先述の国旗以外でも、紙幣の肖像画など、儒教がいろいろなシンボルとして使われている。
例えば、1000ウォン札に描かれているのは朝鮮時代を代表する朱子学者・李退渓(李滉、1501-70年)で、5000ウォン札には、朝鮮時代のもう一人の有名な朱子学者・李栗谷(李珥、1536-84年)が描かれている。1万ウォンは、ハングルの創成者・第4代世宗大王が、5万ウォンには、李栗谷の母親である申師任堂が、それぞれ描かれている。一方、日本の紙幣には啓蒙思想家が多く登場しており、それぞれの国柄が表れていると思う。
2.朝鮮の小中華思想
次に、前節で述べた朝鮮の小中華思想について検討する。
日本の朝鮮史学では、朝鮮の中華思想を「小中華」というが、それは中国の大中華との対比でそう呼んでいる史料の用語に基づくものである。しかし、韓国の学者の中には、「小」の字を避けて「朝鮮中華」と呼ぶ人もいて有力である。
1644年、流賊李自成が、明の最後の皇帝・崇禎帝を自殺に追い込んで、明が滅亡し、さらにその李自成を逐って清が北京に入場したことは、朝鮮王朝の両班士族にとっては驚愕すべき大事件であった。清を建国した女真は朝鮮では、「野人」と呼ばれ、南の「倭」とともに野蛮な夷狄として常に侮蔑の対象であった。中国で「北虜南倭」と称して、周辺国を下に見ていたのと同様である。ちなみに、日本人は、日本は東アジア(中国・朝鮮)の東方に位置すると考えているが、彼らの感覚からすると日本は南方に位置するようで、「南倭」と表現している。
ところが朝鮮は、そのような倭と野人によって相次いで攻撃を受けた。いわゆる「倭乱」(日本でいう「文禄・慶長の役」)と「胡乱」(丁卯・丙子の乱)である。「倭乱」については、明の援軍と朝鮮の李舜臣の活躍などによってなんとか倭軍を撃退したものの、「胡乱」では、屈辱的な結果をもたらした。親ら出陣してきた清の皇帝・太宗に、朝鮮国王仁祖(在位1623-49年)は、1637年、首都漢城の南を流れる漢江のほとりの渡し場・三田渡に設けられた受降壇で、三跪九叩頭の礼1)を(臣下の面前で屈辱的に)行って臣従を誓わせられたのである。その後、朝鮮が清に降伏したことを記念する大きな碑(大清皇帝功徳碑、1639年)まで作らせられ、それは現在でも残っている。
夷狄である清の中原支配は当然長くは続かないはずだという、朝鮮側の予測に反するような事態が現出する。朝鮮では、清が支配する中国の地は中華の文明が消滅した「腥穢讐域」(生臭く汚れた仇敵の地)となり、中華の文明や明王朝の正統な継承者は、わが朝鮮王朝だという(小中華の)考え方が広まっていった。大本の大中華が消滅し地上に存在する中華は朝鮮のみだと考えて、両班士族は自国のことを小華、小中華と称し、そのことに強い誇りを持ったのである。
清とは君臣事大の関係(朝貢関係)にあったので、朝鮮からは朝貢使節が派遣され、年号も公的には清の年号を用いなければならなかった。しかし、両班士族は私的な書簡や墓誌等には、明最後の年号崇禎を本来の14年より延長して(19世紀末ごろまで)使い続けた2)。そこには、朝鮮は明の後継者であるという意味と、中華の文明を朝鮮こそが引き継いだという自負を見て取ることができよう。
しかも、国内には明の皇帝を祀る施設が設けられた。師である朱子学者・宋時烈(号は尤庵、1607-89年)の付託を受けていた権尚夏(号は遂蕃、寒水斎、1642-1721年)は、1703年、即ち明滅亡60年後の同じ甲申の年の前年に、清州近郊の華陽里(現、槐山郡青川面)に、万東祠3)を建てて、「再造之恩」(倭乱の際に、宗主国明の救援軍のおかげで朝鮮が滅亡を免れたとし、その恩義を強調する理念)を表し、(援軍当時の)明の万暦帝と最後の皇帝・崇禎帝を祀ったのである。
さらに翌1704年には、ソウルにも王命によって万暦帝を祀る大報壇(皇壇)が設けられ、49年には洪武帝、崇禎帝も合祀された。万東祠は、当初私的なものであったが、後には朝廷(政府)の援助を受けるようになり、万東廟と呼ばれるようになった。ソウルに設けられた大報壇には、朝鮮王自ら出向いて祭祀を行った。
3.夷と華の狭間で
朝鮮王朝では、ブレーンたちによって当初から儒教社会の確立が目指された。しかし、儒教の理念とは一致しない旧来の習俗慣行は、一朝一夕に変化し得るものではなく、個人の救済や国家の安寧を祈る仏教、社会生活に密着したシャーマニズムや各種民間儀礼等は生き続けた。
やがて儒教の理念を厳格に守る必要性を主張する、士林と呼ばれる人々が科挙を通じて進出するようになると、彼らは「朱子家礼」4)実践の強化、「朱子増損郷約」5)による郷村教化、「三綱行実図」6)刊行や、孝子、忠臣、烈女の 表、即ち国家的表彰制度による民衆教化等の施設を推し進め、儒教の価値観や倫理綱常が普遍的な意味を持つという認識が、次第に庶民にも浸透していった。
しかし朝鮮は、中国を中心とした華夷秩序に照らせば、東方の夷狄、つまり東夷となる。四夷の中では、他の夷狄、即ち南蠻・北狄・西戎とは異なり、「夷」字の中央に「人」を含むとはいえ、本来夷狄である朝鮮が中華(人)になれるのかという根本的な疑問は、両班士族にとっては是非とも解決しておかなければならなかった。
誠に幸いなことに、華と夷との関係は、出自や血統にかかわるものではなく、文明と野蛮との関係に対応する側面がある。唐中期の文人であった韓愈(768-824年)の『原道』に次のような文章がある。
孔子之作春秋也、諸侯用夷禮則夷之、夷而進于中國、則中國之
(大意)孔子が『春秋』を作ったとき、出自が中国の諸侯が夷狄の習俗に従ったときは、これを夷狄として取り扱い、出自が夷狄でも中国の文化を慕い、礼を用いるときは、これを中国の諸侯並みに記した。
つまり、中国でも、中華と夷狄の区別は、居住地域や民族種族に必ずしも関わりなく、中華の文明に浴しているか否かが重要だという主張である。出自が東夷の朝鮮の両班士族は、当然この主張に強く共感した。
さらに朱子学者・宋時烈は、別の根拠を挙げて説明している。
中原人指我東爲東夷、號名雖不雅、亦在作與之如何耳、孟子曰舜東夷之人也、文王西夷之人也、苟爲聖人賢人、則我東不患不爲鄒魯矣、昔七閩實爲南夷區藪、而自朱子崛起於此地之後、中華禮樂文物之地、或反遜焉、土地之昔夷而今夏、惟在變化而已(『宋子大全』巻131)
(大意)『孟子』に、舜も東夷の人なり。文王も西夷の人なり、とある。いやしくも聖人賢人となることができれば、わが朝鮮も鄒魯(孔子・孟子の生地)になり得ないわけはない。昔、福建は閩と呼ばれ南方の夷狄の住む地であった。しかし南宋時代に朱子がこの地から出て以後は、もともと中華の礼楽文物が存在した地も、福建にかなわなくなっている。夷狄の地が中華の地に変化したのである。
つまり、朱子学の興隆によって、朝鮮も福建と同様に中華になり得る、否、実は既に中華になっているのだという誇り高い発言とも理解できよう。
夷狄も中華になれるという考え方は、朝鮮の知識人が野蛮と考えていた清朝でも同様にとられていた。清朝は、出自が夷狄の清が漢族を支配していては反乱が起こりかねないので、自ら中華になるために漢族以上に儒教を重視する姿勢を示した。清は、朱子を特別に評価している。そのため北京にある孔子廟は孔門の十哲を祀っているが、清はそこに朱子も追加した。この点でいえば、清と朝鮮は非常に似た考えをもっていた。
両班士族は中華の人、つまり普遍的な価値の体現者として、中華の文明に必ずしも浴しているとはいえない庶民に対して優位に立ち、その権威を高めることができた。したがって両班士族は、自国を更に理想の中華に近づけるため、自身の存在価値をかけて努力した。とくに清が中国支配を安定させて、朝鮮が唯一の中華になって以降は、その努力は徹底さを加え、宗族制度をはじめとして、場合によっては中国以上に理念に忠実な儒教的伝統が確立していった。
明の滅亡の要因を、朝鮮でも既に李退渓が強く非難していた陽明学という異端の跋扈、即ち中華の文明の堕落にも求めた両班士族は、専ら(陽明学等の)異端を排除し朱子学の純粋さを追究した。そこで学説のそれなりの多様性にもかかわらず、朱子個人や朱子学に対するあからさまな非難攻撃は皆無という朱子学一尊の状況が現出した。
一方、日本(江戸時代)は儒教が朝鮮ほどに普及していなかったこともあり、朱子学批判をはばからずに行った。その辺は、朝鮮と日本の大きな違いだったといえる。
朝鮮の知識人はさまざまな党派を形成し、それらが激しく戦ったが、その党争の場では、相手方を儒教、朱子学に反する「斯文乱賊」(注:斯文=儒教)と攻撃して、弾圧を加えることができた。これが学問上の問題にとどまらず、王朝の存亡にもかかわるという共通認識が存在したからだった。
朝鮮においては、純粋な本来の朱子学を求めて、研究や考証が深まった。朱子の著述や発言にまま見られる矛盾に、それぞれの立場から整合性を持たせようとする注釈や著作がさかんに行われた。例えば、宋時烈の『朱子大全箚疑』、宋時烈と韓元震(号は南塘、1682-1751年)の『朱子言論同異攷』、李震相(号は寒洲、1818-86年)の『理学綜要』等の業績がある。
また研究の結果得られた、現在からするとかなり独特に見える「朱子学」説には、畿湖(京畿・忠清道)地方の気を重視する学派に属する任聖周(号は鹿門、1711-88年)の性即気説と、嶺南(慶尚道)地方の理を重視する学派に属する李震相の心即理説がある。中国の朱子学理解からすれば、性即理が基本であるので、任聖周の性即気説は朱子学といえるかどうかという見かたもある。また李震相の心即理説は、陽明学のようにも理解され、そのように批判されたりもした。
いずれも地縁、血縁で結ばれた両班士族が、それぞれの地域の学説を継承発展させた末に唱えられるようになったものであった。
両班士族の党派は、どのように形成されたのか。その基本は、学縁、地縁、血縁による、両班士族の人間関係に基づいていた。その結果、党派は(政治結社の類ではなく)両班士族の人間関係そのものが反映し、敵対関係に陥りやすい。そのため父親(先祖)の党派の系譜を子や孫が引き継ぐ場合が多い。このことについて韓国の学者の学説の中には、こうした党派の存在によって多様な議論が可能になったと評価するものもある。
もう一つ日韓の違いとして指摘しておきたいことは、日本の儒学者はほとんどが政治に関与できなかったが、朝鮮では中国と同様に、科挙制度があったために儒者は即政治家という点である。日本の儒学者は、極端に表現すれば、政治(徳川政権)にとって、故事来歴等を調べる道具、いわば「百科事典」の代わり、また政治を粉飾する「太鼓持ち」に過ぎなかった。
この違いは現在の日韓の学者と政治家との関係にもそのまま反映している。例えば、ソウル大学などの教授が、大臣(長官)になるケースはしばしば見られるが、日本では学者が大臣になるケースは非常に希であろう。
余談になるが、日本の儒学者の墓は、教科書に登場するような有名な人物であっても、非常にみすぼらしいのに比べ、朝鮮の儒学者の墓は大きくて非常に立派なのである。以前、太宰春臺の墓(東京都台東区・天眼禅寺)に行ったことがあるが、非常に小さい普通の墓であった。江戸時代の「寛政の三博士」(古賀精里・尾藤二洲・柴野栗山)と呼ばれる儒学者一族の墓は(東京都文京区・大塚先儒墓所)、少し前まで誰にも見向きもされず、狭くて「儒者捨て場」とさえ言われていたほどである。
4.日本の古学派と朝鮮知識人の対日観
ここでは二人の朝鮮時代の知識人を取り上げて、伊藤仁斎(1627-1705年)や荻生徂徠(1666-1728年)など日本の古学派について彼らがどのように見ていたかを、その文献をもとに浮き彫りにしてみたい。
(1)丁若鏞
丁若鏞(号は與猶堂または預猶堂、俟菴、茶山など、1762-1836年)は、通例「実学」思想を集大成したとされ、非常に高く評価されている知識人である。若いときに『天主實義』等の天主教関係の書物に触れ、その影響を深く受けて、朱子学とは異なる独特な学説を確立した。数百巻に及ぶ彼の著作は、儒教経典の注釈を中心にして、経世の書、医学書、地理書など、実に幅広く多彩である。
現在でも、韓国のカトリック教会関係者の中には、丁若鏞はカトリック信者だったと主張する人もいる。それは、彼が党派の中でも「南人」に属しており、彼らの地縁にはキリスト教に傾倒した人がいたり、朝鮮時代に初めて中国に渡って本格的な受洗した人物がいたこと、丁若鏞の兄弟やいとこが朝鮮時代後期のキリスト教受難時代(辛酉教難)に殉教したことなど、キリスト教との関係が深いことが背景にある。そして丁若鏞自身も天主教との関係を朝廷より疑われ、18年に及ぶ長い間、全羅道康津郡に流刑に処せられた。
それでは、日本の古学派についての丁若鏞の見解を見てみる。
具体的な学説に関してはともかくとして、日本で伊藤仁斎、荻生徂徠、太宰春臺(1680-1747年)のような学者が輩出していることについて、丁若鏞はかなり好意的に見ている。ただし、丁若鏞が直接、伊藤仁斎や荻生徂徠などの著作に触れて見解を述べたというよりも、当時太宰春臺の著『論語古訓外傳』に述べられた日本の儒学者の見解を引用して、批判を加えている。
太宰春臺の『論語古訓外傳』は、朝鮮にも伝わっており、その中に伊藤仁斎や荻生徂徠、太宰春臺等の見解が示されていて、それを読んで丁若鏞や後述の金邁淳は日本儒学者の説を(間接的に)知ることができたのである。
日本今無憂也、余讀其所謂古學先生伊藤氏爲文、及荻先生・太宰純等所論經義、皆燦然以文、由是知日本今無憂也、雖其議論間有迂曲、其文勝則已甚矣、夫夷狄之所以難禦者、以無文也(『増補與猶堂全書』詩文集巻12、日本論1)
(大意)古学派の伊藤、荻生、太宰等が論じている経典解釈を読んでみると、文が燦然として輝いているので、これにより日本について憂うること(朝鮮に攻め入ること)はない。ただしその議論は曲がりくねってくだくだしいが、その文が優れていることは優れている。夷狄は制御しがたいが、それは文がないためだ。
倭寇や倭乱等で朝鮮王朝にとって大きな脅威であった日本であるが、仁斎の文章、徂徠、春臺の経説をみる限り、議論には不十分なところがあるが文は備わっている。夷狄が制御しがたいのは文がないからで、日本に文が存在する以上、今後は以前のような脅威にはならないであろうというのである。
大抵、日本本因百濟得見書籍、始甚蒙昧、一自直通江浙之後、中國佳書、無不購去、且無科擧之累、今其文學遠超吾邦、愧甚耳(同上、詩文集巻21、示二兒)
(大意)だいたい日本は、百済より書物を得て見ている。初めは甚だ蒙昧だった。江戸時代になると中国の江蘇や浙江と直接取引をするようになって、中国のよい本で買わないものがないほどだ。しかも科挙という制度がないので、いまその文学はわが国を超越しており、甚だ恥ずかしいほどだ。
日本は中国の江南から直接良書を購入するようになり、しかも、朝鮮王朝に存在するような科挙の弊害がないこともあって、文学は朝鮮王朝をはるかにしのいでいるとまで述べている。しかし、上記3人の学者の反朱子学的な学説に関しては、丁若鏞は批判的である。
丁若鏞には、古今の注釈をでき得る限り渉猟して検討した『論語古今註』という著作がある。この中には、仁斎、徂徠、春臺の解釈を、春臺の『論語古訓外傳』から引用して、批判を加えており、そこから彼の古学派に対する反応を窺い知ることができる。
太宰純、日本名儒也、其所著論語古訓外傳、祖述皇侃、詆排朱子章句、異哉、一自風氣、如烟冪霧漲、至及海島之中也、以論語有牢曰憲問一文、遂以七篇爲出琴原二子之手、其言之乖巧、類如此、其淵源、蓋出於伊藤維楨、而轉轉磯激、放肆至此(同上、詩文集巻14、跋太宰純論語古訓外傳)
(大意)太宰は日本の名儒である。彼の著した『論語古訓外傳』は、皇侃7)を祖述し、朱子の章句を退けている。一時の風気が煙幕の如く広がっていて、海島の中によどんでいる。そのような日本の学説を見ると、おかしく見える。論語「牢曰」「憲問」の琴牢と原憲の二人の名から、『論語』はそれぞれが前編と後編に記録したものだとする春臺の解釈は、甚だ巧妙だ。その淵源は、伊藤仁斎からでており、次第に過激になってきたのである。
太宰春臺を「日本名儒」とほめながら、『論語』子罕篇の「牢曰」、憲問篇の「憲問」のように、子張(琴牢)と原憲の名が記されているのを根拠に、『論語』20篇のうち、前半10篇が子張、後半10篇が原憲の記録したものだという、春臺の説を挙げて、言い方が巧妙で狡猾であるとするなど、甚だ批判的である。また、この春臺の説が仁斎から出てものだと推定して、次第に穏当を欠く過激で放恣な論になったとしているのである。つまり朱子の解釈と違うとして、このような批判が出てきたのである。ただし、この見解は、日本では肯定的に受け止められている。
具体的な経説に関して例を挙げて見てみよう。まず、雍也篇の「季康子問、仲由可使從政也與」の「從政」の解釈を取り上げる。朱子の『集注』では、「從政、謂爲大夫」としており、政に従うのは大夫であると解している。ところが、徂徠や春臺の解釈はこれと異なっている。
丁若鏞は、二人の説を次のように反駁する。
荻曰、爲政者大夫、從政者士(注:純云、春秋之世、諸侯之國、爲政者、必其正卿一人)
駁曰・・・今必欲一反朱子之説、壓之曰、爲政者大夫、從政者士、亦豈非心術之病乎
(同上、論語古今註巻3)
(大意)徂徠は、政をなすのが大夫で、政に従うのが士だという。いま必ず朱子の説に反対しようとして強引に、政をなすは大夫、政に従うは士といっているのは、心がねじけているのである。
徂徠が政をなすのは大夫、政に従うのは士というように、いわば大夫と士の役割を区別する解釈をしているのに対して、丁若鏞は、徂徠の解釈を朱子の説に反対すること自体を目的として下されたものと看做し、心がねじけていて動機が不純であると非難するのである。徂徠の解釈は、或いは日本の武士の社会を背景に持つものともみられようが、朝鮮王朝の士大夫の社会に生きていた丁若鏞の目には、上記のように映ったのである。
例えば、忠臣蔵をみても、大石内蔵助は大夫と呼ばれていた。ゆえに家老クラスが政治をするのであって、平侍はそれに従う者だとするわけであろう。日本人の目からすれば、そのような解釈も自然ではあるが、日本の現状を知らなければ、とんでもない解釈だと見えるだろう。
もう一つの例を挙げよう。衞霊公篇の「子曰、有教無類」に関して、朱子の『集注』は、「人性皆善、而其類有善悪之殊者、氣習之染也」(大意:人は生まれながらにしてみな善であるから、概ね善悪の区別があるとすれば、気や習いによって染まっていくのである)と解している。いわゆる性善説の立場をとる。
ところが、春臺の解釈はそうではない。丁若鏞は次のように述べている。
純曰、朱子以爲人性皆善、此祖述孟軻、而叛仲尼
案、不信孟子、非異端乎、孔子言下愚不移者、謂其識見愚迷、不知徙義也、豈謂本性有善悪乎、太宰之學、不知心性爲何物、激於宋儒、竝斥孟子、謬妄甚矣(同上、巻8)
(大意)朱子は人の性は皆善というが、これは孟軻を祖述したもので、仲尼(=孔子)の考えに反するといっている。
私が思うに、孟子を信じないのは異端ではないか。孔子が下愚は移らずというのは、それは識見が愚昧で義に移ることを知らないからだ。もともと性に善悪があるわけではない。性は善であるが、どうやって義に移るかわからないので、下愚は移らないというのである。太宰は、性が何なのか全く理解していない。朱子をはじめとする宋儒に刺激されて、孟子まで退けてしまった。甚だとんでもないことだ。
太宰春臺は『孟子』自体に批判的なのであり、朱子の説は孟子の性善説を継承するものであって、孔子の本旨とは異なるという立場をとっているのであるが、丁若鏞は、朱子学とは異なる学説の持ち主であったが、孔子⇒孟子⇒程朱(程顥・程頤・朱熹)という儒教の道や学問の継承関係については肯定する立場であったから、孟子を信じないのは異端であるとまで述べ、春臺は心性論が全く分かっておらず、宋儒(程朱)に刺激されてそれに反対しようとするあまり、孟子まで斥けようとしており、でたらめも甚しいとするのである。
(2)金邁淳
金邁淳(号は台山、1776-1840年)は、丁若鏞と同時代の人物で、朋友関係にあった。彼は、『朱子大全箚疑問目標補』という『朱子文集』の注釈書を著した篤実な朱子学者であるが、古文の文章家としても知られ、その学徳は一世を風靡したとされる知識人である。
金邁淳の古学派に関する見解を見てみよう。金邁淳は、春臺の『論語古訓外傳』に附した題の中で、日本の儒学の現状について次のように述べた。
日本之俗。精技巧習戦闘、文學非其長、而□明季以來、稍稍有讀書稱經生者云(同上巻8、題日本人論語訓傳)
(大意)日本の習俗は、戦闘には優れているが、文学は優れていない。しかし明末ごろより少しずつ読書をして儒学者と称する者が出てきている。
日本の儒教の水準について、近来、大分改善されているという認識は持っていたが、基本的には低い評価しか与えていない。彼は、この題の存在からも分かるように、丁若鏞と同じく、春臺の『論語古訓外傳』に目を通しており、これについて次のように述べている。
嘗見日本人太宰純所著論語訓傳、凡言仁必以安民釋之、凡言禮必以儀制釋之、力斥集註本心天理等訓、以爲釋氏空虚之學、又曰、私欲淨盡、乃禅家修菩薩之教、心之有私欲亦理也、若果淨盡、則非人也、其説與阮氏不謀而同(同上巻17、闕餘散筆)
(大意)嘗て日本人春臺の著した『論語古訓外傳』を見たが、仁についていうと、必ず安民で解釈する。礼については必ず儀制と解釈する。努めて『集註』の本心天理等の解釈を斥けて、仏教の空虚の学と同じだとまで言っている。また私欲を浄化することをいうが、禅宗のいう菩提悟りの教えと同じだとも言っている。心にはもともと私欲があるのが理であって、それをなくしたら人ではないと主張するのは、清の学者阮元と全く同じだ。
春臺は『論語』の仁や礼を、「安民」や「儀制」と解釈する。そして朱子が『集註』で、仁や礼について、本心、天理等の概念で解釈し、また、私欲を滅することを主張するのは、仏教と同じであると斥ける。また、心に私欲があるのが道理であり、もしそれが全く無くなったら、もはや人ではないと説く。このような春臺の説は、金邁淳の目には、清の阮元8)の説と似ていると映ったのである。ただ、春臺の場合と阮元の場合とでは異なる点もある。
朱子学では、天理を存して私欲を去るとしており、心の中の理を発現させて私欲を閉じ込めるという考え方なので、春臺の考え方とは方向が逆になる。
さらに、前述の資料に続けて金邁淳は、
但純則罵詈程朱、不遺餘力、又上及孟子、以性善爲謬説、而阮氏則雖於程朱内懐訕誹、而不欲顯肆口氣、孟子得與論語并擧、不失聖賢之尊者(同上)
(大意)春臺は程朱の悪口を言っており、余すところ無く、ついでに孟子まで批判して、性善説は間違いだと主張している。阮元は、朱子学について心の中で非難はしていたかもしれないが、具体的に言葉に表現して批判はしなかった。孟子は論語と並挙されていて、聖賢の尊を失っていない。
春臺は程朱を罵って余すところがなく、更に『孟子』まで批判してその性善説を誤まりだとした。しかし、阮元は、程朱について心の内では批判的であっても、露わに口に出すことをせず、『孟子』も『論語』と同じく経書として扱い、敬意を示しているというのである。両者の違いが生じる理由を、金邁淳はつぎのように述べる。
日本僻在海外、初無君師之教、故得以自行自止、無所顧憚、而中州則歴代崇奉、既有彝典、并世閑衞、不無正論(同上)
(大意)日本は海の外の僻遠のところにあり、初めから君師の教えがない。故に勝手なことをやっており、はばかるところがない。しかし中国は歴代にわたり孔子・孟子を尊重しているので、心の中に定まった規則があり、正論はなくならない。
日本は遠く海外の僻地にあり、君を尊んだり師を敬ったりする道徳性が全く欠如している。したがって、春臺のように自己本位で遠慮というものがない。それに対して中国には、儒教の伝統が存在するから『孟子』も尊ばれ道徳性も備わっている。正学である朱子学が必ずしも守られているわけではないが、正論は保たれているのだというのである。
金邁淳は、春臺の『論語古訓外傳』に附した題でも、ほぼ同じことを述べた後、総括して、
日本書籍、余不能多見、而使其學術皆如此、則眞所謂不如亡也、蠻夷鴂舌、不聞大道、啁啾咿嚶、自鳴一隅、誠若無足道者(同上巻8、題日本人論語訓傳)
(大意)日本の書籍を私は多く見ることはできないが、その学術はみなこの程度であるからなくともいい。夷狄が遠方でわけのわからない言葉で何を叫ぼうと、それを論ずる必要はない。
日本人の著作をそれほど多く読むことはできないが、学術が皆この著作のようなものであれば、ない方がましであり、夷狄が遠方でわけのわからない言葉で何を叫ぼうと、それを論ずる必要はないというように、甚だ厳しい姿勢を示しているのである。このような強硬な発言の背景には、或いは、阮元や毛奇齢等の新奇な説(清朝考証学)に魅せられ評価する知識人が一部存在する、当時の朝鮮王朝の学問のあり方に対する金邁淳の危惧があったのかもしれない。
朝鮮の知識人である丁若鏞と金邁淳は二人とも、古学派の個別の学説の内容への反駁はもちろんだが、根本として心がねじけているということを主張する。そこには彼らが考える儒教の道徳性、倫理性を普遍化する観点があり、朱子の学説に反するような説を唱えることはまだしも、その根本で心がねじけているとして倫理性の欠如を批判するのである。
注)
1)三跪九叩頭の礼 清朝の敬礼法の一つで、三たび跪き、九たび頭を地につけて拝する礼。皇帝に対する臣従の意を示す。
2)年号「崇禎」 明最後の年号。1628-44年間。朝鮮王朝では、例えば、崇禎紀元後263年(1890年)、崇禎紀元後再庚午(1690年、2回目の庚午の年)のように使用した。
3)万東廟 権尚夏が師・宋時烈の付託を受けて、その死後15年目に、明の万暦帝と崇禎帝を祀る祠宇をつくった。1703年に完成。名称は、「荀子」の「其万折也必東、似志」による。中国大陸の大河は、基本的に東に流れているが、黄河に見られるように、河は曲がりくねりながら流れていく。しかし最終的には必ず東の海に入るので、それを朝鮮の明に対する事大の誠意に譬えて表現したのである。
4)朱子家礼 南宋の朱憙(朱子)によって著されたとされる冠婚喪祭の四礼に関する儀礼書。
5)朱子増損郷約 宋の呂大臨の著作を、朱子が増補したもので、徳業相勧、過失相規、礼俗相交、患難相恤を骨子とする郷村教化のための書。
6)三綱行実図 世宗の時代に、中国や自国の古今の書物の中から、三綱(父子、君臣、夫婦の義をいう)に関する孝子・忠臣・烈女を各々110名ずつ、計330名の逸話を集め、図入りで解説した書物を編纂し、刊行した。その後、その節略本や、ハングル訳本、さらに続編等が編まれた。
7)皇侃(488-545年) 六朝時代の南朝梁の儒者で、『論語義疏』を著した。この書は中国では伝承されず、日本に古い時代に伝わって知られていた。それが清朝の時代に、逆輸入された。
8)阮元(1764-1849年) 清代の政治家・学者。
(本稿は、2019年7月10日に開催された政策研究会における発題内容を整理してまとめたものである。)