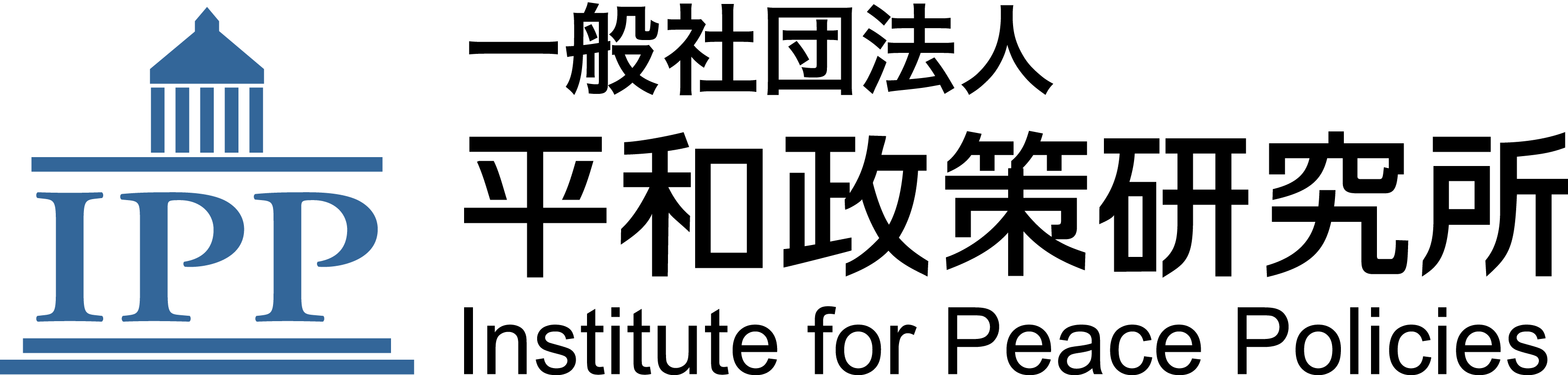1.アフリカ開発会議(TICAD)とは:日本の立場と戦略
日本は冷戦終焉後の1993年、他国に先駆けてアフリカ開発をテーマとする国際会議である「アフリカ開発会議(TICAD:Tokyo International Conference of Africa Development)」を立ち上げた。
冷戦の時代、アフリカは米ソによる覇権争いの最前線となり、双方の陣営が自分の勢力圏にアフリカ各国を取り込もうと大規模な援助を続けていた。しかし、ソ連が崩壊し冷戦が終結した後は、欧米諸国のアフリカに対する関心は急速に低下し、後ろ盾を失ったアフリカの国々は政情不安に陥り、内戦や民族対立が多発するようになった。
そうしたなか、世界第二の経済大国となった日本はアフリカの潜在成長力を評価し、それまでのアジアを中心とした政府開発援助(ODA)をアフリカにも拡大する方針を決め、1993年にアフリカ諸国との対話枠組みであるTICADを発足させたのである。
TICADは、アフリカ諸国の首脳を一堂に集め、開発や援助について多国間で協議する場で、ポスト冷戦の時代に日本独自の外交を展開しようとの政府・外務省の意欲の表れでもあった。また当時日本は、国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指していたことから、国連総会で多数を占めるアフリカ諸国の支持を集めたいという思惑もあった。
こうして生まれたTICADは、日本政府と国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合(AU)の事務局であるアフリカ連合委員会との共催で、1993年の第1回会議以降、2013年の第5回会議までは5年に1回日本で開催されていたが、2016年の第6回会議は初めてアフリカ(ケニア・ナイロビ)で行われ、以後、3年に1度、日本とアフリカで交互に開催するようになった(図表1参照)。
このTICADの枠組みの下、日本は持続可能な開発や人材育成を後押しすることでアフリカとの協調関係を築いてきた。また岸田前政権は、アフリカ諸国を「国際社会における主要なプレーヤー」とみて連携を強め、従来の開発支援に加え、気候変動や感染症対策など社会課題の解決に協働するパートナーシップの構築を目指した。自由や民主主義、法の支配といった価値観を共有し、日本にとって有利な国際秩序を維持・強化しようとの狙いがそこには込められている。
岸田前首相が議長を務めた一昨年5月のG7(主要国首脳会議)広島サミットで、G7として初めて「グローバルサウスへの関与強化」を主要テーマに掲げ、G7以外の参加9カ国の一つとして、アフリカ連合(AU)の議長国であるコモロを招待したのも同様の趣旨によるものだった。そして今年8月には、アフリカ各国の首脳が来日し、9回目のTICADが横浜市で開かれる予定だ。
2.独自の存在感が低下したTICAD
しかし、TICADを核とする日本のアフリカ外交は、いま幾つかの面で試練に直面している。まず世界の主要国が相次いでアフリカ諸国との間でTICAD類似のサミットや協議の枠組みを立ち上げたことだ。
日本がTICADを立ち上げた当時は、アフリカ開発支援の先駆的な試みとして世界からも高く評価された。しかし日本の試みに刺激されて2000年以降、中国、欧州連合(EU)、米国、ロシアなどが相次いでアフリカとの対話枠組みを立ち上げるようになった。
例えば中国は、2000年から定期的に「中国・アフリカ協力フォーラム」(Forum on China–Africa Cooperation: FOCAC)」を開催するようになった。最近の動向を見ると、2021年11月にセネガルで開かれた第8回のFOCACで、中国はアフリカに新型コロナウイルスワクチンを10億回分提供するほか、医療従事者など1500人の派遣を表明するなど巨大経済圏をめざす「一帯一路」構想の下でインフラ建設や巨額の融資を積極的に進めアフリカ諸国との結びつきを強めている。
さらに24年9月に北京で開催された第9回のFOCACでは「新時代の全天候型中国・アフリカ運命共同体の共同構築に関する北京宣言」が採択され、中国とアフリカとの「運命共同体」構築を訴え、中国と全てのアフリカ各国との2国間関係を「戦略関係」のレベルに引き上げることが提案された。
それと同時に「中国・アフリカ協力フォーラム北京アクションプラン(2025〜2027)」も採択され、インフラや保健衛生、農業、人的交流など10分野での協力強化(「10大パートナーシップ行動」)が示され、「アフリカ大陸自由貿易圏の発展を支援し、アフリカの地域間開発のために物流・金融面で協力を深める」とした。
そして習近平国家主席は、100万人以上の雇用創出やアフリカ産農産物の輸入拡大、緊急食料援助などを約束した。また30件のクリーンエネルギープロジェクトを立ち上げる用意があると表明したほか、アフリカ大陸の原子力エネルギー実用化も支援し、電力不足の解消に貢献するとも述べた。そのうえで習氏は、協力深化に向けて今後3年間で総額507億ドル規模の資金を融資及び企業による投資として拠出すると表明した。
さらに第9回のFOCACでは「グローバル発展イニシアチブ枠組みにおける協力深化に関する共同声明」も発表され、中国とアフリカを代表とする「グローバルサウス」が協力し、グローバルガバナンスにおける発言権を向上させる方針が示された。
アフリカ諸国とのサミットの枠組み構築では日本や中国に後れをとったロシアも、2019年 10 月にアフリカ諸国の首脳らをソチに集め、初の「ロシア・アフリカサミット」を開催した。プーチン大統領は「アフリカ各国との関係構築はロシアの外交政策の優先事項のひとつだ」とアフリカ重視の姿勢を強調した。
そして、ロシアと アフリカとの関係強化に関する92の合意文書が締結され、総額1兆40億ルーブル(約125億ドル)相当の成果が発表された。合意文書は、輸出貿易、国際協力、ハイテク、運輸・物流、鉱物資源の採掘、石油ガスの探鉱、さらに投資・金融を含む極めて広範な分野をカバーしている。この時、「ロシア・アフリカ経済フォーラム」も同時に開催され、ロシア政府各省から幅広く11大臣及び7政府機関の長が参加するなど様々な分野でアフリカとの協力関係を広げようとするロシアの意図が読み取れる。
その後、ウクライナへの軍事侵攻を受けて欧米との対立が続くようになったが、そのなかでもロシアは2023年7月にサンクトペテルブルクで第2回の「ロシア・アフリカサミット」を開催し、会議の成果として首脳会議宣言のほかに、宇宙での軍拡競争防止、国際情報セキュリティー分野の協力、テロとの闘いでの協力強化に関する宣言、2026年までのロシア・アフリカ間パートナーシップの行動計画を採択した。
プーチン大統領は記者会見で、アフリカ諸国に対して12億ルーブル(約1560億ドル)規模の感染症対策支援プログラムを開始すると発表したほか、ウクライナと交戦状態にあるなかでもロシアがアフリカに対して農産物を供給し続けることをアピールした。さらにロシアは、前回のマンスリーレポートでも触れたように、資源開発や武器の輸出などを通じてアフリカ各国との関係を深めている(図表2参照)。
米国もアフリカへの関与を強めるようになった。バイデン政権は21年8月、アフリカに対する外交戦略をまとめ、中露両国に対抗する姿勢を鮮明にしたほか、22年12月には、首都ワシントンにアフリカ各国の首脳らを招いて会議を開き、経済や食料の安定確保、テロ対策など幅広い分野での関係強化を図る姿勢を示した。
このほかEU、韓国、インドやトルコなどもアフリカの国々と国際会議を開くようになっており、アフリカにおける影響力や自国の存在感を高めようと互いに激しい競争を繰り広げている。
このように各主要国とも近年、アフリカとの協議枠組みを立ち上げ、関係の強化に動いているが、いずれの国も開発協力や開発支援に限らず、多様で幅広い分野での関係構築を目指すようになっている。特にアフリカへの経済投資やビジネスを重視する傾向が読み取れる。いまや各国は、対アフリカ政策=援助や開発支援という狭い捉え方から脱却し、軍事・経済・安全保障、さらに医療や衛生なども睨んで、より広範かつ戦略的な観点からアフリカ政策を位置づけるとともに、同時に投資を重視し、ビジネス機会の獲得に注力しているといえる。
3.開発援助から投資への切り替えに乗り遅れた日本
国連貿易開発会議(UNCTAD)のデータによると、2022年の各国の対アフリカ直接投資残高は、1090億ドルのオランダを筆頭に、フランス(580億ドル)、米国や英国(各460億ドル)、中国(410億ドル)が続く。投資とはいっても単なる企業任せではなく、各国とも政府が主導してアフリカ諸国との連携を加速させているのが現状だ。
然るに日本のアフリカ直接投資残高は2013年の120億ドルをピークに主要国とは反対に減少傾向にある。2021年には半分以下の57億ドルにまで落ち込んだ。その後、コロナ禍の落ち込みから回復する傾向にはあるものの、23年末は約80億ドルで、依然ピーク時の13年末の7割弱に留まっており足踏み状態が続く(図表3参照)。
他の主要国が対アフリカ政策で投資を重視するようになったのは、自動車や半導体の生産に不可欠なレアアースの獲得など主要国側の事情だけによるものではない。冷戦後、グローバルエコノミーの進展により、中国やインドなどの新興国が急速な経済成長を見せた。それに伴い天然資源の価格が上昇し、ナイジェリアやアンゴラなどの資源国を中心に、アフリカも高い経済成長を謳歌するようになる。そのためアフリカの側から開発援助よりもビジネスチャンスや投資を求める声が強まったためでもある。
これに対し日本の場合、アフリカ政策と言えばイコール開発支援政策であるとの意識や固定観念が強く、TICAD発足以来、社会インフラなどの開発援助が常に政策の中心を占めてきた。だが主要各国の対アフリカ政策の動向や、投資を欲する現地アフリカの生の声を踏まえ、2010年代に入り、ようやくTICADも「援助から投資へ」を合言葉に、開発から民間企業のビジネスチャンス拡大に焦点を移すようになった。
この軌道修正に伴い、2013年の第5回TICADでは、5年間で320億ドルの官民投資が約束された。続く2016年の第6回TICADは、初めてのアフリカでの開催となり、安倍首相(当時)は日本企業約70社と経済団体の幹部を伴い開催地ケニアに乗り込んだ。
続く横浜市で開催された2019年の第7回TICADでは、民間投資の拡大を最大のテーマに掲げ、日本とアフリカの経済界の代表も加わって投資環境の改善や人材育成などの課題、さらに、海洋プラスチックごみ対策や、過激派に参加する若者の問題などアフリカが直面する様々な課題について話し合われた。
その後も政府・外務省はアフリカへの投資意欲を常にアピールしているが、日本企業のアフリカ投資意欲は依然として低調である。そのためアフリカ諸国のTICADに対する関心も低下気味だ。
そうしたなか、22年8月、チュニジアの首都チュニスで第8回のTICADが開かれたが、岸田前首相が開催直前にコロナ感染し、オンライン参加となったこともあり、参加したアフリカ諸国48か国のうち首脳級は僅か20人に留まり、前回TICAD7の時の42人から半減するなどアフリカ諸国のTICAD離れが顕著となった。
岸田前首相はこのTICAD8で、今後3年間で総額300億ドル規模の資金を投入すると宣言したが、先のTICAD7で目標に掲げていた200億ドルの民間投資達成状況については「概ね実現した」との曖昧な表現でお茶を濁した。
4.拡がる中国との格差
日本はかつて対アフリカ貿易及び対アフリカ投資のいずれにおいても中国をリードしていた。TICADを参考に中国がFOCACを創立した2000年当時、中国とアフリカの貿易額はアフリカの貿易総額のわずか2パーセントに過ぎなかったが、日本は2倍の4パーセントを占めていた。
しかし、それからおよそ十年後の2013年には、この数字は中国10パーセント、日本3パーセントと逆転する。この十年間で中国とアフリカの貿易額は日本とアフリカの貿易額を大きく上回るようになったのである。
日本は2000 年代のアフリカにおいて、特定の資源産出国を中心に、無償資金協力や小規模な開発プロジェクトは増加させているが、貿易量はほとんど増えていない。一方、中国の対アフリカ援助は極めて明確に自国の経済的利益とリンクさせたものであり、援助と貿易、投資を結び付けている点において日中両国には大きな差異がある。
対アフリカ貿易での逆転劇に加え、開発援助に係る資金規模でも日本は中国に苦戦を強いられている。経済成長を達成し、GDPで日本を抜き去った中国は、日本を上回る支援額を梃子にアフリカ各国に積極的に浸透しつつある。投資や貿易だけでなく、今や日本はお家芸であった開発援助の分野でも中国の後塵を拝するようになったのだ(図表4参照)。
自国経済の停滞や「債務のワナ」に対する国際的な批判を受け、最近中国はインフラ整備のための援助資金額を絞り込むようになってはいるが、それでも中国との援助競争で日本が優位を回復することは難しい。日本の国力や財政状況を踏まえれば、中国を上回るような巨額のアフリカ投資などを行う余裕がもはやなくなっているからだ。
中国が2000年に始めた「中国アフリカ協力フォーラム」が3年に1度の開催であることを意識し、日本も2013年のTICAD5からそれまでの5年おきの開催を3年おきへと短縮するなど中国への対抗意識を強めているが、対アフリカ政策における我が国の苦戦は否めない。
5.TICAD9に向けて
日本政府は今年8月、横浜市で9回目となるTICADを開催する予定だ。このTICAD9に向けてアフリカ諸国との認識の整合を図るため、昨年8月、「アフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合」を東京で開催した。日本からは上川陽子外相(当時)らが、アフリカからは41か国から閣僚級が参加した。
会合では「社会」「平和と安定」「経済」をテーマに議論が行われたが、主たる狙いは、遅れが目立つ我が国の対アフリカ投資の拡大にあり、アフリカで活動するスタートアップ(新興企業)の支援に向けた環境整備の必要性などを日・アフリカの双方が共有した。初めて企業や投資家も交えた意見交換の場が設けられ、政府と経済界の交流を促す工夫も見せた。
上川外相は、「民間と連携した、自由で開かれたビジネス環境を整備する必要性を共有した」と述べ、また「多くの革新的な解決策が共有され、さらにグローバルな課題解決に貢献していくことで一致した」と閣僚会合の成果を強調した。
そして討議の成果を活かすため、閣僚会合としては初めて共同文書が採択され、アフリカのビジネス環境改善に向けた官民連携の推進が強調された。即ち、アフリカで活動するスタートアップ(新興企業)支援に向けた環境整備の重要性で日本とアフリカ双方が認識を共有し、「アフリカのビジネス環境を改善するため、民間部門との戦略的パートナーシップ構築に向けて努力する」方針が明記されたのである。
また貿易を促進し投資の増加に向け努力することや、アフリカへの投資リスクの認識によりよく対処するための協力を強化する必要性でも一致した。「人工知能(AI)を含むデジタル技術の効果的かつ責任ある活用の必要性」も指摘された。
さらにこの会合では、安全保障分野での女性参画を促進するため、東アフリカ諸国を中心とする地域協力機構である「政府間開発機構(ICAD)」を拠点に、日本政府が「女性平和人材育成イニシアチブ」を創設する方針も打ち出された。援助資金の額で中国を下回る日本は、手厚い技術支援や人材の教育・育成、それに透明性の高い開発金融などでアフリカを支えることによって、中国との差別化を図ろうとしているのだ。
6.対アフリカ政策強化のアプローチ
そうしたなか、まもなくTICAD9が開催される。昨年の「TICAD閣僚会合」の共同文書では、TICAD9を成功に導くため、日本とアフリカ諸国が「緊密な協力を継続する」と明記されたが、今回のTICAD9が果たして行き詰まり感の強い日本の対アフリカ政策を見直し、改める転機となるであろうか。これまで述べてきた問題点や課題を踏まえ、今後の我が国の対アフリカ政策の在り方について、幾つかの提言を試みてみたい。
①開発援助から投資促進への大転換
「最後のフロンティア」とも呼ばれ、経済成長著しいアフリカ地域を世界各国は絶好のビジネスチャンスの場と捉えるようになった。アフリカの各国も開発援助よりもビジネスの拡大を求めるようになっている。そのような潮流変化に日本の当局は乗り遅れたと言える。
日本も第5回のTICAD以後、投資拡大に向けた努力を重ねているが、日本の対外投資に占めるアフリカの割合は未だに0.3%に留まっている。そのためアフリカの側からも日本のアフリカビジネスに対する消極的な姿勢に不満が寄せられている。政府・外務省もこうした事態に対処すべく、日本企業に対してアフリカへの投資促進を促している。
外務省によると、アフリカのスタートアップの資金調達額は15年のおよそ3億ドルから23年には23億ドル程にまで増えた。また外務省が発表している「海外進出日系企業拠点数調査」によると、2022年10月1日時点で、アフリカに進出している日系企業の数は972拠点。前年比+8%の増加で(2021年は900拠点)、毎年増える傾向にはある(図表5参照)。
だが、それでも企業側の反応は総じて鈍い。TICADが始まった1993年当時の584拠点と比べると、30年経過しても1.6倍の増加に留まっている。気候や衛生など生活環境の厳しさに加え、政情やビジネス・商慣習の不安定さなどから、アフリカ市場での売り込みや進出に日本企業が消極的だからだ。
同じ条件下にありながら、中国や韓国の企業がアフリカへの進出に積極的かつ意欲的であるのとは対照的だ。日本企業がアフリカに尻込みする背景には、進出距離の遠さに加え、投資リスクや不安定性の高いビジネスを避けようとする日本企業の安定志向の強さが影響しているように思える。日本の対アフリカ投資の低さや停滞は、アフリカの側だけではなく専ら日本企業の問題といえる。
米国のトランプ政権が開発援助政策の大幅な見直しと削減に踏み切った。それ故アフリカに対する日本の開発援助事業の重要性は高まったとはいえる。だが、アフリカの経済成長の潜在力が世界的に注目される中、日本がアフリカで経済的な存在感を高め、他の主要国に後れを取らぬためには、やはり政府が、インフラ整備のような公共事業的開発援助中心の政策から、民間企業も組み込んでのビジネス促進型援助政策への転換を加速させる必要がある。
今年4月には改正JICA法が成立し、民間資金との連携を図るべく、民間企業からの投資や融資を呼び込むため、JICAが途上国の企業に対し債券の発行を支援したり、融資の保証を行えるようになった。また事業に必要な資金を迅速に提供できるよう、現地政府を通じて供与していたこれまでの在り方を改め、現地の民間企業などに直接支払える形に改められた。さらに日本企業の対アフリカ投資を促がすためには、中小企業や若手起業家によるスタートアップ企業への資金援助や、投資、ビジネス機会拡大につながる情報の提供などをさらに強めていく必要もあろう。
またアフリカに進出する日本の企業も、現在主流となっているインフラ整備やエネルギー開発、環境整備など現地の企業を顧客とするB2B業種ばかりでなく、現地の消費者を顧客とするB2C業種の進出を促す取り組みが求められる。アパレルやファッション、さらに日本が得意とするアニメや映像、音楽産業などソフト面の分野にも対象を広げていくべきではないか。
②現地アフリカとの接点・人的交流を拡大強化せよ
TICADといったアフリカ支援の枠組整備で他国をリードしてきた日本だが、その後、アフリカの求めるものが開発援助から投資へと変化していった動きに素早く対応するという点で他国に後れを取った感は否めない。
そのような事態を招いた理由の一つに、関係者の意識の固着があったように思える。アフリカ支援と言えば人道支援と同義であり、開発援助やインフラ整備がアフリカの発展にとって最も効果的でかつアフリカ諸国の側からも歓迎される政策だと外務省や関係機関が信じて疑わなかったのではなかろうか。
そのような思い込みに加え、さらに言えば、投資や投機は私企業などの私益追求活動であり、それに対しODA(政府開発援助)による資金の提供や技術支援は人道目的に根差した公益性の高い政策であり、投資よりも重要かつ優越すべきものとの意識が無かったとは言い切れないように思える。今後は、アフリカも日本も共に繫栄をめざす共存共栄、ウィンウィンの関係構築をより重視する意識を持つことが重要だ。
さらに、現地の動向を素早く掴み、それを政策に反映するのにタイムラグが生じるのは、現地アフリカの生の声やビビッドな情報を収集する態勢が整っていないからである。アフリカ諸国の考えや動きを読み誤ったといえば、20年ほど前の国連の安保常任理事国入りを巡る交渉での我が国の挫折が思い出される。TICADの創設は国連での安保常任理事国入りを睨んでの措置でもあったが、まさにその常任理事国入りを巡る決議案採択での国連総会の票読みで、日本はアフリカの動きを読み誤ったのだ。
③アフリカ票の読み誤りで安保常任理事国入り挫折の過去
冷戦後における日本の国連外交最大テーマは、悲願である安保理の常任理事国入り実現であった。TICADが創設されたのも、国連総会で多数票を持つアフリカ諸国の支持獲得がその狙いであった。そしてその機会が到来した。1993年12月3日の国連総会で安保理改組問題を検討する作業部会会の設置が全会一致で決まり、94年1月19日、作業部会の初会合開かれた。
改革の焦点は、加盟国の多くが不満を抱いている5大国の拒否権の扱いと理事国拡大問題である。もっとも、拒否権の廃止は現行の5大国が応じるはずがないため、実際には理事国の数をどの程度まで増やすかが最大のポイントになった。日本は同じく常任理事国入りを目指すドイツ、ブラジル、インドとグループを結成し行動をともにしていた(G4)。そして2004年、有識者から構成されるハイレベル委員会はアナン国連事務総長に、
A案:常任理事国を六カ国、非常任理事国を2か国拡大
B案:準常任理事国(再選可能、四年任期)を8か国、非常任理事国を1か国拡大
の2案を提示した。
日本は2005年、A案を基にG4の諸国とともに、常任理事国を6か国、非常任理事国を4か国それぞれ増大する決議案を提出した。非常任理事国の数をハイレベル委員会よりも多くしたのは、アフリカなど途上国の支持を取り付ける狙いからだった。
日本やドイツなどの常任理事国入りを阻むためイタリアなどは反G4グループを組織、中国がそれを支援しており、G4と反G4による総会での得票争いはし烈を極めた。安保理改組には憲章の改正が必要で、加盟国の3分の2以上の支持を取りつけねばならず、勝敗はアフリカ諸国の支援取り付けの有無に掛かっていた。
日本はアフリカ向けODAの増額やTICADの創設などかねてからアフリカ外交に力を入れてきたことから、支援取り付けに自信を持っていた。アフリカ連合(AU)もG4案に同調する意向を示していたのだ。
然るにAUは最後の段階になって、アフリカからの非常任理事国の数を増やしたAU独自の決議案を提起する方針に変更した。その結果、G4,反G4、それにAU案の三つが票決に付されることになり、票が割れてしまうためG4提案は総会で三分の二以上の支持を得る見通しが立たなくなった。AUが土壇場になって態度を変えた事情は明らかにされてはいない。日本やドイツの常任理事国入りを阻止するため、反G4グループやあるいは中国がAUに働きかけをした可能性も考えられるが、いずれにせよ最終的にはAU自身がG4との分離を決断したものであり、アフリカ諸国の意志やそれを取り巻く諸外国の動向掌握が不十分であったことは否定できない。
結局、日本はじめG4は総会での採択を断念し、G4決議案は廃案に終わる。支援してくれるはずとの思惑が外れ、アフリカ諸国の支持取り付けに失敗したのだ。戦後、日本が常任理事国入りに最も近づいた時であったが、この挫折により、以後常任理事国入りは事実上不可能となった。
昨年のTICAD閣僚会合では、アフリカに対する歴史的不正義を解決するため、国連安全保障理事会の改革が不可欠との認識で一致した。日本は現在もドイツ、インド、ブラジルと共にG4の枠組みで安保理改革と常任理事国入りを目指しており、その実現にはいまもアフリカ諸国の支持が欠かせない。常任理事国入りに限らず、国連外交を進めるうえでも国連総会で多数を占めるアフリカ諸国の存在は非常に大きい。この意味でもアフリカとの関係強化は重要であり、過去の教訓を活かし意志の疎通を深めていく努力が求められよう。
④政財官あげてアフリカ関与の拡大を
開発の協力支援やインフラ整備にあたる少数の専門家、技術者が現地に駐在するだけでは、アフリカ各国の政治、経済の内情を広く掬い取ることは困難である。アフリカの生の声を正しく掌握し、適宜適切なアフリカ政策を打ち出すには、数年に一度開催するだけのTICADでも不十分である。
開発援助の関係者に留まらず、より多くの政府関係者や企業の職員が現地アフリカに常駐する体制作りが必要に思える。2014年1月の安倍首相(当時)のアフリカ訪問の以前は、長い間、日本の首相はアフリカを訪れていなかった。外相のアフリカ訪問も決して多いとはいえず、アフリカの現地を実際に見て回る国会議員はさらに少ない。また日本の場合、現地に人を送り込んでも3〜5年程度の任期が来れば帰国し、折角現地で築いた人脈や情報のネットワークが後に続かないことも多い。
これに対し、中国の外相は過去数十年にわたり毎年初、アフリカ諸国を歴訪している。閣僚だけでなくアフリカには中国企業の進出が活発で、企業の経営者や幹部がアフリカに進出、さらには多数の中国人労働者が現地に職を求め、アフリカで定住している。政財官、さらに最近では軍関係者もアフリカに出向くようになっている中国と比べれば、日本及び日本人のアフリカ関与の薄さはあまりに対照的だ。
主要国が国家戦略としてアフリカ進出を強めつつある状況の中で、日本もそれに伍して本格的なアフリカ政策を構築する意志があるのならば、政府関係者も企業の人たちも足しげくアフリカを訪れ、またアフリカに住み続け、現地に根を張るような体制作りが急務だ。アフリカへの派遣人員の増大や日本とアフリカの間の人的交流を大幅に拡大強化する必要性も高い。
⑤包括的戦略的なアフリカ政策の構築
グローバルサウスの中心であり、レアアースやエネルギー資源が豊富、さらに経済成長目覚ましく、ビジネスチャンスも期待できるアフリカは魅力の高い地域であり、権威主義勢力と自由民主諸国双方の争奪戦の舞台となっている。
なかでも権威主主義勢力はアフリカをはじめとするグローバルサウスへの接近を強め、その取り込みを図ることで世界の多極化を実現し、米国中心の世界秩序を打破しようとも考えている。一方、自由民主諸国はそのような政治的思惑を阻もうと動いている。
それゆえ主要各国は政治、経済、軍事など様々な分野を包含させた幅の広いアフリカ政策を次々に打ち出し、アフリカとの関係を強化し自らの影響力拡大に腐心しているのだ。
日本もこうした流れに乗り遅れること無く、開発オンリーから投資主体のアフリカ支援政策への転換を急ぐだけでなく、それと同時にアフリカ地域の政治的安定や安全保障をも視野に収めた包括的かつ戦略的なアフリカ政策を打ち出す時期に来ている。それはまた日本の対グローバルサウスの外交や戦略の重要な一環として位置づけられるべきである。
安倍首相(当時)が「自由で開かれたインド太平洋」を提唱したのは、16年8月の第6回アフリカ開発会議(TICAD6)の場だった。安倍氏は、インド洋と太平洋に面したアジアとアフリカを結ぶ地域を「力や威圧と無縁で、自由と法の支配、市場経済を重んじる場として育てる」と強調した。共同文書でも、国際法順守や法の支配を促進する重要性を盛り込んだ。こうした普遍的価値観の共有についてアフリカ諸国と合意した意義は大きい。
だが近年、アフリカ含む新興・途上国「グローバルサウス」への接近を強める中露などの権威主義国は内政不干渉を名目に対象国の人権や民主主義の状況に関わりなく資金や武器、さらに軍事力の提供を続けている。
そのためアフリカなどグローバルサウスの国々は自由民主主義諸国の人権や民主主義重視の姿勢を「価値観の押し付け」と敬遠する傾向が強まっている。日本としては国際法順守や法の支配促進などの普遍的な価値観の遵守が、長期的にはアフリカの安定と繁栄に繋がることを今後も粘り強く訴えていく必要がある。
⑥欧米諸国との連携も視野に
さらに、アフリカが権威主義枢軸に取り込まれる事態を防ぐには、自由民主諸国の各アフリカ政策を連携させ、戦略的により大きな効果が発揮できるような体制の整備も必要になっている。だが、世界で分断と対立が進む中、アフリカでは旧宗主国である欧州諸国への反感が強まっている。他方、日本は歴史問題などを抱えておらず、長年の政府開発援助(ODA)などの実績から、総じてアフリカ諸国からは好意的な印象を持たれている。
そこで欧米とアフリカの双方と良好な関係を築維持している日本が仲介役となり、自由民主諸国による戦略的なアフリカ支援策を話し合う国際的な枠組みを立ち上げてはどうか。そのような枠組みの下で、各国のアフリカ政策間の調整や相互の支援、役割分担などを協議し、全体としてより効果の高まる支援策の構築を目指すべきであろう。
また国力が低下するなか、限られた資金と資源を最大限に活かすためには、日本も一国の狭い視野に囚われず、欧米など同盟関係にある諸国との連携連絡を深め、自己完結型に拘らず各国との相互補完的な支援政策の在り方を模索してはどうか。
日本は技術支援、中でも一過性の支援に終わらせず、アフターケアに配慮した持続発展的な技術支援の体制を整えてきた。そのような我が国の長所や強みを各国のアフリカ支援政策の中で共有しあうための工夫が求められる。また戦略的な支援となすため、アフリカ諸国への「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の枠組みを活用することも検討すべきである。
(2025年6月20日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)