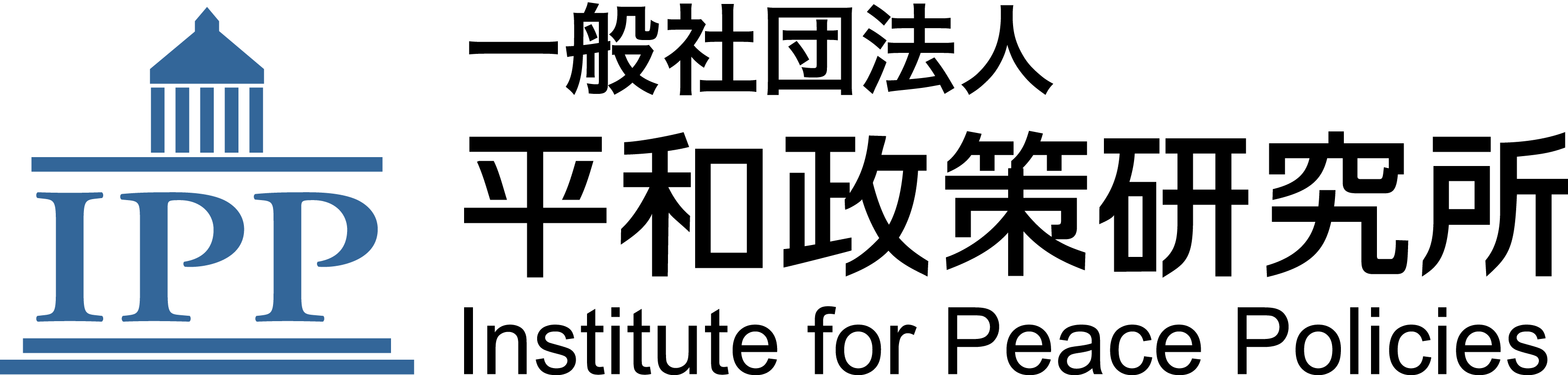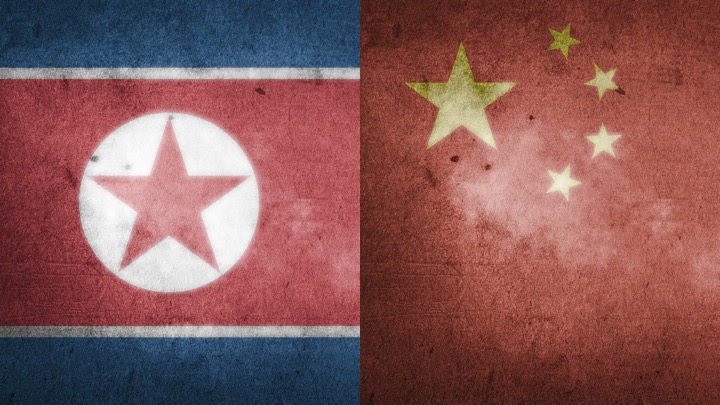1.西欧諸国の対アフリカ政策
アフリカへの浸透、進出を強める中国やロシアの動きを先月眺めたが、それに対し民主主義諸国はどのように対応しようとしているのだろうか。民主主義諸国の中でもアフリカとの関係が深いのは、長きにわたってこの地の植民地支配を続けてきた西欧諸国である。そこで西欧の地域統合組織である欧州連合(EU)やその重要なメンバー国のフランス、ドイツ、イタリアなどの対アフリカ政策の状況を眺めてみたい。
欧州連合(EU)のアフリカ政策
欧州連合(EU)とアフリカの関係は、サハラ以南のアフリカ諸国と地中海周辺の北アフリカ諸国という2つの地域に分かれ別々に発展してきた。しかし2000年代に入り、EUはアフリカ大陸全体との戦略的パートナーシップ構築を目指すようになり、その手始めとして、2000年4月にカイロで第1回のEU・アフリカ首脳会議を開催した。 2005 年 12 月には欧州理事会(EU首脳会議)で、「EU・アフリカ間の戦略的パー トナーシップに向けた戦略」を採択し、平和と民主主義、将来の繁栄など、EUが アフリカ諸国と共有すべき価値観や、アフリカ諸国の自立支援、持続可能な経済成長と地域統合および貿易の促進、人への投資などの基本原則を定めた。
また2007年12月にリスボンで開催した第2回EU・アフリカ首脳会議では、2005年 に策定した戦略を基にEU・アフリカ間の長期的な政策の方向性を示す「アフリカ・EU戦 略パートナーシップ:アフリカ・EU共通戦略」を採択し、EU・アフリカ間の政治的パートナーシップの改善や全てのアフリカ諸国におけるミレニアム開発目標の2015年までの確実な達成、 効果的な多国間自由貿易の推進などの目標を示した。共通戦略は貿易や地域統合、気候変動、エネルギーなどの共通課題に取り組むことを目標とし、伝統的な開発政策 の枠組みを超えようとするものだった。
一連の動きを通して、EUの対アフリカ戦略は、それまでの片務的な援助政策から対等なパートナーとしてアフリカの経済的自立を促す政策へと変化していった。さらに、2010年11月に トリポリで開催した第3回EU・アフリカ首脳会議では、「投資、 経済成長、雇用創出」を主要なテーマとし、経済成長の促進と雇用機会の創出とともに、 リー マン・ショック以後の経済回復を確固たるものにするための具体策が討議された(図表1参照)。
中国の「一帯一路」政策に対抗するEU
その後、中国がアフリカへの進出を強めるようになる。冷戦後、経済関係を柱に密接な関係を築いてきた中国と欧州の関係であったが、習近平政権になると、巨大経済圏構想「一帯一路」政策の枠組みの下で中国は西欧諸国を上回る規模の開発支援や経済投資に乗り出し、それと同時にインフラ支援での「不透明性」や国際の秩序やルールを軽視した動きが表面化する。また香港では自治や表現の自由などが強く制限され、また新疆ウイグル自治区で人権問題が浮かび上がるなど中国の強権的な対応が目立ち始めたことから、両者の関係は揺らぎ始め次第にEUは中国への警戒心を強めていった。
2021年12月、欧州委員会は外務・安全保障政策上級代表と共同で、民主主義、法の支配、人権の擁護などの価値に基づく、EU域外向けの新たなインフラ支援戦略を発表した。「グローバル・ゲートウェイ」と名付けられたこの計画は、域外のインフラ整備を支援するため、2027年までに最大3000億ユーロ(約38兆円)を投資するもので、中国の「一帯一路」政策に対抗し、民主主義圏による途上国支援の枠組みを作る狙いがある。
この計画は環境やエネルギー対策、デジタル化、交通網、医療、研究・教育分野に重点を置く方針で、持続可能な発展を後押しするとしている。中国の「一帯一路」構想では、返済能力などを軽視した過大な融資の結果、途上国が「債務の罠」に陥る事例が相次いでいるが、EUは持続可能な形での支援を前面に出し、中国との違いを鮮明にする。フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長も記者会見で「我々の計画は透明で、地域住民に恩恵をもたらすものだ」と述べ、「一帯一路」との違いを強調した。「グローバル・ゲートウェイ」構想は、中国の「一帯一路」というアジア・ヨーロッパ間の陸路・航路で結ばれた地域における経済協力の枠組みに対抗すべく米国のバイデン大統領が音頭を取ったG7(先進7カ国)による途上国向けインフラ支援構想である「ビルド・バック・ベター・ワールド」(B3W)構想とも連動している。
そして翌22年2月、EUとアフリカ連合(AU)の首脳会談が開催され、経済・社会・政治の広範にわたる協力関係の構築に向けた「2030年に向けた共同ビジョン」と題した共同宣言を採択した(図表2参照)。このプランは、先の「グローバル・ゲートウェイ」構想に基づくもので、EUはAUに対し、官民で少なくとも1500億ユーロ(約20兆円)を支援することを発表した。
つまり「グローバル・ゲートウェイ」構想の資金枠の半分が、このAU向け支援に向けられることになる。デジタル、エネルギー、輸送などのインフラ開発のならず衛生や教育の面でのサポートも含まれる。「対等な立場でお互いを尊重し、利益を共有していきたい」とミシェルEU大統領はアフリカ各国の首脳に呼びかけたが、歴史的に欧州との繋がりが深いアフリカでは中国やロシアが勢力を拡大させており、それに対する巻き返しを図るのがこの構想の狙いだ。また同じ2月、欧州議会はEUの「共通外交安全保障政策(CFSP)」の年度執行報告において、中国共産党の脅威に対抗するため民主主義諸国間の協力拡大を求めるとともに、より包括的で一貫した「EU・中国戦略」を制定する必要があるとした。
影響力後退が続くフランス
欧州はアフリカに近く、歴史的な関係も深い。その欧州を代表するEUが中国の「一帯一路」政策に対抗し、人権や民主主義、国際秩序などに準拠したアフリカ開発の戦略を打ち出した意義は大きいものがあるが、他方、ドイツと並ぶEUの牽引役でアフリカの旧宗主国として強い影響力を保ってきたフランスのアフリカにおける地位が最近急速に揺らいでいる。
英国やオランダと並びフランスは、アフリカへの直接投資額で他の国々を上回っている(図表3参照)。またモロッコ、アルジェリアなどの北アフリカやニジェール、ブルキナファソ、マリなど西アフリカのサヘル地域諸国の旧宗主国として、アフリカ諸国が独立を果たした後も影響力を維持し、最近までポコ・ハラムやアルカイダなどイスラム過激派のテロ対策に協力するとして軍隊を各国に駐留させてきた。
だがテロの拡大を防止することは出来ず、しかも民間人の死傷者を多く出す結果となり、現地住民の反発を招いた。反仏感情が高まる中、フランスのマクロン大統領は2017年5月の就任以来、対アフリカ政策の見直しを一貫して主張し、『フランスアフリック』と呼ばれる旧宗主国としてのフランス語圏アフリカとの関係からの脱却を説き、首脳同士や政府・国家間の関係よりもサヘル地域の市民や若者との関係を重視し、また従来の開発協力主体の関わりから文化やスポーツ、起業等新たな交流の柱を据えようと努めた。
しかし、コロナ感染症の拡大に伴う経済状況の悪化も加わり、フランスの存在感が低下し続ける中、アフリカ西・中部のフランス語圏諸国では先月のマンスリーレポートで取り上げたように、クーデターが相次いだ。即ち、2020年8月のマリでの反乱軍によるクーデターでイブラヒム・ブバカール・ケイタ大統領が失脚したのを皮切りに、2021年4月にはチャド、同年5月には再度マリで政変、2021年9月にはギニア、さらに2022年1月と9月にはブルキナファソで軍事クーデターが勃発した。一連の政変に際しては、フランス関連企業や外交団などへの暴力を伴う示威行為も発生している。
この状況に危機感を持ったマクロン大統領は23年2月、アフリカから批判されている仏軍の駐留やフランス開発庁(AFD)を中心とする国際協力、それにCFAフラン(旧仏領西アフリカおよび赤道アフリカの諸国で用いられる共同通貨)による通貨政策の見直しを表明するとともに、同年4月には中部アフリカ4カ国を歴訪しフランスのイメージ回復に努めた。だが、そうした取り組みにも拘らず政変の波は収まらず、23年7月にはニジェールの反乱軍によるクーデターでモハメド・バズム大統領が失脚、翌8月のガボンでのクーデターで3選直後のアリ・ボンゴ大統領が失脚。親フランス指導者層が次々に権力の座を追われていった。
結局、相次ぐクーデターと都市部の若年層を中心とする反フランス感情の高まりにより、現地の「フランス離れ」を押えることに失敗したマクロン政権は、仏軍撤退を求める声に押され、サハラ砂漠以南の7か国から仏軍を逐次撤退することを決断、治安維持やテロ対策から事実上手を引いた(図表4参照)。これにより仏軍がアフリカで軍事駐留を継続しているのはジプチとガボンのみとなった。
フランスは今後、自国が軍事作戦を主導するのではなく、現地政府からの要請が無い限り、軍事訓練の提供や武器供与、過激派に関する情報共有などの協力や支援は積極的に行わない方針だ。そして仏軍撤退の隙を突くようにしてサへルに入り込んだのが先月取り上げたロシアである。フランスはサヘルで失った影響力の回復をいまも果たせず、ロシアの進出に対抗し得る有効な政策も打ち出せずにいる。
ドイツが打ち出したアフリカ版マーシャルプラン
一方、フランスと並びEUの牽引役であるドイツは、これまでアフリカ問題に積極的に取り組んできた。メルケル首相を含む主要閣僚のアフリカ訪問の回数も他のEU諸国を大きく上回っている。具体的にはドイツが主催国を務めた2015年のG7エルマウサミットではアフリカの開発問題をテーマに取り上げ、またG20の議長国であった2017 年には「アフリカ版マーシャルプラン」の構想を発表している。
「アフリカ版マーシャルプラン」とは、1940年代後半から1950年代前半に米国によって西欧で実施された援助プログラムをモデルに、2016年後半に経済協力・開発省のゲルト・ミュラー大臣が提案し、2017年1月に「アフリカとヨーロッパ──開発、平和、より良い未来に向けた新たなパートナーシップ」と銘打った34ページに及ぶ戦略文書として公表された。
それは、従来の援助における「与える側」と「受ける側」という関係を排除し、アフリカと欧州間の戦略的開発パートナーシップの確立を目指そうとする意欲的な構想で、政府開発援助(ODA)を活用した民間セクターの資本移動や対アフリカ投資のための優遇税制の創設によって政府よりも民間主導の投資促進に重点を置くこと、アフリカ連合(AU)への支援を中心にアフリカの平和と安全保障の向上を目指すこと、それに民主主義・法の支配・人権を重視することの3本の柱が中心に据えられた。
アフリカ版マーシャルプランの主たる狙いは、アフリカ大陸の貿易や開発を活発化させることにあった。政府が直接インフラ建設などを行う従来型の開発援助から、政府が初期投資を行い民間が投資しやすくする方向へと転換し、公的資金を呼び水にして民間のアフリカ投資促進を狙ったのである。アフリカの発展を強調しつつも、急成長するアフリカ経済をドイツ企業のビジネスチャンスとして取り込もうとする考えである。ミュラー経済協力・開発相は40万社のドイツ企業が海外進出しているにも拘らずアフリカには僅か1000社しか進出していない実態を嘆き、「アフリカの利権を、中国やロシアやトルコに渡してはいけない」と檄を飛ばしている。
同構想にはもう一つ狙いがあった。それは、地中海を経由して欧州に渡る大量の難民や不法移民の抑制である。構想発表の際、ミュラー経済協力・開発相は「ヨーロッパにとって、アフリカの命運は試練と機会の両方を意味する。共に課題を解決しなければ、いずれ我々に降りかかってくる」と述べたが、良質な雇用機会をアフリカ域内で創出しなければ、アフリカを去って欧州で移民労働をしようとするインセンティブがさらに増大するリスクを懸念したからである。
このアフリカ版マーシャルプランはドイツ国内で大きな注目を集めた。しかし、構想の幅が広く経済協力・開発省の権限を超える部分が多かったことや理念先行に流れ、提案された計画の多くは実行に移されずに終わった。
エネルギー獲得のためアフリカに接近する独伊
その後、2022年にウクライナ戦争が勃発、ロシアによるウクライナ侵略に対し欧州諸国が対露経済制裁を発動したことで、ロシアからの石油や石炭は途絶、ガス供給も大幅に減少してしまった。そのためロシアにエネルギー源を大きく依存していたドイツなど各国は天然ガスなどエネルギー輸入先の多様化と新たなガス田開発、それに化石燃料脱却の加速化を迫られることになった。特に原発重視のフランと異なり、脱原発の政策を打ち出していたドイツは、開発支援よりも専ら新たなエネルギー資源獲得のためにアフリカに接近する動きを強めている。
エネルギーの脱ロシア化を図る必要からドイツが関係強化に乗り出しているのは、アフリカ西岸のセネガルである。セネガルから隣国モーリタニアにかけての大西洋沖では2014年以降、大規模な海底油田・ガス田が相次いで発見された。しかしセネガルには採掘に必要な資金や技術はなく、開発は欧米などの外資頼みだ。セネガルの都市サンルイ沖ではすでに英石油大手BPなどが天然ガス田を開発中だが、ドイツも未開発の鉱区に開発段階から関与することで天然ガスの権益確保を狙っているのだ。
21年12月に首相に就任したショルツ氏がアフリカの最初の訪問国としてセネガルを選んだのは、そうした思惑からだ。ショルツ氏はセネガルのサル大統領との首脳会談後、エネルギー開発は両国の利益にかなっているとして、今後「集中的に取り組む」と強調。サル氏も「ドイツと一緒に仕事をすることを強く望む」と期待感を示した。
もっとも、ドイツは主要7カ国首脳会議(G7サミット)で、天然ガスを含む海外の化石燃料事業への公的支援を22年末までに原則停止するとの表明を出しており、セネガルでのガス田開発に乗り出せばこの国際合意に反する可能性がある。そのため自ら議長国を務めた22年6月の主要7カ国首脳会議(G7サミット)では、ドイツの提案で首脳宣言の中に「ロシア産エネルギー依存からの脱却を加速させるという観点から、現状の危機に対応する例外的措置として、一時的なガス部門への公的投資は適切」との一文が盛り込まれた。ここには、エネルギー確保のためにはなりふり構わないドイツの姿勢が垣間見える。
さらに昨年、G7サミットの議長国になったイタリアもアフリカとの関係を重視している。メローニ首相は議長国となるやいなや、ローマにアフリカの首脳や閣僚を招いて「イタリア・アフリカ」サミットを開催し、G7の議長国としてアフリカの開発協力に全力をあげる姿勢を示した。また24年6月にイタリア南部プーリア州で開かれた首脳会議(サミット)では「アフリカ、気候変動、開発」のセッションを設けるなど議長国としてアフリカに重点を置いたアジェンダ(議題)設定を行、エジプトのほかチュニジア、南アフリカ、アフリカ連合(AU)などアフリカ諸国を中心に招待した。メローニ首相は
「世界の鉱物資源の30%と耕作地の60%がアフリカにある。イタリア、ヨーロッパ、そして全世界は、アフリカを考慮せずに将来を考えることはできない。私たちの将来は、アフリカ大陸の将来に必然的に左右される」
と述べ、アフリカとの経済協力の重要性を強調しているが、ウクライナ戦争の影響でロシアからのエネルギーに頼れなくなったいま、エネルギーの供給源としてアフリカに寄せる期待は強いものがある。EUはチュニジアとイタリアを結ぶ送電線などに3億760万ユーロ(約520億円)を提供する方針を決めたが、イタリアも単独で、北アフリカ産の再生可能エネルギーやグリーン水素、アルジェリア産の天然ガスなどの輸入拡大に動いている。
独伊に留まらず、ロシアのウクライナ侵攻前まで天然ガス輸入の4割をロシアに依存してきた欧州の各国にとって、アフリカからの供給ルート構築は急務である。天然ガス埋蔵量世界第10位を誇る資源大国のナイジェリアとの関係強化もその一環だ。ナイジェリアは既に欧州に液化天然ガスを輸出しているが、さらにニジェール、アルジェリアと共に「トランスサハラ・ガス・パイプライン」を通じて欧州への天然ガス供給の増加に動いている。ナイジェリアでは大規模なガス田が発見され、油田の探査も行われている。
欧州諸国がアフリカを重視する理由は他にもある。地球温暖化対策に必要なレアアースなどの重要な鉱物資源の供給元としても期待されているからだ。中国はレアアースなどの重要資源の輸出規制で米国や日欧に揺さぶりをかけている。中国による経済的威圧政策に屈しないためには、豊かな資源が眠るアフリカの開発を通じ、国に頼らない供給網の構築を図る必要がある。
移民対策としてのアフリカ支援
さらにアフリカとの関係強化は、欧州が抱える移民・難民問題解決のためにも重要だ。2015年、シリアの内戦によって同国から難民が大量に発生し、欧州は難民の大量流入で混乱した。この年だけで欧州には180万人の難民が流入、その後も対岸のアフリカからの地中海ルートとバルカン諸国を陸路経由したルートを中心に毎年難民の流入が続いた。欧州連合(EU)によると、アフリカや中東などから2023年に域内に到着した不法移民や難民は約38万5000人。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、そのうち約15万7000人が地中海経由で押し寄せた。
EUは24年3月、経済危機に見舞われているエジプトの間で戦略パートナーシップ協定を締結し、同国への4年間で総額74億ユーロの経済支援を発表(図表5参照)。前年の23年7月にはチュニジアへの約1億5000万ユーロの経済支援も決めている。いずれも欧州を目指す移民や難民らの経由地で、不法流入の抑止対策を強化してもらう狙いが込められている。先述したドイツの「アフリカ版マーシャルプラン」もそうであったように、アフリカへの経済支援は、移民・難民が増加する根本的な原因である貧困の改善にもつながるからだ。
かようにロシア・ウクライナ戦争の勃発が契機となり、EUや欧州各国はエネルギー源やレアアース獲得の必要性から、またそれと並行して難民対策解消の目的も加わり、アフリカへの接近を強めてはいるが、そうした動きは中露のアフリカ進出の動きを抑えるための有効な戦略や政策とはなっていない。
また対露脅威に対処するための国防力強化やウクライナへの支援、さらにウクライナ戦争の停戦実現などの問題対処に追われ、途上国への開発支援や国際協力への取り組みはどうしても手薄になりがちだ。しかもフランスのような有力国のアフリカでの政治的影響力の低下後退も影響し、現在の欧州は権威主義勢力のアフリカ進出を食い止める余裕を失っているのが実情だ。
2.米国の対アフリカ政策
アフリカでの存在感の低下
冷戦の終焉後、米国はアフリカへの関心を弱めていった。しかし、湾岸戦争を契機にイスラム過激派が米国へのテロ攻撃を繰り返すようになり、2001年には米本土で同時多発テロ(9.11事件)が発生。これを受け、ブッシュジュニア大統領は対テロ戦略を発動すると同時に、テロと戦うためには軍事力だけでは不十分であり開発途上地域の貧困対策や安定化の重要性を痛感し、その任期中にアフリカ向け援助をおよそ4倍に増額した。またアフリカでエイズ(後天性免疫不全症候群)と戦うためのPEPFER(The President’s Emergency Plan For AIDS Relief:大統領緊急エイズ援助計画)と呼ばれる資金拠出プログラムも創設している。
オバマ大統領は、2014年に米国として初めてアフリカ諸国との首脳会議を開催したほか、サブサハラ・アフリカの電力普及率を2018年までに倍にするため70億ドルの経済支援と90億ドル以上の民間投資を約束、さらにソマリアを中心とする「アフリカの角」やサハラ砂漠では、特殊部隊と無人機を活用したテロ組織との戦いを続けた。
だが続く第一期トランプ政権になると、再び米国のアフリカへの関心は薄れていった。トランプ大統領はサハラ以南のアフリカ諸国を訪問することはなかったが、これはレーガン大統領以来初のことであった。その間、中国やロシアは着々とアフリカに接近、2021年に中国とアフリカの貿易額は2610億ドルと過去最高を記録したが、この年、米国とアフリカの貿易額は中国の4分の1に過ぎない640億ドルにまで減っていた。
ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の兵器取引量に関するデータによると、2017〜21年のアフリカ諸国の武器輸入の44%と全体の半分近くをロシアが占めているのに対し、米国はその半分以下に留まっていた。中国が経済で、ロシアが武器進出でアフリカへの影響力拡大に腐心する中、米国はその存在感と影響力を低下させ続けていったのである。
バイデン政権:アフリカ首脳会議開催とサブサハラ戦略
権威主義諸国がアフリカでの影響力を高めつつある状況に危惧を覚え、米国が巻き返しに動くようになったのは、バイデン政権になってのことである。2021年6月、英国南西部コーンウォールで開催された主要7カ国(G7)首脳会議において、米国は低中所得国のインフラ開発のための支援プロジェクトである「より良い世界再建」(B3W:Build Back Better World)構想を提起した。バイデン大統領は、同構想を中国の「一帯一路」政策に代わる、より質の高いものにしたいと述べ、各国首脳の合意を取り付けた。G7首脳は声明で、B3Wにより「価値観に基づいた、高水準で透明性のある」パートナーシップを提供する旨表明。G7諸国はこの構想に基づいて2035年までに約40兆ドルを開発途上国に提供する予定になっている。
B3W構想は、先進国が中国の「一帯一路」政策に対抗して出した初の代案構想として注目され、ニューヨーク・タイムズは、その規模と野心は、第2次世界大戦後に欧州再建に向けて米国が行った『マーシャルプラン』を大幅に上回る」と評価。ロイター通信も「G7国家が中国の影響力に対抗して代案を提示できるということを全世界に示した」と報じたが、その後、構想の具体化が遅れている。
次いで22年8月、バイデン政権はサハラ砂漠以南のサブサハラ・アフリカ向けの包括戦略を発表し、食料支援やインフラ整備の強化、また人権侵害に対して制裁措置を辞さない構えを強調し、中国やロシアに対抗する姿勢を示した。包括戦略ではアフリカにおける人口の増加や貿易拡大に加え、国連での強い影響力に言及。「アフリカの貢献や指導力がなければ、この時代の決定的な課題に対処できない」と指摘した。
さらに22年12月には首都ワシントンで、2014年以来8年ぶりとなるアフリカ諸国との首脳会議を開催し、米国がアフリカに積極的に関与していく姿勢を示した。会議にはアフリカの49カ国の首脳とアフリカ連合(AU)が招待された。会議でバイデン大統領は、AUが主要20カ国・地域(G20)に正式参加することへの支持を表明したほか、経済や安全保障、気候変動などの幅広い分野でのアフリカ諸国への支援強化を約した。経済協力では関係国と連携して食料不安に対応し、食料生産の拡大を支援していくとした。ロシアによるウクライナ侵攻で食料価格が上がり、アフリカの政情不安を招くとの懸念に対処するものである。
米政府は会議開催前、アフリカ諸国を様々な分野で支援するため今後3年間で550億ドル(約7兆5600億円)を拠出すると発表、米国のアフリカ回帰を印象付けた。インフラ整備などを通じて地域への関与を拡大し、台頭する中国やロシアに対抗するためである。翌23年にはブリンケン国務長官がエチオピアとニジェール、エジプトを、カマラ・ハリス副大統領がガーナ、タンザニア、ザンビアをそれぞれ歴訪。ガーナの首都アクラでハリス氏は「アフリカ大陸への投資を増やし、経済成長とその機会を促進する」と述べ、アフリカ諸国に寄り添う姿勢を強調した。24年にもブリンケン国務長官がカーボベルデ、コートジボワール、ナイジェリア、アンゴラの4カ国を訪問している。
またバイデン政権は24年9月、国連安全保障理事会の常任理事国にアフリカ地域からの代表として2議席を創設することへの支持を表明した。安保理は現在、米英仏ロ中の常任理事国5カ国と、任期2年で毎年5カ国が地域ごとに改選される非常任理事国10カ国で構成されている。アフリカには非常任理事国の3枠が与えられてきたが、現状の体制では不十分という声が多く、その不満に応えて2枠増設への支持を打ち出したのである。
さらに10月にはバイデン大統領が親中国の一つアンゴラを訪問。バイデン氏のサハラ砂漠以南のアフリカ訪問はこれが初めてで、サハラ砂漠以南のアフリカを現職米大統領が訪れるのは2015年のオバマ氏のケニア訪問以来。バイデン氏は2022年に第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP27)が開かれたエジプトを訪問しているが、数時間滞在しただけで、本格的なアフリカ訪問はこれが初。任期中にアフリカを訪問するという公約を守った形となった。アンゴラは1975年の独立後も内戦が続き、最近まで軍需品の調達をロシア、インフラ整備を中国に頼ってきた。だが2017年に大統領に就任したロウレンソ氏は米欧側に接近する姿勢を見せている。
この動きを受け米国は、「一帯一路」政策を推し進め開発投資で影響力を拡大している中国を牽制するため、一昨年、欧州連合(EU)と共同でアンゴラとザンビア、コンゴ民主共和国を結ぶ鉄道を整備する「ロビト回廊」事業を打ち出した。大西洋岸にあるアンゴラのロビト港からコンゴ民主共和国、ザンビアを結び、最終的にはタンザニアまで延ばして大西洋とインド洋をつなげる計画で、沿線は銅やコバルトなどの鉱物の産地である。電気自動車や半導体に不可欠な重要鉱物のサプライチェーン(供給網)強化に繋がると期待されている。バイデン米大統領はアンゴラのロウレンソ大統領と会談し、米国がアフリカ側の条件に基づき長期的に関与していく姿勢を示した。またロビト港を視察して周辺国首脳らとも会談し、回廊沿いのインフラ投資に民間資本も含めた5億6千万ドルの拠出を発表した。
価値観外交の重視がアフリカ諸国の反発を招く
だが、こうした取り組みにも拘らず、バイデン政権の公約は未達成のものばかりで、これまでのところ具体的な成果には繋がっていない。またニジェールでは仏軍に続き米軍も24年4月撤退に追い込まれている。米軍は約1億ドル(約150億円)を投じ、ニジェールの砂漠地帯にドローン基地を設置し約千人を駐留させていた。だが軍事政権が米国との軍事協定を一方的に破棄し、テロ対策の名目で国内に駐留していた米軍の撤収を求めたからだ(図表6参照)。
このように依然としてアフリカでの米国の存在感は後退気味だ。ギャラップが実施した米中露三国のアフリカにおける好感度調査でも、中露の好感度がアップしているのとは対照的に、米国の好感度は低下している。
アフリカ各国は表面上、米国など西側や中露のいずれにも肩入れしない立場を取ってはいる。しかし、先進国に対抗し途上国に寄り添う姿勢を見せ、また人権や民主主義の確立などの価値観を強要せず、経済支援や武器の提供に応じる中露両国に対するアフリカ諸国の支持には根強いことが伺える。
22年に開いたアフリカ諸国との首脳会議で、バイデン大統領は中露の浸透を意識し、米国はアフリカに広がる強権主義に対抗すると表明し、腐敗を摘発する健全なジャーナリズムへの支援や民主主義の規範に基づく改革を後押しする考えを明らかにし、その実現のためには恩恵的な経済支援だけでなく制裁を含む懲罰的措置も取る考えであると説明した。
しかし、人権や民主主義といった普遍的価値観を支援の前面に押し出すことは、アフリカ諸国の反発を招きやすい。法の秩序や国際正義を重視し強調する米国の価値観外交が逆にアフリカ外交の進展を妨げ、中露を利する結果を招く恐れがあることには注意を払う必要がある。
アフリカへの関心が薄い第二期トランプ政権
援助資金凍結の打撃
今年1月、第二期トランプ政権が発足。翌2月初め、ソマリアで米軍がイスラム過激派組織「イスラム国」の拠点を空爆。第二期トランプ政権で初の大規模な軍事作戦となり、ヘグセス国防長官は「今回の行動は、米国と同盟国を脅かすテロリストを排除する用意が常にあることを明確に示すものだ」との声明を発表、トランプ大統領もバイデン政権が実行しなかった対テロ作戦を実施したと自賛した。
しかし、第一期の時と同様、トランプ大統領のアフリカに対する関心は低い。それどころかトランプ大統領は1月20日の就任初日に海外援助を90日間停止し、内容の見直しを行うとする大統領令に署名したことから、多額の援助を受けているアフリカの国々では混乱と懸念が広がっている。アフリカは貧困国が多く、2024年には米国際開発庁(USAID)から120億ドルの支援を提供されていた。だがコスト削減を重視するトランプ政権は、バイデン政権時代に決まっていたこうした支援のほとんどを停止させ、米国際開発庁の解体に着手、同庁職員の大量解雇に踏み切っている。
さらにトランプ大統領はアフリカに関する事業の大幅削減を指示する大統領令の署名や国務省を再編し、アフリカにある大使館や総領事館を閉鎖するほか国務省の気候変動や難民、民主主義、人権問題担当部局の廃止も検討中とされる。
援助金の削減で国際機関の業務にも支障が出ている。トランプ大統領はやはり1月20日、世界保健機関(WHO)から脱退する大統領令に署名し、WHOへの支援拒絶の姿勢を鮮明にさせた。米国はWHOに対する最大の資金拠出国であり拠出額は全体の約18%を占める。2024ー25年の2年間の予算は68億ドル(約1兆0574億円)で、米国は同期間、エイズウイルス(HIV)や他の性感染症の治療プログラムにかかる資金の75%を提供したほか、結核と闘うための資金についても半分以上を拠出している。
こうした巨額の資金拠出が途絶えることは、WHOの活動に対し大打撃となる。感染症のパンデミックが発生した場合に備えて世界的な連携を図るためにWHOが主導するパンデミック条約の合意にもトランプ氏は懐疑的で、米国は条約交渉から離脱しており、成立した条約への参加も危ぶまれている。
さらに国連世界食糧計画(WFP)もトランプ政権の対外援助打ち切りなどで深刻な資金不足に陥り、今年4月、アフリカ東部・エチオピアでの支援活動の一時停止に追い込まれた。栄養失調の女性と子供約65万人を支援する取り組みの一時停止を余儀なくされたという。エチオピアでは2年にわたる内戦から立ち直りつつある北部ティグライ州、アムハラ州、オロミア州など、いくつかの地域で散発的な戦闘が続いており、1000万人以上の市民が今も深刻な食糧不足に陥り、その中には紛争や異常気象によって避難を余儀なくされた約300万人の国内避難民や、内戦で荒廃した隣国スーダンからの難民も含まれている。
そのスーダンも国民の60万人以上が飢餓に苦しみ、800万人が飢餓直前の「崖っぷち」状況にある。米国は昨年、スーダンに8億3千万ドルと世界最高額の緊急援助を供与し、約440万人を支援した。しかし今年に入りトランプ大統領が援助を止めた後、ハルツームは壊滅的な打撃を被っており、人道援助団体が運営する給食施設が閉鎖に追い込まれている。
トランプ政権がこうした政策を採り続ければ、アフリカの開発や医療衛生・生活環境改善のための支援事業やさらには難民対策にまで深刻な打撃を与えることになる。中国は武器輸出や開発投資に留まらず、医療援助でも「健康シルクロード」を謳(うた)い文句に病院建設、医療チーム派遣、ワクチン外交などを重ねており、米国の援助後退を最大限利用しアフリカへの影響力のさらなる拡大とグローバルサウス取り込みを加速させることも大きな懸念材料だ。
「アフリカの夢」を潰す関税戦争 特恵制度事実上崩壊
このほか第二期トランプ政権は、米国産業の復興を目指すとして全世界を対象に高い関税政策を打ち出した。中国や欧州諸国、また日本や韓国、東南アジア各国が被る貿易への打撃はしきりにメディアで取り上げられるが、アフリカも決して無関係ではいられない。確かにアフリカには米国を最大輸出・輸入相手国とする国は多くはなく、引き上げられた関税率も先進国程には高くない。
しかし米国向け繊維製品の多いレソトのように50%の関税を課せられた国もある。レソトは干ばつや洪水で慢性的な食糧不足に苦しむ最貧国だが、対米貿易の黒字国であることから、この国の経済的な劣弱性を無視して法外な高関税をかけられた。南アフリカの自動車産業も損失を蒙ることになる。マダガスカル、ナイジェリアなども高関税を課せられており、一部の国は大きな打撃を受けることになる。一方、米国の貿易相手の中でアフリカの比率は2%以下で、米国が受ける影響は小さい。
また米国はこれまで『アフリカ成長機会法』(AGOA)によって、アフリカ諸国からの輸入品を無関税にするなどの特別待遇を与えてきた。2000年に成立したAGOAは、特恵関税制度を通じてアフリカ各国の市場発展や民主化を支えることを狙いとするものである。だがトランプ大統領は今秋で起源切れとなる同法の更新は行わない意向を示している。しかもその廃止前に高関税を課したことで、AGOAが事実上既に廃止されたのと同様の悪影響がアフリカ全域で出始めることになろう。
さらには、世界経済停滞の余波がアフリカに及び鉱物資源の取引が減少する可能性や、米国市場を失った中国製品がアフリカに大量に流れ込むことで、アフリカの産業が破壊され経済に深刻なダメージを与える恐れもある。
南アフリカとの対立・コンゴ民主共和国の対米接近
国ごとの状況に触れると、トランプ政権は南アフリカを敵視する政策を採っている。南アフリカは米国向けに自動車触媒用のプラチナや完成自動車を輸出しているが、トランプ政権の南アフリカ敵視政策で同国の産業や貿易には影響が出ることも予想される。南アフリカではアパルトヘイト(人種隔離政策)後も、人口7%の白人が70%超の土地を所有している。そうしたなか、今年1月、ラマポーザ大統領は、正当で公益に資する場合、政府は補償なしに私有地を公的管理のもとにおける土地収用法を成立させた。
これが一部で白人所有地の収用と黒人への再分配を念頭においたものと受け止められ、トランプ政権は同法を露骨な白人差別と非難。南ア政府は同法は米国の土地収用制度と類似したもので、土地や私有財産を恣意的に処分する意図はないと反論するが、トランプ大統領は2月に南アフリカへの資金援助を無期限停止する大統領令に署名したほか、駐米大使を国外退去処分とし相互関税を30%課すと発表した。さらに5月からは南アフリカの少数派白人を「難民」として米国に受け入れている。
トランプ政権の南ア敵視の背景には、南アフリカ政府が、ガザの住民に対するイスラエルの攻撃をジェノサイドだとして国際司法裁判所に提訴したことが親イスラエルのトランプ大統領の怒りを買ったことが影響している。トランプ政権の南アフリカ敵視政策には他のアフリカ諸国も反発を強めており、アフリカの米国離れと対中傾斜に拍車がかかることが心配だ。
他方、米国に接近の動きを見せている国もある。今年1月下旬、ルワンダが支援する反政府勢力「3月23日運動(M23)」がコンゴ民主共和国(旧ザイール)の東部に進軍し、主要都市を掌握するなど支配を拡大させている。そのためコンゴ政府は中国に依存してきたこれまでの政策を転換、トランプ政権と取引(ディール)し、豊富な鉱物資源の利権の一部を米国に与えることと引き換えに米国からの軍事支援や紛争の仲介を求めている。コンゴは世界有数の銅とコバルトの産地である。これを受けトランプ政権が仲介努力を続けており、和平合意の機運が高まりつつある。和平合意が成立した場合、コンゴ民主共和国、あるいはコンゴ民主共和国・ルワンダ両国と米国との間で鉱物に関する協定が結ばれる可能性もある。
3.テロと内戦が多発するアフリカ
アフリカでは、民族や宗教の違いによる対立や豊富な天然資源の争奪、経済の悪化や貧困に起因する国内政治の不安定状況がクーデターや内戦、さらに辺諸国を巻き込んでの国際紛争へと拡大するなど紛争が絶えない。
例えばスーダンでは、2023年4月以降、国軍と即応支援部隊との武力衝突が継続しており、国内外の避難民が1100万人以上に及ぶなど深刻な人道危機が発生、スーダンに隣接する南スーダンには約45万人の難民や避難民が押し寄せている。
その南スーダンではスーダンから分離独立した後、最大民族「ディンカ」出身のキール大統領率いる国軍と2番目に多い「ヌエル」出身のマシャル副大統領の勢力の間で2013年に内戦が勃発、一旦は停戦で合意したものの今年3月、キール氏側は扇動容疑でマシャル氏を拘束、自宅軟禁にし、国連安保理の求めにも応ぜず開放を拒み続けている。国連難民高等弁務官事務所によれば、約200万人の国内避難民が発生している。さらに上述したように、ルワンダが支援する反政府勢力「3月23日運動(M23)」とコンゴ民主共和国の間で武力衝突も起きている。
またイスラム過激派によるテロ行為も多発発しており、イスラム国(ISIL)によるアフリカでのテロ件数は2022年に初めてシリア 及びイラクでのテロ件数を上回るようになった(図表7参照)。今後もアフリカ各地でイスラム国やアルカイダ関連組織等によるテロが続発するとみられている。
紛争やテロが多発、しかも長期化する背景には、武器や軍隊を武装勢力や軍事政権に提供し、影響力拡大に動く権威主義諸国の存在も関わっている。一方、欧米諸国はエネルギーや鉱物資源獲得、難民の流入阻止には積極的だが、アフリカ地域の平和と安定のための活動や紛争の解決に乗り出す意欲は薄らいでいるのが実情だ。それが、グローバルサウスが中露への傾斜を強める要因にもなっている。
国連の力も低下している。国連の活動は大国間の協調を前提とするが、ロシアのウクライナ侵略により安全保障理事会が一致した決議や行動を打出せず、加えて国連を軽視する第二期トランプ政権の誕生で、国連の紛争処理能力は形骸無力化が著しい。
また冷戦当時のアフリカの紛争は専ら国家間の対立で、しかもその背後に大国が関与していたため、紛争の調停や停戦に向けた協議の枠組み作りが軌道に乗りやすく、停戦決議も比較的尊重され、国連の平和維持活動も行い易かった。
だが、冷戦後にアフリカ各地で起きている中央政府と武装集団が闘う内戦型紛争の場合、武装集団によって国連の権威は平然と無視され、しかも多数の市民を巻き込む無法無秩序な暴力行為が横行するようになった。そのため限られた規模と自衛のための装備しか持たない平和維持部隊だけでは紛争を抑え込むことが困難になっているのだ。
4.総括
アフリカは、国際政治で存在感を増しているグローバルサウスのまさに中心地域である。そして経済の成長も著しいが、その反面、安全保障環境の悪化や貧困からの離陸が依然として困難な状況にある。
冷戦が終焉した当時は、大国間の協調が存在し、国連の平和維持機能も強化された。また民主主義や基本的人権など普遍的な価値観への支持も強まり、主要国や国際機関によるアフリカ支援にも勢いがあった。さらに世界のグローバル化と相互依存の進展を背景に、地球規模の経済活動が活発化し、ビジネスや投資などアフリカへの関心も強まった。
しかしその後、米国の影響力低下と中国の覇権主義的行動の強まり、さらにロシアによるウクライナ侵略など自由民主主義陣営と権威主義陣営の間の対立が先鋭化し、協調から対立・分裂へと世界の潮流が大きく変化してしまった。そのような現状では、アフリカの経済発展や政治的な安定、さらに民主化を進めるための国際協力のレジームは構築し難くなっている。
国際環境が厳しさを増す中で、日本はアフリカに対しどのよう政策で臨むべきであるのか。8月には横浜でTICAD(アフリカ開発会議)が開催される。そこで来月は日本のアフリカ政策の過去と現状、そして課題について取り上げてみたい。
(2025年5月20日、平和政策研究所上席研究員 西川佳秀)