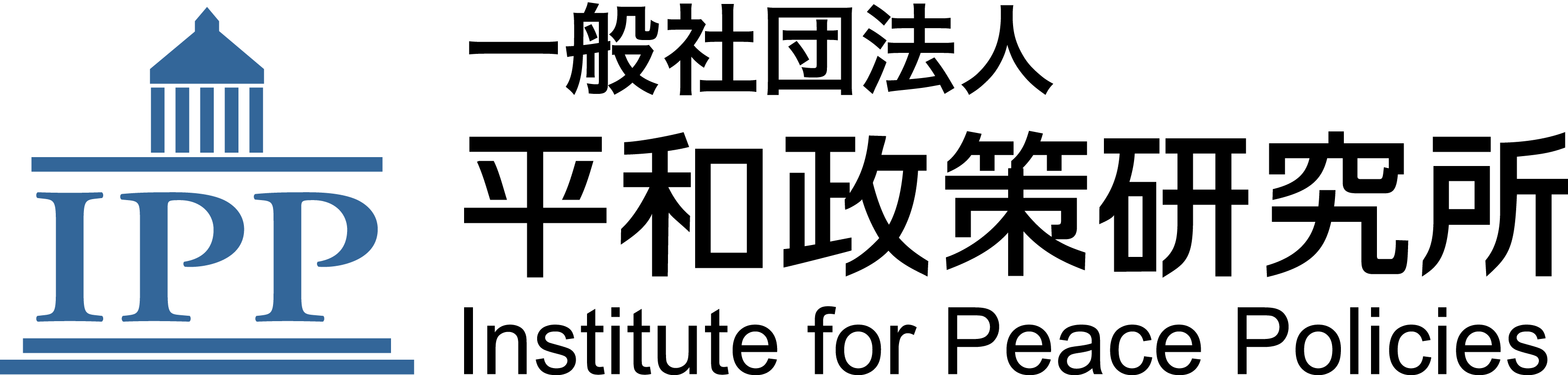はじめに
昭和百年のうち、その8割の期間を占めるのが戦後である。戦争に包まれた戦前期昭和とは対照的に、戦後の日本は経済的な繁栄と平和を謳歌する時代であった。その80年に及ぶ戦後日本の在り方を規定した指導者が吉田茂である。昭和百年、なかでも戦後の80年の軌跡を振り返るうえで、吉田茂の存在は決して無視することが出来ない。
いま少し具体的に述べれば、敗戦後の日本は戦前とは一転し、「経済中心・軽武装」を国家政策の基本とし、「日米安保条約を礎とする日米関係」を外交政策の基軸に据えた。この枠組みを築いたのが吉田茂である。そして吉田以降現在に至るまで、このスキームが日本の政治、外交、それに安全保障の在り方を規定し続けている。
このような政策の根底には日本国憲法の存在があるが、戦後における憲法制定を巡りGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)と日本政府の駆け引きが演じられた際、吉田は外相の地位にあった。そして所謂マッカーサーノートを核とするGHQ草案に部分的な修正を加え、1946年11月3日に日本国憲法として公布、翌年5月3日に施行された。この時の首相は吉田茂である。
憲法の制定後、戦後日本の独立回復が大きな政治課題となる。当時、自由主義諸国(西側陣営)とのみ講和条約を結ぶ単独講和か、あるいは社会主義諸国(東側陣営)も含めての全面講和とすべきか、国論は割れた。吉田首相は西側諸国との単独講和を選ぶ。また講和(平和)条約と同時に、吉田は国会や世論に図ることもなく米国と日米安保条約を締結し、米国との同盟を日本外交の基本に据えるとともに、独立回復後も米軍の日本駐留を認め、日本の安全保障を米国に大きく依存する体制を作った。
さらに、「陸海空軍その他一切の戦力はこれを保持せず」とうたう平和憲法を抱きつつも、警察予備隊から保安隊、そして現在の自衛隊へと戦後日本の再軍備を常に“なし崩し”の形で進めたのもほかならぬ吉田茂であった。そのため自衛隊の憲法上の位置づけが未だに議論され、かつ国防・安全保障の在り方が常に憲法問題と絡むという異常な状況がこの国では続いている。
いま日本を取り巻く内外の環境は吉田が政権を担当していた独立回復前後とは大きく異なっている。だが我が国が直面している課題や克服すべき問題は当時と異なっていても、吉田が残した政治の枠組みも、またそれに伴う国家の基本法(憲法)と国家の基本政策(国防や安全保障)間に横たわる齟齬軋轢もともに生き続けている。
そのような過去の政策の桎梏を克服し、いまの時代に適合した新たな日本の外交・安全保障政策を策定すべきではないか、かつ、それは如何なる政策であるべきかという重要なテーマについては稿を改めて論じることとし、本稿ではそれに先立ち、昭和を。そして戦後80年を顧みるという視点から、政治家吉田茂の政治、その功罪の双方を改めて見つめ問い直し、吉田茂が敷いた経済中心・軽武装、そして対米関係重視の戦後路線は日本にとって果たして正しい選択であったかどうか。正しくなかったとすればどのような道を辿るべきであったのかについて考えてみたい。
検討を加える前に、吉田茂の外相、首相、そして政権末期から引退後の各時期に分け、本テーマに関わる部分を中心に、吉田政治の軌跡を概観しておきたい。
第1章 戦後日本政治の軌跡と吉田茂
1 外相吉田茂と日本国憲法制定過程
終戦後の1945年9月、吉田茂は東久邇宮内閣の外務大臣に就任。程なく東久邇宮内閣が立ち行かなくなるや東久邇、木戸幸一、近衛文麿らは吉田に後継首相となるよう説得したが本人は固辞。同年10月には吉田自身も後押しした幣原喜重郎が首相に担ぎ上げられ、吉田は引き続き幣原内閣の外務大臣に収まった。
敗戦後、占領下日本の統治者であった連合国軍最高司令官マッカーサーは幣原首相に五大改革の実施を指示するとともに、大日本帝国憲法の改正を示唆した(45年10月11日)。幣原は国務相松本蒸治に憲法改正の研究着手を指示、松本は憲法問題調査委員会(松本委員会)を発足させる(10月25日)。
同委員会は10月27日から翌46年2月2日まで7回の総会と15回の調査会を開催した(非公開)。幣原内閣の憲法改正の基本方針は①「天皇が統治権を総覧」するという大原則(統治大権)には変更を加えない②議会の権限を拡充して大権事項にある程度制限を加える③国務大臣は国政全般について議会に対し責任を負う(責任内閣制)④人民の権利・自由を法律によらず制限できないものとする、の4原則であった(松本4原則)。この原則の下、松本は46年1月に松本試案(甲案)を脱稿、さらに委員会の意見等を踏まえ乙案も作成された。甲案は①「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」を「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」と改める②軍の制度は存置するが、統帥権の独立は認めず、統帥も「国務」であり、内閣の補弼を要し、内閣が議会に対して責任を負うものとする③軍の編制及び兵力は法律で定める④宣戦、講和および一定の条約については帝国議会の協賛を必要とする等を骨子とした。
マッカーサーノート
46年に入るとGHQから幣原内閣に対し、憲法改正作業を急ぐよう督促がなされた。それには次のような事情が存在した。占領政策の円滑実施のためには天皇を戦犯から外し天皇制を存続させることを既に決意していたマッカーサーは,本国政府にその旨働きかけていたが,連合国の中には天皇の戦争責任追及の姿勢が生まれており、特にソ連と豪州は天皇戦犯論の急先鋒であった。また45年12月に開かれたモスクワでの米英ソ三国外相会議で極東委員会の設置が決まり、最高司令官はこの委員会の下に置かれその決定に従わねばならない立場となった。
そのため占領政策における影響力維持をめざすマッカーサーは,東京裁判で天皇不訴追に持ち込むとともに、極東委員会の発足が予定された46年2月26日までに,自らのイニシアティブにおいて天皇制存続をうたった憲法改正を断行したかったのである。
一方、GHQの督促を受けた松本委員会は先の甲案を改正案(憲法改正草案要綱。松本試案)とし、2月8日にその要綱と説明書をGHQ民政局に提出した。要綱は議会の強化や貴族院の民主化,基本的人権の尊重等を定めていたが戦争放棄条項はなく,統帥権と交戦権が明記されていた。将来,日本が独立を回復した場合,当然再軍備がなされるであろうことから、軍隊の地位と性格に明確な法的根拠を与えるためであった。
だが46年2月1日、毎日新聞のスクープ記事で松本試案の保守性に驚いたマッカーサーは、日本側案を無視し、司令部独自の案を起草してそれを日本政府に飲ませる他に方法はないと判断、翌2日、自ら民政局長のホイットニー准将に対して新憲法の骨子として以下の3項目を示し憲法改正案の策定を命じた。
①世襲制の天皇を元首とするが、その義務及び機能は憲法に基づいて行使されるものとし、人民の基本的意思に対して責任を負う。
②国家主権の発動としての戦争は廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争のみならず、自国の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄し、その防衛と保護とを、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海軍を持つ権能は、将来とも与えられることはなく、日本軍に交戦権が与えられることもない。
③封建制度の廃止。皇族を除き、華族(貴族)の権利は生存者一代限りとする。華族の授与には政治権力を含まないこと。予算の型は英国の制度にならうこと。
世に謂うマッカーサ—ノートである。日本に戦争放棄、軍備禁止を強いる考えは米本国にはなく、マッカーサーは独断で自らの私見を基に新憲法制定に動いたのである。
GHQ草案の作成と日本側への提示
マッカーサーの指示を受け,ホイットニーはケーディス大佐等側近を集め、憲法草案の作成作業に入ることを指示し、翌2月4日から民政局スタッフ25人による憲法改正案作りが開始された。作業の総括にあたったのは法律家出身の民政局次長ケーディス大佐であった。当時40歳であったケーディス大佐のほか、ハッシー海軍中佐、ラウエル陸軍中佐、エラマン嬢で構成される運営委員会が全般を統括し、その下に立法、行政、人権、司法、地方行政、財政、天皇・条約・前文の七つの小委員会が設けられたが、戦争放棄に関する第2章はケーディス自らが担当した。メンバー25人のうち弁護士資格保有者が3人(ケーディス、ラウエル、ハッシーの3人がロースクール出身の弁護士)いたが、憲法の専門家は一人も含まれていなかった。
2月13日、ホイットニー准将,ケディス大佐ら総司令部側は外相官邸で松本国務相,吉田外相らと会見した。ホイットニーは、松本試案はその保守性ゆえに承認できないとこれを拒否、逆にGHQ(マッカーサー)草案を日本側に手交し、①日本政府による憲法改正作業はこのGHQ草案を基礎とすべきこと②本案は天皇を守る唯一の方法であり、日本側がGHQ草案を受諾せぬ場合、天皇の身柄は保障しかねること、また③日本側がGHQ草案を受諾せぬ場合には、総司令部が自ら日本政府の頭越しに草案を国民に提示するであろうこと、更に④改正案は日本側の発意として発表すること等の強い意向を示した。
松本試案(憲法改正要綱)に対する回答をもらえるもの思っていた日本側は、総司令部が独自の改正案を用意していたことに、またその思い切った内容に茫然とし、さらにはその採用を迫る強い姿勢に驚愕した。態度を保留してその場を辞去するのが精一杯で、「草案は侵略戦争のみを放棄するものか、自衛戦争をも否定する趣旨なのか」など国家にとって極めて重要なポイントについて質した日本側関係者は吉田茂をはじめ皆無であった。
帝国憲法改正草案の発表
2月18日、日本側は松本が書いた「憲法改正案説明補充」を提出し、松本案の再考を要請した 。しかし総司令部側に峻拒されたばかりか、48時間以内(=20日午後まで)にGHQ草案に対する諾否を回答するよう求められた(その後、回答期限は22日まで延長された)。
2月21日、幣原はマッカーサーと会談したが、GHQ草案は天皇制維持のためのものであること、天皇の規定と戦争放棄の基本原理変更は認めない旨マッカーサーは語り、幣原としても、天皇の地位を安泰なものとするためにはGHQ草案の受入れも已む無しの判断を固めた。翌日の閣議で、象徴天皇と戦争放棄を規定するGHQ草案の受入れはやむを得ず、「この米側案を基本として、できるだけ日本側の意向を取り入れたものを起案してみることにしようではないか」ということで見解が一致、幣原内閣はGHQ草案に基づいて憲法改正をなすことを正式に閣議決定し、天皇の了承を得た。
そしてGHQ草案をもとに松本国務相が一院制を衆参の二院制に改めるなど修正を施した「3月2日案」を纏め、3月4日午前、松本と佐藤達男法制局第一部長は同案を総司令部に持ち込み、30時間におよぶ徹夜の折衝で最終案作成作業が一気呵成に進められた。翌5日に「帝国憲法改正草案要綱」が完成、非常な短期間のうちに極く一部の関係者の手で、しかも占領軍に押し切られる形で日本国憲法は世に送り出されることになったのである。
GHQと日本側の交渉に際しては吉田の側近白洲次郎が終戦連絡中央事務局参与として関わっており、彼を通して吉田も改憲作業の進捗を掌握していた。しかし外相吉田茂がGHQやマッカーサーに対し、戦力放棄や自衛権の有無などについて意見を交わしたり、再考を促すような動きに出たという記録はない。
2 自衛戦争の権利まで否定した吉田首相
46年4月10日に行われた戦後最初の総選挙で、幣原率いる進歩党は第二党の地位しか確保できず、幣原内閣は総辞職に追い込まれた。これを受け5月に吉田茂を首班とする自由党内閣が成立(第1次吉田内閣)、吉田の下で大日本帝国憲法第73条の定める改正規定に則り、憲法改正の手続きが進められた。政府案は枢密院の審議を経て6月20日に招集された第90回帝国議会に提出、同月25日衆議院に上程された。
吉田首相は6月25日の衆議院本会議で、第9条について「日本国は永久の平和を念願して、その将来の安全と生存を挙げて、平和を愛する世界諸国民の公正と信義に委ね」ると説明、さらに翌26日、衆議院本会議で進歩党の原夫次郎議員の
「我が国を侵略せんとするものがでてきた場合に、我が国の自衛権というものまでも放棄しなければならぬのか・・・不意の襲来とか、侵略とかいうようなことが勃発した場合において、わが国は一体いかに処置すべきか」との質問に対し、
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります。・・・・正当防衛、国家の防衛権による戦争を認むるということは、偶々戦争を誘発する有害な考えであるのみならず、もし平和団休が、国際団休が樹立された場合におきましては、正当防衛権を認むるということそれ自身が有害であると思うのであります」と述べている。
また6月28日の衆議院本会議で共産党の野坂参三議員が
「ここには戦争一般の放棄ということが書かれてありますが、戦争には二つの種類の戦争がある。一つは・・・他国征服、侵略の戦争である。これは正しくない。同時に侵略された国が自国を守るための戦争(自衛戦争)は、われわれは正しい戦争といって差し支えないと思う。・・・一体この憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、われわれはこれを侵略戦争の放棄、こうするのがもっと的確ではないか」と質したのに対し、吉田は
「国家正当防衛権に依る戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくの如きことを認むることが有害であると思うのであります。近年の戦争は多くは国家防衛権の名において行われたことは顕著なる事実であります。・・・故に正当防衛、国家の防衛権に依る戦争を認むるということは、偶々戦争を誘発する有害な考えであるのみならず、もし平和団体が、国際団体が樹立された場合におきましては、正当防衛権を認むるということそれ自身が有害であると思うのであります」と言い切った 。
自衛権まで否定したように受け取られることを懸念した吉田は46年7月4日の衆議院帝国憲法改正特別委員会における林平馬議員(協同民主党)に対する答弁において
「今日までの戦争は、多くは自衛権の名に依って戦争を始められたということが、過去における事実であります。自衛権に依る交戦権、侵略を目的とする交戦権、この二つを分けることが、多くの場合に於いて、戦争を誘起するものであるが故に、かく分けることが有害なりと、申した積もりであります」と軌道修正を試みたが、一連の答弁から窺えるように、憲法制定前後、吉田(日本政府)は自衛戦争さえも否定する立場(2項全面放棄説的な立場)をとっており、野坂に対する吉田答弁は、この時期、政府の見解が自衛権すら否定していた根拠として、以後の防衛論争でしばしば引き合いに出されることになる 。
当時文部省が作成した社会科教科書『新しい憲法のはなし』(1947年8月2日発行)のなかに「兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、一切持たない」との記述がある。46年11月8日の施政方針演説でも吉田は
「軍備のないことこそ、我が国民の安全幸福の保障でありまして、またもって世界の信頼を繋ぐ所以であります。また平和国家として世界に誇るに足る所以であると私は確信いたすのであります」と述べている。
天皇制存続の代償として戦争法規を定めた憲法案を受諾した以上、一切の戦争を否定し、憲法の平和主義を強調することで世界から日本が不信と警戒心を招かぬようにすることこそが天皇制を維持せしめ、また日本の主権を回復するためにも肝要だと吉田は判断したのである。
枢密院において彼は「占領が終われば日本としては兵力を持つことになるのではないか。しかし、それは今日は言えないことである」とも答弁しており、吉田が防衛のための軍備の必要性を心底否定していたとは思えない。当面、日本は武力と思わせるものを放棄せざるを得ないが、あくまでそれは国体の護持と独立・復興を実現までのいわば戦術であった。それは恒久的な国家戦略の方針転換を意図するものではなく、やがて冷戦が激化するにつれて、自衛戦争否定の政府解釈には逐次修正が施されていくのである。
政府案は衆議院及び貴族院での審議を経て再び衆議院に戻された後、1946年10月7日帝国議会で最終的に可決され、11月3日に公布、翌47年5月3日に日本国憲法が施行された。
3 吉田政権の基盤確立
1947年4月25日、新憲法の下で新しい政府をつくるため衆参両院議員の選挙が行われた。その結果、大衆運動の高揚を背景に日本社会党が第一党となり、民主党・国民協同党との連立で片山内閣が発足。だが炭鉱国家管理問題で翌年2月に総辞職に追い込まれ、3月10日民主党総裁の芦田均が内閣を組織した。
東西対立の激化に伴い、48年後半を境に米国の対日政策はそれまでの民主・非軍事化から日本の復興と西側陣営への取り込みを目指すものへと転換する。それに伴い民主化推進の原動力としてニューディーラーが多数を占めていたGHQ総司令部民生局の影響力は後退する。僅か7カ月での芦田内閣崩壊はそれを象徴する出来事でもあった。芦田を内閣総辞職に追い込んだ昭電疑獄は、GHQの参謀第二部(G2)による民政局追い落としがその背景にあったからだ。
この逆コ−ス路線を日本国内から支えたのが、第2・3次吉田内閣だった。48年10月に中道連立の芦田内閣が倒れ、民主自由党の第2次吉田内閣が成立。これは少数単独の内閣だったが、翌年1月の総選挙で民主自由党は絶対多数の議席を獲得、加えて総司令部、特にマッカーサーの支持をバックに、吉田は1954年12月まで6年余の長期政権を打ち立て、その間、講和による独立回復を実現した一方、なし崩しの再軍備、それに日米安保条約を締結し日米同盟の枠組みを築いていった。
またこの選挙で吉田は池田隼人(大蔵次官)、佐藤栄作(運輸次官)、岡崎勝男(外務次官)、増田甲子七、前尾繁三郎(造幣局長)等官僚出身者を多数起用した(官僚政治家の登場)。いずれも吉田の弟子として、後に吉田路線を継承する役目を担うことになる。2月16日に発足した第3次吉田内閣では、池田隼人を蔵相(この時、池田蔵相の秘書官に選ばれたのが宮沢喜一、大平正芳)、増田甲子七を官房長官に任命した。第2次内閣で議席を持たずしていきなり官房長官に抜擢された佐藤栄作は、民自党政調会長に登用された。52年10月まで3年8か月の安定政権となった第3次吉田内閣は、経済再建と講和実現を推進したが、それは吉田ワンマン体制の幕開きであると同時に、戦後日本における官僚政治の出発点でもあった。
4 単独講和を選択
1948年になると講和条約締結の動きが出始めた。同年7月、米国務省は極東委員会構成諸国に対し、対日講和条約締結のための予備会談開催を提案したのだ。だがソ連が異を唱え、講和に向けた動きは一旦頓挫する。そのため第2次吉田政権が発足した48年後半当時、講和への見通しは全く立たなかったが、米国からの強い経済安定化要求と共産勢力の挑戦という左右双方からの圧力に第3次吉田政権が耐えている間、中国大陸が共産化する等国際情勢の緊張は一段と進み、米国もようやく対日講和に向けての動きを本格化させることになる。
当時、講和条約締結の方式について、社会主義諸国をも含めた全ての交戦国と講和条約を結ぶ全面講和を主張する立場と、中ソを除外して米国を中心とする西側諸国とだけでも早期に講和すべきだとする単独講和論が国内の世論を二分していた。49年11月1日、国務省当局が対日講和を検討中と発表した。11日には吉田首相が参議院で「単独講和も、それが全面講和へと導くものであるのならば喜んで応ずる」と発言し、単独講和によってでも主権を早急に回復すべきであるとの考えを明らかにした。
5 米軍駐留を自ら提案した吉田
早期講和の実現にあたって、もう一つ吉田が取り組むべき問題に、独立回復後日本の安全保障をどうするかという問題があった。この時期、米政府内では対日講和の時期と米軍基地確保等独立後の日本の安全保障を巡り米軍部と国務省の意見が対立し、これが講和問題の進展を妨げていた。中国大陸の共産化に伴い、49年秋以降米国務省は再び講和の促進に動くが、朝鮮戦争遂行の重要拠点として日本を手放したくない米軍部はこれに強く抵抗していたのだ。
一方、独立回復後も引き続き米軍の駐留を認めることで早期講和を実現させようと考えた吉田は、米軍の日本駐留に反対だったマッカーサーを経由せず、直接その旨を米本国に伝えるため、50年4月に池田蔵相を密使として渡米させた。池田には吉田側近の白洲次郎が同行し、宮沢喜一が秘書官として随行した。一行は4月25日に日本を出発、5月3日、池田は当時国務省公使であると同時に陸軍省顧問でもあったドッジと会談し、次のような吉田の提案を披露した。
「日本政府はできるだけ早い機会に講和条約を結ぶことを希望する。そしてこのような条約ができても、おそらくはそれ以後の日本及びアジア地域の安全を保障するために、米国の軍隊を日本に駐留させる必要があるであろうが、もし米側からそのような希望を申出にくいならば、日本政府としては、日本側からそれをオフアするような持ち出し方を研究してもよろしい。・・・米軍を駐留させるという条項がもし講和条約自身の中に設けられれば、憲法上はその方が問題が少ないであろうけれども、日本側から別の形で駐留の依頼を申出ることも、日本憲法に違反するものではない・・・」。
これは、日本が米国に対して講和後に米軍の駐留を認めることによって、講和条約の促進を図ろうとした最初の意思表示であった。かように吉田は、戦後日本の復興とその安全保障を米国に委ねるべきと考えたが、彼が対米協調を重視した根本的な理由は経済にあった。
「(我が国は)明治開国以来、英米両国との政治的、経済的協調によって、国運の隆昌を来した(が)・・・・日米関係の重要性はそうした歴史的な必然からばかりでなく、我が国民経済の根本的性格からも、その意義を理解することができる。日本は島国であり、海の国である。狭い国土に、世界でも稀な稠密なる人口を抱えている。これを養うためには、海外貿易の拡大は是非とも必要であるし、また経済の成長発展を絶えず図るためには、先進国の資本技術の導入を、どうしても欠くことはできない。・・そうした関係から世界を眺めれば、米国、英国などの自由諸国こそ、日本が最も尊重すべき相手となる」(吉田茂『回想十年』)。
敢えて独立回復の後も米国の保護を受ける道を選ぶことで、講和の早期実現と経済復興、それに日本の安全保障を達成しようと吉田は考えたのである。この吉田のメッセージは国務省や陸軍省にも伝えられた。対日講和がソ連の極東進出を誘発するのではないかと統合参謀本部が恐れていた時に、講和後の米軍駐留に途を開こうとするこの吉田提案は、講和に向けた動きを促進させるとともに、日米安保条約を誕生させる契機ともなった。
6 独立回復と日米安保条約締結、その陰で進む“なし崩し再軍備”
以後、米軍の日本駐留が講和交渉の前提となったが、6月に勃発した朝鮮戦争は日本の進路に大きな影響を与えた。まずこの戦争を契機に警察予備隊が発足し、日本の再軍備が始まった。また朝鮮特需により経済復興が加速され、高度経済成長に途を開いた。さらに朝鮮戦争への中国参戦もあり、講和交渉の過程で米側は日本の防衛努力を強く要求した。
一方、この戦争で日本列島の軍事戦略的価値がさらに高まったと考えた吉田は、対米交渉に際し基地提供という切り札をなるべく高く売りつけ、その見返りとして安全保障を米国に全面的に依存しつつ、日本自らの再軍備は回避するとの交渉戦術で臨もうとした。だが、51年1月から2月にかけて来日したダレス特使の強い再軍備要求の前に、吉田は米軍への基地提供のみならず、民主的軍隊の出発点となる「保安部隊(security force)」と国防省に相当する「国家保安省」の設置を約束させられることになった。こうした折衝、譲歩の結果、1951年9月8日,対日講和(平和)条約が調印され、52年4月28日発効した。平和条約の発効によって、日本は6年8か月ぶりに独立を回復する。
平和条約と同じ日に吉田は日米安保条約(旧安保条約)を締結し、日本の対米協調路線、西側陣営の一員としての座位が明確化した。もっとも旧安保条約は片務的な基地貸与協定の性格が強く、米軍には日本駐留の権利が与えられながら、米国の日本防衛義務は明記されなかった。これは「継続的で効果的な自助及び相互援助が可能な国」との間でしか、米国は対等な条約は締結できないというバンデンバーグ決議の存在によるものであった。条約の前文には、国の対日再軍備要求が「期待」という言葉で盛り込まれた。
防衛力増強を求める米側の要求は安保条約の存在によってさらに加速された。52年1月から日米間で日本の防衛力漸増と独立後の予備隊の改編について話し合いが行なわれた。米側は警察予備隊を10個師団、32万5千人に増強するよう求めたが、吉田が抵抗したため、13万人の増員でひとまず決着した。これを受け、52年5月に保安庁法案が国会に提出され、会期末の7月31日に成立し8月1日、保安庁が設置された。これに伴い、海上警備隊が警備隊と改称され海上保安庁の管轄を離れるとともに、警察予備隊は10月15日から保安隊に改組された。
保安隊、警備隊は「警察の予備」であるとの文言を削り軍隊に一歩近づいたものの「わが国の平和と秩序を維持し,人命及び財産を保護するため特別の必要がある場合において行動する」(保安庁法第4条)ことを任務とし,間接侵略への対処が主たる任務であることは警察予備隊と変わらなかった。吉田は新憲法を楯にとり、また経済再建優先を唱え米国の軍備増強要請に抵抗を続け、独立回復後も憲法改正や正式な国軍の再建には手を付けようとしなかった。
7 政治基盤喪失と高まる吉田政治批判
1949年2月16日に成立し52年10月24日の退陣まで3年8か月余にわたって続いた第3次吉田政権は、戦後初の長期安定政権であった。政権安定の直接的な要因は49年1月23日の第24回総選挙で与党の民主自由党(50年3月から自由党)が過半数の議席を獲得したことにあったが、より根本的な理由は、占領軍とマッカーサー、さらにその背後にある米国という絶対権力が吉田を支持し、吉田もまたそうした権力の意に添った政策を実行してきたことによるものであった。
また、占領下において戦前の有力政治家の多くがGHQによって公職を追放され政界の第一線から退いていたことも吉田に権力を集中させる一因となった。外務官僚出身の吉田は、長期政権を担う中で有能な官僚を抜擢し自身の政治基盤を固めるとともに、後の自由民主党に見られる官僚政党的体質の原型を作った。通称“吉田学校”の人脈は、戦後日本政治における保守本流を形成することになる。
しかし、平和・安保両条約発効と独立回復の大業を残した前半とは対照的に、第3次吉田政権の後半は、追放の解除で政界に復帰した鳩山との抗争や造船疑惑、指揮権発動等で泥まみれとなった。それまで、その対米従属性が指摘されつつも、他方で吉田の持つ頑固さや硬骨漢ぶりが国民の共感を呼び、彼に対する批判を緩和する働きをなしていた。
だが、講和実現後、明らかに国民は吉田長期政権に飽きを感じていた。世論や野党を無視しがちな彼の強引かつ秘密的な政治手法への国民の反発も高まった。そのため、平和条約調印時には58%あった支持率も発効前月には33%に急落、また講和独立とともに吉田政権を支えていた政治環境が変化した。51年4月にマッカーサーは解任され、さらに平和条約の発効によって翌年4月に総司令部は解消し、占領軍の絶対権力という後楯を吉田は失ったのである。
しかも吉田政権動揺のより直接的な契機となったのが追放解除(51年6月以降)による戦前派政治家の政界復帰であった。追放を解除され、52、53年の総選挙で政界に返り咲きを果たした解除組党人派の中心は鳩山一郎であり、解除組官僚派には重光葵と岸信介がいた。このうち鳩山は戦後、日本自由党を結成し、初代総裁として組閣直前に追放された。不運にも鳩山は追放解除直前に脳溢血で倒れるが、一年余の療養ののち52年9月政界への復帰を果たし、憲法改正と再軍備、それに日ソ国交回復の必要性を訴えた。
日本の安全保障を専ら米国の軍事力に頼り、改憲も本格的な国軍建設も回避し、なし崩し漸増再軍備の手法に拠る吉田の政治姿勢には、軍拡反対・平和憲法擁護を唱える革新勢力のみならず、憲法改正と正規の国軍再建を求める政界復帰を果たした戦前政治家を中心とする保守の内部からも強い反発が生まれるようになる。彼ら戦前派の政治攻勢を受け、吉田政権も遂に崩壊へと至るのである。
8 対日援助獲得のため自衛隊を創設
国内だけでなく米国からも吉田は防衛力増強の圧力に晒された。トルーマン政権の跡を継いだアイゼンハワー政権は軍事費削減を目指し、核への依存を強め米軍通常兵力を削減、それを同盟国の軍隊で補おうとした。そこで日本に大規模な防衛力増強を行わせるために米側が構想したのが相互安全保障法(MSA:Mutual Security Act)の日本への適用であった。同法は、米国が従来同盟国に行ってきた様々な対外援助計画を一本化し、軍事・経済・技術の各援助、供与を総合的に行なう対外援助プログラムで、このMSA援助を日本に適用し対日援助を与えることと引き換えに、再軍備を求める動きが52年頃から出始めた。
MSA締結の方針を固めた吉田内閣は対米交渉を申し入れるが、米側は日本の防衛努力の不足を指摘し、保安隊を35万人・10個師団程度まで増強するよう求めてきた。経済援助に固執する日本側と、日本の防衛努力不足故に援助を軍事分野に限定しようとする米側の意見は対立し、交渉は中断に陥る。
そのため、対米折衝を有利ならしめるには国内政治基盤の安定が必要と考えた吉田は、自由党総裁として改進党総裁重光葵との党首会談に臨む。この会談で両者は自衛隊の創設と長期防衛計画の策定で合意が成立。この合意を受け53年9月29日、吉田首相の特使として池田政調会長が訪米し、ロバートソン国務次官補との折衝に臨んだ。池田の任務は、米側の防衛力増強要請を極力抑えつつ、最大限の経済利益を引き出すことにあった。
激しい両者のやり取りが続いたが、35万人・10個師団を求める米側に対し、池田は18万人・10個師団の増強案で押し切った。日本側は経済の安定発展が防衛力漸増の先決要件との立場を押し通し、相互安全保障法が定める「自国の防衛力を増進しかつ維持する」義務についても、国内の経済等諸条件の許容する限度内で応じるとの姿勢を堅持した。
米側は、国内の制約要因を口実に防衛費を米側に肩代わりさせようとすると日本の姿勢を非難したが、無理強いして親米政権が倒れ、日本の中立・共産化を招くことにでもなれば元も子もなくなってしまうとの懸念も働いた。そこに米側の弱みがあり、日本が駆け引きに持ち込める余地があったのだが、この会談でもそのような構図が示された。安全保障努力を経済復興実現のための援助獲得の交渉材料とし、かつ、平和憲法の存在など国内の制約要因を盾に米側の防衛力増大要求を極力抑えようとする吉田の姿勢は、これ以降も歴代政権に継承され、戦後日本外交における対米交渉の基本的スタンスとして定着することになる。
54年3月8日にMSA協定が調印された。これによって米政府は5千万ドルの余剰農産物を日本政府に提供し、日本政府はその代償に見合う円を米政府の特別勘定に積み立て、兵器等米国からの軍事援助物資や役務の調達及び日本の工業能力発展のために使用できることになった。
他方、米国から防衛力増強措置の実行を迫られた吉田は、自由・改進に日本自由党を加えた保守3党間の協議を経て防衛庁設置法案および自衛隊法案(防衛2法案)を国会に提出し可決成立の運びとなり、54年6月9日公布、7月1日施行となった。防衛二法の施行により保安庁は防衛庁となり、保安隊は陸上自衛隊、警備隊は海上自衛隊に改編され、新たに航空自衛隊が設けられた。防衛庁は「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的」(防衛庁設置法第4条)とし、自衛隊は「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略および間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法第3条)ものとし、それまでの治安維持を目的とした警察予備隊、保安隊、警備隊と異なり、自衛隊は外部からの武力攻撃(直接侵略)に対処する軍事力であることが明記された。
米国からMSAに基づく防衛力増強を迫られ、国内では保守派の突き上げに直面する等出発当初から不安定な政局運営を強いられた第5次吉民田内閣であったが、年が明けるやいわゆる造船疑獄に直面した。また保守合同の動きが持ち上がり、54年11月、吉田の自由党を脱党した鳩山一郎のグループや同党を除名された岸信介が改進・日本自由の保守両党と合流し、日本民主党を結成した。
国力回復(=経済復興)を優先させ、本格的な急速な再軍備を求める米国の要求に抗しつつ、「戦力なき軍隊」論にみられるように、自衛隊の存在を現憲法の拡大解釈でその場凌ぎ的に乗り切ろうとする吉田と袂を分かち、鳩山や岸らは憲法改正と再軍備を志したのである。この動きに吉田は解散で対抗しようとしたが、側近らの強い助言を受け容れ、54年12月7日吉田内閣は総辞職する。講和実現後の吉田は政権への執着極めて強く、その末路は惨めであった。
第2章 吉田茂:その政治手法と功罪
1 アングロサクソンとの提携
吉田茂は、その長期政権を通して、日本の独立回復を実現し、戦後日本外交の基調である対米協調の路線を定着させた。また日米安保体制の下、軽武装・経済中心主義を戦後日本国家の基本方針に据えることで、吉田は戦後復興を為し遂げ、ひいては高度経済成長に途を開いた指導者として評価されている。確かに、敗戦以降、外国軍隊の支配を受ける状態から一日も早く抜け出し、国家としての独立と主権を取り戻したいというのは日本人全体の総意であり、単独講和という格好にはなったが、これを実現した功績は評価されるべきである。
日本外交のあるべき姿として常々吉田が頭に浮かべていたのはアングロサクソンとの提携であった。日英同盟を高く評価していた吉田は、戦後日本外交の路線もこれを踏襲したものたるべきだと考えていた。そして、もはや覇権を失った英国に代わり、新たな世界国家として登場した米国との同盟関係を構築し、パクスアメリカ−ナの秩序を受入れ、その枠組みの中で日本の復興と経済的発展をめざした。日本国家発展の基礎が自由貿易を前提にせざるを得ない以上、こうした吉田の選択は基本的に正しい判断であった。
吉田が選んだ道は、取り得る選択肢が極めて限られていた当時の日本の状況下では、彼ならずとも他の保守政治家も同様の選択をした可能性が高い。しかし、国論が分裂する中、平和主義に拘るマッカーサーと良好な関係を築き、マッカーサーの絶大な権力と威光を利用して自身の政策を実現させた彼の力量は認めねばなるまい。
ただ、吉田が終始再軍備に反対し、軍事力ではなく経済をもって戦後日本発展の基本路線に据えたという理解の仕方には留保が必要である。後年、こうした軽武装・経済中心主義の考え方は「吉田ドクトリン」という名の下に美化、さらには神話化され、吉田がそうした路線を戦後日本の確たる国家方針として打ち出したかのような解釈が広く流布しているが、これは誤解あるいは曲解といわざるを得ない。
2 現実主義者としての吉田
本来、吉田が採用した再軍備回避の経済中心主義なるものは、あくまで戦後復興を実現するまでのいわば暫定的、便宜的な手法に過ぎず、平和憲法の理念を体現化させた戦後日本の恒久普遍的な国家方針などではなかった。無論、戦前のような軍事大国路線の復活を吉田がめざそうとしたわけではないが、外国に自国の安全保障を全て委ねる、あるいは外国軍隊の長期駐留を許すということは、彼にとって当座のやむを得ない選択肢であって、それ以上の価値ある政策ではなかった。
米ソに拮抗する軍事力を持つことは「敗戦日本が如何に頑張ってみても、到底望み得べきことではな」(吉田茂『回想十年』)く、しかも、集団安全保障が世界の通念となりつつあるならば、日米安保に依存することはこの流れに添うものであり、そのうえ日本の復興にも専念できる。吉田の真意はこのようなもので、それは極めて実利的な判断であり、と同時に没理念的な選択でもあった。つまり、自らが選択したものでありながら、吉田はその心底において軽武装・経済中心主義なるものに積極的な価値観や意義を見出したわけではなく、かかる当座の便法ないしは交渉戦術を新生日本の国家方針や外交理念へと発展せしむる意図も彼にはなかった。
吉田がそうした手段を選んだのは、日本が置かれていた敗戦国家という当時の国際環境厳しさもさることながら、彼が理念家や理想主義者では決してなく、極めて現実主義的なプラグマティストであったことと深く関わっている。生前吉田は自らの政治、外交哲学を体系的に語ることが少なかった。それが吉田ドクトリン神話を生み出す一因ともなるのだが、寡黙であったのは彼の性格だけでなく、そもそも吉田の政治姿勢が現実的かつ状況対応的なため、原理原則を語り難かったためでもあった。しかも、敗戦を境として日本が大きく生まれ変わった、あるいは大きく生まれる変わるべきだという強い意識は吉田にはなかった。彼が重要だと考えたことは、日本外交の基軸を再びアングロサクソンとの連携に戻すことであり、貿易を活発化させることにあった。
吉田にとっては経済復興こそが重要なのであり、経済が豊かになってこその民主主義であり、国民が潤ってこそ、民主主義も日本に根づくという発想。それはまさに、衣食足って礼節を知る、恒産なければ恒心なしという考え方である。戦前、彼が軍部の台頭に反発したのも、それが英米との対立を不可避ならしめ、満洲における経済権益確保を危うからしめることを恐れたためであり、軍国主義そのものを憎んだわけでもなければ、中国における民族主義の興隆に深く思いを巡らせることもなかった。吉田にとって理念やイデオロギーは、外交における至上価値たるべきものではなかったのである。
さらに付言すれば、商人的な国際政治観を持ち、英米と連携し、その自由貿易体制にはいることで日本の経済復興と戦後の発展を吉田は考えたが、それ以上の構想、即ち、独立を回復した後の日本の長期的な国家ビジョンや戦略を持ち合わせていたわけではなかった。
3 当面的措置としての護憲・再軍備反対
それは再軍備反対に彼が揚げた理由にも見て取れる。そもそも吉田が再軍備に反対した理由は、経済的負担の増加、周辺諸国の警戒心、国民の反軍感情や軍国主義復活への懸念であった。さらに朝鮮戦争当時においては、再軍備した場合、日本の部隊が朝鮮半島に投入される事態を吉田は恐れていたといわれる。しかし、こうした反対理由は時の時代環境からくる制約や状況対応的なものに過ぎない。日本国憲法の掲げた平和主義の尊重や実現といった崇高な理念やイデオロギーに由来するものでは全くなかった。吉田は後年、憲法調査会の質問に対し、憲法第9条について、
「この戦争放棄については、私自身も賛成であったのであります。日本は平和に害のある好戦国民であるというのが、当時の連合国における通念であったと思われますが、そのような誤解をとき、日本国民が平和愛好の国民であることを認めさせるためには、戦争放棄の規定を設けることは適切であると考えておったのであります。・・・朝鮮事件のころ、再軍備論争が起こりましたときに、私はこの憲法の条項を楯にとって正面からこれに反対し、幸いにこの問題は日米双方の検討の後、マッカーサー元帥の理解ある示唆によって処理され、日本に残存する旧陸海軍の遊休設備を活用することによって、その要望に間接に協力することにしてはどうかということに落ち着いたことがありました。このときなどもこの第9条が役立ったというように考えておるのであります」(『回想十年』)と述べている 。
しかし、吉田がマッカーサー草案を初めて見せられたとき、戦争放棄条項に賛成したというのは明らかに事実に反する。再軍備の経緯にも虚飾が加えられている。ここで吉田は、自らの採ってきた政策を“積極的な軽軍備路線”と美化しているが、彼自身が新憲法に満足していなかったことは、新憲法公布直後の47年2月に吉田がしたためた「新憲法 棚のダルマも赤面し」という色紙の文句から窺え、さらに以下の評価からも明らかである。
「憲法第9条は、いわゆる不磨の大典との一条項として、将来に亘って変わらざる意義を持つものというよりも、どちらかといえば間近な政治的効果に重きを置かれた傾きがあり・・・第9条第2項の軍備否定の条項は、永きにあたり亘って堅持すべき憲法の規定としては、多かれ少なかれ問題があることはこれを認めなばなるまい」(吉田茂『世界と日本』)。
彼にとって平和主義を掲げた憲法は、軍国主義の否定を宣言することで諸外国の日本に対する信用を回復するための国際公約あるいは条約の如きものでしかなく、その目的を達成した暁には当然改廃されてしかるべきものであったのだ。
現に吉田は、幾度か改憲の意志表示をなしてもいる。例えば第3次吉田政権末期の52年7月、岡崎外相はマーフィー駐日大使に、(抜き打ち解散後に予定されている)総選挙後に吉田は憲法改正を行う決意である旨伝えており、クラーク国連軍最高司令官が米国の統合参謀本部に宛てた同年10月4日付けの報告書の中にも、吉田自身がマーフィー大使に同様のことを口頭で伝えたことが記されている。吉田は保安隊を正式の国軍とすべく改憲を意識していた。岸信介も吉田から直接、その意志を聞かされている。
「吉田さんは、・・・おれも今の憲法は気にくわないけれど、あれを呑むよりほかなかったのだから、君らはそれを研究して改正しなきゃいかんと言う。・・・吉田さんは改憲論者だったんです。しかも占領軍がいる間に改正しないと、できなくなると言っていた」(岸信介・矢次一夫・伊藤隆『岸信介の回想』)。
要するに吉田も、戦争放棄と国家の自衛権をも否定するかのような新憲法の平和主義にはその本心において反発を覚えていたのであり、それは戦前派官僚に共通した一般的な意識でもあった。彼は決して戦後派ではなく、鳩山らの戦前派と意識の面では同根であった。近衛文麿が「吉田君の意識は『大日本帝国』時代の意識だ」と評したのは正当な判断であった。だから、彼が採った路線は、反吉田派が批判したように実は彼自身にとっても苦渋の選択というべきものであって、理念や理想を下敷きに構想、遂行されたものではなかった。そうであるがゆえに、できれば占領終了前マッカーサーの威光のあるうちに、あるいは独立回復後も機を窺って改憲を為し遂げたかったのである。
しかし、マッカーサーが突然解任されその機を逸し、また吉田に反発する鳩山ら復帰組が再軍備、改憲を声高に掲げたため、それまでの責任者として、かつ自己弁護の立場から吉田は態度を翻し護憲に回った。『回想十年』の中で、
「憲法改正のごとき重大事は、仮にそのこと有りとするも、一内閣や一政党の問題ではない。もちろん私といえども、永遠に改正を不可とするものではない。・・・国民の総意がどうしても憲法を改正せねばならぬというところまできて、それが何らかの形で表面に現れた時に、始めて改正に乗り出すべきである。・・・一内閣や一政党が改正の功をあせるが如きは、強く排撃せねばならぬ。・・かかる点からしても私はわが国の憲法改正のごときは急ぐべからずと確信するのである」
とも書いているが、これも鳩山の改憲論を意識しての感情的反発と見るべきであろう。
憲法に対する吉田の処し方は、再軍備問題においても全く同様であった。吉田は、当面再軍備は得策でないが、やがて独立を達成し、国力も逐次回復すれば、おのずから国家としての軍事力を整備、保有することは自然の成り行きだと考えていた。ただ、それを公言することは米国の再軍備要求を許し、日本の復興を阻害するため、当面採るべき合理的な選択ではないと判断したのである。吉田の再軍備に対する本音は、宮沢喜一が語る以下のようなものであった。
「再軍備などというものは当面到底出来もせず、また現在国民はやる気もない。かといって政府が音頭をとって無理強いする筋のことでもない。いずれ国民生活が回復すればそういう時が自然に来るだろう。狡いようだが、それまでは当分米国にやらせて置け。憲法で軍備を禁じているのは誠に天与の幸で、米国から文句が出れば憲法がちゃんとした理由になる。その憲法を改正しようと考える政治家は馬鹿野郎だ」(宮沢喜一『東京−ワシントンの密談』)。
事実、独立を前にしての保安隊創設を吉田は国防軍建設の第一歩と認識し、政治情勢如何によっては、改憲とともに、正規の国軍建設を打ち出していたかもしれない。服部機関を遠ざけるなど軍国主義敵勢力の復活には警戒心を持っていたが、辰巳栄一を重用して再軍備計画に当たらせるなど吉田自身は独立後の再軍備にさほど抵抗感を持ってはいなかった。
しかし、この問題でも反吉田勢力の台頭に直面した吉田は、改憲と同様、結局、国防問題においてもイニシアティブをとることはなく、首相の職にある間、それまで同様に再軍備否定一点張りで押し通したのであった。その際、彼の胸中には、自分が国防を認めれば鳩山らによって軍事大国路線が復活することへの懸念があり、それを阻止しなければならないといった使命感が芽生えていたのかもしれない。だが、たとえそれが彼に再軍備反対を貫ぬかせた一因であったにせよ、それ以上に、これまでの自らの路線を否定されることへの反発や鳩山に対する敵対心の方が遥かに強かったものと思われる。
4 高邁な理想なけれど目標あり
では、こうした吉田の選択をどう評価すべきであろうか。繰り返すが、吉田の外交や安保に対する姿勢には、長期的な視点や崇高な理念が伴ってはいなかった。しかし理想主義的でないにせよ、独立の達成と戦後復興という明確な目標がそこには掲げられていたわけで、現実主義、状況対応的ではあっても、それはゴ−ルのない場当たり主義とは異なるものであった。そもそも実利主義的で没理念的であるのは我が国の対外交渉にしばしば見られる民族的伝統ともいうべきものであり、吉田もその例外ではなかったということである。それは吉田一個人の限界に帰せしめるよりも、日本外交の限界として論じられるべき問題かもしれない。
吉田と同じ時期に戦後西独の首相として、その復興に功績を残した人物にアデナウアーがいた。彼は西独を西側の一員として位置づけ、同国の国際社会における復帰を促すため、吉田とは対照的に早い段階から軍事的な貢献を前面に押し出し、また国軍の新生、再建を政権の重要課題として重視した。しかし、共産大国と地続きの西独と周囲を海に囲まれている我が国とでは地政的環境が異なり、国防や安全保障に対する認識ばかりか、その拠るべき立場も大きく相違している。そうした差異を考慮することなく安易に両者を比較してもさほどの意味はない。冷戦の主戦場となり、しかも民族分断という事情を抱えるアデナウア−の場合、どうしてもソ連の軍事的脅威を重視せざるをえない立場にあったが、これに対して吉田は日本国内の治安維持には懸念を示しつつも、ソ連軍の日本侵攻の蓋然性については極めて低いものと判断していたし、マッカーサーも同様の認識であった。こうした判断は朝鮮戦争勃発後も変わらなかった。
吉田の脅威認識は、共産勢力の軍事侵攻の可能性を深刻視する米軍部の情勢判断や冷戦思考を強調するダレスの善悪二元的な認識よりも冷静かつ客観的であり、しかも正当なものであった。そしてそうだとすれば、むやみに東西軍事対立の脅威、危険性論に同調することなく、大国米国の東アジア冷戦戦略の中で高まりを見せる日本列島の戦略的価値を基底に、急ピッチな再軍備を避け、米国の庇護とパワーの中で戦後復興に専念しようとした吉田の姿勢や路線は、日本の立ち直りを早め、その後の経済成長をもたらしたという経済国益の観点からは、高い評価が与えられてしかるべきである。
5 取引材料としての安保・防衛政策
だが、吉田は「再軍備は致しません」と繰り返しながら、実際には講和の前も、そして講和後も少しずつ再軍備を進めていった。(当初は自衛すらも否定する形で)再軍備を拒否しながら、現実には密かにそれを受け入れたこと、その際、自主的にではなく、米側の要請に最後まで抵抗した挙句、屈伏・譲歩の格好をとって再軍備に応じたこと、その実、そこにはバーゲニングの論理が働いており、再軍備が本来の安全保障とは別に、独立の回復や米国らの経済援助獲得の見返りとしてなされたこと等々吉田の外交・安全保障に対する便法的な姿勢と、その背後にある没理念性は、その後の日本の外交・安保政策のみならず、日本社会の精神構造にも極めて大きな問題を残した。
彼の手法は、安全保障を自身の問題として考える姿勢を失わしめ、歴代保守政権も、程度の差こそあれ、一様に国防や安全保障問題を対米交渉を有利に進めるための−特に経済的利益獲得のための−取引材料として扱い、何時しかそれが対米外交の基本スタイルとして定着してしまう。しかも内政問題である憲法の規定を根拠に、それを米国へのエクスキューズとする戦術は、内政の延長で国際政治を捉える習慣を日本人に植えつけたし、他面、米国には再軍備を認めながら、国内おいてはその実態を最後まで認めなかったことは、国の内外で建前と本音を使い分けることへの抵抗感を消失させた。そして何よりも、なし崩し再軍備の手法は、国防の位置づけや必要性、さらには憲法解釈をも曖昧なし崩し化させ、国家存立の基礎である理念や規範の混迷化を招いたのである。
吉田のなし崩し再軍備路線が芦田、鳩山らの正式再軍備派と完全な非武装主義者という左右双方から攻撃され続けた結果、その中間として適度な自衛力(軽い武装経済中心主義)に限定できたという効果を高坂正堯は指摘するが(高坂正堯編『吉田茂:その背景と遺産』) 、鳩山の自主防衛論なるものが多分に反吉田を意識した政治的スローガンの域に留まり、実際の防衛力増強にさほど熱心ではなかったこと、また仮に鳩山らが安定政権を確保し再軍備路線を推し進めたとしても、そもそも世論がそれに消極的であった以上、急激な軍備拡大は現実的な選択肢とはなりえず、結果的に吉田とほぼ同様の路線に落ち着かざるを得なかったであろうから、これを吉田の功績とみるのは結果論としても過大評価である。問題は防衛力の単なる規模ではなく、その根底にある理念や思想の堅固さである。もともと実利的な日本の対外姿勢であるが、吉田流は一層日本外交から理念を喪失させた。
6 理念の共有なき同盟
さらに、アングロサクソン重視とはいえ、吉田の対米接近は米国力を日本の復興に利用しようとする戦術的な色彩が強く、米国的な価値観や民主主義の共有という理念的な連帯感を見出す意識は乏しかった。それは彼が親英ではあっても親米ではなかったことも関係しているが、米国との連帯の意義を国民に十分説明し、また民意に耳を傾けることもなく、占領の延長として米軍を受入れ、日米安保体制という国家の基軸をいわば国民に対して押しつけたことは、外交選択における国民の参加意識や安保条約に対する世論の支持・定着を阻害させてしまった。
常々吉田は日米安保体制をかつての日英同盟とオーバーラップさせていたが、「日英同盟が成立するや、・・朝野に亘って快くこれを迎えた。そして、やれ、これで日本は英国の帝国主義の手先になるとか、英国の植民地化するとかいう如き、猜疑心的悲観論を唱えるものは、何ら見当たらず、むしろ“東洋の英国”たることを誇りとした」。にも拘らず「いわゆる進歩的文化人や左翼の革新的思想の持ち主と称せられる連中が、何か対米関係の問題が起こると、米国の植民地化だとか、アジアの孤児になる」と非難することを批判し、「これが日英同盟から僅々半世紀を下手に過ぎない日本人の姿かと、私はむしろ奇異の感を抱かされるのである」と嘆いている(『回想十年』)。
しかし、それは国民的な意見の表出を経ぬままに再軍備を行ったのと同様、彼が世論や国民的論議に立脚するかたちで日米安保体制を受け入れなかったことの必然の産物に他ならなかった。そのうえ、彼の理念不在外交は、米国への依存意識ばかりが強く、理念を分かち合う真の同盟へと日米関係を発展させようとの意識が日本社会に芽生えにくいこととも無関係ではあるまい。
7 戦後教育の在り方に関する無関心
理念に対する拘りや意識の希薄さは安全保障や国防の在り方だけではなかった。国の防衛と同様に、国歌存立の基盤を為す教育に対しても、吉田は関心や努力をさほど払わなかった。先に見た西独のアデナウアーは、戦争に敗れたとはいえ、ドイツにおける国防と教育の在り方については、民族の在り方に関わる問題でドイツ自らがその基本を定めるとして、極力戦勝国の口出しを許さなかったといわれる。
これに対し吉田はどうであったか。国防については既に取り上げたが教育はどうであったか。戦後、民主国家として生まれ変わった我が国の新しい教育の在り方について検討を行うため、46年3月に米教育使節団が来日、その勧告に基づいて教育刷新委員会が設置された。官僚を含めず理想主義的な傾向が強かったこの委員会は、46年4月から6334制を導入すべしとの答申を出した。
だがこの案では、戦前に比べ義務教育の期間が3年も延びることになるため財政負担が重く、敗戦によって財政的な困窮状態にある政府は実施困難として難色を示した。そこで交渉の結果、63制は46年4月から実施することとなり、以後、高校・大学は1年ごとの実施とされた。
「戦後日本の再建復興に教育は重要」との声が国民の間からも強いものがあったが、吉田は財政面からの早期導入に抵抗し、実施を五月雨式に引き伸ばしただけで、戦後教育の在り方やその内容についてはほとんど興味を示さなかった。先にも引用したが、近衛が「吉田君は大日本帝国時代の意識だ」と評したように吉田茂は明治日本人の意識をそのまま戦後も継承し続けていた。それならばGHQや日本の中にもあった進歩派知識人が説く西洋流の民主教育に押し切られることなく、明治あるいはそれ以前から続く日本人としての徳目や精神倫理を戦後においても廃絶させぬような取り組みや指示がなされて然るべきであったろうが、そうした事実はない。吉田の関心や拘りは食料の確保や経済復興、財政などあくまで現実的な問題に限られ、国家百年の在り方を規定する教育問題は視野の外であった。彼は戦後教育を軽視したのである。
8 現実主義者の非柔軟性がもたらす悲劇:固執、誇示そして神話へ
話を再び外交や安全保障問題に戻すが、ここでは独立回復後の吉田の政治姿勢に焦点をあわせたい。それは見落としてはならないさらに重大な問題があるからだ。それは、現実主義的な吉田がやがて、現実主義の前提から逸脱していったという点だ。
そもそも吉田の現実主義外交は、それが理念的理想的なものではなく、あくまで現実主義的なものであるがゆえに、状況が変化したならば、それに適切に対応、変化すべきものでなければならなかったはずである。そして何よりも大きな状況変化は独立の達成であった。しかし、独立を果たした後においても、吉田は政権への執着ゆえか、公的そして結果的に、それまでの自らの路線に固持し続けた。そのうえ(現実主義者としての限界のためか)固執するばかりで、吉田は自らの路線を理念的なものへと昇華させる努力を怠り、世論に平和主義、平和外交の意義を訴えかけることもなかった。
さらに政界を退いて後、日本の国力充実に伴い、経済中心主義に対する国民の評価が定着するや、あくまで便宜的、暫定的なものであった自らの路線の正当化に意欲を見せ、また日ソ正常化や岸の安保改定に反対する等吉田路線を否定するような動きに対しては強い反発を示した。1960年代に彼が著した『回想十年』も、かような背景を踏まえて読み取らねばならない。そして、こうした便法主義再評価の動きがやがて吉田ドクトリン神話となって形を整え、日本外交の方向転換の阻害要因になったのである。
戦後復興と独立達成という当面の目標達成にとって、彼が選んだ路線とその成果を吉田が自負していけない道理は無論ない。だが、本来吉田のなすべきことは、そうした路線が過去に実績を挙げ得たものであっても、単なるその踏襲、延長は既に高度経済成長への途を歩みつつあった日本にとって好ましい選択ではなく、むしろ日本の発展を妨げることへの危惧を訴えるべきではなかったろうか。
実は吉田田自身も晩年、自らの現実主義が安全保障政策に大きな影を残したことを憂慮していた。例えば1964年、辰巳栄一に宛てた書簡において吉田は「国防問題の現在ニ付深く責任を感し居候次第」と述べている。だが、そうした悔悟を日本外交の方針転換のための糧足らしめるには至らなかった。高度成長の成果と夢に、彼もまた飲み込まれてしまったのである。
独立回復と復興という戦後初期の課題達成に関して吉田の政策は評価さるべきである。しかし、その後の日本を取り巻く国際環境の変化に対応し、あるいは徐々に自身を取り戻しつつあった国民の意識変化を直視し、舵取りの方向を変化させる作業を彼は怠った。現実主義者であることそれ自体をもってではなく、問われるべきは、状況変化への対応を怠り、あるいはそのタイミングを失したことに対する現実主義者としての責任である。また現実主義者の宿命あるいは政治家吉田の限界ともいうべきか、暫定、便宜の路線に理想やビジョンといった生命を吹き込み、それを戦後日本外交の理念的支柱に高からしめようとすることにも、吉田は熱意を示さなかった。このような吉田の政治姿勢が、戦後日本の政治や外交、安全保障における理念・哲学の不毛不在を決定づけた点を看過することも出来ない。
総括 吉田茂は宰相の名に値する指導者であったか
では、吉田茂は果たして「宰相」の名に値する指導者であったろうか。そもそも「首相」と「宰相」は何が違うのか。一般に「首相」が「内閣を構成する閣僚(大臣)のうち首席の者」を意味するのに対し、「宰相」とは「特に君主の命を受けて宮廷で国政を補佐する者」と捉えられている。従って、近代以後の各国の行政府の長を「首相」と呼ぶのに対し、近世以前において宮廷で国政を担当した者を一般に「宰相」と呼んで区別するのが通例である。
つまり「首相」と「宰相」は、それぞれ異なる時代と政治システムを反映した言葉とされるわけだが、現代でも内閣総理大臣や首相の通称として使われることが間々ある。それは特筆に値する功績や事績があった首相に対する敬称として用いられる場合だ。原敬を「平民宰相」、高橋是清を「だるま宰相」と呼ぶが如くである。
本稿では、単に首相在職時の評判や治績が評価されているだけではなく、むしろ首相在任当時の世論の評価や支持率はたとえ芳しくなくとも、国家の行く末や進路を正しく見定め、それに筋道をつけたり、その路線を切り開き、定着させるなど国家百年の計を踏まえその実現に寄与し、功績を遺した首相という意に解釈したい。
講和の実現と国際社会への復帰、それに日米安保を軸とする日米同盟構築に道筋を付けた。また米国の再三にわたる再軍備要求を交わし、経済中心・軽軍備の路線を貫き、それが我が国の戦後復興、さらには高度成長へと繋がった。これが吉田茂の二大功績と言える。
また吉田の政策を戦後日本を規定したより長期的な政策、ドクトリンの形勢者として高く評価する声が強い。だが、吉田自身そのような吉田路線の固定化を正しき途とは考えていなかった以上、所謂吉田ドクトリンの形成者ゆえに宰相と評価することは的外れである。
では吉田自身が吉田路線の固定化を望んでいなかった以上、改憲・再軍備という本来の道筋に契機を付けるような取り組みを彼はしたのか。特に問題視したいのは、独立回復後、そして首相の座を降りた後の彼の政治姿勢である。吉田は経済中心の外交や軽軍備の路線はあくまで敗戦直後の国力喪失という異常事態における便法と考えていた。そして時が来れば再軍備するのは当然のことと理解していた。また戦後憲法も評価してはいなかった。それはマッカーサーが押し付けたものであり、独立回復後は自主的な憲法を制定することに異論を持っていたわけではない。平和憲法なるものは再軍備に抗い、その抗弁に使い得る好都合な代物に過ぎなかった。
そして独立の回復によって、正式な再軍備や改憲を為し得る時期が到来したが、吉田はそのような動きを見せず、それどころか改憲再軍備論者に激しく反発、抵抗した。確かに現職の首相として、自らが押し進めた路線や手法を自らが否定して回ることには無理もある。またレイムダック化した政権末期にそのような力は残されていなかったかもしれない。
だが引退後ともなれば、弟子や後継者、あるいは後継の内閣に対し、再軍備・改憲を促し、支援を為すことは可能だったはずだが、事実は全くの逆であった。吉田は改憲再軍備を説く鳩山の路線やより対等な形になすべく安保条約の改定をめざした岸の取り組みに反対した。自身の内心に近い路線を進めようとする後継者の足を引っ張り、便宜的な自身の政策の固定化に固執したのである。再軍備はまだ早いということだったのか。しかし、独立回復を果たしてなお再軍備が早計という発想は、大日本帝国当時の意識の持ち主としては不自然に過ぎる。
「講和条約後においてさえ、もし日本が憲法改正をしていたならば、日本は米国の再軍備要求を断るのにより大きな苦労をしたことであろう。そのため日本の経済発展の速度はかなり遅くなっていたかもしれない」(高坂正堯『宰相吉田茂』)と吉田の判断を是とする向きもある。だが、経済成長の速度が国家の基本をなす憲法の問題よりも重要だとは思えない。
確かに改憲・再軍備や安保条約の改定は国民には不人気だった。その点吉田の判断は正しかったともいえる。だが、吉田茂という政治家は世論を重視するポピュリストではなく、その真逆、民主政治の時代においても、政治や外交は世論にただ従うのではなく、それに抵触しても独立国家としての本義大道を誤らぬよう指導者が主導し、自らの責任の下で高度な政治判断を下すべきと信じる人間であった。自らの信念と齟齬し、その実践を怠ったことで、彼が望んではいなかったはずの吉田路線が定着してしまったのだ。
吉田茂という政治家は、当座の課題を便法的な措置を用いて克服し、敗戦直後の混乱期から成長と繁栄、それに安定の時代へと日本を導いた、その面では戦後日本における偉大な指導者ではあった。だが、当座の課題は便法的な措置を用いて克服したものの、吉田は国家にとってより重要な百年の計を立て、それを成し遂げることは出来なかった。
それどころか、国軍の再建を厭い、なし崩し再軍備の手法を繰り返した結果、国防の位置づけは曖昧。また自らの国は自らで守るというのが独立国家本来の姿であるところ、改憲を避け国家固有の権利である自衛権の行使も限定化され、安全保障を米国に大きく依存する体質を招くなど根深い問題を抱え続けての戦後80年となってしまった。その原因の根源は吉田茂に負うころが大きい。戦前期日本との断絶が続く一方、国家としての真の独立は未だ道半ば、それが我々の生きる戦後80年の姿である。彼を為政者とは言い難いのではなかろうか。