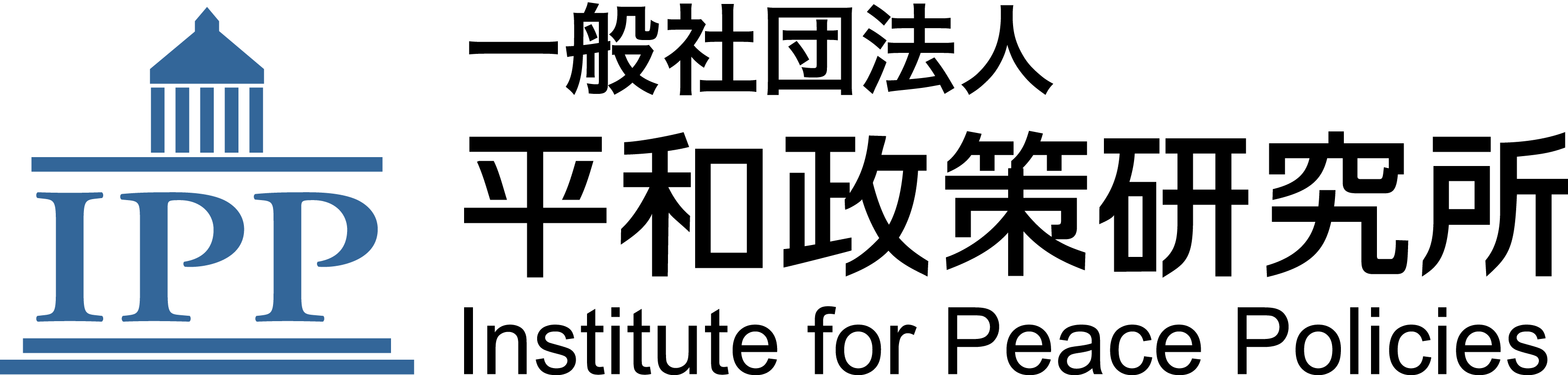1.はじめに
最初に国際政治をどう見るかについて、私の基本的スタンスを述べておきたい。まず、国際政治を分析する視点にはいろいろあるが、ジオポリティックス(地政学)の視点だけでは把握しきれないということ。もう一つは、エビデンスに基づく政策分析(Evidence-Based Policy Analysis)があまりにも軽視されているのではないかという点である。
とくに欧州のリアル(現実)を強調する識者も少なくないが、その意味は、日本の識者でどれほど欧州情勢についてリアルに基づいて認識しているのかということだ。EUは誕生以来70年の歴史を経て(われわれが想像する以上に)深化してきている。ところが、多くの方は、その方が欧州を理解した「時点」のリアルにとどまっていて、70年の深化の全体像をダイナミックに理解していないのではないかと思う。そうしないと欧州理解は、限定的で浅いものになってしまう。
譬えてみれば、メディアの特派員はロンドン、パリ、ベルリン、ローマなどに軸足を置いて報道しているが、それはまさに二国間外交をベースにしているといえる。しかし統合以降の欧州(EU)を理解するには、(その本部のある)ブリュッセルで何が議論され起きているかを理解しないと、現今の欧州情勢を語ることはできないと思う。ところが現実に、メディア、学者、外務省などは、二国間外交中心の発想になっている。今こそ、日EU関係を前提に見てほしいと思う。
もう一つ強調したい点は、EUの原点は「経済」ではないということだ。
このような観点を理解しない限り、欧州理解は皮相的なものに留まってしまう。そこで私は、欧州を中心に40年余の外交実務を経験した者として、現在は現場から離れた立場(中衛、後衛)で、(外交、国際政治の)理論の側から検証しようと考えている。ここではその一端を述べてみたい。
ところで、戦後欧州の秩序形成の最大の課題は、第一にドイツ問題の解決、第二に共産主義ソ連にどう対応するか、という二つであり、それに対応するべく(米国とも関与しながら)再興を始めたのだった。「ドイツ問題」は、独仏主導で欧州統合に足を踏み出した。もう一つの「共産主義ソ連との競争・共存」は、冷戦としてスタートし、ソ連の崩壊後は、ロシアをどう欧州秩序に取り込むかという課題に直面した。そして現在、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻によって、その課題は未完成のまま、あるいは粉々になっている情況である。一方、欧州の外に目を向けると、中国という21世紀最大の地政学的課題に覚醒しつつある。
このような問題意識の中、EUがこれまでの70年をどのように歩み、今後こうした挑戦にどう対処していくか、こうした観点から欧州(EU)情勢と今後の展望を述べてみたい。
2.欧州で成立した国際政治
(1)ウェストファリア体制(1648)からヴェルサイユ体制(1919)まで
ウェストファリア体制の意味は何かというと、中世が終わり、近世が始まったということ、つまり中世的秩序原理(精神世界のローマ教皇と、地上世界における神聖ローマ帝国およびそれを支える各国の王権の共存)から主権国家平等という体制への移行であった。言い換えれば、「ローマ・カトリックのヨーロッパ帝国」の終焉により、領土主権に基づく「対等の主権国家間の共同体(Community of Equal Sovereign States)」としての近代ヨーロッパの国際関係構造の確立であった。
その後、1919年(第一次世界大戦終結)までは、基本的に主権国家が自らの国益に動機づけられた権力の行使(武力行使)を肯定した期間だった。そこでは「平和価値」には高い優先順位が与えられなかった。そのため主権国家平等原則に基づく国家間の対立・紛争の手段としての戦争(武力行使)が肯定された。
18世紀以降の世界は、帝国主義/対外膨張主義の時代として規定できると考える。その終着点が第一次世界大戦だった。
(2)ヴェルサイユ体制(1919)成立から第二次世界大戦までの戦間期
第一次世界大戦の悲惨さに直面した欧米諸国は、「戦争」の違法化、少なくとも、主権国家による戦争を集団安全保障体制で防止せんとする人類初めての試みとして、ウィルソン米大統領の提唱により国際連盟を創設した。
しかし国際連盟は、当初から限界を抱えていた。とくにフランスは、普仏戦争以来の対独恐怖・憎しみ・復讐心を持っていたし、米国は孤立主義に回帰して国際連盟に加盟せず、独・日・伊は対外強硬のナショナリズムを背景にした対外膨張を展開し、国際連盟は無力をさらけ出した。そしてドイツのポーランド侵攻と日本の真珠湾攻撃により、第二次世界大戦に突入した。
(3)第二次世界大戦とは何であったか?
①世界史的には巨大な歴史的転換点
17世紀に出現した主権国家全体の国際社会は、ハンス・モーゲンソーの言葉を借りれば、国家理性が「力」に基づく「国益」を追求する場であり、その実現のための手段として「戦争」を容認する時代であった。それが、第二次世界大戦までの、国際政治の基本的動因であった。
第二次世界大戦の最重要の特質は、ファシズムと帝国主義に対する民主主義(普遍的価値擁護)の戦いであり、その戦いに民主主義が勝利した戦争であったということだ。そして勝利した(英米を主とする)連合国主導により、侵略戦争及び植民地主義否定の法理の実定国際法化の道筋をつけ、1945年に国際連合が創設された。国連憲章は、侵略戦争及び植民地主義否定を憲章規定に盛り込んだ(立憲主義の国際化)。
これによって「普遍的価値」(自由・民主主義・法の支配・人権)の重要性が高まり、1948年12月には「世界人権宣言」が採択されたことで、普遍的価値の国際法規範化が進んだ。
ちなみに日本の学校教育(義務教育)では、「世界人権宣言」の意義と価値についてほとんど教えていないように感じる。「個人はその権利と尊厳において平等である」ということを叩きこんでいない。
②帝国主義・植民地主義諸国間の戦争
第二次世界大戦は、英仏米にとって、帝国主義的政策で獲得した植民地をドイツの侵略から防衛するという意味で戦われた戦争でもあった。更に言えば、インド、アジアの植民地地域やアフリカにおいては、第二次世界大戦は植民地主義国間の戦争であった。
ドイツ帝国主義にすれば、第一次世界大戦の連続であり、日本帝国主義にすれば、「利益線」(山縣有朋)を守るための対外膨張であり、英米仏の植民地主義との戦いに挑む中で、アジア諸国を侵略した戦争であった。日中戦争は、帝国主義国家(日本)による侵略・植民地化とこれに対する民族解放戦争の性格を持っていた。
独ソ戦が第一次世界大戦の東部戦線の戦争と異なる点は、帝国主義国による社会主義国ソ連に対する侵略戦争であった。但し、ソ連の対日参戦は、帝国主義的な対日侵略戦争であることは否定できない。
(4)第二次世界大戦後から現在まで:戦後の新国際秩序構築
2025年は、1945年からちょうど80周年を迎える年でもあり、この期間を振り返るよい機会だと思う。私は、「国益」と「普遍的価値」に動機づけられた「力」の行使の時代の始まりだったと考えている。
①国際連合の創設
戦後秩序の基本は、「主権国家平等」原則であり、主権国家を超える権威を認めないという意味でリアリズムそのものである。さらに5大戦勝国の常任理事国化という意味では、might is rightを是認した。この点で言えば、ウェストファリア体制と何ら変わっていない。
他方で、「戦争の違法化」(平和価値の追求)、「非植民地主義」(帝国主義の終焉)、「人権価値の普遍化」というアイディアリズムをも体現している。
つまり、国連はリアリズムとアイディアリズムの相剋・妥協の中でできているといえよう。しかし日本人の傾向として、等身大ではなく、アイディアリズムのみの視点で見がちである。
②世界人権宣言の採択
国際政治の主動因としての「価値」の重要性が、今日ますます高まっている。
国際政治の主動因としての「価値」の登場は、「普遍的価値」(自由かつ平等な個人)を自国の独立・共和制樹立の基本理念に据えた米独立宣言(1776年)とフランス革命(1789年)を嚆矢とする。
「自由かつ平等な個人」という理念の誕生は、個人の自由の尊重と対等な個人が両立しうる政治制度(秩序原理)として、立憲民主主義を誕生させた(英米仏)。しかし、この秩序原理が地球規模の普遍的原理になるのは、第二次世界大戦の終了、国連創設を待たなければならなかった。
国連は、1948年、自由・民主主義・人権という国家が遵守すべき「普遍的価値」を「世界人権宣言」として採択した。その後、国際人権A規約(社会権)及びB規約(参政権・政治的自由権)として国際法規範として確立し、1976年に発効した(現在、A規約締約国:170、B規約締約国:173)。
ちなみに、B規約未批准国には、中国、ミャンマー、サウジアラビア、シンガポール、北朝鮮などがある。
③国連が掲げた理想と現実の乖離
戦後直ちに開始した米ソ冷戦、さらには1989年の冷戦終結後の現実世界は、「戦争(武力行使)の違法化」という理想を現実のものにできていない。
冷静に戦後世界の歴史の現実を眺めるなら、戦後「相対的平和」をもたらしたのは、「自由主義世界」対「共産主義世界」の間の集団安全保障体制(米ソ冷戦下でのNATO対ワルシャワ条約機構間の戦争抑止体制)であったことは否定できない。
その最大の理由は、「支配の正統性」(マックス・ウェーバー)をめぐる対立が続いていることだ。国民主権を支配の正統性とする「リベラル・デモクラシー」は、世界の三分の二以上の国家が受け入れている。一方で、「権威主義」(共産党独裁国家、首長制)を支配の正統性とする国家が複数存在している。この「価値」をめぐる争いは、21世紀最大の課題の一つと言えよう。
3.戦後の欧州国際秩序形成の歩み
(1)米・欧連合国にとっての戦後欧州の安全保障問題の本質
第二次世界大戦後の欧州の安全保障問題の核心は、次の二点に集約できる。
1)ドイツが二度と欧州の安全保障の脅威にならないようなシステムの構築
2)ソ連共産主義の脅威への対処
マクロン仏大統領がよく言及する「欧州の戦略的自立性」(Europe’s Open Strategic Autonomy)について言えば、欧州自身で、(核戦力などを考慮すると)欧州の安全保障を自立的に担保することはできないことを認識すべきである。欧州の戦略的自立性は、お釈迦様の掌(=米国)の上でのことに過ぎない。もちろん、大局的にはそうであるが、もう少し分け入ったところに限定すれば、欧州の自立性を論じることは可能だ。
(2)ソ連の脅威及びドイツの軍国主義化脅威への対処の略史
1948年3月17日、英仏白蘭ルクセンブルクなど西欧5カ国は、ブリュッセル条約(西欧同盟条約)を締結し、相互安全保障同盟を結成した。各国外相からなる理事会を設け、国防相、蔵相がそれぞれ防衛と財政について協議し、共同防衛を図ることになった。
その発端は、同年2月に共産党によるチェコスロバキアのクーデタ成功に衝撃を受けたチャーチル英首相が主導して、共産圏の武力侵攻に対抗する目的と同時に、ドイツ軍国主義の復活を阻止する目的もあって結成されたのだった。脅威認識の対象は、一義的にはソ連・東欧共産圏であったが、ドイツに対する警戒感は依然解けていなかった。
翌49年、ソ連の軍事力の脅威が高まったとして、西欧同盟加盟5カ国は米加に参加を呼び掛けた。米は、48年6月、米議会ヴァンデンバーグ決議によって孤立主義を克服し、欧州との軍事同盟への加盟を認めたことによって道が開け、49年4月4日、北大西洋条約が締結されNATOが創設された。
その後55年5月5日、米英仏西独が締結したパリ協定に基づき、西独の再軍備が認められ、翌日NATO加盟が認められた。ソ連は強く反発し、55年5月14日、NATOに対抗する軍事機構としてワルシャワ条約機構を結成した。
1955年から91年の冷戦終結とソ連解体までの間、欧州の安全保障は、NATOとワルシャワ条約機構の間の核戦力及び通常戦力の総体としての抑止戦略を双方が是認することで維持されてきた。つまり冷戦後の欧州の安保体制をどう構築するかが90年代の課題であった。
(3)ポスト冷戦期におけるNATO・ロシア関係の新たな展開
1989年の冷戦終結、ドイツ統一、91年のソ連崩壊は、NATO同盟に新たな課題を突き付けた。すなわち、依然として核保有国、核大国であるロシアを欧州安保秩序にどう取り込むかという課題だ。
冷戦後、ソ連の解体(共産主義の終焉)により、西側の対ロシア脅威認識が低下した。さらに「自由・民主主義」対「共産主義イデオロギー」という「価値」をめぐる戦いに勝利した西側は、ソ連の後継国であるロシアがNATOに敵対することのないことを期待した。しかし、そうはならなかった。
戦後1946年当時の欧州に、チャーチルの演説に見られるように、図1のような形で「鉄のカーテン」が下ろされた。
「バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで、ヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが降ろされた。中部ヨーロッパおよび東ヨーロッパの歴史ある首都は、全てその向こうにある」(1946年3月5日、米ミズーリ州フルトン「鉄のカーテン」演説)。
その後、ソ連崩壊後の1990年代になると、東欧諸国が共産圏のくびきから離れたものの、西側・東側のどちらにも属さない地域となった。
(4)検証:ソ連解体後のロシアの対欧米脅威認識に西側はどう向き合ったか?
*以下の分析は、板橋拓己「ヨーロッパにおける冷戦終結を問い直す—ドイツ統一とNATO拡大問題を中心に」『学士会報』No.961(2023-Ⅳ)に依拠する。
①ウクライナ侵攻を正当化したプーチンの「論理」
ソ連解体後、ロシアの欧米に対する脅威認識はどのようなものであったか。それに対して、欧米はどう対応したか。そこにはパーセプション・ギャップがあった。そのギャップがどう推移したかをしっかり把握しないと、なぜ2022年2月にプーチンがウクライナ侵攻に踏み切ったかは理解できないと思う。
まずウクライナ侵攻直前におけるプーチンの認識を、2022年2月24日のプーチン国民向け演説から見てみたい。そのポイントは次の二点だ。
▶NATOの東方拡大は、ロシアにとってとても根源的な脅威。
▶西側は「NATOを1インチたりとも東方に拡大させないと約束」したが、「われわれは騙されたのだ」。
もちろん、いかなる理由があろうとも侵略は許される行為ではなく、プーチンのウクライナ侵略の理由には一理もない。しかし、NATOの東方拡大については、プーチンの指摘する発言を冷戦終結時に西側の指導者がしていたことも事実であった。
②NATOの東方拡大
1990年2月9日にベーカー米国務長官がゴルバチョフ大統領に対して、口頭で次のような内容を伝えた。
▶「NATOの管轄及び軍事的プレゼンスが1インチたりとも東方に拡大されることはない」
(There would be no extension of NATO jurisdiction for forces of NATO one inch to the east.)
その真意は、ソ連が東西ドイツ統一及び米軍の西ドイツ領域への駐留継続を容認してくるなら、NATOを東方拡大させないという保証を口頭で言及したのだった。この約束を反故にされたロシアの不満も無理からぬが、NATO東方拡大については条文や公式声明の形で成立していない、というのが欧米諸国の立場だ。
③米国の方針変更:NATOの「統一ドイツ」への管轄権拡大
フランスにもドイツ統一については警戒心があったが、統一はやむなしという認識が形成され、サッチャー英首相も認めていた。
1989年11月にベルリンの壁が崩壊した後の翌90年2月24-25日、米独首脳会談(ブッシュ大統領・コール首相)で、旧東ドイツ地域へのNATO管轄の拡大が合意された。更に90年7月16日、コールドイツ首相が訪露してゴルバチョフと会談、ゴルバチョフからNATOの統一ドイツ拡大についての同意を得た。
この件について米ソ英仏・西独・東独が2プラス4合意をし(Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany、1990年9月12日署名)、同条約第5条3項で、旧東独地域へのNATO管轄権適用を承認したのであった。そして同年10月1日、統一ドイツが誕生した。
④1990年代における東方諸国のNATO加盟要求の高まり
図1に明らかのように、東西の空白地帯であった東欧諸国は、ソ連のくびきから逃れただけでは済まなかった。自らの安全保障をどう担保するかという課題に直面し、結果的に、NATO加盟を求めるようになった。
1991年2月、ヴィシュグラード・グループ(ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア。93年にチェコスロバキアがチェコとスロバキアに分離しV4となった)が、NATO加盟とEU加盟に必要な改革の実施を目的として設立された。
そして1997年5月17日、NATO・ロシア基本文書が合意された。この合意の意義は次の通り。
▶米NATO側にとっては、NATOの東方拡大をロシアに認めさせた意義があった。
合意文書の中に、「the territories of new members」や「on new members territories」という文言の挿入に成功した。結果、ロシアは本文書においてNATO東方拡大をいやいやでも認めたと見ている。
▶ロシアにとっては、NATO拡大に関するロシア側の具体的な懸念に対する米NATO側の以下の譲歩を踏まえ妥協した。
・現在及び予想可能な安全保障環境の中にあってNATOは、そのミッションの遂行は、新規加盟国へのNATO戦闘軍の常駐ではなく、相互運用性、統合性、増援能力を通じて遂行すると約束。
・核兵器と通常兵力(NATO部隊)の双方に関して新規加盟国への配備の制限を表明。
・冷戦時代の枠組みを前提に合意された通常兵器削減条約(CFE)を見直すことに合意したことなど。
こうした状況に対してエリツィン大統領は、97年5月のNATOとの基本文書署名後の演説で以下のようなコメントした。
・ロシアは依然としてNATOの拡張計画を否定的に見ている。
・しかし同時に、NATO諸国はそのような困難にもかかわらず、ロシアとの合意に達し、我々の利益に配慮する用意があることを認めている。
・それこそが、我々が現在経験している状況、ロシアとNATOの間の交渉の難しさの根拠であり、また本合意そのものの本質、推進力でもある。
さらに、97年12月に発表した国家安全保障計画の中で、NATO拡大は「容認できない」ものであり、ロシアの安全保障に対する脅威であると明確に述べた。
一方、97年7月のNATO首脳会議の直前の6月26日、ビル・クリントン大統領に宛てた公開書簡では、ビル・ブラッドリー(民主党上院議員)、サム・ナン(民主党上院議員)、ゲイリー・ハート(民主党上院議員)、ポール・ニッツェ(国家安全保障・核軍縮専門家)、ロバート・マクナマラ(元国防長官)など40人以上の外交政策専門家は、「現時点でNATO拡大は、ロシアに冷戦後の解決策全体に疑問を抱かせ、欧州全体の安定を不安定にする」としてNATO拡大を一時停止することを求めた。
しかし、結局97年7月8-9日のNATO首脳会談(マドリード)では、ポーランド、ハンガリー、チェコのNATO加盟招請を決定した。
つまり、基本文書合意は、「きわめて不安定な合意」であった。言い換えるなら、その後の欧州安全保障秩序形成にとっての「礎石」になるか「躓きの石」になるかの分かれ道に位置するものであった。
⑤CFE適合条約の署名
1999年11月、欧州安全保障協力機構(OSCE)首脳会議(イスタンブール)において、NATOとロシアはCFE適合条約に署名した。
CFE適合条約(ACFE: Adapted Conventional Forces in Europe Treaty)とは、97年当時の東西間の境界を尊重したもので、具体的には、NATOの東方拡大に懸念を示すロシアに配慮し、適合条約では、ハンガリー、ポーランド、チェコなどのNATO新規加盟国に対する外国軍の駐留禁止や、ロシアに対する配備規制の緩和が盛り込まれた。つまり、欧州の通常兵力に関して、軍備削減と透明化のプロセス改善を追求したものだった。
⑥米露間の相互不信の拡大
ACFE(CFE適合条約)をめぐるその後の展開は、リベラル・デモクラシーを普遍的な価値とみなし、それを世界に広げようとする米国流の安全保障観と、ロシアの主張する地政学的勢力圏を前提とする安全保障観の摩擦を示すものだった。
現実には、特に通常兵力に関する規定は、NATOとロシアとの関係において常に争点となった。バルト海諸国やポーランドなどへのNATO部隊の配備を、ロシアは適合条約違反だと主張し、NATOがそれを否定することが繰り返されてきた。
1999年以降、ジョージア、トランスニストリア(モルドバ共和国)などにおけるロシア軍の撤収問題をめぐり、米露の間で不信感が高まり、結局2007年、ロシアはACFE条約の一時不履行を決定した(2015年には条約を離脱)。米国はさまざまな理由を付けて同条約には未批准だった。
更に2008年4月のNATO首脳会議(ブカレスト)において、G.W.ブッシュ大統領は、ウクライナとジョージアの加盟に対する期待を述べ、「加盟アクション・プラン」を掲げた。これはロシアにとって実に挑発的な決定であった。
そこでロシアは、2008年8月、ジョージア軍と南オセチア軍の軍事衝突に介入し、ジョージアを武力制圧した。その後、EUなどの仲介により停戦したものの、ロシアが南オセチア及びアブハジアの独立を一方的に承認すると、ジョージアはロシアとの外交関係を断絶。同年10月、ロシア軍は国際合意を受けてジョージア領内から完全に撤退した(ただし、南オセチアとアブハジアには駐留を継続)。
そして2014年3月のロシアによるウクライナ・クリミア併合は、NATOの東方拡大に対するプーチンの「対欧米脅威認識」(危機感)を踏まえた軍事行動であった。
⑦ウクライナ侵攻に至る直前の動き
2021年12月17日、ロシアは、米国・NATOに対し、NATOの東方拡大(ウクライナのNATO非加盟の保障)などを求める内容の条約案を公表し、ロシアの安全保障に関する法的保証を求めた。具体的に言うと、NATO東方拡大の停止、欧州での軍事配備はNATOの東方拡大前の1997年までの状態に戻すことなどを求めた。つまり、「勢力圏維持」の発想がロシア側に息づいていた。
現在から見ると、これはプーチン大統領による米・NATO諸国に対する最後通牒であったと言える。
ロシアの条約案に対して米・NATO側は、翌22年1月、次のような回答をした。
・1月7日、ストルテンベルグNATO事務総長「全ての国が自らの道を選ぶ権利がある」。
・1月26日、ブリンケン米国務長官「NATOの門戸は開かれたままである」。
米・NATOがロシアの要求には応じないとの方針を明確に示したことによって、プーチン大統領に「もはや対ウクライナ武力行使しか手段はない」と思わせた可能性が大きい。
そして2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻が始まったのである。
⑧ウクライナ戦争後の欧州安保の再構築
前述のような経緯から、戦争に訴えたプーチン大統領の行為は暴挙であるが、この戦争は先に見たように、冷戦後の欧州安全保障体制にロシアを包摂することに失敗したことの帰結でもある(1997年6月26日付、クリントン米大統領あての公開書簡を想起したい)。
この戦争に対する国際社会の責任が問われているとすれば、その点にある。欧州安全保障秩序の在り方について、真剣に考えない限り、この戦争が提起した問題の真の解決はないと言えよう。
4.戦後欧州秩序形成にとってのもう一つの課題:ドイツ問題
(1)NATOは欧州の安全保障にとって不可欠
戦後欧州の安全保障において、独仏の和解なしには欧州の永続的平和も繁栄もないということは、当時の政治指導者の共通の認識だった。言い換えれば、ドイツを欧州にどう根付かせるかという課題であった。
そこで西欧諸国は、独仏が中心となり、6カ国で「欧州石炭鉄鋼共同体」が出発した。これは西欧において武力行使のあり得ない秩序の定着であった。一般に、この動きは経済統合の観点から説明されることが多いが、経済はあくまでも手段であって、武力行使に訴えないで紛争解決を図ろう、そのための平和的に解決する統一秩序は何かを追求したところにその本旨があったのである。これこそが、人類史上例のない取り組みである欧州統合の原点であった。
この点は、日本から見ているとなかなか見えないところだ。これはアセアン統合とは質を異にする取り組みだ。欧州統合は、主権国家を超えた秩序を創ろうという試みであり、まさに「超国家的実在」(supranational entity)の追求だった。
(2)欧州統合の開始と深化
欧州の安全保障は、NATOに決定的に依存するという認識が共有され、安全保障以外の分野においてEUは、域内統合、対外的な一体性の強化を追求することになった。
以上の安保認識を前提として、西欧諸国は、欧州自身が自ら自立的に取り組む課題として、「武力行使のあり得ない秩序の定着」即ち、「欧州統合」という人類史上類を見ない取り組みを開始した。
①統合プロセスの第一段階:石炭鉄鋼共同体の創設ビジョンに合意
1950年5月9日(5月9日は、欧州の平和と統一を祝う「欧州の日」)、シューマン仏外相の提唱により、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)が創設された。翌51年4月18日に、ECSC設立条約がパリで署名された。
その内容は、仏独の石炭及び鉄鋼の生産をすべて共通の最高機関(超主権国家)の管理下に置き、6カ国域内に石炭と鉄鋼の単一市場を創設することを提案するものだった。石炭と鉄鋼生産に限ってのことではあったが、それを主権国家を超えた「権威」(High Authority)に管理させる、という意味で、ECSCは超国家的機関(supernational institution)であり、欧州統合の第一歩と評価されている。その他、域内関税・課税の廃止や共通競争政策の実施も盛り込まれた。この共同体の実現はまさに6カ国の域内における「国境」がなくなったことを意味する。
この核心は、永続的な独仏和解を根付かせることにあり、ECSCはそのための仕組みであった。このECSCの創設の中に、その後の欧州連合(EU)の構成要素の全てが入っていることは特筆すべきであろう。両者を対比すると下記のようになる。

その後、1955年6月1-2日に、ECSC外相会議において「メッシーナ宣言」が採択され、欧州経済共同体(EEC)および相州原子力共同体(EAEC=Euratom)の創設が決定された。
②統合プロセス第二段階:欧州統合に向けたローマ条約
1957年3月25日にEEC設立条約(第1ローマ条約)およびEAEC設立条約(第2ローマ条約)がECSC加盟6カ国により署名されてEEC(欧州経済共同体)が創設され、翌1958年1月に設立条約が発効した。
EECとは、加盟6カ国による地域的経済統合のための機関で、域外共通関税の設定、域内関税の撤廃(モノの自由移動)、労働・サービス・資本の自由移動などを実施した(域内単一市場創設のビジョン設定)。関税自主権を加盟国がEECに委譲したという意味で、「超主権国家」的統合プロセスの開始を画すと言える。
③統合プロセス第三段階:EECによる関税同盟の完成と1970年代〜80年代前半の危機
その後、1968年7月1日に始動した関税同盟(customs union:対外共通関税の創設)は、EEC加盟国6カ国の領域を単一の関税地域として、域内の貿易につき関税その他一切の制限を廃止し(域内工業製品関税を全廃)、域外の関税領域に対しては同一の関税その他の貿易規制を適用することを目的として創設された。
農業・貿易に関しては、共通農業政策のもと農業共同市場を実現し、保護主義的な政策により価格支持、最低価格の維持などを実施した。
しかし1970年代にはいると、経済的な困難に直面し、一種の「欧州動脈硬化症(Eurosclerosis)」、「欧州ペシミズム(Euro-Pessimism)」の時代を迎えた。
例えば、失業率を見ると、5.5%(79年)、8.1%(81年)、11%(86年)と年々悪化した。また70年代には二度にわたる石油危機に見舞われ、益々内向き傾向が顕著となり、欧州レベルでの協力推進に消極的になった(出典:EU MAG Vol.63、2027年9・10月号、2017年10月5日)。
ただし、このような情況の中でも、EEC加盟国は拡大し、73年にはアイルランド、英国、デンマークが加盟し、9カ国となった。
④統合プロセス第四段階:単一欧州議定書とシェンゲン協定
ユーロ・ペシミズム脱却のためにも、欧州統合を加速化させるために、単一欧州市場(モノ、ヒト、サービス、資本の域内自由移動)の完成の目標期限を1992年と明定する単一欧州議定書(Single European Act=SEA)交渉を1986年2月に妥結した(87年7月1日発効)。
前後するが、1985年、西独・仏・白・蘭・ルクセンブルクの5カ国は、「人の移動の自由」の実現に向けて、域内国境検査を段階的に撤廃することに合意した(シェンゲン協定The Schengen Agreement)。
単一議定書合意(86年)からマーストリヒト条約合意(92年)のプロセス、単一市場完成に最も貢献したのは、英国、なかんずくマーガレット・サッチャー首相であった(サッチャー首相ブルージュ演説、1988年9月20日)。仏独はむしろ保護主義的であったが、英国は域外に対して自由主義的にやろうと積極的だった。
そして加盟国は、80年代に12カ国に拡大した(81年ギリシア、86年スペイン・ポルトガル)。
⑤統合プロセスの第五段階:EUの創設
1992年2月、欧州連合(EU)を創設するマーストリヒト条約に署名した(93年11月発効)。この条約は、それまでの関税同盟、域内単一市場(モノ、ヒト、サービス、資本の自由移動)に加えて、経済通貨同盟(通貨統合)の創設にコミットした。すなわち、単一/共通ユーロの創設である。
その結果、巨大単一市場が誕生した。これは欧州共同体加盟国域内には、もはや域内国境は存在せず、域内外の「財」が自由に流通する巨大な「単一市場」が形成されたことを意味する。2021年のEUの貿易総額は、世界貿易に29.6%を占めた(米国10.4%、中国13.6%)。
現実には、1999年1月にユーロが誕生した。金融政策(ユーロ発行権限、政策金利決定権限など)については、欧州中央銀行に排他的権限が与えられ、各国の中央銀行にはその権限はない。
加盟国はさらに増えて、15カ国になった。
⑥EUの更なる統合深化のプロセス開始(リスボン条約)
欧州憲法条約は否決されたものの、2007年にリスボン条約が署名された(2009年発効)。
欧州の統合に関しては、経済的な観点からだけで語ってほしくないと思う。その大きな特徴は次の二点である。
▶普遍的価値の共同体:EUは、人間の尊厳の尊重、自由、民主主義、平等、法の支配および少数民族に属する者の権利を含む人権の尊重という価値観に立脚する(第2条)。
EU加盟のためには、第2条を受け入れなければならない。そうなるとトルコやセルビア、ウクライナのEU加盟はそう簡単なことではない。加盟を申請さえすれば加盟できるというものではない。
▶平和価値の共同体:EUは、「平和」及び「EUの価値」及び「EU人民の幸福」を促進することを目的とする(第3条)。
さらに、EUは統治機構の強化にも取り組んだ。
主権国家の権利を制限することに対して反発する国もあり、統合を進めたからと言ってすぐにThe United States of Europeが実現するわけではない。しかしそれでもEUの統合プロセスは深化している。
例えば、EU理事会(閣僚理事会)の決定方式について、特定多数決方式が導入されており、意思決定の方式には、全会一致、単純多数決、特定多数決(加盟国の55%以上、域内人口の65%以上の賛成を必要とする)の3種類がある。そして全会一致原則の例外が規定されていること自体、超国家的実在であることの証左と言えよう。
2009年、西欧同盟の集団的自衛権条項がこの年に発効したリスボン条約(42条7項)に引き継がれた。
(3)統治機構としてのEU主要機関の権限
EUの統治機構は、欧州理事会(主権国家である加盟国の合議体)、欧州委員会(超国家的実体)、欧州議会(超国家的実体)の3者によって構成・運営されている。
最高意思決定機関は、加盟国首脳から構成される「欧州理事会」だ。欧州委員会が提案するEU法案及び域外国との国際約束締結は、全加盟国の合意を経た上で、欧州議会の同意を得て成立する仕組みだ(加盟国の拒否権が可能)。
「欧州委員会」は、EUの「行政府」である。EUの執行機関として、EU法(規則、指令、決定など)の排他的提出権限を有する。
「EU議会」は、EU予算及びEU法の共同意思決定機関としての地位を持つ。
欧州理事会(加盟国首脳会議)の常任義都央と欧州委員会委員長(EUの執行機関の長)の二人が、「EU最高首脳」として国連、G7、G20などの場に出席する。
(4)BREXITから見えたEUの本質
①英国ななぜEUを離脱したのか?
欧州統合を主導した独仏と英国との間には、欧州統合のビジョンに関する同床異夢がその底流にあったと考えている。
独仏両国にとってEUの本質は、「運命共同体」(Community of Shared Destiny)であった。第二次世界大戦後に、独仏和解により誕生した「欧州共同体」には、もはや、第二次大戦終了までの数世紀にわたって欧州大陸の平和の維持・回復に貢献してきた「バランサーとしての英国」の居場所はなかった。
“Over the centuries we have fought to prevent Europe from falling under the dominion of a single power”(サッチャー首相ブルージュ演説、1988年9月)。
英国は、1973年にEECに加盟した。しかし、英国にとってのEUの意義とは、「独立した主権国家の合議体」による意思決定を通じて実現される「域内単一/統合市場」の創設であったから、90年代前半のマーストリヒト条約の締結で完了した。これ以上の統合プロセスに対して英国は、NOを突き付けるしかなった(共通通貨ユーロやシェンゲン協定への不参加など)。
実際、離脱の国民投票で離脱に投票した「EU離脱派」の主張は、EUへの主権移譲に対する異議申し立てであり、政治家レベルでは、英国議会権限喪失への不満、庶民レベルでは、EU統合による移民・低賃金労働者の流入による仕事の喪失などの不満があった。
②BREXITのEU統合への影響
英国がEUを離脱したから、それに続いて離脱国が出てくる可能性は極めて低い。
2018年10月、EU28カ国加盟国において行われた世論調査で、「もし明日あなたの国がEUに残留すべきか、或いは離脱すべきかの国民投票が行われたら、あなたはどちらに投票するか?」との質問への回答結果は、次の通りだった(各国約1000人にインタビュー)。
▶EU28カ国平均で、残留66%、離脱17%、不明17%。
▶残留と答えた比率が低い国は、(低い方から)イタリア44%、チェコ47%、クロアチア52%だった。
また2022年秋の世論調査では、EU27カ国の市民の72%は、加盟国であることに裨益していると評価した。最高はマルタ95%、最低がオーストリア55%だった。
昨今、欧州各国でポピュリズムの台頭、反移民の声などが上がっているが、EU議会選挙結果を見てもわかるが、三分の二は中道右派・左派で占められているように、EUの安定性に大きな変動はないと見られる。
もう一つの視点として、EUに加盟することによって、経済の貧しい国は、英独仏などからの拠出金によって平準化の恩恵を受けていることがある。その結果、欧州全体の経済格差は数十年前と比べてかなり是正されている。
一人当たり名目GDPで比較すると(IMF World Economic Outlook Database)、EUは1990年の16,735ドルから2022年には53,201ドルに大きく増やしている。日本の停滞ぶりと比べると実に顕著な違いだ(2022年33,821ドル)。
5.EUはどこへ行くのか?(Quo Vadis Europa?)
(1)SWOT分析から読むEUの現在と将来
内部環境と外部環境のプラス面・マイナス面を洗い出す現状分析手法であるSWOT分析の手法を使って、EUの現在と将来を展望してみたい。
〇強み(Strength)
▶巨大な経済力(世界貿易の約30%、世界GDPの17%)を背景にしたグローバルな規則パワー
・EU規制(EU競争法、一般データ保護規則、炭素国境調整措置、AI規則等)
▶巨大なソフト・パワー(国連における27票の重み)
・人権外交(経済制裁発動を含む)
〇弱み(Weakness)
▶安全保障問題におけるハード・パワーを有さない
▶豊かで人権を重視するEUゆえにアフリカ・中東からの移民・難民の流入が止まらない
▶加盟国(主権国家)合議体が有する弱点
(決定できない、遅い意思決定、全会一致方式)
〇機会(Opportunity)
▶EU政治・経済統合の更なる深化
・共通外交・安全保障政策の強化
・経済通貨同盟/銀行同盟/資本市場同盟/財政同盟
・環境・気候変動(欧州グリーン・ディールの推進)
・エネルギー市場同盟
・デジタル単一市場
▶加盟国拡大:27⇒36加盟国へ(?)
・西バルカン6カ国、ウクライナ、モルドバ、トルコ
〇脅威(Threat)
▶地政学上の脅威(ロシア、中国など)
・安全保障リスク
・エネルギー・食糧サプライチェーンリスク
▶気候変動リスク
▶ポピュリズム/ナショナリズム
・移民・難民問題
・加盟国拡大に対する抵抗
・少子・高齢化問題
(2)EUの意思決定の4類型
オランダのEU研究者・歴史研究者ルーク・ファン・ミドゥラーは、数年前の著書で、EUの意思決定について4類型に分類している(Luuk van Middelaar、Alarums & Excursions)。
EUが正常に機能した場合は、図の第一象限、第三象限のところで運営される。第三象限は、EU法に依拠した欧州委員会によって管理される世界だ(ノーマルな世界)。ウクライナ戦争など域外での事態に対しては、加盟国主導で対応が行われる(第一象限)。
一方、アブノーマルな世界(第二象限)ではどうなるか。2003年、独仏は経済同盟の安定・成長協定に関する予算規則違反(単年度財政赤字額がGPD比3%未満基準不遵守)を犯したことがあった。
もう一つのアブノーマルな世界が第四象限である。例えば、EU加盟国の全会一致がない問題について、十分なEU市民の支持がないままに、欧州委員会主導で政治的決定を行ったことがあった(2015年9月22日、緊急EU理事会は、16万人の庇護申請者の再定住割り当てに関する特別多数決による決定を行ったが、反対国、棄権国によって実行できなかった)。
このような困難についてEUは改善の努力を積み重ねている。
6.おわりに
私自身は、地政学的リアリズムを「リアル」として受け入れる一方で、「価値」が国際政治を動かす動因として、21世紀においてその重要性を高めると確信する規範的リアリストと自認している。
プーチンのウクライナ侵略という地政学的リスクに対峙することは、普遍的価値を復旧させようとする取り組みである。更に、17世紀以降の主権国家システムを開始・発展させた欧州が、21世紀の現在、主権国家システムを超えた「超国家的政治経済統合体」の深化に突き進んでいることも歴史の大潮流の一つ(世界史のリアル)であると考える。
「規範的リアリズム」外交こそが、今後日本が進むべき道ではないかと思う。
第一に、「国益」と「普遍的価値」に動機づけられた「力」(ハード/ソフト・パワー)の行使である。古くなるが1958年版『外交青書』には、次のように記されている。
「日本の国是は、自由と正義に基づく平和の確立と維持にあり、この国是に則って平和外交を推進し、国際正義を実現し、国際社会におけるデモクラシーを確立することが、わが外交の根本精神である」。
第二に、「普遍的価値」を共有する日本とEUは、ソフト・パワー大国であるという点で共通しており、強力なパートナー足りうる。
最後に、「令和の日本論」の登場である。日本が直面する多くの課題は、世界各国共通の課題であり、「課題先進国」日本の取り組みは、「先駆け国家」の取り組みとして、その成功も、失敗も教訓とすべきである(FT誌、英エコノミスト誌)。世界の日本へのまなざしは、最早「異質の国」ではなくなっていると自覚すべきである。
(2024年11月21日、IPP政策研究会における発題内容を整理した)