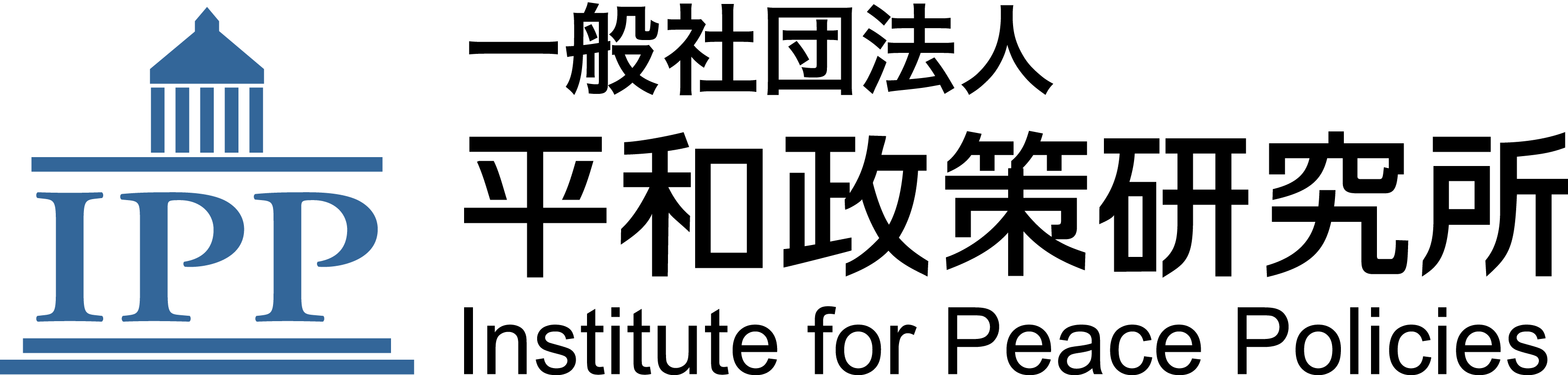1.はじめに
世界の多極化が進む中で、開発途上国・新興国は「グローバル・サウス」と称されるようになり、国際社会においてその存在感が増している。開発協力に関しても、中国が独自の枠組みで開発途上国への対外援助や融資を急増させている他、OECD/DACに参加していない新興国による開発途上国支援も増えている。「貧しい途上国を豊かな先進国が支援する」という単純な構図は崩れ、様々な協力関係が築かれるようになった。民間の財団などによる支援も増加しており、開発途上国への資金の流れは多様化している。
1990年代にはODA拠出額第1位を誇った日本も、2022年には米国、ドイツに次ぐ第3位(OECD/DAC諸国における順位)となっており、開発協力における日本のプレゼンスは相対的に低下している。開発途上国にとっては資金源の選択肢が増えている状況でもあり、日本のODAが“選ばれる”ように努力する必要性も高まっているといえる。
本稿では、第2章で日本のODA実績の変遷を確認し、第3章で過去のODA/開発協力大綱を振り返り、第4章で2023年に改定された現在の開発協力大綱のポイントを紹介することで、日本の開発協力の現在地を確認してみたい。
2.日本のODA実績の変遷
日本の一般会計におけるODA予算は1997年をピークとして2015年まで減少が続き、過去10年間はピーク時の約半分の規模となっている(図表1)。それにもかかわらずODA実績が大きく減少することはなく、むしろ近年は増加している(図表2,4)。これは、補正予算、特別会計、有償資金勘定、(円借款実施機関の)財政投融資・自己資金・回収金などが影響した結果であると考えられる(小島2023)。
1990年代を通して世界一であった日本のODAは、支出純額/贈与相当額1では2001年に米国に抜かれ、その後2007〜2020年は4〜5位であったが、2021年以降は米国、ドイツに次ぐ3位となっている(図表2、3)。支出総額でみると(図表4、5)、2001年まで1位で、その後2007年を除いて2013年まで2位、2014〜2019年は4位(2016年の3位を除く)で、2020年以降は米国、ドイツに次いで3位である。図表6からもわかるように、日本のODAは「政府貸付け等」に含まれる有償資金協力(円借款等)の割合が多いので、支出純額では順位を落としがちであった。
有償資金協力の割合が高いのは、開発途上国自身が主体性を持って自国の開発に取り組む意識を高め、開発途上国の人々による経済成長への努力を支援することを目的としているためである。この「自助努力」の重視は、かねてより日本のODAの特徴となっている。
主要ドナーであるG7諸国は教育、保健、上下水道などの社会インフラ分野への支援を重点的に行っているのに対し、日本は有償資金協力によって道路や橋、鉄道、通信、電力などの経済インフラ分野に対して多くの支援を行っている。外務省(2024:18)によれば、その割合は2022年実績ではODA全体の44.4%となっている。これは、日本が自らの復興経験から、経済インフラを整え自助努力を後押しすることが持続的な経済成長を通じた貧困削減などの達成のためにも重要だと考えているためである。
日本のODAはアジア地域を中心としており、その傾向は以前から変わっていない。次いで中東・北アフリカ、サブサハラアフリカ、中南米となっている(図表7)。
日本がトップドナーの座から退いて久しいが、図表2、4を見てもわかるように、日本のODA実績が大きく減少したわけではない。冷戦終結後、東西両陣営による勢力圏争いを背景とした途上国支援のインセンティブが低下するなか、1990年代には日本が世界一のドナーに躍り出た。しかし、2001年に米国で発生した同時多発テロ以降、G7諸国は国際社会の平和と安定を実現する上でのODAの重要性を再認識して支援額を大幅に拡大した。その結果、日本の順位が下がったと考えられる。
さらに、中国をはじめとする新興ドナーの台頭もあり、開発協力における日本のプレゼンスは相対的に低下している。刻々と変化する国際環境に対応すべく、日本は2023年に開発協力大綱を改定した。2023年にはODA実績は支出純額/贈与相当額、支出総額ともに過去最高となり、支出純額/贈与相当額で見ると2014年の約95億ドルから196億ドルへと倍増した。ただし、日本のODAはGNI比0.44(2023年)であり、経済規模に見合った援助という観点からは、フランスおよび英国にも後塵を拝している。また、一般会計当初予算については過去10年間5,500億円前後で大きな変化はない。
3.日本の開発協力戦略の変遷
1992年ODA大綱:援助理念の明確化
日本が初めて政府開発援助(ODA)大綱を策定したのは1992 年であった。日本はこの時期にトップドナーとなっていたが、欧米ドナーと比較すると円借款の割合が高いこと、また援助プロジェクトで必要となる物資の調達先を日本企業に限定したタイド援助の割合も高いことなどが批判を受けていた。また、1980年代終わりに日本が最大の援助国であったミャンマーで国軍によるクーデターが生じ、中国では天安門事件が生じた。それにより国際社会から日本に対して、ODAを提供するにあたっての考え方や方針を明確にすることが求められた。あわせて国内においても、増大するODA予算の透明性や効率性についての議論が行われ、その理念を明確化する必要に迫れていた。その結果、「国内外の理解を深めることによって幅広い支持を得るとともに、援助を一層効果的・効率的に実施するため」(外務省1992)、1992年に初のODA大綱が策定された。
「基本理念」には、「人道的見地」、「国際社会の相互依存関係の認識」、「環境の保全」、「国力に相応しい役割」が挙げられ、それらの考えのもとに、「開発途上国の離陸に向けての自助努力を支援すること」が掲げられた。また、「原則」には「(1)環境と開発を両立させる」、「(2)軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」、「(3)国際平和と安定を維持・強化するとともに、開発途上国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配分すべきであるとの観点から、開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う」、「(4)開発途上国における民主化の促進、市場指向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保証状況に十分注意を払う」、の4点が明記された(外務省1992)。
2003年改定ODA大綱:量から質への転換、「人間の安全保障」、「平和構築」
初のODA大綱が策定されたのち、日本国内ではバブル崩壊後の経済停滞で財政状況が厳しくなり、ODAについても量的拡充から質の向上への方向転換が図られた。2003年の大綱改定時の議論では、いかに効果的・効率的にODAを実施していくかが論点となり、「戦略的」「顔の見える」「国益」が主要なキーワードとなった(金子2023:68)。結果として大綱に「国益」という文言は明記されなかったが、その目的は「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資することである」とされ、「世界の主要国の一つとして」ODAを積極的に活用し、国際社会における諸問題に率先して取り組むことは「我が国自身にも様々な形で利益をもたらすものである」と記載された(外務省2003)。
また、1994年の国連開発計画(UNDP)による「人間開発報告書」をきっかけとして国際社会で広く知られるようになり、日本がイニシアティブをとってきた「人間の安全保障」概念が、5つの「基本方針」の1つとして盛り込まれた(外務省2003)。
さらに、重点課題として「(1)貧困削減」、「(2)持続的成長」、「(3)地球的規模の問題への取組」、「(4)平和の構築」が掲げられた。「平和の構築」は、米国同時多発テロをきっかけとして、内戦や地域紛争、テロなども国際社会の平和を破壊する脅威であることが改めて認識された結果、紛争の予防・早期終結、紛争後の緊急人道援助、復興支援におけるODAの役割について活発な議論が行われ、新たな観点として「重点課題」に位置付けられた(金子2023:87-88)。
2015年開発協力大綱:ODAから開発協力へ、「積極的平和主義」
途上国開発にかかわるドナーが多様化し、援助国と被援助国の関係性や途上国の開発に関する認識が変化していること等も踏まえ、「多様な主体が途上国の開発を共通の目的として、それぞれの強みを活かし、対等なパートナーとして協働していくという新しい時代の協力のあり方を明確化するため」(外務省2014c)、2015年にODA大綱は「開発協力大綱」へと改定された。また2013年に閣議決定された「国家安全保障戦略」が、ODA大綱の上位のものと位置付けられたことも、大綱の改定および名称変更につながったと考えられる。
「国家安全保障戦略」にはODAの戦略的活用が明記され、その役割が戦略上に位置付けられた。2015年の開発協力大綱においては、「我が国は、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献することを目的として開発協力を推進する」とし、こうした協力を通じて、「我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった国益の確保に貢献する」と、2003年改定版では明記されなかった「国益」が初めて明記された(外務省2015:3)。
また、「重点課題」に「質の高い成長2」という概念が登場した他、全体を通して「民間」への言及が増え、開発協力における民間部門との連携への期待がより明確となった。
「開発協力の適正性確保のための原則」の「(イ)軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避」については、従来の「開発協力の実施に当たっては、軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」に続いて、「民生目的、災害救助等非軍事目的の開発協力に相手国の軍又は軍籍を有する者が関係する場合には、その実質的意義に着目し、個別具体的に検討する」との文言が追加され、軍または軍籍を有する者へのODA供与も可能となった(外務省2015:9)。これは「国家安全保障戦略」が、積極的平和主義に基づき、普遍的価値の共有や人間の安全保障の実現、開発課題や地球規模課題の解決、国際平和協力等のためにODAを積極的・戦略的に活用するとしたことと関連していると考えられる(内閣府2013:27-28)。
4.2023年改定開発協力大綱のポイント
2022年12月に国家安全保障戦略が改定され、それを踏まえて2023年6月に、8年ぶりに開発協力大綱が改定された。改定された開発協力大綱は、「国際社会が歴史的な転換期にあり、複合的危機に直面している」という認識のもと、開発協力政策の新たな方向性を示している。そのポイントを以下に挙げる。
(1)開発協力の目的としての「国益」
2023年改定版では「開発協力の目的」として、(ア)国際社会への貢献と(イ)日本の国益の実現の二つ(以下本文掲載)を掲げた。
———
ア 開発途上国との対等なパートナーシップに基づき、開発途上国の開発課題や人類共通の地球規模課題の解決に共に対処し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の下、平和で安定し、繁栄した国際社会の形成に一層積極的に貢献すること。
イ 同時に、我が国及び世界にとって望ましい国際環境を創出し、信頼に基づく対外関係の維持・強化を図りつつ、我が国と国民の平和と安全を確保し、経済成長を通じて更なる繁栄を実現するといった我が国の国益の実現に貢献すること。
———
本稿で見てきた通り、ODA/開発協力大綱における国益の扱いについては長らく議論が重ねられてきたが、2023年改定版で初めて、日本の国益の実現を開発協力の目的の一つとして明示した。その上で、開発協力を「外交の最も重要なツールの一つ」と位置づけ、「一層戦略的、効果的かつ持続的に実施していく」としている(外務省2023a:9)。
2022年に改定された国家安全保障戦略では「FOIPというビジョンの下、自由で開かれた国際秩序を維持・発展させ、国際社会の共存共栄を実現するためにODAを戦略的に活用していく」(内閣官房2022:26)としており、国益を実現するための外交ツールとしてODAに対する期待はこれまでになく高まっていると考えられる。
2023年開発協力大綱においても、これに呼応するように「重点政策」の一つに「『質の高い成長』の前提となる『平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化』」を掲げている。また、全体を通して繰り返し「自由で開かれた国際秩序」に言及しており、それに対する挑戦に対抗する姿勢を示している。
(2)「共創を実現するための連帯」
2023年改定大綱では、「共創」と「連帯」という文言が初めて登場した。「基本方針」では、「人間の安全保障」を開発協力の指導理念として掲げた上で、その下で多様な主体が共通の目標を持って「連帯」することを柱としている。また、新たな解決策や社会的価値を共に創り上げる「共創」も新たに掲げ、開発途上国との対等なパートナーシップの下で、お互いの強みをいかし、対話と協働を通じて新たな解決策を共に作り上げていくこと、それを日本の経済・社会課題の解決や経済成長にもつなげていくことを目指すとしている。
さらに「実施」の「効果的・戦略的な開発協力のための3つの深化したアプローチ」における第1の方策として「共創を実現するための連帯」を挙げ、民間企業、公的金融機関等、他ドナー、国際機関等、市民社会、地方自治体等、大学・研究機関等、知日派・親日派人材等といった「様々な主体がその強みを持ち寄り、対話と協働によって解決策を共に創り出していく競争が求められる」としている(外務省2023a:7-9)。あわせて資金についても、「ODAに係る幅広い資金源の拡大を推進する」としている。
「効果的・戦略的な開発協力のための3つの深化したアプローチ」の第3の方策「目的に合致したきめ細やかな制度設計」では、動きの速い民間投資との連携を想定し、「時代のニーズに合わせた迅速な協力」を実施するため、制度改善を行っていくとしている。また「基本的考え方」の「策定の趣旨・背景」においても、「ODAとその他公的資金(OOF)や民間資金(PF)との連携を強化し、開発のための相乗効果を高めていく」としており、民間企業等の活動を後押しする姿勢が見られる。
(3)戦略性の強化と「オファー型協力の導入」
日本はODAを実施する際に、被援助国側からの要望を受けて支援する要請主義をとってきた。これは、被援助国の主体性を最大限尊重し、その自助努力に対する支援をするという考えからであった。1992年ODA大綱では「原則」の中に「相手国の要請、経済社会状況、二国間関係などを総合的に判断の上、実施するものとする」と記されており、その方針は以降も維持されてきた。ただし、2003年改定大綱では「援助政策の立案及び実施」において「開発途上国から要請を受ける前から政策協議を活発に行うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である」とされた。さらに、2015年開発協力大綱には、「基本方針」に「相手からの要請を待つだけでなく、相手国の開発計画、制度を十分踏まえた上で我が国から積極的に提案を行うことも含め、当該国の政府や地域機関を含む様々な主体との対話・協働を重視する」と記された。
2023年改定大綱ではさらに踏み込み、「実施」の「効果的・戦略的な開発協力のための3つの深化したアプローチ」の第2の方策に「戦略性の一層の強化」を掲げ、「相手国からの要請を待つだけでなく、共創の中で生み出された新たな社会的な価値や解決策も活用しつつ、ODAとOOF等様々なスキームを有機的に組み合わせて相乗効果を高め、日本の強みを活かした魅力的なメニューを創り、積極的に提案していくオファー型協力を強化する」としている。
(4)中国の援助国としての台頭への対応
中国の援助国としての台頭および債務問題は国際社会における開発協力全体の構造に大きな影響を与えている。中国の台頭により開発資金源が拡大し、被援助国の選択肢が広がっているという評価もあるが、中国が行う一部のプロジェクトでは、債務問題や環境問題、社会問題が生じ、国際的にも課題が指摘されている。
中国は2010年代から一帯一路構想をはじめとして、開発途上国に対するインフラ投資を中心とした対外援助・対外経済協力を拡大してきた。これらは外交・安全保障政策と密に関連付けられており、2023年改定大綱で「自由で開かれた国際秩序」や「質の高い成長」、「質の高いインフラ3」を強調する背景には、中国が援助国として台頭しているという事実があると考えられる。
2023年改定大綱では、「債務持続可能性への配慮が十分でない借款供与等により一部の開発途上国で債務問題が発生する等、開発途上国の自立的・持続的成長につながらない支援も見られている」(外務省2023a:1)との認識を示したうえで、「開発協力の適正確保のための実施原則」に「債務の持続可能性」を明記した。これは明示してはいないものの、中国の債務問題を念頭に置いていると考えられる。
2019年6月のG20大阪サミットでは「質の高いインフラ投資に関するG20原則」が策定され、日本はこれを各国が遵守すべき国際基準であるとして推進している。「新しい時代の『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」が「重点政策」の一つとなっているが、大綱中で「質の高い成長」や「質の高いインフラ」を多用することにより、国際基準の遵守とその推進を国際社会に示していると捉えることもできる。
5.おわりに
ODA/開発協力に求められる役割や手法は、国内外の情勢により変化してきた。過去に策定されたODA/開発協力大綱からはその変遷が浮かび上がる。第二次世界大戦後に日本は国際社会からの支援を受けて復興を遂げた。「責任ある主要国」として「その過程で得た知見・経験・技術・教訓を活かし、特色ある協力によって開発途上国の発展の土台の形成を後押しするとともに、地球規模課題の解決、そして国境を超えた円滑な経済・社会活動の国際環境づくり」(外務省2023a:2)に取り組むという大義は第一に保持しながらも、2023年改定大綱においては我が国の「国益の実現」、民間部門との連携の強化、援助国として台頭する中国を念頭に置いた国際基準の推進に力点が置かれているように見受けられる。
新興国や民間企業・団体などを含めドナーが多様化する中で、開発途上国の発展、そして国際社会の平和秩序の維持に貢献し、なおかつ、自国にも利する戦略的なODA政策が求められている。また、中国をはじめとする新興ドナーによる途上国支援が国際的な基準や取組と整合的な形で透明性を持って行われるように、国際社会と連携しながら働きかけていくことも、日本の重要な役割となっている。
今後の検討点として「国際安全保戦略」の下で設けられた「政府安全保障能力強化支援(OSA:Official Security Assistance)4」との関係性が考えられる。OSAは、「同志国の安全保障上の能力・抑止力の向上を目的として、同志国に対して、装備品・物資の提供やインフラの整備等を行う、軍等が稗益者となる」ODAとは別の枠組みであるとされる。しかし「OSAの実施方針」には支援分野として「人道目的の活動」や「国際平和協力活動」が挙げられており、他方で2023年改定大綱では「切れ目のない平和構築支援」を行うとしている。今後OSAの実施がどのように展開されていくか、注目が集まっている。
1 ODAの支出純額(ネット)は、支出総額(グロス)から回収額(被援助国から援助国への返済額)を差し引いたもの。贈与相当額(GE)は、有償資金協力について贈与に相当する額をODA計上する方式。OECD/DACでは2018年の統計から、従来の純額(ネット)方式に代えて贈与相当額計上方式を導入した。純額(ネット)方式では、日本の政府貸付等は、過去の貸付の回収額がマイナス計上されることによって相殺されていたが、新たなGE方式では回収額のマイナス計上がなくなった。
2 成長の果実が社会全体に行き渡り、誰ひとり取り残さない「包摂性」、世代を超えた経済・社会・環境が調和する「持続可能性」、自然災害 や経済危機などの様々なショックへの耐性および回復力に富んだ「強靱性」を兼ね備えた成長(外務省2023a:5)。
3 透明性、開放性、ライフサイクルコストからみた経済性、債務持続可能性等を兼ね備え、「質の高い成長」に資するインフラのこと(外務省2024a)。
4 国家安全保障戦略(内閣官房2022:26)に記載されている「キ ODAを始めとする国際協力の戦略的な活用」にある「新たな協力の枠組み」のこと。
参考文献
外務省(1992)「旧・政府開発援助大綱(1992年6月30日閣議決定)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/honpen/hp203020000.htm(2024年11月27日閲覧)。
外務省(2002)『ODA白書2001年版』、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/01_hakusho/index.htm(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2003)「政府開発援助大綱の改定について(2003年8月29日閣議決定)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/honpen/hp203010000.htm(2024年11月27日閲覧)。
外務省(2014a)『2013年版 政府開発援助(ODA)白書』、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/13_hakusho_pdf/index.html(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2014b)「岸田外務大臣ODA政策演説『進化するODA 世界と日本の未来のために』」(2014年3月28日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ap_m/page3_000726.html(2024年11月27日閲覧)。
外務省(2014c)「ODA大綱見直しに関する有識者懇談会報告書」(2014年6月)、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000071302.pdf(2024年11月26日閲覧)。
外務省(2015)「開発協力大綱について(2015年2月10日閣議決定)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072774.pdf(2024年11月27日閲覧)。
外務省(2016)『2015年版 開発協力白書』、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/press/shiryo/page23_000988.html(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2021)『2020年版 開発協力白書』、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/press/shiryo/page22_001366.html(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2023a)「開発協力大綱〜自由で開かれた世界の持続可能な発展に向けた日本の貢献〜(2023年6月9日閣議決定)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100514690.pdf(2024年11月27日閲覧)。
外務省(2023b)「政府安全保障能力強化支援の実施方針(2023年4月5日)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100487214.pdf(2024年11月29日閲覧)。
外務省(2024a)『2023年版開発協力白書 日本の国際協力』、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100634339.pdf(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2024b)「OECD/DACにおけるODA実績(2024年4月19日)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki.html(2024年11月25日閲覧)。
外務省(2024c)「ODA予算(2024年4月3日)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html(2024年11月26日閲覧)。
金子七絵(2023)「開発協力大綱のあゆみと2023年の改定—目的として明記された『国益』、創設されたOSAとの関係—」、https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2023pdf/20230928082.pdf(2024年11月25日閲覧)。
小島誠二(2023)「予算と実績の面から開発協力の未来を考える—ODA実績拡大のための現実的シナリオの提示—」、霞関会ホームページ、https://www.kasumigasekikai.or.jp/%E4%BA%88%E7%AE%97%E3%81%A8%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E3%81%AE%E9%9D%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E9%96%8B%E7%99%BA%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E2%80%95oda/(2024年11月26日閲覧)。
神田道男(2023)「ODA/開発協力大綱の変化の一側面」、SRIDジャーナル第25号、https://www.sridonline.org/j/doc/j202307s03a02.pdf(2024年11月27日閲覧)。
内閣官房(2022)「国家安全保障戦略」、https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/national_security_strategy_2022_pamphlet-ja.pdf(2024年11月28日閲覧)。
内閣府(2013)「国家安全保障戦略について」、https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-j.pdf(2024年11月27日閲覧)。