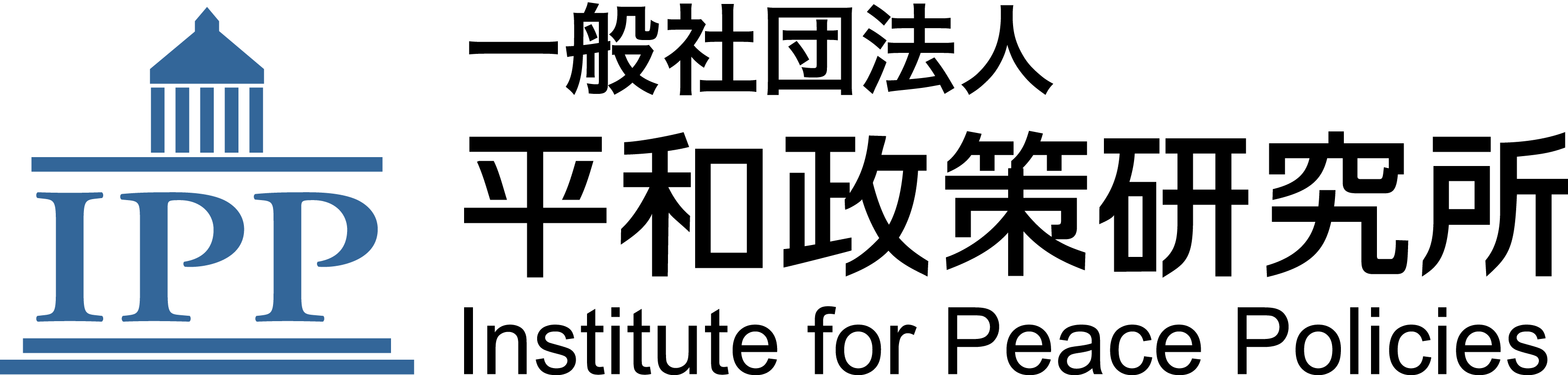はじめに
今から40年以上前の1980年前後に、「日本型福祉社会」という言葉がよく使われていた。歴史をひもとくと、1970年代半ば頃から「日本型福祉社会」という言葉が現れた。
それがピークになるのは、1979年1月の第87回国会における大平正芳内閣総理大臣の施政方針演説である。大平総理は、「家庭基盤の充実、田園都市構想の推進等を通じて、公正で品格のある日本型福祉社会の建設に力をいたす方針であります」といい、「活力ある日本型福祉社会の建設」をスローガンに掲げた。「日本人のもつ自主自助の精神、思いやりのある人間関係、相互扶助の仕組みを守りながら、これに適正な公的福祉を組み合わせた公正で活力ある日本型福祉社会の建設に努めたいと思います」と述べた。
政府は1979年8月閣議決定をした「新経済社会7か年計画」の中で、「新しい日本型福祉社会の実現」を掲げ、「個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等の連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するという自由経済社会のもつ創造的活力を原動力とした我が国独自の道を選択的に創出する、いわば日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指すものでなければならない」と記述した。
こうして日本型福祉社会の建設が政府の政策方針となった。
しかし、この日本型福祉社会の概念は1990年代頃には使われなくなった。それはなぜなのか。
自由民主党の『日本型福祉社会』論
本稿では、自由民主党の研修叢書『日本型福祉社会』(1979年8月)により、日本型福祉社会の考え方が登場した背景やその概念を説明するとともに、当時の日本型福祉社会論の問題点を整理する。さらに、21世紀前半の現在において、新しい日本型福祉社会の構想の可能性について考察する。
自由民主党の研修叢書『日本型福祉社会』は、B6サイズで210頁という結構大部な冊子である。
全体で6章構成であるが、前半の3章をつかって、イギリスとスウェーデンという2つの福祉国家がさまざまな問題を抱えていることを記述している。イギリスは、社会保障の充実のために税金や社会保険料負担が重くなり、「英国病」といわれたように経済活力を失った。スウェーデンは、高い自殺率、犯罪発生率の高さ、アル中患者の多さなど、「理想の福祉国家」といわれながら多くの問題点を抱えていた。後半の3章で、日本型福祉社会の構想や高齢社会の到来の中で今後のめざす方向を説明する。
この研究叢書から、日本型福祉社会という概念が登場してきた背景を次のように整理できる。ひとつは、日本は、第2次世界大戦後、ヨーロッパの福祉国家を目標にしてきたが、高度経済成長とともに進めた社会保障制度の整備によりヨーロッパの福祉国家に追いついたとする「自信」である。もうひとつは、今後人口高齢化の進行により社会保障の負担の増加が見込まれる中で、イギリスやスウェーデンのような税負担が重く経済的に低迷するような福祉システムではなく、日本社会の特性を生かした効率的な活力ある福祉システムをつくっていこうとする「意思」である。
同書によれば、日本型福祉社会とは、家庭と企業の機能が基本となり、保険などの市場におけるリスク対応システムによって補完し、最終的には国が用意する社会保障制度で対応するという社会である。重要になるのは、家庭基盤の充実と企業の安定と成長、ひいては経済の安定と成長を維持することである。
「かりに企業が定年を大幅に延長し、終身雇用制を堅持していくことができれば、高齢化社会の問題の70%は解決するといってもよい。それに加えて、子供の少なくとも1人がその家庭に老齢の親を同居させ、看護を引き受ける力を備えていれば、老人福祉問題の半ばは解決するのである」と記述する。
日本型福祉社会論の問題点
こうした政府や自由民主党の日本型福祉社会論に対して、野党や有識者から激しい批判が展開された。もっとも強い批判は、家庭や企業に福祉充実の責任をゆだねることにより、福祉予算を抑制しようとする「福祉の切り捨て」という指摘であった。
「昭和53年版厚生白書」(1978年)において、老親と子供の同居を日本社会の「福祉における含み資産」と評価し、「世代間の相互扶助という面からみれば、老親がまだ元気なうち(たとえば50〜65歳ぐらい)においては子ども夫婦にとって、出産育児の手伝いや援助を期待でき、さらに就労を希望する主婦にとっては、留守番や子どもの世話の一部をまかせることができる。次に老親がしだいに身体機能が衰える時期(たとえば70歳以上)においては子ども世帯による老親の介護が期待できる」とし、三世代世帯のメリットが強調された。この「含み資産」論は、家族に育児や介護を押し付けるとんでもない考え方として、有識者たちの批判の的となった。
第二に、日本型福祉社会の重要な要素である「家庭」の在り方は、「夫は企業で働き、妻は家事や子どもの世話をする」という性別役割分業を前提にしたものであった。つまり、男性(夫)が家庭の主たる稼ぎ手となり、女性(妻)は家事や子供の世話をするということが前提となっていた。夫は仕事に専念し、妻はもっぱら家事を行うという「男性稼ぎ手モデル」および「専業主婦世帯」を前提としていたものであった。
当時は専業主婦世帯が共働き世帯よりも多かったが、1980年代以降、共働き世帯が増加の一途をたどる一方で専業主婦世帯は減少していく。1990年代に入って、共働き世帯が専業主婦世帯よりも多くなり、以後、その差は年々拡大していった。
第三に、日本型福祉社会を構成するもうひとつの重要な要素である「企業」については、いわゆる日本型雇用システム、すなわち終身雇用制と年功序列制、手厚い企業福祉が前提となっていた。しかし、こうした日本型雇用システムは、1990年代のバブル経済崩壊後の経済不況を経て大きく変化した。中途解雇というリストラの増加、能力給の導入、転職の拡大、パート労働等の非正規雇用の増大といった雇用システムに変化した。企業が安住できる場ではなくなった。
以上述べてきた家庭や企業の変化の概要を記したものが、表1である。日本型福祉社会を支える根底が崩れてしまった。
日本の家庭の変容
日本の家庭の在り方について1980年頃の状況と現在を比較すると大きく変化した。
表2の「家族の姿の変化」にあるとおり、1980年には「夫婦と子供からなる世帯」が全体の42.1%、次いで「3世代等の世帯」が19.9%を占めていた。ところが、この2つの類型の世帯割合は年々減少し、2020(令和2)年では、「夫婦と子供からなる世帯」は25.0%に減少、「3世代等の世帯」は7.7%と激減した。代わって増加しているのが、日本の世帯類型のトップとなった「単独世帯」で38.0%、「夫婦のみ世帯」が20.0%、「ひとり親と子供世帯」が9.0%となっている。
日本型福祉社会論では、「3世代世帯」が福祉に一定の役割を果たすことを期待していたが、その構成割合は小さくなってしまった。
仮に「夫婦と子供からなる世帯」と「3世代等世帯」を「家庭基盤がしっかりしている世帯」に、「単独世帯」、「夫婦のみ世帯」と「ひとり親と子供の世帯」を「家庭基盤がぜい弱な世帯」に区分すると、1985年では「家庭基盤がしっかりしている世帯」の割合が62.0%と日本の家庭の大宗をしめていたのが、2020年では「家庭基盤がぜい弱な世帯」の割合が63.8%と、逆転している。
このように日本型福祉社会を構成する基本要素である家庭の構成が、「家庭基盤がぜい弱な世帯」が増える方向で推移したことも、日本型福祉社会論が積極的に言及されなくなった原因の一つであろう。
新しい日本型福祉社会に向けての考察
以上のとおり、1980年頃に政府や自由民主党が推奨していた日本型福祉社会論は、家庭や企業の変化の中で姿を消してしまったかのようである。
日本型福祉社会論の消滅を印象づけたものが、1990年代半ばの介護保険制度の創設をめぐる議論である。家族に依存した高齢者介護が限界を迎えているという認識のもとに、介護問題を社会全体で支えるという「介護の社会化」がスローガンになった。要介護高齢者をどのようにして外部の介護サービスで支援していくのかということが主要課題となり、家族などの介護者を介護システムにどのように位置づけるのかということの議論はなかった。前出した研修叢書の中の言葉「老親を同居させ家族が看護をすれば問題は解決する」という考え方は、全く否定された。
一方、介護保険制度の創設から10年以上を経て、1980年頃の日本型福祉社会の考え方と似たような文言をもった法律が登場してきた。2012(平成24)年8月に制定された「社会保障制度改革推進法」である。
同法第2条に、社会保障制度改革を行う上での基本事項として、「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと」という規定がおかれた。
この表現は、本稿冒頭の大平総理の施政方針演説の中の日本型福祉社会と類似している。大平総理の言葉を借りれば、「自助」とは「自主自助の精神」、「共助」とは「思いやりのある人間関係、相互扶助の仕組み」、「公助」とは「公的福祉」ということになろう。
この「自助・共助・公助」の概念を基に、21世紀における新たな日本型福祉社会について考察してみたい。
福祉の提供主体
人間社会の歴史をひもとけば、現在のような国家による社会保障制度の整備が始まったのは、公的扶助制度ではイギリスにおける17世紀の救貧法、社会保険制度では19世紀後半のドイツのビスマルクによる社会保険各法の制定である。それまでは、各人の生活を支えていくのは、個人や家庭の自助努力か、近隣住民や帰属団体によるボランタリーな相互扶助が中心であった。いわば自助が中心で、それを共助が補い、公助はなかった。イギリスの公的扶助制度やドイツの社会保険制度を参考にして、20世紀前半の欧米や日本で、年金、医療、社会福祉、失業保険などの社会保障制度の整備、すなわち公助が整備されていった。
R・ローズは、社会の福祉の全体量は、H(家庭によって供給される福祉)+M(市場によって供給される福祉)+S(政府によって供給される福祉)であるとし、いずれか一つに依存するのではなく、それぞれが補完しあっているという概念を示した。いわゆる福祉ミックス論である。この場合のHは自助に、Mは共助に、Sは公助に相当するとみることができる。
政府(行政)による福祉が充実していると言われる北欧諸国のスウェーデンでも、高齢者介護分野ではS(政府によって供給される福祉)によるサービスが中心であるようにみえるが、介護サービス総量の約3分の2は、家族や親戚、友人により個人的に提供されているという(増田雅暢編『世界の介護保障』)。このように福祉サービスの提供主体は、政府ばかりでなく、家族や市場が大きな役割を占めているという見方は、実態に即したものである。
福祉多元主義を提唱したN・W・ジョンソンは、福祉サービスの供給部門として、「国家」、「営利」、「ボランティア及びコミュニティ」、「インフォーマル」の4部門を挙げている。これを自助・共助・公助に当てはめれば、「国家」は公助、「営利」と「ボランティア及びコミュニティ」は共助、「インフォーマル」は自助に相当するとみることができる。
自助、共助、公助の定義
ここで、自助、共助、公助の定義について確認してみたい。
前述の社会保障制度改革推進法では、これらの言葉について特段の定義はなされていない。この法律制定の前提となった社会保障制度改革国民会議の報告書(2013年8月)には、「日本の社会保障は、自助を基本としつつ、自助の共同化としての共助(=社会保険制度)が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に公的扶助等の公助が補完する仕組みが基本」としている(同報告書概要版から)。ここでは、共助について社会保険制度であるとしている。
筆者は、この社会保障制度改革国民会議の定義は、次の2点から修正すべきではないかと考えている。
ひとつは、社会保険制度を共助に位置づけていることについて。社会保険は被保険者の支え合いの仕組みであるが、被保険者は加入を強制され、保険者は国や地方自治体等の公的団体である。多額の公的補助が投入され、国家がその制度運営に責任を負っている。このことから、共助というよりは公助とみなすべきである。市場における民間の保険の方が共助にふさわしい。
もうひとつは、国民会議の自助・共助・公助論は、自助を基本とし、それを補完するものとして共助があり、これらでも対応できない場合に公助があるという「三段論法」をとっていることについて。これは正しくない見方であると考える。これでは自助や共助で対応できるのであれば、公助は必要がないという社会保障の充実を抑制する論理として使われかねない。
筆者は、自助とは、自分の能力を活用し、自立した生活を営むことと定義する。自らの労働収入などを基に自分のことは自分で行う。共助とは、家族や親戚・知人、地域の共同体等の助け合い、あるいは民間保険のような市場経済のサービスを利用することと定義する。公助とは、公的機関による支援や、公的な福祉制度や社会保険を活用することと定義する。
その上で、自助、共助、公助の関係は、図1のとおりと考える。すなわち、自助、共助、公助はそれぞれが相互補完的なものである。公助があるから自立した生活を送るという自助が成立する。自助や共助があるから、公助の役割・負担が過大になることを防ぐ。
法制度化されているものを「フォーマル」、そうでないボランタリー的なもの、あるいは民間市場で生まれてきたものを「インフォーマル」とすれば、自助はインフォーマル、共助はインフォーマルとフォーマル、公助はフォーマルな仕組みということになる。
家族介護への支援
筆者の自助・共助・公助の概念を、高齢者介護の分野に当てはめてみよう。前述した通り、2000年4月から実施されている介護保険制度は「介護の社会化」をスローガンにしていた。すなわち公助の世界の制度である。一方、自助の世界に入る家族や知人などによるインフォーマルな介護は、介護保険制度には組み込まれていない。それどころか、訪問介護の生活援助サービスについては要介護者に家族が同居している場合は介護保険が適用されない。ここには「家族は介護するのは当然」という考え方が潜んでいる。また、家族介護者に介護手当を給付することについては、検討時点で大議論となり、「現金給付は家族介護を固定化する」などの批判から制度化されなかった。
すなわち、日本の介護保険では、自助と公助の世界が分断されている。厚生労働省の国民生活基礎調査結果をみると、在宅で要介護3以上の高齢者を介護している家族介護者は、1日のほとんどの時間を介護に費やしているが、介護保険からの支援は不十分な現状にある。結果的に、家族による介護虐待や介護殺人といった不幸な事件が起きている。
また、日本の介護保険システムは公助中心型であるがゆえに、財政負担の増大や介護人材不足というリスクに見舞われている。
他方、ドイツの介護保険制度では、要介護高齢者の選択により現金給付の給付を受けることができる。これにより、家族や知人といったインフォーマルな介護者がその現金を受け取って在宅で介護をしている。ドイツの介護保険は家族などによる介護を基本として、介護保険はそれを補完するものという思想で設計されている。家族などの介護者に対して社会保険適用などさまざまな支援策が介護保険法に位置づけられている。いわば、家族機能に期待しつつ、介護保険という公助が家族などの介護という自助を支援している、ということができる。
筆者は日本においても、家族などのインフォーマルな介護者支援を介護保険制度上位置づけて実施すべきであると主張している(増田雅暢著『介護保険はどのようにしてつくられたか』)。そうすることにより、家族などによる介護という自助部分を強化し、家族の介護虐待などの不幸な事例を減らすことができるだろう。高齢者が高齢者を介護する「老老介護」が増えている中で家族介護を支援することにより、家族介護者の負担軽減や家族のきずなの強化につながるだろう。また、家族介護が適正に行われれば、自助が公助を補完することになり、介護保険制度が提供するサービスや財政負担の増大を抑制し、さらには介護人材の需要を軽減することになるだろう。
自助、共助、公助の相互補完
高齢者介護分野での共助とは、地域の団体やNPO団体による介護支援、あるいは民間企業による民間の介護保険や介護保険外のサービス提供である。地域の民間団体による介護サービスの提供については、国は、介護保険制度の地域支援事業による総合事業という形で普及を図ろうとしている。また、民間介護保険は公的な介護保険を補完するものであり、民間事業者による全額自己負担の保険外サービスの提供が東京などの都市部で行われている。
このように高齢者介護分野において、介護保険という公助部分のみに依存するのではなく、家族や知人などのインフォーマルな介護という自助部分、ボランタリーな民間団体によるサービス提供や民間企業の取組といった共助部分を組み合わせることが、新しい日本型福祉社会の姿である。
高齢者介護分野を例にしたが、他の福祉分野においても、図にある自助・共助・公助の相互補完関係を基にして考えることができるのではないか。
家庭の変化への対応
検討にあたって見逃せないのが、日本社会の家庭や家族のあり方の大きな変化である。表2のとおり、日本の家族は、単独世帯や夫婦のみ世帯、ひとり親と子供の世帯が増加している。2040年の将来推計では、全体の4割は単独世帯、ひとり親と子供世帯も1割を占める。大平首相は、所信表明演説の中で「家庭は、社会の最も大切な中核であり、充実した家庭は、日本型福祉社会の基礎であります」と述べた。その家庭の姿が21世紀には大きな変貌をとげており、「21世紀の日本型福祉社会」を構想するには、そのことを前提にしなければならない。単独世帯といっても、若い未婚の男性や女性の一人暮らしから、中高年の一人暮らし、高齢者の一人暮らしなどさまざまであり、特に公的年金水準が低い高齢女性の一人暮らしが多いだろう。
単独世帯が約4割を占める社会でも、皆が安心して生活できるような社会の仕組みの構築が求められる。
(『EN-ICHI FORUM』2024年8月号より)
〈参考文献〉
1 自由民主党研究叢書『日本型福祉社会』(1979)
2 堀勝洋著「日本型福祉社会論」(「季刊社会保障研究」第17巻第1号)(1981)
3 丸尾直美『日本型福祉社会』(日本放送出版協会、1984)
4 内閣府「令和4年版男女共同参画白書」(2022)
5 小林甲一「社会保険の政策理念と経済社会倫理」(名古屋学院大学論集社会科学編第58巻第4号、2022)
6 本多真隆著『「家庭」の誕生』(ちくま新書)(2023)
7 増田雅暢編『世界の介護保障(第2版)』(法律文化社、2014)
8 増田雅暢『介護保険はどのようにしてつくられたか』(TAC出版、2022)