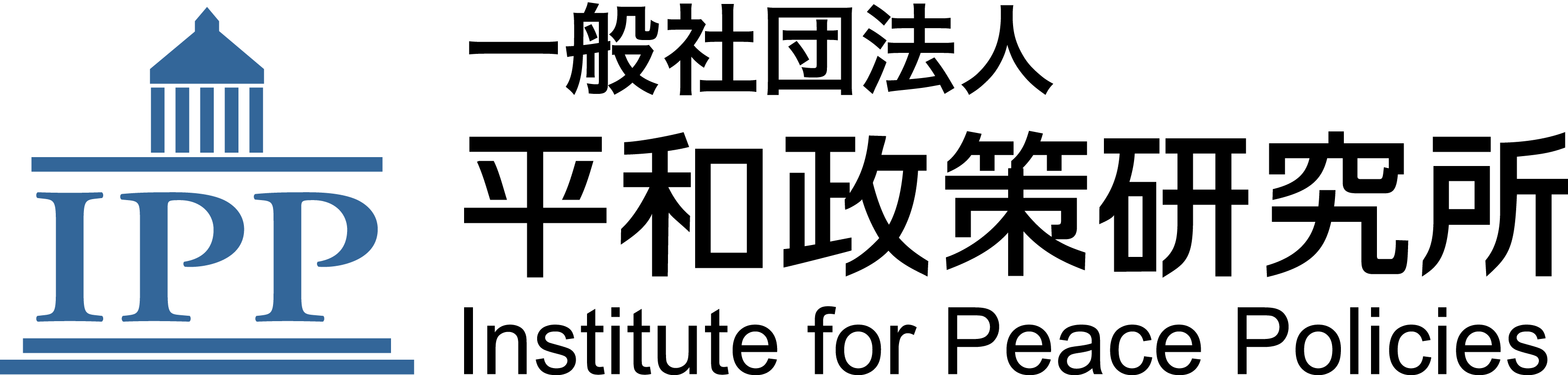1.地域社会が抱える課題
地域社会は様々な課題に直面している。少子高齢化の進展と人口減少、若者の都市圏への流出、それに伴う働き手の減少等により、地域社会の活力が低下している。いかに雇用を創出し、若者を定着させ、安心して子供を産み育てられる地域を創っていくかが切実な課題となっている。
これらの課題は今に始まったことではない。地方の農山村では、高度経済成長期の1960〜70年代から住民が都市圏に流出し人口減少が問題となった。この頃に「過疎」という造語が生み出された。1980年代の中頃からは中山間地域で耕作放棄地が問題化し、次第に平地にも拡大した。1990年代には集落機能の衰退・脆弱化が問題となり始め、2000年代後半に「限界集落」(65歳以上が人口比率50%以上を占める集落)という概念が広まった(小田切2021)。地方の農山村を中心に地域社会の持続可能性が問われている。
その様な状況下では、生産年齢人口も減少し、地域産業の衰退も課題となっている。後継者不足・労働力不足から休廃業せざるを得ない中小企業が増加し、働く場所が減少して、若者がさらに都市圏に流出するという悪循環が生まれる。地域経済が停滞すると、行政サービスや社会インフラの維持が困難になり、さらに地域の持続可能性を削ぐことになる。
2.近年の地域振興政策
2014年5月、有識者からなる「日本創生会議」(座長:増田寛也)が、全国の市区町村のおおよそ半分にあたる896の自治体は消滅しかねないという衝撃的な予測を盛り込んだ「増田レポート」を発表し、人口減少に警鐘を鳴らした。それに呼応するかのように、当時の安倍政権は「地方創生」政策を本格化させた。
地方創生は「まち・ひと・しごと創生法」の施行により開始された。人口減少および少子高齢化が進む日本社会において、地方における人材創生、コミュニティ創生、仕事創生を一体的に進め、東京一極集中を緩和すると同時に持続可能な地域社会を創ろうという政策である。地方創生政策は岸田政権下でデジタル田園都市構想へと転換したが、一貫して①地方に仕事をつくる、②地域への人の流れをつくる、③結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつくるという方向性を踏襲している。
地方創生政策が開始されてからちょうど10年が経った。目標の一つである東京一極集中の是正はコロナ禍で一時は進んだように見えたが、2022年以降はふたたび東京への転入者が増え、2023年には4年ぶりに10万人以上の転入超過となった。出生数については年々最少を更新しており、2023年は76万人弱であった。東京一極集中の是正も少子化の歯止めも、達成には程遠い。それでも、中には希望的な地域社会づくりを実現している地域もある。
3.希望的な地域社会づくりの事例
2024年4月に有識者グループ「人口戦略会議」(議長:三村明夫、副議長:増田寛也)が「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」を公表した。これは、2014年の増田レポートの手法を踏まえ、さらに詳細な分析を行ったものである。本レポートによれば、2014年に「消滅可能性自治体」とされたものの、今回の分析で脱却した自治体が239あった。脱却した自治体における希望的なまちづくりの事例をいくつか紹介する。
・島根県邑南町
島根県邑南町は、島根県中南部の中山間地に位置する人口約1万人、高齢化率45.9%(2024年8月時点)の町である。2004年の平成の大合併で3つの町村が合併して発足した町で、人口は減少を続けているが、この10年で下がり方が緩やかになり消滅可能性自治体を脱した。
邑南町は2011年から移住・定住を促すための取組みとして、「日本一の子育て村構想」や「A級グルメのまち」といった戦略を展開してきた。
「日本一の子育て村構想」は、中学校卒業までの医療費無料、第二子以降の保育料完全無料といった施策を中心に、地域で子育てをする町を目指してきた。2013年には町村合併後初めて人口増加を記録し、近年は社会増で推移している。
また移住者に対しては移住後の仕事の斡旋や住居の支援の他に、事前に集落住民との話し合いの場を設けたり、定住支援コーディネーターがあらゆる相談に応じてサポートしたりするなど、「徹底した移住者ケア」を行っている。
2015年に策定した「邑南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に伴い、12公民館区ごとに「地区別戦略」(ちくせん)をつくり、地区ごとにまちづくりを推進している点も注目に値する。各公民館区では住民が中心となって地域の事情を踏まえた人口減少対策を策定・実施している。
「A級グルメのまち」を目指した取組みでは、地元でつくった農作物や加工品を使った一流レストランを邑南町に創ることを目指し、2011年5月に里山イタリアンレストラン『ajikura』を町直営で立ち上げた。質は高いが量が少ない邑南町の特産品を、都会に出すのではなく地元に食べに来てもらうという発想である。レストランのスタッフなどの人員確保には、地域おこし協力隊制度を活用した。地域おこし協力隊とは、1〜3年の任期で、都市地域から人口減少・高齢化等の進行が著しい地域に移住し、自治体の委嘱を受けて地域おこし支援や地域協力活動を行い、その地域への定住を図る総務省の取組みである。自治体の資金負担は原則ゼロで、1人当たり400万円を上限に国から自治体に補助金が交付され、それが隊員の活動資金や給与になる。「耕すシェフ(町内での起業を目指す料理人研修制度)」や「おーなんアグサポ隊(町内での就農を目指す農業研修制度)」のように、地域おこし協力隊制度を食と農に絞り込んで募集し、さらには研修を終えた隊員が町で就業・就農できるように体制を整備した。50人を超える協力隊員が任期後も町内に定住している(邑南町HP)。この取組みは功を奏し、町の人と外から来る人が協働して次々と飲食店を立ち上げた。邑南町独自の推計では、コロナ前は年間90万人もの観光客が訪れるようになっていた(邑南町2020)。
・北海道下川町
北海道の山地に囲まれた名寄盆地に位置する下川町は、人口約3,000人、高齢化率約40%(2020年時点)、森林面積約90%の町である。1960年代のピーク時には人口が1万5000人を超えていたが、鉱山の閉山や鉄道の廃止など様々な要因により過疎化してしまった。一時は過疎化率が北海道で1位になったが、2000年代からは持続可能な森づくりを中心として、環境と経済、社会を調和させるまちづくりを進めてきた。これらと親和性の高いSDGsもまちづくりに活用してきた。その結果、2010年以降はIターンやUターンの増加によって転入超過になる年も出てきた。
具体的には、60年間で植林・間伐・伐採を一回りさせる「循環型森林経営システム」のもと、豊富な森林資源を余すことなく活用する自立型の森林総合産業の創出や、間伐材や端材を細かく砕いたチップを原料とする木質バイオマスを中心とした再生可能エネルギーの完全自給などをめざした地域づくりを進めている。下川町の持続的な森づくりに魅力を感じて集まってくる人もおり、森林組合では職員35人のうち25人が町外の出身という(朝日新聞 2018)。
木質バイオマスによる熱供給では、現在11基のボイラーが役場や学校、町営の温泉施設など30か所に暖房と温水を供給している。公共施設で約7割、町全体の約5割が、木質バイオマスによる熱供給で賄われている(上田2021)。
また、「エネルギー自給型高齢化社会のモデル地区」として、高齢化率50%を超える集落に高齢者が暮らすための集合住宅を建てたが、この住宅もバイオマスボイラーによって熱源が供給されている。
他にも熱源を使ったシイタケ栽培を町営で始め始めたり、地域おこし協力隊でやってきた若者が集合住宅に住んで併設するカフェの運営や住宅の管理を行ったりしている。
これらの取組みは、森林産業、熱自給、高齢化対策という環境、経済、社会が調和した持続可能な地域づくりのモデルとして評価されており、「環境モデル都市」(2008年)、「環境未来都市」(2011年)、「バイオマス産業都市」(2013年)、「SDGs未来都市」(2018年)に選ばれている。
・大分県豊後高田市
大分県北東部の国東半島西側に位置する豊後高田市は、人口約2万2000人で高齢化率38.8%(2020年時点)の町である。周防湾に面しており、豊かな自然と温暖で過ごしやすい気候が魅力である。現在でも古い町並みや伝統行事が残っており、2011年に立ち上げられた商店街「昭和の町」は全国から注目を浴び、観光地としても賑わっている。
豊後高田市は移住者獲得の実績に長けている。『田舎暮らしの本』(宝島社)の「住みたい田舎」ベストランキング(人口3万人未満の市)において、全国で唯一2013年の第1回から12年連続でベスト3に入り続けている。2024年には若者からシニアまでの全世代の部門において、全国初となる4年連続第1位に輝いた。2014年から2023年まで10年連続で転入が転出を上回る社会増が続いており、近年は毎年300人以上が移住している(大分合同新聞2024)。
特に「教育のまちづくり」や「子育てにやさしいまちづくり」に力を入れてきた。具体的な取組みは下記のとおりである。
①最大200万円の子育て応援誕生祝い金
(第1子・第2子:10万円、第3子:50万円、第4子:100万円、第5子以降:200万円)
②子育て応援入学祝い金(小中高入学時各5万円)
③妊婦健診の助成
④妊産婦の医療費助成
⑤産婦健診の助成
⑥0歳から高校生までの医療費無料、入院時の食事代も無料
⑦保育料・幼稚園授業料が無料
⑧保育園・幼稚園・小中学校の給食費無料
⑨幼児・小中学生・高田高校生対象の無料市営塾
⑩県立高田高校の授業料無料
※豊後高田市HP参照
また、市内全域に光インターネットのケーブル網が張り巡らされ、どこでも快適にインターネットを利用できるようになっており、リモートワークに適したネット環境を整えている。移住前の企業でのリモートワーク移行や田舎暮らしをベースにした会社勤めなど、様々な働き方を想定している。
移住者向けのきめ細やかな移住支援策も充実している。「空き家所有者」と「移住希望者」のマッチングを行う『空き家バンク』を運営し、移住希望者の家探しをサポートしている。リフォーム事業補助金やDIY奨励金といった多様な奨励金なども充実している。新築を希望する移住者に対しては土地代無料の宅地を提供したり、子育て世代や移住者向けの市営住宅を提供したりもしている。
移住希望者向けに田舎暮らし体験プログラムや移住体験会を実施している。2024年から日時や公共・教育施設の見学などの希望に柔軟に対応するオーダーメード型の移住体験も始めた。移住を検討するところから定住するまで、あらゆる段階においてきめ細かい支援をしている。
移住支援策についての情報発信も積極的に行っている。田舎暮らしを希望する人に人気の雑誌への情報発信、都会で開催される「定住フェア」への参加、市公式ホームページ以外にも「IJU(いじゅう)支援サイト」「ぶんごたかだに住んでくだサイト」などの専用サイトの運営もしている。様々な情報媒体をうまく活用して情報発信やコミュニケーションに努めている。
非常に充実した移住支援策を展開している豊後高田市だが、その根幹には移住者の「夢をかなえる」ことを重視し、移住希望者の「夢」の実現と地域のリソースを結び付けるという価値観がある(自治体ポータル2017)。この価値観ゆえに、移住者のニーズに合う多様な支援策がうまれ、移住者の希望に沿って定住までをトータルでサポートする体制が見事に構築されているのであろう。
4.政策提言:地域から日本を再生させるために
①地域の魅力をテコに「関係人口」を増やす
無関係人口(地域に関心も関与もない人口)の層に、段階を踏まずに移住を迫るような移住政策は現実的ではない。「特産品の購入→寄付(ふるさと納税)→頻繁な訪問→二地域移住→移住」といった数段階のステップを踏んで最終的に移住したくなるような政策が重要である。つまり、移住以前の段階を特定化し、対象をターゲティングする発想を持って、関係人口を拡大し、ステップを登りやすくすることが重要である。その際、地域のリソース(特産品、豊かな自然など)をテコにして、魅力的な産品のブランド化、訪問したくなるイベントや場所を創るといった工夫が必要である。
②多様な人が関わる開かれた地域社会へ
地域おこし協力隊は、任期後の定住率が7割を超えている。若者の移住を促すためにも、地域おこし協力隊は最大限活用すべきである。
また、地方の国立大学において各地のローカルな社会課題の解決を担う人材を育成することも重要である。産官学が連携して大学を社会課題解決の研究拠点、および地域活性化の拠点にし、若者の地元定着を促すことを期待したい。
さらに、若い女性が戻ってきて定着するために、男性の育休取得、女性管理職の割合増加、女性のリーダーシップ・プログラム実施、女性にとって働きやすく働き甲斐のある企業の認定等、ジェンダーギャップの解消に取り組むことも重要である。
ただし、日本全体で人口減少が起きている以上、様々な地域で人口を増やし人口減少に歯止めをかけることは現実的でない。関係人口も含め、様々な形で地域に関わる「人材増」を目指すことも必要であろう。
③長期的家族支援策に取り組み定住者を増やす
地方移住は新たに住み始めて初めの1〜3年間と、4年目以降の期間で段階を区別することができる。現状では、行政の意識は初めの1~3年間に集中しており、それ以降の期間に対する政策が手薄となっていることが課題である。初めの1~3年間は就職(所得)と人脈づくり、4年目以降では仕事の安定化、さらに将来的に永住を考える段階では子供の教育などが関心事となる。長期的な家族支援をも視野に入れた移住支援策が必要である。邑南町や豊後高田市の子育て支援策が参考になるだろう。
④各地の強みを活かした産業政策を展開する
各地域で基盤産業のもととなる固有の有形・無形の資源をいかに見つけ、それをいかに育てていくかが重要である。下川町の事例は、地元の森林資源を最大限に活用している。邑南町の事例は、町の農作物や加工品といった特産品をテコにして農業を盛り上げ飲食店の起業を促し町の活性化につなげている。
弱体化した地域産業を復活させることや基盤産業候補を外から誘致することも選択肢となる。地域において伸ばすべき基盤産業を識別し、地域内の産業間のつながりを強化することで、域内市場産業への波及効果の向上も目指すべきである。
また、地方の大学・研究機関を巻き込み、産学官連携のもと基盤産業に関する研究を促進するとともに、そこに持続的に貢献する人材を育成することも有効だろう。
⑤「経済」「社会」「環境」の統合的解決をはかり、自律・自立型の地域社会を確立する
下川町の例のように、「経済」「社会」「環境」分野の諸課題を統合的に解決することを目指すことが望ましい。各自治体において、これまで経済成長、社会課題の解決、環境保全に別々の政策で対応してきたアプローチを見直し、複雑化する諸課題の同時解決を図るべきである。SDGsの要素を取り込むことにより、自治体、民間企業、金融機関、大学、NGO/NPO、多様な地域コミュニティなど、これまで関係の薄かった異分野のアクターが連携できるプラットフォームが用意されうる。そういった場で、地域に固有の魅力や弱みを再発見し、「ローカル・アイデンティティ」を確立して自律的な地域づくりを実現していくことが望ましい。
<参考文献>
朝日新聞(2018)「SDGs 国谷裕子さんと考える:森と生きる町 北海道下川町」、朝日新聞デジタル、2018年11月26日、https://www.asahi.com/special/sdgs/shimokawacho/(2024年10月2日閲覧)。
上田裕文(2021)「北海道下川町におけるSDGsによる地域づくりのチャレンジ」、ランドスケープ研究85(2)、pp.100-103、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/85/2/85_100/_pdf/-char/ja(2024年10月2日閲覧)。
大分合同新聞(2024)「日時や内容、柔軟に対応…豊後高田市がオーダーメード型の移住体験受け付け」、2024年9月7日、https://news.yahoo.co.jp/articles/9e84f5f8469f96f5d25c7c9c99563fb69737bd74(2024年10月2日閲覧)。
邑南町ホームページ「邑南町の地域おこし協力隊」、
https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1695888737863/index.html(2024年10月2日閲覧)。
邑南町(2020)「邑南町観光戦略(観光ビジョン)」、https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1600826220207/simple/2020michinoeki_kankou.pdf(2024年10月10日閲覧)。
小田切徳美(2021)「田園回帰と地域づくり—持続可能な都市農村共生社会をめざして—」、平和政策研究所。
サステナブル・ブランドジャパン(2021)「北海道下川町:町民とともに持続可能なまちづくりを進める、北海道のSDGs未来都市」、SUSTAINABLE BRANDS、2021年11月22日、https://www.sustainablebrands.jp/news/jp/detail/1205749_1501.html(2024年10月2日閲覧)。
自治体ポータル(2017)「先進地域の取り組み最前線 地域活性〜大分県豊後高田市の取り組み〜 移住で実現する夢を支援し人口の社会像180人を達成」、2017年2月22日、https://www2.nec-nexs.com/supple/autonomy/interview/bungotakada/(2024年10月2日閲覧)。
人口戦略会議(2024)「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート—新たな地域別将来推計人口から分かる自治体の実情と課題」、https://www.hit-north.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/01_report-1.pdf(2024年10月2日閲覧)。
中貝宗治(2021)「『小さな世界都市〜Local&Global City〜』をめざす豊岡の挑戦」、平和政策研究所。
農林水産省(2015)「人口減少社会における農村整備の手引き」、農林水産省、https://www.maff.go.jp/j/nousin/seibi/sogo/s_seibi/pdf/jinkou_jirei02.pdf(2024年10月2日閲覧)。
藤山浩(2022)「地元から世界を創り直す—地域社会から日本を再構築するビジョンと戦略—」、平和政策研究所。
豊後高田市「全国トップレベルの子育て支援を『本気』で目指しています!!」、https://www.city.bungotakada.oita.jp/soshiki/4/2381.html(2024年10月2日閲覧)。
豊後高田市(2024)『令和6年度版 市勢要覧 豊後高田市の姿 資料集』、https://www.city.bungotakada.oita.jp/uploaded/attachment/9628.pdf(2024年10月2日閲覧)。
山下祐介(2020)「人口減少時代における持続可能な地域づくり—家族と世代間継承の視点から—」、平和政策研究所。