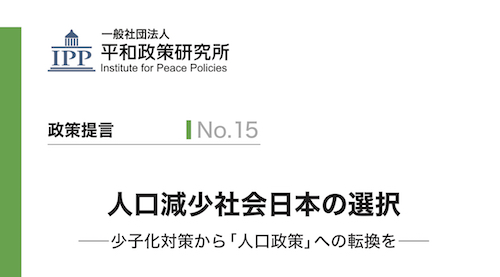政治と宗教の関係モデル
現実の社会・政治を理解するためには、理論的な研究だけでは不十分で、生きた社会の政治や宗教の実相を現実に即して捉えなおして考えてみる必要がある。
さて「宗教」も「政治」もともに翻訳語として導入された。しかし、この点に気付くことは少なく、それゆえに、それらとわれわれ日本人の持つ伝統的観念との乖離がある。そのため学問的にも使用言語の意味のあいまいさのために、われわれの思考が深まらないことが多い。
例えば、一般の日本人にアンケートで「あなたは宗教を信じているか?」と聞くと7割は「なし」と答える。私自身大学で十数年間同様のアンケートを学生から取っているが、(宗教についての講義を受ける前は)5割以上が「無宗教だ」と回答している。これは西洋的な「宗教」概念からくる結果ではないかと思う(「宗教」という言葉構造の多元性などに関する詳細は、拙著『癒しと鎮めと日本の宗教』北樹出版社を参照のこと)。
次に「政治(学)」だが、これもpolitical scienceの翻訳語である。明治以前の日本には、政治に相当する言葉としては、「マツリゴト」「成敗」「万機」「政道」「政事」などがあった。興味深いものとしては、「政治算術」という訳語が一時辞書に掲載されたことがあったが、それは「いかに自分に有利な立場をつくるかが政治であり、政治とは損得勘定の算術だ」という意味で、ある面で近代政治学の本質を突いているともいえる。これらの言葉は日本人の歴史の中で、キチンと機能してきた言葉であるのに、あえてそれらと断絶して、「政治」なる言葉を考察したところに、日本近代の特徴というか、限界がある。
政治学者丸山真男の日本政治思想史研究においても、「政治」はせいぜい荻生徂徠あたりまでしか遡らない。もちろん講義録などを見れば古代のことも押さえてはいるのだが、それは「政事」としてであって、「政治」となると、欧米の政治学概念に近いものとして、朱子学の日本的展開である荻生徂徠以降となるようだ。もっとも日本の朱子学理解は、天や易姓革命を拒絶している点で、真の朱子学、否儒教ではないであろう。せいぜい儒教倫理である。
それでは日本やアジアには「政治」に相当するものはなかったのか。インドの政治思想研究でも、わずかに古代のことを言及するだけですぐに近代に入ってしまう。日本は1500年以上の歴史の中で、どのような考え方・思想によって国を治めてきたのか。それを扱える概念や独自の方法論、否より広い政治思想が本当は必要なのではないだろうか。
そこで以下、ヨーロッパ、中国、インド、イスラーム世界、日本について政治と宗教の関係モデルを提示しながら説明したい。
(1)ヨーロッパの政治構図
(欧米の学問に立脚した)政治学者の学説に拠れば、政治と宗教の関係は「世俗化」と「政教分離」を基本とする。そして大枠はキリスト教世界だが、その中に「グレコ・ローマ型の伝統」と「ヘブライズム型の伝統」(預言者的宗教=キリスト教の提示する政治思想)が楕円構造の中に並存し、それらが互いに影響を及ぼしあいながらヨーロッパの政治世界を形成してきた。全く違った要素が同じ土壌の上にあって、それらが牽制しあってきたわけだ。中世はローマ教会という宗教帝国主義ともいえる組織宗教が優勢で、信仰はヘブライズム的だが、組織はローマ帝国的な形態を持っていた。これに対して、近代のはじめは極端なヘブライズムが優勢となり、世俗主義と呼ばれるものが生じた。この世俗主義は、反教会主義であるが、むしろ神と人が直結するという意味で、ヘブライズムの原点帰りではないかと思う。カルバンの思想などを見ると、<神→人>という直線的支配関係が明確化し、神政政治(theocracy)のようになった。その後、その厳しさはそれはばらけてしまい、現代のように政治と宗教の一応の分離、つまり政教分離が結果として成立した。もっともこれもヘブライズム的政治と宗教の変形ともいえる。
(2)中国の政治構図
中国では、天の定めた天子を中心として宗教・軍隊・官僚などすべてを支配するとともに、それらは天子の一存で動く専制体制(天子=政治)である。この構造は、共産主義体制の今も本質的に同じであろう。
(3)インドの政治構図
インドの場合は、宗教の中に世俗生活や政治が入ってくる構図だ。それを立体的に見ると、宗教と政治は段差、すなわち、世俗(俗)と宗教(聖)の間に意識・空間・時間のギャップがある。ただしそれらは密接に関連していて、宗教的なものによって政治が支配され影響を受けており、その度合いは非常に強いのが特徴である。
(4)イスラームの政治構図

イスラームは、同心円状の構造で、中心にはクルアーン(コーラン)とハディース(ムハンマドの言行録)があり決してぶれることはない。そして同心円の中に政治も経済も含まれ、それらが枠組みから出ることは決してない。ここでは政教一元(タウヒード)の原則が貫かれている。
もちろん、現実の世界を見ると、モロッコ(中世型王政)、旧イラク(社会主義体制)、シリア(バース党支配の社会共産主義体制)など多様な政治体制があるが、クルアーンを否定しない限りにおいてはどのような体制をとろうとも問題はないという考え方だ。それはクルアーンやハディースに抵触しなければ、いかなる政治支配体制でもよいとハディースに書かれてあるからである。クルアーンを中心とする枠内に収まることが大原則であるが、それを強調しすぎると、「イスラーム国」のようになり、緩めるとインドネシアやマレーシアのような国になる。
(5)日本の政治構図
それでは日本はどうか。明治以前は、俗(政治)と聖(天皇)は<ずれた形>の支配構造だった。天皇が退位すると一仏教徒となり最後は仏門に入るのは普通のことだった。ところが明治になるとそれを否定する。つまり、仏教国としての日本の過去を否定した。廃仏毀釈(神仏分離)政策である。このとき日本は近代国家を目指しながらも、実は神道一辺倒の国家、すなわち古代の神聖祭政一致の政治体制を作った。そこでは神=国家だった。日本の近代化とは、古代国家体制の復興を目指した神道原理主義化であったといえる。この点の反省がないので、敗戦後、政治と宗教の位置関係があいまいとなり、今日に至っている。こうしたところにも日本人の宗教意識の欠落、思考停止状態が生まれる背景があると思う。
(6)社会における宗教の構造的理解
以上をまとめると上図のようになる。
近代的枠組み(19世紀)では、基礎に生命原理があり、その上に技術、経済、政治、文化と階層化されており、上にいくほど地域性(特殊性)が強く現れ、下にいくほど普遍性が強くなる。近代的枠組みでは、宗教が文化の中に含まれてしまうので、政治・経済・技術とはあまり関係がないという意識構造が生まれた。こうなると、政治や経済の中に宗教を見出そうという発想は出てこない。そのため政教分離が強調されると「そうだ」と納得してしまう。しかし実際はそうではなく、宗教は各レベルに対しても強い影響力がある。ただ、その影響力には強弱がある。
そこで実態に即した枠組みを描いてみると、図6、7のようになる。どの段階にも宗教は関係しているが、それぞれの段階でその程度に濃淡が見られる。経済は政治分野よりも宗教の影響は少ないが、それでもその影響が見られるように、人間の文化的営み(文化領域)においては宗教と無関係に存在するものはないのである。
こうした見方を持たないと、人間の営みとしての文明の全体像は見えてこないし、政治と宗教の関係は明らかにならないであろう。少なくとも、近代以前の国々やイスラーム世界を理解することはできない。そうでないとイスラーム世界を見下すような見方を持つことになる。さらに言えば、自分自身の文化理解においてさえも正しい理解にいたることができない。宗教から離れた個人、社会、国家はありえない。なぜなら宗教は、その国、地域の最も共通の共有されるべき基層部分であり、その文化を形成するのに大きな役割を果たしている精神世界の重要な要素だからである。
ここで日本の宗教について考えてみよう。日本人は「無宗教だ」といいながら、元旦に神社やお寺にお参りし、彼岸にはお墓参りをし、クリスマスどころか近年はハロウィーンまでお祝いしている。しかしそれらが宗教行事だという意識はほとんどない。日本人にとって、みんなが集まり祝う、騒ぐということが、「宗教行事」なのだ。個人の意思を超えた共同体のしくみを作る、みんなで楽しんでガス抜きするという機能もあるが、これこそ日本人がもつ「救いの形=魂振り」なのである。
以前は気を失った人を激しくゆすって正気を戻させることがあったが、「ゆする」ことで摩擦を起こし熱を発生させて元気を注入するという意味がある。また神社の鈴はたくさんついているが、それをガラガラとゆすって音を出すのは、神社の奥にましますカミに音の振動が伝わってカミを喜ばせるのである。魂を振るわせるので「タマフリ」というわけだ。
みんなで集まってわいわいがやがや楽しむことが、日本人にとっての<宗教>であり、それが宗教的役割を果たしている。教理はどうでもいい。こうした現象も含めて「宗教」として理解しないと、ヨーロッパ的な「宗教」概念で掬えない現象は宗教ではなくなってしまう。そうなるとわれわれ日本人のやっている行動は一体何なのかということになる。明治時代には、それらを宗教ではなく「祖先からの伝承」「道徳」だなどと言ったが、それは詭弁に過ぎない。
こうした現象も宗教の一形態だと定義ができるようにならないと、<宗教の普遍性>が出てこない。ヨーロッパがつくった「かたち」に合わないものは、非科学的といって無視してしまう。学問・研究レベルの議論ならともかくも、実際の人間が生きている社会の分析において、それでいいのかという反省である。
アジア的宗教と政治 -インド仏教に学ぶ平和思想
以上の前置きはこれくらいで、本題に入ることにしたい。
(1)暴力装置を持たない政治権力のあり方
「政治」を「統治の仕方」という意味で考えると、政治は民衆の社会を形成する宗教とどのような関係にあるのだろうか。
古代インドの社会統合理念は、争いの絶えない今の時代こそ注目していいのではないかと思う。中国とヨーロッパには共通しているが、インドとは異なる点がある。それは暴力装置としての軍隊という物理(軍事)的力による支配の有無である。「政」という漢字の意味は、旁「攵」は人が鞭を持った姿で、鞭(力)でもって人々に権力者の言うこと(正)をきかせることだという。物理的な力による支配、あるいは従わせるという発想である。しかし古代インドには、そうではない発想によって、人々を従わせ、秩序を保ち、生活できる社会の枠組みがあった。古代インドには、そのような可能性をわれわれに気付かせてくれる材料があるように思う。
世界四大文明の一つであるインダス文明は高度な文明を築いたが、強力な中央集権的体制として、武力で人々を威圧するようなシステムを感じさせるようなものがないといわれる。例えば、どの遺跡を発掘してみてもほとんど武器類が出土しないし、強力な王の権威を象徴するような宮殿も出てこない。集会所遺構はあるのだが、王の前に軍隊が整列するような威圧的なものではなく、あくまでも民衆の集会所だ。
主な遺跡としては、神殿、沐浴場、集会所の跡がある。沐浴場には、民衆のものと祭司王(バラモン王)のものと2種類がある。これらの跡は、宗教的な儀礼によって心の内面から支配・統治するためのものではなかったのか。
ヨーガや瞑想を行うと、心の内面に踏み込んでいき、さらに内面をどんどん深くしていくと「すべての人間(を含む全存在)はつながっている」というインド思想の世界観に至る。お釈迦様、インドの聖者はみなこれによって悟りを開いた。外に向かうのではなく、内に入っていく。この発想だ。
ユダヤ・キリスト教や中国では、神(絶対者)は外の高みにいて、神託が外から預言者などに与えられる。一方、インドは内から来る。人間が深く無意識の中に沈潜していくと(ヨーガや瞑想)、全存在が繋がっているという悟りに至る。そのような内面からの宗教的権威を基として王はで人々を従わせることになるのである。
しかし古代インドには文字の文献がほとんど残っていないので、想像されるだけなのだが、遺跡から出てくるのは玩具やサイコロなどで、武器が出土しないこと、一番力を入れていたと思われるのが、沐浴場だという事実をどう読み解くかということだろう。
インダス文明は紀元前18世紀ごろに衰退し、その後アーリア人が中央アジア方面から移動してきて先住民を征服し支配構造をつくった。アーリア人はどちらかといえば遊牧民系で、共和制の国をつくった。もちろん軍隊(後のクシャトリア=武人階級)を持ってはいたが、あまり中央集権的発想はなかった。インダス文明滅亡後、それを引き継いだ民衆は生き残っていたので、アーリア人と民衆が相互に影響を与えあって独自の政治システムを形成したと思われる。
すなわち、この時代にバラモン・クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラという4つのヴァルナによるカースト制度の元型ができた。そこではバラモン(司祭階級)がクシャトリア(王侯・武士階級)の上に立っていた。なぜこのような制度ができたのか。
現代でもタイでは王といえども僧の前では跪くし、インドの最高権力者も僧の前では同じ位置に立たない。これらは聖なる世界(宗教)が世俗より一段上という伝統を(形骸化しつつあるが)示している。インドの理想像を宗教(心の世界)に訴えて、社会的安定を維持していくという政治哲学が脈々として生き残っているのである。もちろん武力もあったが、武力は最小限にとどめて政治を実践していくという言説が歴史の中に残り、実践されてきた。
(2)アショーカ王の平和政治
マウリヤ朝の創始者チャンドラグプタ(Candragupta、在位:前317頃-前293年頃)はジャイナ教を信じていたが、60歳ごろに出家して王位を息子に譲ると、「裸の行者」となってインド南部に修行しながら最期は餓死(修行の完成)したという。権力の最高位にいた者が惜しげもなく権力を放棄して、宗教世界に入ってしまったのである。
ちなみにインドでは、人生には学生期・家住期・林住期・遊行期の4つの住期があるとし、それを理想的生き方とみる。チャンドラグプタ王はそのような生き方を実践したわけだ。
その孫の第3代アショーカ王(Asoka、在位:前268頃-前232年頃)は、父祖以来の王=国家という考えに基づき、あらゆる手練手管を使って民衆を支配し今日のインドに相当する領域を支配した。マキャベリの「君主論」が子どもじみたと言われるほどに、細かく厳しい統治を行った。そのため「悪魔のアショーカ」といわれるほどの力に基づく政治を実践した。
ところが、あるときその方向を180度転換した。当時最強とも思われた軍隊を解散し、最低限の軍隊で王宮を守り、余った武器は農機具等に作り直し、余裕のできた予算で道を整備した。道には4キロごとに水飲み場などを備えた駅舎をつくった(駅伝制)。 また屠殺業を禁止し、その従事者たちに薬草栽培の仕事を与えた。仏教が教える不殺生や和合を単に仏教思想にとどめることなく政治として実践したのである。インダス文明以来の、武力支配ではなく、精神・心で宗教的理想を共有することによって社会を統治するという、政治哲学を実践した。
ただし、アショーカ王の晩年は、仏教に肩入れしすぎて国家財政の破綻を招き国家衰退の道へとつながった。しかし道路網を整備しながら道沿いにはマンゴなどの樹木を植え、そのマンゴを売って民衆の生活に資するシステムは今でも活きている。そのほか、言論の自由、刑罰の軽減化、税の軽減、救貧制度、病医院の設置などを進めながら、法の統治(ダルマ=法の政治)を実践した。しかし余りにも急進的に推し進めたので失敗してしまったとはいえ、その伝統はインドに長く継承された。この点は今日、もっと評価されるべきだろう。
一方、アショーカ王とほぼ同じ時代の中国は、秦の始皇帝の時代だった。始皇帝は朕=国家と考え、国の富はすべて自分のために使う一点集中の強力な中央集権体制を築いた。アショーカ王も同様の位置にいたが、後にひっくり返してすべての民衆の奉仕者としての王という概念を作った。即ち、アショーカ王の政治思想の核心には「王は民衆によって選ばれたがゆえに、民衆への奉仕者である」「すべての世の人に利益を為すより崇高なものはない」などがあった(詳細は、中村元『原始仏教の社会思想』『宗教と社会倫理』参照)。
またアショーカ王の政治思想には「寛容の思想」もあった。「寛容」とは何か。この日本語も明治期に作られたtoleranceの訳語であるが、一般的なイメージとして、「一方が他方を許してやる」という意味に理解されている。しかし本来仏教の唱えた「寛容」は、「許しあう」という意味だった。「慈悲」とも言ったが、私は「同置」という言葉を使いたい。自分が相手と同じ立場に立つという意味だ。Toleranceには耐えるという意味もあるから、自分が耐えていれば相手は何をしても許し続ける。ところが耐え切れなくなったときに、暴発して暴力を振うこともあり得る。だが同じ立場に立てば互いに許し合える関係になるので、堪忍袋の緒が切れることにはならない。
われわれが直接知りうる存在としては、マハトマ・ガンディー(本名はMohandas Karamchand Gandhi、1869-1948年)がいる。彼が目指したものは、暴力などの力によって相手を支配するのではなく、共感しつつ同じ立場に立って争いあわずに争いを超えるという発想だった。その淵源は、インド、とくに仏教的政治哲学の中に見出すことができるのではないか。
武力という外からの力による共生ではなく、内からの感動・共感によって社会を安定させていく。そのような政治的発想の可能性があることをインドは教えてくれている。それを最も取り入れているのが仏教の政治哲学だろうと思う。
ヒンドゥー教にも似た考え方があるのだが、インド地域を超えて広がることはほぼないから、世界に影響を与えたという観点に立って、ここでは仏教の政治哲学に限定して言及した。しかも仏教は、中国、朝鮮、日本、中央アジア、南アジアなどに伝播して根を下ろし、宗教と政治が密接に関係しながら文化を発展させてきた。そして仏教の政治思想、アショーカ王が実践した跡がいろいろなところに(断片的ではあるが)残っている。
ところで、中国南朝の梁の武帝(在位502-49年)は「皇帝菩薩」と自称した。中央集権的政治体制の中国史においては珍しく、恐ろしい中央集権ではなく緩やかな中央集権で民衆を喜ばせる政治を行った。ただ、軍備をおろそかにしたために隣国に攻められてあっという間に滅亡してしまった。しかし彼が民衆に与えたインパクトは小さくなかった。慈悲、搾取しない皇帝の姿を見せたように思う。
日本における仏教的政治の実践
(1)日本最初の仏教徒天皇の出現
実は明治以降、仏教と政治・国家の関係について本格的に研究することが憚れる「雰囲気」があったが、例外的に取り組んだのが哲学・仏教学者・中村元先生(1912-99年)だった。もちろん仏教の宗派内で論じられることはあったと思うが、学問的に客観的に研究した例はほとんどなかった。仏教と政治・国家について客観的に論じないでよいものかとの反省からだと、中村先生は話しておられた。あの悲惨な戦争を防げなかった反省があったと思われる。
仏教を日本で最初に受け入れたのは、聖徳太子の父親である第31代用明天皇(在位585-587年)だった。用明天皇の和風諡は「仏法信神道尊(ホトケのミノリをウけカミのミチをトウトブ)」、つまり仏法を信じかつ神道も尊ぶ、仏教と神道はぶつかり合わないという意味で、日本の神仏習合を決めるスタンスを宣言したことになる。神仏習合の点では聖徳太子がよく引き合いに出されるが、本当は用明天皇が仏教と神道を結びつけ協調して日本を作っていくのだという路線を決めた。
「信仰」には外の高いところを見上げるようなイメージがあるが、日本では元来人の言葉・教えを身に受け入れる、信(う)けることが信仰(もともとは「しんぎょう」と読んだ)だった。用明天皇が仏教を信け入れたことによって、それ以降の天皇や皇族は仏教を受け入れることに躊躇しなくてもよくなった。日本最初の正式に受戒した天皇は第45代聖武天皇(在位724-749年)で、「沙弥勝満」という戒名を使った。
聖武天皇は大仏を作って国費を浪費したと批判される。しかし、東大寺の記録によると、延べ150万人の人が大仏建立に関与したというが、彼らには1日玄米7合、味噌・野菜が支給された(これは男子の場合で、女・子の場合はその半分程度)。また傷病者には手当てをした。決して民衆を搾取したのではなかった。
ちなみに、正倉院御物の半数は武具だ。それは聖武天皇がアショーカ王の事例に倣い、自分が亡くなったときに武具を正倉院に奉納することで軍気を封印したのであった。歴代の天皇が武力を持たなかったのは、ここに原点があった。この辺にインドの仏教哲学との接点があったのではないか。用明天皇前後まで天皇家は殺し合いの連続だったが、やがてそのようなことが薄れていった背景には、仏教思想の浸透があったと思う。
仏教の精神によって国を治めると宣言して為政者天皇が実践した政治、あるいは政治哲学とは何だったのか。これを現代の政治学が取り上げない理由はないと思う。それこそ日本の伝統に即した政治哲学の基礎だと思う。これを研究する必要がある。これまでの西洋概念一辺倒を反省して、日本のこともよくわきまえながら、西洋の概念に接していくことが求められるのではないか。
(2)仏教的政治思想の実践者
天皇の中には、アショーカ王に見られる仏教的政治思想の具現者としての姿を実践した天皇もいた。
その一人が山背大兄王である。山背大兄王は蘇我氏の実権が入鹿に移ると、入鹿は蘇我氏の意のままになるとみられた古人大兄皇子の擁立を企て、その中継ぎとして皇極天皇を立てた。蘇我入鹿は巨勢徳多など100名の兵に斑鳩宮の山背大兄王を襲撃させると、山背大兄王は生駒山に逃亡。家臣の三輪文屋君は「東国に難を避け、そこで再起を期し、入鹿を討つべし」と進言するが、山背大兄王は戦闘を好まず、「われ、兵を起こして入鹿を伐たば、その勝たんこと定し。しかあれど一つの身のゆえによりて、百姓を傷りそこなわんことを欲りせじ。このゆえにわが一つの身をば入鹿に賜わん」と答えて自害し一族郎党とともに絶えた(643年)。まさに自らの身を犠牲にして大義に生きる姿勢を示したのであった。 私はインド中世のイスラームを研究しているが、権力者は民衆を犠牲にしても、自分だけは助かりたいという人ばかりだ。このような権力者は、ほとんどいないように思われる。
もう一人例を挙げれば、南北朝時代の最初の北朝天皇といわれる光厳天皇(在位1331-1333年)である。足利尊氏や後醍醐天皇に翻弄された人生だったが、夢窓疎石に帰依した。南朝の軟禁下に5年間置かれ、1357年(正平12年)に河内金剛寺から還京し、深草金剛寿院に入り、ついで嵯峨小倉に隠棲。晩年は丹波山国荘の常照皇寺で禅僧としての勤めに精進し、京都で崩御した(*最近では、光厳天皇は正式に即位しておられたと考えられている)。
光厳天皇も(いろいろな政治的駆け引きもあったと思うが)民衆を苦しめるのはいかんとしてぱっと身を引いた。さっと身を引いて権力から遠ざかることによって社会や民衆のために生きようというのは、インドに由来する仏教的政治思想があったからだと思う。真の帝王とは何か。民衆の安寧を護る人のことであり、自らの地位のために民衆を犠牲にする人のことではない、ということである。この天皇の血統が今日の天皇家であることは興味深い。
そのような思想に着目することによって、宗教、宗派、民族が、いがみ合ったり、殺しあったりする現状に、多少は違った方向性を与えられるのではないか、可能性があるのではないか。軍備増強による守りだけでは、いつまでたっても戦争はなくならない。オバマ大統領やキング牧師は、マハトマ・ガンディーの影響を受けて核廃絶や非暴力による公民権運動を展開したといわれる。
いずれにしても古代インド仏教思想が問いかけているものは、武力以外の手段で社会をコントロールする可能性を見せてくれていると思う。これを何とか掬い上げるような政治思想、哲学がつくれたらいいのではないか。
日本にもそのような伝統があるわけだが、なるべく相手の対場に立って相手に寄り添うような政治・平和社会を作っていくためには、確固たる理念、思想があったほうがよいと思う。そのためにも日本の過去、そのルーツであるインドにも着目してもらえればと願う。
(2014年12月3日に開催された「平和学術フォーラム」での発題を整理してまとめた)