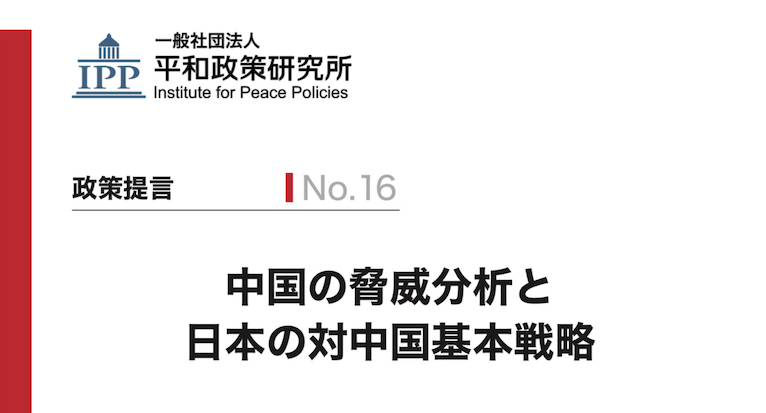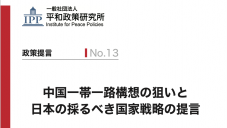はじめに
中国の全人代常務委員会は2020年6月30日、香港の反政府運動を取り締まる「香港国家安全維持法」を異例の早さで可決し、同法は即日施行された。同法が付与する新たな権限の下で、香港警察は①令状なしでの家宅捜査、②インターネット企業へのコンテンツ削除命令、③国家の安全を危うくすると疑われる人物に対する渡航制限と資産押収、④香港外での政治団体からの情報請求、⑤通信傍受と監視活動、などが可能になる。中国の「一国二制度」は終焉したと言ってよい。
中国政府は、かねてより香港の「中国化」を意図していた。2002年9月、当時の江沢民国家主席は香港政府に対して国家安全法の制定を指示したが、香港返還以来最大規模のデモが展開され、香港政府は制定を断念した。2012年11月、共産党大会での退任演説で、胡錦濤総書記は「次期習近平政権が香港政策を転換する」と表明。香港の「長期の繁栄と安定」重視から、「国家の主権と安全と発展の権利」最優先へと政策転換することを明らかにした。2014年に習近平政権が初めて作成した「一国二制度の香港での実践白書」に、この方針が明示されている。2017年の香港返還20周年記念演説でも、習近平国家主席は「一国は根であり、一国抜きの二制度はありえず、一国を揺るがすことは認めない」と強調した。
このように「香港国家安全維持法」の制定は、習近平政権がもともと意図していたものである。実際には、2019年の逃亡犯条例改正案に対する反対デモにより、香港が体制の危機を迎え、それを機に国際社会の反対を押し切る形で強行された。米中新冷戦の下で、香港が「火薬庫」になることは予見されていたが、それが現実のものとなった。
本稿では2019年香港デモが巨大化かつ長期化した要因を分析するとともに、米中新冷戦の最前線である香港の「戦略的立ち位置」と今後のシナリオ、及び日本の対応について考えたい。
一、2019年香港デモ巨大化長期化の要因とその後の動向
2019年香港デモの発端と背景
逃亡犯条例改正案の発端は、非政治的な事件であった。2018年2月、香港の若いカップルが台湾旅行中に喧嘩になり、男性が女性を殺害、女性の遺体を台北に遺棄したまま香港へ逃げ帰った。1997年に制定された「逃亡犯条例」によれば、香港は「香港以外の中華人民共和国」へ容疑者を引き渡すことができない。このため香港政府は、容疑者を台湾政府(中国政府は台湾を中華人民共和国の一部としている)に引き渡すことができずにいた。そこで、逃亡犯条例を改正し、「香港以外の中華人民共和国」に引き渡ししないとの規定を削除しようとした。しかし、改正案が可決されれば、台湾だけでなく中国政府へも容疑者を引き渡すことが可能となる。それで巨大な反対運動に発展したのである。
2019年香港デモが巨大化・長期化した背景には、主に次の5つの要因がある。①自由を重視する「香港DNA」への香港政府の無理解、②普通選挙を求めた2014年「雨傘運動」の失敗を民主派が教訓として生かしたこと、③習近平政権における情報収集体制の麻痺、④米中新冷戦による米国の強力な後押し、⑤民主派と香港政府とのイデオロギー対立の先鋭化、である。
自由を重視する「香港DNA」への香港政府の無理解
民主派は当初から改正案には反対だったが、通常は政府を支持する財界系議員や政党関係者、保守派学者からも異論が相次いだ。引き渡しの罪状に「賄賂罪」が含まれていたからだ。中国ビジネスでは賄賂が日常化しており、これが香港財界人には現実的脅威と映った。中国政府が条例を脅しに使う懸念もあった。条例改正案には、普段政治には関心がない一般市民も「身にかかる危険」を感じた。改正案撤回を求めた6月9日の「103万人巨大デモ」への参加者に、香港紙『明報』がアンケートを実施している。参加の動機として、「私・家族または友達が中国本土へ引き渡される懸念があるから」と答えた者が、56.2%にも上った。
「103万人巨大デモ」にもかかわらず、香港政府は民意を無視し、デモ終了の一時間後には予定通り条例改正案を審議することを公表した。審議入りの6月12日、デモ隊は立法会を包囲、これに対して林鄭月娥行政長官は、同日夜のテレビ談話で「自身を優しい母親、市民を子供」に例えた。これが香港市民の神経を逆撫でした。13日・14日も立法会の周辺は混乱し、開会不能となった。15日、林鄭月娥は記者会見で改正審議の一時停止を発表したものの、謝罪の言葉はなかった。加えて会見当日、最初の自殺者が出た。これがさらに多くの市民を動かし、16日にはついに200万人デモに発展した。こうして香港は、政治的社会的大混乱に陥ったのである。
香港政府が改正案を撤回したのは9月4日で、遅すぎた。9月2日には「私に選択肢があるなら、まっさきに謝罪して辞任したい。私には警察を使う以外に何もない」との林鄭月娥の肉声を、ロイターがリーク。私的会合での発言とされているが、香港の行政長官は自身の進退の決定権すらないことが白日の下になった。
香港はいわば「逃亡犯の街」である。今の香港を作り上げたのは、文化大革命や大躍進運動の際に難民として流れ込んだ中国人やその子孫である。香港の存在意義は、中国本土にはない「政治的自由」にあった。条例改正案は、こうした「香港DNA」に改造を迫るもので、一般市民も脅威を感じた。香港政府による「香港DNA」への無理解が、巨大デモと政治的社会的大混乱を招いたと言える。
普通選挙を求めた2014年「雨傘運動」の失敗を教訓
2019年香港デモが長期化したもう一つの要因は、2014年「雨傘運動」の失敗を民主派が教訓として生かしたことにある。
「雨傘運動」は普通選挙の実施を求めたもので、デモ参加者は79日間にわたって香港中心部を占拠した。これに対して、中国政府と香港政府は「妥協せず、流血せず」の長期化戦術を取った。長期戦の中で、平和的に民主化を求める「和理非」(和平・理性・非暴力の略)路線と、状況に応じて実力行使も辞さない「勇武」路線が内部分裂し、運動の弱体化と市民の反発を招いた。デモに対する市民の反発が強まる中、警察はデモを強制的に排除し、運動は幕を閉じた。
2019年香港デモでは、「雨傘運動」失敗の教訓が生かされた。「和理非」(非暴力派)と「勇武」(武闘派)は考え方や手法、人間性も大きく異なるが、両者は当初から少なくとも「お互いを批判しない」ことで一致、「兄弟爬山 各自努力」(兄弟で山登り、お互いに努力しましょう)を協調のスローガンとした。従来は、デモの過激化により市民の支持を失うことが多かったが、今回は両者の結束もあり、市民はデモの過激化ではなく「警察の暴力」を問題視した。
習近平政権における情報収集体制の麻痺
2019年香港デモの長期化の要因には、中国共産党内部における異常な忖度や隠蔽体質に加え、習近平独裁体制の構造的問題があった。
2019年香港デモの特徴は「Be water」といわれる。ブルース・リーが1970年代に、カンフーの極意を米国メディアへ説明した際に使った言葉で、「頭をカラにして自分の形をなくし、相手の出方に合わせて水のように融通無碍に動く」というものだ。デモの発案や議論は、ネット上の匿名の呼びかけで行われ、明確な組織やリーダーは存在しない。デモ当日の不測の事態には、各人が瞬時に判断し、「逃げる」ことを最重視する。捕まっては元も子もないからだ。
他方、中国共産党は習近平総書記を頂点とする巨大なピラミッド型組織である。香港政府はピラミッドの末端に位置しており、2019年香港デモのような事態に対し、独自に判断できない。香港政府の上位は中央人民政府駐香港特別行政区連絡弁室、その上位は国務院香港マカオ事務弁公室、その上位は政治局常務委員の韓正副総理がいる。しかし、韓正も自ら判断を下せない。最終的には習近平主席の決断が必要となる。この巨大組織は「Be water」のデモに全く対応できなかった。
習近平政権の構造的欠陥が顕著に現れたのは、2019年11月に実施された区議会選挙においてだ。区議会選挙では、過去最高(前回の2015年)の投票率47%を25ポイントも上回った(71.2%)。「香港の人々は政治に無関心」という通説からみて、驚くほど高い投票率であった。
結果は、民主派が85%の議席を獲得し大勝利した。香港の区議会選挙は小選挙区制のため、6割程度の票を取れば、地滑り的に議席を獲得できる。香港政府の不支持率は8割を超えていたため、世界の香港ウォッチャーは「民主派の勝利」を当然視していた。ビックデータによれば、選挙前夜には「投票率が7割を少し越える」ことも予見されていた。
ところが、中国政府はこの選挙結果を全く予想できていなかった。中国メディアは親中派勝利の予定稿を作成し、あとは数字を入れるだけであった。中国政府はあらゆる個人情報を収集し、ビックデータの最高度の技術を持っているが、情報収集体制は著しく麻痺していたのである。その背景には、習近平政権が推進してきた反腐敗運動がある。
香港情報を収集する担当者が賄賂を受け取るなど不正を犯せば、その上司も断罪される、このため、香港へ送られる情報官は香港にコネクションがなく、広東語もできない素人が用いられた。上司にとって、その方が安全だからだ。情報官は、反中国情報には接触しないように情報収集し、報告書は大公報や文匯報などプロパガンダ新聞ばかりを引用して作成された。中国共産党による偽情報をもとに作成された報告書は、上位への報告でさらに脚色され、「香港の人々はみな、デモの暴動に怒りを感じ、愛国心に燃えて政府を支持している」との報告が、習近平主席に伝えられた。それで、習近平主席は勝利を確信して区議会選挙を実施したのである。
米中新冷戦による米国の強力な後押し
香港のデモ参加者だけで、巨大な中国共産党政権に対抗することは不可能である。国際社会、とりわけ米国の後押しが頼りであった。米中新冷戦の進行はデモ参加者への強力な追い風となり、2019年香港デモが長期化した最大の要因であった。
1997年に香港が英国から中国へ返還されるにあたり、米国は「香港政策法」(香港返還を5年後に控えた1992年に施行)を制定した。同法は香港を中国本土とは別の関税区として扱うと規定、その前提条件として「香港に十分な自治が保証されている」ことを挙げていた。
しかし、2018年11月、米国議会の米中経済・安全保障審査委員会は、年次報告書の中で「一国二制度」への疑念を表明。2019年3月には米国政府が「香港政策法報告書」を発表し、それまで一貫して「香港には十分すぎる自治がある」としていたのを、「自治は減っているが、今のところ十分」へと変更した。米国内で香港の優遇措置を見直す可能性が浮上するや、香港財界や自由党(親中派)の立法会議員は直ちに警戒した。李克強総理は2018年12月、林鄭月娥行政長官に「香港が独立した関税であることは『容易ならぬもの』(香港が別地域になっていることは非常に重要)」と伝えた。
さらに2019年11月には、トランプ大統領の署名を経て「香港人権民主主義法」が成立した。同法は、①中国が「一国二制度」を守っているかどうか、国務省が毎年検証すること、②香港を中国本土とは異なる地域とみなして、関税やビザ発給などで優遇措置を与えている「香港政策法」の妥当性を毎年検証すること、③香港の自治や人権を侵害した人物に対し、米国への入国禁止や資産凍結などの制裁を課すこと、などが盛り込まれている。同法は中国政府が香港に直接介入する抑止力となり、デモ参加者には大きな励みとなった。
中国政府は、米中関係悪化と国際社会の反発を避けるため、できれば威嚇だけで事態を収拾させたいと考えてきた。香港デモを「テロ」と断定すれば、北京が直接介入せざるを得なくなるため、記者会見でも「テロの苗」や「テロの匂い」という表現が使われた。
妥協できないイデオロギー対立の先鋭化
このようにデモが巨大化長期化した要因は様々あるが、最も本質的な原因はデモ参加者と香港政府との妥協点を見出せないイデオロギー対立の先鋭化にあった。
「一国二制度」は、権威主義的政府と欧米型の自由な市民社会が共存するために考案されたものだ。イデオロギーが全く異なるため、政治と社会が安定するためには、双方による妥協が不可欠である。しかし、2019年香港デモでは、この相容れない二つの価値観が真っ向から衝突した。
古株の民主派連合組織・民間人権陣線は、平和的な合法デモ(「和理非」路線)の筆頭格で、毎年、香港返還記念日(7月1日)にデモを行っていた。彼らは200万人デモ(6月16日)で「五つの要求」を提示、①逃亡犯条例改正案の完全撤回、②警察と政府の、市民活動を「暴動」とする見解の撤回、③デモ参加者の逮捕・起訴の中止、④警察の暴力的制圧の責任追及と外部調査実施、⑤林鄭月娥行政長官の辞任、である。7月には、5番目の要求「行政長官の辞職」に「民主的選挙の実施」が加えられた。こうして、逃亡犯条例改定案をめぐる反対運動は、巨大デモ発生から1ヶ月を待たずに体制の民主化を求める運動へとエスカレートした。
「改正案の完全撤回」は2019年9月4日に実現したため、残りの要求を要約すれば、「デモ参加者を許し、警察を罰せよ、民主的選挙を実施せよ」となる。しかし、これは習近平政権には絶対に受け入れられない要求であった。習近平政権はもともと香港の「中国化」を意図し、妥協を認めない方針であったから、体制の危機が迫る中、国際社会の反発を無視して「香港国家安全維持法」制定へと踏み切ったのである。
立法会選挙勝利と中国本土への反政府運動拡散阻止へ
中国政府が「香港国家安全維持法」制定を強行したのは、香港で2020年9月に実施予定のされる立法会選挙を見据えたものである(※)。立法会選挙は、中国政府が苦汁を嘗めた2019年11月の区議会選挙とは政治的な重みが全く異なる。万一、民主派が立法会選挙で過半数を取れば、中国政府は香港議会をコントロールできなくなる。
同時に、香港での民主化の躍進を許せば、それが中国本土へ拡散する恐れもあった。2019年11月末に、広東省でデモが起こった。目的は火葬場や墓地の建設計画に対する抗議だったが、市民は香港デモと同じスローガン「時代革命」を叫んだ。中国本土で反政府的な動きを画策している人々は、香港の動きを注視している。2019年を通して中国政府は香港への直接介入を避けたが、2020年4月以降は、強硬路線へ舵を切った。立法会選挙の勝利と香港制圧に向けて、万全を期して「香港国家安全維持法」制定に乗り出したのである。
※林鄭月娥行政長官は2020年7月31日、立法会選挙の1年延期を発表した。
二、米中新冷戦の最前線としての「香港」
香港は「中国の銀行が呼吸する肺」
これまで香港は、非政治的な欧米型の法体系と安定した金融機能を有してきた。これは150年以上に及ぶ英国統治下で築かれたもので、1997年の中国返還後も、米国は「香港政策法」により関税やビザ発給などで優遇措置を与え制裁対象外としてきた。
経済規模だけをみれば、既に上海や深圳が香港を上回っている。2020年3月発表の世界金融センター指数によれば、香港は世界3位から6位に転落、上海は4位であった。しかし、上海が香港の機能を代替することはできない。香港には、これまで自由な情報の流通や公正な法制度などの環境が整っていた。上海や深圳では中央政府の介入が強いため、公平性を担保することができない。中国本土では自由な資本移動が認められていないが、香港には資本規制もない。これまで中国企業だけでなく政府系銀行も香港を重宝してきた。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、2019年9月11日付の記事で、香港を「中国の銀行が呼吸する肺」と表現した。いかに大男でも、肺が潰れたら死ぬしかない。香港が中国経済にとっていかに重要な役割を果たしているか、それを「肺」に例えたのである。
国際金融センターとして香港の地位を支えてきたのは「ドルペッグ制」である。一国二制度の香港には中央銀行がない。代わりに香港上海銀行(HSBC)、スタンダードチャーター銀行、中国銀行の都市銀行3行が香港ドルを発行。これら3行は香港ドルの発券規模以上の米ドルを購入し、香港金融管理局(事実上の中央銀行の役割)に預けている。香港金融管理局は外貨残高を調整する形で、ほぼ固定レートで香港ドルと米ドルを交換することを可能にしている。ドルペッグ制のゆえに、投資家や企業は米ドルを香港で為替損失なく安定的に運用することが可能となっている。
香港は金融だけでなく、情報、東南アジアの華僑人脈など世界的な人的ネットワークを有し、有形無形の資源を保有している。2018年のIPO(株式公開)による資金調達額で、香港証券取引所はニューヨーク証券取引所を超えて世界第1位であった。2019年9月の中国国家統計局長の報告では、海外から中国本土へ投資される資金の約70%が香港経由、中国本土から海外へ投資される資金の約60%が香港経由である。中国経済は今後も海外から多くの資金を必要としている。香港が中国経済にとって重要な戦略的都市であることに変わりはない。
香港をめぐる米中対立は、すでに活発化している。「香港国家安全維持法」が制定されたことにより、米国は香港に与えていた「特別な地位」をはく奪した。7月14日には、香港の自治の侵害に関わった中国政府の高官らに制裁を科す「香港自治法」が、トランプ大統領の署名により成立した。
さらに、米政権内では、香港ドルペッグ制弱体化についても検討されているという。具体的には、香港の銀行が購入できる米ドルに限度額を設けるというものだ。ドルペッグ制が見直されれば、為替リスクが上昇、香港で活動する金融機関の活動が制限され、香港の国際金融センターとしての地位は大きく揺らぐ。今や、香港は米中新冷戦における最前線となっている。香港をめぐる米中のこうした神経戦は、今後も継続するであろう。
「攻めの最前線」香港、「守りの最前線」台湾
2014年以来、台湾と香港の政治情勢は密接に連動している。台湾では同年3月に、中国とのサービス貿易協定に反対する「ひまわり運動」が起き、香港では同年9月に、普通選挙を求める「雨傘運動」が起きた。双方ともに現地政府を相手取った抵抗運動だったが、背後の巨大な中国政府を見すえていた点で共通していた。
2019年1月、習近平主席は「台湾同胞に告げる書」発表40周年記念大会で演説を行い、包括的な台湾政策を発表した。前国家主席の胡錦濤は中台関係について曖昧さを含んだ表現が多かったが、習近平主席は一つの中国の下、一国二制度による国家統一を明確にした。
これに対し、蔡英文総統は直ちに強烈に反論した。低迷著しかった支持率は急激に回復し、香港デモを追い風として2020年1月の総統選では地滑り的勝利を収めた。「今日の香港は明日の台湾」という言葉が象徴するように、台湾の人々の心はますます中国から遠ざかっている。中国が強調する一国二制度に対して、全く魅力を感じていない。香港と台湾の連帯は、かつてなく強まっている。
「中華民族の偉大な復興」を掲げる習近平政権にとって、台湾統一は最重要課題である。しかし、台湾の世論が中国の統治を受け入れる可能性はもはやない。台湾統一のためには軍事力行使しかなくなった。覇権をかけた米中新冷戦が激化する中、台湾と香港の戦略的立ち位置は、かつてなく重要になっている。米国からみれば「攻めの最前線」香港と「守りの最善線」台湾、中国からみれば「守りの最前線」香港と「攻めの最前線」台湾となっている。
三、今後のシナリオと日本の対応
消耗戦により米中双方の国力が低下する可能性
英国が香港返還と50年間の「一国二制度」で合意したのは、中国が経済発展すれば、いずれ民主化が進み、中国が香港化するとの希望的観測があったからだ。米国も同様の考えから、いわゆる「関与政策」を実施し、中国を支援し続けてきた。しかし、習近平政権になって独裁体制と世界の覇権を求める侵略的行動が強化され、ついに香港の「中国化」が始まった。COVID-19の世界への拡散も、中国共産党の隠蔽体質が大きな要因で、世界各国は少なからず反感を抱いている。
米中対立は、もはや貿易不均衡などの経済的対立ではなくなっている。世界の覇権と国家のアイデンティティーをかけた、妥協の余地のないイデオロギー対立こそ、米中新冷戦の本質である。米国では対中強硬路線は超党派的で、次期大統領選の結果に関わらず、米中新冷戦が激化することは避けられない。
今後は米中が消耗戦を繰り広げ、ともに国力を低下させるシナリオが濃厚である。世界の覇権を単独で確保することは両国とも困難となり、世界の平和と安定にとって、わが国の役割がこれまで以上に大きくなることが想定される。今後のわが国の対応について考えてみたい。
中国包囲網が進行し、インド太平洋構想の本格稼働へ
現在の状況は、1989年6月の天安門事件直後と似ていると言われる。当時、民主化運動を武力で弾圧した中国政府に対して、西側諸国は制裁を強化、中国は国際的に孤立した。同年7月フランスでG7サミットが開催されたが、日本は「中国を孤立化させることは、日本の国益に合わない。中国を孤立化させず、改革開放を推し進めれば、中国は民主化するはず」との考えから、中国包囲網には加わらなかった。日本はG7で孤立し、人権問題より経済的国益を優先したと見なされた。
今回も同様に、中国包囲網の形成と中国の孤立化が進行している。香港情勢は米中覇権争いに決定的影響を与える可能性がある。まず、中国全人代の発表を受けて、5月28日「ファイブ・アイズ」と呼ばれる英語圏の主要四カ国(米国・英国・カナダ・オーストラリア)が「香港国家安全維持法」制定の動きに反対する共同声明を発表、中国政府に強く抗議した。6月17日には、「香港国家安全維持法」制定の再考を求める「G7外相共同声明」が発表された。これはG7議長国の米国と、「G7声明をリードしたい」としていた安倍首相の共同作業と言えるものだ。「天安門事件の轍は踏まない」という、日本政府の強い覚悟の現れとも言える。
6月19日には欧州議会が、香港国家安全維持法の導入に対する非難決議を行い、国際司法裁判所に提訴、あわせて中国への制裁措置に踏み切るよう、欧州連合(EU)と加盟国に求めた。6月30日には国連人権理事会で、英国や日本、EUなど27カ国が参加し、「香港の自由が侵害されないよう促す」共同声明が発表された(米国は人権理事会を脱退しており不参加)。
ただし、国連人権理事会では「香港国家安全維持法」に賛成した国も多い(53か国)。中国と同じく独裁的もしくは権威主義的国家、イスラム過激派の反政府勢力を抱えている国々である。「一帯一路」で多額の資金援助を中国から得ている国々も賛成に回った。
こうした一連の動きとともに、わが国にとって重要なのはインドの動向である。これまで対中融和の可能性も残していたインドが、対中強硬路線に大きく舵を切ったことだ。これまで関係が必ずしも良くなかったオーストラリアと軍事協力関係を結ぶことに合意、「2+2」と呼ばれる外務大臣と防衛大臣の4者協議も軌道に乗せることになった。中印国境地帯では軍事衝突も起こっている。
わが国は、インド太平洋に進出しつつある中国を抑止するため、米国と共に日米豪印を主軸とする「インド太平洋構想」を基本戦略としている。これまでインドの曖昧な態度とインド・オーストラリア関係がネックとなっていたが、ようやく環境条件が整いつつある。「自由で開かれたインド太平洋」の具体的実現に向けて、海洋国家相互の多国間協力を強力に推進すべきである。
米国・台湾とのさらなる連携強化とロシア外交の再開を
習近平政権の情報体制は危機的に麻痺している。2019年11月区議会選挙で親中派が大敗した後も、2020年1月の台湾総統選挙で親中派候補(韓国瑜)が大敗した。COVID-19発生時では中央政府の初動対応が致命的に遅れた。習近平政権がトランプ政権や国際社会の動向、香港情勢などを読み誤る可能性は高い。
元来、権力争いが熾烈な中国では「外交は内政の延長」の傾向が強い。特に習近平主席はコロナ禍対策(内政)における失点が大きく、国内を掌握するために国際社会の動向にほとんど耳を傾けない可能性が高い。習近平政権は、今後ますます孤立化と暴走へ向かうことが予想され、中国はわが国にとって、正に最大の現実的脅威となっている。
このような状況下では対中経済関係の再構築を行うべきであるが、米ソ冷戦時代とは異なり、中国は経済面で、日米にとって最大の相手国である。共産党独裁のもとで恣意的な規制が行われている特殊な環境下でも、多くの日本や米国の企業が中国に工場を有して生産活動を行っている。中国との経済関係を断つのは容易ではないが、諸政策を動員して対中依存度を下げるべきであり、特に安全保障に関わる分野では徹底的に規制すべきである。
わが国は、コロナ禍への対策では中国とも協力する必要がある。しかし、自由・人権・民主主義といった普遍的価値に関わることには、断固とした立場を貫くべきである。また、米中対立が深まり、軍事衝突の可能性も懸念されているが、一旦軍事衝突があった場合には、わが国は同盟国である米国に付くことを明確にしておく必要がある。仮に米国が敗退すれば、尖閣はもちろん、沖縄も中国の支配下に入ることになる。中国が領有権を主張している南シナ海も同様である。
アジア太平洋における米中の軍事バランスは、中国に有利との分析もあるが、これは日本を見落とした見方だ。憲法9条の解釈変更により、限定的ではあるが、わが国は集団的自衛権の発動が可能となった。日米が軍事面で一体となって、対中抑止に当たれば中国は手を出せない。それによって軍事衝突の危険性もかえって低くなる。日本の立場を明確にした上で、場合によっては米中の仲介役を務めることも考えるべきである。
既に述べたように、米中新冷戦が激化する中、台湾と香港の戦略的立ち位置が、かつてなく重要になっている。わが国としては、台湾との関係をこれまで以上に重視する必要がある。わが国は従来一貫して、台湾のWHO加盟を支持してきたが、これを具体的に進める手立てを考えることも必要である。また、自由と民主主義の価値を共有する台湾をTPPの一員として参加させることも検討すべきであろう。台湾の地政学的位置や台湾のもつ経済的重要性に鑑みて、日本が台湾加盟に主導的役割を果たすことを考慮すべきである。
最後に、わが国はロシア外交を再開すべきであろう。原油安とコロナ禍で、プーチンの支持率は2020年4月・5月に就任以来最低(59%)を記録した。コロナ禍でも中露蜜月をアピールしているが、プーチン政権の対中不満は大きい。これまで安倍政権が積み上げた対ロシア外交を再開して、ロシアとの関係を改善し、中露分断を仕掛けることができれば大きな成果といえる。
■参考文献
倉田徹・倉田明子編『香港危機の深層』(東京外国語大学出版会、2019年)
平和政策研究所「香港問題の背景と行方—米中対立を踏まえて—」
Pew Research Center,“U.S. Views of China Increasingly Negative Amid Coronavirus Outbreak”
WEDGE Infinity「コロナの裏で進められる中国の香港支配」
LIMO「香港市場の優位性が変わらない理由。中国にとって金融面でどう重要なのか?」
梅原直樹「一国二制度における香港の評価」
中西輝政「米英仏独が築く『包囲網』で習近平の『覇権の夢』は潰える」