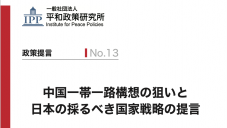Ⅰ.はじめに:広域経済圏の形成をめぐる主導権争い
現在、世界は広域経済圏をめぐる主導権争いが熾烈化しつつある。2010年3月、環太平洋経済連携協定(Trans-Pacific Partnership:TPP)の交渉が8か国で開始された。経済的な影響力を増しつつある中国を警戒するアメリカは、TPPを基礎にアジア太平洋自由貿易圏(Free Trade Area of the Asia-Pacific:FTAAP)を実現するというシナリオを描くようになっていく。「中国のような国にグローバル経済のルールを書かせることはできない。我々がルールを書くべきだ」とのオバマ大統領の声明からも伺えるように、より貿易自由度の高い広域経済圏をアメリカのイニシアティブの下に立ち上げようと動いたのである。これに対し、TPP構想に込められた意図を見抜いた中国は、TPPと切り離した形で自らに有利なFTAAPを実現するため、東アジア地域包括経済連携協定(Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP)を軸に交渉を進めるようになった。
その後、TPP交渉は2015年10月のアトランタでの閣僚会合で実質合意が成立し、2016年2月にニュージーランドで協定書の署名式が行われた。しかし、アメリカの政権がオバマからトランプに代わるや、トランプ大統領はTPPからの離脱を表明した(2017年1月)。そのため、以後は日本が中心となって、将来のアメリカの復帰も視野に収めながら、アメリカ以外の国々との間での新たなTPP(TPP11)の発効をめざし、今年2018年1月には新協定の締結で合意した。
この間、中国の習近平政権はアジア太平洋経済圏にとどまらず、中央アジア、南アジア、中東からヨーロッパ、さらにアフリカに至る東半球の全てを包み込む「一帯一路構想(シルクロード経済圏構想)」を推し進めるようになった。また同構想を実現に導くための手段として、アジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank:AIIB)という新たな国際金融機関を創設した。一帯一路構想やAIIBをめぐる動向は、ユーラシア~アジア太平洋地域における広域経済圏のあり方を左右するだけでなく、世界経済の今後の動向にも極めて大きな影響を与えることは必至である。さらには、21世紀における世界経済の秩序やルールを誰が中心となって構築し、また誰がそこから最大の利益を得ることになるのかを決する大問題でもある。
日本はTPP11実現の推進役を担っているが、アメリカがTPPから去ったことで、参加国の国内総生産(GDP)の合計が世界に占める割合が38%から13%に低下するなどTPPの生み出す経済効果が減少したこと、他方、中国の掲げる一帯一路構想の規模の雄大さに幻惑され、より大きな経済効果を期待して、わが国も一帯一路構想に参加し、AIIBの運営に関わるべきであると説く声も聞かれる。果たしてそのような論説に耳を傾け、TPPを基軸としたアジア太平洋広域経済圏の創設を主導するだけでなく、さらに中国が進める一帯一路構想にも積極的に参画し、AIIBという新たな国際経済機関の運営に深く関与することが日本にとって好ましい選択となるのであろうか。この問題を考えるには、中国がなぜいま一帯一路構想を打ち出し、AIIBの創設に踏み切ったのか、その意図や背景を詳らかにする必要がある。それは中国経済の現状や抱える問題とも深く関わっている。そこで、まず一帯一路構想を概観したうえで、大きな曲がり角を迎えた中国経済の実態を眺めてみたい。
Ⅱ.一帯一路構想とは
(1)陸と海:二つのシルクロード
中国の資本で諸外国のインフラ整備を進めようという一帯一路構想の起源は、1990年代に中国国内の辺境地域の産業振興政策として始まった。新疆ウィグル自治区や雲南省などで、国境に向かう交通路や産業道路を建設し、中央アジア諸国やパキスタン、ラオス、ミャンマーなどとの交易を活発化させようとする計画だった。その後、胡錦涛政権下の2009年には、重慶とドイツのデュースブルクを結ぶ渝新欧鉄道の敷設工事に着工(2011年開業)、またカザフスタン(06年)やトルクメニスタン(09年)など中央アジアと中国を結ぶ天然ガスパイプラインの建設も始まった。
しかし、「一帯一路」の名称が登場したのは、習近平政権に入ってからのことである。即ち、2013年9月、カザフスタンを訪問した際に習近平国家主席は「シルクロード経済ベルト」(一帯)構想を発表し、中国政府として初めて、アジア、ロシア、それにヨーロッパを繋ぎユーラシア大陸を貫く経済ベルトを構築するという大構想を打ちあげた。この構想は、古代におけるシルクロードの存在とその歴史的意義を巧みに取り込み、その現代的発展のプロジェクトとして、中国西部と中央アジア諸国、さらにヨーロッパを鉄道、道路、航空、通信、送電網、エネルギーパイプラインなどで結び、大規模なインフラ整備を進めようというものである。
続いて同年10月、インドネシア国会での演説において習主席は、中国沿岸部から東南アジア、インド洋を経てアフリカ、中東、ヨーロッパと繋がる「21世紀海上シルクロード」(一路)構想を明らかにした。習近平は、「東南アジア地域は昔から海のシルクロードの重要な中枢だった。中国はASEAN諸国と海上での協力を強化し、中国政府が設立した中国ASEAN海上協力基金を活用して、海洋協力のパートナーシップを発展させ、相互補完を図り、ASEAN諸国とチャンスを共有し、ともに挑戦し、共同の発展、繁栄を実現することを願っている」と述べたが、21世紀海上シルクロードとは、15世紀初め、明の永楽帝の時代に、東南アジアを経由してインド洋、アフリカまで大遠征を行った鄭和の艦隊が辿った海路の現代版といえる。
そして2014年11月に北京で開催されたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議で、習近平はこれらの構想を広く世界各国にアピールし、以後、陸海二つの構想は併せて「一帯一路(one belt, one road)」構想と呼ばれるようになった(1)。そのカバーエリアとルートは、陸のシルクロードである「一帯」では、中国(陝西省の西安)から
①中央アジア~パキスタン~イラン~トルコを経て地中海沿岸地域(南ヨーロッパ)
②中央アジア~ロシアを経てバルト海沿岸地域(北ヨーロッパ)
③東南アジア~南アジア~インド洋
に至る3ルートが想定されている。中央アジアからロシアに伸びる②のルートは、古代のシルクロードとは無縁だが、ロシアのプーチン大統領が主導して中央アジア諸国と立ち上げた「ユーラシア経済連合」や、やはりプーチンが上海協力機構の枠組みを基にした「大ユーラシア経済パートナーシップ」構想を打ち出したことを考慮し、中露の連帯感を誇示する目的で付加されたものである。このルートに添って中国と他の地域を結ぶ高速鉄道などの大規模プロジェクトが既に動き始めており、江蘇省連雲港市を出発点として新疆、カザフスタン、ロシアを経由してアムステルダムまでを鉄道で繋ぐ新ユーラシアランドブリッジ計画が進められている。このほか、シンガポールに繋がる経済回廊、バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー経済回廊(BCIM)など基幹ルート形成に向けた動きも活発化している。
一方、海のシルクロードである「一路」は、中国沿海部(福建省福州)から
①南シナ海~インド洋を経てアラビア海~アフリカ(ケニア)、さらに紅海を北上してスエズ運河から地中海に出てギリシャ、さらにマルコポーロの生地ベニス(陸路と結合)
②南シナ海~オセアニア~フィジーなど南太平洋の島嶼諸国
に繋がる2ルートが想定されている。②の南太平洋ルートは、当初の構想にはなかったが、後になって突然付加されたものである。
一帯一路構想の対象地域は、アジアのみならずヨーロッパ、アフリカ大陸にまで伸びており、構想に含まれる国の数は優に70か国を超えている。大西洋を除いた地球のほぼ全域に広がる一帯一路の構想は、中国経済をさらなる成長へと導くとともに、中国主導によるインフラ整備で途上国の経済発展と近代化を促し、相互の友好信頼と共存共栄、ウィンウィンの関係を構築するものと中国政府は盛んに喧伝を繰り返している。
(2)アジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立
一帯一路構想に基づくインフラ整備のための資金面の受け皿作りとして創設されたのが、シルクロード基金(SRIF)やアジアインフラ投資銀行(AIIB)である。SRIFは、中国単独で400億ドルを出資して2014年末に設立されたものだが、AIIBは参加国を募って各国から資本を集め、その信用力でインフラ建設プロジェクトの起債を行い、資金を調達する制度である。一帯一路構想を成功させるには、中国が主導権を取れる資金供給システムが必要となる。だが、後述するように近年の中国の経済状況は芳しいものではなく、中国一国だけで長期的なリスクを背負う危険も大きい。そこで、巨大なインフラ整備を担当するための国際機関を設立することになったのである。AIIBの資本金は1000億ドルで、中国がその半額を出資することとされた。
2014年10月、AIIB設立の覚書調印式が行われた時、参加を表明したのは、ベトナム、シンガポール、タイ、ミャンマー、モンゴルなど21か国にとどまった。ところが15年に入って、ニュージーランドやサウジアラビアなど一部の先進国や中東の富裕国が参加を決めた。さらに同年3月、局面は大きく変わった。アメリカの同盟国イギリスが突如AIIBへの参加を決めたのだ。親中派のオズボーン英財務省の取り込みに中国が成功したためである。このイギリスの動きを受けて、ドイツ、フランス、イタリア、スイスなどのヨーロッパ勢が雪崩を打ったように相次いで参加を決定、しかもアメリカが参加しないよう強く要請していた韓国とインドネシア、オーストラリア、それに台湾も参加を表明。最終的な創設メンバーは57か国(台湾を含めると58か国・地域)に膨れあがった。2015年6月、AIIB協定にその57か国が調印し、同年末に発足した。本部は北京に置かれ、初代総裁には財務部副部長(副大臣)の金立群が就任した。現時点でのAIIB参加国は80か国・地域に上る。主要国の中でAIIBへの参加を見送ったのは、日本とアメリカのみである。
このほか、やはり中国のイニシアティブで、BRICS5か国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の共同出資による発展途上国向けの新開発銀行が2015年7月、上海に設立された。こちらもAIIBと同様に、外貨準備全体の5割のシェアを中国が持っている。
Ⅲ.行き詰まりを見せる中国経済
一帯一路構想の雄大さは、経済大国となった中国の強大さを象徴するものと一般には思われている。しかし、その構想のあまりの巨大さは、実は中国経済の脆弱性の大きさの反映でもある。これほど広大なインフラ投資の市場をなかば独占的に獲得しない限り、現在の中国は行き詰まりをみせる経済的苦境から抜け出すことが困難な状況に追い込まれているからだ。
(1)高度経済成長の終焉
鄧小平の主導の下、1970年代末から始まった改革開放路線によって、中国は目覚ましい経済成長を遂げた。特に2001年に世界貿易機関(WTO)加盟を果たした以後、工業化と輸出拡大のスピードに拍車がかかり、中国は年率10%を超える経済成長を続けた。IMFの統計によれば、中国の名目GDPは、2000年に1兆1928億ドルであったものが、2005年にフランス、2006年にイギリスを、次いで2007年にはドイツを抜いた。その翌年、アメリカに端を発したリーマンショックの影響を受けるが、それも克服し、遂に2009年には日本を抜き、世界第2位の経済大国に浮上した。しかも、その5年後の2014年には中国のGDPは10兆4000 億ドルに達し、わずか4年で日本のGDPの2.2倍、アメリカのGDP17.3兆ドルの60%に迫るほどの急速な成長ぶりであった。
しかし、過去20年にわたり年率2桁を記録した中国の経済成長率は2011年を境に徐々に鈍化し始め、2015年の成長率は対前年比6.9%にまで落ち込んでしまった。実態ベースでは、5%以下に留まっているとの見方も強い。高度経済成長の時代が終焉し、中国経済は低成長という新たな時代へと大きな転換期を迎えたのである。経済成長の鈍化によって、中国がこれまでのような高い成長率を維持することはもはや望め得なくなった。こうした変化を受けて、2013年に発足した習近平政権は、中国経済の状況を「新常態(ニューノーマル)」と名付け、低成長下における新たな経済政策の在り方を模索している。
なぜ、中国経済は停滞に陥ったのか。その理由は大きく ①輸出依存モデルの崩壊、②過剰生産能力や非効率な国有企業の存在、それに③経済格差の拡大という三つの要因から説明することができる。
(2)過度な輸出依存政策の限界
これまでの中国の目覚ましい経済発展は、輸出の著しい増加に負うところが大きかった。2003年から07年まで、中国の輸出は毎年25%以上のスピードで増加し、35%を記録する年もあった。一国の経済の輸出貿易に対する依存度は、対外貿易依存度(対外貿易係数)で判断できるが、改革開放路線が緒に就いたばかりの1985年当時、中国の対外貿易依存度は22.8%に過ぎなかった。それがWTOに加盟した2001年には38.5%となった。その後も右肩上がりで上昇を続け、2006年には67%にまで上昇した。バブル景気が終結した1991年当時の日本の貿易依存度は15.3%であったから、如何に中国経済の繁栄が輸出貿易に大きく依存しているかを窺い知ることができよう。中国の主力輸出品であった紡績、衣料、玩具などが世界市場に占めるシェアは40~60%を占め、中国は「世界の工場」と呼ばれるようになった。
中国が「世界の工場」になれたのは、コスト面での比較優位を実現できたからである。中国の土地と労働力のコストが低く、また外国資本に対して優遇政策を実施していたことも効果を高めた。さらに中国政府は環境保護に配慮しないため、各企業は環境保護コストを支払う必要もなかった。こうしたコスト面での優位性によって、中国は途上国の中では最大の外資導入国となり得た。そして、外国資本主体の生産力拡大と安価な商品の輸出攻勢によって、瞬く間に経済大国の座を獲得したのである。
だが、中国製品の安全性や製品の劣悪性が問題視されるようになると、世界の市場から中国製品はボイコットを受けるようになった。また2004年頃から上海などの沿海地域、中西部の企業で十分な労働力の確保が難しくなり(民工荒)、それに伴って人件費が高騰し、コスト面の優位性が次第に失われていった。2007年に新たな労働契約法が公布され、各地で賃上げブームが出現、特に外資が集中する広東省の広州、深川などでは最低賃金基準の見直しで労働者の賃金が20%も上昇した。そのうえ中国の輸出加工業の重点地域である、珠江デルタ地域の土地価格も高騰した。人件費や土地代の上昇に加え、2008年からは新たな企業所得税法が施行、外資への優遇税制措置が撤廃され、外資と国内企業の税率が同一化された。外資系企業が中国で業務認可を受けるには、役人や共産党幹部への付け届けや賄賂が必要不可欠になる。こうした不法、不透明なビジネス慣行も中国に進出した外国企業の経営コストを高めることになる。コスト面の比較優位が崩れたことで、多くの外国企業は中国よりも生産コストの安い東南アジア地域などに工場を移転させるようになった。
(3)過剰在庫・過剰生産と非効率な国有企業の存在
中国経済の成長が鈍化した第二の理由は、経済効率の悪い国有企業が大量の過剰在庫、過剰設備を抱えていることにある。中国の経済統計は、政治的な意図から改ざんが日常茶飯事であり信用できないことは周知の事実であるが、例えば最近の統計を見ると、鉄道貨物の輸送量が大幅に落ち込んでいるのに、中国の実質経済成長率はそれほど急落しておらず、両者の指数の間に不自然な乖離が生じている。これは、操作によってGDPの水増しが図られたり、過剰在庫が増大している実態を物語っている。
現在、中国には、中央政府が管轄する中央国有企業が100あまり存在する。また地方政府が管轄する地方国有企業は10万社を超えている。しかし国有企業には資本主義経済のメカニズムが機能しないため、その多くは、存続はしているものの慢性的な赤字や莫大な不良債務を抱えたいわゆるゾンビ企業である。経済効率が悪いからと閉鎖すれば、大量の失業者を生みだすことになる。だが、共産党が支配する企業から失業者が生まれるということは、党の面子や社会主義の正当性を潰してしまう。かといって閉鎖しなければ、中央や地方政府の財政を圧迫し続け、経済の回復が遠のくばかりだ。政府は、業界の効率的再編、省力化を目指して国有企業の合併を進めているが、内部の抵抗に遭い難航、また合併による大型化が逆に生産効率のさらなる低下を招いているとの指摘もある。ゾンビ化している国有企業の存在は、中国の内政にとって最も頭の痛い問題の一つになっている。
しかも、上命下達の共産党一党独裁の体制が、問題の本質的解決を一層困難にする。党の上からの指令は絶対であり、その指令は経済的な観点よりも、中央政府が掲げた経済成長率の達成が至上命題とされる。そのためモノを作れば生産高が売上高として評価されるので、作れば作るほど幹部の評価も上がることになる。つまり、既に低成長の時代に入ったにもかかわらず、ノルマの達成や生産力の拡大が企業幹部の出世、人事評価に直結するシステムのため、近視眼的な発想でとにかく生産増に取り組んでしまう。それゆえ国有企業では、慢性的に過剰な商品在庫や生産設備を抱え込むことになる。
さらに2008年9月のリーマンショックで、中国経済も大きな打撃を蒙った。この経済不況を克服するため、中国は4兆元に上る巨額の緊急経済対策(大規模公共事業計画)や大胆な金融緩和政策を発動した。この時、国有企業で構成される基幹産業も、設備投資を大幅に増強した。その結果、鉄鋼や電力、セメント、石油化学、アルミなどの業種がさらなる過剰在庫を抱えてしまった。その中でも特に深刻なのが、鉄鋼産業である。
中国の鉄鋼生産能力は12億トンで、世界の約半分を占める。そのうち日本の鉄鋼生産の3倍にあたる3億トンの生産能力が余剰と言われる。内需が伸び悩む中で、中国の鉄鋼メーカーは輸出に活路を求め、15年の中国の鋼材輸出は初めて1億トンを超え、日本の粗鋼生産を上回った。しかし中国の鉄鋼メーカーが国内で売りさばけなかった鋼材を安値で大量に輸出するため、海外での鋼材の相場が下がり、日本や欧米の鉄鋼メーカーの収益を圧迫している。このため、2016年6月の米中戦略経済対話でアメリカがこの問題を取り上げ、中国側に強い懸念を示した。中国政府は、過剰生産能力の解消について、鉄鋼と石炭の2業種を重点に指定した。特に鉄鋼では、粗鋼生産能力を1億~1億5000万トンと、日本の粗鋼生産を上回る規模で削減する方針を示したが、鉄鋼と石炭の2業種の過剰生産能力の削減によって、合計180万人の失業者が見込まれるため、雇用の確保を重視する国有企業や地方政府の幹部は、合理化施策に抵抗を続けている。
過剰生産の問題は国有企業だけでなく、地方政府でも生じている。地方政府も経済成長を牽引するため、これまで不動産開発やインフラ整備に全力を挙げてきた。しかもリーマンショック後の経済の落ち込みを防ぐため、さらに拍車をかけて地下鉄、道路などのインフラ建設やマンション、住宅などの不動産建設にのめりこんでいった。銀行による不動産関連融資の残高は、2013年末で約15兆元(280兆円)に上る。ノンバンクなどが高利回りの理財商品として広く一般の預金者や投資家から資金を集め、地方政府系の不動産開発業者に融資するシャドーバンキングからも銀行の倍近い資金が不動産関連事業に流れていった。2013年末のシャドーバンキングの規模を、日本銀行は35兆元(GDPの約6割)と推計している。
莫大な資金を投入した住宅建設事業は、一時的には投資主導の成長を生み、所得の増加を実現し、住宅需要も増加した。いわゆる住宅バブルの発生である。中国では、海外投資の機会が限られているため投資対象が少なく、膨大な貯蓄が不動産に集中する(投機する)傾向が強い。不動産相場が急上昇すると、海外からの投機資金も流入する。銀行はそれを吸い上げ、人民元資金を大量に供給したため、国内総生産に占める固定資産投資の比率は50%を突破。固定資産投資が前年比20%増えれば、GDPを10%程度押し上げるので、中国はこうした不動産・インフラ投資の手法でリーマンショックを乗り越え、再び中国経済を二桁の高度成長に復帰させたのである。
しかしその後、住宅購入に規制がかけられ、不動産市場は一転して供給過剰に陥ってしまった。現在、鬼城と呼ばれるゴーストタウンが中国各地に出現している。地方政府の歳入は激減し、債務は膨張した。また銀行の抱える不良債権の総額は既に20兆元を越え、中国のGDPの30%に達しかねない。近い将来、不動産バブルがはじければ、中国経済が大打撃を蒙ることは必定である。そのうえ無秩序な乱開発が続いたことで国土は荒れ放題となり、大気汚染は住民の生命を危険に晒す程の危機的状況に陥っており、水汚染問題も深刻化している。
(4)広まる経済格差と格差の固定化
中国は世界でも格差が著しく大きな社会になってしまった。しかも、経済成長とともに格差は縮小するどころか、拡大する傾向にある。中国におけるジニ係数の変化をみると、1988年に38.2%だったものが1995年には45.2%と高まり、この国の不平等化、格差の拡大が進行していることがわかる。中国の格差は、都市と農村のほか、経済発展の著しい東部沿海地区と中西部内陸の間の格差、職業の違いによる格差、さらに同じ都市の住民の間の格差など、多岐にわたる。
このうち、豊かになった沿海部の諸都市と開発の遅れた農村間の格差の拡大が問題であることはかねてから指摘されている。例えば2015年の都市住民の平均可処分所得は3万1195元だったのに対し、農村住民の平均可処分所得は1万1422元だった。この数字で見ると、都市と農村の収入格差は2.73倍となるが、社会保障制度の普及状況なども加味すれば、実質的な都市と農村の所得格差は5倍から6倍に広がっている。農村と都市の格差を産んだ背景には、都市と農村を切り離す中国の戸籍制度の問題が横たわっている。
豊かになった沿海部と内陸の間でも格差は大きい。2015年の統計で、東部地域の1人当たりの平均可処分所得は2万8223元であったが、中部地域は1万8442元と東部の65%にとどまっている。西部地域は1万6868元で、東部の60%だった。地域格差を是正していくためには、産業の発展が遅れた地域で新たな企業を誘致するためのインフラ整備が欠かせない。そのためには資金が必要で、例えば日本の地方交付税のような財政移転措置が考えられる。だが、中国ではこのような財政資金の再配分機能が十分働いておらず、地方政府は、慢性的な資金不足に悩まされている。それで自らで資金を獲得するため、地方政府は土地の売却収入に頼ることになる。不動産バブルを生み出したのはそのためである。さらに近年では都市内部の格差も著しい広がりを見せている。都市では、高級官僚や共産党幹部など既存の支配層に加えて、投資家や私営企業の経営者、高級技術者などニューリッチと呼ばれる階層が台頭し上流階級を形成する一方で、失業者、流入農民、「低端人口」と呼ばれる下層階級が膨張し、都市の二極分化が進行しているからである。
そのうえ格差の固定化も進んでいる。中国経済が低成長の時代に入ったことに伴い、発展から取り残された農村に住む農民や都市部の単純労働者は、もはや豊かな生活を得ることができない。彼ら「貧二代」と、企業経営で莫大な富を得た家族(「富二代」)、あるいは特権を背景に子弟を海外留学させ海外資産を膨らませている政府高官や共産党幹部たち(「官二代」)との不平等、格差は広がるばかりである。改革開放路線を進めた鄧小平はかって「条件のあるところが先に豊かになる」という「先富論」を提唱したが、これは「先に豊かになったところが、遅れているところを助けて共に豊かになる」という「共同富裕論」と一体になっていた。しかし、「先富論」は実現したが「共同富裕論」実現の見込みが立たないのが現在の中国の実情である。
生活水準の向上によって、中国でも国民の権利意識が高まりを見せている。社会主義を掲げる国でありながら、「機会の不平等」が広く社会に存在し、しかも益々格差が広がっていくこの国の社会構造に不満を持ち、国民大衆の間では無力感や共産党への批判が強まっている。2015年以降、黒竜江省の双鴨山炭鉱の労働者をはじめ、全国各地の国有企業の労働者が大規模な抗議行動を展開している。環境汚染の工場建設に反対する住民運動が増え、建設が中止に追い込まれる事態も多発している。格差の拡大は、中国共産党支配の根幹を揺るがしかねない大問題になっている。
(5)経済の苦境を克服できない社会構造:共産党独裁の矛盾と限界
中国が採ってきた海外からの投資と輸出主導に頼る成長モデルは、今や完全に行き詰まっている。生産コストの上昇が起きても輸出を増加させるには、これまでのような安価低質な商品から、高価でも付加価値の高い商品へと輸出主力品を改めなければならない。しかし、日米など先進国の技術の模倣に依拠してきた中国では、独自技術の発展が遅れている。中国でも新しい産業の萌芽はあるが、資金の多くは赤字体質の国有企業救済に使われるため、新産業の発展や研究開発に投入できないでいる。経済の自由化を進め、基幹産業は民営企業に開放すべきだが、逆に国有企業が民営企業を買収する「国進民退」がいまも続いている。
外需に頼らず、国民の生活水準の上昇を活かして消費を中心とした内需主導型の成長モデルに移行させることも急務だが、この国では外需から内需主導経済への転換も難しい。格差の拡大による中流層の薄さが内需を拡大させないからである。中国のGDPに占める家計消費の割合は35%強に過ぎず、日欧の約6割、アメリカの約7割と比べて圧倒的に低い。家計消費を挙げるには大幅な賃上げが不可欠だが、人件費の高騰は中国の国際競争力をさらに低下させる要因になる。地方政府が主導してきた地下鉄建設などの公共事業や不動産投資に代わる内需拡大の牽引役がこの国では見当たらないのだ。
一人っ子政策の影響で、15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口(労働力人口)が減少し始めたことも減速の要因として挙げられる。各国の生産年齢人口の増減率推移データを見ると、その増減が経済の盛衰とリンクしており、非常に高かった中国経済の成長率が低下したのも、生産年齢人口の増加率が急速にゼロに近づいているためと考えれば納得できる。中国はこれから生産年齢人口のマイナスが長期間にわたって続く。しかも、高齢化社会の到来が目前に迫っており、社会保障制度が不十分な現状などを考えると、経済成長率は今後さらに低下するものと予想される。
一時は国家資本主義ともてはやされた中国共産党独裁の経済運営は、共産党にすべての資源(リソース)を集中させるのに都合がよく、短期間に高度成長を達成するとともに、巨万の富を手にする大富豪を多数誕生させた。だがその一方で腐敗の蔓延をもたらし、数億の困窮者を生みだしたばかりでなく、経済の民主化や自由化への途を閉ざしている。それは、共産党独裁体制下の中国では、共産党幹部など一部特権階級が自らの既得権益を放棄しようとしないからである(2)。習近平が如何に反腐敗キャンペーンを大々的に展開しても、党幹部や政府の高官らは、不作為に徹してその場をやり過ごそうとするだけで、面従腹背の消極的抵抗は抜本的な改革を阻害する。民主政を採らず、下からではなく上からの改革しか実施することの出来ない国家の宿命である。党中央も、経済の自由化を認めると社会主義体制を維持できなくなることを恐れ、思い切った経済の自由化に着手しようとしない。民主化・政治改革の遅れが、産業構造の転換を阻んでいるのだ。
それどころか、毛沢東の時代を凌ぐほど習近平への権力集中が顕著である。一昔前の韓国や台湾も、中所得の段階までは権威主義や党、軍部の独裁体制を維持していた。しかし1980年代後半、民主主義体制への転換を図ったことで、高所得の段階へと上昇することに成功した。こうした過去の史例に鑑みれば、中国が共産党の一党独裁という政治制度を続け、しかも習近平による独裁集権化を強めていくならば、自由主義的な経済システムの導入は一層困難となり、「中所得の罠」から抜き出すことは難しい。詰まるところ、共産党独裁の社会主義体制を維持し続ける限り、この国がアメリカを抜いて真に世界最大の経済大国になることは到底不可能だということである。経済発展を持続させることが出来なければ、共産党への不満を抑え、民意を安定させることもかなわない。社会主義を維持したまま、独裁体制が抱えるこうした矛盾や限界を解消するには、国の外に活路を見出し、対外膨張的な経済政策を打ち出す以外に途は見出せない。それが、一帯一路構想である。
Ⅳ.一帯一路の実相
(1)国内矛盾解消の施策
「新常態」なる低成長の時代に入った中国は、2015年以降の実質経済成長率目標を7%とし、それまでの7.5~8%から下方に修正した。中国は2013年に国家目標として2020年までに中国人の所得とGDPを2010年比で2倍にすると公約している。この7%という数字も、その公約を実現する前提で逆算された数値に過ぎず、達成の目算が立っているわけではない。また成長率7%といえば一般の国であれば高度成長の水準とみなせるが、膨大な人口と広大な低開発地域を抱える中国の場合、これまで「保八政策」が叫ばれていたように、8%を割り込んだ成長率では国民全体の生活水準を浮揚させることは難しい。そこで、広大な海外市場に目を向けさせて国民に夢を与え続ける政策として登場したのが、一帯一路の構想である。
中国はこの構想を「中国版マーシャルプラン」と自画自賛しているが、この構想の真の狙いは、途上国支援やウィンウィンの経済関係の構築にあるのではない。一帯一路の本質は、中国経済の克服し得ない問題を解決するためのプロジェクトという点にあり、国内過剰設備の軽減や過剰在庫の一掃、中国人労働者の雇用確保に主たる目的がある。また中西部の発展を促し、沿海部と中西部の経済格差を解消するという中国国内の地域振興の狙いも一帯一路構想には込められている。
さらに、インフラ整備や武器輸出、独裁政権との関係強化によって、石油やレアアースなど中国の経済成長に不可欠な海外資源を安定的に確保することも重要な目的になっている。陸のシルクロード構想の場合は、陸路やパイプラインによるエネルギー・天然資源の供給が可能になるため、インド洋や南シナ海で米海軍の影響を受ける心配がなくなることが中国にとって大きな意味を持つのである。
(2)覇権主義外交の手段
中国は、フィリピンやベトナムと争っている南シナ海の領有権問題を巡ってASEANで討議がなされる際、会議の開催国や中国寄りのカンボジア、ラオスなどに莫大な経済援助やインフラ整備のための融資を行うことでASEAN内部の論議を分裂させ、中国非難の声明や行動規範の採択が出されることを阻もうと図っている。敵対するフィリピンやベトナムに対しても、多大な経済援助の提供によって自らの側に取り込もうと画策を続けている。このように中国は、自らの経済力を自国の外交・安全保障政策の利益実現のための直截的な手段として活用することが常である。一帯一路構想の場合も、経済的利益の獲得に留まらず、政治・軍事的な影響力を拡大するための手段にこの構想が利用される可能性が極めて高い。
そもそも「一帯」にあたるシルクロード経済ベルト上には、軍事施設が多い。また中国内陸部の蘭州、西寧は新疆ウィグルに近く、成都はチベットに近い。いずれも少数民族との紛争を抱える中国にとって、国内治安を維持するうえで重要な拠点である。「一路」にあたる海上シルクロードのルート上にも、上海、寧波、広州、深川、湛江など中国の軍事施設や軍港が多数含まれている。国内だけでなく、今後ルートに添って中国がインフラ整備を進めていく過程で、途上国に自らの軍事拠点や基地を併設することが予想される。
一帯一路構想の重要な事業として中国が最も建設を急いでいるプロジェクトに中国・パキスタン経済回廊(CPEC)がある。これは、総工費450億ドルを投じて、中国の新疆ウィグル自治区のカシュガルからアラビア海に面したパキスタンのグワダル港までの3000キロにおよぶ長大なルートに道路・鉄道網を建設、中国と中東を直結する陸上ルートを確保するとともに、グワダル港を含む周辺の開発を行う計画である。グワダルは、ペルシャ湾の入り口であるホルムズ海峡から400キロに位置する戦略的要衝である。CPECが完成すれば、インド洋、南シナ海を経ずに中東の石油を中国に運び込むことが可能となり、米海軍の脅威に晒されることもなくなる。イランからも100キロしか離れておらず、CPECを将来イランまで延伸すれば、石油をイランからパイプラインだけで直接輸入できるようになる。2015年11月、同港内に自由貿易区を建設するための土地300ヘクタールが中国企業に譲渡され、43年間の開発使用権を得ている。今後、中国はグアダル港の軍事拠点化に乗り出し、将来的には中国海軍の常駐化も考えられる。
またスリランカでは、コロンボ沖に人口島を建設するほか、南部のハンバントタには、中国の融資で大型船が停泊できる港が建設中だ。ハンバントタ港の開発は、2010年に親中派のラジャパクサ政権の下で始まったが、その後誕生したシリセナ政権が脱中国を目指し、一旦計画が凍結された。しかし、財政難のためにシリセナ政権は2016年、11億ドルで港湾管理企業の80%を99年間中国企業に貸し出すことに同意せざるを得なくなった。ハンバントタには既に中国の軍艦が入港しており、いずれ中国海軍の基地も建設されよう。
このほか、バングラデシュ第二の都市チッタゴンでも港湾の収容能力を3倍にするプロジェクトが中国の主導で進行中だ。さらにモルディブのマラオ、ミャンマーのシイトウェ、ケニアのラム、それにギリシャのピレウスなどでも、中国は港湾施設を幣備する見返りとして中国船舶の寄港権を要求している。近い将来、いずれの港湾も中国の軍事艦艇の寄港施設として使用される可能性が高い。南シナ海~インド洋、さらにアフリカに伸びるシーレーンを押さえ、インフラ整備を名目に各地の港湾使用権を獲得し、やがて軍事拠点を次々と建設する手法は「真珠の首飾り」戦略とも呼ばれている。一帯一路構想の下で中国はこの戦略をさらに推し進めており、2017年には、アフリカのジプチに中国軍初の正式な国外基地が建設された。ジプチは紅海とアラビア海が交わるシーレーンの重要ポイントで、スエズ運河の入り口を扼す戦略的要衝でもある。
21世紀海上シルクロードや真珠の首飾り戦略は、中東、アフリカからのエネルギー資源などが通るインド洋を自らの勢力下に収め、アメリカの影響力を排除すると同時に、インドを封じ込めるための戦略でもある。中国はカシミールなど中印国境地域の領有権を主張するなど北からもインドを圧迫しており、海と陸の双方からインドの膨張を抑え込もうと企図しているのである。そのためインドは一帯一路構想に強い警戒感を抱いており、2017年5月に中国が主催した「一帯一路国際協力サミットフォーラム」には首脳のみならず一切の政府関係者も派遣しなかった。
目を東に転じれば、一路構想に組み込まれた南太平洋ルートの島嶼諸国は、豊富な漁業資源やレアアースなどの海底資源に恵まれた地域というだけでなく、中国が自らの海洋防衛線として掲げている第二列島線の上に位置している。中国がインフラ整備を名目に南太平洋の島嶼諸国に影響力を行使する背景には、この地域の国々(パラオ共和国やナウル共和国、ソロモン諸島など)と友好関係を結んでいる台湾を締め出すとともに、この海域から米海軍を駆逐し、南太平洋を“中国の海”にしようとする中国の野望が潜んでいる。
(3)中国による開発事業の悍ましい実態-環境破壊と雇用収奪、人権抑圧の独裁政権延命-
一帯一路構想に潜む問題点は、ほかにもある。中国がこれまで進めてきた開発協力やインフラ整備事業には計画性が乏しい無謀な開発が多い。また中国だけが一方的に利する不公平な内容のため、環境の破壊や地元住民からの土地収奪など被援助国の側に様々な悪影響を生みだしている。中国側の契約不履行などで計画が途中で頓挫、中断する事業も相次ぎ、再開を求めると契約条件の一方的な変更や高い金利を中国側に要求され、仮に完成したとしても事業や施設、利権が中国に支配されるというケースも多発している。
その一例として、中国がメコン川で進めているダム建設事業を挙げてみよう。メコン川は、3000万人の生活を支えるアジアの大河だ。チベットの雪原に源を発し、東南アジアを南下し、世界屈指の農業地帯であるベトナムのデルタ地帯から南シナ海に注ぐ。水産資源の規模は、淡水漁場としては世界最大。生態系の多様性は、南米のアマゾン川に次いで世界で2番目である。メコン川を支配する者は、東南アジア経済を支配すると言っても過言でない。そのため、アジア開発銀行が主導して1992年から大メコン圏(GMS)開発プログラムが始動しているが、近年中国もメコン川流域での水力発電ダム建設事業などを積極的に推し進めており、これまでメコン川の中国領内に建設された大型ダムは6つ。しかし、中国には水利権を他国と共有している意識が全く欠落しており、ラオスやカンボジアなど下流域の国との相談や協議なしに一方的にダムを建設し続けている。そのため「ガイ」と呼ばれる淡水藻などの水産資源が壊滅、魚の孵化場所も損なわれてしまった。また水位の変動が激しくなり、突然の洪水に見舞われたり、逆に水量が激減して船の通行ができなくなるなどの弊害が相次いでいる。環境・人権保護団体「インターナショナルーリバース」によれば、中国は今後雲南省に28力所のダムを造る計画で、下流域の被害はさらに拡大することが懸念されている(3)。
こうした実態は他の河川でも起きており、ミャンマーやパキスタン、ネパールでは、中国が計画していた大規模な水力発電ダムの事業中止を決定している。ミャンマーでは2011年にティンセイン政権が、中国がイラワジ川で建設を始めた水力発電ダム工事の中止を表明した。資金、技術、労働力の全てを中国側が提供するという一見ミャンマーには好条件な事業計画だが、メコン川の場合と同様、大規模ダムの建設が深刻な環境破壊を招いたこと、ダムで発電される電力の8割以上が中国側に送電され、ミャンマーへの電力供給は限定的なこと、さらにダム建設作業には大量の中国人が従事し、地元の雇用機会拡大にならなかったことなどがその理由だ。中国の主導でインフラ事業が計画されると、資機材の調達を含めて中国企業がそのほとんどを請け負い、しかも大量の中国人労働者が国内に入り込み、工事終了後も帰国せずそのまま住み着いて中国人人口の増加が続くケースが東南アジアだけでなくアフリカなどでも多発している。こういったタイド援助は現地の雇用促進や技術の移転を伴わず、途上国での波及効果が期待できないので問題が多いのである。
中国は、物流を活発化するため鉄道などのインフラ整備にも余念がない。低コストをアピールして、タイやオーストラリア、ヨーロッパ、アフリカなど海外での鉄道事業獲得に力を入れている。しかし、メキシコ初の高速鉄道の建設プロジェクトを約500億円で落札したものの、メキシコ政府から契約を取り消されている。中国が狙っていたインドの高速鉄道建設も、日本の新幹線を採用することで決着した。杜撰な事業計画や環境への配慮に欠けるためである。このほか中国は、雲南省の省都昆明を起点とする東南アジア縦断鉄道の構想を打ち出しているが、中国資本によるこの鉄道建設プロジェクトについても、2014年にミャンマー政府は一旦中止を決めている。乱開発による環境破壊を恐れる住民の反対や、中国の政治的影響力浸透を懸念しためといわれる。
当初は低い予算で落札するが、あとから理由をつけて工事料金の上積みを要求し、それが無理とわかると途中で工事を放り出し逃げ出してしまうケースも数知れない。2004年頃から中国はフィリピン・マニラ首都圏の鉄道整備への無償資金協力を提案したが、工事の中断が相次いだ末に中国は途中で放り出し、その後の処理は日本のODAで進められた。中国が日本から契約を勝ち取ったインドネシアの高速鉄道(ジャカルタ―バンドン間)も、工事が大幅に遅れている。2017年11月、アメリカのティラーソン国務長官が「中国のインフラ融資の仕組みは些細なことで債務不履行に陥るようにできており、融資を受ける国々の多くは膨大な債務を背負わされる危険がある」と中国によるインフラ投資を激しく批判、太平洋・インド洋地域の新興諸国に対して警告を発したのも、こうした実態があるからだ。
ユーラシアにとどまらず、中国はアメリカの裏庭である中南米ニカラグアで、カリブ海と太平洋を結ぶ「第二パナマ運河」の建設事業に乗り出している。運河の長さは278㎞とパナマ運河の3倍を超える巨大インフラ事業で、運河に付随して港湾施設、空港、観光施設なども建設され、総工費は500億ドルに上る。ニカラグア政府は、工事期間中に5万人、運用開始後には関連産業を含め20万人の雇用が生まれ2桁の経済成長を見込んでいる。これが完成すれば、アメリカの影響力が強いパナマ運河に物流を依存せずに済むという中国政府の政治意的な意図も透けて見える。
ところが、当初の計画では2020年の完成を予定していたが、現実には未だに本格着工に至っていない。工事を請け負う中国企業が株の暴落で資金不足に陥ったためである。また運河建設のために自由に土地を接収できる法的権限が中国企業に与えられたが、土地を奪われる住民に対して何の説明も行われなかった。三峡ダム建設の折、膨大な数の住民を強制移転させた過去を持つ中国にとって、この問題の重大さが認識できなかったのである。さらにルートの一部に含まれるニカラグア湖(淡水)に海水が流入することで漁業にも深刻な被害が出ることから地元住民が反発、激しい住民運動が起きたことも影響している。しかも、2017年6月にはパナマが台湾と断交し、中国と国交を結んだ。パナマの不利になる第二運河の建設計画を今後も中国が進める可能性は極めて乏しくなっている(4)。
さらに中国はアフリカにも進出、スーダンのバシル大統領やジンバブエのムガベ大統領など強権政治や汚職、身内の重用が目立つ独裁者、独裁政権と深い関係を維持している。中国政府は、内政不干渉を名目に人権抑圧を続ける独裁政権を追認、さらには強権支配の指導者と利益を分ち合う形で事業を仕切っている。それが政治腐敗の温床となり、あるいは非民主的政治家の延命に手を貸す結果を招いているのである(5)。少数民族の虐殺などでムガベ独裁政権は欧米から経済制裁を受けたが、その窮状を救ったのが中国からの援助であった。中国がジンバブエに食い込んでいることは、膨大な経済支援やインフラ整備が物語っている。2015年にはムガベに「孔子平和賞」を授与、ムガベとの強い関係を活かし、中国はダイヤモンドやプラチナ、金、クロームなどの鉱山採掘利権を牛耳っている。2017年11月に起きた政変でムガベは失脚したが、利権を取り戻すためダイヤ採掘利権の国有化に踏み切ったことが中国の反発を招き、ムカベ失脚に繋がったともいわれている。
ニャンシベ大統領一族が独裁体制を敷く西アフリカのトーゴとも、中国はつながりが強い。2016年にはニャンシベ大統領が訪中し習近平と首脳会談を実施、経済関係が強まっている。中国はトーゴで道路補修やインフラ構築など40以上のプロジェクトを手掛けており、旧宗主国のフランスを押さえて、トーゴの最大の貿易相手国となっている。
このように中国の援助を評価しているのは、強権支配を続ける独裁者や賄賂などを懐にしたその側近官僚軍人たちに過ぎず、経済発展による民主化を期待した国民大衆の失望と怨嗟は大きいものがある。
以上、幾つかの例を挙げたが、共産中国が主導したインフラ整備事業で、途上国の発展や民主化に貢献し、高い評価を得たプロジェクトは皆無といっても過言ではない。中国は非同盟運動等を通して建国初期から途上国への支援に取り組んでおり、開発援助事業の経験に乏しいわけではない。しかし中国が進める事業は、常に自国の利益のみが優先され、相手国の環境やバランスの取れた発展への配慮は軽視されてきた。その実相はまさに「新植民地主義」と呼ぶべきものである。自らの経済利益を得るためには、被援助国の環境を破壊しても、あるいは人権抑圧の独裁政権を支援することも厭わない、こうした中国の方針が、一帯一路に限って影を潜めるとは考え難いのである。
しかも集権化を進める習近平政権は、インターネット通信を規制する法律を施行させたほか、民間ビジネスの世界でも共産党の統制を強化する方針を打ち出し、外国企業でも中国でビジネスを行うには、中国共産党への報告・相談を義務付けるなどグローバルスタンダードに逆行した動きを強めている。国内で政治的自由や情報活動を規制し、環境や人権を平然と無視し続けている国が、途上国に好ましい経済発展やウィンウィンの関係を構築し、民主的な国際ルールを築けるとも思えない。そもそも一帯一路に参加する日本企業に、自由で公正な経済活動が許容される保障すらない。
日中両国の企業が交流や提携関係を深め、技術やノウハウ、資本などそれぞれの得意分野を提供し互いのビジネスチャンスを拡大させることは歓迎すべきことである。しかし、一帯一路構想は純然たる民間ベースの事業とはいえず、中国共産党の主導する政治的色彩の濃いプロジェクトであることを見落としてはいけない。これまでの実態を踏まえれば、自由主義経済や国際協調の精神を欠き、途上国の発展を逆に阻害するような共産党政権の事業に日本の政府・企業が加わることは、中国共産党の勢力拡大に日本企業が利用される恐れがあるばかりか、インフラ整備や開発援助政策でわが国がこれまで築き上げてきた国際的な評価や高い信用を失う結果ともなろう。
Ⅴ.AIIBの問題点:資金不足の不安と信用度の低さ
(1)資金調達力の弱さ
一帯一路構想だけでなく、中国が主導するAIIBにも問題は多い。アジアではインフラ需要の増大に対して十分な資金の供給が必要だが、アジア開発銀行(ADB)だけでは対応が難しいこと、また国際通貨基金(IMF)やADBは融資条件が厳しく審査にも時間がかかり、インフラ整備のニーズに適合できないため、これに取って代わり得る国際機関を設立する必要がある、というのがAIIBを設立した中国の説明である。しかし、これは表向きの理由に過ぎない。AIIBを立ち上げた実際の理由は、一帯一路構想の実施に必要な多額の資金獲得に加え、人民元を国際通貨とすること、そして最大の狙いは、アメリカが主導する戦後国際経済秩序への挑戦にある。
経済大国となり、世界最大級の外貨準備を持つ中国が主催するAIIBであるから、その運営に問題はないと考えるのは早計である。確かに米国債を含む中国の外貨準備高は、2008年以降の6年間で約2兆ドル増え、14年末には世界最大の3兆8430億ドルに上った(2位の日本は1兆2000億ドル)。しかし、外貨は輸出や外国企業からの直接投資、さらに投機資金がその資金源になるため、内需不振や輸出減、外国からの直接投資の減少などで中国はその後、外貨を減らす傾向にある。外貨準備の縮小に歯止めをかけようと躍起になっている中国は、国際金融市場からの借り入れを増やしている。
国際決済銀行(BIS)の統計に拠れば、中国の海外の銀行からの借人残高は1兆700億ドル(14年9月時点)と前年比で2800億ドルも増えており、国際金融界にとって中国は発展途上国のなかで最大の融資先である。また債券の発行額も、中国一国だけで途上国全体の発行額の5割近くを占めている。人民元防衛のため外貨準備は約3000億ドル減少し、5兆ドルの対外債務を大きく下回っており、実質的には中国は債権大国どころか「債務大国」なのである。AIIBは必要な資金を債券発行によって調達することになるが、このような状況では金利を高くするなどよほどの好条件をつけない限り、AIIBという運用実績の全く無い新しい国際金融機関が巨額の資金調達を行うことは難しい。
この局面を打開する手段として中国が期待するのが、人民元の国際通貨化である。2015年末、中国は人民元国際化に向けての目標であったIMFにおける特別引き出し権( SDR)獲得に成功し、ドル、ポンド、円、ユーロに続き、元は5番目の国際通貨となった。AIIBの資金は当面ドル建てだが、借入国が承諾すれば人民元建てとなる。人民元がSDR通貨となったことで人民元建ての融資が活発になり、シルクロード経済圏を人民元の経済圏へと変貌させようと中国は狙っているのである。
しかし、人民元の国際化を支えるための通貨・金融システムの整備が、中国では遅れている。現在、人民元での貿易はドルにペッグされた固定相場となっており、中国での貿易通貨は実質的にドルである。これまで中国は人民元の対ドルレートを固定することによって、投機筋に翻弄されることなく輸出主導と外資の導入で外貨を獲得してきたのだ。人民元の国際通貨化を目指すには、人民元の直接取引市場を広め、人民元を単独通貨として流通させる必要がある。そのためには完全な変動相場制への移行は避けて通れないが、元安と資金の流出を恐れる中国当局は為替管理の自由化や人民元の変動相場制への移行に反対している。それどころか中国は、2016年に両替、海外送金、外国企業の買収を大幅に制限し、資本規制を本格化させている。
その結果、2015年には中国の貿易額の3割近くが元で決済されていたものが、17年1~9月期にはその半分以下に減少。国際金融全体の決済でも15年に2.79%と円を抜き4位となった元の比率は、17年には1.46%、通貨別で7位へと大きく後退した。中国人民銀行は36の国・地域と計3.3兆元の通貨交換協定を結んでいるが、16年末の利用残高は221億元と前年末比56%に減少した。人民元の「国際化」を唱えながらも、通貨規制を大幅に緩和し自由化に乗り出さない限り中国経済はドル基軸体制から逃れられず、人民元の国際化も難しい。
厳重な通貨管理の下で開放型の経済を実現した国家は世界に一つもない。見かけの上では世界第2位の経済大国になったとはいえ、債務の焦げ付きも予想されるなど返済が難しい途上国に大量の資金を長期にわたり貸し出す余裕は、中国にはなくなりつつあるのである。
(2)運営システムの不透明性
AIIBのさらなる問題点は、その運用システムの不透明性の高さにある。世界銀行、ADB、IMFなど既存の国際金融機関は、主要出資国の代表で構成される理事会によって運営されている。しかし中国は、世銀やADBなどとは違う中国優位の意思決定方式を描いている節がある。AIIBは多国間の共同出資銀行ではあるが、設立時の資本金1000億ドルのうち中国は約300億ドルを拠出している。最大の出資国である中国のAIIBでの議決権は約28%。重要案件には全体の75%以上の賛成が必要となるので、中国は理事会において事実上の拒否権を持つことになる。また中国の楼継偉財政相は2015年3月に北京で開いた国際会合で、「西側諸国のルールが最適とは限らない」と強調した。中国の当局者も世銀やADBのように理事会の頻繁な開催による決定方式には否定的で、理事会はあまりを開かず、専ら総裁の専決によるトップダウンでの即断即決方式の導入を示唆している。AIIBを否定するのではなく、むしろ積極的に関与し、内部から問題点を改善すべきとの意見もあるが、AIIBは中国の意向をストレートに反映する機関にほかならず、日本がマイナーな出資比率で参加したところで、大きな影響力を持つことは不可能なのである。
中国の四大銀行(中国工商銀九、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行)はすべて国有企業である。その貸し付けは中国全体の80%を占めており、貸付先や融資条件は銀行が査定するが、最終決定は中国共産党が行っている。AIIBにあっても、重要事項は総裁が中国共産党中央委員会に伺いを立てることになれば、中国政府の各部局と同じようにAIIBも党の指令の下に置かれることになる。四大銀行の融資先の多くは業績の悪化が続く国有企業で、不良債権化の問題を抱えている。しかるに公表されたデータでは不良債権比率が1%程度と非常に低く発表されている。金融機関である以上、ガバナンスを含めた情報公開は徹底されなければならないが、運営のシステムやルールだけでなく、運用実態に関する情報開示についてもこうした不透明な姿勢がAIIBで踏襲される危険性は高い。
さらに、融資基準や融資条件などが不明瞭であることに加え、プロジェクトの審査や評価、融資条件の決定などに関する経験やノウハウ、つまり開発協力に必要なソフトパワーが中国には決定的に不足している。途上国の立場に配慮しつつ、融資案件の適性審査・査定やプロジェクト評価の出来る人材や経験の蓄積がないからである。そもそも中国には世界に普遍的価値を提供できるだけのソフトパワーが欠けている。そのため金銭的な価値で力を保つか、軍事力でパワーを誇示しようとする傾向が強い。独裁国家との間ではうまくゆくかもしれないが、多くの国や民族と価値観を共有できなければ、開発支援大国としては失格なのである。
組織運営、ガバナンスのいずれもが不透明で、財務の健全性にも懸念がある国際金融機関の信用力は低くならざるを得ない。そのようなAIIBに出資をする場合、投資家は高い金利を要求するであろう。5~6%程度の高い金利で調達した資金を、ADBと同じ2.2~2.5%で途上国に融資すれば、AIIBはたちまち破たんに追い込まれてしまう。そのため、中国は日本の高い信用力を必要としているのである。AIIBへの日本の参加を求めてくるのは、日本の信用力を利用して低金利での資金調達を図ろうとの思惑からである。世界最大の貸し手である日本と国際金融の元締めであるアメリカが参加しなければ、AIIBの信用力は低くならざるを得ず、必要なインフラ資金を国際金融市場で長期・低利で調達することは容易でない。日米抜きでは、AIIBは機能しないということである。
(3)アメリカの金融支配体制への挑戦
新たにAIIBを立ち上げた理由として、中国はADBの融資条件が厳しいこと、審査に時間かかるなどの問題点を挙げている。しかし、本当の狙いはアメリカ主導の国際金融システムに挑戦し、日米のアジアにおける影響力を削ぐところにある。
これまで中国は、国際通貨基金(IMF)における出資比率の見直しを求めてきた。IMFは、出資比率に応じて議決権が割り当てられる。圧倒的な出資比率のアメリカ(16.7%)に対して、中国は第6位の6.39%(日本は第2位の6.56%)。IMFでは、重要事項の決定においては議決権の85%以上の賛成が必要で、15%以上の議決権を持つアメリカは事実上の拒否権を持っている。米議会は中国の発言権拡大を警戒し、出資比率の変更承認を拒否し続けており、これに中国は不満を抱いている。
またアジアにおけるインフラ投資なら、すでにアジア開発銀行(ADB)が存在する。ADBの最大の出資国は日本であり、出資比率は15.7%。アメリカはこれに次ぐ15.6%で2位だ。またADBの歴代総裁は1966年の創設以来、9代続いて日本人が務めており、アジアの開発援助は完全に日米が主導権を握っている。ADBにおける中国の出資比率は6.5%で第3位だが、日米が30%以上を占めていることを考えれば、その存在感は極めて小さい。中国はIMF同様、ADBにおいても出資比率の拡大を求めているが、日米の壁に阻まれて実現していない。そこで中国は、自らが主導する国際金融機関としてAIIBを設立し、日米になりかわって自らが国際金融システムを主導するとともに、強い経済関係を築くことで周辺諸国への影響力を格段に広げようと考えているのである。日本やアメリカの排除、追い落としを意図した国際金融機関に協力支援する愚行は避けねばならない。
Ⅵ.二つの百年構想と覇権国家の実現という中国の野望
(1)習近平思想と一帯一路
一帯一路構想とそれを資金面で支えるAIIBに関わる種々の問題点や、その奥に潜む危険性を眺めてきた。しかし昨今の中国の動向を眺めて我々が最も注意を要すべきは、習近平政権が進めているこの事業が、21世紀の覇権国になるという中国の目的実現のための重要な手段と位置付けられている点にある。
習近平は国家主席に就任した直後から、「二つの100年計画」を中国の国家目標に掲げてきた。「二つの100年計画」とは、2021年の「中国共産党創立100周年」までに小康社会を全面的に築き上げること、そして2049年の「中華人民共和国建国100周年」までに、富強・民主・文明・調和の社会主義現代化強国を築き上げることである。2017 年10月、第19回中国共産党大会が開かれ、習近平は3時間以上にもおよぶ大演説(政治報告)を行い、二つの重要な指針を示した。
一つは自らの名前を冠した「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義」思想であり、もう一つは、「中華民族の偉大な復興」である。前者は党の規約に盛り込まれたが、習近平は就任1期目の5年間で「新時代の中国の特色ある社会主義思想を形成」したとし、同思想を「全党・全国人民が中華民族の偉大な復興に奮闘する行動指針」と位置づけた。また習近平は「近代以来、長く苦しんできた中華民族は、立ち上がり、豊かになる段階から、強くなる偉大な飛躍の段階を迎えた」と語り、21世紀半ばまでに「現代化した社会主義の強国」を建設し、中国は「総合的な国力と国際影響力で世界をリードする国家になる」と宣言した。
つまり、習近平思想と名付けられた「新時代の中国の特色ある社会主義」思想の核心は、「二つの100年目標」を達成することにあり、それが「中華民族の偉大な復興」という夢の実現に繋がるとこの演説で定義づけたのである。二つの100年目標を具体的に言えば、2021年までに中国が日本を押しのけて中国がアジア第一の大国となること、さらに2049年までに世界一の覇権国家になるということである。中国がアメリカに提案した「太平洋の東西分割」や「新型の大国関係」の構想は、いずれもこうした中国の野望の現われと見なければならない。
さらに習近平は「中華民族の偉大な復興という中国の夢のためにたゆまず奮闘する」と述べ、そのためには、党の指導と社会主義制度を堅持すること、「中華民族の偉大な復興」に向けて中国の特色ある社会主義を発展させること、そして外国の政治モデルをそのままの形で導入することはしないと明言した。中国は鄧小平以来の改革開放、韜光養晦の路線と完全に決別し、覇権国家の実現という新たな目標に向けて舵を切ったのである。そしてそのための施策として、軍事力の拡大や共産党支配の強化、さらに失われた版図の奪還、そして欧米主導の世界秩序を退け中華秩序の下で中華グローバリズムによる世界支配実現を目標に掲げているのである。
(2)失われた版図の奪還
一帯一路は、過去において中国が最も栄え、広大な領域を支配していた栄光の時代を強く意識し、その時代における中国の影響力を回復しようとする野心を秘めたものである。
まず「一帯」(陸路)で結ばれる経済圏は、13世紀のモンゴル人による元帝国の版図と重なっている。このモンゴル帝国は、大都(北京周辺)を本拠にし、強大な軍事力を背景に広大な領域を支配するとともに、中国大陸から中東、ユーラシア大陸全域に交鉦と呼ばれる紙幣を流通させた。史上初の紙幣によって結ばれる世界通貨帝国の元と、今日の経済大国中国をオーバーラップさせているのである。元は明によって駆逐されたが、その明は清にとって代わられた。清は満州族を中心にモンゴル族、漢族、チベット族などの連合体であったから、現代の中国は元の後裔に相応しいとの論理であろう。
「一路」については、明代における中国の海洋進出がイメージされている。1405年から始まった鄭和の南海遠征は、現在のベトナム、マレーシア、インドネシア、スリランカ、インド、イラン、サウジアラビア、ケニアに至るものであった。習近平政権はこれをヨーロッパにおける大航海時代幕開けの100年近くも前の偉業であり、中華民族の復興に相応しい歴史的治績として利用したのである。通商を通じて諸外国との共存共栄を目指すプロジェクトであるかのような印象操作も施し、中国国民に向けた政治的アピール、ナショナリズムの鼓舞と、相手国との関係円滑化の両立を狙う構想に仕立て上げられている。
(3)中華秩序の再興
いま中国は、東アジアの国際秩序を、中国を頂点とする朝貢に基づくヒエラルキー制度、即ち旧来の華夷秩序へと変転回帰させようとしている。華夷秩序とは、古代から日清戦争の敗北まで、東アジアに機能していた秩序体制で、冊封体制とも呼ばれる。冊封体制とは、宗主国と朝貢国(属国)からなる主従関係を意味する。宗主国は、文化文物が花開く世界の中心(中華)、すなわち中国であり、朝貢国とは中国の周辺諸国を指す。中国は常に宗主国の座にあり、他方、北狄・東夷・南蛮・西戎というその呼称が示唆するように、周辺諸国は野蛮な未開の国として常に中国への朝貢を強いられる。つまり、西欧の国際体制が、主権国家の平等を前提とする横の関係であるのに対して、冊封関係は上下を固定した階層秩序を基本とする命令関係である。
この華夷秩序の機能領域をアジアからユーラシア、さらに世界へと広げるのが習近平政権の目指すナショナルゴールである。一帯一路構想に関わる地域の人口は約45億人、世界総人口の65%近くを占める。中国はその人々を自らの秩序の下に置こうとしているのである。
Ⅶ.日本のリーダーシップで推進すべき3大国家戦略
(1)覇権外交・膨張的軍事戦略と一体の一帯一路構想に加わるべきでない
一帯一路構想の雄大さは、実は中国経済の脆弱性の現れであると同時に、それはまた中国の野望の大きさの表象でもある。中国の覇権外交や膨張的な軍事戦略とセットになっている。AIIBはインフラ投資のための国際金融機関とされ、国際公共財の様を装っているが、その実態は覇権外交を進めるための中国共産党の政治工作機関とみるべきものである。そのような構想や組織に日本が加わるべきでないことは火を見るよりも明らかである。人民元を経済圏拡大の武器として中国主導の経済圏を立ち上げ、日米欧を軸とする既存の国際経済のルールに代わり中国主導のルールを構築する。それは、中国の、中国による、中国のための国際経済秩序であり、それを作るための手段である一帯一路の構想に加わるべきではない。
習近平の下で独裁と集権化が進めつつある中国は、対外政策でも南シナ海や尖閣で覇権主義的な行動を強めている。そのような国に、自由で開かれた社会・経済システムの整備構築は望むべくもない。日本だけの問題ではなく、自由で開かれた国際社会にも甚大な悪影響を及ぼす。それゆえに日本は、ガバナンスや透明性、公平性に問題があるとして、アメリカとともにAIIBへの参加を見合わせてきた。極めて賢明な選択であった。
2015年4月、ジャカルタでのアジアアフリカ会議で、習近平国家主席は一帯一路の建設とAIIB設立の意義について言及した。そのあと演壇に立った安倍総理は、60年前のバンド会議の原則を再確認し、「力ではなく法の支配」の重要性を説いて中国の姿勢を牽制した。この時の日中首脳会談でも、安倍総理はAIIBへの日本の参加を促す習近平に対し、「ガバナンスや透明性に問題あり」と切って返している。
もっとも、わが国の大手メディアは、イギリスがAIIBへの参加を決め、主要国が雪崩を打ったようにそれに続くや、不参加は対米追随だと日本政府を批判、遅れをとってはならないとばかりに一帯一路、AIIBへの参加を主張するようになった。しかも最近では、財界や政府・自民党の幹部からも参加容認、あるいは前向きな発言が聞かれはじめている。
安倍首相も2017年6月に開催された「アジアの未来」での講演で、一定の条件を満たせば一帯一路構想に日本も協力する用意があると明言、さらに硬かった中国の対日姿勢に緩和の兆しを読み取り、河野外相は「一帯一路は世界経済にメリットあり」と語り、11月のベトナムでの日中首脳会談では、初めて笑顔を見せた習近平国家主席に対し安倍首相が「日中関係を新たな段階に押し上げてきたい」と発言、両首脳は「一帯一路を含め、日中両国が地域や世界の安定と繁栄にどのように貢献していくか共に議論していくこと」で意見を一致させている。
EU諸国は相次いでAIIBに参加しており、このままでは日本だけがビジネスチャンスから取り残されるのでは、との不安感が企業関係者には募っている。一方政治のレベルでは、一帯一路が事業の公正さや透明性の面で問題が多い構想であることを理解し警戒しているものの、アメリカのアジアにおける存在感の低下や北朝鮮情勢の緊迫を受け、中国の対日姿勢の変化に合わせて日本も一帯一路に前向きな姿勢を示すことで、日中関係の改善を図りたいとの政策的な配慮が窺える。
だが、日本側の焦りや安易な対中期待感に乗じて、わが国の先端技術や経営ノウハウを吸収するのが中国の狙いである。日本が加わらないことには、一帯一路もAIIBもともにその先行きは不透明・不安定である。抱える不安や焦りは中国の方が大きい。その大きさゆえに、執拗に日本に秋波を送ってくるのである。
自らにとって利用する価値があると思えば、最大限の甘言や巧言を弄して日本を取り込もうとするが、所期の目的を果たすや一転、距離を置き、傲然倨傲、時に威圧的な姿勢に変化するのが中国外交の常道である。焦りと短慮に任せ、ムードに流されるべきではない。バスに乗らない勇気を持つ必要がある。
(2)アジアにおける質の高いインフラ整備体制を推進する
日本は一帯一路構想に距離を置き、またAIIBについても当面その参加を見送るべきであるが、中国が繰り広げているこの広大な覇権獲得の戦略に対して、わが国は如何なる構想の下に対抗すべきであるのか。ここでは三つの柱からなるカウンターストラテジーを提言したい。それは、①ADBの充実強化など質の高いインフラ整備体制の推進、②海洋同盟の連携強化、そして③開かれた広域経済圏創設の3本柱である。
いまアジアには膨大なインフラ需要が存在する。ADBの試算によれば、2010年から20年にかけてアジアには8兆ドル規模のインフラ整備需要があるが、ADBだけではその2割程度しか供給することが出来ないという。その不足分をガバナンスの信頼性や透明度低い中国主導のAIIBで埋めるのではなく、日本がイニシアティブを発揮して、ニーズに対応できる資金基盤の確保に務める必要がある。2015年5月、安倍首相は東京で開催された「アジアの未来」の晩餐会で演説し、今後5年間で約13兆円をADBと連携するかたちでアジアのインフラ建設に投じる考えを示した。これはドル換算に直すと約1100億ドル。中国主導のAIIBの資本金(1000億ドル)を上回る規模となる。
しかし、課題は資金の多寡だけではない。先の演説で安倍首相は、「安かろう悪かろうはもう要らない」と安値攻勢をかける中国のやり方を痛烈に批判し、「短期的なやり方で現地政府に必要以上の支払い保証を求めるやり方がまかり通ってきた」が、これからは「質の良さ」がアジアのインフラ整備には欠かせないと語っている。経済の規模で途上国を惹きつけようとする中国への対抗策は、「質」である。例えば、ADBの融資には審査に長期の時間が必要となり、なかには10年を要したものもあった。今後は被援助国の事情を踏まえて、迅速柔軟な審査が可能となるよう専門家の育成も含めてADBの組織・機能の強化が求められる。
また最近は、政府の負債を減らすため、政府主導ではなく官民共同で実施するPPP(Public Private Partnership)事業や民間主導のインフラ整備事業が増加する傾向にあるが、こうした民間主導プロジェクトに対するADBの融資には限界がある。2015年に安倍政権が策定した『開発協力大綱』には「官民連携による開発協力の推進」がうたわれており、今後は公共投資だけでなく、民間の資金やノウハウを活かしたPPPにも応じられる円借款の提供や、ADBと国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、日本貿易保険(NEXI)など関係諸機関との連携を強めることが望まれる。
2016年6月の「アジアの未来」晩餐会で安倍首相は、インフラ事業は「万人が利用できるよう開かれており、透明で公正な調達によって整備されること」、「プロジェクトに経済性があり、借り入れをして整備する国にとって返済が可能で、財政の健全性が損なわれないこと」が国際社会で広く共有されている考え方であると指摘、一帯一路構想を批判したうえで、日本がこうした「質の高いインフラパートナーシップ」を進めていくと述べている。
日本の進む途はAIIBへの加入ではなく、これまでの豊富な経験を基に、被援助国の自主性や債務の持続可能性、環境、社会に対する影響、人権擁護への配慮などに目配せした手厚い援助政策の継続によってさらに実績を重ねるとともに、アジア諸国の期待に応えられるようADBの規模・機能両面の発展に尽力することである。
(3)自由で開かれたアジア太平洋戦略による海洋同盟を構築する
これまでの人類の歴史は、大陸国家(ランドパワー)と海洋国家(シーパワー)の戦いと捉えることができる。大航海時代以降、ポルトガル、スペイン、オランダ、英国、アメリカといったシーパワーがランドパワーを抑え、世界を主導してきた。19世紀後半から20世紀にかけてはドイツ、ソ連(ロシア)というランドパワーが幾度か英米に挑戦したものの、いずれも敗れ去っている。しかし21世紀に入るや、今度は中国という新たなランドパワーが再び海洋勢力に挑もうとしている。
両勢力の角逐についてアメリカの地政学者ニコラス・スパイクマンは、ユーラシア大陸の沿岸地帯(リムランド)を支配した側が、覇権闘争の勝者になると説いた。リムランドとは、バルカン半島から中東~コーカサス~南アジアを経て東南アジア~朝鮮半島に至る地域で、これは、中国が提唱する一帯と一路に挟まれた地域に概ね合致している。スパイクマンの予言が正しければ、中国が一帯一路構想によってハートランド(ユーラシア内陸部)だけでなくリムランドをもその影響下に収めることになれば、アメリカに代わって中国が世界の覇権を握ることになってしまう。
民主主義を認めず、一党独裁の閉鎖抑圧的な社会主義の思想や政治システムが世界を席巻するようなことになれば、自由で開かれた民主的な国際秩序の維持は困難となろう。そのような事態を防ぐためには、ランドパワー中国の膨張と覇権主義を抑えるため、自由と民主主義を基調とする開放的な世界秩序をめざす日米豪、ASEAN諸国や台湾、インドなど海洋勢力の連携の強化、即ち海洋諸国間の同盟を構築することが必要となる。これに関し本研究所は「海洋同盟論」構想を提唱しているが(☞政策提言「環太平洋文明の発展と海洋国家日本の構想」参照)、安倍政権が掲げる「自由で開かれたインド太平洋戦略」も同様の考えから生まれたものといえる。
2016年8月にケニアで開かれた「アフリカ開発会議(TICAD)」に出席した安倍首相は、成長著しいアジアと潜在力の高いアフリカを世界の重要地域と位置付け、この二つの地域を包含するインド洋と太平洋地域全体の発展をめざす「自由で開かれたインド太平洋戦略」を打ち出した。インフラ整備や投資の促進によって経済の成長を実現するとともに、法の支配に基づく海洋の自由を訴え、また人道、災害支援協力などによってこの地域の平和と安定の確保をめざす構想である。一帯一路を意識した構想であることは言うまでもない。2017年11月の日米首脳会談で、トランプ大統領と安倍首相は、この戦略を日米共通の方針とすることで合意し、オーストラリアやインドを加えた4か国の連携を軸に、自由貿易や開発援助、安全保障面で同地域に関与する枠組み作りに向けて協議を深めていくことでも認識が一致した。これを受け、日米豪印による戦略対話の枠組み作りが進められている。
(4)貿易自由度の高い「開かれた広域経済圏」の創設を推進する
一帯一路を推進する一方、中国は、アジア太平洋地域では自らが主導するRCEPの立ち上げを急いでいる。しかし、貿易自由度の低いRCEPでは、開かれた自由貿易圏の創設は望めない。RCEPやAIIBを通じて中国がアジアなどの新興国への経済的影響力を高めている中で、中長期を見据えた多国間の包括的で自由度の高い経済連携の枠組みを構築することは、日本が貿易大国として生き残るための鍵である。その中でも最大の鍵となるのが、RCEPよりも遙かに高いレベルの自由貿易圏創設をめざしているTPP11だ。TPP11の発効は日本にも大きな経済効果をもたらすだけでなく、多くの品目の関税が撤廃、減額されることで参加国同士の貿易や投資といった経済的な結びつきが一段と強固になり、アジア海洋同盟の紐帯を強めることにもなろう。
日本は“オーシャン・イレブン”と呼ばれる他の海洋諸国家と協力し、TPP11の早期発効を実現するとともに、アメリカを多角的な世界経済の枠組みに呼び戻すことによって開放的な自由貿易圏をアジア太平洋地域に作り上げ、共産主義ランドパワーの覇権主義的な膨張を食い止める責任がある。
結論として纏めるならば、①中国が一帯一路構想やAIIBの立ち上げでめざしている国際金融体制への挑戦には、ADBの充実強化など質の高いインフラ整備体制の推進、②覇権主義的な影響力の拡大には、自由で開かれたインド太平洋戦略による海洋同盟の構築、さらに、③中国主導のRCEP経済圏には、より貿易自由度の高い広域経済圏TPP11の早期発足で対応することが、日本外交の採るべき戦略である。
これら政策の一部は安倍政権の下で実行に移されつつあるが、より一層この3本柱の施策を強力に推し進めていくことで、太平洋~インド洋に至る地域の貿易と海洋の自由が確保され、かつ自由と民主主義を基本とする政治、経済秩序の構築も可能となる。さらにわが国が強いリーダーシップを発揮することで、日本の中国に対するバーゲニングパワーの向上にも資することになるのである。
TPPからの離脱に象徴されるように、アメリカの東アジア太平洋地域における影響力は後退気味である。そのような国際環境の下、質の高いインフラ整備、自由度が高く開放的な広域経済圏の創設、そして自由と民主主義の国際秩序構築という三つの重要課題実現の主導役はわが国をおいて他にない。いま日本は、地球的な広がりと世界史的な意義を帯びた壮大な時空的課題を果たすべき使命を担っているのである。
●注釈
(1)一帯一路構想には、このほか北極海航路が第三のルートとして含まれるようになった。ロシアのムルマンスクの埠頭を開発し、欧州~ロシア~日本~中国をむすぶルートである。ロシアのプーチン大統領が一帯一路と北極海航路の連結という形で提唱し、中国は「氷上シルクロード」と呼んでいる。
(2)何清漣らは、社会主義市場経済論という矛盾極まりない体制を共産党資本主義と呼び、その問題点を鋭く指摘している。「共産党資本主義とは独裁政権下でのクローニー資本主義(権力者・富裕層による縁故資本主義)と国家資本主義の合体であり、「中国モデル」とはその耳触りの良い別名にすぎない。つまりそれは、資本主義の廃絶を目指した中国共産党が社会主義経済体制の失敗を経て、資本主義経済体制に切り替えることで中国共産党政権の統治を維持することを意味する。と同時に、中国共産党の各クラスの官僚とその親族は、市場化を通して手中の権力を行使し、企業家や大規模不動産所有者、巨額の金融資産保有者といった各タイプの資本家へと変貌し、中国社会の大半の富を握るに至った。こういった利益構造のあり方ゆえに、「紅い」権力者や富裕層は中国共産党政権による統治の維持を必要とするのである。というのも、中国共産党政権のみが彼らの生命と財産の安全を保障でき、今後とも政府が独占する業種で彼らが大金を搾取し続けることを保証してくれるからである。」何清漣・程暁農『中国』中川友訳(ワニブックス、2017年)17頁。
(3)『ニューズウィーク日本語版』2017年11月14日号、
(4)『日本経済新聞』2017年10月24日。
(5)「中国当局は、独裁主義国が多く民主主義国が少ない地域を好む。・・・中国の力が増大していくにつれ、中国寄りの独裁的政府を保護し、民主主義政府を弱体化させる力も劇的に増大していくだろう。・・・・中国の戦略の一つは、不干渉の原則について、アフリカの政府と“相互に有益な提携”を結ぶことだ。中国政府は、アフリカのビジネスパートナーが「政治の約束事を伴わない、ただのビジネス」(胡錦濤前国家主席の言葉)という方針のもと現地の人々を虐待していることを無視している。中国は、国際基準を無視することにより、アフリカの民主主義をさらに弱体化し、独裁政権をさらに強化するだろう。中国は、このジンバブエのモデルを、アジア、アフリカ、南米に適用した。また、シリア、ウズベキスタン、アンゴラ、中央アフリカ共和国、カンボジア、スーダン、ミャンマー、ベネズエラ、イランの独裁政権も支援した。中国経済がアメリカの3倍の大きさになれば、発展途上の国々を、紛争解決と健全な統治とは逆の方向へ進ませようとする中国の行動は、さらに影響力を強めるだろう。」マイケル・ピルズベリー『China2049』野方香方子訳(日経BP社、2015年)276~8頁。
●参考文献
秋元千明『戦略の地政学』(ウェッジ、2017年)
安達誠司『中国経済はどこまで崩壊するか』(PHP研究所、2016年)
アーロン・L・フリードバーグ『支配への競争―米中対立の構図とアジアの将来―』佐橋亮 監訳(日本評論社、2013年)
石平・宮崎正弘・福島香織『中国バブル崩壊の全内幕』(2016年、宝島社)
エドワード・ルトワック『自滅する中国』奥山真司訳(芙蓉書房出版、2013年)
エドワード・ルトワック『中国4.0 暴発する中華帝国』奥山真司訳(文藝春秋社、2016年)
遠藤誉『習近平VSトランプ』(飛鳥新社、2017年)
小野寺史郎『中国ナショナリズム 民族と愛国の近現代史』著(中公新書、2017年)
梶田幸雄他『中国対外経済戦略のリアリティ-』(麗澤大学出版会、2017年)
何清漣・程暁農『中国』中川友訳(ワニブックス、2017年)
柯隆『暴走する中国経済』(ビジネス社、2014年)
関志雄『中国「新常態」の経済』(日本経済新聞出版社、2015年)
黄文雄『断末魔の中国経済』(ビジネス社、2015年)
此本 臣吾 ,松野 豊,川嶋 一郎『2020年の中国』(東洋経済新報社、2016年)
近藤大介『中国経済「1100兆円破綻」の衝撃』(講談社、2015年)
近藤大介『パックス・チャイナ 中華帝国の野望』(講談社、2016年)
榊原英資『世界を震撼させる中国経済の真実』(ビジネス社、2015年)
櫻井よしこ『地政学で考える日本の未来』(PHP研究所、2017年)
唱新『AIIBの発足とASEAN経済共同体』(晃洋書房、2016年)
鈴木英夫『新覇権国家中国×TPP日米同盟』(朝日新聞出版、2016年)
田村秀男『人民元の正体』(マガジンランド、2015年)
田村秀男他『中国経済はどこまで死んだか』(産経新聞出版、2016年)
ディビッド・シャンボー『中国グローバル化の深層』加藤祐子訳(朝日新聞出版、2015年)
ニコラス・スパイクマン『平和の地政学:アメリカ世界戦略の原点』奥山真司訳(芙蓉書房、2008年)
西村豪太『米中経済戦争 AIIB対TPP』(東洋経済新報社、2015年)
日本再建イニシアティブ『現代日本の地政学』(中央公論新社、2017年)
浜矩子『中国経済あやうい本質』(集英社、2012年)
真壁昭夫『AIIBの正体』(祥伝社、2015年 )
南亮進・牧野文夫編『中国経済入門 第4版』(日本評論社、2016年)
宮崎正弘『「中国大恐慌」以後の世界と日本』(徳間書店、2016年)
三潴正道 監修『一帯一路・技術立国・中国の夢……いま中国の真実は』而立会翻訳(日本僑報社、2017年)
室井秀太郎『中国経済を読み解く』(文眞堂、2017 年)
渡邊哲也『中国壊滅』(徳間書店、2015年)
渡辺昭夫編『アジア太平洋と新しい地域主義の展開』(千倉書房、2010年)
リチャード・マクレガー『中国共産党―支配者たちの秘密の世界』小谷まさ代訳(草思社、2011年)
王義桅『「一帯一路」詳説』川村明美訳(日本僑報社、2017年)