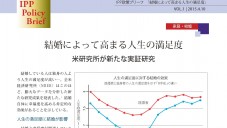1.解決の糸口を見出せない少子化問題
私は厚生労働省(旧厚生省)に30年間勤務し、社会保障すべての問題を担当した。特に少子化問題に取り組み、90年代に児童家庭局の3つの課で課長を務めた。同じ局で3つの課長を務めることなどほとんどないが、これは決して誇らしいことではない。「児童家庭局は女の仕事」という考えが厚生省内に根強く、実はこのことが、少子化が深刻な問題として受け止められなかった要因でもある。 私は「少子化」という言葉が誕生した1990年代に政策の策定に携わっていたので、元祖少子化担当官と言えるかもしれない。それゆえ、今も少子化問題解決を政治信条としている。 なぜ、少子化問題が未だに解決の糸口を見いだせないのか。最初の担当者として、原因をお話ししたい。 「少子化対策は主に厚生省が担当する」と政府内で決まった1990年代、省ではもう一つの大きなテーマを抱えていた。「介護保険の創設」である。この二大テーマが一度に与えられたが、厚生省はこれに同時に取り組むのではなく、「介護重視」を選択したのである。 介護の分野では2000年に介護保険法が施行され、今では9兆円産業にまで拡大している。予算を比較しても、少子化対策(国際的には家族手当政策)は介護の十分の一である。少子化対策は真正面から取り扱われることなく、常に後回しとなり、介護の陰に隠れてしまったわけである。 もう一つの原因は、「女子供の仕事は女がやればいい」という認識を政府も厚生省も持っていたことである。これが大きな足かせになった。当時は政治家も少子化問題に無関心だったと言っていい。 今日ようやく少子化に目が向けられるようになったが、政府と官僚の中には少子化問題を軽視する雰囲気が依然として残っている。なぜなら、20年前(1994年)に作成した資料と現在の資料、そして予算もほとんど変わっていないのである。これを早急に変えなければならない。 安倍政権は「デフレ脱却、経済再生」を訴えるが、経済政策で最も重視すべきは「人口政策」である。2010年に刊行されベストセラーになった藻谷浩介氏の『デフレの正体』(角川新書)でも指摘されているが、子供が増えれば消費も促進されるはずである。ところが現在の人口構造では、そもそも結婚自体が少ない。経済政策を進めていくためには少子化対策、さらに言えば人口政策に取り組んでいくことが本質的解決策なのである。
2.日本の人口の推移
最初に、日本の人口の推移を確認しておきたい。「日本の人口推移と将来推計人口」(図1)をみると、明治維新直後の1872年の総人口は3400万人であった。それが1912年(大正元年)には5000万人に増加。さらに1967年に初めて1億人を越え、翌年にはGNP世界第二位の経済大国となった。 しかし、2008年の1億2808万人を頂点に人口減少に転じ、2050年には1億人を下回ると予測されている。生産年齢人口(15~64歳)は1995年以降減少が続いている。 「出生数および合計特殊出生率の年次推移」(図2)では、出生数が最も多いのは第一次ベビーブームと呼ばれる団塊の世代が生まれた1947~49年。この3年間は狭義の団塊の世代と言われ、毎年270万人が生まれた。広義の団塊の世代は47年から52年で、毎年200万人が誕生している。さらに1971~74年の団塊ジュニアの世代が第二次ベビーブームとなった。ただし、最も多い73年でも210万人なので、第一次ブームに比べると規模は小さい。 一方、合計特殊出生率に関しては2012年に1.41、2014年では1.42と発表されている。数字上は回復傾向にあるように見えるが、そうではない。合計特殊出生率は15~49歳の女性の平均出生率から算出される。つまり、この年代の女性が減少し、分母が小さくなった。そのため若干高い値が出たに過ぎない。2012年の新生児は100万3000人で、100万人割れ寸前だった。今年(2015年)は若干回復する可能性もあるが、出生率の低迷を根本的に改善するには至っていない。
3.「人口政策」ではなく「少子化対策」に
少子化対策の歴史に言及する前に、もう一つ指摘しておかなければならない問題がある。太平洋戦争開戦の1941年、人口政策に関する閣議決定がなされた。いわゆる「生めよ 増やせよ」閣議決定である。しかし戦後、これが長くタブーになった。このことも、後の少子化対策を遅らせる一因になったと言える。 1947年、日本国憲法が施行された同じ年に児童福祉法が成立した。憲法で定められた生存権を具体化するために、一連の福祉法の中で最初に制定された法律である。現在の法律は「児童の自立支援」が基本理念だが、当時は「児童の保護」が中心であった。同じ年、児童を含む家庭の保護を進める意味で、児童局が児童家庭局に改編された。 さらに翌1948年には優生保護法が成立した。この背景には優生思想があった。これが少子化と何の関係があるか。この法律により堕胎が合法化されたのである。「経済的理由で堕胎ができる」という条文が入ったことで、ベビーブームの後に出生率が落ちた一因となっている。堕胎を希望するのは主に既婚の女性で、「子供は3、4人いるので、これ以上は要らない」という人が少なくなかった。家族の形が「父母と子供2人」に定着したのも、優生保護法の影響があったと言える。 その後も様々な福祉法が生まれた。その中で、最後の最後に登場したのが1971年の児童手当法である。欧州では当たり前とされたが、日本では必要視されにくい法律だった。一昔前まで、「日本は人口が多すぎるのに、なぜ生まれた子供にお金を出さなければならないのか」という議論が厚生省内でもあったほどで、なかなか意見の一致ができなかった。最終的には「貧しい家庭にはお金を出すべきだ」ということでまとまった。ただ、当時は第三子以降にしか給付しなかったが、施行後も給付の是非の議論は根強く続いた。 1989年には合計特殊出生率が過去最低の1.57まで落ち込む。いわゆる「1.57ショック」である。それ以前の合計特殊出生率の最低記録は「丙午(ひのえうま)」にあたる1966年の1.58だった。当時、こんなことは二度と起こらないと言われていたが、それをさらに下回る過去最低水準に落ち込んでしまったのである。さすがに政府も放置できず、総理府内に各省連絡会議ができた。ただし、予算は一銭もつくことはなかった。 そして1992年、国民生活白書の中に経済企画庁が造語した「少子化」が登場する。そもそも、なぜ「少子化」という言葉にしたのか。当時は男女平等論が叫ばれている時期である。本当は「人口政策」という言葉を使いたかったが、使える雰囲気ではなかった。苦肉の策で出てきたのが「少子化」だったのである。実際、92年以前の辞書には「少子化」という言葉は出ていない。 少子化対策として、労働省では育児介護休業法が制定された。労働省は戦後いち早く女性を採用してきた唯一の省で、この問題にも対応が早かった。
4.「少子化」イコール「保育所対策」に
政府あげての少子化対策は1994年のエンゼルプランからである。私は児童家庭局の課長として策定に携わった。最初に担当したのは厚生省、労働省、文部省、建設省だけで、しかも議論の中身は大半が保育の問題だった。 各省とも保育以外には関心を持っていなかったと言わざるを得ない。建設省が加わったのは児童公園の整備が関わっていたからである。また労働省は女子労働の改善に関わっていた。文部省も熱意があったとは言い難い。ただ、少子化対策として唯一取り組んだのがゆとり教育であった。 そのため、エンゼルプランは事実上「保育プラン」となった。この考えは20年経過した今でもほとんど変わっていない。発表される政策の文章・大綱もほとんど当時のままである。つまり、「少子化」イコール「保育所対策」という意識が依然として行政に深く蔓延しているというわけである。 しかも1990年代はバブル崩壊で税収が減少し、政府としても少子化対策に予算が組める状況ではなかった。ただ、予算がないとプランにもならないので、特別会計を使った。医療保険や年金保険には特別会計が使われているが、この中には事業主負担が含まれ、その一部を児童手当の給付に当てていた。「特別会計なら政府の負担にもならない」という次元でしか、児童手当は扱われなかった。エンゼルプランの財源もこの特別会計である。 エンゼルプランの策定を受けて、1995年には厚生白書が初めて少子化をテーマに取り上げた。 「子供を持つ夢」と謳った白書はとても評判がよかった。政府が作る白書で「夢」という言葉が使われることなどほとんどない。戦後しばらくは一人の学者が白書を作成していた。ここ30年は各課に少しずつ分担させ、集まったものをまとめている。そのため味気ないものになってしまうことは否めない。 しかし、95年の白書は「夢」という言葉を掲げ、多くの人を引きつけた。なぜ、「夢」という言葉が出てきたのか。児童福祉法は子供の保護を目的としてきた。従来、日本では子供は生産財だった。子供は生産力になり、老後は子供が面倒をみてくれる。「夢」という言葉を使ったのは、その考え方を根本から変えるためだった。「社会保障制度が整ってきた現代、子供を持つのは贅沢財です…」。この白書が日本社会における転機になったと言っても過言ではない。 また、1997年に児童福祉法が50年ぶりに改正された。「子供の保護」という理念から、「自立支援」に転換したのである。 さらに、2001年の省庁再編により内閣府に権限が集められた。2003年には内閣府が少子化対策基本法を作成する。これはプログラム法で予算はつかず、5年ごとに大綱を作るという方向性を示しただけである。3番目の大綱は2014年に発表されたが、中身はエンゼルプランとほとんど変わっていない。
5.混乱した子ども手当て法
2010年、民主党が政権についた翌年に子ども手当て法が立法された。公約では子供一人当たり毎月2万6000円を支給する。財源は事業仕分けで16兆8000億円の無駄遣いを掘り起こし、それを充てる計画だった。しかし実際は3000億円しか見つからなかったために、予算はつかなかったのである。 そこで、とりあえず半額の1万3000円を支給することとし、予算の確保を先送りにしたのである。ところがその矢先に東日本大震災が起こった。「増税するしかない」と混乱していた時、所得制限のない子ども手当てに自民・公明党が強く反対した。 2012年、所得制限のないヨーロッパ流の子ども手当は難しくなり、所得制限が設けられた。「所得制限のない子ども手当」を実現できなかった直接的要因は東日本大震災だったが、元々予算上は実施が極めて困難な案だった。子ども手当て法を立法する際、私は「金銭給付は無理です」と進言したが、民主党幹部は耳を貸してくれなかった。 もう一つ、所得制限のない子ども手当が実現できなかった理由として、社会構造の違いも挙げることができる。ヨーロッパは若い時から職能給を受け取るため、勤続年数が長くなるほど増えるという給与システムではない。日本は逆に、年を取るほど給料が上がる年功序列賃金体系である。日本の構造であれば、子供が就学する頃には多額の給与を受け取ることができるので、児童手当が切実に求められるというほどではない。しかし、ヨーロッパでは緩やかなアップでしかないため、子育て期に手当が必要になるという違いがあった。 2012年には、やはり民主党政権下で「子ども・子育て関連三法」が成立した。ただし、ほとんどプログラム規定で指針を示したに過ぎない。目的は「認定こども園」の導入により、長年の懸案だった幼保一体化を実現することにあった。しかし実際には、幼稚園、保育園ともそのままの形態で運営を継続したいという声が多く、当初の予想ほど移行申請は行われなかった。関連三法の中身も率直に言ってお粗末と言わざるを得ない内容であった。
6.政治家も官僚も出生率低下を読み違え
少子化の議論を整理しておきたい。 1990年代に出てきたのが、女性の社会進出否定論である。「女性が社会に進出するから子供を生まなくなる」というもので、昭和30年代の女子大生亡国論に似ていた。実は当時の厚生省でも同様の声が上がっていた。 90年代後半には「第三次ベビーブーム到来論」も挙がっていた。誰が何の根拠で言い出したかはともかく、「現在の出生率の低下は、第三次の波が来るまでのこと」という専門家の話を、霞が関は素直に受け入れてしまったのである。 本来は年金制度構築のためにも、合計特殊出生率の低下をもっと詳細に分析すべきであった。平均寿命の伸びがどのように影響するかについても、極めて楽観的に捉えていた。そこに合理的な理由は一切なかったと言ってよい。 2000年以降、予想を上回る平均寿命の伸びと合計特殊出生率低下に直面し、2004年の年金法改正の際に給付額が大幅に減少する。かつては月に30万円が給付されても珍しくはなかったが、現状は高額でも月20万円。近い将来にはさらに減少する可能性がある。政治家も官僚も長年にわたって、合計特殊出生率・平均寿命の状況を読み間違えたと言わざるを得ない。 実は年金法が成立する直前、合計特殊出生率がわずかに上昇しているという情報があった。しかし、法律が成立するまでその事実が伏せられたのである。合計特殊出生率や平均寿命をどう分析するかによって、制度設計が決まってくる。担当する官僚は、まさに1億2700万人のための設計図作成という重大な責任を担うことになる。 次に金銭給付論について述べておきたい。これも一時期流行したが、第三子を出生した家庭に数十万円の祝い金を出す制度である。菅直人氏が厚生相だった時、八丈島で採用していた施策を視察し、「第三子の出生に対して100万円の祝い金を出す法律」の作成の指示を受けた。しかし、国家規模で導入するには予算上不可能ですと説明させていただいた。 その他、出会い機会提供論というお見合い政策などもあった。予算はさほどかからなかったが、結局失敗に終わった。子育て環境論、つまり良い環境を提供すれば出生数が増えるという議論は現在も続いている。
7.短絡的な女性活用論
2000年代には若者の非正規雇用問題が浮上する。非正規雇用と婚姻率は反比例の関係にあり、特に男性の場合、正規・非正規の間で有配偶率の差が大きい。中でも35~39歳層では正規雇用労働者の有配偶率は約7割であるのに対して、非正規雇用労働者は約3割にとどまっている。現在も、正規雇用を増やすことが最優先課題だと指摘される。 最近は女性活用論などが盛んである。ただ、安倍首相の女性活用論には疑問を感じる。例えば霞が関のキャリア人事では、単純に女性の採用を増やすという短絡的な雰囲気がある。 何でも“象徴的に”女性を活用するというのではなく、麓にいる多くの女性の底上げのほうがはるかに重要である。中小企業の事務職、保育士、介護職、製造業に携わる女性など、彼女たちを底上げしてこそ出生率アップにも結びつく。政治家、大臣になった女性が業績を残して、後輩の女性たちを引き上げたという話は、残念ながらほとんど聞いたことがない。 この他、社会保障改革の議論も繰り返し行われてきた。社会保障は若い世代から高齢の世代にお金を渡すという仕組みだが、これを廃止するという議論である。スウェーデンではエーデル改革によって、社会保障をすべて積み立て方式にすることで世代間の負担の公平を実現させた。人口950万人という規模の国だからこそ実現できた政策で、現状に合わせながら適時変更し、運営している。 しかし、1億2700万人の日本でいきなりこのような政策を導入するのは乱暴すぎる。例えば、年金を20万円受け取っている高齢者に対して、「積立金方式に変えるので10万円に変更する」と言い始めると、さすがの日本でも革命が起きるかもしれない。現実的には給付を徐々に減らして対応している。 さて、少子化の議論の中で移民政策論は一貫して否定されてきた。 もう一つ、非常に重要な問題でありながらタブー視されてきたのが「加齢と妊娠率」の関係である。加齢とともに生殖機能が低下していくことについて、日本では間違った認識をしている女性が実に多い。 ある調査によると「生理がある間は子供が生まれる」と考えている女性が、イギリスやフランスでは1割未満であるのに対して、日本では実に8割を超えている。この認識の誤りが少なからず少子化促進の一因になっている。ところが日本では、この問題がタブー視され、議論にさえ上らない。妊娠率は22歳をピークに低下していく。30歳を超えると急激に下がり、30代後半では3割の女性は妊娠できないという。では男性はどうか。アメリカの研究では、高齢の男性と若い女性の間で生まれた子供は精神疾患にかかりやすいというデータもある。 間違いなく言えることは、人間にも生物的適齢期があり、出産の適齢期は20代だということである。こうした事実をもっとPRしていくべきだろう。
8.少子化問題が「女子労働の改善」に偏る
政策官庁・厚生省のボトルネックを再度列挙すると、「介護保険が優先された」「女・子供の仕事として軽視された」。加えて「厚生省と労働省が一緒になった」ことがある。 私は厚生省の立場で、医療や福祉、子供の視点から行政に携わってきた。しかし、労働省は女子労働という視点で少子化問題を扱おうとしている。「子供の健全育成」という福祉の視点では「保育所に入れっぱなし」という発想は出てこない。例えば「24時間保育所」の発想は女子労働の視点から出てきたものである。 女性職員が少なく「少子化は女子供の話なので女性にやらせよう」と考えている厚生省と、女性職員が比較的多い労働省が省庁再編で統合された結果、局長には全て労働省出身者が就任した。だから、少子化問題は「女子労働の改善」という視点で捉えられるようになり、「子供の健全育成」の視点がない体制になっている。これは現在も続いている重大な問題である。 また、国と地方の関係にも大きな問題が存在する。一言で言えば、中央官庁は地方自治体を尊重していない。少子化対策基本法でも大綱でも、自治体の扱われ方が小さいのである。最後に「自治体や企業も協力してほしい」といった意味の文言が出てくる程度。官庁は「待機児童ゼロを目指す」というが、私が住んでいる茨城県には待機児童など存在しない。官僚は、全国が東京と同じだと思い込んでいるのである。 これは地方創生にも関わる問題だが、国は規制をしすぎている。「交付金をこれだけ出す。標準型はこうなるので、ここを目指してプランを考えてほしい」と。査定基準も今までとほとんど変わっていない。交付金を渡して、もっと地方の創造性や独創性が発揮されるようにすべきであり、そもそも自治体をもっと尊重すべきである。
9.各国の少子化予算と出生率の推移
家族給付という視点で、諸外国の少子化対策予算を比較してみる。合計特殊出生率が2.01のフランスではGDPの3.2%を給付に当てている。また、1.98のスウェーデンでもGDPの3.8%を給付している。 一方、合計特殊出生率が1.39の日本では0.96%、日本以上に少子化が進む出生率1.23の韓国でもGDPの0.8%しか給付に当てていない。 次に、主な先進国の合計特殊出生率について。アメリカのベビーブームは1946年から19年間続いた。70から80年代にかけて、先進国は軒並み合計特殊出生率が低下したが、アメリカは現在も2.0を維持している。移民が多いというアメリカの社会的事情があるが、特にスペイン系移民の出生率が高い。ヨーロッパも昔から移民は多い。ただ、移民一世の出生率は高いが、移民二世はその地の国民と同じ出生率になる傾向がある。 また、1990年代以降、かつて三国軍事同盟を結んだ日本、ドイツ、イタリアの出生率が低下した。ドイツでは、ナチス時代の家庭婦人対策の影響がある。「女は家庭にいて金髪を生め」という政策だったが、これが次の世代のトラウマになっている。日本の「生めよ 増やせよ政策」が戦後タブー視されたのと似ている。 イタリアは1970年代に離婚法が制定され、初めて離婚が認められるようになった。それまでは男が強ければ子供が多いと言われていたので、「出産を強要されるのは嫌だ」という雰囲気が女性の間で広がった。
10.各国の少子化対策
各国の家族政策を簡単に紹介する。スウェーデンでは、1981年の「親保険」の改正が効果的であった。女性が出産し子育てをする際の休業補償をアップすることに少子化対策の軸を置いたのである。第一子と第二子の間をおかずに生んだ場合には、より大きな休業補償を出すとしたことで、全国で続々と第二子まで生まれるようになった。もちろんスウェーデンの国民性も大きく影響しているが、改正ゆえに多くの子が生まれたのは事実である。 ドイツでも金銭給付はあったが、スウェーデンとは国民性が違い、それほど大きな効果はなかった。ドイツには、子供は母親が育てるべきという伝統的子育て観があり、小学校でも給食がない。つまり家庭で食事を用意しなければならないのである。 フランスは、家族政策のオンパレード。日本にない政策としては、子供がいる家庭に支給される住宅手当がある。日本では持ち家政策なので、住宅政策を福祉政策とは考えていない。OECDの中でも珍しい例である。 近年はアジアでも、出生率が急激に低下している。香港、シンガポール、韓国は日本よりも低く、未婚率も高い。中国は一人っ子政策の影響で男女の割合が6対5となって、結婚できない男性が増えている。少子高齢化が急速に進み、ようやく一人っ子政策の廃止を発表した。 もう一度日本と諸外国を比べると、教育費に関しては、日本は公費の割合が少ない。日本は私立大学が多く、国民にとって教育費の負担はかなり大きいものである。これは「現金給付と現物給付の比較」にもつながるが、スウェーデン、フランス、フィンランドなど出生率が高い国は現物給付に力を入れている。フランスでは学費は無料、というようにサービスそのものを給付する。 一方、日米韓は現物給付が少ない。実際、金銭給付では出生率アップにつながっていない場合が多い。子ども手当を実施した際に、何にお金を使ったかを調査したところ「1に貯金、2に家賃、3に子供」という結果だった。
11.提言
最後に、次の5点を提言し、まとめとしたい。 第一に、経済政策に人口政策を組み入れる。消費が回らないと経済も回らないので、経済政策の中の人口政策として国をあげて取り組んでいく。縦割り行政の日本では、政府から各省へ人口政策としての役割を与えていくべき。少子化という言葉はやめて、「女子供の仕事だ」という先入観を払拭させる。 第二に、若者の声を優先する。 第三に、教育費の問題を改善していく。低出生率の対策として保育所ばかりが注目されやすいが、実際は教育費がかかりすぎることに大きな要因がある。これを改善しなければならない。 第四に、現物給付でなければ、少子化対策に直接の効果はない。 第五に、適齢出産について。人間には生物的な適齢期があることを堂々と教えるべき。25歳で二人生むのは容易だとしても、35歳で二人生むのは生物学的に見て困難である。
(2015年10月2日に開催された政策研究会における発題を整理してまとめた)