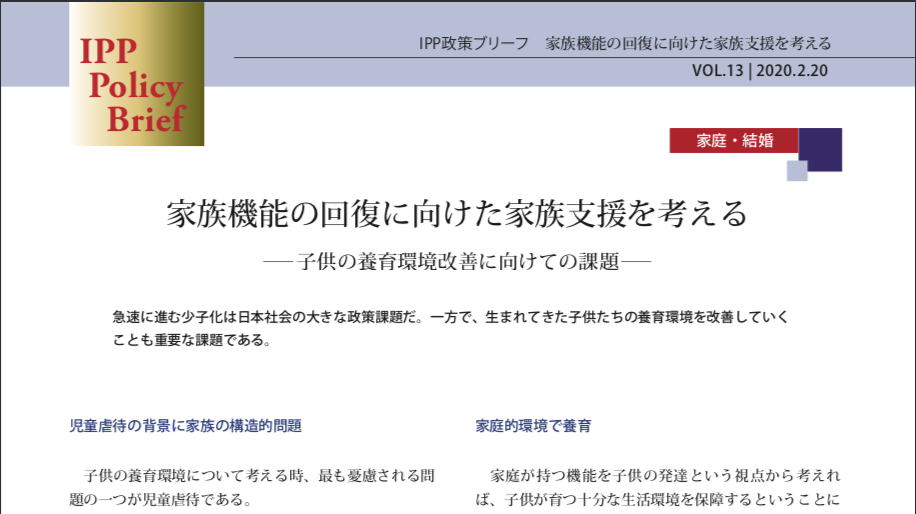1. はじめに
いま、各国で、優秀学生の資質をさらに伸ばすことに多くの関心が払われている。そこでは、学生エリートにはかなり高いハードルの課題が提示される。しかし、その要求に応えられなければ、途中で参加資格を失う。厳しい課題や要求を突きつけるのは、学生エリートこそが、将来リーダーとして、高い志を持ち、それを実現しようとする強固な意思を持つことが期待されるからである。現実には、高度の知を援用しつつ、困難な社会的問題の解決、国家レベルでの責任ある意思決定、また特に科学技術研究の場合は“自然”との厳しい闘いに直面する可能性が高いからである。ときには、利害の衝突を引き起こしたり、予期せぬ駆け引きに巻き込まれたりするなど、問題解決に極限の精神力が求められることもある。各国では、予期的リーダーとしての学生エリートを選良し、またそのような極限をも考慮しつつ、彼らの資質を徹底的に伸ばすような養成プログラムの開発・運用を押し進めているのである。
そこで、本稿では第一に、学生エリート養成に焦点を当てる。まずは、優秀学生に対する特別措置を整理し、本養成プログラムの位置づけを行う(2節)。その養成プログラムは、外国では、アメリカと中国で開発事例が多い。そこで、日米中3カ国の実施状況を概観する。日本は、筑波大学の大学院向けプログラムの実施状況を垣間見る(3節)。また、高等教育の社会的背景や養成プログラムに対する意識的背景をまとめる(4節)。そして、今後日本で養成プログラムを開発するにあたって留意すべき事柄をまとめるため、アメリカでのその開発・運用方針を参考にしつつ、考察を行う(5節)。
第二に、学生エリート養成プログラムの課題を含みつつ、これをより広く捉え、人材育成一般に焦点を当てる。そこでは、植物モデルを用いた規範的人材育成論を構成する。そして、これをキャリア形成のための一モデルとして用いることを提案している。その適用例として、ある研究エリート/実業エリートの生涯を樹木で表現する(6節)。最後に、2節~6節のまとめとして、学生エリート養成企画に資する組織開発と人材育成を推進するための法制化を政策提言している。科学技術時代に相応しい人材育成基本法に関することである(7節)。
2. 優秀学生の特別措置とエリート養成
(1)エリートとオナーズ
国語辞典によれば、エリートとは「選り抜きの人々」とある。つまり選良という意味である。アメリカで実施している優秀学生のための養成プログラムは、後述のように一定の学力を前提としている。したがって、彼らを学生エリートと呼ぶことができる。
しかし、アメリカでは、そのプログラムをオナーズプログラムと呼ぶことが多い。また、そのプログラムを受講する学生をオナーズ学生と呼び、その授業クラスをオナーズクラスなどと呼ぶ。つまり、アメリカでは、“オナーズ”がその企画のキーワードとなっている。
一方、中国では、同様の主旨の企画に対して、その企画者の氏名を冠することが多い。あるいは、××実験班などという表記もあって、プログラムの名称は一定しない。
そこで、該当するプログラムや学生の総称として、アメリカでは“オナーズ”を用いた。それ以外の場合は、個別の呼称や“エリート”を用いた。以下の記述では、文脈によりこれらの用語が混在する。
(2)学生エリートの特別措置
野地[1]は、オナーズプログラムを、ある一定程度の成績を収めた学生のみが履修できるプログラム、と定めている。そのようなプログラムは、表2.1のようにまとめることができる。“促進”の代表例は、いわゆる飛び級である。“拡充”は、通常の履修とは別に、何らかの優れた資質をもつ個人や集団を対象にして、それをさらに伸ばすために準備した企画である。建学理念を養成するような私塾形式の企画もこれに相当する。
アメリカのオナーズプログラムは、同表の“観点”の比較で明らかなように、“促進”にも“拡充”にも該当しない。新たなタイプとして“オナーズ”を設ける必要がある。
表2.2は、学生エリートを対象とした特別措置をまとめたものである。Level1の“教育(養成)”に対しては、表2.1で示した“タイプ”をそのままLevel2としている。さらに、アメリカで実施されているオナーズプログラムを概観すると、Level2の“オナーズ”は、表中のLevel3のように4つのカテゴリーに区分することができる。
“経済”は、奨学金が代表例である。経済的に困窮の学生を対象とするニードベースと優秀学生を対象とするメリットベースがある。本稿での奨学金は、メリットベースに該当する。
“栄誉”は、学生エリートに何らかの特典を与えたり優秀さを表彰したりするような企画を指す。
(3)教育上の機会均等
大学入学後の学生は、一定の学力が保証されたことになっている。しかし、入学者の学力はやはり相応の差があるのがふつうである。それを、便宜上、表2.3に示すように、低学力、中学力、高学力に分けておこう。学生エリートは、その中で、高学力(さらには超高学力)に相当する。いずれの学力者も同じ経済負担が求められているはずである。そこで、教育上の機会均等を考察してみよう。
表2.3において、“中学力”は、通常のカリキュラムで対応する。そして、カリキュラムの策定は、所定の卒業生像を想定し、その学力レベルを満たすように構成するはずである。その焦点は、“~数年先”であり、近未来とみなすことができる。
“低学力”は、“中学力”に比べれば、そのままでは授業に難を感じることが多いはずである。ときには、授業の前提知識を欠いていることもある。その場合は、授業開始前にどの知識が不足しているのかを把握し、対処しなければならない。直前のリメディアル対応である。したがって、焦点の当て先は、“直近”である。
それならば、“高学力”に対しても、その学力に相応しい対応を図らなければ、“機会均等”に疑問が生じるはずである。
高学力”に対しては、“低学力”、“中学力”から類推するならば、“焦点の当て先”は“遠未来”である。つまり、数十年先の“職業エリート時”である。しかし、高学力者の中には、20代で会社経営を担うこともあるだろう。したがって、その時期は、“~数十年先“との表記になる。
低学力者に対しては、何らかのリメディアル対応を図らないと、退学の懸念が生じる。それに比べれば、高学力者への対処は緊急性が低い。しかし、緊急性が高くない事柄は後回し、という優先順位だけを問題するのでは、いつまで経っても何もしない、ということになり兼ねない。この点は、大学人の長期的視野vs.短期的視野という課題のようにも思える。先の表2.3に戻るなら、2段目最右欄の“?”のセル部分を問題にすべきなのである。
3. 国内外の養成プログラム
(1)アメリカ
(i)発展の経緯 優秀学生に養成的特別措置を採ったのは、19世紀初頭のベルリン大学とされている。神学部と哲学部333名の中から40名を選抜してゼミナールを行った[3]。アメリカでは、1922年にペンシルバニア州の小規模のリベラルアーツカレッジであるスワスモアカレッジでスタートした。F.アイデロットが、オックスフォード大学で行われていた優秀学生の教育をモデルにしたのである。これが、今日のオナーズプログラムの原型となった。小規模授業、個別指導方式、セミナー形式の授業等を特徴とする[4]。
アメリカでは、大学進学率が1917年には5%未満であったのが、その後20年間に15%となった。大学の大衆化である。おのずと卓越性の確保が課題となる。1920年代には、3つのオナー協会が設立された。アメリカ・オナー協会(NHS)、カレッジ・オナー協会(AHCS)、アメリカ・ジュニア・オナー協会(NJHS)である。時代が下り、1966年には、アメリカ大学オナーズ委員会(NCHC:National Collegiate Honors Council)が設立され、今日に至っている。
NHSでは、学業に対する熱意、奉仕の精神、リーダーシップの向上、人格の形成を趣旨とした。NJHSでは、それに加えて市民性の育成を趣旨とした。
NCHCでは、各大学のオナーズ活動を調査し、その結果をWebや印刷物で公表している。また、定期的に全国的な集会を開催して情報交換を行い、アメリカのオナーズ活動を推進している。
(ii)特徴 以上のように、アメリカのオナーズプログラムは約100年の歴史があるが、2000年以降には、600弱以上の大学でオナーズプログラムが稼働している。特徴として、以下の4点が挙げられる。
4年間のプログラムの場合、1~2年次(前半)には基礎的科目を、3~4年次(後半)には専門的科目や社会サービスに関する科目を重視している。
コミュニケーションスキルを重視している。授業参加者間の相互作用を意味するが、授業外活動に関しても、例えば、オナーズ寮での他のオナーズ学生との交流や、学内外の学識者との交流を求めることがある。
リーダーシップを重視している。オナーズ学生が下位学年の世話役をすることで、リーダーシップの養成を図ることがある。
学業成績を維持できないとオナーズプログラムから排除される。
上記のうち、最初の3つの特徴は、一般学生対象のプログラムの場合でもほぼ同じである。
また、オナーズに関するいくつかの統計的特徴を示しておく[5]。プログラムが4年間に跨る企画が、85%で、2年間に跨るのが15%である。設置区分は、公立が65%、私立が35%である。プログラムの規模は、100人未満が35%、100人以上で500人以下であるのが45%、500人超が19%である。
(2)中国
(i)発展の経緯[6] 中国では、1990年以降、計画経済から市場経済への体制の移行と情報通信技術の進展に伴う経済のグローバル化という現象を経験することとなった。それが高等教育にもインパクトを与え、特に、市場原理が大学に導入されたのに伴って、大学が企業や地域社会とより連携を深めることとなった。また、グローバル化の進展で、大学の国際化も活発になった。
国家政策としては、90年代前半の211工程と後半の985工程が挙げられる。211工程では、中央政府による学士課程カリキュラムの改革や重点大学・学科の設置等により、世界一流大学の創建を目指すこととなった。985工程では、 高等教育の大衆化の実現と質的向上という大学改革を重要な課題とした。
中国における優秀生対象の教育プログラムは、後述のように、70年代に始まり、90年代に急激な量的拡大を示したが、時期的には既述の大学改革の流れの中で進められたことになる。
その開発は、2000年代にも続き、2005年ごろまでに少なくとも40の重点大学で進められた。重点大学は100余指定されたが、優秀学生向けの教育プログラムはそれ以外の大学にも設置されている。
(ii)特徴 3つ挙げておこう[7]。
第一に、4年間のクラスでは、1~2年次を基礎段階とし、3~4年次を専門段階とみなして研究活動等に従事させている。これは、「2+2」モデルと呼ばれている。
第二に、英語力の強化に対する関心が高い。学年ごとに英語国家試験で所定の成績を求めることもある。
第三は、学業の不振者を排除する体制がある。
(iii)事例 華東師範大学では、1994年に「21世紀人材学院」を設立した。そこでの募集と修学の要件を見てみよう。
募集人数は、50名~60名である。要件として、道徳、知力、体育などで総合的に発達しており、(学業における)基礎力と発達面の双方を兼ね備えた学生であること、と示されている。また、卒業時に以下の項目でどれか1つに当てはまると、卒業することができない。
-授業に関し、6回以上の無断欠席者
-社会実践への不参加者
-協力課題研究を行っていない者
-授業中、メモをしていない者
-国家英語試験6級あるいは上海市PC試験の中級に不合格の者
-学院入所後、新しい成果を挙げていない者。例えば、英語6級とパソコン中級試験に合格したものの、在学中、専門雑誌で論文を発表したことがない者。
-学院の規制に違反した者
-評価による不合格者
(3)アメリカと中国の比較[5]
(i)設立年 1950年~2005年に関し、学生エリート対象の養成プログラムの設立年を調査した。表3.1は、両国のそれぞれで、設立数の総数に対する割合を示したものである。この結果から、中国では、時代が下るにつれて設立数が急増しているのに対し、アメリカでは、そのような傾向が見られない。アメリカでは、1950年代に比し1960年代で急激に増加している。これは、50年代末に起きた、米ソの宇宙開発でソビエトに先を越されたことによるいわゆるスプートニクショックに刺激されたのが、その原因とされている。
設立年の調査方法は、次のようである:アメリカについては、[8]と[9]の双方に紹介された大学のうち、公立大学を対象とした。中国については、重点大学を対象とした[7]。
(ii)用語調査 上記の調査対象とした大学について、養成プログラムの紹介文に含まれる用語を調査した。その結果を図3.1に示す。紹介文の中に同図の右に示したa~eの項目に該当する概念用語が1度でも現れたら、その概念に該当する紹介文、と判断してカウントした。
図3.1は、米中の結果を比較したものである。アメリカではコミュニケーションの重視という特徴があり、中国では伝統的な学問に対する意識の高さという特徴がある。
いずれの国の場合も、日本語訳にて調査した。当該概念に相当するか否かの判断には、恣意性を排除できないので、概略の比較に止まる。また、語数は、両国で統計的な有意差がないことが分っている。
(4)日本
養成プログラム事例として、九州大学の21世紀プログラム、筑波大学の大学院オナーズプログラム、愛媛大学の学生リーダー養成プログラム、早稲田大学のグローバルオナーズカレッジ、立命館大学の人材養成特別プログラムが知られている。以下、科学技術系の大学院生向けプログラムとして、筑波大学を紹介する[5]。
(i)経緯 文部科学省概算要求特別経費産学連携プロジェクトの一環として、2010年度に開始した5年間の時限プログラムである。ナノエレクトロニクスの人材養成を目的とする。大学院博士後期課程の学生を対象とする。
このプログジェクトは、筑波の地域的な特色を背景として企画が進められた。すなわち、筑波大学の誕生後、数十年の間に、研究施設や先端企業が集積した。しかし、知の相乗・集積効果が現れていないとの見方があった。そこで、産学独が連携を図ることを特色とするプロジェクトが誕生した。
(ii)特色 以下の6点が挙げられる。
-“共鳴場”での長期OJT:3年間の研究活動で培ったスキルを将来の仕事に活かそうと試みる。
-連携コーディネータ:国際的に著名な産学独の研究経験者7~9名を配置する。
-産学独アドバイザによる教育:各学生に産学独から1名を配置する。
-国内の他大学との教育・研究連携:東京工業大学、東京理科大学、早稲田大学から学生6名を受け入れている。また、大阪大学のテレビ講義に参加する体制を採っている。
-海外拠点との交換プログラム:国際的環境での研究討論や発表能力の育成を図るため、海外大学の大学院授業を履修する制度を設けている。フランス・グルノーブル/MINATECやベルギー・ルーベン大学/IMEC等。
-学生選抜と財政・学生支援:学生は、公募と審査で選抜している。また、毎年度、オナーズ学生に奨学金として70~200万円を給付している(SRA)。
(iii)評価 3年次を終了した時点で、プログラム評価を行った。その結果を表3.2に示す。10項目と総合評価で構成されている。評価者は、国内大学教員2名、アメリカ大学教員2名、国内企業幹部職員2名、国内公的機関幹部職員2名の、合計8名である。評価結果は、高い方から、S、A、B、Cで、総合評価では「最多」欄でSを得ていることがわかる。
4. 高等教育の背景
(1)社会的背景
日本の学生エリート養成プログラムの社会的背景として、3つ挙げることができる。
(i)知識社会化 第一の背景は、知識社会化である。知識社会では、技術の知識が価値を持つ。ここでいう技術は、「自然法則(または公理)をうまく組み合わせて所望の高度の有機体(または処理体系)を構成する仕組み」を指している[10]。また、その仕組みを熟知した人を技術者と呼ぶ。高度な技術的有機体が社会的価値を持つ時代なのである。したがって、技術的知識の斬新さが直接、ビジネス競争の根源となる。技術者は、斬新な知識を得ようと、常に継続的な学習を心がける。また、学習した高度な知識を戦略的に活用するため、さまざまな工夫を試みる:技術者の研修、産学間の人材交流、同じく知の連携、学生エリートの求人、大学における寄付講座、等々。
新たな知識に対する意欲は、企業人にとどまらない。一般の社会人も、技術革新時代に遅れまいと学習意欲を燃やす。そのため、人々は、大学卒業後も継続的に学習を求めるようになる。
上記のような現況に対し、大学には、学習者の資質に相応しい教育・研究機能を最適化することが求められる。本稿の趣旨に即すならば、高度の知が期待される学生エリートに関して、その資質に相応しい高等教育の制度が求められるのである。
知識の範囲は、上記の技術的知識に止まらない:新たな知識がどの程度長期的な価値を持つかを問われる時代でもある。AIは、人間の仕事を奪うのかそれとも補助するのか。しかもAIは、どんどん進化するから、ダイナミックな大局的判断力が求められる。通常の知識に加えて、そのようなメタ知識も求められる。
(ii)国際化・グローバル化 第二の背景は、国際化・グローバル化である。技術を原動力とした有形・無形の社会的インフラが整備され、これが国際化・グローバル化を推し進めた。技術革新が通信容量を飛躍的に増大させ、大容量のコンテンツの高速電送も可能になった。輸送インフラについても、ローコストの移動を可能にしている。人やモノの移動が容易になり、情報通信を駆使した国際的な巨大企業が現れるなど、市場経済の大変革をもたらしている。
国際化・グローバル化の波は、高等教育にも変革をもたらしている。その一つが遠隔教育である。マサチューセッツ工科大学は、2001年に授業シラバスをオープンコースウェアという形でWeb上に公開した。その後、シラバスのみならず著名な教授による授業ビデオの閲覧も可能にした。それを大規模化した高等教育向け無料オンラインMOOCsも、グローバルに広がっている。インターネットにアクセス可能であれば、どの地域でも同じオンライン授業に参加することができる。
また、その学習を通じて優秀とみなされた学習者を、オンライン授業の提供者が関連企業に紹介するという事例報告もある。オンライン授業自体が、結果的に、労働力の人的受給の手段にもなっているのである。高度な情報技術を駆使したオンラインシステムが、高等教育の国際化と市場化をさらに推し進めるに違いない。学生エリートなどは、真っ先にその市場化の対象になるだろう。それをも視野に入れた大学教育体制が求められるのである。
無料であったはずのMOOCsは、2018年になって有料化の動きがある。諸般がダイナミックに変動する時代であるので、高等教育にも、諸情報に常にアンテナを張りつつ、変化を恐れない柔軟な体制が求められる。
(iii)大衆化 第三の背景は、高等教育の大衆化である。大学等進学率は、2005年(平成17年)現在、図4.1に示すように、50%前後である。同じ図で、高等進学率がその値を示すのは、1950年代後半(昭和30年代前半)である。したがって、単純に見れば、進学率に関するかぎり半世紀ほどの間に教育課程の機関ランクが一つ下がったことになる。つまり、大学学士課程段階のエリート性が減少したのであるから、平均的学力が低下したことが明るみに出ても、不思議ではない。
学力や学習者が多様化すると、授業自体にもそれなりの工夫が必要になる。いわば、授業の実質化である。ここに学生エリートの課題が浮上する。
なぜ多くの高校生が大学に進学するようになったのだろうか。高度な知の獲得が就業を確実にする時代と相成ったからという理屈があるだろう。それとともに、「皆がいくのだから…」とか「大学ぐらい出ていなければ…」というありふれた風潮も無視できないように思われる。
なお、18歳人口減少も、日本の社会的背景の大きな一つである。間接的に学習者の多様化につながることが予見される。その意味では、この課題は上記「(iii)大衆化」の範疇となる。しかし、ここでは、議論の対象から外す。
(2)図式化
以上に述べた3つの社会的背景に対して、学生エリート養成を図4.2のように位置付けることができる。以下は、同図の説明である。「」内の用語は、図中の用語でもある。
この企画は、同図上部に示すように一種の人材育成である。一方、既述の3つの社会的背景は、同下部に示すように技術革新の上に成り立つ。
「知識社会化」は、技術の高度化に伴い、技術的知識が価値を持つ社会と相成ったことに由来する。技術の高度化は、「知の連携と競争」をもたらしている。それを全うするために、知の「継続的な学習」が求められる。そのような環境の中で、学生エリートには、知の獲得のみならず「リーダーシップ」が期待されている。
「グローバル化・国際化」は、情報・輸送インフラが充実する中で、高等教育の市場化をもたらした。学生エリートは、当然ながら、その「市場化」の対象となる。
「大衆化」は、高度な知の獲得が就業を確実にする知識社会の時代と相成り、多くの人が知を求めて大学に集合するようになる。大衆化と相成れば、「学力が多様化」し、「授業の実質化」が求められる。自ずと、学生エリートの特別措置にも関心が生じてくる。
以上に述べたような高等教育の社会的背景のいずれからも、学生エリート養成企画の推進が求められるのである。彼らには、将来、各自の進路でリーダーシップを発揮することが期待されている。学生エリートの存在は、技術革新という視点からも、またリーダーシップを含む人材育成論という視点からも、クローズアップされなければならない。
(3)意識的背景
2節冒頭に述べたように、エリートは、選良された存在である。将来、国家や社会をリードすることが期待される重要な存在である。しかし、日本では、エリートという言葉を積極的な意味ではあまり使いたがらないようだ。むしろ、不問に伏す傾向がある。いわばマイナスイメージである。なぜそうなのか。その理由は、以下のように考察できる。
目標を一にする集団の中から何らかの基準で選良された人たちは、エリートと呼ばれる。そのように選ばれると、エリートには、自ずと一般人に対する意識が芽生える。さまざまな優遇措置の運用に伴い、特権意識もそれなりに高まる。そして、一般人は、そのことをよく知っている。問題は、そのような選良感(または優越感)と、エリートに養成された国家的・社会的使命感とを天秤にかけたときに、後者が前者に優っているか否かである。
このとき、一般人にとって使命感が選良感に優るようなエリート言動と感じるなら、プラスイメージを引き起こす。逆なら、マイナスイメージを引き起こす。要するに、そのプラス・マイナスは、両者の比較結果に直接依存して定まるということである。したがって、たとえマイナスを引き起こしたとしても、エリート養成の存在に問題があるのではない。養成の内容に問題があるのだ。そこに混同があると、“エリート”なる文字列を見ただけで、マイナスイメージが現れる。もしマイナスを感じたら、当該養成プログラムに使命感を扱う養成内容を強化する必要があるのではないかと、プラスの問題提起をすべきである。使命感が選良感より“重く”なるようにエリート意識を涵養するのが、エリート養成の一大使命なのである。比喩的には、図4.3の右と左では、左図が歓迎される人材像なのである。
5. 養成プログラムの開発と運用
L.Adaは、かつて、アメリカのオナーズプログラムの開発・運用に資すると思われるガイドラインを作成した[12]。そこでは、特に、オナーズカレッジのディレクタの資質を論じている。これを参考にしつつ、日本での養成プログラムの開発・運用にあたって検討すべき事柄をまとめる。
(1)ディレクタの資質
(i)役割の二重性 オナーズカレッジのディレクタは、ファカルティとアドミニストレータの2つの役割が求められる。
そのため、Godowは、オナーズディレクタの選抜基準を表5.1のようにまとめている。つまり、同表内の最左欄に示すaからfの6つをクリアしなければならない。そして、中央欄と最右欄に示す要件等からすると、ファカルティとアドミニストレータの資質が異なることが理解される。
ちなみに、領域別のファカルティが概ね持っていると思われる資質とアドミニストレータのそれを比較するため、表5.2を作成した。同表において、職種例として理学のファカルティを取り上げ、これをアドミニストレータと比較する。すると、かなりの部分において、両者の資質が異なるものと理解される。
(ii)業務の多重性 オナーズディレクタには、定常業務のほか、多くの非定常業務が必要とされる。
定常業務として、予算の獲得、年次報告、学生データベースのメンテナンス、スタッフの監督、危機管理等。また、非定常業務として、カリキュラム開発、学生のリクルート、入学業務、スカラーシップ、所外との連携、学生へのアドバイス、教員のリクルート、オナーズ関連の学外活動。
(2)開発の推進
日本の大学でその推進に寄与する事柄は、以下の3点である。
キーパーソンがいるか:これを積極的に進めようとする学内教職員がいるかどうかである。そのキーパーソンを中心とし、組織体制を組むことができれば、持続可能性が高まる。
日本の大学で、先進的と思わせる教育体制を見聞しても、ある時点で、稼働が停止していることがある。特定のキーパーソンが転出してしまったためである。活動を持続させ進化させるには、活動が組織的になされていることが前提である。
また、日本の大学に適したディレクタの選抜基準の検討が必要である。教職連携という業務形態も検討の対象となるであろう。
予算措置が可能か:養成プログラムの開発と運用では、比較的少人数の学生に対してディレクタとスタッフが貼り付く。そのためには、相応の予算措置が必要になる。持続可能な企画とするには、安定した予算措置が必要である。
学内協力が得られるか:学内教員からは、この企画に対する理解だけでなく、業務負担についての理解が必要である。それをどのような形で依頼するか、教育業績をとしてどのように扱うかを決めることが必要である。
6. 樹木理論:植物モデルによる人材育成論の提言
3節で述べた学生エリート養成プログラムは、何を規範として構成を図ったらよいのか。本節では、学生エリートの課題を含めて、より広く人材育成の課題として考えよう。人材育成の基本像として、植物の生長の様態をモデル化する。一つの規範的人材育成論に関する提言である。
(1)基礎
(i)規範の概念構成 モデルには、(1)言語、(2)数理、(3)図式という3種類の表現形式がある。(1)は、主に人文社会系である。(2)は、理工系である。(3)は領域不特定である。本稿の植物モデルは、(3)図式という形式に該当する。
一方、理工系で扱うモデルには、(a)予測、(b)規範という2種類のタイプがある。(a)は、予測精度の高さが、その価値の高さとなる。天気予報が好例であろう。(b)は、合理性を前提としたモデルである。理の高さが、その価値の高さとなる。理工系では、大多数が予測モデルである。規範モデルは、統計的決定理論やゲーム理論等の意思決定の数理がこれに該当する。
次に、人材育成では、(A)著名人・名言、(B)体験、(C)自然物、という3つのどれかに依拠させつつ、その規範を求めることが多い。いずれに依拠しているかは、各事例の捉え方に依る。例えば、イソップ物語という事例では、動物という自然物に依拠して人間社会のあるべき規範を示唆している。したがって、(C)とみなすことができる。しかし、イソップ自身や知人の体験を素材とし、その素材を自然物に準えて表現した規範と捉えれば、(B)と(C)を組み合わせた依拠となる。一方、ソクラテスの言明は、とりあえず、(A)となる。
本稿で述べる植物モデルは、(C)に該当する。それを含めた比喩をまとめると、その枠組には、(P)動物モデル、(Q)植物モデル、(R)鉱物モデル、の3種類の比喩が含まれる。イソップ物語は、(P)と(R)の比喩による規範が多い[13]。しかし、いずれの比喩でも、そこに現れる主体は、意思を持ったり会話をしたりする。一種の擬人化である。その意味では、イソップ物語は作者自身の恣意が多い。
本稿で述べる規範的人材育成論は、上述したモデルの形式、タイプ、依拠、比喩という4つの概念構成の上に成り立つものである(図6.1)。
(ii)植物モデルに見る規範 本稿で述べる植物モデルの構成では、極力恣意性を排除する。そのため、自然界で生長する植物をそのまま眺めることを基本とする。そこから得られる生長の規範は、以下の4つである。
存在の規範:多くの場合、一つの植物は、地中と空中という2つの環境に存在する。そして、2つの環境の間には、地表という境界が存在する。
順序の規範:植物の種は、地表を含む地中に静止する。その後、空中に芽を伸ばす。つまり、生長の初期の存在場所は、地中が先であり、空中が後である。
均衡の規範:地中部分の生長と空中部分の生長はほぼ同時である。空中部分を先に生長させ、地中部分を後から生長させるような植物は、力学的均衡を保ちにくく、自然界には存在しない。
可測の規範:空中部分の距離的諸量は、ふつうの物差しで測定できる。しかし、地中ではその測定ができない。
(iii)規範の図式化 存在、順序、均衡、可測という4つの規範を、図6.2を用い、簡単な事例とともに説明する。以下、自然物の規範に準じた思考過程を、「自然の流れ」と呼ぶことにしよう。また、説明の都合上、植物を樹木に限定することがある。
図6.2の左側には、3つの事例が示されている。この場合、存在の規範は自明である。すなわち、いずれの概念も「内」と「外」という場所の属性を有する。そして、その間には目に見えない境界がある。国境もその一つである。したがって、不用意な国境軽視は、自然の流れに沿ったものとは言えない。その場合は、理由を明確にして、限定的に考えるのが基本である。
特に情報通信時代には、国境の存在を意識することなく同じプロトコルで情報授受が可能である。植物モデルでは、情報の送受信体が樹木の地中部分と空中部分のいずれに附置されていても区別がないということである。しかしそうであっても、地表という境界は依然として存在する。つまり、“情報通信時代”は、国境の存在を軽視する理由にはならない。それが、存在の規範が意味するところである。
順序の規範については、「家庭」の事例では、「家庭内の関心」を先とし、「家庭外の関心」を後とするのが自然な流れとなる。したがって、家庭内の不和をよそに地域社会の和を求めるのは、自然の流れに沿ったものとはいえない[14]。「組織」と「国」についても、ほぼ同様である。
図6.3は、個人、家庭、地域社会、組織、国、世界なる概念に対して、存在の規範と順序の規範を図式化したものである。
均衡の規範は、先の図6.2右部の(a)、(b)、(c)の事例に示される。(a)の樹木は、(b)のように生長する。常に、地中部分と空中部分が均衡を保つようにほぼ同時に生長する。(c)のように生長させた樹木は、自然の流れに則ったものとは言えず、自然界では生きていくことができない。
可測の規範は、自明である。つまり、空中部分に対する高精度の距離測定は、地中部分に対しては単純には不可能である(しかし、地中部分の生長の具合は、空中部分を揺さぶってみれば、ある程度見当がつく)。
(iv)対概念の図式化 対概念が先の4つの規範のいくつかを満たしていれば、植物モデルで図式化できる可能性がある。その満たすべき数については、ある程度弾力的に考える。
中国古典「菅子」は、「世の中は反対物の結合によって成り立つ」と言い、対概念を挙げている[15]。それを含めて、5つの事例を考える:善と悪、上司と部下、美と醜、知と徳[16]、専門と教養。いずれも日本では対概念とみなされるから、存在の規範を満たすように思われる[18]。しかし、最初の3つは、空中/地中の対応が難しい。これに対して、最後の2つは可測の規範をより満たしやすいので、図式化の対象となる。知と専門は、その生長ぶりをペーパーテスト等何らかの手段で計量しやすいのに対し、徳と教養は比較的計量しにくいと思われるからである。
図6.4は、以上に述べた対概念のうち、植物モデルとして図式化しやすい概念を表示したものである。その中で、ハードスキルとソフトスキルは、それぞれ比較的測定容易なスキルと困難なスキルを表している[20]。また、図6.5は、図6.2内の「国内」と「国外」を、より詳細な要素を含めて図式化したものである。
(v)樹木間の関係 多くの大学では、ハードスキルを重視し、グローバル人材の育成を図ろうとしている。これは、図6.5の空中部分の生長に相当する。一方、地中部分はふだんは目にすることができない。だからこそ、常にその生長への留意が求められる。「測定困難」と「不要」は異なるのである。
先に述べた「空中部分の揺さぶり」の考察をさらに深めよう。図6.5の(b)と(c)を比較する。その空中部分から、同じ生長を遂げた樹木のように見える。しかし、両者が図6.6(a)のように握手をしたものとしよう。その際に、どちらかがその手を多少揺さぶって見れば、どちらも地中の育ち方がある程度比較できる。その後、片方がぐいっと手を引けば、どちらが手を引いたにせよ、両者には同図(b)のように同じ大きさの力Fが逆向きに作用する。その結果、右側の樹木が倒れる。つまり、生長の差は、周囲の樹木との関係において明確になるのである。
では、同図(c)ではどうか。図(b)との相違は、右側の樹木が“より高い知性”の持ち主であるという点である。この状態で、右側の樹木が“上から目線”で握手を求め、左側のが“下から目線”で握手を求めたとする。その後、どちらかが手を強く引っ張ると、右側の樹木が図(b)の場合よりもっと簡単に倒れる。要するに、高度なハードスキルを有するものの、地中部分が発育不良で、しかも“上から目線”で応対すると、その樹木はちょっとした動機で倒れる。やはり、決定的に重要なのは地中部分ということになる。地中部分を周囲の樹木と同じかそれ以上の強度で発育させるのが基本なのである。さらには、“横から目線”が一番自然であろう。そのような発育を前提として、“高い知性”を計らい、しかも“横から目線”による他者対応を計らうのが、人材育成の基本と言える。
上記の考察は、2者間の協調と競合のうち、競合だけを考慮したもののように見えるかもしれないが、双方とも考慮したつもりである。実際、図6.6(c)の右側のような樹木に対して、真剣に協調関係を結ぼうとする樹木があるだろうか。先の図6.5に戻せば、(a)と(b)が健全な樹木である。均衡の規範は、渉外の多いリーダー養成にも参考になると思う。
樹木間の関係は、諸国間の関係にも当てはまる。グローバル人材の育成では、そのような観点が必要である。その際、地中の発育に関しては、関連の深い他国でどのような教育を計らっているかを調査し、それに準じた自国版を作るのが基本となるはずである。そのような養成が、グローバル社会を生き抜くことのできるエリートとなる[21]。
図6.4では、知と徳が対をなすことを示した。空中・地中部分の均衡ある生長が健全な樹木と呼べる。その比喩において、知の高い存在がall mighty とは限らないのである。
特に企業人の場合は、均衡ある人材育成を自分自身の問題として積極的に捉えることが求められる。本提案の規範的人材育成論が、各自のキャリア形成に資することを期待するものである。
(2)応用
研究エリートと実業エリートについて、1名ずつその生涯を植物モデルとして表現する。以下、著名人の場合は、尊称を略すことがある。
(i)研究エリート~木下杢太郎(1885~1945)[22]~
木下杢太郎(本名:太田正雄)は、医学から文学・美術に至るまで幅広い知識を有した。さらには、関心を持ったどの領域もその道の専門家と呼ばれるほどの博識ぶりを示した。
独逸協会中学、第一高等学校、東京帝国大学医科大学を経て、南満医学堂教授兼皮膚科部長、愛知医科大学教授、東北帝大医学部教授、同医学部付属病院長、東京帝大医学部教授を歴任した。また、フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章を授与され、文芸雑誌「文藝」の編集顧問を務めた。
その生涯を、研究人としてのキャリア形成という視点で分析すると、次のようにまとめることができる:
1.杢太郎は、進路選択に関し、自分の意思と親しい人たちからの進言が異なるとき、後者の「進言」をそれなりに尊重している。しかし、自分の意思は、捨て去らずに二義的にそのまま温存させている。
圓三という次兄は、杢太郎にとって最も影響力のあった家人とされる。森鴎外に対しても、師弟関係ではなかったが尊敬の情を持っていたといわれる。家人か否かはともかく、正雄に進言してくれた「親しい人」とは、正雄自身が充分に尊敬できるような幅広い教養と人格を持ち合わせていた人物であった。
2.杢太郎の探求心は、その場の環境・状況やそこに居る人たからの刺激に依ることが多い。いわば、自然発火的な探求心である。そして、一旦火がつくと当該対象を深く追究しようとする:一高入学~医科大学では、ゲーテを読み、三宅克己に洋画を学び、美術評論にも興味をもつ。満州赴任後は、大陸の文化史、仏教美術史を研究する。
3.杢太郎の行動は、有識者から高い評価を得ている:皮膚科学研究者高橋明教授、新詩社同人与謝野晶子等。両者の意見に共通するのは、杢太郎は、人には真似のできない天分を有し、その上、何事にも全神経を払い全力を尽した人物であったという認識である。
4.杢太郎のどの研究活動も、一貫した精神的基礎に基づいている。詳細は、杢太郎自身による言論が示唆している:科学も藝術も其の結果は、世界的のものであり、人道的のものである。然し、其の研究、其の創作は、研究者、創作者の精神の統覚に依従する。其の統覚は国土、時代、国民性から影響せられる。熱烈なる愛国者から生れる科学、藝術の果実も、其の真正なるもの、其の佳良なるものは、やがて世界的であり、人道的であり、両者に何等の矛盾もない。それ等の結果を取って之を特殊の目的に利用するといふことは、これは別の事である。
野田[22]の言論に依れば、杢太郎は「真のユマニスト」である。科学も芸術も、すべてこの精神的基礎から発せられたものである。
杢太郎自身による上記言論は、「健全な愛国心から生れる科学や芸術の成果は、何の矛盾もなく世界的かつ人道的なものである」という意味を含んでいる。つまり、彼の生涯に跨る成長は、図6.7に示すように、土壌に育つ樹木の様態そのものと言えるのである。
杢太郎が、統覚的精神等に根付いた世界的・人道的視野を有していたことは、生涯にわたる彼の行動からも推測できる。彼の人格的基礎の一面を今様の言葉に置き換えて解釈するならば、「グローバル化に伴う活動推進は、必要不可欠なことではある。しかし、常に、永らく培ってきた国民固有の精神(または伝統精神)に根ざしたものでなければならない」ということである。
(ii)実業エリート~アンドリュー・カーネギー(1835-1919)[23]~
鉄鋼で大成功を納めた。スコットランドに生まれ、その後一家でアメリカに移住した。10代半ばから電信局に配達夫、技手として働いた。新聞には機会あるごとに自分の考えを投書した。フィランスロピストの先駆者とされるベンジャミン・フランクリンを尊敬していた。カーネギーの自伝は、フランクリンの自伝とともにアメリカの勤勉精神を伝える傑作とされている。
故郷のスコットランドに公共図書館を寄付し、ピッツバーグ市には百万ドルを寄付した。これにより、同市に、図書館、美術館、女子校、工業学校等が設立された。その一部が、カーネギー・メロン大学である。彼が設立したカーネギー・スチールは、1901年にモーガンに売却された。売却代金の四億ドルを人類福祉のために使うことが、実業界から引退したカーネギーのその後の仕事になった。
多様な労働の経験を経て、鉄鋼で実業エリートとなったが、そこにはフィランスロピー、勤勉、社会奉仕の精神がその基盤に寄与している。その樹木モデルは、図6.8のように表すことができる。カーネギーは、自身にはスコットランド人固有の用心深さがあり、それによって、自分の会社は倒産せずに済んだ、と述懐している。そこで、地中部分に「用心深さ」を記載した。
7. 政策提言
(1)学生エリート養成の推進
2、3節では、米中の学生エリート養成プログラムを概観するとともに、筑波大学の大学院オナーズプログラムを垣間見た。筑波大学の例は、時限予算に依るものであったが、今後日本で、新たなプログラムを組織的に開発・運用するには、それなりの持続的体制が求められる。それには、相応の予算と政策的なきっかけが必要になる。
そこで、各大学にその推進の働きかけを行うオナーズ推進組織の設置を提言する。2節で述べたアメリカ大学オナーズ委員会に対応するものである。日本の場合は、車に準えれば、エンジンのスタータ-モーターの役割を担う組織である。それによってエンジンを始動させ、そのあとには、当該大学の自律的な持続体制を求めるのである。以下に述べるような法制上の裏付けがあれば、より確実な予算的裏付けが可能になろう。
(2)人材育成の推進
1990年代に科学技術基本法が制定され、その後科学技術基本計画が5年ごとに策定されている。いま日本は、科学技術立国としてその1本のレールの上を走っている。しかし、その状態を図式的に見た場合、一輪車よりも、双輪車のほうが見るからに安定感がある(図7.1)。そのもう一本のレールが、人材育成基本法である。
元文部大臣の有馬朗人氏は、第二科学技術基本法を政策提言した[24]。これには、人材育成の課題を多分に含む。そこで、第二の国家的レールとして人材育成基本法の法制化を提言する。そこに、有馬提言と本稿での学生エリート養成プログラム(オナーズプログラム)に関する提言を含めるのである。その基本法は、今日の人材育成・教育課題を視野に入れて、以下の構成とする。
1 大学教育・研究の推進:予算面、組織面
2 技術・技能教育の推進:学校教育、職業人の教育
3 職業人の意識改革:エリート(オナーズ)/リーダー養成
4 科学技術教養:概略的知識、情報の裏読みスキル等のメタスキル
以下、簡単な説明にとどめる。
本稿で述べたオナーズプログラムは、①の「大学教育」または③に含める。大学の運営交付金は、①の「大学での研究」に含める。いま、若手研究者の継続的雇用には重大な課題がある。それを保証する意味でも、予算の継続的措置が求められるのである。②には、企業人のスキルアップが含まれる。その場合のスキルは、コンピュータや英語等のハードスキルを指すことが多い。ソフトスキルは、直接的な評価測定が困難であるために、軽視されやすい。そこで、③の意識改革なる項目が必要になる。そこには、第6節で述べた人材育成論における樹木の地中部分の養成を含む。④は一般社会を対象としたものであり、科学技術時代に必要な教養的知識を指している[25]。
以上が、科学技術時代に相応しい人材育成基本法の構想である。かつて吉田松陰が「…国は人を以て盛なり」と言った。当時は、科学技術という用語はまだなかったかもしれないが、科学技術を創造・運用・利用するのは“人”である。“人”なくして、科学技術は存在し得ない。適正な人材育成があって、初めて科学技術が健全な発達を遂げる。そのために、いま科学技術立国日本には、2本のレールによる安定感のある国家ビジョンが求められているのである。
(本稿は、2018年8月8日に開催したIPP政策研究会における発題を整理してまとめたものである。)
<参考文献等>
[1]能地泰代「選抜型リーダー育成の最前線を追う」『リクルート カレッジマネジメント』2012.
[2]松村暢隆「アメリカの才能教育」『東信堂』2003年.
[3]潮木守一「大学大衆化時代の大学像―フンボルトのリネンをもとに」『世界平和研究』No.196, 2013年.
[4]田中義郎「大学教育において卓越性と多様性の共存を目指すプログラムの開発」『広島大学高等教育開発センター大学論集35』2005年.
[5]北垣郁雄「学生エリート養成プログラム-日本, アメリカ, 中国-」東信堂, 2017.
[6]黄福涛「1990年代以降の中国高等教育の改革と課題」広島大学高等教育研究開発センター叢書, 2005.
[7]北垣郁雄・黄福涛「中国の学生エリート養成企画の調査」『広島大学高等教育開発センター, 高等教育研究叢書』2008年.
[8]Joan Digby ed., Thomson: Peterson’s Smart Choice; Honors Program & Colleges, Thomson Peterson’s, 2005.
[9]Eric Owen, Meltzer Tom, and the staff of the Princeton Review, America’s Best Value Colleges, Random House, Inc., 2006.
[10]併せて, “操作”を, 技術的産物に所定の機能を発揮させる行動, と定義できる。
[11] 文部科学省より
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/shiryo/008.htm
[12]Ada Long, A Handbook for Honors Administration, National Collegiate Honors Council, 1995.
[13]動物モデルの例には,カラスvs.キツネ,がある。鉱物モデルの例には,北風vs.太陽,がある。[14]情報通信時代の家庭の出来事を例示しておこう:母親の愛情ある料理に対し,子供たちは味わいながら食べるのが自然の流れである。その味わいをよそに,スマホに熱中しながらの食事は,自然の流れとは呼びにくい。家庭内不和を引き起こすだろう。それが,存在の規範と順序の規範の示唆するところである。一方,「家庭内の関心」が先とは言っても,既述の家庭料理のように,積極的な関心を前提とする。いわゆる内向き思考や引き籠りは,これには該当しない。
[15]高畠襄『中国古典「菅子」に学ぶ知謀と行動力の極意;男を鍛える』三笠書房, 1986年.
[16]ここでいう徳は,主に使命感を指している。徳は,本来,利他精神を指すようだ[17]。その意味では,使命感は,徳の本来の意味と共通性が高いように感じられる。
[17]菅野覚明「日本の元徳」日本武道館, 2009年.
[18]中国の華東師範大学のエリート養成プログラムでは,入所にあたって,知,徳,体の3者を求めている。一方,精神,心,魂,肉体の4者をすべて知性と解釈する事例もある[19]。そこでは,心が徳に対応していると言えそうだ。
[19]クラウス・シュワブ(世界経済フォーラム訳)「第四次産業革命」日本経済新聞出版社, 2016, pp.141-146.
[20]Han Lei https://bemycareercoach.com/soft-skills/hard-skills-soft-skills.html (参照日 2017.6.10)
[21] エリート性の高い大学の場合は,ほぼ全員の学生が養成プログラムの対象になる。そのときには,彼らの知力を念頭に置きつつ一般学生向けの養成プログラムとして具体化すればよい。
[22]野田宇太郎『木下杢太郎の生涯と藝術』平凡社, 1980年.
[23]アンドリュー・カーネギー(田中孝顕訳):私の履歴書, きこ書房, 1997.
[24]有馬朗人:人材育成へ新基本法を, 日経新聞2017.4.17(11).
[25]北垣郁雄:近未来社会のための技術教養と教育工学研究について, 日本教育工学雑誌, Vol.13, 4, pp.159-164, 1989.