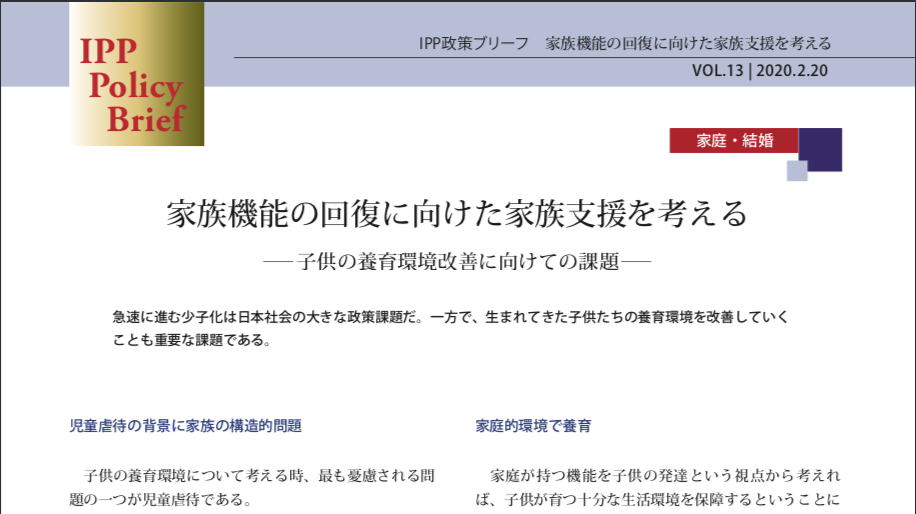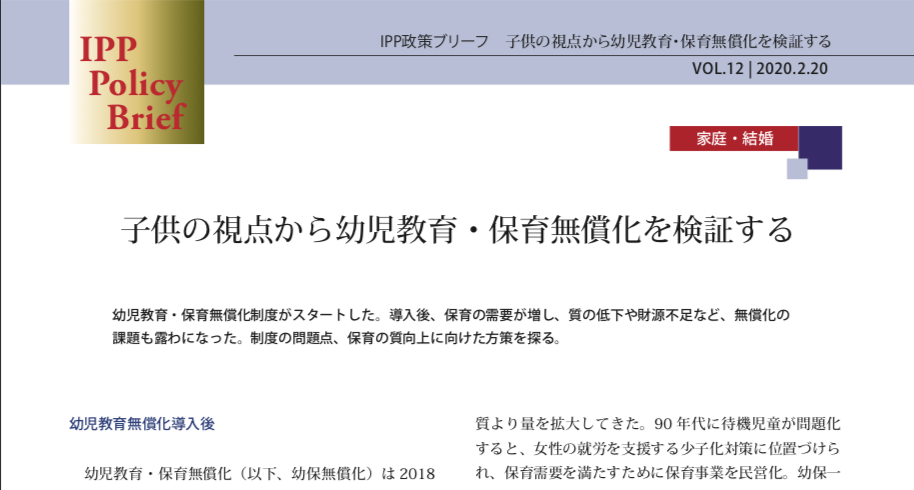相続税制度の制定の背景
わが国は第二次世界大戦(1941~1945年)で無条件降伏をした。これを機に、新憲法の制定をはじめとして、民法、相続税法などを整備しながら、新しい国家体制創りが急ピッチでなされた。相続税制度は、従来の制度が完全に白紙となり、新たなキャンバス上にシャウプ税制が勧告・施行された。同制度はその後、わが国の相続税制度の根幹となって今日に至っている。
シャウプは、戦勝国の連合国最高司令官マッカーサーの要請で、荒れ地と化した日本に税制調査団長として来日した米・コロンビア大学の経済学者である。団員の中で相続税を担当したウィリアム・ヴィックリー(当時35歳)は、同大学の卓越した経済学者であり、後にノーベル経済学賞を受賞(1996年)している。
文化で異なる相続の概念
しかしながら、相続法・相続税制度の依って立つ相続の概念は、その民族内で長い時代を経て形成されてきたものであるから、わが国の人々の相続の概念とシャウプ勧告の相続の概念は互いに整合性のないまま、今日まで存続してきた。その間、わが国の国民性に整合するように幾多の大小改正が行なわれてきたものの、社会的諸問題の噴出や家族の絆の瓦解が先行し、税制改正は後追いの感が拭えない。幾多の改正は、根源的な解決には至っていないのである。
筆者は、この問題に対し、文化圏の異なる諸外国6カ国における相続の概念を、その国の歴史・宗教文化に視点を置いて考察した。その結果、相続は、歴史を経て形成されたその国固有の文化に根付いた概念であることが判明。いずれの国においても相続法・相続税制度には、その国の成り立ち及び宗教文化がそれぞれに具現されていたのである。遺産を血液関係の「横に継承して行く」イスラーム文化、わが国のように血液関係の「縦に継承して行く」儒教文化、米国のように血液関係による「継承観の無い」キリスト教(ピューリタン)文化など、文化で異なる相続の概念とそれを具現化した相続(税)制度が照射されたのである。
わが国のファミリー事例
「妻と二人の子供(長女、長男)を持つ被相続人(父)は、店舗兼自宅で材木業を営んでいた。父の遺産は建物を妻が、土地を長男が、預貯金は母と嫁いだ長女が相続し、廃業した(第一次相続)。数年後、建築士になった長男は古い家を取り壊し二世帯住宅をローンを組んで新築した。そして、29歳の時、妻と2歳の子供を残して突然クモ膜下出血で死亡した(第二次相続)。被相続人(長男)の妻(A子)が子供と里帰りをしている折に、A子の代理人の不動産業者が来て、義母の立ち退きを要求してきた。嫁A子と孫が相続した二世帯住宅を売って、実家の近辺で生活を立て直す、という」。
このケースは義母と嫁との非血族者間に生じた問題である。民法では、この二人の間には扶養の義務はない。しかし義母からすれば何で自分が立ち退かなければならないのか、ということである。民法(相続法)により所有権はすでに嫁に移っている。
家族の絆の瓦解
この問題は、遺産継承の意義に遡って考える必要があるだろう。家族を基盤として、家を「包括的に継承する」と考える伝統的な日本の相続文化と、戦後の新たな個人主義に基づき「遺産は相続人の固有の所得である」とする相続観の確執である。この違いは家族に亀裂を生み、さらに老親の扶養に係わる社会問題となり、今日まで尾を引いている。
最近の相続税改革
シャウプ税制は、その後長い年月をかけてわが国の国民性に合うように幾多の改正がなされてきた。上記の事例は、今日では使用貸借権として、解決できるようになった。また2019年には、民法(相続法)改正によって、配偶者に対する居住権や寄与分が認められるようになる。しかしながら、税制は一度走り出すとなかなか根幹的な改革は実行しにくい。とくに相続税は難しく、平時には出来ないであろうと思われる。
異文化の論理で形成された相続の制度は、それがいかに優れた制度であっても、他国にとって優れた制度であるとは限らない。
万国普遍の望ましい相続税制はあり得ない。