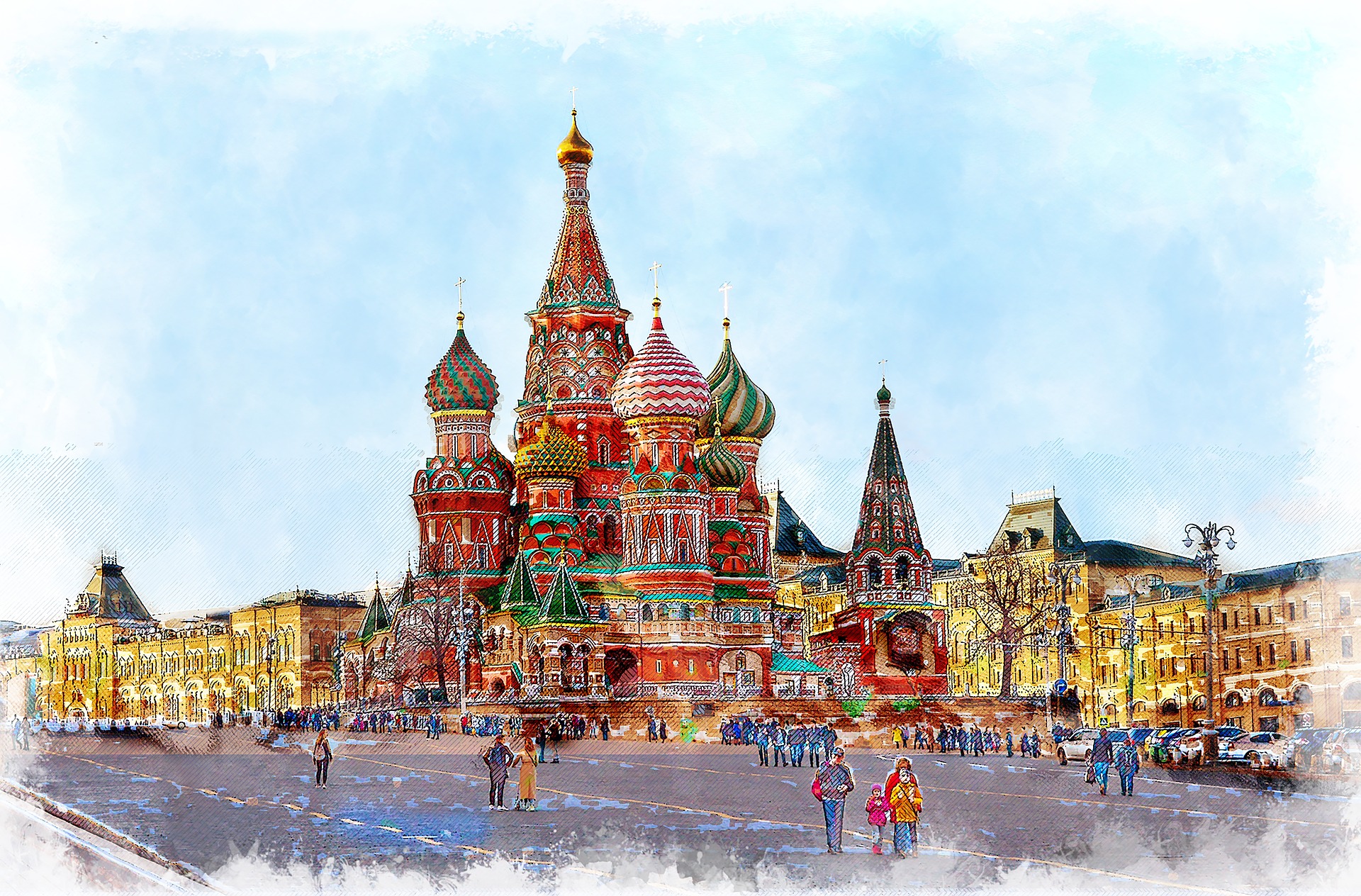はじめに
ウクライナが旧ソ連から独立して来年で30年を迎えるが、この間、ロシアは2014年にクリミアを武力で制圧した上で併合し、各国から制裁を受けている。ウクライナとロシアは、中世のキエフ・ルーシ時代以来、キリスト教(正教会)の受容と合わせて密接な関係のもと歴史を繰り広げてきた。ロシアが小さなクリミアにこだわる背景を理解するには、キエフ・ルーシの後継の正統性ともかかわる、その両国の歴史を紐解くとともに、彼らの情緒的な面までたどる必要がある。そこでウクライナの歴史を振り返りながら、ウクライナとロシアの微妙な関係、そしてウクライナ危機の世界史的意義について考えてみたい。
1.ウクライナの歴史
(1)ヨーロッパの大国:キエフ・ルーシ
ウクライナとロシアの関係について考えるためには歴史的な経緯を押さえておく必要があるが、ここでは中世時代にまで遡って見ておきたい。
ウクライナの地域には、今から1000年以上も前の中世時代に、(現在のウクライナの首都)キエフを中心としたキエフ・ルーシ大公国という、中世ヨーロッパに燦然と輝く大国があった。その黄金期にヴォロディーミル聖公(在位978〜1015年)という大公が出て、中世ヨーロッパのキリスト教世界の中でも、コンスタンチノープルを中心とした正教会を取り入れキリスト教国家となった。キリスト教を取り入れた背景には、宗教的な意味だけではなく、一神教というキリスト教のヒエラルキー的構造が、中央集権国家を治めるのに都合がいいということがあったようだ。
ただこの民族は、兄弟相続を原則とし父子相続も行っていたため、代替わりごとに兄弟間、親族間の争いを呼び次第に領地が分割されて大公の権威も低下し、モンゴルに占領されるまでの1世紀余りの期間はキエフ・ルーシ公国のゆっくりとした解体過程となった。やがて10〜15の公国(独立国)を寄せ集めた連合体の国になった。そのおもなものが、ウラジーミル・スーズダリ公国(のちにモスクワ大公国となる)、ノヴゴロド公国、ハーリチ・ヴォルイニ公国などである。
その後、ユーラシア大陸を西に向けて侵攻してきたモンゴル帝国によってキエフが陥落(1240年)、キエフ・ルーシは約350年の歴史に終止符を打つこととなった。モンゴルは占領地を完全に支配するのではなく、税を納めれば自治を許すという統治方式であったため、むしろモンゴル支配の時代は、比較的平和な時代(パクス・モンゴリカ)であった。この間のウクライナの地は、古代からクリミアを通じてギリシア・ローマ世界及び海の世界へとつながる中継地であった。
ところで、草原地帯の南部(黒海北側など)と森林地帯のモスクワでは、モンゴル帝国(キプチャク汗国)の支配の程度が違っていて、草原の民であるモンゴル人にとってなじみのある草原地帯に比べモスクワなど森林地帯への支配は緩やかだった。そのことも影響して、モスクワの支配者たちは(ウラジーミル・スーズダリ公国)、モンゴルに従順だったため、他の諸公に対する徴税を任された。モスクワはそうして蓄財しながら勢力を伸ばし、やがてそれがモスクワ大公国に発展していく。一方、弱体化したキエフ地域には、(14〜17世紀にかけて)リトアニアやポーランドが進出して支配域を拡大するようになった。
キエフ・ルーシ解体後、南のステップ地帯は荒れ果て、人口が希薄化した。キプチャク汗国も14世紀末より衰退し始め、クリミア汗国などの汗国に分裂するとともに、他の遊牧民がステップ地帯に跳梁するようになって、荒廃が進んでいった。
15世紀ごろからウクライナやロシア南部のステップ地帯には、出自を問わない自治的な武装集団(「コサック」)が形成された。もともとウクライナのステップ地帯は、肥沃な土地で魅力なところでもあったから、コサックたちが集まり、平等なコミュニティを作るようになった。
この地域に入ってきたポーランド人の支配に甘んじていたコサックであったが、ポーランド人の抑圧に我慢できなくなると、おもにモスクワ大公国に助けを求めた。その結果、ドニエプル川の東側は、次第にモスクワ大公国の支配下に入り、西側はポーランドの支配下となった。最終的には、18世紀後半の3度にわたるポーランド分割によって、ドニエプル川東側を中心に、ウクライナの大半をロシアが支配するようになった。
(2)キリスト教からみたウクライナ・ロシアの葛藤
ここでウクライナとキリスト教とのかかわりを見ておく。
キリスト教は政治と密接に関係して発展してきたが、西方教会(カトリック)と東方教会(正教会)とでは教権と王権の関係が違っていた。西方では宗教改革、主権国家・国民国家の成立などを経て政治と宗教が分離していった。一方、正教会はコンスタンチノープルを中心に宗教と政治が表裏一体となった体制で、教会を従えていることが政治支配の正統性を担保することにつながった(注:正教会の組織は、国名もしくは地域名を冠した組織を各地に形成するのが基本)。
キエフ・ルーシの時代は、正教会の中心(キエフ府主教)もキエフにあったが、キエフの衰退とモスクワの興隆によって、正教会の中心がキエフを離れモスクワに移動するようになった。1326年には、「キエフ府主教座」が最終的かつ恒久的にモスクワに置かれることとなった。
その後、17世紀後半(1686年)にロシア正教会はウクライナ正教会をモスクワ総主教座の下に置くとの決定をコンスタンチノープル総主教に認めさせ、それ以来ウクライナ正教会はロシア正教会の管轄下におかれるようになった。
ウクライナにおいてはポーランドによって支配されたという歴史的経緯もあって、その東部と西部とで宗教的に大きく色分けされており、東部は正教会、西部はカトリックが支配的となっている。その中にあって、カトリックと正教会を合同させようという動きもあった。とくにウクライナがポーランドに支配された時期に、ウクライナの正教会をカトリックに合同させようとした。ローマ教皇もこの合同には熱心で、正教会側からも同調する者が現れた。そのため1596年にブレストで会議をしたがまとまらず、結局一部のみがカトリックと合同し、新たに「ユニエイト(ギリシア・カトリック)」というウクライナ独特の教会が生まれることとなった。ユニエイトの特徴は、正教会の典礼に従い、ユリウス暦を使用し、聖職者の結婚も認めるが、ローマ教皇に服従するというものである。そしてユニエイトは西部に多く、その全体的傾向は西ヨーロッパ的だ。
(3)ウクライナ正教会の「独立」
ここで話は現代世界に飛ぶ。
ウクライナは第一次世界大戦直後のロシア革命のさなか、わずかな期間ではあったが独立した時期があった(ウクライナ国民共和国、1917〜20年)。このときウクライナ正教会もあわせてロシア正教会から独立しようという動きがあったが、それが現実的な動きとなったのは、ソ連が崩壊しウクライナが独立した時だった。
一部のウクライナ聖職者はロシア正教会から独立して「ウクライナ正教会キエフ総主教座」を創立し、コンスタンチノープル総主教座にも訴えたが、コンスタンチノープルの総主教座のモスクワへの気兼ねもあって取り合ってもらえなかった。モスクワ総主教座はこの独立を決して認めなかった。その結果、ウクライナの正教会は、ロシア正教会ウクライナ支部(ウクライナ正教会モスクワ総主教座系)とウクライナ正教会キエフ総主教座とに分かれて存在するようになった(注:1453年のコンスタンチノープル陥落によってビザンチン帝国は消滅したものの、その後もコンスタンチノープル総主教が各国の正教会の首位を占めるとの認識は正教会圏の中では共有されていた)。
ところが、2014年にロシアによるクリミア併合が行われたときに、自国の領土を奪取した国の教会が自国の教会を支配し続けるのは許せないとの声が高まり、当時のポロシェンコ大統領もその動きを支持してそれを後押しした。しかしロシアのプーチン大統領これに真っ向から反対した。そもそもロシア正教会は、正教会の中における最大の勢力として、「モスクワは第三のローマ」との立場を公にしていたから、2016年の正教会公会議(クレタ)においてもウクライナ正教会(独立)問題を議論することに対して不満で参加をボイコットしていた。
もしコンスタンチノープル総主教がウクライナ正教会の独立を認めれば、ロシアと対等なキエフを中心とした正教会がウクライナに誕生することになる。
正教会は政治と密接に結びついている教会なので、こうしたウクライナ正教会独立問題は、宗教レベルの話にとどまらず、ポロシェンコ大統領を中心とするウクライナ政府とプーチン大統領を中心とするロシア政府との政治的な争いまで巻き込むこととなった。
その後、2018年10月のコンスタンチノープル総主教庁の教会会議において、ウクライナ正教会への自治権が認められ、併せてキエフ府主教区をモスクワ総主教座に委ねるとした1686年の決定が取り消された。
2019年1月、バルトロメオス1世・コンスタンチノープル総主教は、ウクライナ正教会のロシア正教会からの独立を認める正式文書(トモス)に署名してウクライナ正教会の府主教に授け、同年4月にはポロシェンコ大統領、最高会議議員、ウクライナ正教会の聖職者などが署名して、キエフ府主教座の独立が正式に認められたのである。
これによってウクライナは、1991年の政治的独立に加えて、ようやく宗教的独立も果たすことができたのである。他方ロシアにとっては、政治に続いて宗教の面でもウクライナがロシアから独立することになるので、「キエフ・ルーシの継承国ロシア」という国家の正統性が問われかねない事態ともなっている。
2.現代につながるクリミアの歴史
(1)エカテリーナ2世によるクリミア支配
エカテリーナ2世(在位1762-96年)の統治下だったロシア帝国は、トルコとクチュク・カイナルジ条約を結び(1774年)、ドニエプル川とブーフ川の間にまたがるトルコ領の黒海沿岸地帯を獲得した。これによってロシアは、クリミア汗国の独立をトルコに認めさせ、長年にわたるトルコとの紛争に一応の終止符を打った。
1775年、エカテリーナ2世は数次にわたる露土戦争の結果、ロシアに編入された広大な黒海沿岸地域を一括して「新ロシア県」を創設した。新ロシアの総督になったのがポチョムキンで、彼は大胆な植民地政策を進めた。その結果、黒海沿岸には多くの都市ができた。オデッサ、ミコライイフ、ヘルソンなどの都市で、これらは穀物の輸出港として発展した。
その後、クチュク・カイナルジ条約によってすっかり孤立無援になったクリミア汗国は、1783年、エカテリーナ2世の寵臣ポチョムキンが首都バフチサライを攻略して滅亡した。これはスラブ民族の遊牧民に対する最終的な勝利ともいえる出来事で、これによりロシアは全クリミア半島を領有することとなった。
(2)クリミア戦争とその後
クリミア戦争(1853-56年)は、東欧や地中海に進出しようとしていたロシアを英仏がトルコを助ける形で食い止めようとした典型的な帝国主義戦争で、クリミアを主戦場として展開された。
ロシアは18世紀末にクリミア半島にセヴァストーポリ軍港を築き、そこに黒海艦隊を置き、黒海・地中海への進出の基地とした。英仏・トルコ軍は、ロシア黒海艦隊を壊滅させるためセヴァストーポリ軍港を、そしてその守りであるセヴァストーポリ要塞を攻めた。双方合わせて20万人以上の兵士が動員され、凄惨な攻防戦が繰り広げられ、最終的にロシアの敗北として終わった。このクリミア戦争は、若き文豪トルストイも参戦したほか、ナイティンゲールの活躍も有名であるが、この戦線におけるロシア軍の勇敢さはロシア人の誇り(アイデンティティ)の源にもなっている。
クリミア戦争の敗北によって大きな打撃を受けたロシアは、農奴制の廃止(1861年)、地方行政・教育・司法などの改革を進めた。その後、ウクライナはロシア帝国の下で大規模な開拓が進められて大穀倉地帯となり「ヨーロッパのパン籠」と称されるようになった。こうしてこの地域は、ロシア帝国最重要の穀物生産地となり、20世紀初めには、ロシアの小麦輸出の98%、とうもろこしの84%、ライムギの75%がウクライナから輸出されるほどだった。
こうした穀物輸出のために黒海沿岸には、オデッサ、ミコライイフ、ヘルソンなどの港町が建設されたが、その最大の港がオデッサだった。すでに述べたように、オデッサは、1794年にエカテリーナ2世の勅令によって建設され、無税特権も得て目覚ましい発展を遂げた。さらにオデッサとポディリア地方を結ぶウクライナ最初の鉄道が敷設され、穀物の内陸輸送が可能となった。1847年には、全ロシアの穀物輸出の半分以上がオデッサ港からなされた。19世紀末には、人口も40万となり、サンクトペテルブルグ、モスクワに次ぐ第三の都市となり、港町オデッサは、まさにロシア帝国の「世界への南の窓」であった。鉄道の建設とともに、ウクライナ東南部で石炭と鉄が発見されたことで、工業化も進展し帝国最大の工業地帯に発展した。
(3)ソ連時代
1922年に成立したソ連は、制度上は各共和国の自由意思による結合の連邦国家で、ウクライナもソ連を構成する共和国の一つだったが、スターリンの時代になると、モスクワに完全に統制されソ連の一行政単位となった。
1923年ソ連は、各共和国の民族、文化に応じた施策を慫慂する「土着化」政策を進めた。これは、1917年末から1921年末まで続いた内戦でモスクワの共産党に執拗に抵抗したウクライナを取り込むための政策でもあった。これによってウクライナでは、ウクライナ人の登用、ウクライナ語化などが進められた。正教会においてもウクライナ化の動きがみられた。1920年ウクライナ独立正教会が設立され、21年にはキエフおよび全ウクライナの府主教が任命された。儀式にもウクライナ語を使用した。しかし、ソ連政府は次第に規制を強め、30年には同教会の解散が命じられた。
①ヤルタ会談
第二次世界大戦末期において英米ソの首脳が戦後秩序について話し合ったヤルタ会談は、クリミア半島のヤルタにあるロマノフ王家のリヴァディア離宮で開催された歴史に残る出来事である。
なぜ会談の会場としてヤルタが選ばれたのか。それは、スターリンが自らの対独戦争について多くの決断をなさねばならず、ソ連領を離れられないと英米首脳に申し入れたからだった。季節は冬で、病身のルーズヴェルトのことも考慮して、暖かいクリミア半島、しかもソ連第一の保養地であるヤルタが選ばれた。
リヴァディア離宮は、1860年代ロシアの皇帝アレクサンドル2世がマリア皇后の健康のために建てたのが始まりである。皇后はクリミアの景観とタタール人など地元の住民の風習にすっかり魅せられた。白い宮殿と緑の庭、青い海が三位一体となった素晴らしいところである。
以来、歴代の皇帝一家が愛して訪れるだけではなく、上流階級の社交場、芸術家のたまり場ともなっていた。チェーホフ、ゴーリキーもヤルタに住んだ。
②ユニエイトに対する処遇
先述したカトリックと正教会が融合したユニエイトは、ロシア帝国やソ連の下では原則禁止されていたが、西ウクライナでは存続が許されており、同地域のウクライナ人のアイデンティティのよりどころともなっていた。
西ウクライナがソ連下に入るにあたり、ソ連政府は、西側と結びつきがあり民族主義的なユニエイトは危険と考え、1946年これを禁止し、モスクワのロシア正教会に併合させた。表面上ユニエイトは消滅したが、多くの聖職者はロシア正教の名の下で秘密にユニエイトの教義を実践し続けた。そしれそれは1980年代後半に活発化した民族主義運動の原動力の一つとなった。
③フルシチョフ時代
スターリンの跡を継いだフルシチョフは、統制を緩め民族文化活動を自由にした。フルシチョフ自身、ウクライナ共産党第一書記を務めたこともあり、ウクライナ文化に好意を持ちウクライナ人の間で人気があった。
1954年、ウクライナ史上最大の英雄フメリニツキー(1595〜1657年)がロシアの宗主権を認めたペレヤスラフ協定(注:コサックとウクライナ人はツァーリに忠誠を誓うこと、ツァーリはウクライナに軍事援助することなどの内容)の締結300周年記念の際に、これまでロシアの一部だったクリミアが「ウクライナに対するロシア人民の偉大な兄弟愛と信頼のさらなる証し」としてウクライナ共和国に移管された。
これは対ウクライナ懐柔策であったが、他方ロシア系住民が人口の7割以上を占めるクリミアをウクライナに帰属させることによって、ウクライナの中でロシアの比率を高める意図もあったとされる。いずれにせよ、当時はウクライナが将来独立するなどとは毛頭考えられていなかったので、行政上の措置程度の軽い気持ちでなされた決定であった。
(4)ウクライナ独立後
ソ連崩壊によってウクライナは独立を果たしたわけだが、クリミアはフルシチョフの措置によって独立後もウクライナ領だった。独立を目前にしたころ、ウクライナで独立の是非を問う住民投票が行われたが、その結果は、90.2%が独立に賛成した。ロシア人が過半数を占めるクリミアにおいてさえ賛成54%と過半数を上回った。
ウクライナ独立後、クリミアはウクライナの枠内で「クリミア自治共和国」として特別な地位を与えられたが、当初はウクライナから分離する動きも強かった。しかしそれも、ロシアからの支援が減ったこととウクライナの統治が安定化したことで次第に弱まり、2014年頃までにはほぼ沈静化した。
セヴァストーポリ軍港については、ソ連崩壊後の1997年にロシア・ウクライナ間で2017年までロシアが租借する旨の協定を締結し両国が共同で使える軍港となった。さらに2010年には再締結されて2042年までソ連軍の駐留が認められることになった。
3.ロシアはなぜクリミア併合をしたのか
(1)ウクライナ(クリミア)に対するロシア人の特別な感情
前節で述べたようなクリミアをめぐる歴史的経緯を考えると、ロシア人の心底にはクリミアに対するセンチメンタル(情緒的)な思いがあることがわかる。クリミア半島は、地中海気候で温暖なため、帝政時代にはロシア皇帝をはじめ多くの貴族、文豪が、ソ連時代には共産党幹部が避暑地としてあこがれの地であった。ソ連時代には一般大衆にとってもクリミア海岸は、サナトリウムに出かけ、バカンスを謳歌する絶好の保養地であった。このようにクリミアは、ロシア人の「心のあこがれの地」であった。クリミアがロシア領でなくなったことにロシア国民はたいへん残念がった。
指導者、とくにプーチン大統領は、ソ連がみじめにも解体し分裂してしまったことに対して後悔の念を持っており、「ロシアは世界に冠たる大国であって、その位置に戻らないといけない。そのためには、やはりウクライナが何らかの形で戻ってくる必要がある」と考えている。
それではロシアにとってのウクライナとは、どのような位置づけなのだろうか。
———(キエフ・ルーシの時代からロシアとウクライナは一体不可分の関係だったのに、ソ連崩壊後)分離独立してしまった。これはあってはならないことであって、元の姿に戻るべきだ。キルギス、アゼルバイジャンなど(ソ連から同じように独立した)コーカサスの諸国は、ロシアとは民族、宗教も違う国々である。しかしロシア人にとってウクライナは、西ヨーロッパに一番近いところに位置し、同じスラブ民族であり、文化・言語・宗教も似ているうえ、ロシア系住民がウクライナの約2割を占める。そのようなウクライナがロシアから離れていくことは耐えられない。
こうした感情は、社会のトップ層から庶民に至るまで共通したものだ。つまりロシア人の素朴な心情においてウクライナ人とは、「われわれの兄弟」という感覚なのである。兄弟(兄がロシアで、ウクライナは弟)なのだから、別れても戻って来いというわけだ。恐らく旧ソ連の中でも、一番気心が知れた国がウクライナであった。
さらに深い心理的レベルでいうと、自分たちよりも「よりヨーロッパ的」な要素を持つウクライナが離れてしまうと、ロシアはより「非ヨーロッパ的(アジア的、モンゴル的)」になってしまいかねない。ロシア人の心の奥底には、自分たちはあくまでもヨーロッパ人だというアイデンティティがある。そのヨーロッパ的なものが、三分の一もなくなってしまう。それは耐えられない。
普通のロシア人は、ヨーロッパ人でいたい。ところが、国の上層部の指導層は世界戦略の観点からアジアが重要だと主張する。しかし極東地域に住んでいるロシア人は、折あらばモスクワやサンクトペテルブルクに引っ越したいと思っている。ウクライナがなくなったら、ロシアはヨーロッパではないといわれかねない。
経済的に見てもそうだ。ソ連は多民族国家で多くの共和国からなっていたこともあり、工業振興政策において一つの共和国に集中させずに分散させる政策を取ってきた。例えば、ある機械製品を作る場合、本体はどこの共和国、この部品はどこの共和国で作るといった具合である。ウクライナには、宇宙開発の基地、戦車などの軍事産業、重工業などがあり、ロシアの産業にとっては、非常に重要な地域であった。ロシアにとっては欠くことのできないところである。
ウクライナが戻ってこない限り、ロシアはかつてのような大国に戻れないと考えているので、何とかウクライナを取りこもうとしている。もちろんそれが難しいことは分かっているが、少なくともウクライナがNATOやEUに一旦入ってしまうともう戻ってくることは不可能だから、それだけは阻止したい。それまでは押したり引いたり、あの手この手を使ってとどめおこうとしてきた。
ところで、ウクライナの中でウクライナ人とロシア人の関係はどうなっているのだろうか。
ウクライナはロシアの支配下にある時期が長かったが、そのころからロシア人はウクライナ地域の都市部に住んでいる程度でそれほど多くはなかった。その後、19世紀後半に産業革命が及んで、ウクライナに工業が発展するようになり、労働力不足を補うべく、ロシア人が多く流入するようになった。またウクライナは、ロシアに比べると気候も温和なために、そうした環境を求めてやってくるロシア人も少なくなかった。
(ナショナリズムにかかわるような政治的主張を除けば)ウクライナ人もロシア人も普通の日常生活ではうまく共存してきた。個人レベルでいえば、ウクライナ人にはロシア人に対する憎しみはないと思われる。もちろん、ロシア(ソ連)は長年ウクライナの政治や文化を抑圧してきた面もあるから、それに対するウクライナ人の反発心は存在する。ただし、ウクライナ国内でも、ロシア人の多い東部は、反ロシア感情はそれほどでもないが、ポーランドに近い西部は、反ロシア感情が強いという傾向がみられる。
(2)クリミア併合の動機
2013年、(親ロ派の)ヤヌコーヴィチ大統領(在職2010-2014年)はバランスを考えて、EUとの協力協定を結ぶことを国民に約束した。それを阻止しようとしたプーチン大統領は、強い圧力をかけヤヌコーヴィチ大統領に断念させた。
そのことに対して怒ったウクライナの国民が抗議活動を起こした(2014年2月、ユーロマイダン革命)。キエフは騒乱状態となり、同大統領はロシアに亡命。新政府は親西欧路線を明確に表明した。
こうなると何としても阻止しないといけないと強く考えたプーチン大統領は、クリミア併合の行動に出た。クリミアは、ソ連時代の1953年まではウクライナ共和国ではなくロシア共和国に属していたし、現在もロシア系住民が多数(約7割)を占めており、かつてウクライナが旧ソ連から独立した当時も、ロシア系住民が多いことからロシアに帰属したいという運動もみられた。それにソ連国民の間にクリミアへのノスタルジアが強いことから、もしクリミアをロシアに戻したら、それはロシア国民から大歓迎されるだろう。プーチン大統領はこのような計算をしたのではないか。
ロシア軍の制圧の下、国際監視団もない中で行われた住民投票(2014年3月16日)であったので、かなり怪しいものだった。住民投票の結果(注:クリミア共和国中央選管の発表で、投票率83%、ロシアへの編入賛成96%)を受けて、3月18日ロシアはクリミア編入への条約に調印した。領土の支配を変更するためには、ウクライナ議会の了承も必要なのに、そのような憲法的手続きもないままにロシアは、一方的にクリミアを併合した。ただロシア国民は非常に喜んだ。
ロシアはクリミア併合によってセヴァストーポリ軍港は押さえたわけだが、さしあたって地中海でロシア海軍が西側と対峙するという可能性もほぼないので、このことによってロシア対西側の軍事的、戦略的バランスが大きく変化することはないだろう。
ロシアの黒海艦隊は、冷戦時代は黒海から地中海へ艦隊を展開させて英米艦隊と対峙していたが、現在では、艦隊の老朽化とともに、地政学的に地中海に出るにもボスポラス海峡で阻止されてしまいかねないという課題があって、大西洋に向けての不凍港という点では、北極海沿岸のムルマンスクやバルト海沿岸のカリーニングラードがより重要になっている。
4.ウクライナ危機の世界史的意義
ロシアによるクリミア併合後の今日でも、反政府勢力の支配するウクライナ・ドンバス地域(東部)では小規模な戦闘が今なお繰り広げられているが、最後に、このウクライナ危機が、世界史的にどのような意味をもっているか考えてみたい。
第一に、ウクライナ危機は、ソ連崩壊の「余震」と見ることができる。大きな地震が起きると、その後、余震が何度か続いて、やがておさまっていくわけだが、それに譬えられる。ソ連崩壊は、20世紀の大事件(大地震)だった。それによって、ソ連が分解し、東欧が分離した。この余波でユーゴは分裂して内戦状態となり、民族浄化などの悲惨な出来事が起きた。ジョージア、キルギスなど旧ソ連の一部だった地域で、花革命(Flower Revolutions、ジョージアのバラ革命、キルギスのチューリップ革命、ウクライナのオレンジ革命など)が次々と起こった。そうした「余震」があちこちで起きたが、次第におさまっていった。ウクライナ危機は、その「最後の余震」と見ることができる。もっとも、いつおさまるかは見通しが立っていない。
第二に、遅ればせながら、(ウクライナ問題には)植民地解放・独立という側面がある。英仏、オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガルなどヨーロッパ列強によって支配された多くの植民地は、20世紀の二つの世界大戦を経てほとんどが解放され独立を果たした。これによって植民地問題をある面ですっきりさせることができた。
これに対して中国は、清朝時代に抱え込んだウイグル、チベットを解放せずに抱え込んだまま現代まで引き継いだために、いまだに火種として残っている。また近代のロシアも、陸続きで領土を拡張しながら「植民地」を増やしていった。ヨーロッパ列強の場合は、海を越えたところに植民地を作ったので、宗主国と植民地の区別がつきやすかったが、中国とロシアの場合は、地続きであったために、本国か植民地か不明のまま現代に至った。中国とロシアは、自分の植民地主義を自覚せぬままに、戦後ヨーロッパ諸国の植民地主義を批判し、アジア・アフリカの盟主としてふるまってきた。しかし考えてみると、両国とも国内に「植民地」を抱えたままだったのに、そのことを誰も指摘しなかった。ところがソ連崩壊によって、多くの国が民族独立を果たした。これはまさにヨーロッパ列強からの独立と同じことではないのか。
ソ連から独立した諸国はほぼ落ち着ているわけだが、唯一ウクライナだけは、いまだにロシアがあきらめきれていない。つまりカザフスタンやキルギスなどの諸国は仕方ないとしても、ウクライナはロシア本国と一体不可分の関係だったのに「無理やり引き離された」とロシア人は感じている。一方、ウクライナ人の立場からすれば、「長い歴史にわたってわれわれはロシア人に苦しめられてきた。ようやく植民地独立を果たした」というような感情が彼らの心底にある。
そうだとすれば、ロシアもウクライナ問題について「植民地からの解放・独立」だと潔く考え直してくれたら、ウクライナ問題の真の解決(ロシアとウクライナの真の和解・平和)につながるのではないか。
佐藤優氏は「プーチンは非共産的ソ連を再建しようと思っている」と述べた。今のロシアは、共産主義国家ではないが、かつての旧ソ連の領域を取り戻したいというのが、プーチン大統領の野望なのではないか。
第三に、大国と小国との関係で、大国の隣にいる小国は、苦労が多いということである。米国の隣のカナダやメキシコは、米国の身勝手な振る舞いに苦しめられてきた。インドは平和的な国と見られているが、パキスタンやネパールなどの隣国には大国的な振る舞いをしてきた。中国も、ベトナム、モンゴル、朝鮮に対して強い姿勢で対応してきた。ウクライナは隣の大国ロシアに何世紀にもわたって苦しめられてきたが、今回のクリミア併合もその典型的な一例である。
それでは小国ウクライナが生きる知恵は何か。それは、できるだけ早く、EUないしNATOに入ることだ。自分がなりたいのはどちらなのか。ロシア的なやり方がいいのか、西欧的なやり方がいいのか、その選択でもある。現在の若者は、ほとんどが西洋的なやり方を求めている。ロシア的なやり方をした場合、経済も決してうまくいかない。ロシアはエネルギー資源を輸出して国を立て、宇宙開発、軍事では優れているとしても、一般消費財で世界の中で競争力はない。そうなると、石油・天然ガス資源に乏しいウクライナは、西欧的なやり方でやるのがよいということにならざるを得ない。NATOに加盟しておればクリミアを取られてしまうこともなかっただろうし、EUに加盟すれば、さまざまな共同体の恩典を受けることができる。
ポロシェンコ前大統領も、ゼレンスキー現大統領も、ロシア的やり方では未来はないと言っている。ただし、EUやNATOに加盟するにはさまざまなクリアすべき条件があって、道のりはまだまだだが、方向性としてはそれ以外ないであろう。国民感情としても、その方向にある。しかしロシアは、それを何としてでも阻止したいと思っている。クリミアやドンバス地方は「人質」のようなもので、あらゆることを考えているだろう。
ウクライナ問題に、双方が短期的に満足するような「解」はない。他国の領土を一方的に占領することは、近代国際法の論理からするとあり得ないことであるから、ロシアは撤退すべきだが、プーチン大統領は全くその気はない。領土問題は一旦実効支配し既成事実化してしまうとなかなか解決しない。この点でクリミア問題を抱えるウクライナと北方領土を抱える日本は、同じような立場にあるともいえる。
(2020年5月26日、インタビュー内容を整理して掲載)