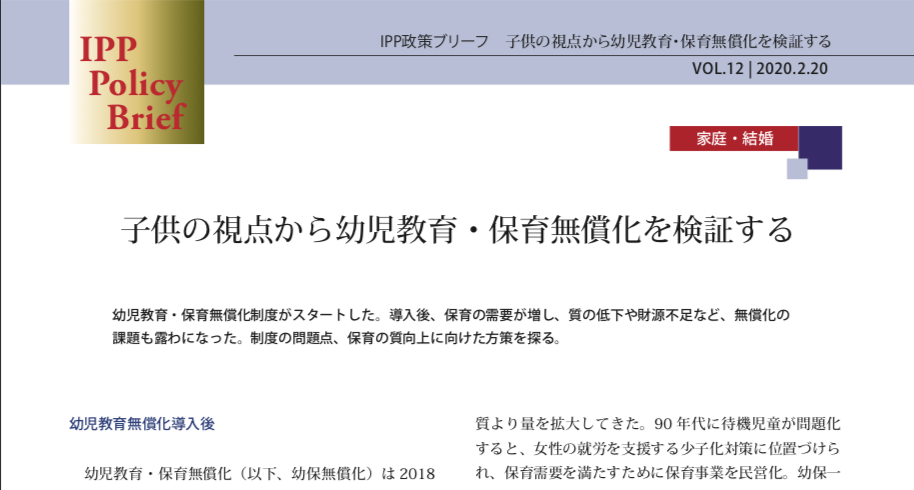1 「パーソン」とは何か
何が「人格」と呼ばれるのか
日本の教育界でよく使われている「人格の完成」、また同じような「人格の形成」という言葉は、日本になじみがあるようで、よく考えてみれば、ほとんどなじみのない言葉である。というのも、「人格」は、英語のpersonality(パーソナリティ)、ドイツ語のPersönlichkeit(ペルゼンリッヒカイト)の訳語であり、「完成」は、英語のperfection(パーフェクション)、ドイツ語のVollkommenheit(フォルコメンハイト)の訳語であり、どちらの言葉も、古来のキリスト教思想を前提にしなければ、理解不可能だからである(教育基本法(1947年制定)の第1条「人格の完成」の英語表記は、full development of personalityであり、「完成」がfull developmentであるが、これはperfectionの現代風の表現だろう)。本講の主題は、この二つの言葉の含意を、キリスト教思想の概念として敷衍することである。それは、私たちが抱いている「人格の完成」という言葉の意味とは異なる心の歓びに彩られている。しかも、その心の歓びは、現代日本社会と無縁のそれではなく、むしろ再確認されるべきものである。
おそらく、日本で「人格」という言葉が意味しているのは、理性的に自律する「主体」だろう。自分で判断し、それに基づいて行動し、その行動に対して責任をとることができる人間だろう。シスターの渡辺和子(1927-2016)は、2012年の『置かれた場所で咲きなさい』という著作で知られているが、長く「人格論」を講義してきた大学人でもある。彼女は、その「人格論」の講義のなかで、6世紀の思想家ボエチウス(Boethius)の『ペルソナの二つの自然』(De Persona et Duabus Naturis)の言葉(persona est substantia individua rationalis naturae 「ペルソナは一人ひとりの基礎であり、理性的な自然である」)を引きながら、「人格」(ペルソナ)とは「理性と自由意志を備えた個としての責任の主体」である、と述べている。また、20世紀のフランスの哲学者マルセル(Marcel, Gabriel)の言葉を引きながら、匿名の「ひと」(man/on)と、固有な「人格」(personne)を区別し、自律的な判断、決断ができ、責任をもつ固有な「人」(homme)を「人格」と呼ぶ、と述べている(渡辺 2005(1988); Marcel 1940/1968: 125)。つまり、付和雷同ではなく、固有名をもつ理性的に自律する「主体」である、と。
渡辺の人格概念は、キリスト教思想(カトリシズム)に彩られているが、その子細はともかく、その大要は、キリスト教思想を知らずとも、よくわかるだろう。しかし、キリスト教思想をさかのぼり、その思想的原点からとらえなおすとき、まったく違う意味世界が、そこに開かれるだろう。本講でめざすところは、このまったく違う「人格」の意味世界を示すことである。
「パーソン」と「ヒューマン」
まず確かめるなら、「人格」と訳される「パーソン」は、「人間」と訳される「ヒューマン」とどう違うのか。語源を確かめると、「パーソン」は、ラテン語の「ペルソナ」(persona)に由来し、「ペルソナ」は、ギリシア語の「プネウマ」(puneuma)の翻訳である。「プネウマ」は、「息吹・響き」、そして「生き生き・いのち」を意味する。これに対し、「ヒューマン」は、「人(の)」を意味するラテン語の「フーマーヌス」(humanus)に由来し、それはさらに「フムス」(humus)に由来する。このフムスは「大地・土壌」、つまり「支えるもの」を意味する。この「フーマーヌス」から、15世紀あたりにフランス語の「ユマニテ」(humanité)が派生し、この「フーマーヌス」「ユマニテ」が、18世紀に英語の「ヒューマン」、ドイツ語の「フマニテート」(humanität)に翻訳された。つまり、「人格」は本来的に近代以前の概念であるが、「人間的なもの」「人間性」は近代以降の概念である。
もう一つ、「パーフェクション」(フォルコメンハイト)について簡単にふれておけば、これらは、近世における、ラテン語のperfectio(ペルフェクティオ)の翻訳である。そしてこの「ペルフェクティオ」は、ギリシア語のteleiosis(テレイオーシス)の翻訳である。「テレイオーシス」は「成熟[したもの]・達成[されたもの]」を意味する。キリスト教思想のなかで、この言葉は、神の属性としての、とりわけ人にわかるそれとしての、「イエスの無条件の愛(アガペー)」を意味する。
思考の自由を享受するために
つまり、キリスト教思想の歴史に即して考えれば、「人格の完成」とは、「息吹・響き・いのちとしての人が、イエスのような無条件の愛を体現すること」を意味するが、むろん、このような意味で「人格の完成」という言葉が日本の教育基本法に盛り込まれたのではない。どのような意味で、この言葉が教育基本法に組み込まれたのか、今のところ、はっきりわかっていない。
私が、このような概念の思想史的確認を行った理由は、この「人格の完成」「人格の形成」といった言葉の「人格」(パーソン)を、より豊かな意味・感覚で使う可能性を広げるためである。もうすこし具体的にいえば、「人格」を、道徳規範をたんに体現する人間ではなく、ものごとの善し悪しを深く考える自由――思考の自由――を享受できる人間として、意味づけるためである。フランスの哲学者ドゥルーズ(Deleuze, Gille)は、「だれひとりとして裁きによって成長する者はいない」。「自由を求める闘いによってこそ、人は成長する」と述べている(Deleuze 1993: 166-7, 168/2002: 263-4, 265)。
思考の自由、いいかえれば、答えのない問いを考える自由は、勝手気ままに考えることではなく、一定のベクトルとともに考えることである。それは、〈よりよく生きようとする〉ベクトルである。さしあたり、このベクトルの行き先を「テロス」(telos 終着点・終わり)と呼んでおこう。このテロスは、先にふれたテレイオーシスに通じる言葉である。つまり、思考の自由は、テロスへのベクトルに方向づけられている。確かめたいことは、このテロスとはどのようなものか、である。
以下、まず、日本の教育学において「人格」が「パーソナリティ」の訳語として導入されたことを確認する(第2節)。続いて、このパーソナリティの語源であるラテン語のペルソナの思想的意味、その語源であるギリシア語の「プネウマ」の意味を参照しつつ確かめ、いささか大胆な解釈を試みる(第3節)。最後に、そこで浮かびあがる人間の存在様態(在りよう)が、音楽に通じる詩的な思考に見いだされることを、谷川俊太郎の詩論にふれながら、語ってみたい。
2 人格を支える完全性論
カントに由来する人格
さかのぼれば、「人格」という言葉は、1892(明治25)年にイングランドの思想家グリーン(Green, Thomas Hill)が用いた「パーソナリティ」に対し、井上哲次郎(1856-1944)、中島力造(1856-1918)が作りだしあてた言葉である。つまり、「人格」は、漢語ではなく日本語である。グリーンが用いた「パーソナリティ」は、彼がカント(Kant, Immanuel)の Persönlichkeitに与えた訳語である。したがって、「人格」は、カントの「ペルゼンリッヒカイト」に与えられた訳語である、ということができる(グリーンが「パーソナリティ」を用いたのは、カントの『プロレゴーメナ』を思わせる、1883年のProlegomena to Ethics(『倫理学へのプロレゴーメナ』)だろう。グリーンは、そこで人を「自分の完全性」に向かわせる内在性「永遠の意識」(eternal consiousness)を「パーソナリティ」と形容している(Green, PE: 293)。
カントのペルゼンリッヒカイト(直訳すれば「人間的なる性質」)は、キリスト教的なニュアンスのつよい「道徳哲学」の概念である。カントの生きた18世紀のヨーロッパ思想界では、「人間の完全性」(human perfection/perfection humaine/Vollkommenheit des Menschen)を論じる思想――完全性論が広まっていた(Luhmann/Schorr 1988)。カントも、この完全性論をふまえ、『実践理性批判』や『人倫の形而上学』で、Person(ペルゾン 人間)を「道徳的完全性」(moralischen Vollkommenheit)に到達するために無限の努力を義務づけられた存在である、と位置づけた。ペルゼンリッヒカイトは、このペルゾンを「道徳的完全性」にみちびく内在的審級(つまり理性・良心)である(KW 7, KpV; KW 8, MS)。
「人格の陶冶」と「人格の完成」
大正期の日本において、このカントのペルゼンリッヒカイトの形成を論じたドイツの教育学言説――リンデ(Linde, Ernst)、ブッデ(Budde, Gerhart)などが1900年代から1910年代にかけて展開した――「ペルゼンリッヒカイトスペダゴギーク」(Persönlichkeitspädagogik)が「人格的教育学」と訳され、いくつかの教育雑誌を通じて紹介された。この「人格的教育学」がめざしたことが、「ペルゼンリッヒカイトスビルドゥング」(Persönlichkeitsbildung)である。たとえば、教育学者の中島半次郎は、1914年に著書『人格的教育学の思潮』において、この「人格的教育学」を紹介し、この「ペルゼンリッヒカイトスビルドゥング」を「人格の陶冶」と訳している。教育学者の篠原助市も、1918年に論文「最近の教育理想」のなかで、この「人格的教育学」を紹介し、「ペルゼンリッヒカイトスビルドゥング」を「人格の陶冶」と訳している(田中 2005)。
1933年にデューイ(Dewey, John)の『民主主義と教育』が、帆足理一郎によって『教育哲学概論――民本主義と教育』という表題で、はじめて翻訳出版された。同書では、「人格の完成」という言葉が2回用いられているが、どちらも、原語がcomplete development of personalityである(CWD, mw 9, DE: 118, 128)。デューイがそこで言及した「人格の完成」も、当時のドイツ教育学で語られた「人格の陶冶」だろう。デューイはそこで、「文化(culture[これはBildung(陶冶)のことである])は、人格的(personal)である。‥‥文化と呼ばれようと、人格の完全展開と呼ばれようと、それがもたらすものは、一人ひとりの個人に内在する特異性(what is unique)‥‥が顧慮されているかぎり、真に社会的に有為な能力にひとしい」と述べている(CWD, mw 9, DE: 128)。この「人格の完全展開」は、「〈内的〉人格の完全化」(perfecting an “inner” personality)とも言い換えられている(CWD, mw 9, DE: 129)。
こうした歴史をもつ「人格」(「人格の完成」「人格の陶冶」)が、政策的に日本の教育の中心に位置づけられたのは、第二次大戦後、教育基本法が成立してからである。それから現代にいたるまで、日本の学校教育においては、「道徳の時間」のみならず、さまざまな教育場面で「醇風美俗」につうじる道徳規範の形成が行われてきた。しかし、ここでは、そうした日本の人格形成的な教育の展開を脇に置き、カントのペルゼンリッヒカイトのめざしていた「完全性」の意味内容を確かめよう。
「人間の完全性」を志向する人格性
ペルゼンリッヒカイト(以下「人格」)は、さきにふれたように、人の心のなかにあり「人間の完全性」を指向する何かである(Luhmann/Schorr 1988)。人間の完全性は、基本的にキリスト教思想に由来する概念であり、再確認しておくなら、この言葉は、〈人間は、イエスのような完全性に到達できるように努力しつづけるべきである〉という考え方と一体である。この考え方は、とても到達できないだろうこの目的に敢えて向かい続けるという、敢然な態度がふくまれている。さきにふれたマルセルは、「人格の特質とは、大胆に立ち向かうことである」と述べている(Marcel 1940/1968: 122)。
この人間の完全性に向かうという考え方は、キリスト教思想の原点、新約聖書にさかのぼれば、パウロの次の記述に依拠している。「私たちすべてが、神の子[=イエス]を信じるという信仰で一致し、また彼を知るための知識において一致し、完全な人となり、ついにキリストの豊かで気高いヴァーチュにいたる。こうして、私たちは子どもではなくなり、だまし惑わす策略、悪巧みによって、さまざまな考え方に満ちた風潮に惑わされたり、もてあそばれたりすることがなくなり、愛に満ち、真理を語り、あらゆる点で成長し、めざすべきキリストに達する」(エペソ 4. 14-16)。
こうしたキリスト教的な完全性論においては、イエスは、唯一の「師」(magister)と位置づけられている。たとえば、アウグスティヌスは、『師について』において、「すべての師のなかで、師はただひとり。天上にいる師だけである」と述べている(AO, M: 14. 46/276)。この天上の「師」は、一人ひとりの心のなかに「イマーゴ」(imago 象り・像・形象)として映しだされる。このイエスのイマーゴが「神の像(象り)」(Imago Dei イマーゴ・デイ)と呼ばれる。そのイマーゴとしての「師」と向きあうとき、人は「内在する人」となる。その「師」は、その人に「呼びかけ」、人は、その呼び声に「応える」。ここに、内的な呼応の関係が生じる。この呼応の関係のなかで、人は、「神の似姿」(similitudo Dei シミリトゥード・デイ)となる。アウグスティヌスが、『三位一体論』において、「私たちが神を知るとき、‥‥いくらか神の似姿(similitudo)となる」と述べているように(AO, DT: 9. 11, 16)。
ようするに、カントの人格は、いわゆる「信仰」から距離をとりつつも、人間が創りだし従う意味・価値を超越する存在(すなわちイエス)を前提としながら、人が〈よりよく生きようとする〉ことそれ自体である。「信仰」の有無にかかわらず、この〈よりよく生きようとする〉ベクトルそれ自体は、否定できないだろう。しかし、前述の思考の自由という観点からすれば、イエスは、思考の自由を妨げる絶対的価値にもなるべきではなく、〈よりよく生きようとする〉ベクトルを喚起する契機に留められるべきだろう。キリスト教思想をさらにさかのぼり、その可能性を探ってみよう。
3 共鳴共振と交感性
共鳴共振としてのペルソナ
ラテン語辞典に即していえば、「ペルソナ」(persona) は「仮面」「役」「人」を意味する言葉である。しかし、これらの意味に従い、キリスト教思想の「ペルソナ」を理解しようとすると、困ったことになる。つまり、キリスト教思想でいわれている「三位一体」(Trinitas [ tres personae in una substantia])論、すなわち「父(神)」(Pater)と「子(イエス)」(Filius)と「聖霊」(Spiritus Sanctus)が、「ペルソナ」として一体である、ということは、いろいろ論じられているが、わからないだろう。
しかし、この「ペルソナ」がもともと、トマス(Aquinas, Thomas)が『神学大全』に記すような「響き」であるとすれば、それはいくらかわかりやすくなる。「ペルソナ」が、ギリシア語の「プネウマ」の訳語であり、「息吹・響き」を意味していたことを踏まえて、トマスは、「ペルソナ」を「ペルソナーレ」(per-sonāre 通して-響く)の名詞形と解釈している。そして、役者が「仮面」を通して話すとき、そのくぐもった響きが尊厳をもたらすと主張し、「ペルソナとは、尊厳あるものに属する者として[他のものから]区別される固有な実体(hypostasis proprietate)である」と断じる(A, ST: 1, q 29, a 3 ad 2)、「すべてのペルソナは[それぞれ]一つの実体である」と(A, ST: 1, q 29, a 3 ad 3)。
もうすこし大胆に考えてみよう。トマスが言及する「ペルソナーレ」は、たしかに「響き渡らせる」「反響する」「共鳴する」を意味している(LED 1968: “per-sono”)。「ペル」(per) は「通して」「拡がり」を意味し、「ソナーレ」(sonāre)は「声を出す」「音が出る」を意味する。とすれば、ペルソナは、何らかのものではなく、二つのものが響きあう状態を意味している、とも考えられる。つまり、「神」と「イエス」が共鳴共振している状態である、と。この共鳴共振状態が「ペルソナ」と形容されていると考えるなら、それらが「一体」であることも、理解しやすい。そして「聖霊」は、この「ペルソナ」のはたらきを形容する言葉と考えられる。アウグスティヌスも、『三位一体論』のなかで、「父(神)」と「子(イエス)」を結びつけるのが「聖霊」であるといい、この「聖霊は、父と子に共通であり、‥‥両者のコンムニオ(communio)と呼ばれる」と述べているからである(AO, DT : 15. 19. 32, 37)。つまり、この「コンムニオ」(共通するもの)が「ペルソナ」(共鳴共振)である。
近代の「人格」にかんする記述も、その言葉のなかに「共鳴共振」(映しだし)というニュアンスを感じとりながら読むとき、しっくりくるだろう。たとえば、アウシュヴィッツの生き残りであり『夜と霧』の著者フランクル(Frankl, Viktor)は、一九四八年の『識られざる神』において、「人格(Person)はただ、神の似姿としてのみ理解しうるものである。人格は、自分自身をただ超越者[=イエス]から把握するほかない」としつつも、「人はさらに、自分を超越者から理解する程度においてのみ、人である。人は、超越者から人格たらしめられる程度に応じてのみ、人格である。すなわち、人は、超越者の呼びかけが彼のうちで鳴り響き、響きわたる程度に応じてのみ、人格である。この超越の呼びかけを、人は良心において聴きとる」と述べている(Frankl 2009/2016: 175[私訳])。
共鳴共振と交感性
この共鳴共振は、もっとも生き生きとした営みといえるだろうし、一般に善悪を決するものと見なされている「道徳性」を下支えしているものともいえるだろう。文科省の『学習指導要領の解説』は、「道徳性」は「道徳的価値の総体」と規定し、それを支えるものの一つが「すべての生命のつながり」という「自覚」である、と述べている。同書は、この「自覚」を生みだす「つながり」が何であるのか、解説していないが、さしあたり、共鳴共振である、と考えてみよう。
むろん、異論もあるだろう。この自覚は、たんなる「社会化の結果」として生じるものである、という考え方もある。いつのまにか身につけた思考の習性(ハビトゥス)のようなものである、と。あるいは、そうした社会化論的な考え方を否定し、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世のように、この自覚は、「スピリトゥスの働き」によって生じたものである、ということもできる。すなわち、神がすべての人に贈ったスピリトゥスが、人の心のなかにあり、はたらくから、と(Pinker 2002/2004)。
ここで、これらの考え方の当否を子細に検討することはやめて、「道徳性」の基礎である「すべての生命のつながり」という「自覚」は、自・他の共鳴共振である、と考えてみよう。身近なことを例示すれば、それは、私たちが、生まれたばかりの子猫を見て感じる歓びであり、捨てられた子犬を見て感じる痛ましい思いであり、緑生い茂る立木を切り倒さなければならないときに感じる躊躇いなどである。また、誰かへの憧れ、畏敬も、共鳴共振である。キリスト教に即していえば、無条件に人を愛し、また弟子に裏切られ、十字架にかけられた人、イエスに対する深甚の畏敬である。
おそらく、人は、人(個人)という象り(輪郭)を超えて、それからはみだし広がる感覚、いわば「交感性」(sympathia 自・他をつなぐ感受性の広がり)をもっているのだろう。それは、見えないし語りがたいが、無理にいえば、「阿吽の呼吸」「以心伝心」のような、言葉にしなくても、誰かと響きあい・通じあうことである。それは、「自律する個人」という鎧を着ているかぎり、さえぎられ、断ち切られる音波のようなものである。感覚されるものであり、かつ想像されるものである。
この交感性は、それが強く刺激されるとき、共鳴共振となる、と考えられる。いいかえれば、共鳴共振は、何か重大なことに直面したときに強く掻き立てられる交感性である、と。そして、そうした共鳴共振のなかで、相手を「助けなければ」という衝迫が生じるとき、その衝迫が「良心」(倫理的衝迫)と呼ばれる、といえるだろう。この衝迫は、命題としての道徳規範、社会常識、宗教教義などではないが、そもそもそれらが語られたときの、前提だったのではないだろうか。
4 ペルソナが示す生の歓び
音楽と言葉――交感性に支えられて聴く
谷川俊太郎の詩作論、『聴くと聞こえる』(2018)に与りながらいえば、交感性は、たとえば、人里離れた山奥の小屋で、夜半に目を覚まし、どこから聞こえてくる、かすかな何かの物音、虫の羽音、風の音、小川の音などが、聴くともなく聞こえることである。その音、その静寂は、自分が実在することよりも、さまざまな生命に満ちた世界が在ることを黙示している。私なりの表現をすれば、このとき、人は、エゴを忘れて、ただこの世界(外界)を感受している。この感受される世界は、耳で知覚されるものでもあれば、心に描かれるイマージュ(イマーゴ)でもある。
交感性はまた、人が音楽を聴くことを支えているだろう。私たちは、音楽をまるごと受け容れること、心身を音楽に浸すことで、はじめて音楽を聴くことができるからである。そして、その音楽が、何度も聴きたくなるほど自分を引きつけることが、音楽と人の共鳴共振かもしれない。谷川によれば、作曲家の武満徹は、仕事にとりかかるとき、いつもバッハの『マタイ受難曲』の終結部の合唱を聴いたという。そして、病床で最後に聴いた音楽も『マタイ受難曲』だったという(谷川 2018: 94)。
こうした音(楽)に対し、言葉は、他者にかかわろうとしている。生まれたばかりの赤ちゃんがあげる産声は、おそらく最初に人が発する呼びかけの、かかわりの言葉だろう。その言葉が、もっとも切実な言葉であるように、本来、かかわりの言葉は、だれかに対する切実な想いと一体だろう。
この切実な想いと一体の言葉にすっかり聴き従うことも、交感性に支えられているだろう。たとえば、「おお」「ああ」といった呻き声は、たんなる同じひらがなが並ぶ文字列であるが、その文字列に呻き声、つまり他者の苦しみ・つらさを感じることは、「AI」がしているような学習の成果ではないだろう。その感じとりは、感受する心のなせるわざ、ではないだろうか。つまり、静寂の世界を感受することも、他者の想いに聴従することも、同じ交感性の営みに支えられているように思う。
「意味・価値」といわれるものは、ここでいう交感性を前提にしながらも、すなわちそこから活力を得ていながらも、あまりにもしばしばその事実を忘却しているように思われる。多くの場合、エゴ(恣意・願望)、すなわち交感性を簡単に凌駕するそれが、意味・価値に取り憑いているからである。谷川俊太郎の言葉を引こう。「どんな天才も音楽を創りはしなかった 彼らはただ意味に耳をふさぎ 太古からつづく静けさに つつましく耳をすましただけだ」(谷川 2018: 103)。マルセルの言葉を借りれば、こうもいいかえられるだろう。「創造する者を包みこみ、彼を通じて噴出する神秘(mystère)がなければ、創造はありえない」と(Marcel 1940/1968: 131)。
交感性は、「私」のエゴが大きすぎると、言葉とともに失われるが、「私」のエゴがそれに寄り添うと、言葉とうまくはたらきだす。谷川俊太郎は「どんな言葉が私に親しいのか」と自分に問い、「‥‥私が歌うことではなく 私の歌われるのを私は聞く‥‥」と続けている。何かに誘い出されるように、思わず口ずさんでいる歌を聞くときのその言葉が、「私に親しい」と(谷川 2018: 23)。そのような言葉は、教育の世界に見いだされるだろうか。
教育を支える交感性
教育の世界では、「表現する力」や「自己形成」を育むことが、重視されている。そもそも人とは、みずから表現し、自分を形成する存在である、ともいわれる。そうした人間は、あの理性的に自律する「人格」に重なるようにも見える。たとえば、大正期・昭和前期の教育学者、木村素衛(1895-1946)は、人間を「表現的・形成的存在」と規定している。すなわち、人は、自分をつねに作り変えつつ生きていく存在、すなわちみずから表現しつつ、おのれを形成する存在である、と。しかし、木村の強調することは、理性的な自律ではなく、為すべきことは、日々の具体的情況のなかにしかないということである。彫刻家が、一打ごとに石と対話し応答しながら、鑿を打ち込んでいくように、自分が生きている今ここで他者・自然に応答しつつ、自分を表現し形成するしかない、と。
ひるがえっていえば、日常的な教育実践も、同じような応答の相をふくんでいる。教師は、いつも所与の目標から逆算し、いわばPDCAサイクル(目的合理性)で子どもたちに働きかけているのではない。教師はむしろ、具体的情況のなかで、子どもの表情・仕草を感じながら、その子どもに必要なものを洞察し応答している。その行為は、目的合理的というよりも呼応関係的である。そのような教師の応答は、さまざまな条件づけ、家庭環境、生育歴、気質、性格、習慣、交友、学力を勘案しなければならないにしても、眼前の子どもを感じとる交感性によって支えられている。
何が、この、子どもへの交感的応答の中味を決めているのだろうか。その応答が、心を込めたものであっても、ふりかえってみれば、「ふさわしくなかった」という場合もあるだろう。事実、後悔と無縁の教師などいないのではないだろうか。一つひとつの教育実践は、やりなおしがほとんどきかない一回性のはたらきかけであるから、教師は、できるかぎりその働きかけを後悔しないものにしたい、と思うはずである。そうであるとすれば、この教育実践における誤りを避けるうえで必要なものは何か。他者への教育的働きかけの「ふさわしさ」を決定するものは、何か。
私見を述べれば、それは、子ども一人ひとりの共鳴共振する力を無条件に信じることである。子どもが自分を圧倒する何か・誰かに出会い、心を揺さぶられること、憧れることをただ信じることである。一人ひとりの子どもに、その子どもに固有特異なテロスが象られることである。さきほどふれた思考の自由は、このテロスのためにあるのではないか。ともあれ、教育者に信じるものが必要であるとすれば、それは「無限の可能性」ではなく、共鳴共振する力である(と私は思う)。
経験が頽落するなかで
こうした人格(パーソン、ペルソナ)概念の思想的含意、すなわち交感性や共鳴共振は、現代社会を生きる私たちが、あらためて確認すべきことではないだろうか。というのも、現代社会は、ことさら有用性を重視するからである。バウマンが「リキッド・モダニティ」(液状的近代性)という言葉で形容しているように、現代社会は、意味・価値が、経済的利益に結びつけられているからであり、またそこで生じる不正・犯罪を防ぐために、規則・規範への僕従が強く求められているからである。
こうした現代社会の息苦しさのなかで、「理性的に自律する」人格が求められるなら、その人格は、有用性を「理性的に」求め、その有用性に向かい「自律する」人格になってしまわないだろうか。交感性よりも金もうけを「理性的に」重視し、金もうけに向かい「自律する」人格に。人を「自律」させる「理性」は、「合理性」(ratio ラティオ)でもあれば、「神言」(Logos/verbum ロゴス)でもある。合理性は経済的になるが、神言はそうならない。しかし、神言としての理性は、日本社会に根づいていないし、キリスト教やギリシア哲学の衰退とともに忘れられるだろう。そして、理性は合理性となる。
現代アメリカの哲学者、ドレイファス(Dreyfus, Hubert)は、1984年に「ニヒリズム」(Nihilism)という言葉を使って、神言が失われ、「経験」が、畏敬・崇高ではなく、享楽・興奮に向かうそれに変わりつつあるアメリカの現状を形容している。「私たちの関心がことごとく、通俗的な意味の〈経験〉[=勝ち負けのあるゲームに興奮するような]に還元されるとき、私たちは、ニヒリズムの最終局面に到達している」と(Dreyfus 1984: 136)。いいかえれば、私たちが、神言のような何らかの「大いなるもの」(Greatness)を分けもたないとき、私たちは、たんなる「享楽」「興奮」を得るために、だれかの優れた能力や人生を傍観的に〈経験〉することになる、と。そののち、現代にいたるまで、この通俗的な〈経験〉は、ますます広がっているように思われる。
しかし、現代社会の圧倒的な有用性志向のなかで、人はもはや過去に戻ることはできない。ドレイファスは「もしもあなたが歴史の昇りエスカレーターを降りようとしても、あなたはここ[=現代]に戻ってくるだけである」と述べている(Dreyfus 1984: 144)。私の提案は、この過去に奉じられた神言を脇におき、かわりに交感性、共鳴共振が生みだす生の歓びをもっと大切にすることである。それは、いいかえれば、声なき声で呼びかける他者に無条件にかかわることである。それは、ドレイファスが「関係の同定」(defining relation)と呼ぶことにひとしい。ドレイファスは「このような絶対的な[他者との]かかわりのみが、人格としての生(person’s life)に心豊かな特異性を生みだす」という(Dreyfus 1984: 144)。この無条件のかかわりに必要なものは、すでに私たちに与えられている。
見てきたように、「人格」の語源である「パーソン」(ペルソナ)は、本来、こうした生の歓びに通じていた。この生の歓びもまた、現代社会を生きる私たちが心に描くべきテロスではないだろうか。
〈文献〉
田中智志 2005 『人格形成概念の誕生――近代アメリカの教育概念史』東信堂.
田中智志 2017 『共存在の教育学――愛を黙示するハイデガー』東京大学出版会.
谷川俊太郎 2018 『聴くと聞こえる――on Listening 1950-2017 』 創元社.
渡辺和子 2005(1988) 『「ひと」として大切なこと』 PHP研究所.
Aquinas, Thomas 2006 Thomas Aquinas, Ecclesiae Doctores, De Ecclesiae Patribus Doctoribusque, Documenta Catholica Omnia Cooperatorum Veritatis Societas [wwwdocumentacatholicaomniaeu][Aと略記]
ST = Summa Theologiae / 1960-2012 トマス・アクィナス(高田三郎・稲垣良典ほか訳)『神学大全』(全36巻) 創文社
Augustinus, Aurelius 2006 Aurelius Augustinus, Migne Patrogia Latina, Documenta Catholica Omnia Cooperatorum Veritatis Societas [wwwdocumentacatholicaomniaeu] [AO と略記] DT = De Trinitate, PL 42 / 2004 アウグスティヌス(泉治典訳)「三位一体」『アウグスティヌス著作集』第28巻 教文館.
M = De Magistro, PL 32. / 1979 アウグスティヌス(赤木善光ほか編訳)「教師論」『アウグスティヌス著作集』第6巻 教文館.
Frankl, Viktor E 2009(1948) Der unbewußte Gott: Psychotherapie und Religion München: Deutscher Taschenbuch Verlag / 2016(1962) フランクル(佐野利勝・木村敏訳)『識られざる神』みすず書房.
Dewey, John 2008 The Collected Works of John Dewey, 1882-1953 ed, Jo Ann Boydston Carbondale, IL: Southern Illinois University Press [CW と略記 Early Works= ew / Middle Works=mw / Later Works= lw].
DE = Democracy and Education (1916, mw 9).
Dreyfus, Hubert L 1984 “Knowledge and Human Values: A Genealogy of Nihilism,” Daglas M Slaon, ed Toward the Recovery of Whoeness: Knowledge, Education, and Huamn Values New York: Teachers Cillege Press.
Dreyfus, Hubert / Tayor, Charles 2015 Retrieving Realism Cambridge, MA: Harvard University Press / 2016 ドレイファス/テイラー(村田純一監訳)『実在論を立て直す』法政大学出版局.
Green, Thomas H 2003(1883) Prolegomena to Ethics, Oxford: Clarendon Press[PEと略記]
Kant, Immanuel 1974 Immanuel Kant Werkausgabe, 12 Bdn Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag[KWと略記]/ 1999-2006 カント(坂部恵・有福孝岳・牧野英二編)『カント全集』全二二巻 岩波書店.
KpV = Kritik der praktischen Vernunft, W 7. / 2000 カント(坂部恵/伊古田理訳)「実践理性批判」全集七 .
MS = Die Metaphysik der Sitten, W 8. / 2002 カント(樽井正義・池尾恭一訳)「人倫の形而上学」全集一一 .
Luhmann, Niklas und Schorr, Karl E. 1988 Reflexionsprobleme der Erziehungssystem 2 Aufl Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Marcel, Gabriel 1940 Du refus a l’invocation. paris: Éditions Gallimard. / 1968 マルセル(竹下啓次・井藤晃訳)「拒絶から祈願へ」『マルセル著作集』3 春秋社.
Oelkers, Jürgen 2007 “Lernen versus Wissen: Eine Dichotomie der Reformpädagogik,” Allgemeine Pädagogik, Pädagogisches Institut der Universität Zürich [wwwpaeduzhch/ap].
Pinker, Steven 2002 The Blank Slate : The Modern Denial of Human Nature New York : Viking Press = 2004 山下篤子訳『人間の本性を考える』上/中/下巻 日本放送出版協会.