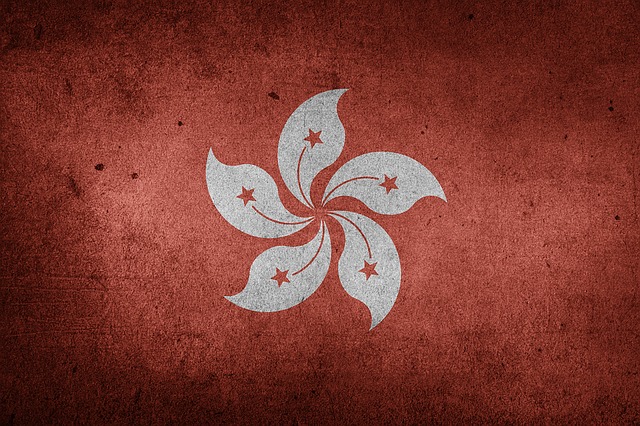はじめに
朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)は、その成立過程を調べてみると、端的にいえば<ソ連の強い指導の下につくられた国>といえる。北朝鮮の成立過程は、戦後のポーランド共和国成立過程に類似しているので、まずそれを見てみよう。
戦後ポーランドでは、ナチス・ドイツからの解放後の1944年7月、ポーランド統治の臨時執行機関としてルブリン政権(ポーランド国民解放委員会)がその樹立を宣言した。ルブリン政権とは、ソ連がポーランドの共産主義者をソ連領内で養い、解放前後にポーランドに送り込んで軍事占領させて新たに立ち上げた「ポーランド政府」だった。
さて、太平洋戦争直前の1940年ごろ、満洲国軍と同国警察は満洲国東部にいた朝鮮人パルチザンを徹底的に討伐し国内に存在できないまでに掃討した結果、朝鮮人パルチザンは沿海州に逃げて行った。ソ連はハバロフスク近郊で彼らをソ連軍人(第88独立狙撃旅団)として養った。この旅団は、元東北抗日聨軍将兵が中核となり、中国人と金日成(同旅団第一大隊長)ら朝鮮人から編成され、中国共産党は「東北抗日連軍教導旅団」と称していた。
ソ連は1945年8月9日早朝、対日参戦したが、ソ連軍は金日成らパルチザン・グループを連れて朝鮮半島に進駐した。金日成を領袖として押し立て、ソ連の息のかかった政権を樹立しようとしたのであった。
日本の敗戦当時、朝鮮半島に戻ってきた朝鮮人の政治的派閥にはいくつかあった。一つは金日成を中心とする朝鮮人パルチザン・グループ、次に中国・延安を根拠地とする中国共産党の指導下にあったグループ(延安派)、そしてソ連に滞留していた人たちを中心とするソ連派、朝鮮半島内部で抗日運動を展開してきた南朝鮮労働党のグループ(南労党派)などで、それらの派閥が競合していた。
1.開戦の経緯
(1)スターリンと毛沢東の承認
朝鮮戦争が、北朝鮮のいかなる政策によって始まったのかについて簡単に見てみよう(参考:赤木完爾編著『朝鮮戦争―休戦50周年の検証・半島の内と外から』慶應義塾大学出版会、2003)。
まず金日成には正規軍によって戦争を起こし、南朝鮮を解放しようという野望があった(南朝鮮解放戦争路線)。それに加えて南朝鮮内でゲリラおよびパルチザン活動を展開して革命につなげようという、朴憲永(1900-56年)を中心とする南朝鮮労働党主導の南朝鮮革命路線があった。これらが合流して戦争に至ったというのが、スタンダードな歴史解釈である。つまり、朝鮮戦争の開戦に決定的であった最大の要素は、金日成の南北武力統一の意思であり、それにスターリンの承認、毛沢東の積極的同意が付け加えられて朝鮮戦争の開戦につながったのである。
その経緯についてもう少し詳しく見てみよう。
1949年3月に、金日成を中心とする北朝鮮政府代表団は「朝ソ経済文化協力協定」等を結ぶことを主目的としてモスクワを訪問した。そのとき金日成は、南朝鮮を武力で解放できる機が熟したので南に進撃したい旨をスターリンに伝えたが、スターリンは、「北側の軍隊は潜在的な敵に対して絶対的な優位に立っていないし、加えてソ米間には38度線に関する協定がある。ゆえに南側が先に攻めた場合のみ攻撃は正当化される」と述べて、金日成に対南攻撃を思いとどまらせたという。
その後も金日成はスターリンに対して何度も対南攻撃計画の承認を求めたが、スターリンはそれについて一貫して慎重な態度であった。ところが約1年後の1950年3月末から4月25日にかけて金日成を中心とする北朝鮮政府代表団は再びモスクワを訪問し、スターリンとの首脳会談に臨んだ。そこでスターリンは次のように語った。
国際情勢の変化により朝鮮半島統一のために積極的な行動を取り得る条件が整った。すなわち中国共産党が国民党政権を打倒し、ソ中が条約を締結、ソ連が原爆を保有したことなどで、米国も朝鮮問題では下手な行動は取れないだろう。
このようにして金日成はスターリンから対南攻撃計画の承認を得ることができたが、スターリンは金日成に対して毛沢東に会って彼の同意を得ることを条件として求めた。そこで金日成と朴憲永は、5月13日に北京を訪問し、毛沢東と数回の会談をもって協議をした結果、毛沢東はソ朝首脳会談で合意された対南攻撃計画を全面的に支持した。
当時毛沢東は、1949年10月に中華人民共和国を建国し、翌50年1月に中ソ友好同盟相互援助条約を結んだばかりの状況だったから、共産主義のいわば宗主国であるソ連のスターリンの要請を断れるような立場にはなかった。また毛沢東は、建国前後に米国との関係改善のための工作を秘密裏に進めていたが、それがスターリンに知られてしまった。そのため毛沢東としては、スターリンの革命路線(国際共産主義)に対する忠誠を獲得する必要に迫られていた。このような背景があって、毛沢東の金日成の南進政策に対する態度は非常に積極的だった。このような中ソ関係は、朝鮮戦争勃発後に中国の人民志願軍を送るかどうかを決断する際にも影響を与えていた。
これらの経緯を総合してみると、この戦争がスターリンの許可なしにはできないことは明らかであるにもかかわらず、その責任はすべて中国(毛沢東)に肩代わりさせようとしたのである。
(2)スターリンが対南攻撃を承認した理由
前後するが、1950年4月に金日成は(対南攻撃計画への合意を得るべく)訪ソしてスターリンと会談した際、次のように語って説得した。
北朝鮮の決定的な奇襲攻撃によって戦争は3日間で終結すること、攻撃と同時に韓国内の多くの共産党員が蜂起するとともに韓国に潜伏しているゲリラも北朝鮮軍を支援するだろうから、米国が介入する時間的余裕はないと。
しかしスターリンは、「米国は介入してこないだろう」という金日成の主張を額面どおりに受け取るような人物ではなく、自分なりの情報を持って情勢を判断していた。それでは、それまで北朝鮮による対南攻撃計画に対して慎重だったスターリンが、許可を与えた背景としてどのような国際情勢の変化があったのだろうか。
スターリンにとっての最大の懸念事項であった米国の介入の可能性に関して、韓国を米国の不後退防衛線(defensive perimeter)から外すことを示したアチソン演説(1950年1月12日)は、北朝鮮の対南攻撃に慎重なスターリンの考えを翻意させた一つの要因であったと思われる。
アチソン演説当時、中ソ友好同盟相互援助条約交渉のために毛沢東と周恩来はモスクワに滞在していた。演説当日、その内容についてヴィシンスキー外相が、二人に対してブリーフィングした。それは米国がいかにアジアに対して消極的かということをエンドースするような話だった。
アチソン演説以外にもスターリンの考え方に影響を与えたできごとがあった。
ひとつは、アチソン演説の数日前の1月5日には、トルーマン大統領が台湾への不介入を宣言したことである。これもアメリカのアジアに対する消極性を示すものとして受け止められた。
もうひとつは、ソ連の英国人スパイを通じて、1949年12月に承認された米国家安全保障会議の政策文書NSC48の内容をスターリンが承知していたということである。NSC48には、米国の不後退防衛線に関する内容が含まれていた。当時、駐米英国大使館は、常時米国務省やその政策企画本部と連絡を取り合っており、同大使館にいたドナルド・マクリーンなどの英国人スパイがそれをソ連にリークしていたのである。
(3)巧みな金日成の外交術
金日成が1950年4月に訪ソしてスターリンと会談した際、スターリンは朝鮮半島の再統一を進めようとする朝鮮の提案に同意したが、(最終的には中朝両国の一致によって進めなければならないとして)中国(毛沢東)の同意を得るように求めた。
それを受けて金日成は、同年5月に訪中し毛沢東を訪問した。当初、毛沢東は懐疑的で米国が介入する可能性について再度警告した。それに対して金日成は、まず対南侵攻成功の見込みについてスターリンが言っていたよりも誇張して、さらに楽観的に説明した。
また、当時毛沢東は、台湾侵攻を計画してソ連の支援を求めていたが、スターリンは米国を刺激する恐れありとして台湾侵攻には反対していた。しかし先述したように、トルーマンの台湾への不介入宣言(1月5日)を受けて考えを変え、毛沢東に対しても金日成の計画を推し進めるように促した。
毛沢東は金日成に対して、米国が実際に介入した場合に、中朝国境に兵力を駐留させることを中国に求めるかと聞いたが、金日成はその必要はないと答えた。その後、金日成は、毛沢東が(戦争には応分の協力を惜しまないと)非常に強く支持してくれたとスターリンに報告した。
以上をまとめると、金日成はロシア人と中国人の双方に対してそれぞれがいかに支援してくれるかを、金日成の期待する程度まで<誇張して>両方に伝えているのである。ある意味で離れ業の外交交渉をやったのだった。
2.戦争準備について
(1)ソ連軍人による戦争計画の作成
スターリンは、北朝鮮におけるソ連の軍事顧問団の増強については認めていて、1950年2月ごろにヴァシリエフ中将を朝鮮人民軍の主席軍事顧問として北朝鮮に派遣し、戦争の指導に当たらせた。3月には金日成がヴァシリエフ中将に頼んで1カ月余りで作戦計画を立てさせた。そしてソ連から戻った兪成哲(1917-96年、朝鮮人民軍中将)が、ロシア語の作戦計画を朝鮮語に翻訳した。
その計画に関して毛沢東が事前にどの程度知っていたかは明確でない。毛沢東は、朝鮮半島で何が起きようがほとんど関心がなく、朝鮮戦争開戦(6月25日)2日前に、台湾海峡への部隊派遣を指示していたというから、毛沢東も油断していたのではないか。
朝鮮人民軍の南侵計画は次の3段階からなっていた。
1)ソウルを攻撃し3日以内に占領し、韓国軍主力を撃滅する。
2)戦果を拡張し、群山・大邱・浦項に進出。
3)韓国軍を掃討し南海岸に進出し統一する。
第一段階をみると、かつてソ連軍がノモンハンやスターリングラードで行った両翼包囲の再現であり、ソ連の軍事指導の跡がみえる。第二段階以降の計画は、極めて大雑把であり、ソウルを占領すれば戦争は終わると考えていたようにも思える。
またソウル占領後は、パルチザンなどの人民蜂起により韓国の内部崩壊を誘発することを前提にしていたようである。しかし実際の戦争は、作戦で描いたようには進まなかった。期待した人民蜂起は起こらず、意外にも早期に米軍が介入し、それによって韓国軍も次第に再建されて抵抗した。
上記の内容を裏付ける証言を紹介する。
「われわれの南侵計画は3日以内にソウル占領で終わることになっていた。われわれは、首都ソウルを占領しさえすれば、全土が手に入るものと錯覚していた」(兪成哲『北朝鮮元作戦局長の証言』)。
「ソウルを占領すれば、南の全土に潜伏している20万の南労党員が蜂起して、南の政権を転覆するという朴憲永の大言壮語を頭から信じていた」(同上)。
「戦争計画はソウル解放までだけを計算して作成されていた。それは準備期間が不足だったり、他に理由があったためではなく、金日成がそれ以上の必要性を感じなかったためである」(林隠『北朝鮮王朝成立秘史』)。
ところで、開戦時に朝鮮人民軍は約18万人いたが、そのうち6万人が中国人民解放軍から転籍した部隊だった。これは朝鮮系中国人、すなわち鴨緑江の北にある間島(現・中国吉林省付近)に多く住んでいた朝鮮族から人民解放軍がリクルートした兵士たちで、3個師団約6万人だった。1949年5月に毛沢東が承認して2個師団が朝鮮人民軍に転籍し、その後1950年1月初めの中ソ同盟の条約交渉のときに、3番目の最強といわれた部隊の転籍を認めたのだった。この最強部隊が、戦争が始まったときにソウルの正面に登場したのだった。
(2)先制打撃作戦
前節で述べた「先制打撃作戦」の構想は、概ね次のとおりだ(『朝鮮人民の正義の祖国解放戦争史』1961年より)。
・敵の進攻を挫折させた後、直ちに反撃に移り、米国がその大兵力を朝鮮戦線に増派する前に、高度の機動力と連続的な打撃をもって李承晩傀儡軍を撃滅、掃討し、南半分の全地域を解放する。
・敵の進撃を阻止した後、決定的な反撃に移ってソウル地域で敵の基本主力を包囲殲滅し、その戦果を拡張して南海岸に進出する。
ところで、かつて日本では朝鮮戦争の開戦に関して南北どちらが先に進攻したかという「先攻論」が盛んに論じられたことがあったが、その後、各種資料の公開によって現在では北朝鮮が先攻したというのが定説である。そうした議論が起きた背景の一つに、上述に示された文章の中に示された「反撃」という概念があった。つまり、モスクワから派遣された軍事顧問団が戦争計画を立てたときに、南が先に北を攻撃したというフィクションを作ろうとして「反撃する」という言葉を意図的に用いたのである。
後に北朝鮮のある将軍は、「反撃と言う言葉を使ったのは、偽造の、すなわちわれわれの計画を隠蔽するための偽情報(disinformation)だった」と語った。それが後に日本のメディアや学界で増幅されたのだった。
朝鮮人民軍の作戦計画で期待されていた南のゲリラについては、南朝鮮国防警備隊(米軍政庁統治下の南朝鮮の防衛組織で、韓国陸軍の前身)が1948年以降、南朝鮮労働党のゲリラ活動に対して徹底的な弾圧を加えており、50年6月の開戦時には、南のゲリラはほぼ壊滅状態だった。一方、南朝鮮国防警備隊は、韓国各地の山岳地帯を中心にゲリラ掃討に集中していたために、かえって在来型の戦争の準備や訓練が手薄になっていた。
そのような態勢の韓国軍は、6月25日早朝、朝鮮人民軍の侵攻は、予期しない時期に、予期しない方向から、予期しない規模での奇襲となり、開戦3日後の6月28日にはソウルが陥落した。このとき命令系統が混乱した韓国軍は、漢江にかかる橋を避難民ごと爆破してしまうという事件も起こり、漢江以北に多くの部隊や住民が残され自力で脱出することにもなった。
その後、韓国軍は一気に釜山まで追い詰められたが、9月にマッカーサーが仁川上陸作戦を展開すると、釜山を拠点としていた米第8軍が猛反抗に出て朝鮮人民軍は全面的な敗走を余儀なくされた。
釜山橋頭堡での戦闘において朝鮮人民軍18万人は、全滅とはいえないまでも、国連軍の猛攻によってほぼ攻撃能力を失ってしまったといわれる。その後、敗走する朝鮮人民軍を韓国軍ないし国連軍が鴨緑江まで追撃した。そこで中国の人民志願軍が介入し始めると、米第8軍は歴史始まって以来の大敗北を喫して南下を余儀なくされた。
このようにして開戦から3年1カ月にわたり戦線が展開され53年7月に休戦となった。
3.中朝連合と戦争の余波
中朝聨合司令部を中国では「聨司」と呼んでいるが、その実体について明らかになったのは、実はここ十年くらいのことだ。この合意形成は、中朝関係を象徴するような性格が見られるので、述べてみたい。
1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争は、朝鮮人民軍が奇襲をかけて緒戦に勝利したが、9月15日に国連軍の仁川上陸作戦によって軍事的優位を失った。国連軍が38度線を突破する中、毛沢東は(人民解放軍を改編して)中国人民志願軍を編成し、彭徳懐(1898-1974年、中国の軍人・元帥)をその司令官に任命した。そして10月19日には彭徳懐率いる中国人民志願軍(副司令官には延安派の朴一禹が任命)が参戦した。10月25日には中国人民志願軍と朝鮮人民軍の間で、中朝聨合司令部が設置され、朝鮮人民軍は朴一禹の指揮下におかれた。実質的には、朝鮮戦争はこの時点から<米中戦争>だったとみるべきではないかと思う。
中朝聨合司令部に関して、次のような合意がなされた。
1)朝鮮国境内では中国が軍事的統一指揮を行う(⇒北朝鮮の戦争指導に関する無能力を含意)。
2)北朝鮮の政治工作には干渉しない(⇒敗走の政治的責任の存在を含意)。
3)指揮命令は、朝鮮人民軍総司令部と中国人民志願軍の二系でなされる(⇒北朝鮮の面子の保持)。
4)新聞報道は聨合司令部での編集後、朝鮮人民軍総司令部名義で統一的に配布する。
その上で、中朝空軍聨合司令部(1951年3月中旬)、中朝聨合運輸司令部(瀋陽、1951年8月上旬)がそれぞれ設置された。統一指揮組織は、いずれも中国がチーフで副司令官を北朝鮮が担当するというやり方をとった。
以下、それぞれについて詳しく述べてみよう。
1)軍事的統一指揮
北朝鮮は戦争指導に関してはほぼ無能力だった。そもそも戦争の作戦から命令まで、ソ連軍事顧問団の指導を受けて行い、最初ロシア語で書かれたものを翻訳して進めたくらいだった。そうせざるを得なかった背景には、北朝鮮軍の能力の問題もあったのだろうと思われる。この取り決めはそれらを含意している。
2)北朝鮮内政への不干渉
中国は北朝鮮の政治工作に関与しないというのは興味深い項目だ。北朝鮮が米韓軍に負けたことについて政治的責任が生じ、それが追及された場合、中国はその責任問題には関わらないという意味だ。つまり敗走の政治的責任については、中国は云々しないということである。
無傷で残った朝鮮人民軍は3万人ほどだったが、その部隊を政治工作に、あるいは金日成の政治的権力基盤強化のために使うことを、聨合司令部とのやり取りの中で中国は認めていたのではないかと思われる。
3)指揮命令の二系統
指揮命令を二系統でやることの意味としては、北朝鮮の面子を尊重しているということだろう。ここで強調したいことは、後方兵站のための運輸司令部を設置するときに北朝鮮は、司令官は北朝鮮から出すことについて非常に固執し強く主張し続けた。中国はそのつどスターリンに関与してもらい、北朝鮮を納得させていたほどだ。北朝鮮の主張がスターリンの介入によってようやく覆されるというパターンが繰り返された。
思うに、北朝鮮の軍事的能力には限界があったことは認めざるを得ない。延安派やソ連派の人々はそれなりに軍事能力を持っていたものの、パルチザン派の古参幹部は、字が読めない人もいたようで、すべてが近代戦に対応できる人材とは言えなかった。
中朝聨合司令部の設置によって、戦争中は北朝鮮の存続が保証されるとともに、中国人民志願軍の助けを借りて戦線の建て直しに成功することができた。しかしその一方で、(最終的に北朝鮮は事実上戦争に負けたために)開戦までに築かれていた金日成の権力基盤がゆらぐことになった。そして戦後、金日成がもう一度権力基盤を確実にするための派閥争いが起きるきっかけにもなった。
3.戦争後の金日成による権力基盤確立
中朝関係は「血で固められた友誼」「血盟関係」などとよく表現されるが、その真実はどこにあったのか。中朝関係はソ連を抜きにしては考えられない。当時スターリンは、共産主義陣営において圧倒的な存在だった。毛沢東は、困難な条件の下でも人民志願軍の参戦を決意したことで、ソ連と社会主義陣営に対する中国共産党の忠誠心を示すと同時に、アジアの革命の実質的リーダーとして、ドライバーズ・シートに座ったような気持ちだったと思う。これによって毛沢東は、スターリンの信頼を得て、中ソ同盟を強固なものにすることができた。
戦争期間中、モスクワと北京の意見は一致していた。大規模な志願軍を連続して朝鮮半島に送ったことによって、中国はかなりの程度で戦争の戦略戦術について実質的な発言権、指導権を手に入れた。
また中ソ両国の考えが一致したということは、中朝間でトラブルが起きたときに、スターリンは概ね例外なく重要問題については毛沢東の側に立つことになった。もちろん、当時の北朝鮮がソ連に対して楯突く勇気はなかったが、他方で北朝鮮の側では中国に対する不満、怨恨が生じたであろうことは想像に難くない。
金日成は、強烈な民族独立、ナショナリズム意識の持ち主で、朝鮮において圧倒的な独裁的支配的地位を樹立しようとした。しかし北朝鮮内部では、パルチザン・グループ、ソ連派、延安派、南労党派が対立していた。
なかでも延安派は、大部分が軍事分野の指導者で、彼らは参戦した中国軍と密接な関係を持っていたために、それは金日成にとって将来への不安材料ともなった。
また中国の人民志願軍の関与によって、金日成は軍事権力を一時期延安派(朴一禹など)に渡さざるを得なくなった。その意味では金日成を支持するパルチザン派は、権力内で後退した。
朝鮮労働党はソ連派の許歌誼が握っていたが、金日成は南労党派と延安派とが連携するのではないかと恐れていた。そこで金日成はソ連派を最初に粛清し、その後、慎重に権力闘争を進めながら延安派をも粛清して権力基盤を固めていった。
おわりに
以上、朝鮮戦争をめぐる経緯について簡単にみてきたが、この含意を考えてみる。
ひとつには、金日成の高度な交渉力である。金日成は、対南攻撃の承認を得るために、開戦前からスターリンが言ったことと毛沢東が言ったことをそれぞれうまく自分の都合のよいようにアレンジして双方に伝え、曲芸のようなネゴシエーションをやって、自分が引き出したい利益をうまく引き出すことができた。
50年代終わりから60年代に中ソ対立が徐々に深刻化していく中で、金日成は中ソ両国にうまく立ち振舞って、双方から巧みに援助を引き出した。金日成は、北朝鮮の内政においてその指導権を確立させつつ、対外的には1961年7月にソ朝友好協力相互援助条約と中朝友好協力相互援助条約を相次いで結び、両者のバランスをとった(ただし、ソ朝友好協力相互援助条約は1996年に破棄・失効した)。
もうひとつは、北朝鮮の人々は生易しい人々ではないということである。冷静に見た場合に、北朝鮮にとっては、中国であれ、ソ連・ロシアであれ、相手に対する信頼感がないのだろう。第三者を関与させながら、中ソ(ロ)を天秤にかけて、一方がダメになったときにはもう一方を使うといったように、リスクヘッジ、リスク分散として戦略的に利用する傾向が見られる。
「主体思想」は、中ソ論争・対立の時代に金日成が主張・強調し始めたものだが、そこには当時のソ連ないしは中国の一方への依存を回避し、北朝鮮の行動の自由(自主性・主体性)を確保するために、生み出されたものではないかと思う。一方との関係が仮に破綻したとしても、もう一方との関係が維持されていれば、すぐさま北朝鮮の安全保障体制が崩れるわけではない。そのようにしてしたたかに何十年もやってきた。
最後に、北朝鮮はなぜ核兵器にこだわるのかについて、朝鮮戦争の経験から考えてみたい。北朝鮮のGDPは韓国の50分の1程度(『エコノミスト』誌)という経済力の国だが、その北朝鮮が核兵器に固執するのには、彼らが経験した歴史的理由があると思う。
朝鮮戦争中の米軍の爆撃は、ひとことでいえば、おぞましいほどの破壊レベルであった。あの狭い地域にあれほどの爆撃をして破壊すると、ある種のシニシズムやトラウマが世代を超えて残っているのではないかと思われる。
単純な比較はできないが、日本では、広島・長崎の原爆の陰に隠れてあまり言われないが、8月14日の夜まで米軍は日本本土の中小都市を全滅させるつもりで爆撃を遂行した。例えば、富山、八王子、沼津など、市街地のほぼすべてが焦土となった都市が少なくなかった。朝鮮戦争における北朝鮮全土への米軍の爆撃は、そのレベルをはるかに超えるものだった。これに対するトラウマはわれわれの想像を絶するものがあったに違いない。
朝鮮戦争後、アイゼンハワー政権時に米国は在韓米軍に戦術核兵器を積極的に配備したことがあった。そして韓米の合同軍事演習が毎年行われているが、そのような米韓との長期間にわたる対峙状況にいると、核の問題は、北朝鮮にとって国家の存立とイコールになってくるのではないかと思われる。ここに北朝鮮が核にこだわる歴史経験的理由があると考えている。
(本稿は、2017年10月4日に開催した政策研究会における発題内容を整理してまとめたものである。)