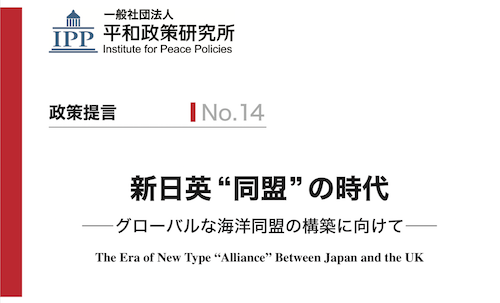1.現代世界を支配する情報・インテリジェンス
(1)インテリジェンスとは
近年日本でも、「インテリジェンス」ということばが広く知られるようになったが、一般にそれから連想されるのは、「諜報」「スパイ」などかもしれない。インテリジェンスを学術的に定義をすれば、「相手国の秘密や将来の事項について、断片的なデータを集め、それらを集約、分析することによって作られる情報」であり、「そのような情報は政策決定者や軍人(⇒カスタマー)の判断に寄与する」ものである。そのような基本的な意味からさらに拡大して、「秘密情報」、(インテリジェンスを扱う)「情報組織」、「情報活動」をも含むことになる。
つまり、世の中にある多くの一次情報(外部環境・状況)データから精選し(=インフォメーション)、それらをさらに収集・分析してカスタマーにとって意味のある情報とする(=インテリジェンス)というイメージである。
(2)国家の情報活動
国家は、一体何のために情報活動を行うのか。米国家情報局の資料によれば、米国における(対外情報機関の)情報活動の最大の目的は、国家に対する脅威の有無(認識)と有事の際の危機管理に必要な情報を提出することにある。その他に、①対テロ情報収集、②大量破壊兵器の拡散対策、③サイバー情報の収集とセキュリティ、④防諜活動などが挙げられている。
最近の例でいうと、2018年6月12日の米朝首脳会談に向けて米国では最初にCIAが動いた。日本であれば外務省が動くところだろうが、諸外国の場合は、対外情報機関が動くことはよくあることだ。米朝間には公式の外交関係が存在していないこともあるが、対外情報機関は大抵外交とは別の交渉ルートと独自の情報を持っており、水面下で動くことが可能なことがある(=バックチャンネル)。
その他の対外情報機関の活動には、秘密工作がある。例えば、プロパガンダ、ハニートラップ、暗殺・破壊活動、政治工作、準軍事作戦などである。最近の事例では、ロシアの情報機関によるフェイク・ニュースの作成・流布、ソチ・オリンピックのドーピングへの関与等がある。
またインテリジェンス大国としては、米国、英国、イスラエル、ロシアなどがよく知られている。
(3)ルールや規範の希薄な世界
インテリジェンス(スパイ)の世界にルールはあるのか。外交の分野では国際条約などの国際法規があり、軍事分野では戦争法規があるが、インテリジェンスの世界には、慣習を含めても明確なものはあまりない。しいていくつか挙げれば、次のようなものだろう。
①サード・パーティー・ルール:協力関係にある外国の情報機関から提供された情報は、その提供者の許可なしに第三者に提供してはいけない。
②しっぺ返し:やられたらやり返してもいい。
サード・パーティー・ルールは、厳格に遵守されているが、しっぺ返しは非常に曖昧に運用されている。例えば、自国のスパイがA国で捕まった場合、自国にいるA国のスパイを捕まえて、スパイ同士の相互交換を行うというものである。
インテリジェンスのために対外情報機関はありとあらゆる手段を用いる。例を挙げれば、古くからあるものとして、ゴミ箱漁り(タマリスク作戦)、ハニートラップ、ほかにCIAのネコ(注:ネコに通信傍受器をつけて対象大使館の敷地に放して盗聴)、スターゲイト・プロジェクト(注:とくに冷戦時代の米陸軍で、超能力者をつかって相手国の遠隔透視を行い情報を収集しようとしたがほとんど成果はなかったといわれる)などがある。
インテリジェンスの世界は、常に情報を先に取った者が勝ちという価値観で動く世界だ。時には、情報の盗み、暗殺等、倫理的に問題となるようなことも行う。そのため情報活動者の中には、そのことについて疑問を抱く人もいるが、インテリジェンス・オフィサーには基本的に目的遂行のための確固たる使命感・国家観が要求される。それが欠如した場合には、情報を敵国に売ることにもつながりかねない。
(4)電子情報の「落とし穴」
現代世界のような高度な情報通信技術の発達に伴い、われわれの生活が電子化して便利になればなるほど、それらの情報は知らぬ間に抜き取られている現実がある。はっきりいえば、デジタル化された情報は、どこかで必ず抜き取られていると認識しなければならない。例えば、電子メール、携帯電話の通話記録、LineやFacebookなどのやり取り、SUICAやPASMOのデータ、クレジットカードの使用歴、Skypeのウェブカメラ、テレビ番組の選択、Google Carによる無線LAN情報の収集等、きりがない。
最近の事件としては、スマホアプリKAKAO Talkから2年にわたって数十億人分の個人情報が流出した事件、Facebookの個人情報が英国の調査会社に流れていた事件等がある。ウィキリークスによると、サムスンのスマートテレビの一部には、録音デバイスが仕組まれており電源がオフの状態でも室内の音声を拾っており、電源がオンになったとたん、その情報が対外情報機関に送られたという事例もある。
また元ISAF司令官・CIA長官のデヴィッド・ペトレアス将軍は、ポーラ・ブロードウェルという女性ジャーナリストと不適切な関係にあったが、現役のCIA長官時代にGmailを使ってその女性とやり取りをしていた。Gmailには、自分のアカウントに保存しておいた文書などが、メールで送信せずとも相手がパスワードを知ってさえいれば見ることができる機能があるが、それを利用したのだった。しかし女性との関係のもつれによってそのことが暴露されて問題となった。この事件の何が問題かというと、CIAという対外情報機関のトップですら、自分のメールが誰に読まれているのか配慮しなければならないということだろう。
2.国家による情報活動
(1)国家インテリジェンス
ここでインテリジェンスについて整理すれば、次のようになるだろう。
①第一義的には生物がもつ知性である。
インフォメーションを取捨選択するための能力である。
②国家レベルのインテリジェンス。
国家がインフォメーションを取捨選択するための能力、国家の知性である。
③敵国に関する評価された情報。
インフォメーション=データ+α、情報資料etc
インテリジェンス=(加工された)情報、プロダクツ、査覈(調査)資料
インテリジェンスには「評価」というプロセスが入るために、同じ情報でも立場によっては、情報資料、生情報、情報、インテリジェンス、兆候、証拠などととらえ方が異なる場合もあり得る。
ここで米国のCIA(中央情報庁)のインテリジェンスの定義を見ておこう。
<最も単純化すれば、インテリジェンスとはわれわれの世界に関する知識のことであり、米国の政策決定者にとって決定や行動の前提となるものである>
ただし、英国では、同じ「インテリジェンス」という言葉が、米国とは異なるニュアンスで使われている。米国人は<分析する>ことに重きを置き、「何らかの分析を加えた情報」という意味で使うが、英国人は「秘密の情報源から取ってきた秘密の情報」というように、<情報源>に重きを置いている。
以上を踏まえて私は、インテリジェンスを「国益のために収集、分析、評価された判断のための情報」と定義している。
(2)各国のインテリジェンス組織
英米のインテリジェンス組織を見てみよう。
米国:中央情報庁(CIA)、連邦捜査局(FBI)、国防情報庁(DIA)、国家安全保障庁(NSA)
英国:内務省保安部(MI5)、秘密情報部(MI6)、政府通信本部(GCHQ)
日本における情報インテリジェンスを扱う主な組織は、次の通り。
・内閣情報調査室(=「内調」CIRO)
・防衛省情報本部(DIH)
・公安調査庁(PSIA)
・内閣衛星情報センター(CSICE)
ただし、いまだに諸外国にあって日本にないのは、米国のCIAや英国のMI6のような、いわゆる「対外情報機関」である。ちなみに、「軍隊のない国」としてよく知られた中米のコスタリカにも対外情報機関はあり、世界広しといえども、対外情報機関がない国は日本くらいではないか。
一般に一国の中の対外情報組織に加えて、防諜組織、軍事情報部など複数の情報組織を総称して「インテリジェンス・コミュニティ」と呼んでいる。主なインテリジェンス・コミュニティの規模、すなわち予算と人員数および国防予算に占める割合は、次のようになる。
<米国>8兆円、20万人、12%
<英国>3000億円、1.6万人、10%(但し国防情報部の予算は含まず)
<フランス>1200億円、1.3万人、4%(人員は5~6%)
<イスラエル>6000億円、6000人、10%(但し国防情報部の予算は含まず)
<日本>1500億円未満(推定)、5000人未満、2~3%
欧米では、大体国防予算の5~10%くらいをインテリジェンスに割いていることがわかる。一方、日本はどうかというと、政府自身この分野の予算の全体を試算しておらず、上記の数値は私が推計したものだ。これをみても、日本はインテリジェンス関連にあまり予算を割いていないことがわかる。
(3)情報組織の特徴
情報組織は、単に予算や人員だけでその組織の強さが測られるわけではない。それに加えて、情報の特性とも絡んで、情報の共有・集約がどうなされているかが重要なポイントとなる。情報機関は、基本的に(縦割りの)官僚組織であるから、情報を共有することを嫌がる傾向がある。
例えば、米国のCIAとFBIは、互いの情報の共有がなされておらず、何か事件が起きたときには、一方の組織に情報があったのになぜ(大統領に)上がらなかったのかなどと、問題になることがままある。
ゆえに国家が情報を国家戦略として有効に活用するためには、情報組織間の風通し、情報共有をいかに進めておくかが、重要なポイントである。この点で、英国はうまくやっていて情報機関同士の風通しが非常によい。
英国では、MI6とMI5はふだんから情報を共有しているし、他の組織もなるべく共有できるように、それらの中央に一つの別組織「合同情報委員会(JIC)」を設けて、そこにあらゆる情報が流れ込んでくるようなしくみにしている(図1、同輩的協力関係)。
 一方、米国は英国のような組織になっておらず、各情報組織が独立していて情報が集約されないために、強制的に情報を吸い上げる組織として「中央情報機構(DNI)を設けて、そこからホワイトハウスに情報を上げている(図2、中央集権型)。
一方、米国は英国のような組織になっておらず、各情報組織が独立していて情報が集約されないために、強制的に情報を吸い上げる組織として「中央情報機構(DNI)を設けて、そこからホワイトハウスに情報を上げている(図2、中央集権型)。
 ちなみに、CIA(中央情報庁)はかつて(DNIのような)情報集約の役割を担っていた名残として、「中央」という言葉がついていているのである。しかし2003年のイラク大量破壊兵器問題での不手際によって格下げとなってしまい、現在の位置に落ち着いた。
ちなみに、CIA(中央情報庁)はかつて(DNIのような)情報集約の役割を担っていた名残として、「中央」という言葉がついていているのである。しかし2003年のイラク大量破壊兵器問題での不手際によって格下げとなってしまい、現在の位置に落ち着いた。
主な国のインテリジェンス・コミュニティの特徴を表したのが図3である。
 米国のように強制的に情報を集約するタイプの国が多く、英国のように自然と情報を共有できるタイプの国は例外的だ。英国型は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどコモンウェルスの国々が多く、情報組織について英国から学んだ経緯もありイスラエルはこのタイプである。
米国のように強制的に情報を集約するタイプの国が多く、英国のように自然と情報を共有できるタイプの国は例外的だ。英国型は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどコモンウェルスの国々が多く、情報組織について英国から学んだ経緯もありイスラエルはこのタイプである。
3.英国のインテリジェンス・コミュニティ
図4のように、各省庁の下にそれぞれの情報機関が設置されている。最近、保安部(MI5)の中に合同テロ情報分析センター(JTAC)が設置されたが、このJTACは、2007年のロンドン・テロ事件を契機に設置され、各省庁からテロに関わる情報を集約して分析・管理している。
各情報機関から上がってきた情報は、内閣府の中にある合同情報委員会(JIC)が最終的に情報を集約して、官房長官を経て首相に上げるしくみである。英国のインテリジェンス・コミュニティでは、このJICが要となって情報を分析・統括し、国家安全保障会議(NSC、2010年創設)が戦略を立案する。両者は互いに協力し合い、情報のペーパーと戦略・政策のペーパーを最終的に合作して首相に上げ、首相はそれらをみて最終的な政策決断を下すことになる。このように英国は、非常にシステマティックに情報を運用している。
 次に、英国のインテリジェンスの特徴をいくつか挙げてみる。
次に、英国のインテリジェンスの特徴をいくつか挙げてみる。
(1)MI6(秘密情報部/外務連邦省)とその特徴
正式名称はSIS(Secret Intelligence Service)だが、MI6の名前で広く知られている。MI6は、第一次世界大戦のころ、その存在を隠し国防省の一組織のようにふるまうために、たまたま陸軍省の情報部第6課の部屋が空いていたことから、そのような名前がつけられたという。当時、陸軍情報部には第1課から第14課まであったが、たまたま第5課と第6課が空いていて、第5課に防諜組織を、第6課に対外情報組織を入れ、あたかも陸軍省内の組織であるかのように体裁を整えたのだった。
ただしこの組織は、1994年までは根拠法がなく、「存在しない」組織だったので、世の中にはさまざまな噂が広まったこともあった。
①エリート主義
MI6はもともとエリート主義の特徴をもつ。英国のエリートは工学や医学等の実学を学ばずに、哲学・文学・歴史学といった人文科学を専攻するという伝統があって、MI6は従来からオックスブリッジの人文科学専攻者を多く採用してきた。そのため上流階級出身者が多く、組織の同質化が進んだ。
それではMI6に入って何を訓練するかといえば、社交術である。MI6要員は、世界各国に派遣されると各国にある大使館のパーティなどに出て現地のエリートとの交わりをしながら、情報を収集するのである。そのために彼らと会話ができる教養や社交術・コミュニケーション力を訓練する。
ところが2003年のイラク戦争で大量破壊兵器の存在に関する情報収集での失敗を契機に、人材の多様性を求める声が出て改革が進められた。例えば、要員採用においてMI6に関係する教授の紹介などが主流であったこと、イラク戦争での失敗経験では生物化学兵器等の知識に精通した要員がいなかったことなどが指摘されて、2005年から公募による募集に踏み切った。そのときの募集条件は、父母どちらかが英国人であること、21歳以上で過去10年間に5年以上英国に住んでいた英国民であること、初任給は440万円などであった。
②殺しのライセンス(License to Kill)
よく「MI6の要員は殺しのライセンスを持っているのか」と言われる。それに関して、最近までMI6の長官を務めていたジョン・サワーズ氏は、次のように語った。
「私たちに殺しのライセンスはなし、欲しくもない。MI6の任務は指導者に情報を提供することで、軍事工作はしない。それでも私は大ファンだがね。ダニエル・クレイグ(⇒現在の007映画の主人公を務める俳優)は最高だ」。
③別称
MI6自体も正式名称ではないが、テムズ川のほとりにあるMI6の本部の呼び方もさまざまだ。主なものを上げると、「サーカス」、「Vauxhall Cross」(テムズ川にかかる橋の名前から)、「河向こうの友人」(テムズ川の反対側にある官庁街からMI6を見た言い方)、「レゴランド」(MI6の建物がレゴのような外観をもつ)などだ。
2000年にIRAのロケットランチャーによってMI6本部が攻撃を受けたことがあったが、防弾ガラスと強化コンクリートによって損害は軽微だった。
④暗殺事件
ロンドンは、ロシアやイスラエルの対外情報機関の活動舞台になっており、それと関連した事件も発生している。いくつか事例を挙げると、
・リドビネンコ暗殺事件(ロシア、2006年11月)
・セルゲイ・スクリパル襲撃事件(ロシア、2018年3月)
など、ロシアがらみの事件も多い。
情報提供者の命の保障については、MI6はしっかりやっている。他国の情報機関も同様のところが多く、米国のCIAは情報提供者の命が危険にさらされた場合は、米国籍を与えて亡命させている。しかし日本はそのような措置をしておらず、それが弱点の一つになっている。
(2)合同情報委員会(JIC)
JICは1936年に参謀本部下に設置され、56年に内閣府に移行された。JICは政府内の情報の集約と分析を行う少数精鋭の組織だ。
主な任務は、
①政府内の各情報局の取りまとめ。
②政府高官や軍司令官の情報ニーズの把握。
③情報評価書の作成。
組織は、議長(次官級)と分析官40名程度で構成され、分析官は数週間に1本のペースで評価書を作成する。分析室(JIO)は、①大量破壊兵器・組織犯罪・南米・テロリズム室、②アジア・旧ソ連邦諸国室、③アフリカ・バルカン・トランスナショナル室、④中東・北アフリカ室から成る。また議長は首相やNSCに対して情報報告の義務を負う。
JICの情報評価書のサンプルとして、2013年8月29日にJIC議長から首相に提出されたものを紹介する(図6)。通常、JICの情報評価書は秘密扱いなので公表されないが、当時、シリア空爆を決断する際に、議会からのその根拠開示要求に答えて政府が示したものである。非常に簡潔な文書で、せいぜいA4、1枚程度のものだ。分析官はこうした評価書を作成することに誇りを持っている。
(3)米国との特別な関係(UKUSA)
米国と英国の情報機関(合衆国陸海軍通信諜報局=STANCIBとロンドン信号諜報局=LSIB)は、世界中に張り巡らせたシギント(注:主として傍受を利用した諜報活動)の設備や盗聴情報を、相互利用・共同利用するために、1946年3月5日にUKUSA協定(United Kingdom–United States of America Agreement)を締結した。これは英米の特別な関係を象徴するもので、J.ベイリス教授は、「英米両国の軍事協力の中核的要素」と述べている。その後、1948年にカナダ、56年にオーストラリアとニュージーランドがUKUSAに参加し、これらの5カ国を指して「5 Eyes」とも呼ばれる。
協定の主な内容は、次の通り。
①通信傍受情報
②通信傍受情報の定義、対象国は米英・英連邦を除く外国
③暗号解読技術の共有
④第三国への情報提供
⑤英連邦との将来的な協力
⑥当面の英連邦との協力
⑦配布と秘密保持
⑧商業分野への適用
冷戦時代は、主としてソ連を中心とする東側諸国を取り囲むように傍受活動を行い、現在でも、米国のNSAが北太平洋圏を、英国のGCHQがインド洋から中央アジア・アフリカ圏をそれぞれ管轄している。
(4)英米情報機関の光と影
2003年のイラク戦争の開戦をめぐっては、英米の情報活動が問題となった。当時、国連安保理においてイラクへの攻撃を推し進める英米と、それに反対するフランス等の対立があり、10カ国の非常任理事国が英米を支持するかどうか微妙な情勢だった。そこで米国のNSAのフランク・ゴザ主任から英国のGCHQに「国連の非常任理事国のすべての通信の傍受をお願いしたい。(中略)われわれの方は現在、国連安保理に出席していない国々の傍受活動にかかりっきりである」とのEメールを送った。
それを知って憤慨した英国GCHQの中国語専門員(女性、28歳)キャスリン・ガンは、知り合いの新聞記者に漏洩。同年3月2日に『オブザーバー』紙が同メールの全文を掲載して、ガンは逮捕されたが無罪となった。
さらにクレア・ショート英国際開発担当相は、「定期的にアナン事務総長の電話記録を読んでいた」と堂々と述べた。このように英米両国の情報機関が国連本部の電話やメールを盗聴していたことが、暴露されたのだった。
また2013年のスノーデン事件は大きな衝撃を与えた。米国ノースカロライナ出身のエドワード・スノーデンは、CIAやNSAにも勤務した経験があり、そうした機密情報を新聞記者に漏洩して大問題になった。その中でも米国の情報機関がGoogleやMicrosoftなどの企業から情報を引き抜いていたことは大きな衝撃を与えた。
さらに英国の情報機関の事例としては、米国と欧州を結ぶ光ファイバーの海底ケーブルの情報大動脈は(テンポラ)、米国の東海岸から英国の最西端を通過して欧州につながっているが、そこで英国の情報機関は一日に21ペタバイトという膨大な情報を収集していたことが発覚した。スノーデンは「英国のGCHQはNSAよりひどい」と皮肉った。デヴィッド・オマンドGCHQ長官は「英国には頭があり、米国にはカネがある」と述べたが、以前に米国NSA はテンポラに1億ドルを拠出したこともあった。
それでは何が問題なのか。対峙するロシアや中国の情報を収集するのであれば、それなりに理解できなくもないが、(日韓独仏など)同盟国に対する情報活動が明らかになり、それに対しては疑念の声も出ている。世界各国の米大使館の屋上には通信傍受機器が備えられて情報収集しているといわれている。最近の話題では、メルケル首相の携帯電話の通信傍受活動が明らかになり、外交問題にもなった。
 米国にとって5 Eyesと言われる国々は情報上の同盟国であり、「情報を共有し互いに監視はしない国」であるが、同盟国であっても情報収集の対象となる国がある(独仏日韓など)。NATO諸国の中で英米に一番近い国はドイツといわれており、ドイツは米国からさまざまな通信機器を供与されて通信傍受活動をしている。それでもドイツは通信傍受の対象国になっている。
米国にとって5 Eyesと言われる国々は情報上の同盟国であり、「情報を共有し互いに監視はしない国」であるが、同盟国であっても情報収集の対象となる国がある(独仏日韓など)。NATO諸国の中で英米に一番近い国はドイツといわれており、ドイツは米国からさまざまな通信機器を供与されて通信傍受活動をしている。それでもドイツは通信傍受の対象国になっている。
(5)スノーデン事件の余波
スノーデン事件の後、これに関連して英国ではMI5、MI6、GCHQの各長官が議会で証言し、情報活動の重要性を訴えた。実は、GCHQの長官が公に顔を明らかにするのはこれが初めてであった。それまでテレビ等のインタビューを受けても、必ず顔にモザイクが施されていた。
一般世論は、長官たちの訴えに耳を傾け、GCHQの活動の一定の理解を示した。その背景には、英国民には歴史的に007のよいイメージがあって、情報機関は信頼の置ける組織という通念がある。多少脱法的なことがあったとしても、国を守るためにはやむを得ないという理解なのだろう。
それでも根拠法等が必要だという世論に押されて、2015年11月にメイ内相(当時)が英国議会情報保安委員会に、調査権限法(Investigatory Power Bill)を提出した。これによって英国でも、無制限な通信データやネットに対する情報収集は、第三者からの許可を得てからやらなければならなくなった。それ以前は、調査権限規定法(RIPA、2000年)によっていたが、非常に内容が曖昧で法律の体をなしておらず、MI6やGCHQはやりたい放題だった。そこでRIPAに代わり、時代に即した調査権限を情報機関と捜査機関に与え、監視体制を強化することになったのである。
主な狙いとしては、①情報機関や捜査機関の通信データ収集のルールの明確化、②これらの機関に対する監視体制の強化、③時代にあったデジタル・データの収集、保存を挙げているが、なかでも②に重点が置かれている。
4.日本のインテリジェンス・コミュニティと今後の課題
日本では、公安調査庁、防衛省自衛隊、警察庁、外務省に加えて、最近は拡大コミュニティとして、入国管理局、税関、金融庁、経済産業省、海上保安庁からも、事案に応じて情報提供を行うことになった(図7)。それらの情報は、内閣情報調査室に集められ、内閣情報官を通じて首相に報告されるしくみ(首相ブリーフィング)となっている。安倍政権になってから、それまで週に1回の首相ブリーフィングが、週2回に増えた。

 現在の体制は、内閣危機管理監(事態対処・危機管理)、国家安全保障局長(NSC)、内閣情報調査官(内閣情報調査室)の三本柱で構成されている。ただし内閣情報調査官は他の二つに比べると1ランク下の位置づけとなっている(図7)。
現在の体制は、内閣危機管理監(事態対処・危機管理)、国家安全保障局長(NSC)、内閣情報調査官(内閣情報調査室)の三本柱で構成されている。ただし内閣情報調査官は他の二つに比べると1ランク下の位置づけとなっている(図7)。
(1)外務省国際情報収集ユニット
2013年1月のアルジェリア人質事件、2015年1月のシリア邦人人質事件、同年3月チュニジアの銃撃テロ事件、同年11月のパリ同時多発テロ等を受けて政府は、2015年12月18日、外務省総合外交政策局内にテロ情報を扱うユニットを設置した。
ユニット長は、警察および地域別(東南アジア・南アジア・中東・アフリカ)を担当する4審議官のうち、2名が警察、2名が外務省で、情報収集担当官は外務の語学専門員が担当する。職員は内閣官房国際テロ情報集約室員を併任。
20名程度とされる情報収集担当官は、大使館員の身分で在外公館に出向し、赴任国政府や各国の情報機関とテロ情報を交換する。ただしグレーゾーンの活動は行わない。2016年9月に人員が40人から80人に増員された。
この組織の主たる目的は、テロに関する国内外の情報を収集することである。ただしコンスタントな収集はせず、各国のテロ対策組織との情報交換が基本となっている。危険を冒してまで情報を収集することまではやっていない。
組織自体は、外務省内にあるが指揮命令系統は内閣官房から来る。組織上のトップは外相だが、運用上のトップは内閣官房長官で、内閣官房の国際テロ情報集約室(室長:内閣官房副長官)が実質的な指令を出している。つまり内閣情報調査室が運用を司っている。そもそもこのユニット自体、警察と外務省のハイブリッドの組織で、インフラ(大使館、外交電報など)は外務省が提供するが、実際の情報収集は警察が行うという体制である。
(2)日本のインテリジェンスの課題
情報コミュニティの規模は他国と比べて小さく(⇒要員は推定5000人、予算は1500億円規模)、実戦経験に乏しく、対外情報機関もないなど、課題は多いとはいえ、近年次のように改善されてた点も少なくない。
①合同情報会議の設置、合同情報研修の開始
⇒各省庁間での情報の共有が進んでいる。
②特定秘密保護法と適性評価制度の導入
⇒防諜体制、機密保護制度の不備の改善。
③国家安全保障会議(NSC)の設置
⇒官邸からの情報要求が出るなど、インテリジェンスへの関心が高まった。
(3)インテリジェンス強化に向けた喫緊の取り組み
世界を見回しても珍しいほど対外情報機関がないという日本の現状に対して、現在自民党などが「日本版CIA構想」を提言しているほか、国家安全保障戦略(2013年12月)では「人的情報、公開情報、電波情報、画像情報等、多様な情報源に対する情報収集能力を抜本的に強化」することが謳われ、衆議院の情報監視審査会設置に関する国会法の改正でも(2014年6月)、情報収集のための行政機関の設置について言及があった。
しかし乗り越えるべき課題も山積しており、その実現に向けては「道遠し」という印象だ。その最大の障害は、日本の公務員は海外で脱法行為をすることが可能か、情報収集活動をしていて逮捕された場合の対処、組織をどの省庁の下におくかなどについて、法律的にどう解決するかという問題がある。
例えば、他の国では、自国の情報要員(公務員)がスパイ容疑で逮捕された場合、自国にいる相手国のスパイ(情報要員)を(スパイ容疑でもって)逮捕して、情報要員同士の相互交換をする。しかし日本にはスパイ防止法がないためにそれができない。
このような時間のかかる難題を解決することよりも、先にやるべきこと、やれることはたくさんある。例えば、次のような内容だ。
①オシント(OSINT=open source intelligence)の充実。
まずはオシント、すなわち一般に公開されている膨大な情報の中から、必要な情報を収集・分析する活動の強化である。
日本には「ラヂオプレス」という元外務省所管の組織があるが、そこでは海外のラジオやテレビ放送を聴取・視聴し、その情報をもとに翻訳・作成した記事を、報道機関や中央官庁に配信している。北朝鮮の公式情報の多くもこのラヂオプレスからのものだ。ところが最近、予算不足のために新しいアンテナを設置できずに放送・電波の受信に難儀しているという。英国のBBCモニタリング・サービスが70言語、145カ国をカバーしているのと比べると、ラヂオプレスはわずかに20数カ国しか扱っていない。 こうした公開情報の分析は日本が得意とする分野でもあるので、もっと強化する必要がある。
②聞き取り調査
例えば、日本に北朝鮮から帰ってきた拉致被害者に対する聞き取り調査も十分にやっていない。これは危険を冒さずにできる情報収集の方法であるが、それも十分とは言えない現状だ。
③ドローンによる現地情報収集
④低い解像度のマイクロ衛星の可能性の検討
⑤国際的な情報協力ネットワークへの参加
5 Eyes、欧州・東南アジア諸国との情報共有などである。
⑥情報の質向上のための努力
大学や民間シンクタンクとの連携協力、ビッグデータの活用、インテリジェンス・リテラシーの向上などである。
いずれにせよ、対外情報組織をつくれば情報収集ができインテリジェンスが強化されるという安易な考えは捨てて、まずはできるところから地道にいろいろなことを積み上げ、戦略を立てていくことが重要だ。いろいろ手を尽くした上で、対外情報組織を作ることを考えるのが順当な進め方ではないかと思う。
(本稿は、2018年6月13日に開催した政策研究会における発題内容を整理してまとめたものである。)