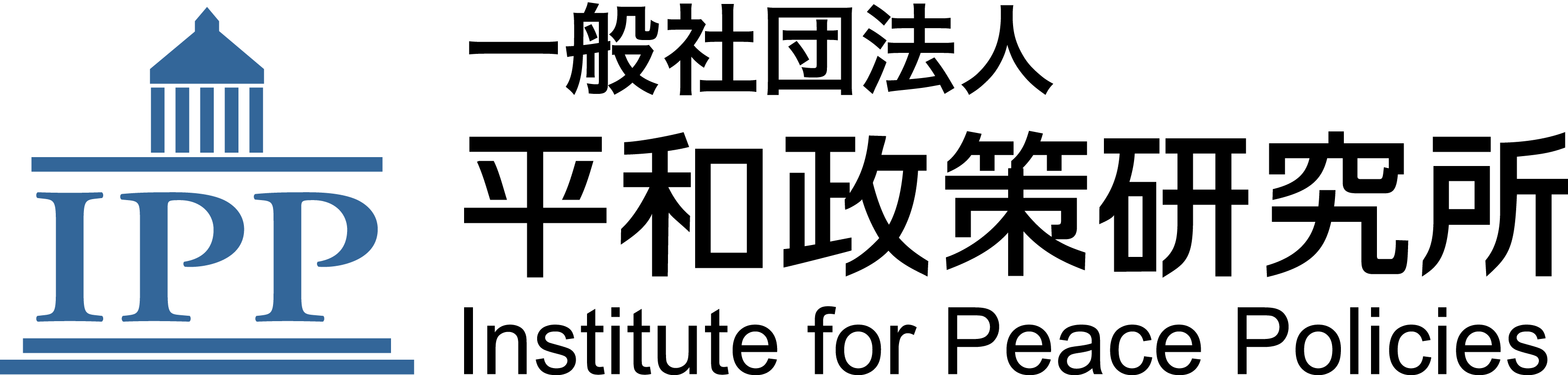コロナ下での分散登校を契機とする変化
令和の学校教育制度改革として、一つは2021(令和3)年度 小学校第2学年から学年進行で実施される35人学級編制が挙げられる。
わが国では1953年以来、公立小中学校の学級編制標準は、50人(1953~63年)、45人(1969~78年)、40人(1980年~)、小1のみ35人(2011年~)へと改正されたが、今回学級定数引き下げ論が急浮上したのは、新型コロナウイルスの感染拡大によるものである。2020年3月からの一斉休校化、5月中旬に学校が再開してからも分散登校を行うなど、ソーシャル・ディスタンスをとる必要があった。また「GIGAスクール構想」が2020年度中に前倒しして実施されるなか、一人一台端末の効果的活用を進める観点からも、定数引き下げの必要性が高まったのである。
さらに児童生徒の心身のケアと新学級に向けた生活リズムを徐々に整えることを意図した分散登校の経験では、きめ細かな指導の可能性、児童生徒の発言する機会の増加、教師の心のゆとりをもたらしたとされている。
30人以下学級の効果
世界で小規模学級の効果に関する調査研究は1900年まで遡るが、代表的な先行研究としてグラス(Grass, Gene V.)とスミス(Smith, Mary L.)のメタ分析がある。グラス・スミス曲線と呼称される学級規模と学力の関係図によると、1学級30人を分岐点として学力のみでなく、子どもの情緒の安定度、教師の満足度も徐々に上昇したのである。また経済的に困難な学区の児童やマイノリティ児童に対する小規模学級の実現は児童の学力を高めることが裏付けられ、質(Quality)、平等(Equality)、均等(Equity)に向けた政策として評価できる。
日本の全国学力・学習状況調査における5年間の学校追跡調査を使ったパネルデータを用いた学級規模の効果検証でも、特に学級規模の効果は、小6の社会階層が相対的に低い児童が多くいる学校(学級)に対して効果的であった。中3時点の学力格差が大きくなる前、なるべく早期に学級規模を縮小することが望ましいと推察される。
35人以下(できれば30人以下)学級をベースとして、適切な少人数指導、後述する小学校教科担任制、授業持ち時間数を含む教員の働き方改革、外部人材の活用といった多方面からの政策アプローチが期待されてくる。
義務教育9年間の学びの系統性
もう一つは、中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(2021年1月26日)で提示され、2022(令和4)年度から実現する運びとなった小学校高学年教科担任制である。
対象教科として「外国語」、「理科」、「算数」を例示しているが、これまでのTT(ティーム・ティーチング)による協力教授組織や一部の教科(例えば、音楽科、家庭科)の学科担任制の相違として考えられるのは、“義務教育9年間を見通した指導体制”の構築である。学習内容においては系統的な指導により中学校への円滑な接続を図り、中学校の教員が小学校で教えるなど、小・中学校の連携が促進されることは確かである。
今日的小学校高学年教科担任制導入の背景としては、概ね以下の点を列挙できる。
- 教育内容や学習活動の量的・質的充実が図られる中、小学校高学年での専門的指導を充実させ、児童の学習内容の理解度・定着度の向上と学びの高度化を図る必要。
- 思春期が早期化し、子どもたちの態様が多面化している中、学級担任制と一部教科担任制を併用して様々な教員が多面的に子どもの指導に当たり、心の充実に資する必要。
- 教師の持ちコマ数の軽減や授業準備の効率化により、学級の教育活動の充実や教師の負担軽減に資する必要。
- 小・中学校の連携による小学校から中学校への円滑な接続(中1ギャップの解消等)を図る必要、など。
先導ケースと教員配置支援策
先導的ケースは、2016(平成28)年度から義務教育学校、小中一貫型小学校・中学校が制度化され、全国的に展開された、さまざまな小中一貫教育に見られる。例えば、品川区立品川学園では、前期課程の第5学年及び第6学年において学級担任7人と副担任2人、講師2人、後期課程の区固有教員(品川区で採用)1人の計12人で全教科を教科担任制とした時間割編成が特徴的である。
また横浜市のように、5・6学年それぞれ教科分担制を伴うチーム学年経営の仕組みが2018年度から推進されている。タイプとして、(ア)教科の授業時数を考えての交換授業、(イ)特別活動、総合的な学習の時間、道徳の授業は学級担任。それ以外の教科は教科分担制(学級担任、非常勤講師)を伴ったチーム学年経営がある。
今後小学校高学年教科担任制を導入するに当たり、肝要な基本的課題は、次の点である。
各学校の規模(学級数)、直面する課題といった学校の実態に応じた対応である。あくまでも学級担任制を基盤としつつ、実情に応じた実施学年・教科を考える必要がある。その際、学級担任の交換授業のほか、担任外教員(専科、担任を持たない学年主任、中学校からの乗り入れ指導等)による指導を加えて、指導教科数を減らしたり、空き時間を増やしたりして教材研究や教材作成の時間などを確保することが不可欠となる。そのためにも国や自治体による“教員配置支援策”が一層望まれてくる。
<参考文献>
八尾坂修『明日をひらく30人学級』(かもがわブックレット23)かもがわ出版、1999年