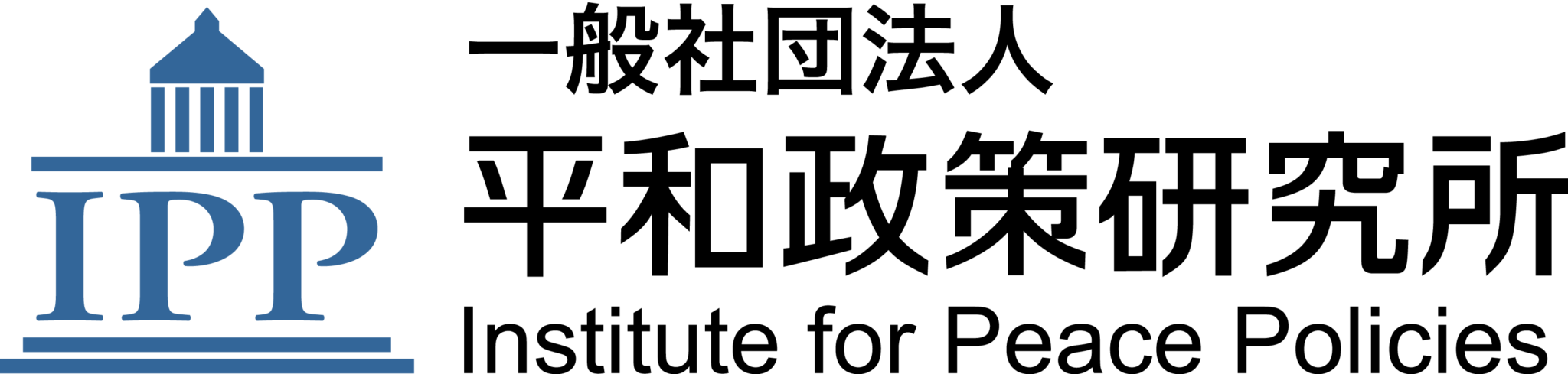文明の転換期における日本の課題
2.日本が直面している国内の最重要課題
①少子高齢化と急激な人口減少
中長期的に見て、日本国内における最大の危機は、急速に進む少子高齢化と人口減少である。少子高齢化による人口減少と人口構造の変容は、現在の社会機能の維持を困難にする。
第一に、経済に悪影響を及ぼす。人口減少が市場を縮小させるとともに、最も消費活動が盛んな現役世代が減少することで、個人消費が落ち込むことが予想される。同時に、生産年齢人口の減少は、労働力不足と労働生産性の低下をもたらし、国民一人当たりの実質GDPの伸びを鈍化させる懸念がある。その結果、経済力・国力が低下し、国際競争や安全保障面へ負の影響を及ぼす。
第二に、社会保障制度について、財政面と人材確保面の双方の観点から、その持続可能性が困難になりつつある。社会保障給付費は年々増加し、今やその総額は国の一般会計予算の規模に匹敵する。社会保障の財源は、主に公費(税金)と保険料(被保険者本人負担と事業主負担)であるが、その負担は巨額なものになっている。公費については税金だけでは賄いきれず国債収入にも依存している。国の負担分の4割強は国債で賄われているため(2024年度予算ベース)、財政赤字が拡大する。保険料負担については、被保険者本人ばかりでなく事業主にも重い負担になっている。また、年金、医療、介護の負担の多くは現役世代が負っており、人口減少の中で現役世代の負担が限界に達する恐れがある。
さらに、医療サービスや介護サービスは、大勢の医療・看護職や介護職の人材に支えられており、今後も高齢者人口の増加によるサービスの需要増加から現在以上の労働者人口が必要とされる。しかし、生産年齢人口の減少等から人材確保の困難が予想され、このままでは良質かつ十分なサービスを提供できなくなる恐れがある。このため、産業界からはさらなる外国人労働力の導入拡大を求める声も上がっている。
第三に、労働や社会活動の担い手が減り、地域社会が立ち行かなくなる。少子化が続いて現役世代が減少すれば、人々のネットワークも縮小し、相互扶助の維持も困難になる。また、自治体職員の減少による公的サービスの縮小に加え、需要を確保できない民間事業者の撤退も起こるようになる。現在都市部では元気な高齢者が強力な支えとなっているが、2025年には団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となる。後期高齢者の割合が高まれば、高齢者が社会の主たる支え手となることは難しくなっていく。
第四に、少子高齢化は子供の養育環境に悪影響を与える。様々な年齢の子供同士の触れ合いが減り、子供たちが共通の規範や文化を習得したり、他者とは異なる自分の個性に気づいたりする機会が減る(集団社会化理論)。そうした多様な子供同士の関係や他所の家庭の様子に触れる機会の減少が、将来自分が親になったときの養育態度に影響し、少子化により養育環境が世代を越えて悪化する可能性がある。加えて、子育て家庭が減少することにより、地域の人々が子育てに触れる機会が減る。それにより、子育てへの共感や配慮が難しくなり、子育て家庭が孤立しやすくなる可能性もある。
日本では長年少子化対策が取り組まれてきたが、出生数・出生率は回復していない。その理由は、少子化の原因と少子化対策のミスマッチにある。
日本における少子化は、主に「未婚化」「晩婚化」が原因となって進んできた。日本は婚外子が少ないことから、未婚化の進行はそのまま少子化に結びつく。また男女とも、年齢が高くなるほど子供をつくる力と育てる体力は弱まるため、晩婚化も少子化につながる。
未婚化・晩婚化の進行には、結婚意欲はあるが結婚できない人の増加と、結婚の意欲自体が低い、またはない人の増加の2つの経路がある。
意欲があるのに結婚できない人が増加している主な理由の一つは、1990年代以降、若年男性の雇用状況が悪化し、賃金の低い正規雇用者や非正規雇用が急増したことである。また、職縁を中心とした結婚相手と出会う機会の減少も挙げられる。そもそも結婚意欲が低い・ない人も増加しているが、その背景には、個人中心のライフスタイルの浸透がある。仕事において高い収入や地位を得て豊かに暮らすこと、およびそのための勉強・能力開発、加えて独身生活を謳歌するために、制約の多い結婚生活や子育てを先送りにしたり、忌避したりする可能性が指摘されている(松田2021)。
以上のような原因に対して、従来の少子化対策の中心は、保育の拡大政策、および仕事と子育ての「両立支援」であった。これらの施策は、正規雇用の女性の就業を継続しやすくするため、既婚で夫婦ともに正規雇用で働く世帯に対しては有益であったが、既婚の正規雇用者以外にとっての恩恵は多くない。
婚姻数にアプローチする政策には、自治体の結婚支援策を支援する地域少子化対策重点推進交付金があるが、効果を上げるためには予算規模が小さく(御船20203)、民間のマッチングサービスで相対的に効果を上げているものも考慮しつつ、どのような事業を支援すべきか検討が必要である。また、2023年には「こども未来戦略」が取りまとめられ、雇用対策として個人のリ・スキリング支援を打ち出しているが、その他の施策内容は児童手当や出産費用支援、妊娠期からの伴走型支援、男性育休の取得促進など、子育て支援の色彩が強い。未婚化・晩婚化にアプローチする取り組みには、一層充実が求められる。
出生数・出生率を回復させるための政策としては、第一に結婚前の若者の雇用状況の改善、結婚を希望する人への経済的支援、子供の教育費の支援などが有効と考えられる。第二に、結婚を希望しない人が増えていることから、若者が結婚したいと思えるような取り組みも重要となる。若者の結婚に対するイメージには、若者が育った家庭環境が影響する。家族・夫婦関係に関する問題解決の支援や、結婚・妊娠・出産や家族関係の特徴などに関する基礎知識を学ぶ機会を提供することも重要となる。そうした支援を形成するためには、包括的な「家族政策」(family policy)が必要になる。
今後仮に有効な対策を実施しても、当面の間、少子高齢化と人口減少が進むことは避けられない。2056年には総人口が一億人を割り、そのうち3750万人が高齢者になると予測されている(国立社会保障・人口問題研究所2023)。少子化・人口減少の緩和と共に、少子化・人口減少が進んだ社会に対応するための社会システムの整備、地域共生社会の実現に資する「移民政策」への取り組みが必要となる。
②失われた30年と国家的活力の喪失
日本は戦後の高度経済成長期を経て飛躍的な経済発展を遂げ、1960年代終わりには米国に次ぐ世界第二位の経済大国となった。1980年代末に絶頂期を迎え、世界の企業の時価総額ランキングで日本企業が上位20社のうち13社を占めるまでに至った。欧米をはじめ世界各国が日本企業の経営手法に注目し、日本は世界経済の中心になるとさえみなされていた。
しかし1990年代以降はバブル経済の崩壊と共に低成長時代が永く続いている。過去30年間で名目GDPは米国が3.5倍、ドイツが2.3倍になったのに対して、日本は1.5倍にとどまった。経済規模は2010年に中国に抜かれて3位に後退し、2023年はドイツに抜かれて4位となった。スイスの民間研究機関(IMD)による国際競争力ランキングでも、1989年から4年連続で首位を保っていたが、1997年には17位に急落した。その後は20位台半ばで推移し、2019年以降は5年連続で30位台となっている。平成の時代を通じて、日本は「失われた20年」、さらには「失われた30年」と呼ばれる長期の低迷に陥った。
このような長期停滞の原因は、1990年代の不良債権処理の遅れや、2000年以降のデフレに効果的に対応できなかったこと、さらに冷戦の終結や中国の台頭、IT革命などによる世界経済の急激な変化の潮流を捉えきれず、製造業を中心とした産業構造の転換に遅れをとったことなどにある。
同時に、この時代は長く短命政権が続き、政治が安定しなかった。阪神淡路大震災や東日本大震災などの大型自然災害も頻発したが、政治が強いリーダーシップを発揮して危機に抜本的対処をすることもできなかった。日本にとっての深刻な問題は、各分野で必要とされる指導者がしっかりと育成されておらず、人材の質が大幅に劣化していることである。高い能力を持つ人が十分にその能力を発揮できるように教育制度をはじめとする諸制度が整備されなければ、国際競争力は低下するほかない。少子高齢化という量的な変化以上に重要な日本の課題は、質的側面である人材の育成である。
長期にわたる停滞の結果、社会システムに生じた様々なひずみが是正されずに放置されたままになっている。雇用や教育の格差拡大、少子高齢化による社会保障費用の増大などが重くのしかかり、多くの若者は希望ある将来を思い描くことが困難になっている。国際社会が不安定化していることもあり、国民とりわけ若者のあいだには将来を見通すことのできない漠然とした不安が蔓延している。「失われた30年」は、若者の希望が失われた30年だったとも言える。
このような長期停滞の克服には、経済においては海外からの直接投資を拡大する環境整備が重要である。中国やインドの目覚ましい経済発展は、いずれも外国からの投資に門戸を開放したことが大きな要因である。日本の経済はそれらと比べると閉鎖的と言わざるを得ない。日本は資本不足の国ではなく、むしろ資本が豊富な国だが、国内ではなく海外に投資がなされ、かつ海外からの投資は呼び込めないできた。これでは経済が成長しないのは当然である。経済のグローバル化が進む中で、日本から海外に投資するだけでなく、海外からの投資を積極的に受け入れる政策が不可欠である。近年、地政学リスクを背景に、国内で海外の半導体企業による大型投資が相次いでいることは、ひとつの前向きな材料といえよう。ただし、政府の莫大な補助金頼みの誘致であり、この動きをいかに本格的な産業発展につなげていけるかが今後の大きな課題である。
さらに、過去の制度や既得権に捕らわれない大胆な発想の転換と統治機構を含む社会システムの抜本的な変革が必要となろう。未来人材育成のための教育改革や最先端科学技術開発の振興、次世代に向けた新たな産業の創出、若い世代への投資などによって、再び国家の活力を取り戻してゆかなければならない。
③孤独・孤立問題と取り残される社会的弱者
かつて日本では、地縁・血縁ネットワークが相互扶助機能を担ってきた。地縁は高度経済成長期の人口移動により縮小したが、その分終身雇用を基本とする会社縁が人々を包摂してきた。しかし、1990年代以降、家族と安定的な会社に揺らぎが生じ、孤独・孤立が世の中の問題として取り上げられるようになった。
家族については、1990年代以降、結婚しない人の数が急速に増えた。1985年以前、50歳時未婚率は男女ともに5%を切っていたが、2020年の国勢調査を基にした50歳時未婚率は男性が28.3%、女性が17.8%となっている(国立社会保障・人口問題研究所 2022a)。同時に単身世帯が増え、2010年以降は最も多い世帯形態となっている。社会構造の変化や社会福祉制度の発展とともに、家族関係の維持・生成と生活の必要性との結びつきが弱まり、地縁・血縁に頼らなくてもよい社会になったことがその一因である。
また、バブル崩壊に端を発した長期不況と経済停滞により、日本の企業体質も変化した。1990年代後半からは派遣労働が緩和され、正規雇用者が減少する中、非正規雇用者は増加し続け、会社に取り込まれない人々が増えた。その結果、家族や会社を通じて繋がりを自動的に見出すことが難しくなり、自らが人間関係を主体的に築いて維持しなければならない時代となった。地縁や会社縁が薄れた結果、血縁(家族関係・家庭環境)が直接的に個人の孤独・孤立に関わるようになったといえる。特に、家族との関係が希薄で社会福祉も届きにくい人々は、孤独・孤立に直面するリスクが高い。ライフスタイルとしての孤立は尊重すべきという意見もあるが、孤独・孤立から精神疾患や貧困、孤独死、自殺などに至らないようにする予防策は重要である。
特に、失業者、高齢者、障がい者、被災者、難民、低所得の人々等、深刻な状況にある人ほど、行政からの情報も届かず、地縁・血縁が薄れた社会の中で困窮しているケースが少なくない。複合的な要因で社会的弱者となっている人々が、孤独・孤立によって問題を抱えることがないように、あらゆる人々を包摂していく社会政策が必要である。
孤独・孤立による問題を社会で広く予防するためには、第一に多くの人を包摂しうる地域における居場所の提供(新たなコミュニティ政策等)が重要となる。あわせて、孤独・孤立に直接的に関わっている家族関係・家庭環境をサポートする包括的家族政策等の取り組みも重要である。和合・親密・友愛などを特徴とするゲマインシャフト(地縁・血縁などによる自然発生的集団)的な共同体を、現代にあった形の社会関係資本(信頼関係や互酬性の規範、ネットワーク)として再構築することが求められていると言える。各地域の特性や実情にあったこうした地域福祉やコミュニティ政策を実現するためには、分権・分散・地域自立型の社会への転換が必要であろう。
④家族機能低下による家族病理の深刻化
近年、子供の養育環境は悪化し続けしており、児童虐待は1990年の統計開始以来、増加の一途をたどっている。
児童虐待は子供の心身を傷つけるだけでなく、幸福を追求する力そのものに悪影響を与える。心理面からみて、幼少期の中心的発達課題は、親をはじめとする特定の養育者との間に安定したアタッチメント(愛着)関係を形成することである。アタッチメントとは、子供が不安や恐怖を感じたとき、親にくっついて安心・安全を確保し、感情を立て直そうとする性向である。親との間に安定したアタッチメントを繰り返し経験できた子供は、他者への基本的信頼感と肯定的自己イメージを獲得しやすい。逆に、親から虐待を受けた子供は自己や他者への肯定的イメージを獲得し難くなる。
アタッチメントを土台とした自己と他者への肯定的イメージの獲得は、子供の社会的発達にも影響する。子供はある程度成長すると「しつけ」を受けるが、「しつけ」には心身の健全な発達のためにある程度の制限をともなう。子供の中に根本的に親から受容されているという感覚(甘えることができているという感覚)が無ければ、「しつけ」は単なる制限や禁止となりかねない。受容感なく制限・禁止を受け続けると、怒りや悲しみなどの不快な感情(ネガティブな感情)を安全に抱える力が育たず、成長後に攻撃衝動を制御できなくなったり、心身の不調に繋がったりしやすい。小中学校を中心としたいじめや不登校増加にはこうした背景もあると考えられる。
また、幼少期にネガティブな感情を受容してもらえなかった経験は、自身が子育てをするときにも影響しうる。自分が抑えてきた感情を子供が奔放に表現することに不安や怒りを感じ、子供のネガティブな感情に上手く対処できないことがある。育児する親一人が孤立した状態でこうした課題を抱えている場合、虐待など「マルトリートメント」(大人から子供に対する「不適切」なかかわり)に発展する可能性がある。
近年、家族の養育機能を支える仕組みが弱体化してきたことにより、「マルトリートメント」が増加している。具体的には、高度経済成長を機に、拡大家族から核家族へと家族規模が縮小し、地域共同体が弱体化することで相互扶助による福祉機能が縮小したことが影響している。
家族規模の縮小は、集団としての家族の機能を低下させる。それは、世帯内の大人が減少することによって、成員一人ひとりにかかる役割負担が増加するからである。例えば、拡大家族においては、父母世代が働いていても祖父母世代が家事・育児を分担することができる。しかし、核家族では祖父母の手を日常的に借りることはできず、父母世代が仕事と家事・育児の両方を引き受けることになる。さらに近年では、子育てと介護を同時に行うダブルケアや、子供・若者が家族の介護や世話を過度に行うヤングケアラーの問題も注目されている。
成員一人ひとりの役割負担が過大になれば家族のニーズ充足にほころびが生じ、家族機能が低下しうる。実際、子供がいる現役世帯(世帯主が18歳以上65歳未満)で大人が一人の家庭(ひとり親家庭)における相対的貧困率は、2021年で44.5%(厚生労働省2023)である。貧困状態にある子供が増加している原因の一端は、多重役割負担を避けられないひとり親世帯の増加にあるといえる。
また、多重役割負担が増加すると、家族が共にする時空間が減少しやすくなる。多重役割に対応するために生活時間をずらしたり、生活ニーズの充足を外部、すなわち市場や社会に依拠したりするようになるからである。家族が共有する時空間の減少は、コミュニケーションの不足・不全や、家族成員の健康維持に負の影響がある。家族が食卓を共にしない個食(孤食)の増加はその一例であり、共食とは逆に精神的健康や健康的食生活と関連があることが示唆されている(例えば、小西2003; 會退・衛藤2015 )。
加えて、1990年代頃からは、経済状況の悪化と自己実現重視の考え方の広がりを背景にして夫婦共働きが増え、家族成員一人ひとりにかかる役割負担は増加している。
このように、家族規模の縮小により、多重役割負担の増加と家族が共有する時空間の減少が進行した。一方で、地域の交流は減り、相互信頼を形成する機会は減少している。その結果、家族が互いに配慮してケアし合ったり、地域から援助を受けたりする機会が減り、親や子育て家庭がストレスを抱えやすくなるとともに孤立しやすくなった。
こうした状況を改善するには、様々な家庭環境にある子供たちの幸福を追求する力や生きる力を育むとともに、親を取り巻く心理的・社会的課題を解決できる環境を整備する必要がある。その際、家族規模の縮小と地域共同体の弱体化、日本経済などの社会状況を考慮に入れて、家族機能の充実と子育て家庭支援のための「家族政策」を立案する必要がある。
⑤自然災害の頻発・激甚化 とインフラの老朽化
21世紀に入り、世界中で気象災害が頻発しており、自然災害による被害は確実に拡大している。地球温暖化による気候変動と地震活動の活発化によって災害は巨大化し、複雑化している。日本はその自然的条件から各種災害が発生しやすい特性があり、毎年のように水害・土砂災害、地震・津波などの自然災害が発生している。戦後に死者が1000名を超えた自然災害は9回(地震4回、風水害5回)を数える。
特に、2011年の東日本大震災では、想定外の地震による大津波で、災害関連死を入れて約2万2000名が犠牲となり、ストック被害額は16.9兆円(内閣府2011)に上った。また、1995年の阪神・淡路大震災では、高度経済成長に取り残された老朽木造密集地域が、災害に極めて脆いことが浮き彫りになった。
今後30年で南海トラフ地震の発生率は70〜80%、首都直下地震は70%程度とされる。いずれが起きても「国難災害」となり、日本という国家自体が衰退する。同時に、東京湾の高潮や、利根川あるいは荒川氾濫でも国難災害になり得ることが指摘されている。また、近年は豪雨災害によっても大きな被害がもたらされており、頻発・激甚化する災害への備えと対応が急務となっている。
現状では、国難災害への対策は順調とは言い難い。もし、南海トラフ地震が生じた場合、現在の災害救助法や災害対策基本法は有効に適応できず、被害者生活再建支援法も被害が大きすぎて適用できないと言われている。対策推進による減災目標(2014年からの10年間)として、「想定死者数を33.2万人から概ね8割、想定全壊棟数を約250万件から概ね5割減」(内閣府2014)が掲げられたが、2025年3月末に公表された新たな被害想定では、「想定される死者数は約26.4万人(約20%減少)、想定全壊棟数は約208.4万棟(約17%減少)」(内閣府2025)となっている。防災対策は進んでいるものの、2014年の減災目標達成には程遠い。
また首都直下地震が起きた場合、「都市の脆弱性」が問題となる。東京では超高層マンションが乱立しているが、水道や電気などのライフラインはマンション独立ではない。地震が起きてインフラが被災すれば、超高層マンション自体に被害がなくても、停電や断水によりマンションでの生活は不可能となる。東京都23区では、マンション住民が大挙して避難所に避難してくることを想定しなければならない。
インフラの老朽化も、災害拡大の一因となっている。2024年1月1日に発生した能登半島地震では、道路の陥没・崩落により孤立地域が続出したり、上下水道が大きな打撃を受けたことで大規模な水道被害が生じたりと、老朽化したインフラへの懸念が高まった。2025年1月には埼玉県で下水道の老朽化による大規模な道路陥没事故が発生し注目を集めた。国土交通省によれば、高度経済成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾などのインフラは、今後20年で建設後50年以上経過するものが急増する。既に補修が必要とされながらも行われていない橋やトンネル、下水道管が全国に多数あり、補修できない老朽化したインフラは今後も増えていくとみられる。日常生活における安全を守ることが最重要であるのはもちろんのこと、災害時には大きな被害をもたらしかねない。
近年では、財政支出を削減するために国においても地方自治体においても公共事業費は縮小されており、限られた財源の中で難しいかじ取りを行わなければならない。さらに、地域社会の高齢化やコミュニティの衰退、人口減少と東京への一極集中も、災害への耐性を弱めている。
今後の巨大災害に備えるには、防災施設整備などのハード対策、災害情報や避難体制、防災教育などのソフト対策を駆使し、自助・共助・公助にわたる総合的防災対策を精力的に展開する必要がある。また緊急事態に備えた法的整備や、首都機能の分散化など、防災大国にふさわしい体制づくりを検討すべきである。加えて、老朽化するインフラの点検や調査、予防措置に必要な予算や人材の確保については、自治体任せにせず、国が抜本的な対策を講じるべきである。