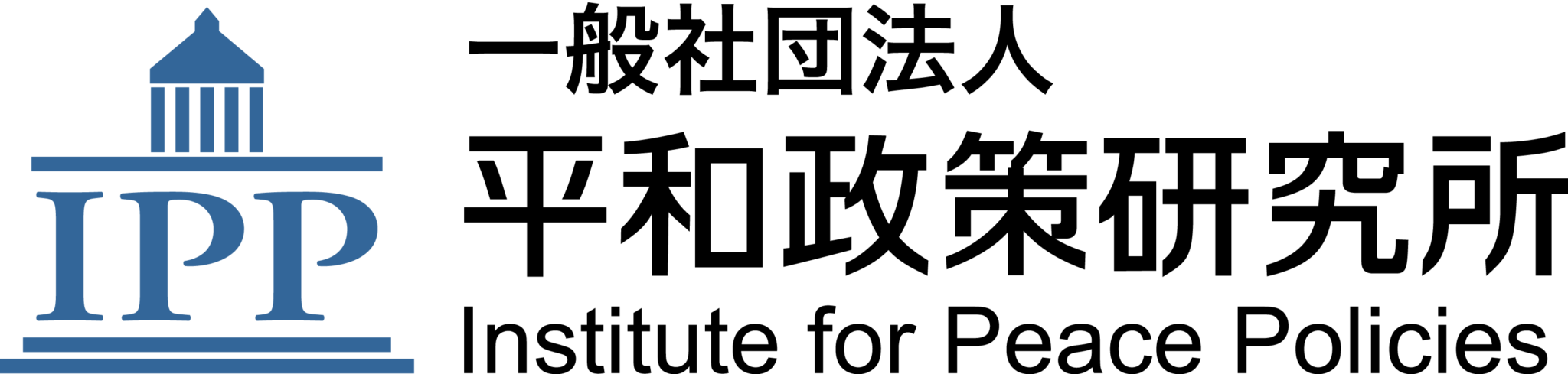国家目標と基本戦略—新たなグローバル文明を主導する日本
目標3.地域から創る活力ある持続可能な日本社会
概要
経済停滞が長期にわたり、かつ、少子高齢化と急激な人口減少が進む現在、活力ある持続可能な日本を地域社会から実現することが基本的な国家目標の一つである。そのためには、各地域の特性が活かされ、なおかつ全体との調和がとれた分権・分散・地域自立型の社会の構築が必要とされる。また、和合・親密・友愛などを特徴とするゲマインシャフト的な地域社会・コミュニティを再生させることは「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現に寄与するであろう。それに資する「移民政策」を検討していくことも人口減少社会においては重要な課題である。第4次産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることで社会課題の解決を目指す「Society 5.0」(超スマート社会)の実現においては、人間のウェルビーイングを高めることを目的とし、精神的道徳的価値と物質的経済的価値が統合した社会を目指すべきである。あわせて、日本経済の主力となる次世代産業の育成も重要である。
①分権・分散・地域自立型の強靭な社会の構築
日本は、先進国の中では唯一に近い中央集権体制国家であり、活力ある地域社会と国を創る上で、地方分権体制に本格的に移行することは不可欠である。中央集権型行政システムは、限られた資源を中央に集中し、効率的に配分・活用することには適しており、日本の急速な経済発展に大きく寄与した。しかし、地域社会の自治や地域経済の存立基盤を揺るがす側面も持ち合わせている。
日本は経済成熟期を迎えており、少子高齢化および人口減少が進む中で、地域間の格差が生じ、抱える課題も多様化して、中央集権型行政システムは制度疲労を引き起こしている。地域によっては国が行う一律の行政が合わない場合もあり、個性ある地域づくり・地方創生が課題となっている。近年増加している自然災害への対応という観点からも、分権・分散・地域自立型の国土計画が急務である。そのためには、国の役割と地方の役割の明確化、中央集権的に対応したほうがよい事柄と地方分権にしたほうがよい事柄の整理、地方で役割を果たすべき事柄についての十分な権限と財源の移譲、そして地方自治への意識向上が必要不可欠であるが、現状まだそれらが不足している。
過去30年余りの地方分権改革の結果、機関委任事務制度の廃止や権限移譲、国の関与の抜本的見直しや新しいルールの創設などが行われ、国と地方の関係を対等・協力の関係に変えていくという理念が具現化されてきた。また、義務付け・枠付けの見直しなどが行われ、個別法令レベルに踏み込んだ制度改正が数多く実現した。
その結果、地方自治体が地域課題を踏まえた多様な法的対応をとることが可能となり、制度的には地方の自主性・自立性が高まった。さらに、地域における実情や課題に精通した地方の発意に根差した地方分権を推進するため「提案募集方式」や「手挙げ方式」が導入されている。
しかし、実質的に地方分権が進んでいるとは言い難い。機関委任事務の廃止に伴い導入された法定受託事務は、機関委任事務制度の下で形成されてきた自治体の国への従属と依存の発想や習慣などを払拭するに至っていない。また、条例の制定権についても、いまだに国が強く介入する事例が見られる。分権化した制度を活用して自治体が主体的、自立的に政策を展開するためには、地方自治体の政策形成能力向上や地方自治に対する住民の意識向上が重要である。
同時に、主体的な財政運営も欠かせない。地方財政については「三位一体の改革」が行われてきたが、財政支出と税収の量的規模から見ると、地方分権が進展したとは言えない。地方自治体の自主財源である地方税が占める割合は低水準であり、依然として地方交付税・国庫補助金体制が敷かれている。国全体としての税の再分配機能に留意しつつ、地方税源の充実、および地方交付税・国庫補助金体制の改革が必要である。
2014年から地方創生政策が始まり、デジタル田園都市構想を経て地方創生2.0に到っている。従来の地方創生政策において、国はあくまでも「伴走」役に留まるとされており、政策5原則の中に「自立性」「地域性」が掲げられていた。しかし実際は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(地方版総合戦略)の策定をはじめ、国の方針や意向に沿った施策事業が企画され、国からの指示通りにPDCAサイクルを実行するなど、逆に国の主導性・統制力が強まり自治体の依存性が高まったという見方もある。
地方創生2.0の基本構想では、国の役割は国でなければできないことに取り組むことであるとして、地方創生には地域自らが真剣に考え、行動を起こし、自主的・主体的に取り組むこととしている。本来の地方創生は国が推進するものではなく、地方自らの創意工夫によって牽引されるべきものであり、そういった形で地方創生が成されれば、地域社会の活力が高まり地方分権化にも寄与することになろう。
そのために重要なのは、第一に地域コミュニティの活性化である。現在地方の村落や都市には、先進的なコミュニティ活動が生まれている地域がある。現状に危機感を持った地域から、創造的な取組が生じている。地域コミュニティの活性化は、地域社会づくりに直結し、住民自治の基盤となりうる。そうした中から、本当の意味での地方分権改革が改めて求められる可能性がある。
第二に、地方自治体は多様な市町村からなる広域連携の仕組みを活用して、分散型の国土形成を推進すべきである。平成の大合併の後に「定住自立圏の制度」(2008年)や「連携中枢都市圏の制度」(2014年)が創設され、広域連携が進められている。地方自治体の創意工夫により、これらの仕組みが活用されることが願われる。市区町村と都道府県が、各地に合った多様な広域連携の在り方を模索しながら、分散型の国土形成に寄与することが重要である。現状のフルセット主義による画一性の追求から脱却すべきである。
第三に、自立した強い地域社会を構築するには、外部に大きく依存している地域経済の内部循環を促していくことが重要である。大型店の立地を制限していた大店法が2000年に廃止されて以降、大型店の郊外立地が進み、商店街など中心市街地の空洞化と地域商業の衰退が加速した。その結果、地域経済の外部依存が促され、地方の活力低下につながった。地域経済の外部依存を解消するためには、食やエネルギー分野において地産地消度を高めていく必要がある。その結果、域外流出額の減少と域内所得の向上という成果が現れるはずである。
最後に、国は、東京一極集中の是正や、権限と財源の地方への移譲など、国でなければできないことを推進すべきである。東京一極集中の是正については、これまでも「多極分散型国土」の構築(1987年)や地域大学振興法(2018年)等の取組みが行われてきた。しかし、その一方で工業等制限法の廃止や国家戦略特区などによる容積率・用途等の規制緩和が行われたことにより、タワーマンションの建築や再開発が進められ、東京一極集中は加速している。集中のメリットもあるためその是正は簡単ではないが、首都機能の移転・分散化といった大胆な政策も含めて、東京一極集中の是正に取り組むべきである。
②地域社会・コミュニティ再生による共助社会の実現
現代日本では少子高齢化と経済の停滞が相まって、社会支出は抑制され、社会福祉はニーズに対して公的部門が小さいまま維持されている。他方で、高齢者、子供、障がい者、貧困者、保健など、国民全体を包括する社会保障サービスはある程度整備されている。日本の社会保障は、高福祉高負担の北欧諸国と、市場にほとんどの福祉供給を委ねている米国の間にあり、「中福祉中負担」と言える。それは、家庭や地域社会、企業が共助としての福祉の重要な担い手として機能してきたという日本的な特色により成り立ってきた。
しかし、1990年代以降、家族の形態や企業の安定性に揺らぎが生じた。社会構造の変化や社会福祉制度の発展と共に、家族関係の維持・生成と生活の必要性との結びつきが弱まり、地縁や血縁に頼らなくても生活していける社会になった。また、長期不況を通して日本企業の体質も変化してきており、非正規雇用者など会社に取り込まれない人々も増加した。その結果、日常生活を阻害する事象が生じた際に、公的な福祉サービス(公助)のみでは十分な支援が受けられない人々が生じている。
公的制度に福祉サービスの提供全てを依存する場合、莫大な財源が必要となる。公債の発行によって賄うか、北欧諸国のように高い税率を国民が引き受けなければならない。しかし、今は崩壊しつつあるとはいえ、日本では伝統的に家族や地域によるインフォーマルな福祉(共助)が大きな役割を担ってきたため、公的福祉のための巨大な税負担について合意が成立することは容易ではない。
また、「ケアされ愛され所属しているという実感」(ジョンソン=シュワルツの5分類より。坂田(2020)から引用)というような心理的なウェルビーイングは、公的サービスからは得にくい。それゆえ、心理的ウェルビーイングを達成するためには、家族や友人、地域コミュニティなどからのインフォーマルなケアが必要となる。
したがって福祉サービスの提供を公的制度のみに期待することは適切ではない。身体的・心理的・社会的すべての福祉ニードを充足しようとするとき、適切な福祉ミックスを考えることが必要となる。福祉ミックス論を提示したR.ローズは、「社会の福祉全体量=H(家族によって供給される福祉)+M(市場によって供給される福祉)+S(政府によって供給される福祉)」というモデルを提示した。ここに使用者としての事業者や地域社会・コミュニティを含め、全ての福祉ニードの充足と福祉供給の持続性を担保していく必要がある。
このように、地域社会やコミュニティの繋がりを再生し、インフォーマルな福祉を拡充することが福祉ニード充足のために重要となってくる。インフォーマルな福祉に着目した議論として、「日本型福祉社会」論が従来から構想されてきた。工藤(2018)によれば、1979年に自民党が発行した『日本型福祉社会』と題した研修叢書では、社会的リスクは国民個人が負担し、その負担能力の限界を超えたとき、国家は最終的に社会的リスクを負担する機関として位置づけられていた。また、同書では、社会保障制度を家庭、企業、市場システムを基盤とした民間保険等、最低生活以上の基準を保障するインフォーマル部門や民間営利の社会システムの供給主体を補完する制度として位置づけていた(工藤2018)。
「日本型福祉社会」論は福祉ミックスの考えにも通じるが、一方で「残余的」との批判もある。福祉の補完性原則によれば、自助・共助・公助はそれぞれ完全に分離できるものではなく、かつ全てが補完的である(小林2022)。すなわち、3つのうちどれもが単独では成立しない。自助は共助と公助に補完される必要があるし、公助は自助と共助に補完される必要がある。したがって、自民党の研究叢書に見られるような公的福祉とインフォーマル部門の分離を乗り越え、公民が最適な役割分担をしつつも、統合的に福祉を創出する体制を構築していく必要がある。
これは言い換えれば、一人ひとりの社会関係資本を拡充し、自助・共助・公助のバランスの取れた地域福祉を充実させていくということである。和合・親密・友愛などを特徴とするゲマインシャフト(地縁・血縁などによる自然発生的集団)的な共同体を、現代にあった形の社会関係資本として再構築するとともに、しがらみが嫌厭され個人の自由が尊重される現代社会において、程よいつながりを保つことのできる場を地域社会につくっていくことが重要である。
また、年金、医療、介護、保育、いずれの分野についても国が大きく行っている公的福祉だけでは、地域や個人の細部にまで寄り添うことには限界がある。人々の人生に寄り添った福祉サービスの提供が重要であるが、そのためには、人々の生活に一番密接にかかわる基礎自治体と住民が、その地域に合った福祉を考え実行していくことが望ましい。その際、NPOや民間企業、さらには、ボランティアや住民による自主的な活動も重要な役割を果たしうる。各地域において、様々なアクターが連携し合うことのできる環境をつくり、地域を基盤とした福祉を手厚くしていくことが望ましい。
③地域共生社会の実現に資する「移民政策」
バブル景気における労働者不足やプラザ合意後の円高を背景に、日本では1980年代後半頃から国内で就労する外国人が増え始めた。1989年には入国管理法改正により、専門・技術分野の外国人労働者の受け入れが本格化し、現在の外国人受け入れ制度の土台が築かれた。その後、技能実習生制度や留学生政策など、多様なルートを通じて多くの外国人が来日し、国内で生活するようになった。日本に住む外国人の数は年々増え続け、法務省『在留外国人統計』によれば、2024年6月末時点で358万人余りに達し、過去最多を記録している。
一方で、政府は一貫して「移民政策はとらない」との立場を維持している。もし本格的な移民政策が導入されれば、①犯罪発生率の上昇による治安悪化、②社会保障費用の増大による財政負担の増加、③日本人の雇用機会の減少、④日本の伝統文化への影響、といった懸念が根強いためである。
こうした否定的な見方がある中でも、政府は2019年に新たな在留資格「特定技能」を創設し、改正入管法を施行した。それまで高度人材に限定していた受け入れ方針を転換し、単純労働者にも門戸を開いた。また、外国人との共生に向けた総合的な施策を打ち出すなど、外国人受け入れの拡大方針をより明確にしている。今後は特定技能の受け入れの拡充に加え、人権侵害の指摘がある技能実習制度を見直し、新たに「育成就労」制度とする方針だ。これらの政策は、「事実上の移民政策」とも指摘されている。
近年の外国人受け入れ拡大の背景には、少子高齢化と人口減少の進行により、特に農林水産業や介護分野での人材不足が深刻化している現状がある。また、グローバルな人材獲得競争が激化する中、産業界からの外国人材確保の要請も強まっている。
しかし、国際的な定義では、外国人労働者の多くが「移民」に該当する。移民の受け入れは、日本社会のあり方に長期的な影響を及ぼす重要な課題であり、「人材不足」という理由だけでなし崩し的に進めるべきではない。受け入れ制度が不十分なまま外国人の数が増え続ければ、かえって社会的な軋轢を招く可能性もある。近年、欧州や米国で移民の受け入れへの反発が強まっているが、日本にとっても他人事ではなくなりつつある。
コロナ禍を経てもなお経済グローバル化は加速しており、国内の外国人の増加傾向は今後も続くと考えられる。移民受け入れに関する懸念については、海外の事例や実証データをもとに研究が進められている。政府は、移民受入れが日本社会や経済に与える影響を冷静に分析し、正面から国民的な議論を促す必要がある。その上で、「移民政策」として明確に方針を定め、移民の資格や権利、受け入れ規模を示し、制度整備を進めるべきだ。
外国人をより多く受け入れることで自動的に「共生社会」が成立するわけではない。目指すべき「共生社会」のビジョンを明確にし、それに対する国民の合意が得られてこそ、適切な外国人受け入れ政策が実現できる。日本固有の伝統文化や慣習を維持しながら、いかに外国人とともに社会の活力を高める「共生社会」を実現するかが問われている。特に、すでに多くの外国人が暮らす地域社会ではグローバル化が急速に進んでおり、地域社会こそが日本らしい「共生社会」のモデルを構築する場となる。
また、日本で働く外国人の多くはアジア出身者である。経済発展に伴い、アジア諸国との経済格差が縮小すれば、日本で働くメリットは相対的に小さくなる。さらに、多くのアジア諸国でも少子高齢化が進行しており、今後は外国人材の獲得競争が激化する可能性が高い。有能な外国人材を確保するためには、日本が「働きたい国」「住みたい国」となるための環境整備が不可欠である。
④ウェルビーイングを高める「Society 5.0」の実現
日本は、第4次産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることで、様々な社会課題を解決し、未来を創造する「Society 5.0」(超スマート社会)を世界に先駆けて実現することを目指している。Society 5.0は、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会である」とされ(内閣府2016)、「経済発展」と「社会課題の解決」の両立を目指している点に特徴がある。
日本は課題先進国といわれており、例えば、世界でも類を見ない超高齢化により、医療・福祉、社会保障制度にかかる課題、製造業における技術継承など、あらゆる産業、地域社会が課題に直面している。このような背景から、デジタル技術を用いた社会課題の解決と経済発展の両立が期待されている。
Society 5.0においては、具体的には、例えば以下のことが想定されている。予防検診やロボット介護によって健康寿命が延び、社会コストを抑制することが可能となる。農作業の自動化・最適な配送が実現し、食料の増産や食料ロスの削減が可能となる。エネルギー需要の予測、分配の最適化により、エネルギーの安定的な供給や温室効果ガスの排出量削減が可能となる。自動生産の実現やサプライチェーンが最適化されることで、人手不足が解消され、持続可能な形で産業を推進可能となる。社会インフラのメンテナンスも効率的に行うことができるようになる。AIを活用した地震予測や津波浸水予測などの防災システムや減災システムが活用される。
これらは正に、経済発展と社会課題の解決の両立、すなわち持続可能な社会の実現につながるものである。課題先進国である日本において、Society 5.0を実現し、国家としての中長期的な成長を遂げることができれば、持続可能な未来社会の一つの在り方を世界へ提示することができると考えられる。
Society 5.0を実現するためには、イノベーションを促進し、新規需要の拡大や新たな財やサービスを創出し続けることが重要とされる。このようなイノベーションの主な担い手は既に存在する企業やベンチャー企業であることが想定されるが、社会課題に直面している各地域、各自治体における多様な主体が参画し、社会課題の解決に向かって協働する必要があるだろう。このような取り組みにおいては、扱う社会課題や、関わる企業や地域、自治体などの個別の事情を踏まえた解決策の提示が必要であり、これは日本が高度経済成長期に大きく発展を遂げたときのような、自国へ革新技術を導入し、洗練させる路線の発展とは大きく異なると考えられる。
そのため、日本はこれまで経験したことのない、従来とは異なる方法で成長を遂げる必要があり、今後は、これを実現するための人材を養成する仕組み、教育システムの構築が必要と考えられる。そこにおいては、各地域における課題解決と地域経済の成長の両立に主体的に取り組む起業家精神(アントレプレナーシップ)の醸成、そして、具体的な解決策を導く創造性の涵養が鍵となるであろう。
Society5.0として目指す社会は、ICTやAIの浸透によって人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させるデジタルトランスフォーメーションにより、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」であることが宣言された(文部科学省2021)。ウェルビーイング(well-being)とは、人々が身体的にも、精神的にも、社会的にも満たされ良好な状態にあることを言う。
本宣言からもわかるように、Society 5.0においては、経済成長と社会課題解決の両立という側面だけではなく、国民一人一人が精神的にも豊かな生活を営める人間社会の実現が願われている。技術革新により様々なことが自動化・効率化されつつある昨今において、人間が本来的に備えている精神性や創造性の重要性が再確認されつつあり、またコロナ・パンデミックによる世界的な混乱は、人と人との繋がりの重要性を浮き彫りにした。
このような必ずしも経済指標のみでは計測できない人間社会の質的な発展が、Society 5.0においても重要である。科学技術と人間の精神性が調和し、人と人の繋がりや各自の人間性が尊重され豊かになるような「Society 5.0」を目指すべきである。それが新たなグローバル文明における社会のあり方のモデルとなるだろう。
⑤日本経済の主力となる次世代産業の育成
戦後の日本経済は製造業を主力産業として大きな発展を遂げてきた。1970年〜80年代にかけて、半導体や自動車をはじめとする日本製の優れた工業製品が世界を席巻し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれるほどの存在感を誇った。しかし、次第に韓国や台湾などアジアの新興工業国との激しい競争に晒され、さらに中国が世界の生産工場としてシェアを拡大すると、日本の製造業はかつての勢いを失っていった。
この間、急速なグローバル化、ICT化の進展とともに世界経済をめぐる状況は一変したが、日本は旧来のビジネスモデルから脱却することができず、今日まで国際競争力の低下が続いている。日本経済が「失われた30年」を克服して再び成長軌道に戻るには、世界経済の変化に対応して革新的な製品・サービスを生み出すことのできる体制を整え、次世代の主力となる産業を育成していかなければならない。
かつて米国も1970年代に日本や西ドイツの急成長によって製造業で国際競争力が低下し、貿易収支の大幅赤字に直面した。しかし80年代以降、主要産業を従来型の製造業からICT関連産業、バイオ産業を始めとするイノベーション型産業に転換し、とりわけ1990年代以降はインターネットを中核にした情報通信技術で世界をリードする存在となった。他の国々に先駆けて、モノづくりからモノが普及した後の情報・サービスや価値提供に重点を置くようになったのである。
米国のそのような新たな産業の創出の過程においては、州立大学を始めとする地方の大学や研究機関が重要な役割を果たしてきた。連邦政府は中小企業技術革新法(SBIR)などの法整備によって産学連携を促しながら、すでに存在していた各州の大学・研究機関を活用して技術の種をもつベンチャー企業を積極的に支援した。同時に、大学は起業家の輩出や学生教育など、人材育成の面でも地域産業の発展に大きく貢献した。シリコンバレーやボストン地域のバイオテック産業、シアトルのベンチャー支援などは、その事例として知られる。
日本もこれまで米国の制度などを参考にしながら、技術革新に基づく経済成長のための様々な政策を進めてきた。政府は2022年を「スタートアップ創出元年」と位置付け、戦後の創業期に次ぐ、第二の創業ブームを実現することを目指して「スタートアップ育成5か年計画」を発表した。しかし、過去30年以上にわたる様々なイノベーション政策は、未だに長期の停滞を脱するような効果を見出せていない。
日本の国力を高めるには経済力の向上が不可欠である。そのためには、分権・分散・地域自立型の社会を目指し、地方の大学・研究機関を活用した地域主導の大胆なイノベーション政策を柱とする成長戦略が必要である。そうしたイノベーション政策が地域における技術革新と新産業の創出に結実し、地域経済圏を形成して日本経済全体を活性化してゆくことが望まれる。