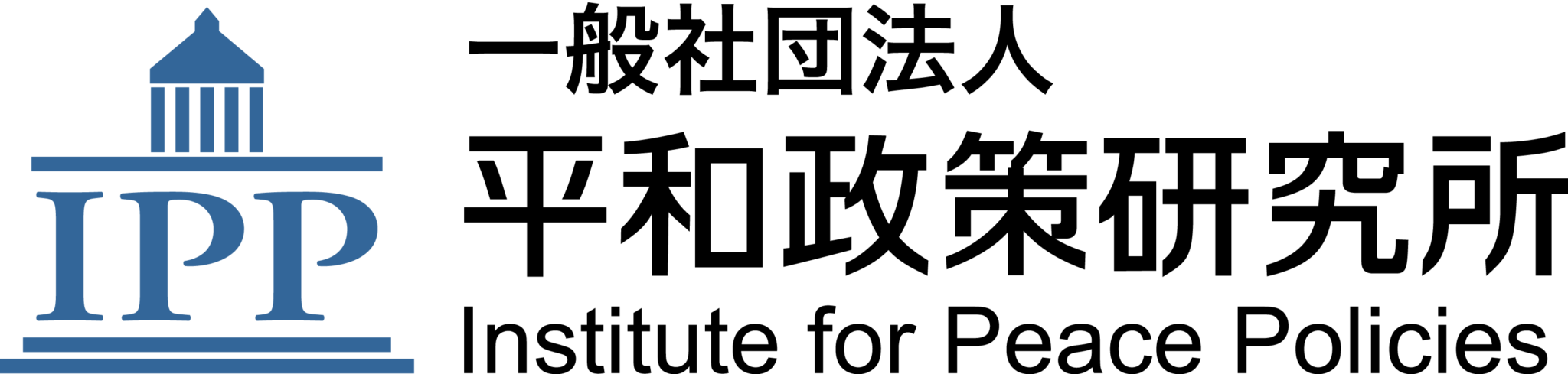文明の転換期における日本の課題
1.激変する日本を取り巻く国際環境
①ポスト冷戦期の終焉と国際秩序の流動化
現在の世界は、ポスト冷戦期の米国一極支配が終焉し、多極化時代への移行期にある。1991年のソビエト連邦崩壊以降、米国は圧倒的な軍事力、経済力、科学技術力、文化力をもつ唯一の超大国とみなされてきた。しかし2000年代に入ると、911同時多発テロを契機とする「対テロ戦争」の失敗、リーマン・ショックに端を発した世界的な金融危機などで国力を消耗していった。米国の地位は徐々に揺らぎ、「ポスト・アメリカ」の時代への流れが加速したとの認識が広がった。シリア内戦への介入に消極的だったオバマ大統領は、自ら「米国は世界の警察官ではない」と宣言した。
米国の後退によって大国間の力関係(balance of power)に変化が生じると、中国やロシアは米国を中心に西側諸国が主導してきた国際秩序に揺さぶりをかけ始めた。中国の習近平政権は「大国外交」を掲げて軍備増強や海洋進出を積極化させるとともに、巨大経済圏構想「一帯一路」を打ち出して経済面でも米国に代わる覇権の獲得を目指している。中国はすでに米国にとって最大の脅威であり、米中対立は「新冷戦」の領域に入ったと考えられている。
一方、ロシアによるウクライナ侵略は、第二次世界大戦後の欧州で初となる大規模な軍事衝突であり、世界の平和秩序を根底から揺るがすほどの衝撃を与えた。欧州各国はすでに対中政策を大きく変更し、インド太平洋地域への関与を深めつつあったが、ウクライナ戦争によってロシアとの対立が一気に顕在化した。その結果、自由、民主主義、人権、法の支配などを重視する欧米・日本などの西側諸国と、全体主義・覇権主義的な統制を強める中国・ロシア・北朝鮮などが鋭く対立し、世界の分断化が進んだ。
ウクライナ戦争はロシア軍の攻勢とウクライナ側の反転攻勢の中で膠着状態が続いている。欧米による対ロ制裁の長期化やウクライナ支援の疲弊により、戦争の行方はいまだ不透明なままである。欧州はこれまで米国と協調しつつウクライナ支援を進めてきたが、戦争の長期化と第2次トランプ政権の発足に伴い独自の対応を模索する動きを強めている。第2次トランプ政権はウクライナ支援の大幅な削減やNATOとの関係再調整を検討しており、欧州の安全保障環境に変化をもたらす可能性が高い。すでにEUは防衛力強化やエネルギー政策の見直しを進め、米国依存からの脱却を図る姿勢を明確にしつつある。ウクライナ戦争を契機として国際秩序の再編が進んでいる。
国連を中心とする国際協調体制も揺らいでいる。国連安保理は大国の対立で機能不全に陥り、国際紛争の解決が停滞する事態が目立つ。米国が孤立主義を強めた場合、国連の役割そのものがさらに低下し、各国が独自の安全保障枠組みを模索する動きが加速する可能性がある。
さらに近年、西側諸国と中露の対立が深まる中で、「グローバル・サウス」への注目が高まっている。「グローバル・サウス」は、南半球に多い新興国・途上国を指し、冷戦期の「第三世界」に代わる概念とも理解される。長年にわたってグローバル資本主義の負の側面による苦しみを強いられてきた「グローバル・サウス」は、欧米的価値観に反発し、先進国主導の国際秩序に必ずしも同調しない。今後も国際社会の重要な意思決定の場面において発言力を高めてゆくだろう。
中東情勢もハマスによるイスラエルへの越境攻撃とイスラエル軍のガザ侵攻によって、一気に緊迫が高まった。米国を後ろ盾とするイスラエルは、ハマスなどのイスラム組織と密接なつながりをもつイランと対立した状態が続いているが、地域大国である両国が全面衝突に至れば、米国やロシアも巻き込んで中東全体が不安定化する事態になりかねない。さらに、中国も中東への関与を強める可能性もある。
国際経済システムも大きな変動期にある。コロナ禍では国境を超えた人とモノの流れが著しく制限され、世界経済は一時危機的状況に陥った。日米欧を含む主要国はかつてない規模の財政出動を行い、世界各国に保護主義的な政策を強化する動きが広がった。経済は自由市場の自律的調整機能を中心とした体制ではなくなり、自由競争に基づいて比較優位を確保するという国際経済の共通基盤は、第2次トランプ政権による関税政策もあって一層弱体化しつつある。WTOによるグローバルな貿易交渉が行き詰まって久しく、剥き出しの国益のぶつかり合いを調整する共通基盤がない世界の現状は、あたかも19世紀の再来の様相を呈している。このような新たな現実を前提として、国際経済秩序を再構築してゆかなければならない。
国際社会が直面する課題はますます多様化・複雑化している。国際・国内紛争、気候変動・環境破壊、疾病・感染症、移民・難民、国際犯罪・テロ、資源・エネルギーなど、様々な分野の問題が相互に影響し合い、解決に向けた政治過程を複雑なものにしている。公共政策が扱う領域は拡大し、技術的にも政治的にも不確実性が増している。その結果、国際社会が地球規模の課題を解決するためのグローバル・ガバナンスのあり方も変革を迫られている。
このような世界的変化の潮流は、国際社会が文明史的に大きな転換期に立たされていることを示唆している。そのプロセスは、大国間の覇権闘争、地域紛争の多発、国際経済システムの混乱、民主制をはじめとした政治制度の劣化、自由を中心とした価値観の緊張、地球公共財の新たな担い手の台頭、社会のデジタルシフトなど、様々な諸課題が複雑に絡み合いながら展開していくであろう。その間、多様かつ想定外の危機が起こる可能性もある。日本はG7の国としてそのような危機を克服するとともに、新たなグローバル文明への移行期における平和秩序の形成に積極的な役割を果たすことが求められている。
②覇権を巡る米中新冷戦の激化
現在、21世紀の覇権をめぐって米国と中国が激しく衝突し、米中新冷戦が激化している。中国の習近平政権は「中華民族の偉大な復興」をスローガンに掲げ、具体的には2035年までに社会主義の現代化を基本的に実現し、中華人民共和国建国100年に当たる2049年には米国を凌ぎ世界一の覇権国家になることを目指している。
これに対し米国は、第1次トランプ政権下の2018年1月に米国防省が10年ぶりに国防戦略(National Defense Strategy, NDS)を発表し、米国の備えるべき脅威が対テロ戦争から中露との大国間競争に回帰したことを明確にした。中でも、最も警戒すべきはロシアではなく中国だと断定した。
米国の対中脅威認識をより鮮明にしたのが、マイク・ペンス副大統領(当時)が2018年10月にハドソン研究所で行った対中政策に関する演説であった。同演説は政治、経済、安全保障、人権など広範囲に及んだ上、中国政府の建国にまで遡り一党独裁そのものを明確に批判した。これにより、米中間の対立が政治、経済、技術、軍事などを巡る総合的な覇権争いであり、価値観の対立を本質とする文明的対立であることが鮮明となった。
バイデン政権においても、対中国政策の基本姿勢は継続され、むしろ強化された。2022年10月に発表した国家安全保障戦略(National Security Strategy, NSS)では、ウクライナ侵略を続けるロシアを「差し迫った脅威」とした一方で、中国を「国際秩序を変革する意図と力を有する唯一の競争相手」と表現し、米国の安全保障・経済に対する最も包括的かつ長期的な課題と位置付けた。ただし、バイデン政権では中国との競争の安定管理に力点が置かれ、対中政策は「デカップリングではなく、デリスキングと多様化」(ジェイク・サリバン国家安全保障担当補佐官)を基本方針とした。
それに対して第2次トランプ政権では、経済的なデカップリングの動きが一段と加速するとみられる。具体的には、貿易・経済面では中国からの輸入品に一律関税を課す政策が発動され、中国に依存するサプライチェーンからの完全な脱却を目指し、重要産業の国内回帰(リショアリング)が強力に推進されつつある。
安全保障面でも対中強硬姿勢が一層鮮明になるだろう。米国のインド太平洋戦略はより強硬なものとなり、特に台湾防衛への関与強化や南シナ海での軍事プレゼンス拡大が顕著になると考えられる。中国側もこれに対抗して軍事的圧力を強めるため、台湾海峡や南シナ海で偶発的な軍事衝突が発生するリスクが高まる。また、米国の国防予算の増額や重点分野への再配分が進み、中距離ミサイルのアジア配備や極超音速兵器の開発などによって、米中間の軍拡競争が一段と加速することが予想される。
技術分野では、半導体・AI・5G・バイオ技術といった先端分野で米中両国はそれぞれ独自の技術エコシステムを形成する動きを加速させることが予想される。米国は中国企業による米国内への投資を包括的に禁止し、中国のバイオ産業やTikTokなど中国発のデジタル・プラットフォームを米国市場から排除する方針を打ち出す可能性が高い。それに対し、中国も米国に依存しない技術自立戦略を一段と推進し、独自のサプライチェーン構築や国家主導のイノベーション強化に取り組むと考えられる。
このような対中強硬路線は、米国内で政治的分断が深刻化する中でも超党派で根強く支持されているため、米中の対立構造は長期的に続くことが避けられない。2025年以降の米中関係は、もはや単なる経済競争にとどまらず、安全保障・技術、そして価値観をめぐる包括的な対立へと深化すると予想される。その世界経済や国際秩序に与える影響は計り知れず、国際社会はこの新たな「ブロック化」の時代にいかに対応すべきかを問われることになる。
③不安定さを増す東アジア地域
台湾海峡および朝鮮半島は、中国・ロシアのランドパワーと海洋国家によるパワーが衝突する戦略的ホットスポットであり、地政学的に日本の安全保障に直結している。
東アジア地域は、今後数年間に地政学上の不安定さと大国間の競争の震源地になりかねない。東アジア地域ほど各国間の利害関係が険しく、当事国の規模が大きく、今後の状況が不透明で、それぞれの駆け引きが激しさを増している地域は他にないからだ。
東アジアが地政学上の不安定さの震源地となっている要因として、マーク・エスパー元米国国防長官は、次の4点を上げている(2022年2月)。①核能力を保有する国が4カ国ある、②世界の経済大国トップ3カ国、および上位12位にランクされる経済強国が5カ国ある、③世界で最大または最強の軍隊を保有する国が6カ国ある、④世界で最高のハイテク国家が6カ国もある、ことである。東アジアで戦争が発生した場合、地理的に東シナ海と隣接海域に限定されたとしても、世界経済は弱体化し、金融システムは混乱、サプライチェーンは崩壊せざるをえない。
現在の米中対立の地政学的最前線は台湾海峡と南シナ海だが、北朝鮮の動向は米中関係に大きな影響を与える可能性がある。北朝鮮はウクライナ戦争を契機としてロシアとの軍事協力を強化している。また、2024年10月に憲法を改正して、初めて韓国を「敵対国」と明文化した。中国は露朝連携に対しては干渉しない立場を堅持しているが、万が一、中国の勢力圏が朝鮮半島全体に拡大するような事態になれば、日本にとって最悪のシナリオとなり、戦略的敗北と言わざるをえない。日本は朝鮮半島の地政学的重要性に鑑みて、戦略的朝鮮半島政策を確立させる必要がある。
日本は、米中新冷戦と東アジア地域の潜在的な高リスクを直視して、長期的な外交戦略の再構築に着手すべきである。第2次トランプ政権が発足して以降、その政策をめぐって西側諸国の間に亀裂が入り、国際協調主義の基盤は脆弱になりつつある。米国は同盟国に対して自助努力を促しており、日本も次世代の多国間連携に対して主体的役割を果たすことが求められている。日米韓の同盟とパートナーシップの強化、クワッドの強化、対中国基本戦略と戦略的朝鮮半島政策の再構築などを、包括的かつ中長期的な視点で推し進めていく必要がある。
④第4次産業革命による社会変革
近年、自ら学習し新たなコンテンツを創り出す生成AIをはじめとするデジタル技術の目覚ましい発展により、社会構造が大きく変わろうとしている。これは、「第4次産業革命」と呼ばれ、デジタル技術の利活用により、生産性の飛躍的向上やエネルギー効率の制御、モノのデータ化・自動化、個々にカスタマイズされたサービスの提供、AIやロボットによる労働の代替・補助などが実現され、あらゆる社会インフラの在り方、さらには人々のライフスタイルが変化していくと考えられている。
このような第4次産業革命を促進するべく、2010年頃から欧米諸国を中心に国家戦略や関連の取り組みが進められている。例えば、ドイツ政府が推進する国家プロジェクトであるIndustry 4.0においては、ドイツの主産業の一つである製造業の国際競争力の強化を狙いとして、重点となるデジタル技術の研究開発やイノベーションの基盤となる産官学連携の推進などの国家的な取り組みが行われている。第4次産業革命を意識した世界での取り組みは、ドイツにおけるIndustry 4.0を皮切りに活発化しており、Manufacturing USA(米)、“Made Smarter”戦略とCatapult Network(英)、中国製造2025、Manufacturing Innovation 3.0(韓)、タイランド4.0など、各国の状況に応じた様々な形で進められている。
このような動向を受け日本政府は、日本が目指すべき未来の社会像として「Society 5.0」(超スマート社会)を提唱している。Society 5.0は、「狩猟社会」、「農耕社会」、「工業社会」、「情報社会」に続く第5の社会に位置付けられ、様々なデータを収集、解析、意味づけを行うことにより、これまでの社会においては実現困難であった新たな価値を創出することが期待されている。
ただし、ICTやAIなどのデジタル技術の導入に関して日本は諸外国と比較してやや遅く、第4次産業革命に向けて取組んでいる企業の割合についても、日本企業は他国企業よりも低い。また第4次産業革命のためのイノベーションの中核的な担い手の一つとしてベンチャー企業への期待は大きいものの、日本では他国と比べ、起業人材やベンチャー企業が育つ環境が整っていない。日本の企業、産業・社会システム、そして国民意識の社会変革に対する抵抗感をぬぐい、諸産業の変革を推進すると共に、ベンチャー企業が育ちやすい環境を整備することが求められる。また、新たな雇用が生まれる部門への円滑な労働移動のためには、同一労働同一賃金の原則の徹底、労働時間の柔軟化、新たな産業に見合った働き方改革、官民や大学を含めた新技術に対応できる能力開発の機会の拡充が必要となる。
第4次産業革命により様々な恩恵が期待されるが、他方でそれにより生じる課題もある。例えば、単純な繰り返し作業や肉体労働、機械や情報システムを操作する仕事等が機械化されることで、多くの雇用が失われ、一部の高スキルの高所得者とそうでない低所得者の間で格差が拡大するとの指摘もある。また高度なデジタル経済社会であればあるほど、人と人とのコミュニケーションや文化・芸術、ホスピタリティなど、人間でないとできない質の高い仕事が求められるようになる。そういったニーズに応えることのできる人材育成、個々人の人格や人間性、創造性の開発が重要になると考えられる。あらゆる面で、第4次産業革命による社会変革に対応していくことが求められている。
⑤地球環境問題の深刻化と循環型経済社会への転換
近年、気候変動やそれに伴う様々な自然災害、生物多様性の損失、海洋汚染、大気汚染、森林破壊・砂漠化、資源の枯渇など、地球規模の環境問題が世界各地に影響を及ぼしている。人間活動の増大が地球環境へ大きな負荷をかけており、これらの環境問題への対処、さらには、自然環境と調和した人間活動の実現が人類共通の課題となっている。
その一方で米国では、国際的な環境合意が国家主権や経済政策への制約になり得るという理由等から、第2次トランプ政権下でパリ協定からの離脱やクリーンエネルギー政策の見直しなど、脱炭素をはじめとした環境政策の転換が続いている。しかし、地球環境問題が深刻さを増していることは事実であり、国際社会の共通課題として避けられない。
近代資本主義体制下の18世紀半ばから19世紀にかけて産業革命が起こり、生産力が飛躍的に高まった。その結果、人口も増え、より多くの人々が豊かな生活を享受するようになった。ここから大量生産・大量消費・大量廃棄社会が始まると同時に、環境問題が始まったと言っても過言ではない。現在では経済活動が限りある地球環境の限界を超えつつある。
戦後、国際社会において環境問題が注目されるようになったきっかけは、1962年に出版された『沈黙の春』であった。著者のレイチェル・カーソンは、次々に開発される農薬や化学物質乱用が環境問題を引き起こす危険性を指摘した。ちょうど同時期に、日本においても四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)が発生し、その後、公害対策基本法の成立(1967年)や環境庁の設立(1971年)に至っている。
国連では1972年に「国連人間環境会議」が開催され、その後絶滅危惧種の保護やオゾン層破壊物質削減についての枠組みが整備された。また、1992年には「国連環境開発会議」(地球サミット)が開催され、気候変動枠組条約や生物多様性条約が採択された。20世紀末までに、地球環境問題に国際的に取組む枠組みがつくられたと言える。さらに2002年に「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(リオ+10)、2012年には「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」が開催され、2015年にはCOP21にてパリ協定が採択された。このように継続的な協議と取り組みが国際的に行われてきたが、地球環境問題は年々深刻さを増している。
地球環境問題は、社会・経済システムと深くかかわっているため、これに対処するためには経済・社会のあり方を変える必要がある。新たな社会のキーワードは、脱炭素、自然との共生、そして循環型である。特に、地球環境問題を生み出してきた大量生産・大量消費・大量廃棄社会から循環型経済(サーキュラーエコノミー)への抜本的転換が重要となる。大量生産・大量消費・大量廃棄は健全な物質循環を疎外するリニアエコノミーであるのに対して、循環型経済では製品や部品を再利用したり、廃棄された素材をリサイクルして有効活用したりする。製品の利用形態を所有からシェア型へと転換させ、資源を循環させる。それにより、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止などが実現できる。日本においても、2001年に循環型社会形成推進基本法が施行されているが、その推進はまだ限定的である。今後は、より一層循環型経済を推進する必要がある。
循環型経済社会を軌道に乗せるためには、資本、情報、ヒトを「地域」で活用することが必要である。近代資本主義は利潤の極大化をはかり、地球規模で資本、情報、ヒトの交流や移動を行い、グローバリゼーションを進展させた。しかし、グローバリゼーションでは、国境を越えた経済活動が行われる反面、地域での資源や資本の循環が生じにくい。そのため、グローバルな活動の一方で、地域に根差した経済活動を活性化させる必要がある。
循環型経済社会は地域社会から生まれるため、それを具現化するには、地域の人々の生活にとって欠かせない食料、エネルギー、医療・介護等を地域で賄う経済システムが必要となる。「グローバル・大規模」の発想から「ローカル・地域規模」への転換と、その両者のバランスを取っていくことが重要となる。