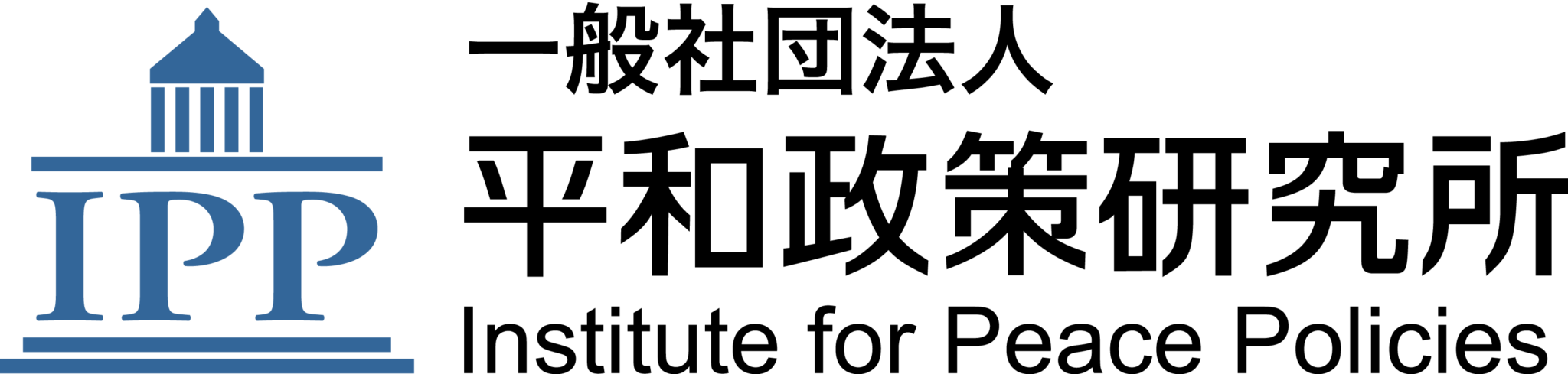国家目標と基本戦略—新たなグローバル文明を主導する日本
目標4.未来にむけた人づくりと家族機能の充実
概要
持続可能な国家と社会をつくる上で、未来に向けた人づくりのための家族機能の充実と教育は、非常に重要な国家目標となる。現代日本では、少子高齢化とともに家族機能の低下が指摘され、児童虐待の増加などが問題になっている。家族病理に対処し、予防するためにも包括的家族政策によって家族支援を充実させる必要がある。あわせて、少子化を緩和・克服し、家族生活の安定と子供の健全な発達を保障するためにも、子育てフレンドリーな社会の実現が望ましい。初等中等教育では、人間性を育む教育(人格教育)を推進するとともに教員人材の確保と質の向上に資する学校改革が急がれる。高等教育に関しては、高度専門人材の育成および中・高等教育の充実による地域活性化により、活力ある持続可能な日本社会の実現をけん引する人材の育成が願われる。
①包括的家族政策による家族支援の充実
近年、家族機能低下により家族病理が深刻化しており、産まれてきた子供たちの成育環境は急速に悪化している。そうした家族病理に対処し、予防するためには、子供や親個人への支援だけではなく家族全体をも支援の対象とする「包括的家族政策」が必要である。
政策を立案する際、家族全体を考慮する必要があるのは、家族が一つの動的な「システム」だからである。家族成員一人の状況が変化すれば、他の成員の状況も連動して変化する。心理面では、夫婦関係の善し悪しが子供の精神状態や問題行動と連動することや、父親が家庭に関わらないことが子供の精神疾患に関係することが指摘されている(家族システム論)。経済面では、特に子供・高齢者や、病気・障害を持つ人をケアする家族において、就労・経済活動とケアや家事の間における時間・労力の配分が問題となる。さらには、経済面の行動の変化は、心理面のシステムにも影響を与える。
家族のシステム性を考慮しない場合、一人ひとりの窮状を解決できないばかりか、問題を生み出すシステムを放置したり、安定しているシステムを破壊するリスクもある。例えば、引きこもりの子供などによる高齢の親への虐待を防止するには、子供に対する自立や就労などの支援が必要となる。個人だけを対象に政策を立案する場合、他の家族成員から受ける、または与える影響を見落とす可能性がある。
加えて、個人だけを対象にした場合、家族ライフサイクルを見落とすこともある。家族問題には多世代性があり、子供に表れている精神疾患や問題行動の淵源が祖父母世代と親世代の関係にあるということもある。家族ライフサイクルを考慮に入れることは、時間的・予防的視点を取り入れ、複雑な問題に対応できる可能性を高める。
一方、現代では家族に関わる政策立案には、個人の多様なライフコースに配慮することを求める声も大きい。両親と未婚の子供からなるいわゆる「標準世帯」が全体の25%程度となるなか(内閣府2022a)、個人の選択を保障するためや、家族内の弱者を保護するための家族政策の必要性も説かれている(例えば、下夷2021)。それらの政策においても、家族全体を支援する観点から、家族の分断を予防する取り組みを含めて立案することが重要である。単身世帯やひとり親家庭なども含め、様々な家庭で子育てや介護がうまくできるような環境を整え、一体的に支援していくことが重要である。
では、包括的家族政策の具体的内容はどのようなものか。増田(2022a, 2022b)によれば、家族政策とは、「家族機能を維持していくために、家族や家庭内の問題を未然に防ぐこと、あるいは解決することを目的として、家計や生活面に対して、社会的に家族を支援する政策」である。そして、家族機能とは「家族により構成される世帯の生活維持や、家庭内における育児、教育、介護等に関する機能」である(増田2022a、2022b)。
増田(2022a、2022b)は、上記の目的を果たすため、家族政策には次の4つの分野があるとした。①家族ケアを支援する分野(出産、子育て支援、家庭療養、介護支援など)、②家計の経済的支援に関する分野(児童手当、児童扶養手当、家族税制など)、③家庭と仕事の両立支援に関する分野(家庭保育、保育所、育児休業など)、④家族構成・構造や意識改革・啓発等に関する分野(結婚支援、家族法制、啓発活動など)、の4つである(同上)。
このうち、④の意識改革・啓発等に関する分野は、今後重要な取り組みとなる。例としては、全国の自治体で広がっている若者への「ライフデザイン教育」等が挙げられる。若者の進路選択において、就職だけではなく結婚や出産、育児などのライフイベントを視野に入れて総合的にキャリアを考えるようにする狙いがある。また、気兼ねなく子育てや家族の問題を相談してもよいという意識の啓発なども重要となろう。
包括的家族政策では、以上に加えて、心理的な面から家族関係を支援する政策も取り入れる。家族内の葛藤や不健全なコミュニケーションを改善するために、家族療法などを含む心理社会的な家族支援の普及が望まれる。また、家族で協力して円滑に家族生活を運営するため、家計管理やケアのあり方などについて、家族内の話し合いやルール作りを支援することも重要である。
家族支援の現場では、2024年に母子保健と児童福祉の両機能の統合を図ったこども家庭センターが設置された。両機能におけるソーシャルワークやケアマネジメントの専門性に加え、家族関係を支援する技能を有した人材を継続的に育成・配置することが肝要である。
こども家庭庁には、包括的家族政策の観点から、家族全員の、将来にわたるウェルビーイングを実現するための政策の実施を期待したい。現在、こども家庭庁は「こども施策」に注力しており、家庭・家族は子育て当事者への支援という文脈で登場する。そのため、現在の親子関係に対する支援は整備されつつあるものの、将来親(社会的親を含む)になるための親性準備に対する支援や夫婦関係への支援には重きが置かれていない。児童相談所の虐待相談対応件数の増加、その内訳で面前DVの割合が増えていることを考えれば、親性準備への支援や夫婦関係への支援は重要事項である。
また、施策の実効性を高めるためには、地方自治体との連携や支援が決定的に重要である。こども家庭センターの設置や未婚化対策の一環として結婚コンシェルジュを配置するなど、こども家庭庁が地方で実体的活動をする体制は取られつつある。今後は、自治体の成功を後押しするようなコンサルタント的な視点がより一層必要となる。
②子育てフレンドリーな社会の実現
少子化を緩和・克服し、家族生活の安定と子供の健全な発達を保障するためには、「子育てフレンドリーな社会」を実現していく必要がある。「子育てフレンドリーな社会」とは、人々が仕事・経済活動と子育て・家族生活の間でバランスをとることのできる社会である。
現在の子育て家庭は孤立しやすく、同時に仕事と子育て・家族生活の多重役割を負っている。高度成長期以降、都市部への人口移動と核家族化により、家族規模が縮小し、地域コミュニティは衰退した。また、1990年代から続く長期の経済停滞により、多くの家庭では共働きを余儀なくされ、長時間労働を強いられている。加えて、少子化により、産業界にとって女性の就労は欠かせないものになった。現代日本社会は、子育ち・子育てにやさしい環境とはいえない。
家族生活を充実させることは、子供の発達と一人ひとりの家族成員のウェルビーイング(心身が健康で社会的にも満たされた状態)にとってきわめて重要である。まず、充実した家族生活は、子供が家族との情緒的関係を肯定的に捉えやすくし、子供のウェルビーイングを実現しやすくする。親にとっても、夫婦で共に子育てをすることは夫婦間の信頼関係を向上させる。良好な家族関係は信頼関係の基であり(例えばFreitag & Traunmüller(2009))、その意味で家庭は社会における共生の核であると言える。
しかし、現在の日本社会は経済の停滞や実質賃金の低下が続いており、多くの場合、人々は仕事・経済活動を中心に時間とエネルギーの配分を行い、その残りを子育てと家族生活に充てざるを得ない状況にある。経済の成長戦略と実質賃金の持続的上昇を実現するとともに、子育てと家族生活もより充実させられるように社会の制度を設計する必要がある。
そのために必要なことは、第一に、家族が共有する時空間への配慮である。子育て期にある男女には、必要に応じて家事・育児に充てる時間をとれるよう、働き方を柔軟に変化させられるようにすることが望ましい。男女の育児休業を取りやすくするとともに、短時間勤務およびその間の一定額の所得保障などが重要となる。
また、子育てしやすい場所で仕事をできるようにすることも効果的である。高度成長期以降の職住分離は、主に父親を家庭から引き離した。その結果、通勤に時間を取られることで家事・育児に充てる時間を圧迫している。ICTを活用した在宅勤務や職住近接への取り組みが進みつつあるが、それをさらに推進すると同時に、頻繁な転勤や単身赴任をしなくて済むような配慮も重要である。子供が乳児期の時から両親が密な関わりをもつことは、子供の発達に必要であると同時に、父親母親の精神的安定に寄与し、虐待防止にもつながる。
第二に、子育て版の地域共生社会の構築である。子育て家庭を支援する重層的なネットワークを形成し、困難に対する予防的支援を充実させる必要がある。福祉における支援ネットワークには、行政・社会福祉法人や各種専門機関などからなるフォーマルなものと、近隣の地域住民や地縁団体などからなるインフォーマルなものがある。フォーマルな支援はより専門的支援が必要なケースを対象とするのに対し、インフォーマルな支援は日常の見守りや困りごとの早期発見に重要な役割を果たすとされ、二つのネットワークを連結することが重要となる(岩間・原田2012)。個別の子育て家庭を支援しつつ地域の人々の社会関係資本を高め、物理的・心理的に子育て家庭が支援にアクセスしやすくなる環境を整備することが望まれる。児童手当などの現金給付にも増して、ソーシャルワーカーなど、そうした活動を行う福祉人材への投資も重要である。
加えて、保育所や学校は、重要な子育ち・子育て支援の場となりうる。少子化の進行に伴い、保育所や学校は、様々な年齢の子供同士の交流の場として重要度が増している。また、子育て困難家庭にとっては、セーフティネットの役割も果たす。ただし、質の高い保育の保証が不可欠である。保育における規制緩和による無軌道な量的拡大は、保育の質を低下させるおそれがある。子供の年齢と発達段階に応じた利用をすすめ、適切な人材の育成と配置によって環境を整備していく必要がある。
「包括的家族政策」(前項参照)と合わせて、以上のような社会環境の整備が「子育てフレンドリーな社会」の構築に寄与するであろう。
③人間性を育む「人格教育」と学校改革
教育基本法第一条(教育の目的)には「教育は、人格の完成を目指し」とある。しかし、これまで人格を完成した人間像が明確に定義されたことはない。
「人格の完成」と最も関連の強い教科は、2018年度から実施されている「特別の教科 道徳」(教科化された道徳)である。その学習指導要領では、「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」ことを目標とし、指導方法は従来の読み物資料だけでなく、「問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れる」といった内容が示されている。また、文科省が定めた第4次教育振興基本計画(2023〜27年度)では、基本方針として「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」と「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」を掲げている。
では、日本が持続可能な社会と国家を築き、新たなグローバル文明の担い手となるために必要な人間像、日本社会のウェルビーイングの向上に資する人間像とはどのようなものであろうか。ここでは「人格の完成」を念頭に、教育目標となる人間像として三つの視点を提起したい。
第一は、個人として成熟した人格を有する人間である。成熟した人格とは、時代や地域・文化を超えて、普遍的に人間としての美徳とみなされている徳目(品性)を備えた人間である。第二に、家庭人・社会人として円満な人間関係を築き、他者と共生することのできる人間である。第三に、個人の特性や個性を活かして社会に貢献する創造性豊かで奉仕の心と習慣を持った人間である。
「道徳教育は、教育の中核をなすもの」(学習指導要領)であると位置付けられている。上記の資質を持ち合わせた人物を育成するために、「特別の教科 道徳」を軸に学校生活のあらゆる活動を通して子供たちの人間性を育むことが重要である。
ところで米国では、1990年代以降、徳目(品性)教育に力点を置いた「Character Education」(人格教育)を推進しており、大きな成果を上げている。米国の人格教育では、「感謝」「従順性」「正直」「思いやり」「勇気」「権威」「責任」「忍耐」「配慮」などを、時代や地域・文化を超えた人間としての普遍的な徳目として教育している。その特徴は、①道徳的知識(知)だけでなく、道徳的感情(情)を養い、具体的な行動(意)に結びつけて「習慣化」させる点、②学校・家庭・地域社会が協力しながら、学校を中核とした「道徳的文化」を地域社会全体に築いていこうとする点にある。
日本でも「道徳」が教科化されたことで、道徳に対する各教員の意識の向上や授業時間の確保などの面で進展が見られる。ただし、教科化により教科書はできたが、依然として従来の「人物の気持ちを読み取る授業」から大きくは変わっておらず、授業内容の質の向上と実効性が課題となっている。道徳の授業では、いじめや自殺をはじめ、人権や生命倫理など広範囲の社会問題を扱うことがあり、教員には幅広い知識と高い専門性が求められる。そのためにも、現在は設けられていない道徳専門の教員免許を設け、教育の質の向上を図ることが重要である。そのためにも、大学で「道徳とは何か」という道徳哲学、道徳に関する学問的な理論体系の構築を図る「道徳学」の研究が不可欠である。
また、学校と家庭・地域社会の連携・協力体制の構築を推進することが重要である。岡山県総社市では、2010年から不登校対策をきっかけに生徒の学校適応を支える「だれもが行きたくなる学校づくり」というプロジェクトを実施している。プロジェクトの一環として、「よい習慣を形成する」ための「品格教育」を取り入れ、アンケートなどによって地域全体で目標となる徳目を定めている(総社市教育委員会2015)。そして、市民にも「見守り声を掛けること,よい行いをする子どもを見掛けたら褒めるとともに学校園に連絡すること」を励行した結果、中学校の不登校出現率や問題行動の減少という成果が出ている(同上)。
学校と家庭、地域社会全体で教育目標やプランを共有することで、子供たち個人の道徳育成はもちろん、地域社会における道徳的文化の造成を促し健全な地域社会づくりにつなげることができる。米国の人格教育で重視しているサービスラーニングのように、教室で学んだ知識を、具体的実践を通じて地域社会の課題解決に生かすといった行動も重要である。
また現在の学校教育現場には、様々な課題が山積している。本来は家庭や地域でなすべきことも学校に委ねられ、学校と教師の負担が増大している。外国人児童生徒の増加、不登校児童生徒の増加、特別支援教育の拡充、貧困やいじめなど、様々な状況にある児童生徒への対応にも追われている。その結果、教員の長時間勤務による疲弊、採用倍率の低下と教員不足が深刻化している。
今後は、人口減少により学校教育の維持と質の保障についても課題が生じることが予測される。「少人数学級」の推進や情報端末を活用したGIGAスクール構想など新たな取り組みも進められており、教員の指導力の一層の向上が必要とされている。教員人材の確保と質の向上、専門性を高める体制づくり、さらに学校現場における働き方改革の推進が急がれる。もちろん、単に在校等時間を短くすればよいというわけではなく、仕事内容の見直しと共に、教員としての働きがい(意欲、熱意)と教員同士の信頼関係構築に配慮しながら進める必要がある。
④高度専門人材の育成および中・高等教育の充実による地域活性化
今後、日本の未来創造のためには、「高度専門人材の育成および中・高等教育の充実による地域活性化」が重要になる。
まず、一点目の高度専門人材の育成についてである。グローバル化により国境を越えた国際間の大学競争、高度専門人材の奪い合いが激しくなっている。近年日本の大学の評価は下がっており、国際間の競争においても、決して優位な位置にはない。他方、少子化により18歳人口が激減しているにもかかわらず、大学設置数は増加し、定員割れの大学が続出している。また、米国、中国、ドイツなど他の主要国が博士課程入学者、博士取得者の数を伸ばしているのに対して、日本は過去20年間に横ばいあるいは減少傾向にある。国際的かつ国内的諸課題解決のためには、科学技術の開発が不可欠であり、日本の高等教育には抜本的改革が必要とされている。
大学を巡る国内外の環境変化に対して、政府の危機意識も強く、2022年、内閣府や文科省が立て続けに未来人材に関する提言を発表した。例えば、内閣府の教育未来創造会議が「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第1次提言)」を発表し、高等教育において重点的に取り組むべき課題として、「文理の壁を超えた普遍的知識・能力を備えた人材育成」「デジタル、人工知能、グリーン(脱炭素化など)、農業、観光などをけん引する高度専門人材の育成」「修士・博士人材の増加」などを挙げた。
特に、専門性の高い博士人材の活用が遅れていることはかねてから指摘されており、博士課程修了者の就職率は臨床研修医やポスドクを含めても70%弱で低迷している。人文科学や社会科学では30〜50%台に落ち込む。企業の研究者に占める博士号取得者の割合は約4%であり、大学の研究職や企業の研究者として高度専門人材が活躍できる多様なキャリアパスをどう創るかが課題である。
博士人材の育成には、教育環境の整備、給与や研究環境の改善、若手研究者が活躍できる安定的なポストの拡充、多様なキャリアパスの開拓などが必要である。欧米では、博士課程学生に対して個人を対象とする研究奨学金のフェローシップ、研究補助業務に対して給与を支払うRA(リサーチ・アシスタント)、教育補助業務を行うTA(ティーチング・アシスタント)など、多様な経済的支援の仕組みが充実している。日本では、2022年度からは科学技術支援機構の「次世代研究者挑戦的プログラム」により、博士後期課程学生を対象に研究費などの支援強化が始まった。2024年には、博士課程への進学者を増やし、企業を含む多方面で活躍できるよう後押しする「博士人材活躍プラン」を文科省が提言している。
研究環境の改善については、政府が10兆円規模の大学ファンドを創設し、世界と伍する研究大学を目指すとして、2023年の東北大学を皮切りに「国際卓越研究大学」が認定された。一部の有力大学に資金を集中する「選択と集中」の手法には、他の大学との格差拡大を懸念する声もあるが、そうした点も踏まえながらも、若手研究者が経済的不安を抱えずに研究に集中できる環境の整備を急ぐ必要がある。
同時に、どのような高度専門人材を育成するかという点についてもビジョンが必要である。専門分野を極めるのはもちろんのこと、専門性と総合性のバランス、パブリックマインド、国際的視野など、未来を創造していく上で重要な素養を育むことが肝要である。また、言うまでもなく現代社会が抱える課題解決のための社会貢献意識や高い志、倫理観が求められる。これらは、初等中等教育との連続性の中で検討されるべきであるが、高等教育においても著名な研究者・実業家の生涯を学ぶなどの教養的な学びの中で育成することも考えられる(北垣2025)。
二点目の「中・高等教育機関による地域活性化」とは、教育機関による人材育成や産官学連携を通じた地域課題の解決を指し、高等教育段階と中等教育段階での取り組みがありうる。
高等教育段階においては、地方の中核大学がローカルな社会課題の解決を担う人材の育成、およびそのための研究拠点となることが期待される。これまで、「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業(COC+R)」、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」などの取組を通じ、若者の地元定着や、産官学連携による社会課題解決と地域貢献を進めることで大学を地方創生の主要アクターとして位置づけることが目指されてきた。
ただ、CRC+Rは令和6年度が補助期間の最終年度となり、J-PEAKSは支援件数が最大25校のところ23校が既に採択されているなど、これらの事業は令和6年度を境に区切りの時期に当たっている。事後フォローアップや後継事業を検討する必要が生まれている。
そのような中、中教審が2025(令和7)年2月に公表した答申では、今後地方大学等と地域関係者間の連携強化が提言されている。従来の仕組みを発展させ、大学等と地方公共団体、産業界等が一体となって地域の将来ビジョンや研究・教育の構想を共有する「地域構想推進プラットフォーム」と、高等教育へのアクセス確保の取組を推進する大学等の連携である「地域研究教育連携推進機構」を設置することが提言されている。これらの取組を通じて、各地域の中核大学等の自走化と持続的発展を促していくことが今後の課題である。
中等教育による地域活性化には、職業教育を行う専門高校の活用があげられる。専門高校は地域産業を支える人材を育成し、日本の高度経済成長・工業化に貢献してきたと言われている(和田2024)。また、生徒にとって「これから就く可能性の高い仕事に関連した職業に対するアイデンティティをはぐくむ場所としての側面を強く有している」(中澤・阿部・石井2009)ため、地域産業と連携すれば教育内容と一致する分野に人材を供給するトラック機能を有する。3年間の本科卒業後にはより専門的内容を学ぶ専攻科があり、専攻科を充実させることで、地域産業が必要とする技術を備えた人材を供給できる可能性が高い。分権・分散・地域自立型の社会を目指すうえでも、専門高校による地域産業人材の育成は大いに期待される。また、高等教育と職業教育を並立させたシンガポールの学校制度も参考になろう。地域のビジョンや課題を見据えた教育・研究により地域活性化を目指すことは、今後の地域社会にとって必須の取組になるといえる。
以上のように、国全体でも各地域においても、人材育成や研究の強化は重要な取り組みとなっている。
各地の具体的な課題解決に携わる人々の全国的なネットワークや、グローバルな諸課題との接続によって、「課題解決先進国」としての日本のプレゼンスを高めていくことが重要である。