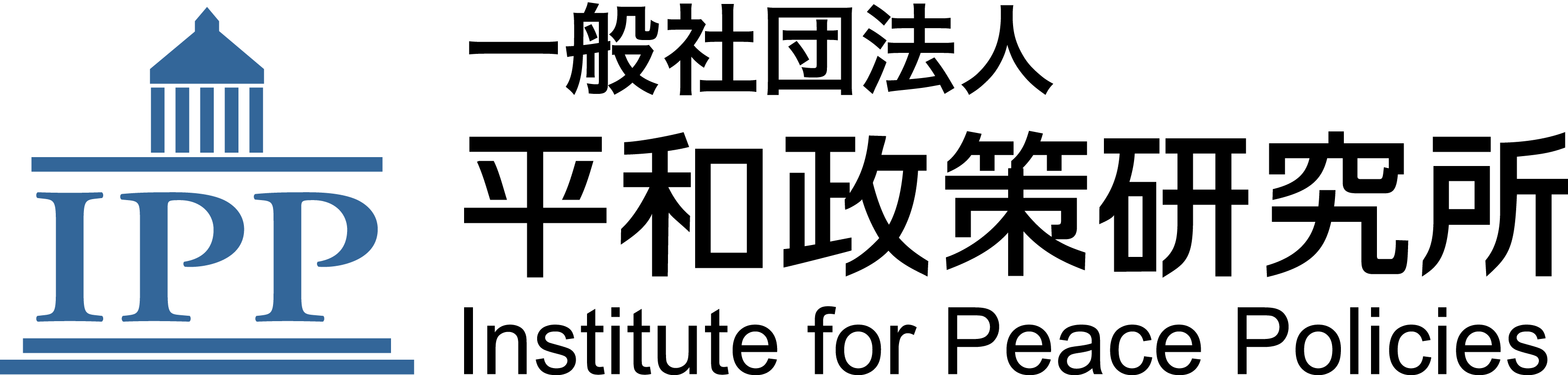翁長雄志知事の死去に伴う沖縄県知事選が9月30日に投開票され、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設阻止を掲げた前衆院議員の玉城デニー氏(58)が当選した。自民、公明の政権与党が総力を挙げて応援した前宜野湾市長の佐喜真淳氏(54)に8万票余りの大差をつける圧勝だった。玉城氏は、辺野古への移設に反対する翁長氏を支えてきた「オール沖縄」と称する保革共闘勢力から後継として擁立され、玉城氏自身も「翁長知事の遺志を引き継ぐ」と訴え、“弔い選挙”を前面に打ち出す戦術で支持を拡大した。当選後、玉城氏は「辺野古に新しい基地は造らせない」と改めて県民に誓い、移設を進めたい政府との深刻な対立は長期化することが確実となった。どうすれば基地を巡る「沖縄対本土」という対立の構図に終止符を打つことができるのだろうか。
国と沖縄 長引く対立
「基地を巡って沖縄の人(ウチナーンチュ)同士がいがみ合う。その姿を本土(ヤマト)の人は高みから笑っている」――。これは翁長氏が生前語っていた言葉で、沖縄県民の複雑な思いとともに、基地問題を他人事としてしか感じていない本土の人々に落胆し、悔しさをにじませた言葉だ。
普天間飛行場を巡る今の基地問題の発端は、1995年9月に起きた米兵による少女暴行事件だった。事件直後、現地で取材した私は、繰り返される米兵による凶悪事件に怒りを爆発させ、「基地はいらない」、「もうたくさん」、「平和だと思っていたのに、本当に癪だ」などと悔しさをにじませる母親たちの姿を今でも思い返すことができる。事件を機に日米両政府は96年、沖縄の過重な基地負担を軽減することで合意、騒音被害と墜落事故の危険を取り除くことを最大の目的に、住宅密集地に隣接する同飛行場の移設を協議してきた。重大な事故が起きれば、日米同盟そのものが揺らぎかねないからだ。案の定、2004年には同飛行場を離陸したヘリが近くの沖縄国際大学に墜落する事故が発生、危険性の除去を最優先に両政府は06年、「米軍再編のための日米ロードマップ」作成した。
その主な内容は、①普天間飛行場の代替施設として、辺野古岬の周辺海域を埋め立ててV字型の滑走路(長さ1800m)を整備する、②在沖縄の海兵隊(定員18000人)のうち約8000人をグアムなどに移駐させる、③米空軍嘉手納基地以南の米軍施設のうち、約1050haを普天間の移設に合わせて順次返還する――などだった。
だが、97年に移設先として辺野古沖の地名が浮上して以来、地元名護市はもとより沖縄県内では反対の声が沸き上がった。それでも私が09年にインタビューした当時の仲井眞弘多知事が語った「日本の防衛と地域の安定のために日米同盟は必要だ。だからこそ、沖縄のためにも同盟のためにも、一日も早く普天間の危険性を除去しなければならない。その信念に基づいて、沖縄県は辺野古への移設という日米合意を受け入れる苦渋の決断を下したのだ」との言葉に象徴されるように、98年から2010年までに行われた4度の知事選では、忸怩たる思いながら辺野古移設を受け入れる知事が当選してきた。
潮目を変えたのは、09年に誕生した民主党政権だ。鳩山首相は社民、共産両党などと一緒に米軍再編の見直しを掲げ、「最低でも県外」をスローガンに普天間飛行場の本土への移設を検討した。しかし、移設先は見つからず、一年足らずで辺野古への移設に回帰した。あまりにも軽率で無責任な行動だが、火がついた沖縄県民の県外移設への期待感は鎮まることなく、14年に続き、今回も移設阻止の候補が勝利する結果となった。
混迷打開の道筋は
選挙結果を受け、安倍政権に批判的な朝日新聞は「辺野古ノーの民意聞け」と題した社説(10月1日朝刊)を掲げ、「辺野古が唯一の解決策という硬直した姿勢を今度こそ改めなければならない」などと主張する。だが、当選した玉城氏を含め、代替案は何一つ示されていない。仮に県外への移設を再検討しても、基地や重要インフラ施設の設置に関して特別なシステムや法律がない以上、早晩行き詰まることは明らかだろう。一方、政府は普天間の危険性除去を最優先に、予定通り移設を進める方針だ。
しかし、それでは対立は深刻化し、挙句、何も進展しないという袋小路から抜け出すことはできない。打開策として私は、政府は沖縄の世論に配慮し、ここはいったん立ち止まることを求めたい。それは辺野古移設を断念するということではない。沖縄の基地問題を国民全体で共有し、考える機会を作るということだ。
例えば、①在沖縄米軍の訓練をこれまで以上に全国各地に移転する、②自衛隊基地を米軍との共同使用にする、③日米で協議し、在日米軍基地の管理権を日本に移す――といった問題を議論すれば、基地問題が他人事ではなくなるはずだ。まずは国民の意識を変えることからはじめる必要がある。