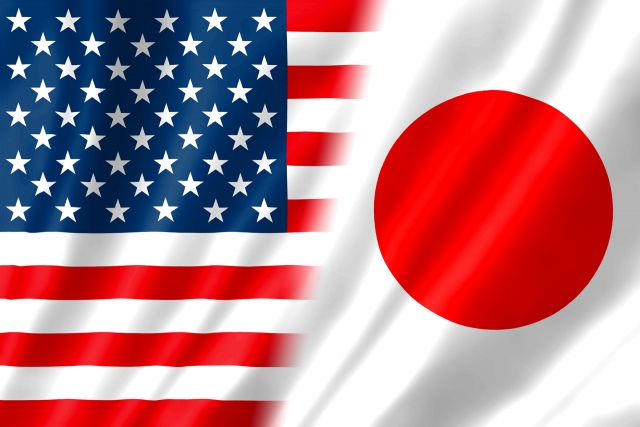はじめに
日本は数多くの国と原子力協定を結んでいるが、そのうち日米原子力協定は歴史も古く、かつ最も重要な協定である。日本の原子力開発は、黎明期から米国との協力を通じて進められ、日米協定はその枠組を設けるものであった。米国との最初の協定は1955年に結ばれた研究協定、次いで協力の範囲を動力炉まで拡大した1958年のいわゆる一般協定、商業用軽水炉導入のための包括的な1968年協定、そして、現行の1988年協定である。現行協定により、NPT体制下の国際社会で唯一日本だけが非核国であるにもかかわらず、包括的事前同意によって自由に原子力を扱うことが公式的に認められてきた。現行協定が日本のエネルギー供給に大きく寄与してきたことは言うまでもない。日々が経つのは早いもので、2018年7月には現行協定の30年の有効期間が到来しようとしている。日米原子力協定の今後について展望する。
原子力エネルギーの必要性
日本に原子力が必要だと考える理由として大きく二つを挙げることができる。一つは日本のエネルギー自給率の低さ(4~5%)である。先進国では韓国と並んで低く、それは昔から変わっていない。ことに戦争中は「石油の一滴は血の一滴」とまで言われた。食料自給率も同じように低いと言われるが、カロリーベースでの食料自給率ではそれでも30%程度ある。単純比較はできないとしても、いかにエネルギーの自給率が低いかがわかるだろう。これを補うための一つの手段として、原子力が必要だと考える。 二つ目は、地球温暖化に対応していくためである。化石燃料を減らした場合、現状として何に頼っていけるか。太陽や風力もあるが、エネルギーとして依存できるレベルとなれば、現段階では原子力くらいではないだろうか。資源論と環境論から、ある程度の原子力が必要だといえる。 ドイツでは、メルケル首相が福島原発事故後、2022年までに国内すべての原子力発電所を停止すると発表した。ドイツに習って日本も脱原発を求める声もあるかもしれない。しかし、ドイツと日本ではエネルギー事情に大きな違いがある。欧州全体に一つの電力市場があり、ドイツで電力が不足したときにはフランスや北欧から供給を受けることができる。日本も、将来は韓国との間で電力パイプラインができれば良いが、今のところ難しい。それどころか日本国内でさえ、西と東で電力の周波数が違うために電力の自由な交換ができにくいというエネルギー的な脆弱さがある。現状の日本では、ある程度の原子力が必要と言わざるを得ないだろう。
原子力協定の成立経緯
簡単に、日本における原子力研究の歴史を振り返る。日本では第二次世界大戦前から理論物理学が発達していた。戦時中は、陸軍の命を受けて理化学研究所の仁科芳雄が原爆の研究を進めた。海軍も別に研究を進めたが、どちらにしても日本の工業力では限界があった。そして本土空襲とともに、研究は中断された。 戦後、日本の原子力研究は禁止されたが、1952年のサンフランシスコ講和条約以降に解禁され、1956年から本格的な研究が始まった。日本の商業原子炉の第一号はイギリスから取り入れたが、耐震性などの問題があり不適切なものだった。それ以降は福島第一原発の第一号機をはじめ、米国の軽水炉を導入した。 原子力の原子力たる所以は、一旦燃やしたウランを再処理すれば、その過程で出てくるプルトニウムを抽出することでもう一度燃料として使うことができるという点である。日本は1950年代から燃料が減らない「核燃料サイクル」を目指していた。 一方で、1952年12月8日のアイゼンハワー大統領の国連演説以降、米国は核拡散防止の方向へ国際社会の舵を切った。放っておけば核技術がどんどん世界に拡散していく。米国が核保有国となって以来、すでにソ連、イギリスが核実験に成功し、やがてフランス、中国も核保有国となった。原子力技術の拡散を何とか阻止したいとして生まれたのが「核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT)」だった。NPTの最たる狙いは西ドイツと日本で、両国は技術力も高い上に、第二次大戦の敗戦国として報復の懸念があった。二カ国をメインターゲットとするNPTは、1970年に発効した。 上述のように、日本は1950年代から核燃料サイクルの実現を目指していた。しかし、当初の日米原子力協定では、箸の上げ下ろし一件一件まで、米国の許可が必要だった。1974年のインドの地下核実験は大きな衝撃を与え、カーター大統領(1977-80年)は核不拡散政策を一層強化した。1977年、日本が東海村の再処理実験炉を動かそうと許可を求めた時、米国は「待った」をかけてきた。日本はプルトニウムを純粋な形で出してはいけないと言うのだ。当時、福田赳夫首相だったが、日本は大騒ぎになった。 米国連邦議会の判断は政治的であり、許可を求めても何を言われるかわからない。このような状況では六カ所村での再処理も難しい。核燃料サイクルを原子力政策の中心に据え、やがては再処理工場の実用化を計画していた日本にとっては大問題だった。日本としては、個々のケース毎に米国の同意を必要とする1968年の協定を改定し、「包括事前同意」制度を導入する必要があった。 しかし、米国としてはNPTの非核兵器国に対し包括事前同意制度を認めたことはこれまで例がなく、「30年もの間、日本でプルトニウムを自由に扱わせるわけにはいかない」と、国防省、原子力規制委員会などが特に反対した。上下両院では、かつて宇宙飛行士だったグレン上院議員が猛反対していた。 結局は、中曽根首相とレーガン大統領の「ロンヤス関係」と、日本がそれまでルールをしっかり守ってきたという実績が認められ、最終的に上下両院の許可がおりた。再処理、濃縮も含めて日本は事前同意を与えられ、NPT体制の非核国で日本だけが特別待遇を受けることになった。
協定の今後―いくつかのシナリオ
2018年7月には現行日米原子力協定の30年の有効期間を迎えるが、協定の今後の行方については理論上次のようなシナリオが考えられる。
- 現行協定第16条により自動延長される。但し、日米いずれか一方が6ヶ月前に文書による通告でもって協定を終了させることができる。
- 現行協定を、そのまま相当期間延長させる条約手続きを取る。
- 現行協定を改定し、新協定を締結する。改定とは、例えば現行協定の包括事前同意制度を以前の個別同意制度に変えることだが、この新協定締結は条約手続き的には上記②と同じである。
- 現行協定を第16条によって終了させ上記①、②及び③のないまま無協定状態になる。
上記シナリオのうち、二番目の同内容で相当期間の延長が日本の核燃料サイクルを安定した基盤に置くには最も好ましいと思われる。だが、このシナリオ実現のためには米国行政府はもちろん、特に議会の積極的な態度が不可欠である(米国1954年原子力法123条)。 一番目のシナリオは手続き的には最も平易な方法であり、米国の関係筋の見方も目下これに傾いているとみられる。現行の協定のもとで日米の原子力関係は順調に進んでいるのだから、何も協定をいじる必要はないのではないかというのが大きな理由なのだろう。しかし、このシナリオの下では米国側の判断次第で、いつでも協定終了となる恐れがあり、いわばダモクレスの剣のようなところがある。 三番目の新協定締結のシナリオは、もし米国側が個別同意制度の再導入を主張するような場合には、大規模な商業用再処理施設の運用が事実上困難となり、使用済み燃料の行き先に困難をきたすことになって原子力発電所が稼働停止に追い込まれる恐れがある。
今後の問題点
日米原子力協定がどのような方向で決着をみるかは、最終的には、2017年に成立する米国の新政権に委ねられていると見られ、他方、日本としてもそれまでに核燃料サイクル政策、プルトニウム政策を整理しなおさなければならない。米国の流れが、仮に自動延長論に向かっているとしても、その行く手には大きな問題が横たわっている。プルトニウム問題である。日本は現在、国の内外に47トン強の分離プルトニウムを持っている。これだけでも大変な量であるのに、これに加えて六ケ所の再処理工場が稼働すると新たなプルトニウムが抽出される。日本は、このような量のプルトニウムを一体どうやって消費するつもりなのか。 米国は、日本が核武装に向かうとは思っていないが、日本にこのようなプルトニウムの保有を認めることは、他国に対して非常に悪い先例になり、核セキュリティ(核テロ)上も大いに問題であると米国は深刻な懸念を抱いている。協定の自動延長はそれとして、その際に何らかの是正措置あるいは代償措置を求めてくる可能性がある。すでに、米国のシンクタンクや原子力の専門家などからプルトニウムの問題が取り上げられ始めている。その論点を、これまで述べてきたことと重複するが以下に主要点を整理しておく。
- 日本は利用目的のない余剰プルトニウムをもたないと内外に公言しているが、その約束は絵に描いた餅のようで実際には膨大な量のプルトニウムを抱え、消費の目途が立っていない。今後、六ヶ所村再処理工場が稼働するとプルトニウム・バランスは益々悪化してゆくことが懸念される。また、MOX燃料加工工場が完成しないままにプルトニウムの抽出が始まると、分離プルトニウムが宙に浮く。
- 日本が核武装に向かうとは思わないが(日本の国内の一部からはそのような声は聞くし、また核燃料サイクルは核抑止になるという著名な政治家の発言もある)、ほかの国への悪い先例になる。また、東アジアの国際政治に緊張激化を招くことになりかねない。大量のプルトニウムの蓄積は、核拡散、核セキュリティ上、ゆゆしき問題である。
- 日本のプルトニウムの消費方法、プルトニウム・バランスの実現の具体的な道筋がはっきりしない。特に福島事故以降は一層不明確となっている。プルサーマル計画もはっきりせず(以前は一応の計画を持っていた)、また、中・長期的には本命である筈の高速炉の将来計画もはっきりしなくなっている。日本は核燃料サイクルの全体像をできる限り定量的な形で示して欲しい。
- もんじゅの将来、高速炉の将来がはっきりしなくなっている。万一、高速炉の将来が不確かになると、核燃料サイクル自身、ひいては、日本の原子力政策が危機に瀕する恐れがある。
日本のとるべき政策
現行日米原子力協定は別名サイクル協定とも言われるように、核燃料サイクルが中心課題であり、これに対して包括事前同意制度が認められていた。今後のシナリオについては、この制度を是非とも維持してゆかねばならないが、その大きなハードルになっているのはプルトニウム問題である。そのために日本のとるべき政策は何か。順不同でいくつかを述べてみたい。
- 日本は、利用目的のないプルトニウムはもたないとの方針を、これまでも繰り返し述べてきているが、原則論的なものであった。この方針をより具体的なものとする。例えば、合理的なworking stockを認めた上で、プルトニウムの抽出と消費の間の期間を明らかにすることなどが考えられないか。
- 現在のプルトニウムの使用先はプルサーマル炉だが、原発自身の再稼働と関係しているので、確定的な計画を作ることは難しいことを承知しているが、高低範囲の計画ないし見通しを作る。そして、なるべく多くのプルサーマル炉を稼働するよう努める。大間発電所をすみやかに立ち上げる。
- すでに述べたように、プルトニウム使用の本命は高速炉である。高速炉実用化に向けての方針を再確認する。
- ドライ・キャスクによる中間貯蔵を増設し、核燃料サイクルに余裕をもたせる。
- 英仏に保管されているプルトニウムについては、両国から所有権の移転に応じてもよいとの提案がなされている。日本はこれまでプルトニウムを貴重なassetとしてきたことから、これをliabilityに考え方を180度転換することは容易なことではないが、この点について真剣な検討を行う。
- いずれにしても、日本は保有プルトニウム量を増やしてはならない。極力縮小に努めるべきである。そのためには、六ヶ所村再処理工場でのプルトニウム抽出量の調節もその一つであろう。
いずれにせよ、これらの諸対策は、すぐれて日本自身の問題であり、官民一致して、(むしろ官がより責任をもって)事にあたるべきである。官においては、かつては原子力委員会が司令塔であったが、現在の体制の下でどこであろうか。司令塔が中心となって核燃料サイクルの全体像を描き、それに従って対策を進めていくべきであろう。